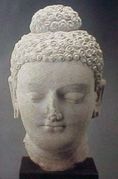一般的な仏教知識と原始仏典の記述との違いを書きます。
1.サハー世界の記述はなく → バッダ・カッパ
2.弥勒如来の出現は56億7000万年後という記述はない
3.六道輪廻の記述はなく → 五趣
4.アヌルッダが失明していたという記述はない
5.ゴータマが如来になるのに三阿僧祇劫かかったという記述はない
6.波羅蜜の修行法に関する記述はない
7.大乗・小乗の記述はなく → 一乗の四念処・梵乗の聖八支道
8.因=直接原因・縁=間接原因という記述はなく → 同じ意
9.嘘としての方便はない → 「タターガタ嘘つかない」
1.原始仏典ではこの世界は「サハー世界」ではなく「バッダ・カッパ」と言う。
一般に「しゃば・娑婆」と言われるこの世界ですが、その記述は原始仏典にはありません。一般的にこの世界の支配者とされる梵天サハンパティ(娑婆主梵天)もこの世界を支配しているわけではありません。原始仏典にはブラフマー・サハンパティは当時、ゴータマ・ブッダの一つ前のブッダであるカッサパ・ブッダのもとで修行していたサハカ比丘という人間で、そこから死んでブラフマーとして生まれ変わりサハンパティとなりました。
パティには確かに「主」という意味がありますが、この世界(一世界は一太陽系)ができてから三人目のブッダがカッサパ・ブッダです。そうすると、この地球が出来てからだいぶ経ってから、サハカ比丘は生まれてサハンパティになっていますからポッと出のブラフマーが突如、この太陽系を支配するのは道理にかないません。実際に、神々の大集会について記述してある長部経典において、「ハーリタ(魅力ある者の意)」という名のマハー・ブラフマー(大梵)が複数のブラフマーの中心としてゴータマに会いに来ます。その経典にサハンパティの名もありますが、やはりハーリタを囲む一柱に過ぎません。この記述からもこの世界は「サハー世界ではない」ということが明らかです。むしろ、この太陽系、あるいは銀河系、どこまで支配しているかわかりませんが、マハーブラフマー・ハーリタこそが最高支配者であるというのが原始仏典の記述です。鬼子母神のハリティーの男性名ヴァージョンだと思います。
バッダ・カッパについてですが、原始仏典では「このバッダ・カッパ(賢劫 bhaddakappa)においてカクサンダ、コーナーガマナ、カッサパ」の三人のブッダが出てそれらはいずれもインド(原典ではジャンブディーパでインドを指す)であったことが原始仏典に書いてあります。それはこの三人とゴータマ・ブッダの時代を貫いて今も変わらずに存在する山の名前がその四人それぞれで呼び名が違ったという記述があるからです。この記述から、一劫は一太陽系が生じて滅するまでの間だとわかります。そうすると、この太陽系の名前は「バッダ(賢い、優れた、吉祥の)」という名前であるとわかります。従って原始仏典の記述に従えばこの世界の名前は「サハー世界」ではなく「バッダ・カッパ」です。弥勒についてはこのバッダ・カッパにおいて人間の寿命が八万歳になったときインドのバーラーナシに転輪王サンカとともに出現すると原始仏典に書いてあります。
2.原始仏典では弥勒菩薩は56億7000万年後とは限らない。
弥勒の正式名称は「メッテーヤ(Metteyya メッテッヤ)」です。メッタは慈しみを意味するパーリ語ですので、意味は「慈しむ者・優しい人」です。このメッテーヤはこの地球が存在するときにインドのバーラーナシに現れると書いてあります。そのときは同時にサンカという名の転輪王も出現し、転輪王サンカはメッテーヤのもとで後に出家します。彼らが出現するまで後どれぐらいかかるかという記述はありません。しかし、とりあえず人間の寿命が十歳になってからそれから美徳の獲得とともに寿命が八万歳になるまでですから、人間の感覚としては相当後世になってからですがそれが果たして56億7000万年後かどうかは不明です。
「弥勒はトゥシタ天に今いてその寿命が56億7000万年だからその寿命が尽きた56億7000万年後に転生してくる」といわれますが、トゥシタ天の寿命は5億7600万年というのが原始仏典の記述です。
「比丘たちよ、人の400年はトゥシタ天の一日一夜である。
このような夜の30夜を一月となし、
このような月の12ヶ月を一年となし、
このような年の4000天年をもってトゥシタ天の寿命となす。
比丘たちよ、また処としてこの世に一部の男女は八分成就のウポーサタを修行すれば、身が破れて死して後にトゥシタ天の仲間に生じるだろう。
比丘たちよ、私はこれを意趣するがゆえに人の王権は天上の快楽に比較すれば微弱であると説く」
(『南伝大蔵経21 増支部経典5』大蔵出版 P148)
トゥシタ天の一日・・・人間の400年
トゥシタ天の一ヶ月・・人間の12,000年
トゥシタ天の一年・・・人間の144,000年
トゥシタ天の一生・・・人間の5,760,000年
400 × 30 × 12 × 4000 → 5億7600万年
ゴータマはカッサパ・ブッダの弟子であり、その時代に生きていました。ゴータマはカッサパ・ブッダの弟子であったジョーティパーラ・バラモンだったときに如来になる決意をしてその修行を満たしたことは十分あり得ます。ですから、ゴータマの弟子の一人が未来の弥勒として如来になる決意と修行をしてトゥシタ天に転生している可能性は高いと思います。複数の如来のもとで修行してブッダになる人もいるかも知れませんが、仮にそうだとしても次のブッダは弥勒ですから、ゴータマを最後の師としていた可能性はより一層高くなりますから、トゥシタ天の寿命の分が弥勒出現までの期間である可能性は高いです。これは弥勒に関する推論であって、実際に如来になるには大人二十戒を成就すればいいというのが原始仏典の記述ですので、「存命中のブッダの弟子でなければ如来にはなれない」という記述は原始仏典にはありませんので、注意してください。
ただ、カクサンダ・コーナーガマナ・カッサパの三ブッダでさえ寿命はみな異なります。トゥシタ天から最後の生に来るということは諸仏の法性であり、それに変わりはありませんが、「人の400年がトゥシタ天の一日」というその「人間の一日自体」が、各時代によって異なります。ヴィパッシン・ブッダは寿命が八万歳ですから、その一日は今の人間に比べるともっと長いことになりますし、剣の七日間がある最悪の時代においては寿命が十歳ですから、逆にその一日がかなり短くなります。こういったことを加味すると「今の時代の人間の時間で何年後に弥勒が出現するか」という問題はますます難しくなってきます。
そうは言っても、彼の教えの内容が「四諦」(四諦の集諦が十二縁起に相当)であることは間違いありません。原始仏典の記述には「あらゆる沙門婆羅門はこの四諦を覚るために出家する」とあり、また四諦を説いたときをもって「初転法輪」としているからです。四諦以外に、あるいは不死・輪廻超越・苦滅・涅槃以外に覚った人の教えはないということです。ですから、あえてメッテーヤを待つ必要はありませんが待っても可です。ブラフマー・サハンパティが次のゴータマ・ブッダに会ったように、神やブラフマーに転生としてメッテーヤ出現を待って会いに行くのも一興かも知れませんが、それは各個人の趣味の問題です。
3.原始仏典では「六道輪廻」とは言わず「五趣」と言う。
一般に輪廻転生は「六道(りくどう、ろくどう)」と言いますが、この記述は原始仏典にはまったくありません。根本的な間違いが「修羅道」でこれは「悪趣」ではありません。暴力団やヤクザやマフィアというものは人間であり、人間は悪趣ではないのと同様に、アスラは四大王やサッカ側のデーヴァと同じ神々であり、ちゃんとした神々です。
ヤクザは人間であって地獄の住人ではないように、アスラは神であって悪趣の住人ではありません。暴力団を絶対悪とするのは誤った見解であり、同様にアスラを絶対悪とするのも誤った見解であり、マーラ(悪魔)を絶対悪とするのも誤った見解です。ある生ける者が絶対悪であるということはあり得ません。一時的にデーヴァダッタのように「全体的に悪」になることはありますが、永遠に悪ではなく一劫後には地獄の寿命も尽きて善法が生じる可能性が出て来ると思います。原始仏教における悪とは「貪りと瞋りと癡かさ」という三悪根、これを絶対悪であると規定します。
原始仏典では「六道」とは言わず、「五趣」五つの行き先と言います。修羅道を除いた、地獄・餓鬼境・畜生胎・人間・天の五つです。これとは別に涅槃道があります。「六道はその生き方であって行き先ではない」と言う人がいますが、原始仏典での五趣の教えは「生き方でもあり行き先でもある記述内容」になっています。その経典では五趣+涅槃道の六つがまとめて語られています。ですから原始仏典の記述は「五趣+涅槃道」であり、よく言われるような「六道輪廻」という単語も関連する記述も原始仏典には存在していません。
4.「アヌルッダが失明していた」という記述は原始仏典には無い。
アヌルッダは自分を訪ねてくるサーリプッタやモッガーラナといつも普通に挨拶して会話しています。また外道を含めた四方サンガに宿を貸している美女と一夜をともにしたときも、彼女は美しく着飾っても誘惑し、裸になっても誘惑しましたがアヌルッダは一顧だにもせず、逆に説法して信者にしたという話が律蔵にあります。この武勇伝はサンガで大いに語られましたが、ゴータマに女性と一夜を共にするなと説教されます。この場合、彼が失明していれば話が変わって来ることになるのは自明の理です。これらの記述から僕はアヌルッダが失明していたという話を信じていません。
5.ゴータマが三阿僧祇劫かけて如来になったという記述は原始仏典にはまったく無い。
むしろカッサパ・ブッダに出会ってから間もなく如来になっており案外早いです。
如来になる方法は大人二十戒の記述しか原始仏典にはありません。
6.「波羅蜜」や「六波羅蜜」の記述は原始仏典にはまったく無い。
そのような修行方法に関する記述もありません。
7.原始仏典では「一乗」と言い「大乗」とか「小乗」という記述はまったく無い。
四念処の修行法のみによってあらゆる生ける者は清浄となり苦しみを乗り越えることから四念処の「一乗」(エーカ・ヤーナ)のみを原始仏典では説きます。「大乗」(マハー・ヤーナ)とか「小乗」(ヒーナ・ヤーナ)という単語も記述も一切ありません。「梵乗」(ブラフマ・ヤーナ)が聖八支道の別名として説かれることはあります。
8.因と縁は同じ原因の意
因[ニダーナ nidāna]を直接原因と捉え、縁[パッチャヤ paccaya]を間接原因と捉える人がいますが、原始仏典では因と縁は並記され、さらに集起[サムダヤ]や生じる[ジャーティ]とも並記され、まったく同じ意味で用いられています。「これがその因であり、縁である」というように。従って、因を直接原因とし縁を間接原因とするのは原始仏典の記述と異なっています。
9.嘘としての方便はない
方便の原語は「パリヤーヤ」(pariyāya)といって「方法・法門・理趣など」を意味します。普通は「方法」と訳されます。様々な方法でゴータマは説法しますが如来は「絶対に嘘をつきません」。嘘をつけば信用が失われます。たとえ利益ある嘘であっても、「この人は利益があるからといってまた嘘をつくかも知れない」という評価になるからです。一切の嘘から離れることは修行者の基本中の基本であり、阿羅漢もまた「自覚して嘘をつくことは不可能である」と書いてあります。
「嘘も方便」と言いますが、それは在家の話で真の阿羅漢が嘘を方便として採用し、ときに嘘をつくことは決してありません。悟った人たちは決して嘘つきではありません。
他にも異なる記述が発見されたら編集して追加することもあるかと思います。
1.サハー世界の記述はなく → バッダ・カッパ
2.弥勒如来の出現は56億7000万年後という記述はない
3.六道輪廻の記述はなく → 五趣
4.アヌルッダが失明していたという記述はない
5.ゴータマが如来になるのに三阿僧祇劫かかったという記述はない
6.波羅蜜の修行法に関する記述はない
7.大乗・小乗の記述はなく → 一乗の四念処・梵乗の聖八支道
8.因=直接原因・縁=間接原因という記述はなく → 同じ意
9.嘘としての方便はない → 「タターガタ嘘つかない」
1.原始仏典ではこの世界は「サハー世界」ではなく「バッダ・カッパ」と言う。
一般に「しゃば・娑婆」と言われるこの世界ですが、その記述は原始仏典にはありません。一般的にこの世界の支配者とされる梵天サハンパティ(娑婆主梵天)もこの世界を支配しているわけではありません。原始仏典にはブラフマー・サハンパティは当時、ゴータマ・ブッダの一つ前のブッダであるカッサパ・ブッダのもとで修行していたサハカ比丘という人間で、そこから死んでブラフマーとして生まれ変わりサハンパティとなりました。
パティには確かに「主」という意味がありますが、この世界(一世界は一太陽系)ができてから三人目のブッダがカッサパ・ブッダです。そうすると、この地球が出来てからだいぶ経ってから、サハカ比丘は生まれてサハンパティになっていますからポッと出のブラフマーが突如、この太陽系を支配するのは道理にかないません。実際に、神々の大集会について記述してある長部経典において、「ハーリタ(魅力ある者の意)」という名のマハー・ブラフマー(大梵)が複数のブラフマーの中心としてゴータマに会いに来ます。その経典にサハンパティの名もありますが、やはりハーリタを囲む一柱に過ぎません。この記述からもこの世界は「サハー世界ではない」ということが明らかです。むしろ、この太陽系、あるいは銀河系、どこまで支配しているかわかりませんが、マハーブラフマー・ハーリタこそが最高支配者であるというのが原始仏典の記述です。鬼子母神のハリティーの男性名ヴァージョンだと思います。
バッダ・カッパについてですが、原始仏典では「このバッダ・カッパ(賢劫 bhaddakappa)においてカクサンダ、コーナーガマナ、カッサパ」の三人のブッダが出てそれらはいずれもインド(原典ではジャンブディーパでインドを指す)であったことが原始仏典に書いてあります。それはこの三人とゴータマ・ブッダの時代を貫いて今も変わらずに存在する山の名前がその四人それぞれで呼び名が違ったという記述があるからです。この記述から、一劫は一太陽系が生じて滅するまでの間だとわかります。そうすると、この太陽系の名前は「バッダ(賢い、優れた、吉祥の)」という名前であるとわかります。従って原始仏典の記述に従えばこの世界の名前は「サハー世界」ではなく「バッダ・カッパ」です。弥勒についてはこのバッダ・カッパにおいて人間の寿命が八万歳になったときインドのバーラーナシに転輪王サンカとともに出現すると原始仏典に書いてあります。
2.原始仏典では弥勒菩薩は56億7000万年後とは限らない。
弥勒の正式名称は「メッテーヤ(Metteyya メッテッヤ)」です。メッタは慈しみを意味するパーリ語ですので、意味は「慈しむ者・優しい人」です。このメッテーヤはこの地球が存在するときにインドのバーラーナシに現れると書いてあります。そのときは同時にサンカという名の転輪王も出現し、転輪王サンカはメッテーヤのもとで後に出家します。彼らが出現するまで後どれぐらいかかるかという記述はありません。しかし、とりあえず人間の寿命が十歳になってからそれから美徳の獲得とともに寿命が八万歳になるまでですから、人間の感覚としては相当後世になってからですがそれが果たして56億7000万年後かどうかは不明です。
「弥勒はトゥシタ天に今いてその寿命が56億7000万年だからその寿命が尽きた56億7000万年後に転生してくる」といわれますが、トゥシタ天の寿命は5億7600万年というのが原始仏典の記述です。
「比丘たちよ、人の400年はトゥシタ天の一日一夜である。
このような夜の30夜を一月となし、
このような月の12ヶ月を一年となし、
このような年の4000天年をもってトゥシタ天の寿命となす。
比丘たちよ、また処としてこの世に一部の男女は八分成就のウポーサタを修行すれば、身が破れて死して後にトゥシタ天の仲間に生じるだろう。
比丘たちよ、私はこれを意趣するがゆえに人の王権は天上の快楽に比較すれば微弱であると説く」
(『南伝大蔵経21 増支部経典5』大蔵出版 P148)
トゥシタ天の一日・・・人間の400年
トゥシタ天の一ヶ月・・人間の12,000年
トゥシタ天の一年・・・人間の144,000年
トゥシタ天の一生・・・人間の5,760,000年
400 × 30 × 12 × 4000 → 5億7600万年
ゴータマはカッサパ・ブッダの弟子であり、その時代に生きていました。ゴータマはカッサパ・ブッダの弟子であったジョーティパーラ・バラモンだったときに如来になる決意をしてその修行を満たしたことは十分あり得ます。ですから、ゴータマの弟子の一人が未来の弥勒として如来になる決意と修行をしてトゥシタ天に転生している可能性は高いと思います。複数の如来のもとで修行してブッダになる人もいるかも知れませんが、仮にそうだとしても次のブッダは弥勒ですから、ゴータマを最後の師としていた可能性はより一層高くなりますから、トゥシタ天の寿命の分が弥勒出現までの期間である可能性は高いです。これは弥勒に関する推論であって、実際に如来になるには大人二十戒を成就すればいいというのが原始仏典の記述ですので、「存命中のブッダの弟子でなければ如来にはなれない」という記述は原始仏典にはありませんので、注意してください。
ただ、カクサンダ・コーナーガマナ・カッサパの三ブッダでさえ寿命はみな異なります。トゥシタ天から最後の生に来るということは諸仏の法性であり、それに変わりはありませんが、「人の400年がトゥシタ天の一日」というその「人間の一日自体」が、各時代によって異なります。ヴィパッシン・ブッダは寿命が八万歳ですから、その一日は今の人間に比べるともっと長いことになりますし、剣の七日間がある最悪の時代においては寿命が十歳ですから、逆にその一日がかなり短くなります。こういったことを加味すると「今の時代の人間の時間で何年後に弥勒が出現するか」という問題はますます難しくなってきます。
そうは言っても、彼の教えの内容が「四諦」(四諦の集諦が十二縁起に相当)であることは間違いありません。原始仏典の記述には「あらゆる沙門婆羅門はこの四諦を覚るために出家する」とあり、また四諦を説いたときをもって「初転法輪」としているからです。四諦以外に、あるいは不死・輪廻超越・苦滅・涅槃以外に覚った人の教えはないということです。ですから、あえてメッテーヤを待つ必要はありませんが待っても可です。ブラフマー・サハンパティが次のゴータマ・ブッダに会ったように、神やブラフマーに転生としてメッテーヤ出現を待って会いに行くのも一興かも知れませんが、それは各個人の趣味の問題です。
3.原始仏典では「六道輪廻」とは言わず「五趣」と言う。
一般に輪廻転生は「六道(りくどう、ろくどう)」と言いますが、この記述は原始仏典にはまったくありません。根本的な間違いが「修羅道」でこれは「悪趣」ではありません。暴力団やヤクザやマフィアというものは人間であり、人間は悪趣ではないのと同様に、アスラは四大王やサッカ側のデーヴァと同じ神々であり、ちゃんとした神々です。
ヤクザは人間であって地獄の住人ではないように、アスラは神であって悪趣の住人ではありません。暴力団を絶対悪とするのは誤った見解であり、同様にアスラを絶対悪とするのも誤った見解であり、マーラ(悪魔)を絶対悪とするのも誤った見解です。ある生ける者が絶対悪であるということはあり得ません。一時的にデーヴァダッタのように「全体的に悪」になることはありますが、永遠に悪ではなく一劫後には地獄の寿命も尽きて善法が生じる可能性が出て来ると思います。原始仏教における悪とは「貪りと瞋りと癡かさ」という三悪根、これを絶対悪であると規定します。
原始仏典では「六道」とは言わず、「五趣」五つの行き先と言います。修羅道を除いた、地獄・餓鬼境・畜生胎・人間・天の五つです。これとは別に涅槃道があります。「六道はその生き方であって行き先ではない」と言う人がいますが、原始仏典での五趣の教えは「生き方でもあり行き先でもある記述内容」になっています。その経典では五趣+涅槃道の六つがまとめて語られています。ですから原始仏典の記述は「五趣+涅槃道」であり、よく言われるような「六道輪廻」という単語も関連する記述も原始仏典には存在していません。
4.「アヌルッダが失明していた」という記述は原始仏典には無い。
アヌルッダは自分を訪ねてくるサーリプッタやモッガーラナといつも普通に挨拶して会話しています。また外道を含めた四方サンガに宿を貸している美女と一夜をともにしたときも、彼女は美しく着飾っても誘惑し、裸になっても誘惑しましたがアヌルッダは一顧だにもせず、逆に説法して信者にしたという話が律蔵にあります。この武勇伝はサンガで大いに語られましたが、ゴータマに女性と一夜を共にするなと説教されます。この場合、彼が失明していれば話が変わって来ることになるのは自明の理です。これらの記述から僕はアヌルッダが失明していたという話を信じていません。
5.ゴータマが三阿僧祇劫かけて如来になったという記述は原始仏典にはまったく無い。
むしろカッサパ・ブッダに出会ってから間もなく如来になっており案外早いです。
如来になる方法は大人二十戒の記述しか原始仏典にはありません。
6.「波羅蜜」や「六波羅蜜」の記述は原始仏典にはまったく無い。
そのような修行方法に関する記述もありません。
7.原始仏典では「一乗」と言い「大乗」とか「小乗」という記述はまったく無い。
四念処の修行法のみによってあらゆる生ける者は清浄となり苦しみを乗り越えることから四念処の「一乗」(エーカ・ヤーナ)のみを原始仏典では説きます。「大乗」(マハー・ヤーナ)とか「小乗」(ヒーナ・ヤーナ)という単語も記述も一切ありません。「梵乗」(ブラフマ・ヤーナ)が聖八支道の別名として説かれることはあります。
8.因と縁は同じ原因の意
因[ニダーナ nidāna]を直接原因と捉え、縁[パッチャヤ paccaya]を間接原因と捉える人がいますが、原始仏典では因と縁は並記され、さらに集起[サムダヤ]や生じる[ジャーティ]とも並記され、まったく同じ意味で用いられています。「これがその因であり、縁である」というように。従って、因を直接原因とし縁を間接原因とするのは原始仏典の記述と異なっています。
9.嘘としての方便はない
方便の原語は「パリヤーヤ」(pariyāya)といって「方法・法門・理趣など」を意味します。普通は「方法」と訳されます。様々な方法でゴータマは説法しますが如来は「絶対に嘘をつきません」。嘘をつけば信用が失われます。たとえ利益ある嘘であっても、「この人は利益があるからといってまた嘘をつくかも知れない」という評価になるからです。一切の嘘から離れることは修行者の基本中の基本であり、阿羅漢もまた「自覚して嘘をつくことは不可能である」と書いてあります。
「嘘も方便」と言いますが、それは在家の話で真の阿羅漢が嘘を方便として採用し、ときに嘘をつくことは決してありません。悟った人たちは決して嘘つきではありません。
他にも異なる記述が発見されたら編集して追加することもあるかと思います。
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏教 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏教のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75484人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6444人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人