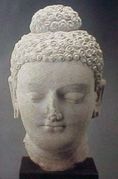涅槃の瞑想、涅槃一直線の三摩地について。
・涅槃三摩地
ここに「これ寂静、これ勝妙、一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」とこのように考える。これに集中することが涅槃三摩地です。これを繰り返すだけです。本当にこれだけです。
「これ寂静、これ勝妙、一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」
(これは寂静である。これは勝れている。一切の行が止まること、一切の執着の対象を完全放棄すること、渇愛が尽きること、貪りを離れること、滅尽していること、ニッバーナ)
増支部経典>三集>第四天使品
「 三十二
一 あるとき、具寿アーナンダは世尊のいるところに詣った。詣って世尊に問訊して一方に座った。一方に座って具寿アーナンダは世尊に言った。
大徳、比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるでしょうか。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
アーナンダ、比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるだろう。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
大徳、ではどのようにして、比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるのでしょうか。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
アーナンダ、ここに比丘はこのようにある。「これは寂静であり、これは妙勝である、即ち、一切の行の奢摩他、一切の依の定棄、渇愛の滅尽、離貪、滅、涅槃である」と。
アーナンダ、このようにして比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるだろう。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
アーナンダ、またこれに関してパーラーヤナ(波羅延那)の中のプンナカの問いの中で私は次のように説いた。
世の中にある勝れると 劣れるものとを思択して
世に何なるがありとても それに心の揺るぎなく
寂静にして煙なき 損害もなく欲も無い
人は生まれと老いとをば 超え渡れりと我は説く、と。」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P215–216
1.この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無い
2.外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無い
3.心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住する
解.ここに比丘はこのようにある。「これは寂静であり、これは妙勝である、即ち、一切の行の奢摩他、一切の依の定棄、渇愛の滅尽、離貪、滅、涅槃である」と。
僕がはじめこれを読んだときは意味がわからず、その重要性もわかりませんでした。この記述は非常に重要な記述です。この三摩地だけで解脱できるということが明らかです。「ニッバーナ・サマーディ」、「涅槃三摩地」です。これは九次第定の究極である想受滅の滅等至(ニローダ・サマーパッティ、滅への入定)とは異なります。そのときは一切想が滅尽し、一切受が滅尽するからです。しかし、この三摩地にはこのような想があります。即ち「これ寂静、これ妙勝、一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」、このような想を伴う有尋有伺三摩地によっても解脱します。このような想を伴う無尋唯伺三摩地によっても解脱します。このような想を伴う無尋無伺三摩地によっても解脱します。このような想を伴う有喜三摩地によっても解脱します。このような想を伴う無喜三摩地によっても、倶悦三摩地によっても、倶捨三摩地によっても解脱します。この涅槃三摩地は有想であって、無想ではありません。無相三摩地は一切相を作意せず、一切相の滅を作意する二つの作意を原因として結果される三摩地です。無想三摩地は想受滅に他なりません。想あるところに感受があり、感受があるところに想があり、両者は不可分だからです。涅槃三摩地は有想です。それを念じるならば念寂静(ウパサマーヌッサティ、upasamānussati、寂静随念)です。この想の三摩地に入るならば涅槃三摩地です。
従ってこの一文は完全丸暗記する価値があります。この「一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」は、ゴータマが悟ったときにもこれは衆生が見難いと言った第二項です。第一項は縁起が見難いと言いました。また、まだ引用していませんが、「それにおいてその想がなく、しかも有想」という想、それがこの涅槃想です。「涅槃想」という単語や「涅槃三摩地」という単語は原始仏典には見られませんが、この想、この三摩地以外に涅槃想、涅槃三摩地という単語に相応しいものは見いだせません。
「これは寂静である」。これによってその想が寂静性において究竟であることを示しています。想受滅は真の、究極の滅ではありません。想受滅に入ってしかも取が有り、愛が有り、貪が尽きないというのはあり得るからです。しかし、この涅槃想においては一切の結は断たれ、有愛は断たれ、慢は永断され、涅槃します。即ち、この想が最上の寂静想です。
「これは妙勝である」。もとは適用されるという意味ですが、転じて適用されるに相応しいもの、即ち、勝れているものとなります。もっとも劣中勝の三界に分ける場合の勝界にその単語が使用されていることから「勝れている」という意味にとって何の問題もないと思います。勝れているというのは、その善性、利性、楽性においてです。欲楽は愛尽楽の十六分の一にも相当しないと説かれています。即ち、この想が最勝想です。
「一切行奢摩他」。一切の行を奢摩他します。サマタとは原始仏典中に「いかにして心を静まらしめるべきか」という記述がある通りに静かにすることです。ここでは心をサマタするのではなくて、一切行をサマタします。行とは輪廻に導くものを形成しないことです。即ち、愛すること、取ること、染まること、貪ることです。一切行を諸行ととって一切五蘊と解釈するのは間違いです。なぜなら、阿羅漢たちにも五蘊がありますから。阿羅漢と凡夫の差異とは五蘊の有無ではなく五蘊への執着への有無にあります。ここに一切五蘊において彼は渇愛せず、執着せず、我と作さずに完全に解脱します。そのとき、彼はどこにおいても行じません。形成しません。彼がどこにおいても愛と取を形成せず、行じないとき、彼は内においても外においても何も取らずに解放されています。これが一切行奢摩他です。そして、それ以外に一切行奢摩他はありません。内においても外においても彼には我と作すことがないのに、しかも彼が行じるということはないからです。戯論は滅しています。
「一切依定棄」。依と訳されるウパディを僕は「執着の対象」と理解します。ウパーダーナ(upādāna)は「取、執着」と訳されます。取られるものは五蘊の他にはありません。それで依は五蘊であるように学者たちの間では解釈されています。しかし、「依なく」というのは五蘊なくと解釈すると合いません。それでウパディを僕は「執着の対象、彼が執着しているもの」と取ります。その一切を「定棄」します。僕はこれを「完全放棄」と受け取っています。七覚支の枕詞である「遠離に依り、離貪に依り、滅尽に依り、放棄に変化する」という文、この最後の「放棄」、これは一般には「捨に回向する」と訳され、原語はヴォッサッガ、vossagga、で意味は「捨、最捨、拾遺、棄捨」と書いてあります。またニッサッガ、nissagga、この意味も「捨遣、放捨」で、このヴォッサッガとニッサッガは「執着を捨てる」という意味で近いと考えています。七覚支において執着は「一つひとつ」捨てられるべきものなのでヴォッサッガなのだと思います。一方「一切依定棄」の場合は、「一切の」執着を捨てるので「パティ」がついてパティニッサッガとなっているのだと思います。それで完全放棄と僕は理解しています。執着を捨てればいいのですが、これが「依」という単語を使用することによって「あなたが執着している当の対象」を捨てなさいというところに意識が集中するところに意義があると思います。
「愛尽」。タンハー(渇愛)がカヤ(尽きる)です。先の執着の対象ができる原因は渇愛ですから、続いて愛尽が来ています。行の原因は取、取の原因は愛、愛の原因は楽受の貪り、ということでこういう順序になっているのだと思います。渇愛が尽きる、いわゆる欲愛、有愛、無有愛の三愛が尽きることによって愛尽解脱します。涅槃は無で阿羅漢は死ぬと無になるという邪見を持つ人はこの無有愛に絡めとられています。
「離貪」。ラーガ(貪)がヴィ(離れる)です。渇愛よりも楽受に重点を置くと貪りとなります。ローバとも同じ意味です。仏法僧を信じるという場合、この「離貪は有為・無為において最上」と信じることが特に最上の法への信であると説かれています。有為法中、最上のものは八正道です。「離貪」こそは原始仏教の根本です。三不善根でも最初に来ます。離貪という単語は聞き慣れないので「あらゆる欲望を断つこと、内においても外においても(外への欲望が主に五妙欲と言われるカーマ)」と僕は言い換えています。あらゆる欲望を断つことは、世間においても聖者の法と漠然とですが理解されています。それで宗教者が欲望にまみれていると世間の人はぶつぶつ言うのです。言い換えれば、「欲望を断つことは聖なることである」と本当は誰もが知っています。
「滅」。離貪するとき、離貪した対象からの解脱があります。そのとき、彼においてそれは滅したのです。逆に離貪していないならば、彼においてそれは生じています。ゆえに渇愛があるものは随伴住者と呼ばれるというのはそういうことです。渇愛があるとき、渇愛の対象がある、即ち、依(ウパディ)がある、従ってその執着対象とともに彼は存在する、ゆえに孤独ではない、執着を伴う悪不善尋が生起すると言われます。一方、あらゆるものを離貪しているならば、依はなく、彼においては内外において全てが滅しています。彼にそれが必要ない、彼はそれを我と見なさない、それが滅です。他に滅はありません。想受滅においては全てが滅しますが、想受滅からは出て来なければならないので、再び生起します。これは真の滅ではありません。また現実にこの外界と自己を完全に無に帰すことは因果律上、不可能です。従って、滅とは世界の滅ではありません。滅とは彼において内外と六触処への渇愛が滅すれば、それが滅です。彼は全然、無所有の修行を完成し、単独住者であり、孤独者であり、ただ滅を見ます。
「涅槃」。この涅槃想とは別の定型句、「一向厭患・離貪・滅・寂静・勝智・等覚・涅槃」という非常に重要な定型句がありますが、涅槃に行くまでに離貪の間に、寂静と勝智と等覚の三つがあります。彼が滅を見るときは心が寂静になり、寂静となったとき勝智し、勝智によって正しい悟りが生じるということでそういう順序になっているのだと思います。ここでその寂静と勝智と等覚が省かれているのは、それは心の働きであって想ではないからです。寂静は多分、寂静随念がありますし、勝智の想を持ってもそれは智の働きを観じるだけです。また等覚の想を持っても智による確信の働きだけです。この勝智と等覚の二つは修行の結果に出て来るものであって、それを想することが直接利益につながるものではないので省かれているのだと考えます。寂静の方は念じる形です。もっとも用語は違いますが「これ寂静」と最初に出ていますが。
涅槃の定義は決して「無ではなく」、「貪尽、瞋尽、癡尽」です。いわゆる三毒根絶です。「涅槃は苦である」と見るのが凡夫です。「涅槃は楽である」と見るのが聖弟子です。そして、現に涅槃は楽であると説かれます。三毒がなければ楽であるに違いなく、三毒があれば苦であるに相違ないからです。涅槃を無であると見て、阿羅漢の境地を息苦しい境地であると見て、如来も単独仏陀も阿羅漢も死後は無になると見る者はこの法と律から堕ちます。しかし、涅槃を楽であると見て、阿羅漢を自由な境地であると見て、阿羅漢の死後は無戯論であると見て、正しくこの法と律に住します。涅槃は悟って死んではじめて涅槃であると見る人は疑いに堕して流れに入りません。しかし、ゴータマは勝義現法涅槃、勝れた義利である現世における涅槃として、無取般涅槃を説きました。即ち、この現世において死ぬ以前において執着が無いことによって涅槃することです。即ち、死んでいない阿羅漢のことです。このように生きている状態における無取般涅槃という最上境地が示されていながら、一部の人は「死ななければ涅槃ではない」と邪見を説きます。これは彼と多くの人々にとって不利益となります。修行の最高境地への誤解が修行への意欲を決定づけるからです。芽吹き始めた人のやる気という新芽を摘む人は自他に不利益を為します。「ニッバーナは三毒の根絶である」と正しく説いて可です。
九次第定との関係においてこの涅槃三摩地を少し考察するのも有益です。大抵の人は、多く欲を考えて住します。それで彼らには常に欲尋が生起し、欲の思考が生起し、五蓋の第一である欲への意欲というゴミ袋に覆われています。五蓋に覆われているとき、彼は初禅という精神状態に達しません。これが普通の状態です。彼は五蓋の不利益を観じて外界への欲を断ちます。外界への欲が滅したその意識状態を名付けて初禅と言い、増上心と言い、坐禅を組むこととは関係ありません。行住坐臥、いつでも彼において欲が滅しているとき彼は初禅を具足しています。外界へ意識が散じることを断つとき、彼の意識は必然、内に集束し、身体の感覚を感じて、喜楽が生じることに気づきます。より一層の自覚によってより一層の安楽は増大します。第二禅において彼は思考を滅します。同様に、喜を、楽を・・・それらは滅です。次第に滅していくので九次第滅とも言います。つまり、精神統一とは心の内容を一つひとつ捨てて滅していく過程にあります。強力な念力で五蓋を押しつぶして想を獲得するというのは三摩地ではなくいわゆる念力です。しかし、九次第定を行なう彼においてはまだ、行はサマタされず、依は定棄されず、渇愛は滅せず、貪りは離れず、滅を見ず、涅槃していません。しかし、この九次第定が有用なのは身によって不死界に触れるからです。その安楽に依止して彼は増上心を修習し、欲への依存を断って、正しく不還となります。また捨によって精神統一を得るので、欲するところの如実知見を得ます。三摩地に入る者の智慧は加速します。さらに想受滅に入って出るならば空・無相・無願の三つの接触があり、また智慧によってその境地を正しく観じることによって無我を極めて、また苦の四諦をも、また漏の四諦をも如実に見て解脱します。しかし、四諦を知らなければ想受滅に入っても不死者にはなれません。想受滅は一つの集中に過ぎませんから。一部の人は想受滅には阿羅漢しか入れないと言います。これは誤りです。原始仏典中においては「想受滅に出入りする比丘が死んで天となるならば、そこにおいてその天は想受滅に出入りする道理はある」とサーリプッタが語っています。それをウダーイが三度否定する場面がありますが、結局、サーリプッタの言はゴータマに認可されます。言うまでもなく原始仏典には「阿羅漢でない者でも想受滅に出入りする」ということが書かれています。また中部経典においては想受滅に入っても不死者ではないということがはっきり書かれており、「如来において最上の寂静への道は明らかに覚知された。即ち、六触処の集滅味患離を如実に知って解脱することである」と想受滅の記述の後に結論として書いてあります。六触処の集滅味患離を如実に知って解脱することは原始仏教の根本です。そこに内外の一切があり、そこに内外の一切に関する智慧があり、その明知の結果として解脱と不死と楽があるからです。また原始仏典においても「梵行の初めとなるものである」と書いてあります。
最上の寂静は涅槃です。最勝もまた涅槃です。一切行をサマタすることは涅槃です。一切依を定棄することも涅槃です。愛尽も涅槃であり、離貪も涅槃であり、滅も涅槃です。それを見て僕はこの三摩地を涅槃三摩地と名付け、またこの想を涅槃想と名付けます。この「一切行奢摩他云々」の一文は最も重要な文章ですので、完全に丸暗記してそれぞれについて念じてみると得られるところが多いと思います。
[有識身と一切相において]
‘‘Siyā, ānanda, bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti.
有識身:識の有る身、saviññāṇake kāye
我慢:我と作すこと、ahaṅkāra、アハン(我)とカーラ(所作)
我所慢:我のものと作すこと、mamaṅkāra、ママン(我所)とカーラ(所作)
慢随眠:マーナーヌサヤ、mānānusayā、マーナ(慢)とアヌサヤ(随眠)
外の:バヒッダー、bahiddhā
一切相:サッバニミッタ、sabbanimitta、
[涅槃想]
‘etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhākkhayo virāgo nirodho nibbāna’nti.
‘これetaṃ 寂静santaṃ これetaṃ 妙勝paṇītaṃ 即ちyadidaṃ 一切行奢摩他sabbasaṅkhārasamatho 一切依定棄sabbūpadhipaṭinissaggo 愛尽taṇhākkhayo 離貪virāgo 滅nirodho 涅槃nibbāna’nti.
エータムサンタム、エータムパニータム。ヤディダム、サッバサンカーラサマトー、サッブーパディパティニッサッゴー、タンハッカヨー、ヴィラーゴー、ニロードー、ニッバーナ。
寂静:サンタ、santa、①寂静の、寂止の、寂者②疲れた、疲労の③ありつつ、現存の;善い、正しい、善人
極妙:パニータ、paṇīta 適用された、勝れた、妙勝の、極妙の、 参考:妙法(パニータダンマ)、勝界(パニータダートゥ、劣界中界勝界の三界の一)
一切行奢摩他:一切の行の寂止、止観のサマタに同じ、sabbasaṅkhārasamatho
一切依定棄:一切の執着の対象の完全放棄、sabbūpadhipaṭinissaggo
愛尽:渇愛の滅尽、タンハッカヤ、taṇhākkhaya
離貪:ヴィラーガ、virāga
滅:滅尽、ニローダ、nirodha
涅槃:ニッバーナ、nibbāna
2. Ānandasuttaṃ
前置き 32. Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca –
アーナンダ ‘‘Siyā nu kho, bhante, bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti?
ゴータマ ‘‘Siyā, ānanda, bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti.
アーナンダ ‘‘Yathā kathaṃ pana, bhante, siyā bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti?
ゴータマ ‘‘Idhānanda , bhikkhuno evaṃ hoti – ‘etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhākkhayo virāgo nirodho nibbāna’nti.
Evaṃ kho, ānanda, siyā bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti.
‘‘Idañca pana metaṃ, ānanda, sandhāya bhāsitaṃ pārāyane puṇṇakapañhe –
偈 ‘‘Saṅkhāya lokasmiṃ paroparāni [parovarāni (sī. pī.) su. ni. 1054; cūḷani. puṇṇakamāṇavapucchā 73],
Yassiñjitaṃ natthi kuhiñci loke;
Santo vidhūmo anīgho [anigho (sī. syā. kaṃ. pī.), anagho (?)] nirāso,
Atāri so jātijaranti brūmī’’ti. dutiyaṃ;
・涅槃三摩地
ここに「これ寂静、これ勝妙、一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」とこのように考える。これに集中することが涅槃三摩地です。これを繰り返すだけです。本当にこれだけです。
「これ寂静、これ勝妙、一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」
(これは寂静である。これは勝れている。一切の行が止まること、一切の執着の対象を完全放棄すること、渇愛が尽きること、貪りを離れること、滅尽していること、ニッバーナ)
増支部経典>三集>第四天使品
「 三十二
一 あるとき、具寿アーナンダは世尊のいるところに詣った。詣って世尊に問訊して一方に座った。一方に座って具寿アーナンダは世尊に言った。
大徳、比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるでしょうか。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
アーナンダ、比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるだろう。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
大徳、ではどのようにして、比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるのでしょうか。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
アーナンダ、ここに比丘はこのようにある。「これは寂静であり、これは妙勝である、即ち、一切の行の奢摩他、一切の依の定棄、渇愛の滅尽、離貪、滅、涅槃である」と。
アーナンダ、このようにして比丘が三摩地を獲得してこのようなことがあるだろう。即ち、この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無く、また心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住するということが。
アーナンダ、またこれに関してパーラーヤナ(波羅延那)の中のプンナカの問いの中で私は次のように説いた。
世の中にある勝れると 劣れるものとを思択して
世に何なるがありとても それに心の揺るぎなく
寂静にして煙なき 損害もなく欲も無い
人は生まれと老いとをば 超え渡れりと我は説く、と。」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P215–216
1.この有識身において我慢・我所慢・慢随眠が無い
2.外の一切相において我慢・我所慢・慢随眠が無い
3.心解脱・慧解脱を具足して住すれば、我慢・我所慢・慢随眠の無いその心解脱・慧解脱を具足して住する
解.ここに比丘はこのようにある。「これは寂静であり、これは妙勝である、即ち、一切の行の奢摩他、一切の依の定棄、渇愛の滅尽、離貪、滅、涅槃である」と。
僕がはじめこれを読んだときは意味がわからず、その重要性もわかりませんでした。この記述は非常に重要な記述です。この三摩地だけで解脱できるということが明らかです。「ニッバーナ・サマーディ」、「涅槃三摩地」です。これは九次第定の究極である想受滅の滅等至(ニローダ・サマーパッティ、滅への入定)とは異なります。そのときは一切想が滅尽し、一切受が滅尽するからです。しかし、この三摩地にはこのような想があります。即ち「これ寂静、これ妙勝、一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」、このような想を伴う有尋有伺三摩地によっても解脱します。このような想を伴う無尋唯伺三摩地によっても解脱します。このような想を伴う無尋無伺三摩地によっても解脱します。このような想を伴う有喜三摩地によっても解脱します。このような想を伴う無喜三摩地によっても、倶悦三摩地によっても、倶捨三摩地によっても解脱します。この涅槃三摩地は有想であって、無想ではありません。無相三摩地は一切相を作意せず、一切相の滅を作意する二つの作意を原因として結果される三摩地です。無想三摩地は想受滅に他なりません。想あるところに感受があり、感受があるところに想があり、両者は不可分だからです。涅槃三摩地は有想です。それを念じるならば念寂静(ウパサマーヌッサティ、upasamānussati、寂静随念)です。この想の三摩地に入るならば涅槃三摩地です。
従ってこの一文は完全丸暗記する価値があります。この「一切行奢摩他、一切依定棄、愛尽、離貪、滅、涅槃」は、ゴータマが悟ったときにもこれは衆生が見難いと言った第二項です。第一項は縁起が見難いと言いました。また、まだ引用していませんが、「それにおいてその想がなく、しかも有想」という想、それがこの涅槃想です。「涅槃想」という単語や「涅槃三摩地」という単語は原始仏典には見られませんが、この想、この三摩地以外に涅槃想、涅槃三摩地という単語に相応しいものは見いだせません。
「これは寂静である」。これによってその想が寂静性において究竟であることを示しています。想受滅は真の、究極の滅ではありません。想受滅に入ってしかも取が有り、愛が有り、貪が尽きないというのはあり得るからです。しかし、この涅槃想においては一切の結は断たれ、有愛は断たれ、慢は永断され、涅槃します。即ち、この想が最上の寂静想です。
「これは妙勝である」。もとは適用されるという意味ですが、転じて適用されるに相応しいもの、即ち、勝れているものとなります。もっとも劣中勝の三界に分ける場合の勝界にその単語が使用されていることから「勝れている」という意味にとって何の問題もないと思います。勝れているというのは、その善性、利性、楽性においてです。欲楽は愛尽楽の十六分の一にも相当しないと説かれています。即ち、この想が最勝想です。
「一切行奢摩他」。一切の行を奢摩他します。サマタとは原始仏典中に「いかにして心を静まらしめるべきか」という記述がある通りに静かにすることです。ここでは心をサマタするのではなくて、一切行をサマタします。行とは輪廻に導くものを形成しないことです。即ち、愛すること、取ること、染まること、貪ることです。一切行を諸行ととって一切五蘊と解釈するのは間違いです。なぜなら、阿羅漢たちにも五蘊がありますから。阿羅漢と凡夫の差異とは五蘊の有無ではなく五蘊への執着への有無にあります。ここに一切五蘊において彼は渇愛せず、執着せず、我と作さずに完全に解脱します。そのとき、彼はどこにおいても行じません。形成しません。彼がどこにおいても愛と取を形成せず、行じないとき、彼は内においても外においても何も取らずに解放されています。これが一切行奢摩他です。そして、それ以外に一切行奢摩他はありません。内においても外においても彼には我と作すことがないのに、しかも彼が行じるということはないからです。戯論は滅しています。
「一切依定棄」。依と訳されるウパディを僕は「執着の対象」と理解します。ウパーダーナ(upādāna)は「取、執着」と訳されます。取られるものは五蘊の他にはありません。それで依は五蘊であるように学者たちの間では解釈されています。しかし、「依なく」というのは五蘊なくと解釈すると合いません。それでウパディを僕は「執着の対象、彼が執着しているもの」と取ります。その一切を「定棄」します。僕はこれを「完全放棄」と受け取っています。七覚支の枕詞である「遠離に依り、離貪に依り、滅尽に依り、放棄に変化する」という文、この最後の「放棄」、これは一般には「捨に回向する」と訳され、原語はヴォッサッガ、vossagga、で意味は「捨、最捨、拾遺、棄捨」と書いてあります。またニッサッガ、nissagga、この意味も「捨遣、放捨」で、このヴォッサッガとニッサッガは「執着を捨てる」という意味で近いと考えています。七覚支において執着は「一つひとつ」捨てられるべきものなのでヴォッサッガなのだと思います。一方「一切依定棄」の場合は、「一切の」執着を捨てるので「パティ」がついてパティニッサッガとなっているのだと思います。それで完全放棄と僕は理解しています。執着を捨てればいいのですが、これが「依」という単語を使用することによって「あなたが執着している当の対象」を捨てなさいというところに意識が集中するところに意義があると思います。
「愛尽」。タンハー(渇愛)がカヤ(尽きる)です。先の執着の対象ができる原因は渇愛ですから、続いて愛尽が来ています。行の原因は取、取の原因は愛、愛の原因は楽受の貪り、ということでこういう順序になっているのだと思います。渇愛が尽きる、いわゆる欲愛、有愛、無有愛の三愛が尽きることによって愛尽解脱します。涅槃は無で阿羅漢は死ぬと無になるという邪見を持つ人はこの無有愛に絡めとられています。
「離貪」。ラーガ(貪)がヴィ(離れる)です。渇愛よりも楽受に重点を置くと貪りとなります。ローバとも同じ意味です。仏法僧を信じるという場合、この「離貪は有為・無為において最上」と信じることが特に最上の法への信であると説かれています。有為法中、最上のものは八正道です。「離貪」こそは原始仏教の根本です。三不善根でも最初に来ます。離貪という単語は聞き慣れないので「あらゆる欲望を断つこと、内においても外においても(外への欲望が主に五妙欲と言われるカーマ)」と僕は言い換えています。あらゆる欲望を断つことは、世間においても聖者の法と漠然とですが理解されています。それで宗教者が欲望にまみれていると世間の人はぶつぶつ言うのです。言い換えれば、「欲望を断つことは聖なることである」と本当は誰もが知っています。
「滅」。離貪するとき、離貪した対象からの解脱があります。そのとき、彼においてそれは滅したのです。逆に離貪していないならば、彼においてそれは生じています。ゆえに渇愛があるものは随伴住者と呼ばれるというのはそういうことです。渇愛があるとき、渇愛の対象がある、即ち、依(ウパディ)がある、従ってその執着対象とともに彼は存在する、ゆえに孤独ではない、執着を伴う悪不善尋が生起すると言われます。一方、あらゆるものを離貪しているならば、依はなく、彼においては内外において全てが滅しています。彼にそれが必要ない、彼はそれを我と見なさない、それが滅です。他に滅はありません。想受滅においては全てが滅しますが、想受滅からは出て来なければならないので、再び生起します。これは真の滅ではありません。また現実にこの外界と自己を完全に無に帰すことは因果律上、不可能です。従って、滅とは世界の滅ではありません。滅とは彼において内外と六触処への渇愛が滅すれば、それが滅です。彼は全然、無所有の修行を完成し、単独住者であり、孤独者であり、ただ滅を見ます。
「涅槃」。この涅槃想とは別の定型句、「一向厭患・離貪・滅・寂静・勝智・等覚・涅槃」という非常に重要な定型句がありますが、涅槃に行くまでに離貪の間に、寂静と勝智と等覚の三つがあります。彼が滅を見るときは心が寂静になり、寂静となったとき勝智し、勝智によって正しい悟りが生じるということでそういう順序になっているのだと思います。ここでその寂静と勝智と等覚が省かれているのは、それは心の働きであって想ではないからです。寂静は多分、寂静随念がありますし、勝智の想を持ってもそれは智の働きを観じるだけです。また等覚の想を持っても智による確信の働きだけです。この勝智と等覚の二つは修行の結果に出て来るものであって、それを想することが直接利益につながるものではないので省かれているのだと考えます。寂静の方は念じる形です。もっとも用語は違いますが「これ寂静」と最初に出ていますが。
涅槃の定義は決して「無ではなく」、「貪尽、瞋尽、癡尽」です。いわゆる三毒根絶です。「涅槃は苦である」と見るのが凡夫です。「涅槃は楽である」と見るのが聖弟子です。そして、現に涅槃は楽であると説かれます。三毒がなければ楽であるに違いなく、三毒があれば苦であるに相違ないからです。涅槃を無であると見て、阿羅漢の境地を息苦しい境地であると見て、如来も単独仏陀も阿羅漢も死後は無になると見る者はこの法と律から堕ちます。しかし、涅槃を楽であると見て、阿羅漢を自由な境地であると見て、阿羅漢の死後は無戯論であると見て、正しくこの法と律に住します。涅槃は悟って死んではじめて涅槃であると見る人は疑いに堕して流れに入りません。しかし、ゴータマは勝義現法涅槃、勝れた義利である現世における涅槃として、無取般涅槃を説きました。即ち、この現世において死ぬ以前において執着が無いことによって涅槃することです。即ち、死んでいない阿羅漢のことです。このように生きている状態における無取般涅槃という最上境地が示されていながら、一部の人は「死ななければ涅槃ではない」と邪見を説きます。これは彼と多くの人々にとって不利益となります。修行の最高境地への誤解が修行への意欲を決定づけるからです。芽吹き始めた人のやる気という新芽を摘む人は自他に不利益を為します。「ニッバーナは三毒の根絶である」と正しく説いて可です。
九次第定との関係においてこの涅槃三摩地を少し考察するのも有益です。大抵の人は、多く欲を考えて住します。それで彼らには常に欲尋が生起し、欲の思考が生起し、五蓋の第一である欲への意欲というゴミ袋に覆われています。五蓋に覆われているとき、彼は初禅という精神状態に達しません。これが普通の状態です。彼は五蓋の不利益を観じて外界への欲を断ちます。外界への欲が滅したその意識状態を名付けて初禅と言い、増上心と言い、坐禅を組むこととは関係ありません。行住坐臥、いつでも彼において欲が滅しているとき彼は初禅を具足しています。外界へ意識が散じることを断つとき、彼の意識は必然、内に集束し、身体の感覚を感じて、喜楽が生じることに気づきます。より一層の自覚によってより一層の安楽は増大します。第二禅において彼は思考を滅します。同様に、喜を、楽を・・・それらは滅です。次第に滅していくので九次第滅とも言います。つまり、精神統一とは心の内容を一つひとつ捨てて滅していく過程にあります。強力な念力で五蓋を押しつぶして想を獲得するというのは三摩地ではなくいわゆる念力です。しかし、九次第定を行なう彼においてはまだ、行はサマタされず、依は定棄されず、渇愛は滅せず、貪りは離れず、滅を見ず、涅槃していません。しかし、この九次第定が有用なのは身によって不死界に触れるからです。その安楽に依止して彼は増上心を修習し、欲への依存を断って、正しく不還となります。また捨によって精神統一を得るので、欲するところの如実知見を得ます。三摩地に入る者の智慧は加速します。さらに想受滅に入って出るならば空・無相・無願の三つの接触があり、また智慧によってその境地を正しく観じることによって無我を極めて、また苦の四諦をも、また漏の四諦をも如実に見て解脱します。しかし、四諦を知らなければ想受滅に入っても不死者にはなれません。想受滅は一つの集中に過ぎませんから。一部の人は想受滅には阿羅漢しか入れないと言います。これは誤りです。原始仏典中においては「想受滅に出入りする比丘が死んで天となるならば、そこにおいてその天は想受滅に出入りする道理はある」とサーリプッタが語っています。それをウダーイが三度否定する場面がありますが、結局、サーリプッタの言はゴータマに認可されます。言うまでもなく原始仏典には「阿羅漢でない者でも想受滅に出入りする」ということが書かれています。また中部経典においては想受滅に入っても不死者ではないということがはっきり書かれており、「如来において最上の寂静への道は明らかに覚知された。即ち、六触処の集滅味患離を如実に知って解脱することである」と想受滅の記述の後に結論として書いてあります。六触処の集滅味患離を如実に知って解脱することは原始仏教の根本です。そこに内外の一切があり、そこに内外の一切に関する智慧があり、その明知の結果として解脱と不死と楽があるからです。また原始仏典においても「梵行の初めとなるものである」と書いてあります。
最上の寂静は涅槃です。最勝もまた涅槃です。一切行をサマタすることは涅槃です。一切依を定棄することも涅槃です。愛尽も涅槃であり、離貪も涅槃であり、滅も涅槃です。それを見て僕はこの三摩地を涅槃三摩地と名付け、またこの想を涅槃想と名付けます。この「一切行奢摩他云々」の一文は最も重要な文章ですので、完全に丸暗記してそれぞれについて念じてみると得られるところが多いと思います。
[有識身と一切相において]
‘‘Siyā, ānanda, bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti.
有識身:識の有る身、saviññāṇake kāye
我慢:我と作すこと、ahaṅkāra、アハン(我)とカーラ(所作)
我所慢:我のものと作すこと、mamaṅkāra、ママン(我所)とカーラ(所作)
慢随眠:マーナーヌサヤ、mānānusayā、マーナ(慢)とアヌサヤ(随眠)
外の:バヒッダー、bahiddhā
一切相:サッバニミッタ、sabbanimitta、
[涅槃想]
‘etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhākkhayo virāgo nirodho nibbāna’nti.
‘これetaṃ 寂静santaṃ これetaṃ 妙勝paṇītaṃ 即ちyadidaṃ 一切行奢摩他sabbasaṅkhārasamatho 一切依定棄sabbūpadhipaṭinissaggo 愛尽taṇhākkhayo 離貪virāgo 滅nirodho 涅槃nibbāna’nti.
エータムサンタム、エータムパニータム。ヤディダム、サッバサンカーラサマトー、サッブーパディパティニッサッゴー、タンハッカヨー、ヴィラーゴー、ニロードー、ニッバーナ。
寂静:サンタ、santa、①寂静の、寂止の、寂者②疲れた、疲労の③ありつつ、現存の;善い、正しい、善人
極妙:パニータ、paṇīta 適用された、勝れた、妙勝の、極妙の、 参考:妙法(パニータダンマ)、勝界(パニータダートゥ、劣界中界勝界の三界の一)
一切行奢摩他:一切の行の寂止、止観のサマタに同じ、sabbasaṅkhārasamatho
一切依定棄:一切の執着の対象の完全放棄、sabbūpadhipaṭinissaggo
愛尽:渇愛の滅尽、タンハッカヤ、taṇhākkhaya
離貪:ヴィラーガ、virāga
滅:滅尽、ニローダ、nirodha
涅槃:ニッバーナ、nibbāna
2. Ānandasuttaṃ
前置き 32. Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca –
アーナンダ ‘‘Siyā nu kho, bhante, bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti?
ゴータマ ‘‘Siyā, ānanda, bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti.
アーナンダ ‘‘Yathā kathaṃ pana, bhante, siyā bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti?
ゴータマ ‘‘Idhānanda , bhikkhuno evaṃ hoti – ‘etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhākkhayo virāgo nirodho nibbāna’nti.
Evaṃ kho, ānanda, siyā bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu, bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu; yañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyā’’ti.
‘‘Idañca pana metaṃ, ānanda, sandhāya bhāsitaṃ pārāyane puṇṇakapañhe –
偈 ‘‘Saṅkhāya lokasmiṃ paroparāni [parovarāni (sī. pī.) su. ni. 1054; cūḷani. puṇṇakamāṇavapucchā 73],
Yassiñjitaṃ natthi kuhiñci loke;
Santo vidhūmo anīgho [anigho (sī. syā. kaṃ. pī.), anagho (?)] nirāso,
Atāri so jātijaranti brūmī’’ti. dutiyaṃ;
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏教 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏教のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75480人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6436人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人