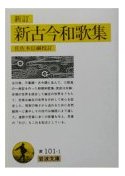和泉式部
783寝覚めする身を吹き通す風の音を
昔は袖のよそにこそ聞きけん(哀傷歌)
「眼を覚まさせるように風が吹きすぎて
いく音を以前は袖に涙することなどない
他人事のように聞いていたものだ」という
歌であろう。
和泉式部は新古今が成立した鎌倉初期の時代よりも
200年ほど前の10世紀末の時代を生きた人物であった。
和泉式部は「恋多き女」という言い方がついて
まわり、実人生での男性との関係について
説明が多く割かれる。
しかし、恋多き女と言われた女はほかにも
いただろうが、和泉式部のような歌を残して
いない。
歌人としてみるには、いったんその生涯と
切り離してその歌だけを読んでみる必要がある。
新古今の技巧を駆使した華やかの歌と比べれば、
和泉式部の歌の多くは平明で、一見、線の細い
華奢な印象がある。しかし、よく読めば、
そのしなやかさは芯に根強いものがある。
歌を作る気持ちは人それぞれのものがあるだろうが
和泉式部は日常の感性の中から言葉が生まれている。
歌の芯となるものが普段の生活と地続きなのだ。
和泉式部には過去の和歌の伝統を踏まえたり
四季を詠んだものが少ない。
本歌取りや詩語ともいうべき地名を
読み込んだような序詞を使った歌も
少ない。
多くの歌人には万葉や古今の詩歌の伝統に
繋がろうとする気持ちが強かったはずだが、
和泉式部の歌にはその気配が薄いのだ。
むろん、そういう秀歌も残しているが、
その歌を詠む方法論には昔の歌を読んだり、
四季に触発されて自然との交感の中から
詩作するということが少ないのである。
自分の中の日常の感性から歌が作られて
いる。
こういう歌人は珍しい。
その平明な詠いぶりは平凡のようでいて
実は他がまねの出来ないスタイルと
なっている。
和泉式部と同時代人である紫式部は
「ものおぼえ、歌のことわり、
まことの歌詠みざまにこそはべらざらめ」
と評している(「紫式部日記」)。
「古典詩歌の知識や歌の理論などは
詳しくないようで本当の歌詠みと言う
ほどではない」という意味であろう。
紫式部は「源氏物語」があまりにも大きな
存在だが、その歌のスタイルは(私見では)
俊成ら後世の歌人に影響を与えた歌人である。
技巧を駆使しイメージを重ね濃密な雰囲気
を作り出す歌は新古今の歌人たちの歌風と
密接なものがある。
和泉式部とは歌のスタイルが違うのだ。
和泉式部はそのスタイルで平安の歌人たちの
なかで孤立していると言っていいのかもしれない。
紫式部日記は続いて「はづかしげの歌よみや
とはおぼえはべらず」と記している。
「こちらが恥ずかしくなるほどの優れた歌人
とは思えない」というのであろう。
この評は自らの文才に強い自負を
もち、源氏物語という前人未踏の
作品を作った人物の評とみないといけない。
和泉式部には文学的な功名心が薄いのである。
和泉式部の歌には紫式部や新古今の歌人の
ような気負いがない。
ほとんど日記をつけるように
歌を詠んでいたように思われる。
和泉式部は日々のメモとして
歌を詠んでいたかもしれない。
その歌にその時期の記憶と
密接に結びついていたのでは。
和泉式部の歌には新古今時代の歌人たちの
ように、歌の中に自分の人生を悲劇化する
ことがない。
新古今の歌人の多くにとって四季や伝統の
歌の世界は自分を悲劇の主人公とする
ための舞台なのだ。
日常の普段の自分から抜けだしたいという
気持ち、日常を嫌う気持ちがそこにある。
和泉式部には和泉式部には悲劇的な感情や
自分を不幸と思う気持ちはない。
日常を嫌う思いがないのだ。
年を経て老いを嫌う気持ちは
あるとしても、歌の多くは
もっと泰然とした気持ちの
なかから生まれている。
新古今に採られた中で好きなのは
宮廷勤めで一緒だった
赤染衛門との歌のやりとりである
(雑歌下)。
1820うつろわでしばし信太(しのだ)の森を見よ
かへりもぞする葛の裏風(赤染衛門)
1821秋風はすごく吹くとも葛の葉のうらみがほには
みえじとぞ思う(和泉式部)
前書きに「和泉式部、道貞に去られて後、
ほどなく敦道親王通ふと聞きて、遣わしける」
とある。
親王を受け入れるよりも前夫である道貞を
あきらめず戻ってくるのを待っては
どうかと親友赤染衛門は言うのである。
友人とはいえ、こういう助言をすることは
難しい。
赤染衛門は包容力のある女性だったと思うが、
その包容力に応えるだけの人間的な器量が
和泉式部自身にもあったのだと思う。
もうひとつ、好きな歌をあげたい。
1640世をそむく方はいづくもありぬべし
大原山はすみよかりきや(雑歌中)
当時の出家は世間との交わりを
断つものだったから周囲にとっても
深刻なことであった。
事情は異にせよ、出家する
友の並々ならぬ気持ちは
痛いほどわかったのだろう。
「大原山はすみよかりきや」と
呼びかける歌に作者の友への
やさしいこころ使いが感じられる。
和泉式部は新古今には25首採られている。
俊成の千載集では21首、死後100年ほど後の
勅撰集である後拾遺和歌集では歌集中
最多の68首が採られている。
「八代集抄」は37首採っている。
高い評価である。
和泉式部の歌で一般に知られているのは
定家の「百人一首」に採られた
「あらざらんこの世のほかの思ひいでに
今ひとたびの逢ふこともがな(後拾遺763)」
であろう。
定家はなぜこの一首を採ったのか。
そこには恋多き女という伝説が
よく現れているとおもったので
あろうし、人間よりも歌の技法により
関心があった定家は「あらざらん」という
思い切った詠み方を評価したのだと思う。
783寝覚めする身を吹き通す風の音を
昔は袖のよそにこそ聞きけん(哀傷歌)
「眼を覚まさせるように風が吹きすぎて
いく音を以前は袖に涙することなどない
他人事のように聞いていたものだ」という
歌であろう。
和泉式部は新古今が成立した鎌倉初期の時代よりも
200年ほど前の10世紀末の時代を生きた人物であった。
和泉式部は「恋多き女」という言い方がついて
まわり、実人生での男性との関係について
説明が多く割かれる。
しかし、恋多き女と言われた女はほかにも
いただろうが、和泉式部のような歌を残して
いない。
歌人としてみるには、いったんその生涯と
切り離してその歌だけを読んでみる必要がある。
新古今の技巧を駆使した華やかの歌と比べれば、
和泉式部の歌の多くは平明で、一見、線の細い
華奢な印象がある。しかし、よく読めば、
そのしなやかさは芯に根強いものがある。
歌を作る気持ちは人それぞれのものがあるだろうが
和泉式部は日常の感性の中から言葉が生まれている。
歌の芯となるものが普段の生活と地続きなのだ。
和泉式部には過去の和歌の伝統を踏まえたり
四季を詠んだものが少ない。
本歌取りや詩語ともいうべき地名を
読み込んだような序詞を使った歌も
少ない。
多くの歌人には万葉や古今の詩歌の伝統に
繋がろうとする気持ちが強かったはずだが、
和泉式部の歌にはその気配が薄いのだ。
むろん、そういう秀歌も残しているが、
その歌を詠む方法論には昔の歌を読んだり、
四季に触発されて自然との交感の中から
詩作するということが少ないのである。
自分の中の日常の感性から歌が作られて
いる。
こういう歌人は珍しい。
その平明な詠いぶりは平凡のようでいて
実は他がまねの出来ないスタイルと
なっている。
和泉式部と同時代人である紫式部は
「ものおぼえ、歌のことわり、
まことの歌詠みざまにこそはべらざらめ」
と評している(「紫式部日記」)。
「古典詩歌の知識や歌の理論などは
詳しくないようで本当の歌詠みと言う
ほどではない」という意味であろう。
紫式部は「源氏物語」があまりにも大きな
存在だが、その歌のスタイルは(私見では)
俊成ら後世の歌人に影響を与えた歌人である。
技巧を駆使しイメージを重ね濃密な雰囲気
を作り出す歌は新古今の歌人たちの歌風と
密接なものがある。
和泉式部とは歌のスタイルが違うのだ。
和泉式部はそのスタイルで平安の歌人たちの
なかで孤立していると言っていいのかもしれない。
紫式部日記は続いて「はづかしげの歌よみや
とはおぼえはべらず」と記している。
「こちらが恥ずかしくなるほどの優れた歌人
とは思えない」というのであろう。
この評は自らの文才に強い自負を
もち、源氏物語という前人未踏の
作品を作った人物の評とみないといけない。
和泉式部には文学的な功名心が薄いのである。
和泉式部の歌には紫式部や新古今の歌人の
ような気負いがない。
ほとんど日記をつけるように
歌を詠んでいたように思われる。
和泉式部は日々のメモとして
歌を詠んでいたかもしれない。
その歌にその時期の記憶と
密接に結びついていたのでは。
和泉式部の歌には新古今時代の歌人たちの
ように、歌の中に自分の人生を悲劇化する
ことがない。
新古今の歌人の多くにとって四季や伝統の
歌の世界は自分を悲劇の主人公とする
ための舞台なのだ。
日常の普段の自分から抜けだしたいという
気持ち、日常を嫌う気持ちがそこにある。
和泉式部には和泉式部には悲劇的な感情や
自分を不幸と思う気持ちはない。
日常を嫌う思いがないのだ。
年を経て老いを嫌う気持ちは
あるとしても、歌の多くは
もっと泰然とした気持ちの
なかから生まれている。
新古今に採られた中で好きなのは
宮廷勤めで一緒だった
赤染衛門との歌のやりとりである
(雑歌下)。
1820うつろわでしばし信太(しのだ)の森を見よ
かへりもぞする葛の裏風(赤染衛門)
1821秋風はすごく吹くとも葛の葉のうらみがほには
みえじとぞ思う(和泉式部)
前書きに「和泉式部、道貞に去られて後、
ほどなく敦道親王通ふと聞きて、遣わしける」
とある。
親王を受け入れるよりも前夫である道貞を
あきらめず戻ってくるのを待っては
どうかと親友赤染衛門は言うのである。
友人とはいえ、こういう助言をすることは
難しい。
赤染衛門は包容力のある女性だったと思うが、
その包容力に応えるだけの人間的な器量が
和泉式部自身にもあったのだと思う。
もうひとつ、好きな歌をあげたい。
1640世をそむく方はいづくもありぬべし
大原山はすみよかりきや(雑歌中)
当時の出家は世間との交わりを
断つものだったから周囲にとっても
深刻なことであった。
事情は異にせよ、出家する
友の並々ならぬ気持ちは
痛いほどわかったのだろう。
「大原山はすみよかりきや」と
呼びかける歌に作者の友への
やさしいこころ使いが感じられる。
和泉式部は新古今には25首採られている。
俊成の千載集では21首、死後100年ほど後の
勅撰集である後拾遺和歌集では歌集中
最多の68首が採られている。
「八代集抄」は37首採っている。
高い評価である。
和泉式部の歌で一般に知られているのは
定家の「百人一首」に採られた
「あらざらんこの世のほかの思ひいでに
今ひとたびの逢ふこともがな(後拾遺763)」
であろう。
定家はなぜこの一首を採ったのか。
そこには恋多き女という伝説が
よく現れているとおもったので
あろうし、人間よりも歌の技法により
関心があった定家は「あらざらん」という
思い切った詠み方を評価したのだと思う。
|
|
|
|
|
|
|
|
新古今和歌集私撰:百人の歌人 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
新古今和歌集私撰:百人の歌人のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75499人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208294人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196031人