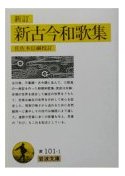(1071)由良の門(と)を渡る舟人梶緒(かじを)絶え
ゆくへも知らぬ恋の道かな(恋歌一)
「流れのきつい由良の海峡を渡る舟人が舵をなくして
ゆらゆらと流され揺れていくように、わたしの恋は
先の見えない中にただ揺れて漂っていく」という歌であろう。
「緒」は「紐」や「綱」の意味で、助詞の「を」ではない。
小学館本の脚注によると、「梶緒」とは「櫨(ろ)の綱」のことで
「 梶緒絶え」で「櫨(ろ)の綱切れ」の意味。
「由良」という地名の音が「揺れる」に通じて
いることは明らかだ。
曾禰好忠は新古今に16首、八代集抄に13首を採られている。
(俊成は千載集にこの歌人を採り上げていない)。
中古三十六歌仙の一人とある。
和泉式部や紫式部とほぼ同時代か、少し早い時代の人らしい。
印象を言えば、詩歌の古典世界を自分の感性を大事にして詠んで
いる歌が眼につく。
自分の感性を大事にした人と言えよう。
ただ、宮内卿や初期の伊勢のように、古典の歌世界を
自分の感性で染め上げる性格のものではない。
日常の生活感覚と地続きなところから歌は始まっても、
その感性がそのまま自立した歌となる和泉式部とも違う。
よく言えば古典と自身の感性を大事にした中庸とも言える
位置だが、悪く言えば、常識的でどっちつかずとも
中途半端とも言える。
「好忠集」を見ると、この人の歌はリズムが似通っていて、
読解力の無さを棚に上げて言えば、読んでいると眠くなる
ところがある。
そんな歌の中で新古今や八代集抄が選んでいるのは、この人の
感性が自分の眼で歌を詠もうとした歌だ。
好忠の自分の眼で見た実景を詠う詩心は、身の周りの自然に敏感で、
言葉の新鮮さや繊細さを感じさせる。
この人の歌は前半で感性に受け止めたものを詠んで、後半で
その受け止めたものの意味を古典詩歌の中で位置づける型の
ものが多い。
(619)草の上にここら玉ゐし白露を下葉の霜とむすぶ冬かな(冬歌)
「草の上にここら玉ゐし白露を」(草の上に白露が数多く置かれたの意)
という前半は 眼の前の自然に作者の感性が打たれ、その実景を詠む気持ちが
そのまま作者を表現の世界に導いている。後半の「下葉の霜とむすぶ冬かな」は、
作者の詩心が主導しているとはいえ、古典の教養で形を整え
詠んでいるように思われる。
(311)朝ぼらけ荻の上葉の露見ればややはださむし秋の初風(秋歌上)
この歌はその型のヴァリエイシヨンで、「ややはださむし」という実景を前に、
「朝ぼらけ萩の上葉の露見れば」、「秋の初風」と古典詩歌の世界を詠み
こんだものであろう。
好忠が古典の枠組みやトーンを尊重した歌作りをしているのは、辛らつに言えば、
歌を作り上げる詩の膨らみと構想力に乏しかったせいだとも言える。
良い歌はあっても力強さ、歌の大きさを感じさせる作は少ない。
五七五七七という詩形のもつリズムに依存し、その詩形を揺さぶる
自分のリズムがない。
その感性は静的で、感性が作者の内面を突き動かす面には弱いものが
ある。
そんな中では、次の歌は例外的と言っていい歌に思われる。
(186)花散ちりし庭の木の葉も茂りあひて天照る月の影ぞまれなる(夏歌)
感性が最後まで歌を主導し、「冬かな」とか「秋の初風」とか
教養的な知識で詠んでいない。
次の歌は霧で眼に見えない様子を詠むことで逆に実景を彷彿とさせる
ユニークな表現で、この歌人の技量を感じさせる。
(495)山里に霧のまがきのへだてずは遠方人(おちかたびと)の袖も見てまし(秋歌下)
「由良の門を渡る舟人舵緒絶えゆくへも知らぬ恋の道かな」は、
好忠の歌の中では抜きん出た作となっている。
好忠の実景を大事にした感性と古典詩歌の枠組みの中に自分の詩心を集約する
スタイルが詩形として見事に生きた例である。
その「由良の門を渡る舟人舵緒絶え」というイメージの
膨らみは新古今の中でも屈指のものであり、感性だけにも
教養だけにもよらない力強いものになっている。
「由良」の地名について諸説があるらしい。
「由良の門は、古くから紀淡海峡を指し、歌枕『由良の岬』として
しられていた、しかし好忠が丹後掾(たんごのじょう)をつとめて
いた関係で、契沖は丹後(京都)の由良河口とする解をとっている。
しかし歌の柄からみて、これは歌枕としての紀伊の由良を考えるのが
自然である。そうとってこそ、波の荒い海峡で、恋の舟の舵をなくして
漂うイメージが生きる。」(大岡信「百人一首」世界文化社)
地名がどこを指すかはともかく、「由良の門を渡る舟人舵緒絶え」
という五七五には、作者が実際に眼にした実景から受けた印象が
刻まれていることは確かであろう。
勅撰集は過去の勅撰集に採り上げられた歌は採らないという
方針があるようだが、この歌は新古今以前に採られていないのが
不思議なほどだ。
定家も百人一首にこの歌を採っている。
新古今の「恋歌」は、この歌の後に一首おいて、良経の次の歌を
続けている。
(1073)梶緒絶え由良の湊(みなと)に寄る舟のたよりも知らぬ沖つ潮風
良経の歌に比べられると、好忠の歌の姿が明らかになる。
好忠の歌を踏まえた本歌取りとはいえ、良経の歌の方が圧倒的な
存在感を持った大きな歌となっている。
現在から見れば、両者の歌が新古今に並んでいるのは残酷なほどだ。
歌人としての力量の違いがはっきりと現れている。
新古今の編集長である後鳥羽は、むろん、好忠の持つ
形の整った味わいを大事にしたのだろう。
百人一首の解説を読むと、必ずと言っていいほど、
この好忠が円融院の子の日の御幸に呼ばれもせずに
姿を現し追いやられたというエピソードが載っている。
他にも奇行が多かったというが、新古今を通して歌を
読む限りは決して強い個性の歌人ではない。
エピソードと歌の姿には乖離がある。
ゆくへも知らぬ恋の道かな(恋歌一)
「流れのきつい由良の海峡を渡る舟人が舵をなくして
ゆらゆらと流され揺れていくように、わたしの恋は
先の見えない中にただ揺れて漂っていく」という歌であろう。
「緒」は「紐」や「綱」の意味で、助詞の「を」ではない。
小学館本の脚注によると、「梶緒」とは「櫨(ろ)の綱」のことで
「 梶緒絶え」で「櫨(ろ)の綱切れ」の意味。
「由良」という地名の音が「揺れる」に通じて
いることは明らかだ。
曾禰好忠は新古今に16首、八代集抄に13首を採られている。
(俊成は千載集にこの歌人を採り上げていない)。
中古三十六歌仙の一人とある。
和泉式部や紫式部とほぼ同時代か、少し早い時代の人らしい。
印象を言えば、詩歌の古典世界を自分の感性を大事にして詠んで
いる歌が眼につく。
自分の感性を大事にした人と言えよう。
ただ、宮内卿や初期の伊勢のように、古典の歌世界を
自分の感性で染め上げる性格のものではない。
日常の生活感覚と地続きなところから歌は始まっても、
その感性がそのまま自立した歌となる和泉式部とも違う。
よく言えば古典と自身の感性を大事にした中庸とも言える
位置だが、悪く言えば、常識的でどっちつかずとも
中途半端とも言える。
「好忠集」を見ると、この人の歌はリズムが似通っていて、
読解力の無さを棚に上げて言えば、読んでいると眠くなる
ところがある。
そんな歌の中で新古今や八代集抄が選んでいるのは、この人の
感性が自分の眼で歌を詠もうとした歌だ。
好忠の自分の眼で見た実景を詠う詩心は、身の周りの自然に敏感で、
言葉の新鮮さや繊細さを感じさせる。
この人の歌は前半で感性に受け止めたものを詠んで、後半で
その受け止めたものの意味を古典詩歌の中で位置づける型の
ものが多い。
(619)草の上にここら玉ゐし白露を下葉の霜とむすぶ冬かな(冬歌)
「草の上にここら玉ゐし白露を」(草の上に白露が数多く置かれたの意)
という前半は 眼の前の自然に作者の感性が打たれ、その実景を詠む気持ちが
そのまま作者を表現の世界に導いている。後半の「下葉の霜とむすぶ冬かな」は、
作者の詩心が主導しているとはいえ、古典の教養で形を整え
詠んでいるように思われる。
(311)朝ぼらけ荻の上葉の露見ればややはださむし秋の初風(秋歌上)
この歌はその型のヴァリエイシヨンで、「ややはださむし」という実景を前に、
「朝ぼらけ萩の上葉の露見れば」、「秋の初風」と古典詩歌の世界を詠み
こんだものであろう。
好忠が古典の枠組みやトーンを尊重した歌作りをしているのは、辛らつに言えば、
歌を作り上げる詩の膨らみと構想力に乏しかったせいだとも言える。
良い歌はあっても力強さ、歌の大きさを感じさせる作は少ない。
五七五七七という詩形のもつリズムに依存し、その詩形を揺さぶる
自分のリズムがない。
その感性は静的で、感性が作者の内面を突き動かす面には弱いものが
ある。
そんな中では、次の歌は例外的と言っていい歌に思われる。
(186)花散ちりし庭の木の葉も茂りあひて天照る月の影ぞまれなる(夏歌)
感性が最後まで歌を主導し、「冬かな」とか「秋の初風」とか
教養的な知識で詠んでいない。
次の歌は霧で眼に見えない様子を詠むことで逆に実景を彷彿とさせる
ユニークな表現で、この歌人の技量を感じさせる。
(495)山里に霧のまがきのへだてずは遠方人(おちかたびと)の袖も見てまし(秋歌下)
「由良の門を渡る舟人舵緒絶えゆくへも知らぬ恋の道かな」は、
好忠の歌の中では抜きん出た作となっている。
好忠の実景を大事にした感性と古典詩歌の枠組みの中に自分の詩心を集約する
スタイルが詩形として見事に生きた例である。
その「由良の門を渡る舟人舵緒絶え」というイメージの
膨らみは新古今の中でも屈指のものであり、感性だけにも
教養だけにもよらない力強いものになっている。
「由良」の地名について諸説があるらしい。
「由良の門は、古くから紀淡海峡を指し、歌枕『由良の岬』として
しられていた、しかし好忠が丹後掾(たんごのじょう)をつとめて
いた関係で、契沖は丹後(京都)の由良河口とする解をとっている。
しかし歌の柄からみて、これは歌枕としての紀伊の由良を考えるのが
自然である。そうとってこそ、波の荒い海峡で、恋の舟の舵をなくして
漂うイメージが生きる。」(大岡信「百人一首」世界文化社)
地名がどこを指すかはともかく、「由良の門を渡る舟人舵緒絶え」
という五七五には、作者が実際に眼にした実景から受けた印象が
刻まれていることは確かであろう。
勅撰集は過去の勅撰集に採り上げられた歌は採らないという
方針があるようだが、この歌は新古今以前に採られていないのが
不思議なほどだ。
定家も百人一首にこの歌を採っている。
新古今の「恋歌」は、この歌の後に一首おいて、良経の次の歌を
続けている。
(1073)梶緒絶え由良の湊(みなと)に寄る舟のたよりも知らぬ沖つ潮風
良経の歌に比べられると、好忠の歌の姿が明らかになる。
好忠の歌を踏まえた本歌取りとはいえ、良経の歌の方が圧倒的な
存在感を持った大きな歌となっている。
現在から見れば、両者の歌が新古今に並んでいるのは残酷なほどだ。
歌人としての力量の違いがはっきりと現れている。
新古今の編集長である後鳥羽は、むろん、好忠の持つ
形の整った味わいを大事にしたのだろう。
百人一首の解説を読むと、必ずと言っていいほど、
この好忠が円融院の子の日の御幸に呼ばれもせずに
姿を現し追いやられたというエピソードが載っている。
他にも奇行が多かったというが、新古今を通して歌を
読む限りは決して強い個性の歌人ではない。
エピソードと歌の姿には乖離がある。
|
|
|
|
|
|
|
|
新古今和歌集私撰:百人の歌人 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
新古今和歌集私撰:百人の歌人のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人