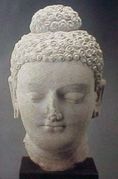簡単に求道と修行について書きたいと思います。参考にして自身の求道を進めてください。
1.判断基準 もっと幸せになるため
2.優先順位 根本を叩く
3.具体的には 宗教最優先
4.宗教研究 自己修養と一神教と多神教
5.総合と包括と整合 世界観と目的と方法と検証
6.まとめ 求道と修行
おまけ.
気をつけるといいこと
求道に向いている人
1.判断基準
その教えを学べば学ぶほど不幸になる → 悪い教え
その教えを学べば学ぶほど幸せになる → 善い教え
2.優先順位
最も有名な教えの教祖を先に学ぶ ← 根本を叩く
分野を横断して広く学ぶ ← 総合性と包括性と整合性を目指す
3.具体的には
宗教 → 死後の世界と超能力・霊能力があるので最優先。
哲学 → 死後の世界と超能力・霊能力がないので後回し。
科学 → 原理・原則は最低限学んでおくと便利。
運動 → 肉体制御を通じて精神制御を学べる。健康にもよい。
精神世界 → リアルタイムなのでちょこちょこ仕入れる。
帝王学 → 現世で有用なのでちょこちょこ学ぶ。
(歴史・英雄論・人物伝・処世術・ハウツー・自己啓発)
4.宗教研究
自力 自己修養の宗教 修行・苦行がメイン
他力 一神教・多神教の宗教 祭祀・祈りがメイン
自己修養の宗教 仏教・儒教・道教ほか
一神教の宗教 ゾロアスター・ユダヤ・キリスト・イスラム・バハイ
多神教の宗教 神道・ヒンドゥー教・神話・民俗信仰他
[自己修養]
仏教 → 原始仏典を読む 論蔵や大乗仏典などは後回し
儒教 → 論語を読む 孟子などは後回し
道教 → 老子を読む 荘子・抱朴子などは後回し
[一神教]
ゾロアスター教 → アヴェスターを読む しかし読みづらい
ユダヤ教 → 旧約聖書を読む タルムードなどは後回し
キリスト教 → 新約聖書を読む 神学などは後回し
イスラム教 → コーランを読む ハディースなどは後回し
バハイ教 → ケタベ・アグダス他を読む バハオラ以後は後回し
[多神教]
神道 → 古事記を読む 日本書紀は長いので後回し
バラモン教 → リグ・ヴェーダを読む 他のヴェーダは後回し
ヒンドゥー教 → マヌ法典とバガヴァッド・ギーターを読む 他は後回し
ギリシャ神話 → ホメロス・ヘシオドスを読む
北欧神話 → エッダを読む
余力があれば科学・精神世界を学ぶ。
善悪を判断する知恵を得ることを先とし、
現実を変える力(超能力など)を得ることを後とする。
誤って悪を行なうことを避けるため。
多くの人が話力・腕力・魅力・知力・財力・権力・武力・超能力・霊能力を
誤って使って罪を犯すのを見る。
5.総合と包括と整合
1 総合的で包括的で整合性ある世界観を自ら構築する
2 道理ある理想・目的を自ら見いだす
3 その理想・目的に到る方法論・修行方法を自ら見いだす
4 自ら実践して検証する
結果 その教えを学べば学ぶほど不幸になる → 悪い教え・悪い見解
その教えを学べば学ぶほど幸せになる → 善い教え・善い見解
「現実をもって最高の試金石となす」
6.まとめ
求道とは善を知ること
修行とは善を得ること
善を知って、善への道を知る
善への道を知って、善への道を修行する
善への道を修行して、善を得る
善を得て悪しきことなし
こうして求道と修行が報われます
[気をつけるといいこと]
ファッション → 求道者は変人になりやすい。変人になれば世間を敵視しやすい。
世間を敵視すれば悪の道に入りやすく結果的に自分に悪い。
清潔なファッションと適度に流行を取り入れることで
人に好感を抱かせれば世間を敵視せず善の道に入りやすい。
在家出家を問わずファッションは社会的な位置を表示する。
気前よくする → 家族と友人に気前よくおごりプレゼントを送れば愛される。
愛されれば世間を敵視せず善の道に入りやすい。
いい趣味 → 大多数の人が自分の好みで信じる教えを決めているのを見る。
悪い趣味は黒魔術や悪魔崇拝や性的なものに愛着する。
趣味をよくすればただ幸福を結果する教えに惹かれるのみ。
心を知る → 人は人に愛され認められたいと解脱しないかぎりは思うもの。
知恵を語っても人の心が見えなければ愛されず認められない。
人の心が見えれば相手が受け入れれる知恵の容量も見極めれる。
人の心が見えれば相手が欲するものも見極めれる。
相手の欲しいものが見えれば愛され認められる道も見えてくる。
読書と思索に耽ることと人の心を知ることはまた別々のこと。
雑念のほとんどが愛され認められたいという欲求から生じるが、
その雑念内容が愛と承認への道に寄与しているか検討する人は少ない。
[求道に向いている人]
「わからない苦しみをよく知っている人」
「無知の苦しみをよく知っている人」
「どうすればいいかわからない苦しみをよく知っている人」
「どう生きればいいのかわからない苦しみをよく知っている人」
こういう無明を原因とする苦しみをよく知っている人がその苦痛から脱出するために知恵を求め、明を求めます。その苦しみが求道のモチベーションになります。逆に無明の苦しみを味わい尽くしていない人は、求道のモチベーションが補充されにくいです。真の求道精神が内にあるかぎり必ず答えに近づきます。
一切の教えが滅んでもこの現実から答えを引き出せるからです。言い換えれば、覚った人がいない時代というのは誰も覚りたくないので覚った人がいないのであり、それはそれでよいということです。世界はそれぞれの欲望に対して道理にかなった結果を与えるようになっているからです。
求道も修行もまた欲する人がやればよいもので義務ではありません。人は自分をもっと幸せにしなければいけないわけでもなく、自分を不幸にしてはいけないわけでもありません。ただ長時間の連続的な苦受はそこからの脱出を求めさせる意欲を結果することが多いというだけのことです。
「これもまた因果連鎖に過ぎない」ということです。
[修行の成果]
一、善人になること (美徳・戒・無害・利他・四摂事など)
二、超人法を得ること(四禅・六神通・漏尽・不死も含む)
これが得れたら修行も報われると思います。
書籍に埋もれて暮らす読書家。これは利益があっても大利ではありません。
自らペンを取る著作家・研究者。これも利益がありますが大利ではありません。
書籍とペンを捨てて何もないところでひたすら瞑想する者。ここに大利があります。
求めるべきは博覧強記の多聞者となることではなく、美徳と莫大な力を有する大賢人にして偉大なる者となることです。
1.判断基準 もっと幸せになるため
2.優先順位 根本を叩く
3.具体的には 宗教最優先
4.宗教研究 自己修養と一神教と多神教
5.総合と包括と整合 世界観と目的と方法と検証
6.まとめ 求道と修行
おまけ.
気をつけるといいこと
求道に向いている人
1.判断基準
その教えを学べば学ぶほど不幸になる → 悪い教え
その教えを学べば学ぶほど幸せになる → 善い教え
2.優先順位
最も有名な教えの教祖を先に学ぶ ← 根本を叩く
分野を横断して広く学ぶ ← 総合性と包括性と整合性を目指す
3.具体的には
宗教 → 死後の世界と超能力・霊能力があるので最優先。
哲学 → 死後の世界と超能力・霊能力がないので後回し。
科学 → 原理・原則は最低限学んでおくと便利。
運動 → 肉体制御を通じて精神制御を学べる。健康にもよい。
精神世界 → リアルタイムなのでちょこちょこ仕入れる。
帝王学 → 現世で有用なのでちょこちょこ学ぶ。
(歴史・英雄論・人物伝・処世術・ハウツー・自己啓発)
4.宗教研究
自力 自己修養の宗教 修行・苦行がメイン
他力 一神教・多神教の宗教 祭祀・祈りがメイン
自己修養の宗教 仏教・儒教・道教ほか
一神教の宗教 ゾロアスター・ユダヤ・キリスト・イスラム・バハイ
多神教の宗教 神道・ヒンドゥー教・神話・民俗信仰他
[自己修養]
仏教 → 原始仏典を読む 論蔵や大乗仏典などは後回し
儒教 → 論語を読む 孟子などは後回し
道教 → 老子を読む 荘子・抱朴子などは後回し
[一神教]
ゾロアスター教 → アヴェスターを読む しかし読みづらい
ユダヤ教 → 旧約聖書を読む タルムードなどは後回し
キリスト教 → 新約聖書を読む 神学などは後回し
イスラム教 → コーランを読む ハディースなどは後回し
バハイ教 → ケタベ・アグダス他を読む バハオラ以後は後回し
[多神教]
神道 → 古事記を読む 日本書紀は長いので後回し
バラモン教 → リグ・ヴェーダを読む 他のヴェーダは後回し
ヒンドゥー教 → マヌ法典とバガヴァッド・ギーターを読む 他は後回し
ギリシャ神話 → ホメロス・ヘシオドスを読む
北欧神話 → エッダを読む
余力があれば科学・精神世界を学ぶ。
善悪を判断する知恵を得ることを先とし、
現実を変える力(超能力など)を得ることを後とする。
誤って悪を行なうことを避けるため。
多くの人が話力・腕力・魅力・知力・財力・権力・武力・超能力・霊能力を
誤って使って罪を犯すのを見る。
5.総合と包括と整合
1 総合的で包括的で整合性ある世界観を自ら構築する
2 道理ある理想・目的を自ら見いだす
3 その理想・目的に到る方法論・修行方法を自ら見いだす
4 自ら実践して検証する
結果 その教えを学べば学ぶほど不幸になる → 悪い教え・悪い見解
その教えを学べば学ぶほど幸せになる → 善い教え・善い見解
「現実をもって最高の試金石となす」
6.まとめ
求道とは善を知ること
修行とは善を得ること
善を知って、善への道を知る
善への道を知って、善への道を修行する
善への道を修行して、善を得る
善を得て悪しきことなし
こうして求道と修行が報われます
[気をつけるといいこと]
ファッション → 求道者は変人になりやすい。変人になれば世間を敵視しやすい。
世間を敵視すれば悪の道に入りやすく結果的に自分に悪い。
清潔なファッションと適度に流行を取り入れることで
人に好感を抱かせれば世間を敵視せず善の道に入りやすい。
在家出家を問わずファッションは社会的な位置を表示する。
気前よくする → 家族と友人に気前よくおごりプレゼントを送れば愛される。
愛されれば世間を敵視せず善の道に入りやすい。
いい趣味 → 大多数の人が自分の好みで信じる教えを決めているのを見る。
悪い趣味は黒魔術や悪魔崇拝や性的なものに愛着する。
趣味をよくすればただ幸福を結果する教えに惹かれるのみ。
心を知る → 人は人に愛され認められたいと解脱しないかぎりは思うもの。
知恵を語っても人の心が見えなければ愛されず認められない。
人の心が見えれば相手が受け入れれる知恵の容量も見極めれる。
人の心が見えれば相手が欲するものも見極めれる。
相手の欲しいものが見えれば愛され認められる道も見えてくる。
読書と思索に耽ることと人の心を知ることはまた別々のこと。
雑念のほとんどが愛され認められたいという欲求から生じるが、
その雑念内容が愛と承認への道に寄与しているか検討する人は少ない。
[求道に向いている人]
「わからない苦しみをよく知っている人」
「無知の苦しみをよく知っている人」
「どうすればいいかわからない苦しみをよく知っている人」
「どう生きればいいのかわからない苦しみをよく知っている人」
こういう無明を原因とする苦しみをよく知っている人がその苦痛から脱出するために知恵を求め、明を求めます。その苦しみが求道のモチベーションになります。逆に無明の苦しみを味わい尽くしていない人は、求道のモチベーションが補充されにくいです。真の求道精神が内にあるかぎり必ず答えに近づきます。
一切の教えが滅んでもこの現実から答えを引き出せるからです。言い換えれば、覚った人がいない時代というのは誰も覚りたくないので覚った人がいないのであり、それはそれでよいということです。世界はそれぞれの欲望に対して道理にかなった結果を与えるようになっているからです。
求道も修行もまた欲する人がやればよいもので義務ではありません。人は自分をもっと幸せにしなければいけないわけでもなく、自分を不幸にしてはいけないわけでもありません。ただ長時間の連続的な苦受はそこからの脱出を求めさせる意欲を結果することが多いというだけのことです。
「これもまた因果連鎖に過ぎない」ということです。
[修行の成果]
一、善人になること (美徳・戒・無害・利他・四摂事など)
二、超人法を得ること(四禅・六神通・漏尽・不死も含む)
これが得れたら修行も報われると思います。
書籍に埋もれて暮らす読書家。これは利益があっても大利ではありません。
自らペンを取る著作家・研究者。これも利益がありますが大利ではありません。
書籍とペンを捨てて何もないところでひたすら瞑想する者。ここに大利があります。
求めるべきは博覧強記の多聞者となることではなく、美徳と莫大な力を有する大賢人にして偉大なる者となることです。
|
|
|
|
コメント(29)
「もし原始仏教が間違っているとしたら」と仮定して、もう一度自分の生き方をゼロからここまで組み立て直せれなければ、まだその信は慧力によって十分に裏付けが取れていない可能性があります。
人は個々人で「証明根拠」とも言うべき判断基準が異なります。普通、現実に実際に検証されたものを普通の人は受け入れるものですが、人によって現実が持つ証明根拠としての有用性をまったく考慮せず、あくまでも現実・事実・真実を否定し続ける人もいます。それは各人によって見解を受け入れる判断記述が異なるからです。僕はそれを単純に「証明根拠」と名付けています。
人によっては自分の目で見たことしか信じない人もいれば、世間一般の通念しか受け入れない人もいます。自分の考える世間が実際の世間とどこまで対応しているのか検証しない人が圧倒的に多いです。自分の考え方を再検討せざるを得なくなるような強烈な刺激が、楽にしろ苦にしろ足りていない、あるいは自分の考え方を再検討せざるを得なくなるような物事を見たり聞いたりしていないということによる原因不足だと思います。単純に存在者としての力が弱いというのが基本にあるとも思います。
多くの人の考え方は自分が育った家庭環境と自分がよく触れる趣味の領域とテレビの情報で世間に関するイメージが構築されています。そしてその自分の全経験の大半が過去に為した業の報いによって強く影響を与えられているという現実は誰にとっても悪夢の続きです。そしてその苦しみの経験が再び自分の見解の再固着に拍車をかけます。こうして人は自分の色をますます強めて行き、自ら望まざる個性、つまりは人に嫌われてしまうような性格の欠点をその身にまとうことになります。
これは悪業と悪業の報いの回転における邪見の再発生に関してです。一方で善業と善業の報いの回転においては正見を生じさせることが多いです。またそのときに自分は自分にとって邪見が割り込まない限りは好ましいもの、美徳を備えた自分として見えるはずです。しかしその見え方も常に現状の見解に左右されるものですが。恐るべきは邪見が持つ全ての美徳の破壊力です。
いずれにしろそれら全ての見解には原因があったのであり、原因がなかったのではないということ、またその見解の訂正と更新にも原因が必要なのであり、原因なく人の考え方や生き方が変わることはあり得ません。
この因果律を前提とする見解は汎用性があり、様々なところで検証できるので、普通は原因と結果という発想を手に入れた人は繰り返し「原因があるから結果がある。原因がなければ結果はない」ということを確認し続けます。それが習慣になるともはやこのような生滅の見解に関しては疑いません。あるいは再検討を強いられる状況が現出しても、検証方法について熟知していれば迷いません。これが如実知見に即した正見・正思・正知を中心とする十正法の再形成性だと僕は思っています。これに基づいて諸々の邪見から始まる十邪からの正解脱があるという考えは道理にかなっています。
あとは五蘊としての存在様式が本当にあるのかを確認し、五蘊以外の存在様式は他にないのかを確認し、その全ての存在様式における因果連鎖、生滅を考察していけば、その存在者はその知恵の蓄積により聖なる存在者になるということもまた道理にかなっています。知、如実知、現実の通りに知るということを原因として何が結果されるかというところに鍵があると思います。
人は六触処における接触内容であるいわゆる経験、自分の人生における全ての経験より他には飛び越えて行くことができません。全ては自分の六触処における出来事でしかありません。これは世界に自分しか存在しないということではなくて、その全経験から類推するまでもない整合性ある直観として、外界が存在するものだということを普通に信じているものです。しかし、その直観がいまだ微細で真実を穿ったものではないからこそ、五感を一時的に絶無にしたときに外界は滅するという発想である四無色の瞑想状態とそのような状態に住する神々を一般の人は発見できなかったと言えます。さらに、六触処への全執着を意識上からも無意識からも自分の全存在から撃滅させることによって、ここに一切の世間、全世界は消滅するという涅槃の発想にも至らなかったと言えます。しかも如来や阿羅漢は六触処を滅してなお、端から見ればいつも通り飲み食いしているように見えます。そして普通に老いて病んで死んだように見えます。
人は個々人で「証明根拠」とも言うべき判断基準が異なります。普通、現実に実際に検証されたものを普通の人は受け入れるものですが、人によって現実が持つ証明根拠としての有用性をまったく考慮せず、あくまでも現実・事実・真実を否定し続ける人もいます。それは各人によって見解を受け入れる判断記述が異なるからです。僕はそれを単純に「証明根拠」と名付けています。
人によっては自分の目で見たことしか信じない人もいれば、世間一般の通念しか受け入れない人もいます。自分の考える世間が実際の世間とどこまで対応しているのか検証しない人が圧倒的に多いです。自分の考え方を再検討せざるを得なくなるような強烈な刺激が、楽にしろ苦にしろ足りていない、あるいは自分の考え方を再検討せざるを得なくなるような物事を見たり聞いたりしていないということによる原因不足だと思います。単純に存在者としての力が弱いというのが基本にあるとも思います。
多くの人の考え方は自分が育った家庭環境と自分がよく触れる趣味の領域とテレビの情報で世間に関するイメージが構築されています。そしてその自分の全経験の大半が過去に為した業の報いによって強く影響を与えられているという現実は誰にとっても悪夢の続きです。そしてその苦しみの経験が再び自分の見解の再固着に拍車をかけます。こうして人は自分の色をますます強めて行き、自ら望まざる個性、つまりは人に嫌われてしまうような性格の欠点をその身にまとうことになります。
これは悪業と悪業の報いの回転における邪見の再発生に関してです。一方で善業と善業の報いの回転においては正見を生じさせることが多いです。またそのときに自分は自分にとって邪見が割り込まない限りは好ましいもの、美徳を備えた自分として見えるはずです。しかしその見え方も常に現状の見解に左右されるものですが。恐るべきは邪見が持つ全ての美徳の破壊力です。
いずれにしろそれら全ての見解には原因があったのであり、原因がなかったのではないということ、またその見解の訂正と更新にも原因が必要なのであり、原因なく人の考え方や生き方が変わることはあり得ません。
この因果律を前提とする見解は汎用性があり、様々なところで検証できるので、普通は原因と結果という発想を手に入れた人は繰り返し「原因があるから結果がある。原因がなければ結果はない」ということを確認し続けます。それが習慣になるともはやこのような生滅の見解に関しては疑いません。あるいは再検討を強いられる状況が現出しても、検証方法について熟知していれば迷いません。これが如実知見に即した正見・正思・正知を中心とする十正法の再形成性だと僕は思っています。これに基づいて諸々の邪見から始まる十邪からの正解脱があるという考えは道理にかなっています。
あとは五蘊としての存在様式が本当にあるのかを確認し、五蘊以外の存在様式は他にないのかを確認し、その全ての存在様式における因果連鎖、生滅を考察していけば、その存在者はその知恵の蓄積により聖なる存在者になるということもまた道理にかなっています。知、如実知、現実の通りに知るということを原因として何が結果されるかというところに鍵があると思います。
人は六触処における接触内容であるいわゆる経験、自分の人生における全ての経験より他には飛び越えて行くことができません。全ては自分の六触処における出来事でしかありません。これは世界に自分しか存在しないということではなくて、その全経験から類推するまでもない整合性ある直観として、外界が存在するものだということを普通に信じているものです。しかし、その直観がいまだ微細で真実を穿ったものではないからこそ、五感を一時的に絶無にしたときに外界は滅するという発想である四無色の瞑想状態とそのような状態に住する神々を一般の人は発見できなかったと言えます。さらに、六触処への全執着を意識上からも無意識からも自分の全存在から撃滅させることによって、ここに一切の世間、全世界は消滅するという涅槃の発想にも至らなかったと言えます。しかも如来や阿羅漢は六触処を滅してなお、端から見ればいつも通り飲み食いしているように見えます。そして普通に老いて病んで死んだように見えます。
人は努力しない限りは現実の通りに知ることはできません。人は努力しない限りは自分の見解と慧力に即した解釈しか得られません。錯覚も錯覚としては事実であり、盲点も盲点としては事実ですが、それとはまた別に外界の有り様もあります。相互に異なっているものを双方とも同じであると判断することを「粗野」と言ってもよいかも知れません。微細な物事のわずかな相違にも気がつける人は、鋭い注意力と洞察力を持った念力と定力と慧力の強い人に限られます。これは誰にとっても程度問題ですが。
これらの発想がもしも真実であるならば、六触処における全経験において最高の整合性を追い求めていく過程で必ず辿り着ける領域であるのでなければならないとも言えると思います。感受、そして苦と苦滅という発想周辺の因果連鎖において整合性を求めて行く過程では必ずいずれ内界と外界とこの双方における執着、それに対応した接触内容とそれに伴う感受について検討せざるを得なくなるでしょうから。
簡単に言えば「あり得るのか、あり得ないのか」というその可能性を見極める意味での見清浄をはじめとする他の清浄です。
結局人は、宗教をやろうとやるまいと、普通の一般常識の枠内で生きていくとしても必ず、何らかの生き方と見解と世界観と人生観を持ち、ただその枠内でのみ生きて行きます。後は、自分の考え方を真っ向から否定する現実と遭遇し、自分の見解に反する六触処における接触内容が飛び込んで来たときにどれだけ柔軟に対応できるか、検証できるか、摺り合わせれるか、反省を繰り返して行けるかにかかっています。
しかし、それもまたそういった繰り返し自分の考え方を反省し更新することが大事なのだというこの見解、この考え方がなければそういった作業も結果としては生じにくいというのがこの現実の因果連鎖の有り様です。
だからこそ、事前に因果の流れを把握して、利益と不利益に導く流れを現実に沿って認識することを繰り返すことによって、この現実自体から自分に対して最高の可能性を引き出す考え方を手に入れることが重要であるということが見えて来ます。「最高の可能性を自分に付与する」という発想はさらなる高みに自分を持ち上げるための原因構築にとって重要な位置を占めるのだと僕は思っています。「最高の可能性を自分に付与する」という発想を原因としては、心は内界と外界で起きる全ての物事に対して心を開き、真実を求めようとする意向が強く生じるからです。そのときは意識に飛び込む六触処の内容に関してはよく見ますし、よく見えるまでは見ることをやめません。
時に応じて原始仏教を含めて自分の今の生き方の全てを疑うのも、反省と再検討と検証のために大変有意義なことだと思います。もしも今の自分のやり方が間違っていれば破滅に行きますから。
これらの発想がもしも真実であるならば、六触処における全経験において最高の整合性を追い求めていく過程で必ず辿り着ける領域であるのでなければならないとも言えると思います。感受、そして苦と苦滅という発想周辺の因果連鎖において整合性を求めて行く過程では必ずいずれ内界と外界とこの双方における執着、それに対応した接触内容とそれに伴う感受について検討せざるを得なくなるでしょうから。
簡単に言えば「あり得るのか、あり得ないのか」というその可能性を見極める意味での見清浄をはじめとする他の清浄です。
結局人は、宗教をやろうとやるまいと、普通の一般常識の枠内で生きていくとしても必ず、何らかの生き方と見解と世界観と人生観を持ち、ただその枠内でのみ生きて行きます。後は、自分の考え方を真っ向から否定する現実と遭遇し、自分の見解に反する六触処における接触内容が飛び込んで来たときにどれだけ柔軟に対応できるか、検証できるか、摺り合わせれるか、反省を繰り返して行けるかにかかっています。
しかし、それもまたそういった繰り返し自分の考え方を反省し更新することが大事なのだというこの見解、この考え方がなければそういった作業も結果としては生じにくいというのがこの現実の因果連鎖の有り様です。
だからこそ、事前に因果の流れを把握して、利益と不利益に導く流れを現実に沿って認識することを繰り返すことによって、この現実自体から自分に対して最高の可能性を引き出す考え方を手に入れることが重要であるということが見えて来ます。「最高の可能性を自分に付与する」という発想はさらなる高みに自分を持ち上げるための原因構築にとって重要な位置を占めるのだと僕は思っています。「最高の可能性を自分に付与する」という発想を原因としては、心は内界と外界で起きる全ての物事に対して心を開き、真実を求めようとする意向が強く生じるからです。そのときは意識に飛び込む六触処の内容に関してはよく見ますし、よく見えるまでは見ることをやめません。
時に応じて原始仏教を含めて自分の今の生き方の全てを疑うのも、反省と再検討と検証のために大変有意義なことだと思います。もしも今の自分のやり方が間違っていれば破滅に行きますから。
もし求道者を自認する人に「今の自分の生き方・在り方を根本的に変革することになるとしてもそれさえ厭わないような強烈な真実への強い思い」があれば、求道者として立派であると思います。
一般の人の多くの方向性としては、頭に思い浮かんだアイデアを良しとして、そのアイデアを突き進めていく方向を取ることが多いと思います。たとえば、日々のことであれば「今日はあれを食べよう」と思えばそれを食べようとしますし、見るのも聞くのも着るのも出かけるのも買うのも趣味を嗜むのも基本的に自分の考えと欲求が生じればそれに従います。五欲の享受において常識の範囲で満たす分には突然、事態が悪化することはなかなかないのでそれはそれでよいのですが、怒りや不満や苛立ちにおいてはその考えや感情が生じた段階で、そのまま突き進めると他者を傷付ける身行や語行を行なって関係が悪化して修復が困難になることがよくあります。これは欲尋や瞋尋が生じてそのままにしたときの結果としては必然的なことです。
日々のことよりもさらに重要なことは「中長期のアイデア」に関してです。人生の進路や身の振り方について考えることは今日何をするかよりもより一層重要なことです。むしろ、長期的な目標が中期目標を設定し、中期において満たすべき条件から今日何を為すべきかが明確になります。それは目標と目標達成に必要な因果連鎖を事前に予測して、実際に現実において原因を蓄積し構築して現実化していくという作業です。
多くの人は、日々の考えでも生じた考えのまま突き進みますし、将来設計や中長期の発想であっても生じた考えのままに突き進みます。普通に進学して結婚して子育てはこうでというふうです。世間一般が与えるところの人生のヴィジョンをそのまま信じて受け入れ、本人も気付かないうちにそれを人生の目標としてすでに設定していることが多々あります。「こういうものだ。そういうものだ」というふうに。しかし、それはその人が見聞きし経験し思った果てに諸行の蓄積として固められた人生航路です。その航海術もまたその経験の中で自分で発見したにしろ教えられたにしろ編み出してきたもので実際にそのやり方で利益を生じておりそれを確認しているからこそ、今もそういうやり方を続けているわけです。
しかし自分が日々世渡りしていく上で用いている武器や技術についても「自分はこういうやり方を採用している」と自覚的に自分の長所や短所を理解している人はほとんどいません。多くの人にとって人生とはただ「そういうもの」として過ぎていきます。そして、一般の人は世界に対してあまりにも無力なので、世間や社会や国家や時代という大勢の動向の前では、ほとんど考え方も言動も大きく規制されてしまい、本人も気付かないうちに萎縮しています。
そういった一般常識の枠組みに強く干渉されている人に、その枠組みを越える感情や欲求が生じると抑圧や放置や屈折という形で漏れ続けるままになってしまい、それが集積すると後顧の憂いとなる可能性があります。これらの自身の見解や生き方、世間一般の通念が自分にどれだけ影響を与えているかというその無知分が常に制御不能領域として、征服されざる大地のごとく取り残されることになります。知らないもの、認識されないものを制御することはできないからです。これらは全て内の法念処の修習によって次第に明らかになってきます。自己の法に関して念じることによって「自分には何があるか。自分は何をしているのか」ということをより一層努力なしで自然に自覚するようになっていきます。
一般の人の多くの方向性としては、頭に思い浮かんだアイデアを良しとして、そのアイデアを突き進めていく方向を取ることが多いと思います。たとえば、日々のことであれば「今日はあれを食べよう」と思えばそれを食べようとしますし、見るのも聞くのも着るのも出かけるのも買うのも趣味を嗜むのも基本的に自分の考えと欲求が生じればそれに従います。五欲の享受において常識の範囲で満たす分には突然、事態が悪化することはなかなかないのでそれはそれでよいのですが、怒りや不満や苛立ちにおいてはその考えや感情が生じた段階で、そのまま突き進めると他者を傷付ける身行や語行を行なって関係が悪化して修復が困難になることがよくあります。これは欲尋や瞋尋が生じてそのままにしたときの結果としては必然的なことです。
日々のことよりもさらに重要なことは「中長期のアイデア」に関してです。人生の進路や身の振り方について考えることは今日何をするかよりもより一層重要なことです。むしろ、長期的な目標が中期目標を設定し、中期において満たすべき条件から今日何を為すべきかが明確になります。それは目標と目標達成に必要な因果連鎖を事前に予測して、実際に現実において原因を蓄積し構築して現実化していくという作業です。
多くの人は、日々の考えでも生じた考えのまま突き進みますし、将来設計や中長期の発想であっても生じた考えのままに突き進みます。普通に進学して結婚して子育てはこうでというふうです。世間一般が与えるところの人生のヴィジョンをそのまま信じて受け入れ、本人も気付かないうちにそれを人生の目標としてすでに設定していることが多々あります。「こういうものだ。そういうものだ」というふうに。しかし、それはその人が見聞きし経験し思った果てに諸行の蓄積として固められた人生航路です。その航海術もまたその経験の中で自分で発見したにしろ教えられたにしろ編み出してきたもので実際にそのやり方で利益を生じておりそれを確認しているからこそ、今もそういうやり方を続けているわけです。
しかし自分が日々世渡りしていく上で用いている武器や技術についても「自分はこういうやり方を採用している」と自覚的に自分の長所や短所を理解している人はほとんどいません。多くの人にとって人生とはただ「そういうもの」として過ぎていきます。そして、一般の人は世界に対してあまりにも無力なので、世間や社会や国家や時代という大勢の動向の前では、ほとんど考え方も言動も大きく規制されてしまい、本人も気付かないうちに萎縮しています。
そういった一般常識の枠組みに強く干渉されている人に、その枠組みを越える感情や欲求が生じると抑圧や放置や屈折という形で漏れ続けるままになってしまい、それが集積すると後顧の憂いとなる可能性があります。これらの自身の見解や生き方、世間一般の通念が自分にどれだけ影響を与えているかというその無知分が常に制御不能領域として、征服されざる大地のごとく取り残されることになります。知らないもの、認識されないものを制御することはできないからです。これらは全て内の法念処の修習によって次第に明らかになってきます。自己の法に関して念じることによって「自分には何があるか。自分は何をしているのか」ということをより一層努力なしで自然に自覚するようになっていきます。
善法は自覚していようと無自覚であろうと、為せば善なる結果が生じます。悪法も自覚無自覚を問わず、為せば悪を結果します。というよりも結果的に悪となったと推測される原因をもって後に悪と規定し、善も同様に結果が生じてから原因と思われることを善として規定するので善悪は事後的に明らかになっていくものというふうに、認識し規定し分類する側からは言えるかも知れません。
しかし自覚それ自体は常に善であり悪ではないということが自覚の性質を幾分観察した人間にとってはある程度言えることです。原始仏典においても四念処は純粋善の集まりと書いてあります。実際、無自覚の時は状況の確認ができずに何が起きているかも理解できず、現実を自分の意志で制御することがまったくできません。気絶状態では人間は外界の影響をダイレクトに受けます。しかし自覚が生じるときは状況が確認でき、何が起きており何が問題なのかを把握し、たとえ身体が拘束されているとしても五感に入る情報をしっかりと自覚し、その五感の情報を自分がどう見てどう受け取っているかをも自覚するがゆえに、自己の心の自覚量の分だけはそこにおいて自在性を獲得できます。肉体を監禁して拘束しても意志し自覚し思考する心は決して拘束できません。
さらにそのような拘束が身体ではなく心への干渉である洗脳であっても、その洗脳内容を自覚することによって洗脳という足かせをも自覚によって外すことが可能です。このような自覚することによって生じる知と自在性、その自覚に伴う念の力をもって生ける者は現実に内界と外界双方に影響力を行使することができます。念力によって克己も外界の制御もその両方が達成されます。自覚とはあらゆる生ける者にとってさらなる力に導く一つの完結した力強い因果連鎖です。
一般の人が世間一般の通念に無自覚なのは、彼らが自覚を修習していないので念力と自覚力が弱いということがその理由であり、他の多くの場合においても無自覚状態で過ごしているのもそれが理由です。世間一般の通念と自分がこれでいいだろうと思って毎日繰り返している方法論は、全て一つひとつのことであり、そこには必ず何らかのヴィジョンを伴っていますが、多くの人はそれが何であるかをほとんど自覚していません。またその採用内容の有用性や現実対応性などを検討する新たなヴィジョンを自ら作り出すことができません。
では何を原因として世間一般の通念への疑問や自覚が生じるかと言えば、それはその世間一般の通念を信じて生きてきたのに人生がうまくいかなくなるという壁にぶつかったときや、賢い人の場合はそういう人の失敗を見たときにそこから学びます。自己や他者の失敗が自覚と反省を促し、今までの自分の信が正しい信ではなく間違った信であったかも知れないと疑い始めるきっかけとなります。そしてそのようなきっかけは多くの場合において苦痛を伴い、その苦痛から逃れるために脱出法の検討として始まるものです。
しかし自覚それ自体は常に善であり悪ではないということが自覚の性質を幾分観察した人間にとってはある程度言えることです。原始仏典においても四念処は純粋善の集まりと書いてあります。実際、無自覚の時は状況の確認ができずに何が起きているかも理解できず、現実を自分の意志で制御することがまったくできません。気絶状態では人間は外界の影響をダイレクトに受けます。しかし自覚が生じるときは状況が確認でき、何が起きており何が問題なのかを把握し、たとえ身体が拘束されているとしても五感に入る情報をしっかりと自覚し、その五感の情報を自分がどう見てどう受け取っているかをも自覚するがゆえに、自己の心の自覚量の分だけはそこにおいて自在性を獲得できます。肉体を監禁して拘束しても意志し自覚し思考する心は決して拘束できません。
さらにそのような拘束が身体ではなく心への干渉である洗脳であっても、その洗脳内容を自覚することによって洗脳という足かせをも自覚によって外すことが可能です。このような自覚することによって生じる知と自在性、その自覚に伴う念の力をもって生ける者は現実に内界と外界双方に影響力を行使することができます。念力によって克己も外界の制御もその両方が達成されます。自覚とはあらゆる生ける者にとってさらなる力に導く一つの完結した力強い因果連鎖です。
一般の人が世間一般の通念に無自覚なのは、彼らが自覚を修習していないので念力と自覚力が弱いということがその理由であり、他の多くの場合においても無自覚状態で過ごしているのもそれが理由です。世間一般の通念と自分がこれでいいだろうと思って毎日繰り返している方法論は、全て一つひとつのことであり、そこには必ず何らかのヴィジョンを伴っていますが、多くの人はそれが何であるかをほとんど自覚していません。またその採用内容の有用性や現実対応性などを検討する新たなヴィジョンを自ら作り出すことができません。
では何を原因として世間一般の通念への疑問や自覚が生じるかと言えば、それはその世間一般の通念を信じて生きてきたのに人生がうまくいかなくなるという壁にぶつかったときや、賢い人の場合はそういう人の失敗を見たときにそこから学びます。自己や他者の失敗が自覚と反省を促し、今までの自分の信が正しい信ではなく間違った信であったかも知れないと疑い始めるきっかけとなります。そしてそのようなきっかけは多くの場合において苦痛を伴い、その苦痛から逃れるために脱出法の検討として始まるものです。
疑いは五蓋の一つで銀に譬えられていますが、この迷いや疑問の状態は頭の周りをぐるぐると旋回し、本人にさらなる新しい苦痛をもたらします。疑う理由となった不快なことも苦痛ですが、どうすればその苦しみから脱出できるのかわからないということも新たなる苦痛です。しかし、うまくすると「わからない」という苦しみを長時間体験した人は「知ることの利益と楽」に気付き、それが繰り返し蓄積されるとその本人の性格の一環として強く形成される場合があります。求道者の卵はこのように疑蓋のうちにあります。
疑蓋自体は純粋悪ですが、その疑蓋によって生じる苦と不利益を長く受け続けた者はその疑いという特定悪からの脱出を他の悪法からの脱出と比べてより強く望む傾向を生じさせます。それは四念処や三善根というすでにあった善法の増大として生じて来ます。内において繰り広げられる善法と悪法の相克です。わからないという苦しみをよく知る者こそが知る利益をよく知るということです。
疑いが生じるためには何らかの強烈な失敗と苦痛が必要な場合が多いです。しかも「この方法でうまくいくと信じたのに駄目だった」という「善を意図していたのに悪を結果してしまった信念」。これがあってはじめて知恵に転じる根本的な土壌になります。そしてここに疑いという雑草の種を蒔けば、疑蓋はゴミ袋のようにその人の頭部をすっぽり包み、答えが出されるまで「わからない苦しみ」の中でのたうち廻ります。そんなわからない苦しみも、正知にもとづく正見という良き種の肥やしになります。疑いという雑草をしっかり分解するだけの信念という土壌微生物・土壌細菌がある場合に限りますが。
従って信念や努力を伴わない単なる疑いだけではいたずらに疲労と苦しみと不安感と意識の散乱しかもたらさず、何も善法を結果しません。疑いというゴミ袋の奥に、必ず何らかの光る善なる信念や努力に転じるような熱いものがなければ、その疑蓋による苦痛は成果をもたらさないことになります。ここに求道者になれる人となれない人の差異があります。つまり「善なる信念」です。疑蓋ならば誰にでもあります。しかし何らかの善への信は得難いものです。善への信が生じるためには正見か正知か正見に関連する教えを聞いて、自ら検討することが不可欠です。強い信念を持つためには彼の中に「強固な理由」が要ります。それは善い環境と善い環境を得るための事前の福という善循環が必要です。そして自らを省みてそのような善に基づく強い信念がすでに自らの内に形成されているのが見えるならば、大いなる利益はそれを育てた先に必ずあるはずです。
この疑いの苦しみは原始仏典では「荒野の旅」として表現しています。答えがないというところに着目すればそのように「真実という飲み水がない」というところとリンクし、一方で外界から提示される解答が多過ぎる場合、これは原始仏典では「見解の密林・世界観のジャングル」として、これもまた苦しみの原因として譬えられます。考えても考えても埒があかないという意味における苦しみの場合は迷路に譬えられます。
疑いと迷いとわからないことによる苦しみを解決するために努力を続けるのか、あるいは思考停止して現実逃避として五欲に逃げ込むかどうかは各人の存在者としての能力如何です。人は常に自分の全存在をもって自分の内側の悩みをはじめとする悪法と、外側からの誘惑と恐怖と快楽と苦痛と不安とに対峙し続けています。圧倒的な意志力で問題の対象を知り尽くしてそれらに勝つか、快楽と苦痛と理解不能な困難さに打ち負けるのか、常に問われずして問われ続けています。その自分の全存在をかけた内と外における肉体のみならず心の要素における摂取と分解と吸収と再生と排除という闘争の結果が今の自分であり、今もそうやって変化し続けていると言えます。
僕が思うのは、前世は含めずとも今生だけであっても、今に至る全人生の出来事を完全に消化し切って、その過去の失敗と後悔と悲しみと苦しみの全てを「丸ごと未来に叩き付ける」ならば、それだけでかなり精神的にスリムになるのではないかということです。過去は過ぎたことです。過去を想って生じる想いは未来に向けなければ悲しみしか生じない因果連鎖になりやすいと思います。多くの人は過去を乗り越えるのに十分な無常想を修習していませんから。僕もそうですが。
過去を想った分は未来を想えば希望が後悔と悲しみを和らげるという算段です。理想は漏尽です。今までの全苦を全想起するがゆえに全苦滅への強烈な意向を生じさせることを意図的に行なうわけです。しかし僕の中では、漏尽への意向を固める決定的な何かがまだ足りていません。やはりいまだ苦を遍知せずということなのだと思います。「道は万里」と出ていますが、その道を外れる気もないというところです。
疑蓋自体は純粋悪ですが、その疑蓋によって生じる苦と不利益を長く受け続けた者はその疑いという特定悪からの脱出を他の悪法からの脱出と比べてより強く望む傾向を生じさせます。それは四念処や三善根というすでにあった善法の増大として生じて来ます。内において繰り広げられる善法と悪法の相克です。わからないという苦しみをよく知る者こそが知る利益をよく知るということです。
疑いが生じるためには何らかの強烈な失敗と苦痛が必要な場合が多いです。しかも「この方法でうまくいくと信じたのに駄目だった」という「善を意図していたのに悪を結果してしまった信念」。これがあってはじめて知恵に転じる根本的な土壌になります。そしてここに疑いという雑草の種を蒔けば、疑蓋はゴミ袋のようにその人の頭部をすっぽり包み、答えが出されるまで「わからない苦しみ」の中でのたうち廻ります。そんなわからない苦しみも、正知にもとづく正見という良き種の肥やしになります。疑いという雑草をしっかり分解するだけの信念という土壌微生物・土壌細菌がある場合に限りますが。
従って信念や努力を伴わない単なる疑いだけではいたずらに疲労と苦しみと不安感と意識の散乱しかもたらさず、何も善法を結果しません。疑いというゴミ袋の奥に、必ず何らかの光る善なる信念や努力に転じるような熱いものがなければ、その疑蓋による苦痛は成果をもたらさないことになります。ここに求道者になれる人となれない人の差異があります。つまり「善なる信念」です。疑蓋ならば誰にでもあります。しかし何らかの善への信は得難いものです。善への信が生じるためには正見か正知か正見に関連する教えを聞いて、自ら検討することが不可欠です。強い信念を持つためには彼の中に「強固な理由」が要ります。それは善い環境と善い環境を得るための事前の福という善循環が必要です。そして自らを省みてそのような善に基づく強い信念がすでに自らの内に形成されているのが見えるならば、大いなる利益はそれを育てた先に必ずあるはずです。
この疑いの苦しみは原始仏典では「荒野の旅」として表現しています。答えがないというところに着目すればそのように「真実という飲み水がない」というところとリンクし、一方で外界から提示される解答が多過ぎる場合、これは原始仏典では「見解の密林・世界観のジャングル」として、これもまた苦しみの原因として譬えられます。考えても考えても埒があかないという意味における苦しみの場合は迷路に譬えられます。
疑いと迷いとわからないことによる苦しみを解決するために努力を続けるのか、あるいは思考停止して現実逃避として五欲に逃げ込むかどうかは各人の存在者としての能力如何です。人は常に自分の全存在をもって自分の内側の悩みをはじめとする悪法と、外側からの誘惑と恐怖と快楽と苦痛と不安とに対峙し続けています。圧倒的な意志力で問題の対象を知り尽くしてそれらに勝つか、快楽と苦痛と理解不能な困難さに打ち負けるのか、常に問われずして問われ続けています。その自分の全存在をかけた内と外における肉体のみならず心の要素における摂取と分解と吸収と再生と排除という闘争の結果が今の自分であり、今もそうやって変化し続けていると言えます。
僕が思うのは、前世は含めずとも今生だけであっても、今に至る全人生の出来事を完全に消化し切って、その過去の失敗と後悔と悲しみと苦しみの全てを「丸ごと未来に叩き付ける」ならば、それだけでかなり精神的にスリムになるのではないかということです。過去は過ぎたことです。過去を想って生じる想いは未来に向けなければ悲しみしか生じない因果連鎖になりやすいと思います。多くの人は過去を乗り越えるのに十分な無常想を修習していませんから。僕もそうですが。
過去を想った分は未来を想えば希望が後悔と悲しみを和らげるという算段です。理想は漏尽です。今までの全苦を全想起するがゆえに全苦滅への強烈な意向を生じさせることを意図的に行なうわけです。しかし僕の中では、漏尽への意向を固める決定的な何かがまだ足りていません。やはりいまだ苦を遍知せずということなのだと思います。「道は万里」と出ていますが、その道を外れる気もないというところです。
漏尽を求めなくても、今までの人生を全ておさらいして「本当の自分の気持ち」に気付くのはとてもよいことだと思います。それは四念処の一環となり、特に心念処の修習になると思います。「本当の自分の気持ち」というよりは普段意識してはいないけれど、常に自分に影響を与え続けており、しかもそれは外界ではなく内界にあるから外界にあるものと違って自分はそれから逃げることはできないという受・想・思などの感情や欲求のことです。一般的には「本心」とか「本当の自分の気持ち」です。
普段のささやかな感情も全て事実としての本当の気持ちですが、一般に言われる「本当の気持ち」というのは様々な心の因果連鎖において「より一層根本的に自己の心の因果連鎖に影響を与えて続けている気持ち」を指します。嫉妬や腹立たしさや不満も本当の気持ちには相違ないですが、この場合「本当はもっと愛して欲しい」「本当はもっと認めて欲しい」というのが本当の気持ちであることが普通です。
普段の暮らしでは何かしらの事件が起きないかぎりはそういった気持ちに気付くことはないし、自分でもあえて見ないし、また見たくもないものです。しかしその本当の気持ちからは誰も逃げることはできず、もしその震源を探るならば、きっとその本当の気持ちは前世も含めた「自業自得 + 間違ったやり方」に行き着くに違いありません。愚かさにもとづく邪見に始まる十邪法とそれによる非福の悪循環です。
聖者レベルの人の本当の気持ちは「絶対に自分に善をもたらさなければ」とか「絶対に多くの人々に真の善なる何かを獲得させなければ」というものかも知れませんが、それにもまた強烈な渇愛や貪り、自己消去不能な使命感などの固定されたヴィジョンがなければなりません。
自業自得の他に運不運の出来事も人生にはありますが、強烈なトラウマや精神の核を為す部分は自業自得の回転により多くは作られていると思います。それだけの強固なものが形成されるには非常に多くの繰り返しが必要であると考えられるからです。もちろんその性格の核もまた生滅を繰り返しますが、これがもっとも強固で濃厚に固められているので、少し忍耐強く物事を考察できない人には自分の性格というものがあたかも変更不可能であるかのように感じます。これは生滅を見る無常想によって徐々に分解すべきですが、なかなか難しいことです。また悪法を滅した後に構築する善法の準備も必要になります。
無常想が難しいのはそれが漏尽にも転じる修行であり、漏尽は欲貪の滅を伴うものなので、欲貪量を上回るだけの十分な信が必要不可欠であり、十分な信を得るためには十分な正見の考察が必要不可欠です。ゴータマが生きている間は別です。ゴータマが生きており、その姿を眼にすることができ耳で声を聞くことができるならば、ゴータマと接するだけで強烈な信が惹起されるでしょうから。しかしもう当時の阿羅漢たちは全員死んでいますので、誰もが単独仏陀のごとく自分で考察し探求し修行するしかありません。
「自業自得 + 間違ったやり方」のうち、間違ったやり方というのは邪見に始まる他の七支がその領域において回転することです。さらに邪知と邪解脱も加わって苦しみと悲しみが完成します。自業自得とはこの十邪法を原因として時間差をおいてから生じる報いの結実のことです。つまるところ六触処における全ての自己の経験というものは、正邪の八支、あるいは正邪の十法という自ら行なう行と、その業の報いによって大きく影響されていると思います。そしてそれが自分の性格を強く形成する原因となるので、善循環と悪循環の意図的なコントロールができるか否かが、幸不幸の分かれ目になると思います。
「間違ったやり方」として十邪法を原因として悪業の報いが来るのですから、結局のところ自己の内において八正道が展開するのか、八邪道が展開するのかという問題に過ぎないとも言えます。業の報いはどちらかが発動した段階で決まっているのですから。誰もが見解によって身の振り方を決めていますが、このような見解に関する正見、正見を原因として生じる結果への正見を持っている正見者こそが賢者です。彼は内の正見によってさらなる正見に達するからです。そこには自己完結的により一層錬磨されて純度を高める正見それ自体が持つ昇華作用があります。正見に努めるときそこに正念と正定を因とする正知も生じますから、仮説と検証としてもよいと思います。
普段のささやかな感情も全て事実としての本当の気持ちですが、一般に言われる「本当の気持ち」というのは様々な心の因果連鎖において「より一層根本的に自己の心の因果連鎖に影響を与えて続けている気持ち」を指します。嫉妬や腹立たしさや不満も本当の気持ちには相違ないですが、この場合「本当はもっと愛して欲しい」「本当はもっと認めて欲しい」というのが本当の気持ちであることが普通です。
普段の暮らしでは何かしらの事件が起きないかぎりはそういった気持ちに気付くことはないし、自分でもあえて見ないし、また見たくもないものです。しかしその本当の気持ちからは誰も逃げることはできず、もしその震源を探るならば、きっとその本当の気持ちは前世も含めた「自業自得 + 間違ったやり方」に行き着くに違いありません。愚かさにもとづく邪見に始まる十邪法とそれによる非福の悪循環です。
聖者レベルの人の本当の気持ちは「絶対に自分に善をもたらさなければ」とか「絶対に多くの人々に真の善なる何かを獲得させなければ」というものかも知れませんが、それにもまた強烈な渇愛や貪り、自己消去不能な使命感などの固定されたヴィジョンがなければなりません。
自業自得の他に運不運の出来事も人生にはありますが、強烈なトラウマや精神の核を為す部分は自業自得の回転により多くは作られていると思います。それだけの強固なものが形成されるには非常に多くの繰り返しが必要であると考えられるからです。もちろんその性格の核もまた生滅を繰り返しますが、これがもっとも強固で濃厚に固められているので、少し忍耐強く物事を考察できない人には自分の性格というものがあたかも変更不可能であるかのように感じます。これは生滅を見る無常想によって徐々に分解すべきですが、なかなか難しいことです。また悪法を滅した後に構築する善法の準備も必要になります。
無常想が難しいのはそれが漏尽にも転じる修行であり、漏尽は欲貪の滅を伴うものなので、欲貪量を上回るだけの十分な信が必要不可欠であり、十分な信を得るためには十分な正見の考察が必要不可欠です。ゴータマが生きている間は別です。ゴータマが生きており、その姿を眼にすることができ耳で声を聞くことができるならば、ゴータマと接するだけで強烈な信が惹起されるでしょうから。しかしもう当時の阿羅漢たちは全員死んでいますので、誰もが単独仏陀のごとく自分で考察し探求し修行するしかありません。
「自業自得 + 間違ったやり方」のうち、間違ったやり方というのは邪見に始まる他の七支がその領域において回転することです。さらに邪知と邪解脱も加わって苦しみと悲しみが完成します。自業自得とはこの十邪法を原因として時間差をおいてから生じる報いの結実のことです。つまるところ六触処における全ての自己の経験というものは、正邪の八支、あるいは正邪の十法という自ら行なう行と、その業の報いによって大きく影響されていると思います。そしてそれが自分の性格を強く形成する原因となるので、善循環と悪循環の意図的なコントロールができるか否かが、幸不幸の分かれ目になると思います。
「間違ったやり方」として十邪法を原因として悪業の報いが来るのですから、結局のところ自己の内において八正道が展開するのか、八邪道が展開するのかという問題に過ぎないとも言えます。業の報いはどちらかが発動した段階で決まっているのですから。誰もが見解によって身の振り方を決めていますが、このような見解に関する正見、正見を原因として生じる結果への正見を持っている正見者こそが賢者です。彼は内の正見によってさらなる正見に達するからです。そこには自己完結的により一層錬磨されて純度を高める正見それ自体が持つ昇華作用があります。正見に努めるときそこに正念と正定を因とする正知も生じますから、仮説と検証としてもよいと思います。
僕は自分の性格についてよく考えるというか念じるのですが、その自分の性格の構造を見ていつも「皮肉だな」という感想を持ちます。
人は本当の欲求がありその欲求を満たす方法がわからないままに、これ以上苦しみと悲しみが持続することを怖れるがゆえに粘り強い努力をやめて、自分は本当はこれが欲しかったというその本当の気持ちに蓋をして通常意識からは分からないように隠してしまいます。人が本当の欲求を満たすための長期の努力をすることは大変困難です。怖いからです。せっかく本当の気持ちを直視して努力してもそれは得られないかも知れない、努力が無駄になるかも知れない、また辛いことになるかも知れないと考えるからです。求不得苦。過去の記憶が処理し切れていないと、過去は未来につながるはずの現在の足を引っ張り、結果的により一層本当の欲しいものから離れてしまいます。
しかし過去の苦い記憶を自分なりに処理し、さらに内界において展開する因果連鎖から逃れることはできないという知識、あるいは強烈な本心との葛藤を経験した人間はもはや自分の気持ちや感情や欲求から逃げることはありません。「自分の内面とは対峙するしかない」ということをよく心得ており、また挫折や失敗もまた原因があって生じることをよく知るからです。
書けば簡単、しかし実践は困難。結局一時的な本心の自覚だけでは、恐怖とトラウマの回転と本当に欲しいものを求めて行動し続けることへの自信のなさ、そして自分の本当の欲求を自ら見て見ぬ振りをして「いつものやり方と生き方に逃げ込む毎日」に埋没していきます。
悲しいことに人間も含めて他の多くの存在者たちもおそらくは、こういった皮肉で悲しい心の因果連鎖の繰り返しによって今の自分が形成されており、本当に欲しいものは決して手に入ることがないという現実を見せつけられ続けています。これらは単に心の不良債権がいたずらにたまっていく日々に過ぎません。自分のやり方を信じていたのに全然幸せになれなかったという悲しみがいかにも焦げ付いた債券のようです。しかもまだ諦め切れていない自分がそこにはいます。
というのも諦めるにしても十分な情報、五蘊生滅の正知が必要だからです。損切りには自身の内面においてよくよく得心することと決断へとジャンプさせる勇気がいります。自分の努力の正否を正しく評価することは誰にとっても困難です。過去の自分の時間の過ごし方がいかに無駄でもっとより良い過ごし方ができたかという指摘は誰にでも言えます。そして、それが他者や自己を傷付けていたならばなおさらです。過去を自分の中で処理し切ろうとしてもどうしても一つの壁、現在の自分につながる動かし難い心の動きに行き着きます。自分の心の状況確認とはかくも困難なことです。
あまりにも自分の本当の気持ちをこの普段の意識によって意識的にとらえることをしないままで来た人にとっては、つまり簡単に言えば自分の本当の気持ちを自覚することを怠って来た人が、自分の本当の気持ちを見つめるときはもう、泣くしかありません。抑圧分の本当の気持ちは過去に起源を持ち、それはすでに過ぎ去ってしまっており、取り返しのつかないと本人が自覚するところの心の違逆、そこにおいてはただ悲しみのみが漂うからです。
人は自分で思う以上に、確実に、正確なまでの過去の描写ととも、悲しみを抱えています。多くの人が心の深いところで泣いていることは、また実際に多くの人が涙を流すことは、自分の利益にならず、むしろ不利益なことです。本当の気持ちを抑圧し切り離して悲しみの涙から逃げていても、それは自らの心に為されるべき返済の先延ばしに過ぎません。人には泣くしかないという時は確かにあります。愚かさも執着も訓練なく今すぐ断つことはできないからです。しかし、いたずらにただ泣き続ける日々も邪見と愚かさと執着による時間と労力と感受性の無駄遣いです。
本当の自分の気持ちと本当の自分の欲求、それを正確に確実に「とらえ続けること」、そしてそこに悪法あるときはそれを排除し、そこに善法あるときはそれを増大させること。この本心を見つめ続ける心念処の継続的作業と、その本心が善悪正邪いずれに分類され、何が予期されるのかを法察覚支によって考察・検査しつつ、精進覚支を発動させること、これが重要です。そして四念処中心に生活を組み立て直すべきです。利益を欲する人は。僕は最近は「原始仏教とは四念処中心」なのだとよく思います。
しかしこれを多くの人に要求することはあまりにも酷です。もっと多くの人々が無理なく楽に、容易に喜んで幸せになれる方法が必要なのかも知れません。しかし念身よりもさらに単純な修行道の提示も不可能だとも思います。「悲しみの大地、地球」、それが僕の感想です。
人は本当の欲求がありその欲求を満たす方法がわからないままに、これ以上苦しみと悲しみが持続することを怖れるがゆえに粘り強い努力をやめて、自分は本当はこれが欲しかったというその本当の気持ちに蓋をして通常意識からは分からないように隠してしまいます。人が本当の欲求を満たすための長期の努力をすることは大変困難です。怖いからです。せっかく本当の気持ちを直視して努力してもそれは得られないかも知れない、努力が無駄になるかも知れない、また辛いことになるかも知れないと考えるからです。求不得苦。過去の記憶が処理し切れていないと、過去は未来につながるはずの現在の足を引っ張り、結果的により一層本当の欲しいものから離れてしまいます。
しかし過去の苦い記憶を自分なりに処理し、さらに内界において展開する因果連鎖から逃れることはできないという知識、あるいは強烈な本心との葛藤を経験した人間はもはや自分の気持ちや感情や欲求から逃げることはありません。「自分の内面とは対峙するしかない」ということをよく心得ており、また挫折や失敗もまた原因があって生じることをよく知るからです。
書けば簡単、しかし実践は困難。結局一時的な本心の自覚だけでは、恐怖とトラウマの回転と本当に欲しいものを求めて行動し続けることへの自信のなさ、そして自分の本当の欲求を自ら見て見ぬ振りをして「いつものやり方と生き方に逃げ込む毎日」に埋没していきます。
悲しいことに人間も含めて他の多くの存在者たちもおそらくは、こういった皮肉で悲しい心の因果連鎖の繰り返しによって今の自分が形成されており、本当に欲しいものは決して手に入ることがないという現実を見せつけられ続けています。これらは単に心の不良債権がいたずらにたまっていく日々に過ぎません。自分のやり方を信じていたのに全然幸せになれなかったという悲しみがいかにも焦げ付いた債券のようです。しかもまだ諦め切れていない自分がそこにはいます。
というのも諦めるにしても十分な情報、五蘊生滅の正知が必要だからです。損切りには自身の内面においてよくよく得心することと決断へとジャンプさせる勇気がいります。自分の努力の正否を正しく評価することは誰にとっても困難です。過去の自分の時間の過ごし方がいかに無駄でもっとより良い過ごし方ができたかという指摘は誰にでも言えます。そして、それが他者や自己を傷付けていたならばなおさらです。過去を自分の中で処理し切ろうとしてもどうしても一つの壁、現在の自分につながる動かし難い心の動きに行き着きます。自分の心の状況確認とはかくも困難なことです。
あまりにも自分の本当の気持ちをこの普段の意識によって意識的にとらえることをしないままで来た人にとっては、つまり簡単に言えば自分の本当の気持ちを自覚することを怠って来た人が、自分の本当の気持ちを見つめるときはもう、泣くしかありません。抑圧分の本当の気持ちは過去に起源を持ち、それはすでに過ぎ去ってしまっており、取り返しのつかないと本人が自覚するところの心の違逆、そこにおいてはただ悲しみのみが漂うからです。
人は自分で思う以上に、確実に、正確なまでの過去の描写ととも、悲しみを抱えています。多くの人が心の深いところで泣いていることは、また実際に多くの人が涙を流すことは、自分の利益にならず、むしろ不利益なことです。本当の気持ちを抑圧し切り離して悲しみの涙から逃げていても、それは自らの心に為されるべき返済の先延ばしに過ぎません。人には泣くしかないという時は確かにあります。愚かさも執着も訓練なく今すぐ断つことはできないからです。しかし、いたずらにただ泣き続ける日々も邪見と愚かさと執着による時間と労力と感受性の無駄遣いです。
本当の自分の気持ちと本当の自分の欲求、それを正確に確実に「とらえ続けること」、そしてそこに悪法あるときはそれを排除し、そこに善法あるときはそれを増大させること。この本心を見つめ続ける心念処の継続的作業と、その本心が善悪正邪いずれに分類され、何が予期されるのかを法察覚支によって考察・検査しつつ、精進覚支を発動させること、これが重要です。そして四念処中心に生活を組み立て直すべきです。利益を欲する人は。僕は最近は「原始仏教とは四念処中心」なのだとよく思います。
しかしこれを多くの人に要求することはあまりにも酷です。もっと多くの人々が無理なく楽に、容易に喜んで幸せになれる方法が必要なのかも知れません。しかし念身よりもさらに単純な修行道の提示も不可能だとも思います。「悲しみの大地、地球」、それが僕の感想です。
全て欲望も怒りも疑いも一度生じればある程度方向は決まっています。欲望を満たすまで頑張るのか、欲望を完全に捨てるのか、あるいは自分の気持ちに一時的に蓋をするのか。また怒りをぶちまけて相手を破滅させるのか、怒りを完全に捨てるのか、あるいは自分の怒りを一時的に抑圧するのか。また迷いが晴れるまで探求を続けるのか、疑いを完全に捨てるのか、あるいは思考停止して考えることをやめて、しかも本心では納得できていないままなのか。他にも様々な道があるかも知れませんが、問題を永劫に見て見ぬ振りをすることは困難です。問題の根本を叩かない限りは。しかし一時的に気持ちを封印する力も時に応じて使えば有用です。問題を解決できる力が手に入ったときにまた自ら問題を取り出して解決への努力をするときまでの時間稼ぎになるからです。しかし大抵の人は心に蓋をしたままですが。
実際に自分というものは自ら望まざる因果連鎖によって構築されています。自分もまた単なる因果連鎖に過ぎないのですが、こんな自分を作るつもりはなかったのにこんな自分を自ら作ってしまったということは悲劇です。そして外界において悪業の報いが次々に熟して降り掛かって来るのは本人にしてみれば悪夢であり、いまだに三悪行や有漏の行を行なう自分を制御できずにさらなる悪業を犯して漏を形成してしまうのは悪夢の続きです。多くの人は楽しみと幸せを望むのにその結果としては、「どうしてこんなことに」と誰もが疑蓋にとらわれることになります。実際に世界の動きが現在の自分の知力では理解できず、納得できず、はっきりとわからないから、その無知を原因としてそのような想が連鎖して結果するということです。
無知の原因は無知の不利益性への無知を問題の根本原因とします。そして、この世界のルールを学ばないのは危険であると知らなかった無知さ、この世界のルールを学ぶ重要性を知らなかった迂闊さ、この世界のルールを学ぶ必要などないと考えた驕りと自惚れ、この世界のルールを学ぶ努力を惜しんだ怠慢と努力を惜しむケチさ加減などが無知がどういうことであるかわかっていないというその無知さの周辺を旋回します。まとめれば正見と邪見についての正見のなさ、その正見を得るための正念と正精進の欠如とそれらの欠如から生じる邪知と邪解脱の回転です。
僕は自分の過去を振り返ると「バカなことをしたな」と思います。そしてその自分自身のかつての愚かさと確かに愚かでなければならなかったその必然性と「今も見落とし続けているに違いない重要なことの数々」に思いを馳せてぞっとします。漏尽に達するまでは全ては程度問題に過ぎません。自惚れる前に未熟な自分を高めることが先決です。
多くの人は仕事で認められて異性の愛を得ると簡単に調子に乗ってしまいます。あるいは仕事と恋愛がうまくいっている人間に簡単に嫉妬します。これら驕りや嫉妬という意悪行を行なわなければ、欲楽を満たせる状況を現出させ維持しやすくなるのに人は心の行ないを軽んじて邪念を放置します。結果、欲楽を満たせる状況は得られず得ても失われやすくなります。全て状況の好転は自らの実力の把握から始まります。またどこで一喜一憂するかの段階がその人の個性とその方向性への力の高低を明らかにします。問題は邪念を原因として生じる結果に対する無知です。邪念を原因として何も悪は結果しないだろうと考えるから、人は邪念を放置します。それは事実に沿っていないと思います。
「どうしてこんなことに」と思うなら、まずは自分の愚かさ加減をはっきりと認めることから本当の再起は始まると思います。反省が嫌いな人間は同じ悲しみに繰り返し泣くことになっても仕方ありません。現実を拒絶する者が現実に拒絶され、現実を受け入れる者が現実に受け入れられることになるというのは、因果連鎖の妙たるところです。知の不思議、とそう思います。そして、「現実を受け入れる」というのはつまるところマスターすれば、全執着の完全放棄たる涅槃そのものに達します。一切の現実に対して反発する動かしがたいヴィジョンが皆無になるから、もしも心が欲するならばそのヴィジョンを滅して不快の感受を断つことができるようになるからです。しかし言うは易しです。世間で交されるちょっとした助言やことわざを本気でマスターしたら、全ての問題は滅します。しかし世間のちょっとした言葉や助言では具体的な修行道がなく、ただ発想だけの叙述や省略されたものがあまりにも多いです。それを達成するためには四諦知から始まる八正道と四念処から始まる七覚支が万般の問題に対応する具体的な修行道だと思います。
実際に自分というものは自ら望まざる因果連鎖によって構築されています。自分もまた単なる因果連鎖に過ぎないのですが、こんな自分を作るつもりはなかったのにこんな自分を自ら作ってしまったということは悲劇です。そして外界において悪業の報いが次々に熟して降り掛かって来るのは本人にしてみれば悪夢であり、いまだに三悪行や有漏の行を行なう自分を制御できずにさらなる悪業を犯して漏を形成してしまうのは悪夢の続きです。多くの人は楽しみと幸せを望むのにその結果としては、「どうしてこんなことに」と誰もが疑蓋にとらわれることになります。実際に世界の動きが現在の自分の知力では理解できず、納得できず、はっきりとわからないから、その無知を原因としてそのような想が連鎖して結果するということです。
無知の原因は無知の不利益性への無知を問題の根本原因とします。そして、この世界のルールを学ばないのは危険であると知らなかった無知さ、この世界のルールを学ぶ重要性を知らなかった迂闊さ、この世界のルールを学ぶ必要などないと考えた驕りと自惚れ、この世界のルールを学ぶ努力を惜しんだ怠慢と努力を惜しむケチさ加減などが無知がどういうことであるかわかっていないというその無知さの周辺を旋回します。まとめれば正見と邪見についての正見のなさ、その正見を得るための正念と正精進の欠如とそれらの欠如から生じる邪知と邪解脱の回転です。
僕は自分の過去を振り返ると「バカなことをしたな」と思います。そしてその自分自身のかつての愚かさと確かに愚かでなければならなかったその必然性と「今も見落とし続けているに違いない重要なことの数々」に思いを馳せてぞっとします。漏尽に達するまでは全ては程度問題に過ぎません。自惚れる前に未熟な自分を高めることが先決です。
多くの人は仕事で認められて異性の愛を得ると簡単に調子に乗ってしまいます。あるいは仕事と恋愛がうまくいっている人間に簡単に嫉妬します。これら驕りや嫉妬という意悪行を行なわなければ、欲楽を満たせる状況を現出させ維持しやすくなるのに人は心の行ないを軽んじて邪念を放置します。結果、欲楽を満たせる状況は得られず得ても失われやすくなります。全て状況の好転は自らの実力の把握から始まります。またどこで一喜一憂するかの段階がその人の個性とその方向性への力の高低を明らかにします。問題は邪念を原因として生じる結果に対する無知です。邪念を原因として何も悪は結果しないだろうと考えるから、人は邪念を放置します。それは事実に沿っていないと思います。
「どうしてこんなことに」と思うなら、まずは自分の愚かさ加減をはっきりと認めることから本当の再起は始まると思います。反省が嫌いな人間は同じ悲しみに繰り返し泣くことになっても仕方ありません。現実を拒絶する者が現実に拒絶され、現実を受け入れる者が現実に受け入れられることになるというのは、因果連鎖の妙たるところです。知の不思議、とそう思います。そして、「現実を受け入れる」というのはつまるところマスターすれば、全執着の完全放棄たる涅槃そのものに達します。一切の現実に対して反発する動かしがたいヴィジョンが皆無になるから、もしも心が欲するならばそのヴィジョンを滅して不快の感受を断つことができるようになるからです。しかし言うは易しです。世間で交されるちょっとした助言やことわざを本気でマスターしたら、全ての問題は滅します。しかし世間のちょっとした言葉や助言では具体的な修行道がなく、ただ発想だけの叙述や省略されたものがあまりにも多いです。それを達成するためには四諦知から始まる八正道と四念処から始まる七覚支が万般の問題に対応する具体的な修行道だと思います。
僕は時を置いて不定期にいつもの疑蓋に悩まされます。
最近も「どうすればいいのか」とずっと考えてました。物心がついたときからこの「どうすればいいんだ病」が発症するので、哲学とか宗教とか人生論とか、どうしてもそういう書籍を読んだり、いかに生きるべきかという在るべき在り方について考えていました。僕は迷ったときは知恵に聞く習慣がついており、確信という光が見えないかぎり考えることがやめられない性格でした。僕の求道が長期間に渡って続いてきたのは僕の努力というよりは、ただ単に「どうすればいいんだ」という苦悩の病気にかかっていたから求道せざるを得なかっただけというのが心の因果連鎖の現実だと思います。
「今はこれを為すべきである」という想が確信を伴って生じない限り、迷いは消えません。根本作意をもって疑蓋を破砕しないかぎりは。為すは行、意志の行使の能動的な側面に着目し、三行あるいは八支として展開していきます。「べき」というところに利益と義と意義と必然性が見いだされなければなりません。その行為を原因として利益が生じる行為、物事の在り方、因果連鎖の在り方として必然的な行為であり、その知を有するものが取るに相応しい行為、その知を有するものが取らざるを得ない行為、それらに関する知をもって為すべきことが明らかになります。
為すべきことは得られるべき善を知り、その得られるべき善の原因となる行為を知ればよいのですが、その得られるべき善を知ることが困難であり、今この状況においては何がもっともその善に対して有効となる行為であるのかを知るのが困難です。普通、得られるべき善は利益や楽、無染にして苦に転じない楽であったりするのですが、さらに勧めると利益や楽の原因となる力、その力の原因となる努力の習慣、その努力を継続する習慣の原因である信念や見解、即ち正見に行き着き、さらにその正見の原因である正しい教えを読み聞きすることと物事を根本的にメタにもぐって考えること、そしてその素材となる自分の過去の様々な経験、その記憶を想起するための記憶力と注意力と想起力と集中力、関連したものを関連付ける力や考えを分解して再構築する力、まとめて念力、根本作意、意志の力。そこに行き着きます。
念が一切の生ける者の心の動きの全てに浸透していることを見て、そこに知の原因の根本があることを見て、念があるときその念分の知があり、念がないときは念がない分の知はないと考えれば、四念処が智慧に導くものであり、正覚にいたる七つの支分である七覚支の最初に来ることに得心が行きます。そうであれば、「今何を為すべきか」という確信、信根、信力は慧力に基づくことが知れ、慧力に応じた日々の対応しか人は取ることができないことも知れ、智慧を得るためには定力念力が必要であることが知れ、念力を鍛えるためには念根を継続して修習することが必要であることが知れ、念根を継続して修習するためには強い念の利益と忘念の不利益に関する考察と知と信と見解が必要であることが知れます。信から勤、念定慧と続き、慧によって日々の自分の行動、言動、三行、八支への確信が生じ、その確信がさらなる努力を生み出します。確信する者はその確信した方向に行為することに関しては勇者となるからです。
念は普通、一般常識内における意志を表し、超常の領域とは関わりを持たないように思えます。果たして念力を鍛えた果てに超常の知覚を得るかどうかはまだわかりません。問題は智慧の根本が接触に依っており、五感の接触とそれを内において想起したり再構築するだけでは不十分であるということです。死後の世界と人ならざる者たちを知覚しないうちは、生存中の適切な行動が導き出せないということです。超能力や霊能力がないゆえに過ちを犯して不利益を蒙っているとされる話はよくあります。どうしても超常の力は必要となります。とくに知覚の方面です。それが天眼です。
慧眼の素材となる五感の経験と天眼による超常の知覚による経験、これらの情報分と整理が本人の知恵のレベルにおいて決定的となります。それゆえに念力とともに天眼も鍛えることが急務となります。三眼である肉眼と天眼と慧眼をフル活用して今まさに為すべきことにおける確信に達すということです。天眼を開発するために四神足があり、光明想と昼想が有効とあります。天眼は賢者たらんと欲する者にとって不可欠な要素だと最近僕は強く感じています。僕自身あまり修行してないですが。
求道において知を得て、修行において力を得るために大切なことは「焦らないこと」「時間をかけること」「労力を惜しまないこと」「忍耐強く粘り強く取り組むこと」「損失を覚悟すること」だということが今回再度、身に沁みました。辛く長い道になることを覚悟しておくことは大切です。心の準備は心の苦受を軽減させるからです。
最近も「どうすればいいのか」とずっと考えてました。物心がついたときからこの「どうすればいいんだ病」が発症するので、哲学とか宗教とか人生論とか、どうしてもそういう書籍を読んだり、いかに生きるべきかという在るべき在り方について考えていました。僕は迷ったときは知恵に聞く習慣がついており、確信という光が見えないかぎり考えることがやめられない性格でした。僕の求道が長期間に渡って続いてきたのは僕の努力というよりは、ただ単に「どうすればいいんだ」という苦悩の病気にかかっていたから求道せざるを得なかっただけというのが心の因果連鎖の現実だと思います。
「今はこれを為すべきである」という想が確信を伴って生じない限り、迷いは消えません。根本作意をもって疑蓋を破砕しないかぎりは。為すは行、意志の行使の能動的な側面に着目し、三行あるいは八支として展開していきます。「べき」というところに利益と義と意義と必然性が見いだされなければなりません。その行為を原因として利益が生じる行為、物事の在り方、因果連鎖の在り方として必然的な行為であり、その知を有するものが取るに相応しい行為、その知を有するものが取らざるを得ない行為、それらに関する知をもって為すべきことが明らかになります。
為すべきことは得られるべき善を知り、その得られるべき善の原因となる行為を知ればよいのですが、その得られるべき善を知ることが困難であり、今この状況においては何がもっともその善に対して有効となる行為であるのかを知るのが困難です。普通、得られるべき善は利益や楽、無染にして苦に転じない楽であったりするのですが、さらに勧めると利益や楽の原因となる力、その力の原因となる努力の習慣、その努力を継続する習慣の原因である信念や見解、即ち正見に行き着き、さらにその正見の原因である正しい教えを読み聞きすることと物事を根本的にメタにもぐって考えること、そしてその素材となる自分の過去の様々な経験、その記憶を想起するための記憶力と注意力と想起力と集中力、関連したものを関連付ける力や考えを分解して再構築する力、まとめて念力、根本作意、意志の力。そこに行き着きます。
念が一切の生ける者の心の動きの全てに浸透していることを見て、そこに知の原因の根本があることを見て、念があるときその念分の知があり、念がないときは念がない分の知はないと考えれば、四念処が智慧に導くものであり、正覚にいたる七つの支分である七覚支の最初に来ることに得心が行きます。そうであれば、「今何を為すべきか」という確信、信根、信力は慧力に基づくことが知れ、慧力に応じた日々の対応しか人は取ることができないことも知れ、智慧を得るためには定力念力が必要であることが知れ、念力を鍛えるためには念根を継続して修習することが必要であることが知れ、念根を継続して修習するためには強い念の利益と忘念の不利益に関する考察と知と信と見解が必要であることが知れます。信から勤、念定慧と続き、慧によって日々の自分の行動、言動、三行、八支への確信が生じ、その確信がさらなる努力を生み出します。確信する者はその確信した方向に行為することに関しては勇者となるからです。
念は普通、一般常識内における意志を表し、超常の領域とは関わりを持たないように思えます。果たして念力を鍛えた果てに超常の知覚を得るかどうかはまだわかりません。問題は智慧の根本が接触に依っており、五感の接触とそれを内において想起したり再構築するだけでは不十分であるということです。死後の世界と人ならざる者たちを知覚しないうちは、生存中の適切な行動が導き出せないということです。超能力や霊能力がないゆえに過ちを犯して不利益を蒙っているとされる話はよくあります。どうしても超常の力は必要となります。とくに知覚の方面です。それが天眼です。
慧眼の素材となる五感の経験と天眼による超常の知覚による経験、これらの情報分と整理が本人の知恵のレベルにおいて決定的となります。それゆえに念力とともに天眼も鍛えることが急務となります。三眼である肉眼と天眼と慧眼をフル活用して今まさに為すべきことにおける確信に達すということです。天眼を開発するために四神足があり、光明想と昼想が有効とあります。天眼は賢者たらんと欲する者にとって不可欠な要素だと最近僕は強く感じています。僕自身あまり修行してないですが。
求道において知を得て、修行において力を得るために大切なことは「焦らないこと」「時間をかけること」「労力を惜しまないこと」「忍耐強く粘り強く取り組むこと」「損失を覚悟すること」だということが今回再度、身に沁みました。辛く長い道になることを覚悟しておくことは大切です。心の準備は心の苦受を軽減させるからです。
僕はまだ求道中で修行中の身ですし、原始仏教もまだ検証中のものです。コミュニティにおける書き込みは推理推論に拠ったものであり、超常の知覚や体験に拠るものではありません。ただ無害・慈心・念身についてはすでに経験的には成果を上げて来ていますのでおすすめできます。しかし原始仏教が目指す所の本懐である漏尽の倶分解脱についてはいまだ通達していません。
また原始仏教等に関する僕の説明は僕の性格や思考回路を通しているので、僕寄りのものです。ですから僕と異なる行動原理を持っている人には受け付け難い面も多々あると思います。そのあたりは僕の人格のマイナス面を差し引いて公正な目で自ら原始仏教を考究していただければと思います。
宗教や精神世界というのはハイリスク・ハイリターンなものではないかと思っています。異次元の領域は知覚、検証が困難なため他者の言葉や書籍を信じる、悪く言えば鵜呑みにせざるを得ないことが多いと思います。その場合、信じた内容が現実に対応していない分は破滅に接近します。しかしもし、信じた内容が現実に対応しているならば、その分は繁栄へと導きます。
検証には時間が掛かります。自分をある特定の修行法によって鍛錬する場合はなおさらです。間違った修行法の選択ほど恐ろしいものはありません。何でも経験すればよいというものではないと思います。断崖絶壁から飛び降りるのも一つの経験だと言われて飛び降りれば多分死にます。実験には代償が付き物です。人生では無駄な労力を支払わなければならないことが多々あります。目的と計画がなければないほど、より一層無駄な労力は増大するでしょう。ロスは避けられませんが、努力をすればロスを軽減させることはできます。反省と改善です。
僕は無職で慈心による業の報いという名の奇跡によって生計を立てれたらと思っています。これは博打です。ハイリスク・ハイリターンの危険な賭けです。もっともバイトしたくなったらバイトしますが。しかし限界までは。「働けば生きていける」というのは世間で広く知られた見解の一つです。しかし働いていても死ぬ人は現実にいます。ですから「働けば生きていける確率が上がる」と訂正したほうがいいかも知れません。僕はいまだ天眼によって業の報いの有無を確認していません。場合によって愚かな者となると思います。というより天眼によって確認していない無知分はすでに愚かです。
それだけ何かを信じるということは恐ろしいことだと思います。かと言って一般の世間の通念が大丈夫だというわけでもありませんが。それもまた一つの時代と地域における信です。僕は時代を超越する考え方を常に心掛けてきましたが、趣味嗜好において時代を超越することは非常に困難であることを感じます。最奥の見解が確立されたその分において、後に非常にゆっくりと自己の習性全体が変化していくと見ています。
普通の生き方、一般常識による生き方はロウリスク・ロウリターンのように思われますが、多分非常に長期の時代に渡っては徐々に堕落し底を打って徐々に向上していくのだと思います。しかしそれでは僕の自尊心はまったく満足しません。僕は凡人というものを「時代と一緒に進歩し、時代と一緒に退化する人々」であると思っています。もちろん彼らは見下すべき存在ではなく哀れむべき存在です。
凡人を超越すること、卓越すること、偉大なる者となること、一般の確率から外れて自らは例外的な優秀者となること、それは求める価値があると思っています。賭ければ勝ったり擦ったり。多分、前世において何かの信仰を持ち一部は正解し一部は間違えを繰り返し、損失を取り戻すためにさらに大きく賭けます。正見と邪見の幅、善業と悪業の幅は大きくなります。力を所有するものの在り方は外界に対してそのようです。美徳に着目するまでは。
僕はこれで最後だと思いたいですし、原始仏教に賭けてみたい気はします。かと言って油断は大敵なので健全なる懐疑的精神をもって慎重に。と言いつつ博打ですが。思い通りにならない自分を思い通りにする、というよりも思いと法とを沿わせる作業、僕は自分がどうなっていくのか見て行くつもりです。この態度があるとき未来において間違いに気付いたときは反省できます。自分で自分を見続ける気がない人は自分を観察し続けるというその行の欠落によって自覚を失い反省と方向転換が失われます。というこの知、これをもまた見続けることによって再確認し、自らの知と慧において信を得るというところです。時間は経過し因果は流れ行くがゆえに、賢者でさえも未来に対する信を外すことはできないと思います。ゆえに信根と信力がはじめに来るのだと思います。
「信じるのは慎重に」という標語が宗教や精神世界には必要だと思います。できれば実生活全般にも。そして信は現実によって試されます。
また原始仏教等に関する僕の説明は僕の性格や思考回路を通しているので、僕寄りのものです。ですから僕と異なる行動原理を持っている人には受け付け難い面も多々あると思います。そのあたりは僕の人格のマイナス面を差し引いて公正な目で自ら原始仏教を考究していただければと思います。
宗教や精神世界というのはハイリスク・ハイリターンなものではないかと思っています。異次元の領域は知覚、検証が困難なため他者の言葉や書籍を信じる、悪く言えば鵜呑みにせざるを得ないことが多いと思います。その場合、信じた内容が現実に対応していない分は破滅に接近します。しかしもし、信じた内容が現実に対応しているならば、その分は繁栄へと導きます。
検証には時間が掛かります。自分をある特定の修行法によって鍛錬する場合はなおさらです。間違った修行法の選択ほど恐ろしいものはありません。何でも経験すればよいというものではないと思います。断崖絶壁から飛び降りるのも一つの経験だと言われて飛び降りれば多分死にます。実験には代償が付き物です。人生では無駄な労力を支払わなければならないことが多々あります。目的と計画がなければないほど、より一層無駄な労力は増大するでしょう。ロスは避けられませんが、努力をすればロスを軽減させることはできます。反省と改善です。
僕は無職で慈心による業の報いという名の奇跡によって生計を立てれたらと思っています。これは博打です。ハイリスク・ハイリターンの危険な賭けです。もっともバイトしたくなったらバイトしますが。しかし限界までは。「働けば生きていける」というのは世間で広く知られた見解の一つです。しかし働いていても死ぬ人は現実にいます。ですから「働けば生きていける確率が上がる」と訂正したほうがいいかも知れません。僕はいまだ天眼によって業の報いの有無を確認していません。場合によって愚かな者となると思います。というより天眼によって確認していない無知分はすでに愚かです。
それだけ何かを信じるということは恐ろしいことだと思います。かと言って一般の世間の通念が大丈夫だというわけでもありませんが。それもまた一つの時代と地域における信です。僕は時代を超越する考え方を常に心掛けてきましたが、趣味嗜好において時代を超越することは非常に困難であることを感じます。最奥の見解が確立されたその分において、後に非常にゆっくりと自己の習性全体が変化していくと見ています。
普通の生き方、一般常識による生き方はロウリスク・ロウリターンのように思われますが、多分非常に長期の時代に渡っては徐々に堕落し底を打って徐々に向上していくのだと思います。しかしそれでは僕の自尊心はまったく満足しません。僕は凡人というものを「時代と一緒に進歩し、時代と一緒に退化する人々」であると思っています。もちろん彼らは見下すべき存在ではなく哀れむべき存在です。
凡人を超越すること、卓越すること、偉大なる者となること、一般の確率から外れて自らは例外的な優秀者となること、それは求める価値があると思っています。賭ければ勝ったり擦ったり。多分、前世において何かの信仰を持ち一部は正解し一部は間違えを繰り返し、損失を取り戻すためにさらに大きく賭けます。正見と邪見の幅、善業と悪業の幅は大きくなります。力を所有するものの在り方は外界に対してそのようです。美徳に着目するまでは。
僕はこれで最後だと思いたいですし、原始仏教に賭けてみたい気はします。かと言って油断は大敵なので健全なる懐疑的精神をもって慎重に。と言いつつ博打ですが。思い通りにならない自分を思い通りにする、というよりも思いと法とを沿わせる作業、僕は自分がどうなっていくのか見て行くつもりです。この態度があるとき未来において間違いに気付いたときは反省できます。自分で自分を見続ける気がない人は自分を観察し続けるというその行の欠落によって自覚を失い反省と方向転換が失われます。というこの知、これをもまた見続けることによって再確認し、自らの知と慧において信を得るというところです。時間は経過し因果は流れ行くがゆえに、賢者でさえも未来に対する信を外すことはできないと思います。ゆえに信根と信力がはじめに来るのだと思います。
「信じるのは慎重に」という標語が宗教や精神世界には必要だと思います。できれば実生活全般にも。そして信は現実によって試されます。
コメント3、4、5あたりの続きの内容で書いたのは少し前で、また前後の文章をコミュニティに書き込まないままに僕個人のメモを削除・改変したりしているため全体の脈絡に問題がありますが、一応少し修正して書き込んでおきます。僕の書き込みにはそういうことがよくあるのですが、継続を優先するために少し手抜きをさせていただいています。以下。
ゴータマ・シッダッタの偉大性は「正しく知る方法」を明確に提示したところにあります。正定に達したときに正知するということです。正定を原因として正知がある。正知すれば知った分に対応して悪法からの解放、正解脱があるということです。そして正定とは「そのような精神統一によって不利益や悪法が生じることがない精神統一」を意味し、そのような邪悪な精神統一でなく正しい精神統一として五蓋を捨てる初禅を説いたところが第一の超人法への快挙です。
人がぼんやりと感じてはいるが明確には気付かない精神状態を意識的に自覚することによってその精神状態を自ら作り出し、維持し、自らその精神状態を破る道筋を完全に見切ったところにゴータマの鋭さがあります。そして、五蓋を始めとして心の要素を次々に滅却すればするほどより一層精神統一は深まるということ、それは道理からして体験していなくてもあり得ると予測できます。そして精神統一の純粋さに対応して知ろうとする対象が覚知されるということ、これが八正道から導き出される正しい知にいたる道理にかなった道筋です。
現実の通り、実際の通りに間違えずに物事を正しく知るために三つの眼を用いるとされています。肉眼・天眼・慧眼です。正定の状態ではこの三つの眼はその正定の度合いに応じて開かれます。僕はまだあまり開いてないのですが理屈上はです。正定を得るために正念を説いたり、戒学を説いたりします。正しく知るための慧学として戒学と心学を学ぶ、あるいは正しく知るために正しく念じて努力する、そこには強い信念が必要だということです。五つの学ぶ者の力である信・勤・念・定・慧。あるいは天眼を開発するための光明想や昼想。
知るために眼が要ります。肉眼と天眼と慧眼を得るための修行が説かれます。ボケッとしていれば肉眼に何が映っているかさえも気付きません。注意深い人間だけがよく見聞きして状況を常に把握しています。
この方向性は一般の生じたアイデアのままに突き進んで行く方向性とは真逆です。世間一般の通念が自分に生じていることを自覚しそれに従うのではなく、なぜそれが生じたのかを考究します。メタに切り込み、前提を破壊します。その自覚が自由を生み出します。自覚という正念を続けることによって正定を得ることがあり、正定を得たときは世間一般の通念の正しい面と間違った面を見切って正知を得て、間違った面を見切ったときは世間一般の通念の間違った側面からの正解脱があります。主に五欲や自らの身体についての見解は世間と聖律においては正反対です。
全宇宙の最奥の法則を知りたいというアイデアのままに突き進んでいたずらに哲学的境地を賛美し求めるよりも、法則という発想自体を検討し、仮に帰納法によって見いだした観念が現実に対応しているとしても、それが果たして生ける者である自己に有用な観念なのかを検討し、そもそもなぜ究極の法則、真理を知りたいと思ったのかを探るほうが先決です。そこには自分の六触処における感受、いわゆる経験と過去に形成してきた学問への信と帰納法への馴染みと「真理」という単語への信や愛着などがあるはずです。もちろん名誉や称賛や疑いや迷いやその他もろもろもです。
そしてそれらの因果連鎖によって今の自分にこのような疑いと解決法への信があり、それら全てには原因があってそれぞれが別々に生滅しており、優勢な思いが実行されていることに気付きます。その過去に形成された諸行が現在において時間差のように現れる意識の連なり、それは確かに海の波のように譬えられるかも知れません。海はよく潜在意識に譬えられます。聖者の律において海とは世間か五欲であったと思います。いずれにしてもこの海を自覚の光によって照らし切り、知り尽くすことによって自己制御の完成に達します。
このように自覚を続けていくうちに、生ける者にとって有用なのは宇宙を支配する諸法則の王である真理を観念の中で構築することではなく、この現実を短時間で即座に把握する強靭な意志力と最高の集中力を鍛えることこそが、現実という真実への知に導くものだと知ります。過去の事実も未来に見いだされるであろう真実も全てはこの現実において結合し一致点を見ているからです。そして結果的にその過程で自己制御に至る法則も自然に帰納されて発見されて観念として自己の内に新たに形成されていくと思います。
ゴータマ・シッダッタの偉大性は「正しく知る方法」を明確に提示したところにあります。正定に達したときに正知するということです。正定を原因として正知がある。正知すれば知った分に対応して悪法からの解放、正解脱があるということです。そして正定とは「そのような精神統一によって不利益や悪法が生じることがない精神統一」を意味し、そのような邪悪な精神統一でなく正しい精神統一として五蓋を捨てる初禅を説いたところが第一の超人法への快挙です。
人がぼんやりと感じてはいるが明確には気付かない精神状態を意識的に自覚することによってその精神状態を自ら作り出し、維持し、自らその精神状態を破る道筋を完全に見切ったところにゴータマの鋭さがあります。そして、五蓋を始めとして心の要素を次々に滅却すればするほどより一層精神統一は深まるということ、それは道理からして体験していなくてもあり得ると予測できます。そして精神統一の純粋さに対応して知ろうとする対象が覚知されるということ、これが八正道から導き出される正しい知にいたる道理にかなった道筋です。
現実の通り、実際の通りに間違えずに物事を正しく知るために三つの眼を用いるとされています。肉眼・天眼・慧眼です。正定の状態ではこの三つの眼はその正定の度合いに応じて開かれます。僕はまだあまり開いてないのですが理屈上はです。正定を得るために正念を説いたり、戒学を説いたりします。正しく知るための慧学として戒学と心学を学ぶ、あるいは正しく知るために正しく念じて努力する、そこには強い信念が必要だということです。五つの学ぶ者の力である信・勤・念・定・慧。あるいは天眼を開発するための光明想や昼想。
知るために眼が要ります。肉眼と天眼と慧眼を得るための修行が説かれます。ボケッとしていれば肉眼に何が映っているかさえも気付きません。注意深い人間だけがよく見聞きして状況を常に把握しています。
この方向性は一般の生じたアイデアのままに突き進んで行く方向性とは真逆です。世間一般の通念が自分に生じていることを自覚しそれに従うのではなく、なぜそれが生じたのかを考究します。メタに切り込み、前提を破壊します。その自覚が自由を生み出します。自覚という正念を続けることによって正定を得ることがあり、正定を得たときは世間一般の通念の正しい面と間違った面を見切って正知を得て、間違った面を見切ったときは世間一般の通念の間違った側面からの正解脱があります。主に五欲や自らの身体についての見解は世間と聖律においては正反対です。
全宇宙の最奥の法則を知りたいというアイデアのままに突き進んでいたずらに哲学的境地を賛美し求めるよりも、法則という発想自体を検討し、仮に帰納法によって見いだした観念が現実に対応しているとしても、それが果たして生ける者である自己に有用な観念なのかを検討し、そもそもなぜ究極の法則、真理を知りたいと思ったのかを探るほうが先決です。そこには自分の六触処における感受、いわゆる経験と過去に形成してきた学問への信と帰納法への馴染みと「真理」という単語への信や愛着などがあるはずです。もちろん名誉や称賛や疑いや迷いやその他もろもろもです。
そしてそれらの因果連鎖によって今の自分にこのような疑いと解決法への信があり、それら全てには原因があってそれぞれが別々に生滅しており、優勢な思いが実行されていることに気付きます。その過去に形成された諸行が現在において時間差のように現れる意識の連なり、それは確かに海の波のように譬えられるかも知れません。海はよく潜在意識に譬えられます。聖者の律において海とは世間か五欲であったと思います。いずれにしてもこの海を自覚の光によって照らし切り、知り尽くすことによって自己制御の完成に達します。
このように自覚を続けていくうちに、生ける者にとって有用なのは宇宙を支配する諸法則の王である真理を観念の中で構築することではなく、この現実を短時間で即座に把握する強靭な意志力と最高の集中力を鍛えることこそが、現実という真実への知に導くものだと知ります。過去の事実も未来に見いだされるであろう真実も全てはこの現実において結合し一致点を見ているからです。そして結果的にその過程で自己制御に至る法則も自然に帰納されて発見されて観念として自己の内に新たに形成されていくと思います。
様々な教えを学び、信じ、実践することになる宗教や精神世界の領域において慎重さと謙虚さの美徳というものは非常に重要であり、同時に非常に難しいものであると強く感じます。
自らの実力を実際の実力の通りに自覚することとしての法念処、その身の程を弁える美徳は内においては慎重さとしても現れ、外においては謙虚さとしても現れるところのものです。身の程を弁えない者は慎重さとは逆の軽卒さを帯び、外においては謙虚さとは逆の傲慢さをその身にまといます。
教えについて慎重にして謙虚に発言することは難しく、自分が説くところとなった自分の見解を正しく判断して自覚することも難しいです。その自らの見解の構成要素に関するいくつかの重要な分類が、経験・情報・類推の三つであると今は考えています。このように分類することによって自分の持つ見解のより確定的で堅実なところと、不確定で仮説にとどまっているところ、変更可能なところをある程度把握できます。
人は自分が体験してきたことにもっとも信頼を置いています。自らの実体験は見解を構築する素材として最重要です。しかし体験や経験はそれだけではただの素材です。漠然と経験を積み重ねてきただけの人間は事実の記憶の集積しかなく「こうすればこうなる。こうしなければこうならない」という努力につながる因果連鎖の知にまで達しません。しかし、縁起の知と縁滅の知に至る材料としては自らの体験を使用するしかありませんし、仮説の実証もまた自らの体験の中で検証するしかないので、いつでも実際の自分の体験は最重要のものです。自分の体験において全ては結合するからです。六触処の接触内容はまさにその人にとって全てです。
この日常の実体験だけでは人生を処し切れないので、人はメディアや学校や会社などの組織からの情報と個人である家族や友人たちからの情報を信じ、受け入れて活用して生きていきます。しかしこれらの情報が意味するところのものは自ら体験したものではありません。この情報、これを「自分はこれを実際に確かめたわけではない」と意識して自覚し、自分の実体験と明確に区別して生きている人は少ないと思います。これらの情報が示す内容と自分の人生の経験内容が明確に分けられず、混同してくればくるほど外界の情報に左右されやすい、流されやすい、洗脳されやすい傾向を持っていきます。「自分の実体験とは異なる価値観を容易に受け入れていく」ということです。その外部から侵入してくる価値観が正見ならば利益となり邪見ならば不利益となります。
この流されやすさは一長一短のように見えますが、実際は自分で考えて自分で判断できない慧根と慧力が劣った状態であり、長期間この状態で生きるのは危険です。これとは異なり、慧根と慧力をもとより尊重する態度として、真実に飛びつき虚偽を排斥する習慣を持つ求道者の判断基準とその在り方のほうが遥かに有意義で優れています。そこには常時の反省と方向転換があるからです。
流されやすさが持つ、自分の見解の構成要素が実体験と、実体験の中の一部である情報が指し示す内容を判然と区別できない傾向は、自分の見解の構成要素への無知分があり、まだ自己の見解をより自在に自ら分解・再構築できる段階ではないということを意味しています。自分の見解の確固たる部分と不安定な部分を自覚できないがゆえに「自分は何かを見落としているはずだ」とも思えないし、「自分はまだこれを確かめていない」とも思えないし、「少なくともこの事実があったということだけは事実だ」という堅実な拠り所も得ていないと言えます。
そういった人の共通点としてはただ漠然と自分の価値観が正しいと信じ込んでいて、それに反発する考え方を提示されると単純に不快になる、困惑するという反応を示すことが多いです。多くの人にとって真実はどうでもいいことであり、ただ自分が固着する想と一致するものを見たり聞いたりしたいと思うだけです。見取と見取にもとづく欲取は強烈な固着です。多くの人は想像し難い自由の利益よりも、よく知り馴れている鎖につながれる安心感を優先します。鎖縛の欠点を知るまでは。
自分の考え方や生き方について慎重に吟味し、それを語る段においては謙虚さに立つということは宗教や思想に関わる人にとっても難しく、普通に生きる人にとっても難しいことです。しかし、これらの美徳を達成すれば自らの過失は減り、そのゆえに生じる安心感とともにさらに内界外界双方からの利益も多いと思います。「無畏にして説く」という説法者の美徳の一つにもつながります。
自らの実力を実際の実力の通りに自覚することとしての法念処、その身の程を弁える美徳は内においては慎重さとしても現れ、外においては謙虚さとしても現れるところのものです。身の程を弁えない者は慎重さとは逆の軽卒さを帯び、外においては謙虚さとは逆の傲慢さをその身にまといます。
教えについて慎重にして謙虚に発言することは難しく、自分が説くところとなった自分の見解を正しく判断して自覚することも難しいです。その自らの見解の構成要素に関するいくつかの重要な分類が、経験・情報・類推の三つであると今は考えています。このように分類することによって自分の持つ見解のより確定的で堅実なところと、不確定で仮説にとどまっているところ、変更可能なところをある程度把握できます。
人は自分が体験してきたことにもっとも信頼を置いています。自らの実体験は見解を構築する素材として最重要です。しかし体験や経験はそれだけではただの素材です。漠然と経験を積み重ねてきただけの人間は事実の記憶の集積しかなく「こうすればこうなる。こうしなければこうならない」という努力につながる因果連鎖の知にまで達しません。しかし、縁起の知と縁滅の知に至る材料としては自らの体験を使用するしかありませんし、仮説の実証もまた自らの体験の中で検証するしかないので、いつでも実際の自分の体験は最重要のものです。自分の体験において全ては結合するからです。六触処の接触内容はまさにその人にとって全てです。
この日常の実体験だけでは人生を処し切れないので、人はメディアや学校や会社などの組織からの情報と個人である家族や友人たちからの情報を信じ、受け入れて活用して生きていきます。しかしこれらの情報が意味するところのものは自ら体験したものではありません。この情報、これを「自分はこれを実際に確かめたわけではない」と意識して自覚し、自分の実体験と明確に区別して生きている人は少ないと思います。これらの情報が示す内容と自分の人生の経験内容が明確に分けられず、混同してくればくるほど外界の情報に左右されやすい、流されやすい、洗脳されやすい傾向を持っていきます。「自分の実体験とは異なる価値観を容易に受け入れていく」ということです。その外部から侵入してくる価値観が正見ならば利益となり邪見ならば不利益となります。
この流されやすさは一長一短のように見えますが、実際は自分で考えて自分で判断できない慧根と慧力が劣った状態であり、長期間この状態で生きるのは危険です。これとは異なり、慧根と慧力をもとより尊重する態度として、真実に飛びつき虚偽を排斥する習慣を持つ求道者の判断基準とその在り方のほうが遥かに有意義で優れています。そこには常時の反省と方向転換があるからです。
流されやすさが持つ、自分の見解の構成要素が実体験と、実体験の中の一部である情報が指し示す内容を判然と区別できない傾向は、自分の見解の構成要素への無知分があり、まだ自己の見解をより自在に自ら分解・再構築できる段階ではないということを意味しています。自分の見解の確固たる部分と不安定な部分を自覚できないがゆえに「自分は何かを見落としているはずだ」とも思えないし、「自分はまだこれを確かめていない」とも思えないし、「少なくともこの事実があったということだけは事実だ」という堅実な拠り所も得ていないと言えます。
そういった人の共通点としてはただ漠然と自分の価値観が正しいと信じ込んでいて、それに反発する考え方を提示されると単純に不快になる、困惑するという反応を示すことが多いです。多くの人にとって真実はどうでもいいことであり、ただ自分が固着する想と一致するものを見たり聞いたりしたいと思うだけです。見取と見取にもとづく欲取は強烈な固着です。多くの人は想像し難い自由の利益よりも、よく知り馴れている鎖につながれる安心感を優先します。鎖縛の欠点を知るまでは。
自分の考え方や生き方について慎重に吟味し、それを語る段においては謙虚さに立つということは宗教や思想に関わる人にとっても難しく、普通に生きる人にとっても難しいことです。しかし、これらの美徳を達成すれば自らの過失は減り、そのゆえに生じる安心感とともにさらに内界外界双方からの利益も多いと思います。「無畏にして説く」という説法者の美徳の一つにもつながります。
人は自らの体験と仕入れた情報を総合し、推理推論を積み重ねることによって世界観を構築しています。そして不安定で不確定な面においては「もしもこうであればこうなる。もしもこうでなければこうなる」と道理によってあり得ることとあり得ないことを推察し仮説を立てています。
この実体験と情報という二つを材料に類推して構築された見解のうちの確信部分に基づいて、人は不確定部分の見解の検証を常時行なっています。ただ普通の人は積極的な実験を試みないので実験と観察による検証領域は人によって大幅な違いがあります。大抵の人は日常生活の範囲でだけの変更があるだけです。根本の生き方を変える人は極少数です。双方ともに自己の見解を自らの六触処による体験により確認して検証していきます。そしてそれによって検証され確認された分が確信分に変わって行きます。
しかしその確信している内容と反する現実が生じれば、またそれを変えることになります。しかし見解への固執である見取分だけは自らの見解に反する現実を否定します。これは邪見を原因として生じる苦です。見取が少ない人は自らの見解を改めることが速やかですので、現実を素直に受け入れ自分の考えを改めます。この人には邪見による苦は速やかに滅し、正見による感受が生じます。
自見のうち自らの確信分は家の基礎的な構造に相当し、一時的で暫定的な信は家具や道具の仮置きに似た状態です。人はそういった家に譬えられるような自らの見解の中に常に住んでいます。地震や水害や火災や空き巣や強盗に耐えれる家と耐えられない家があるように、名誉の損失や財産の損失や健康の損失や家族の損失に耐えられないような見解と耐えられる見解などがあります。そこに見解の個性と優劣があります。四諦知から始まる正見は最終的に自らの家を破壊して無家の者として遊行する形に譬えられると思います。
これら自らの見解の構成要素を改めて知ることは大いに利益があります。「自分がどうしてこういう考え方をするようになったのか」と振り返ってみることは意義深いことです。もう一度、自分の人生の全経験を思い出し、自分が信じて受け入れている全情報を洗い出し、それらを総合して推測することによって作り上げている自分の世界観を検討してみることは自分自身、ある意味興味深いことが多いと思います。
この実体験と情報という二つを材料に類推して構築された見解のうちの確信部分に基づいて、人は不確定部分の見解の検証を常時行なっています。ただ普通の人は積極的な実験を試みないので実験と観察による検証領域は人によって大幅な違いがあります。大抵の人は日常生活の範囲でだけの変更があるだけです。根本の生き方を変える人は極少数です。双方ともに自己の見解を自らの六触処による体験により確認して検証していきます。そしてそれによって検証され確認された分が確信分に変わって行きます。
しかしその確信している内容と反する現実が生じれば、またそれを変えることになります。しかし見解への固執である見取分だけは自らの見解に反する現実を否定します。これは邪見を原因として生じる苦です。見取が少ない人は自らの見解を改めることが速やかですので、現実を素直に受け入れ自分の考えを改めます。この人には邪見による苦は速やかに滅し、正見による感受が生じます。
自見のうち自らの確信分は家の基礎的な構造に相当し、一時的で暫定的な信は家具や道具の仮置きに似た状態です。人はそういった家に譬えられるような自らの見解の中に常に住んでいます。地震や水害や火災や空き巣や強盗に耐えれる家と耐えられない家があるように、名誉の損失や財産の損失や健康の損失や家族の損失に耐えられないような見解と耐えられる見解などがあります。そこに見解の個性と優劣があります。四諦知から始まる正見は最終的に自らの家を破壊して無家の者として遊行する形に譬えられると思います。
これら自らの見解の構成要素を改めて知ることは大いに利益があります。「自分がどうしてこういう考え方をするようになったのか」と振り返ってみることは意義深いことです。もう一度、自分の人生の全経験を思い出し、自分が信じて受け入れている全情報を洗い出し、それらを総合して推測することによって作り上げている自分の世界観を検討してみることは自分自身、ある意味興味深いことが多いと思います。
自己の見解を正しく見て自覚する力を高めていけば、自分の考え方を真実に沿って変えることがより一層吝かではなくなります。最高度に柔軟性のある生き方というのは、たとえ今の自分の暮らしが全て変わってしまうとしても、真実が明らかになったときは自らの見解を真実に沿って改定するということです。
四念処に住する者はよく念じて自覚し、自らの身受心法を如実知見します。その如実知見、正知の分が正見を更新します。ゆえに四念住の出家在家は自帰依・法帰依と言われるに相応しい状態に住します。もし真実が明らかになっても自らの見解に固執する人がいるならば、その人は己からも法からも真実からも遠く離れています。ただ自見に執着する心の汚れとしての事実・現実とともにあるだけです。法と相応せず、自らの実体験と見解との不一致という現実に住します。これ自体が苦であり、また同時に邪見を原因とする邪語とそれを原因とする別の苦と不利益と他の悪も生み出します。
その正知に沿って新しく更新された見解が心の遺伝子として作用し、心の受想行識の配列を新しく設定し、新たな身業と語業の習慣を生み出し、新たな意業としての思考回路が確立されていきます。そして後に至って人格の全面的な変化を結果させることになります。見解は非常に長続きし、同時に長期的な影響を心の全体に与え続けるものであり、その影響を受けた心が身体に反映されてくるのだと思います。従って考え方を変えるということが自分の心と身体の全てをやがては変えることになります。
注意が必要な点は、考え方を変えたからと言って急に人生が好転するのではなく、考え方を本当に納得して正しくしたときはその見解が長期にわたって続くために、正見を原因として生じる正勤ある正命(特に正見にもとづく正思としての思考回路の繰り返し)もまた同様に長続きし、その継続的努力を原因として自分と自分の周囲が意図せずして徐々に徐々に改善されるという結果が生じるということです。
その改善の有り様の全てを正確に予測するほどの慧力はこの段階ではまだないのが普通であり、人は信じて継続的努力を続けるのみの場合が多いと思います。実力を得ていない生徒よりもすでに実力を得て引退したコーチのほうが生徒の進歩段階を長期的に予測できることと同じです。生徒はコーチと十分納得できるまで話し尽くしたら後は信じて特訓するだけです。あるいはコーチなしで一人で訓練する場合も自ら組んだカリキュラムを信じて訓練し続けるのみです。力を得ていない者は「絶対に自分は力を得ることができる」と100%言い切ることはできません。必ず信じるしかない分はあります。
見解は確信部分もあれば暫定的な部分もあります。始めから信じるに足る考え方があるのではなく、信じるに足る考え方を得るために、実験と観察による検証という方法を信じるならば、それが努力に転じるということです。
見解の部分部分に堅い脆いがあるように、見解自体を変更する条件への見解は、より一層優れた見解に至るためのメタな見解です。そのメタな見解が実験と観察による検証を重んじる見解、言い換えれば正見と正知の相互関係を重んじる見解、信根と慧根の相互関係を重んじる見解であり、その見解に向けられた信があるとき、その信を原因として実験と観察に向けられた精進根は発動するというメカニズムです。正見を修習する者にはこの正見が原因となり、正見への修習と進歩という結果があります。そしてこの正見の修習を「社会的立場や思想的立場を変更することになるとしても」意識的にしろ無意識的にしろ継続的に行なっている者が求道者です。というよりも求道者と名付けるわけです。
四念処に住する者はよく念じて自覚し、自らの身受心法を如実知見します。その如実知見、正知の分が正見を更新します。ゆえに四念住の出家在家は自帰依・法帰依と言われるに相応しい状態に住します。もし真実が明らかになっても自らの見解に固執する人がいるならば、その人は己からも法からも真実からも遠く離れています。ただ自見に執着する心の汚れとしての事実・現実とともにあるだけです。法と相応せず、自らの実体験と見解との不一致という現実に住します。これ自体が苦であり、また同時に邪見を原因とする邪語とそれを原因とする別の苦と不利益と他の悪も生み出します。
その正知に沿って新しく更新された見解が心の遺伝子として作用し、心の受想行識の配列を新しく設定し、新たな身業と語業の習慣を生み出し、新たな意業としての思考回路が確立されていきます。そして後に至って人格の全面的な変化を結果させることになります。見解は非常に長続きし、同時に長期的な影響を心の全体に与え続けるものであり、その影響を受けた心が身体に反映されてくるのだと思います。従って考え方を変えるということが自分の心と身体の全てをやがては変えることになります。
注意が必要な点は、考え方を変えたからと言って急に人生が好転するのではなく、考え方を本当に納得して正しくしたときはその見解が長期にわたって続くために、正見を原因として生じる正勤ある正命(特に正見にもとづく正思としての思考回路の繰り返し)もまた同様に長続きし、その継続的努力を原因として自分と自分の周囲が意図せずして徐々に徐々に改善されるという結果が生じるということです。
その改善の有り様の全てを正確に予測するほどの慧力はこの段階ではまだないのが普通であり、人は信じて継続的努力を続けるのみの場合が多いと思います。実力を得ていない生徒よりもすでに実力を得て引退したコーチのほうが生徒の進歩段階を長期的に予測できることと同じです。生徒はコーチと十分納得できるまで話し尽くしたら後は信じて特訓するだけです。あるいはコーチなしで一人で訓練する場合も自ら組んだカリキュラムを信じて訓練し続けるのみです。力を得ていない者は「絶対に自分は力を得ることができる」と100%言い切ることはできません。必ず信じるしかない分はあります。
見解は確信部分もあれば暫定的な部分もあります。始めから信じるに足る考え方があるのではなく、信じるに足る考え方を得るために、実験と観察による検証という方法を信じるならば、それが努力に転じるということです。
見解の部分部分に堅い脆いがあるように、見解自体を変更する条件への見解は、より一層優れた見解に至るためのメタな見解です。そのメタな見解が実験と観察による検証を重んじる見解、言い換えれば正見と正知の相互関係を重んじる見解、信根と慧根の相互関係を重んじる見解であり、その見解に向けられた信があるとき、その信を原因として実験と観察に向けられた精進根は発動するというメカニズムです。正見を修習する者にはこの正見が原因となり、正見への修習と進歩という結果があります。そしてこの正見の修習を「社会的立場や思想的立場を変更することになるとしても」意識的にしろ無意識的にしろ継続的に行なっている者が求道者です。というよりも求道者と名付けるわけです。
求道者を八支について定義すれば、正見の修習者が求道者であり、求道者とは正見の修習者であると言えます。ゆえに求道の見思語業命勤念定ある者が求道者とも言えます。
求道者が求める正見、その正見の修習の分だけは少なくとも彼に他の七支が転回し、その七支分における正知が生じ、その正知が正見の修習ともなるがゆえに、仏教も八正道も知らなくとも求道する者においては部分的に八正道が生じていると言えます。しかし四諦知に達しない限りは流れに入れません。ですから多くの学者は一部の知見において清浄であり正見を得ていても、苦の四諦と漏の四諦の知見を得ていないので、「すでにいずれ苦を滅する因果連鎖体となっている」とは言えないわけです。しかし誰であっても幾分の四諦知を得ていればそれを原因として「いずれ苦を滅すると因果連鎖体となっている」と言えます。流れに入っていなくとも今から学んで苦滅が結果されるような知を得れば、それが苦滅因の確保になるので誰にでも不死の門は開かれています。
いまだ正覚していないゴータマが正覚したのは、正覚以前であっても正見を修習するところの八正道に住していたからであり、正覚に至るまで正見修習も含む修行をやめないという卓越した求道者であったからです。智慧が完成してから八正道に住するのではなく、有漏の八正道に住してから正知を得て智慧に達し、有漏の八正道が無漏の八正道に切り替わり、正知・正解脱を含む無学・学び終わった者である阿羅漢の十法を成就するという順序です。
だから八正道を知っていても知らなくても、真実を求める求道者が真実を追究する分においては常に有漏の八正道が発動しているので、「彼は仏教も八正道も知らないが、真実を求める彼の中には八正道の法が部分的に存在すると言える」ということになります。この八支の正分と邪分の質と分量の違いが個々人の個性を作り上げていて、それらが彼らの未来の行き先も決めていると考えます。
そしてこれらは全て四念処において繰り広げられる自己より生じて自己を知見することに向けられた自己充足的にして自己錬磨の意念の動きです。古今東西の賢者は常に克己を目指してきたし、ゴータマもまた克己を完成しており、その克己に達するのは常に正しく自らに向けられた自らより生じたこの意志の力であるというところに存在の優劣と進歩の不可思議とがあると思います。
求道が正見修習である以上、正知に達するまではいまだ信を出ないと見るがゆえに求道者にとって慎重・謙虚であることは重要な美徳であり、資質の一つです。それらを踏まえた上で改めて自らの見解の起源と妥当性と暫定性をよく自覚するならば、より教えについての発言における謙虚さが増大し、傲慢な発言の減少が期待されるものであると思います。「これは自分が体験して確認した。これはまだ体験せず確認していない。これは読んだこと聞いたこと。これは読んだことではない。聞いたことではない。これは類推したこと。これは類推したことではない。これは確信をもって言えること。これはまだ自信をもって言えないこと」というように自らの見解と自分が話す内容の根拠が自他ともに明瞭明白にするように勤めることです。
謙虚さは他者に向けられた三行において現れますが、特に語行は耳に聞こえ、身行は眼で見ることができるものです。語行をよく左右するところの自らの見解の内実をよく自覚して押さえておけば、失言は減少すると思います。正語を得ようと思えばどうしても自らの思考と見解の再検討をせざるを得なくなり、見解の再検討はつまるところ自己の最奥である心の設計図の成り立ち自体の探索となります。そしてそれが見解の生滅知へと導き、その生滅の知を原因として見解への執着である見取が滅するという成果も獲得できます。一つの善法を追求すればそれに関連する善法も付随して来ます。善循環をうまく使えば修行も楽になります。
求道者が求める正見、その正見の修習の分だけは少なくとも彼に他の七支が転回し、その七支分における正知が生じ、その正知が正見の修習ともなるがゆえに、仏教も八正道も知らなくとも求道する者においては部分的に八正道が生じていると言えます。しかし四諦知に達しない限りは流れに入れません。ですから多くの学者は一部の知見において清浄であり正見を得ていても、苦の四諦と漏の四諦の知見を得ていないので、「すでにいずれ苦を滅する因果連鎖体となっている」とは言えないわけです。しかし誰であっても幾分の四諦知を得ていればそれを原因として「いずれ苦を滅すると因果連鎖体となっている」と言えます。流れに入っていなくとも今から学んで苦滅が結果されるような知を得れば、それが苦滅因の確保になるので誰にでも不死の門は開かれています。
いまだ正覚していないゴータマが正覚したのは、正覚以前であっても正見を修習するところの八正道に住していたからであり、正覚に至るまで正見修習も含む修行をやめないという卓越した求道者であったからです。智慧が完成してから八正道に住するのではなく、有漏の八正道に住してから正知を得て智慧に達し、有漏の八正道が無漏の八正道に切り替わり、正知・正解脱を含む無学・学び終わった者である阿羅漢の十法を成就するという順序です。
だから八正道を知っていても知らなくても、真実を求める求道者が真実を追究する分においては常に有漏の八正道が発動しているので、「彼は仏教も八正道も知らないが、真実を求める彼の中には八正道の法が部分的に存在すると言える」ということになります。この八支の正分と邪分の質と分量の違いが個々人の個性を作り上げていて、それらが彼らの未来の行き先も決めていると考えます。
そしてこれらは全て四念処において繰り広げられる自己より生じて自己を知見することに向けられた自己充足的にして自己錬磨の意念の動きです。古今東西の賢者は常に克己を目指してきたし、ゴータマもまた克己を完成しており、その克己に達するのは常に正しく自らに向けられた自らより生じたこの意志の力であるというところに存在の優劣と進歩の不可思議とがあると思います。
求道が正見修習である以上、正知に達するまではいまだ信を出ないと見るがゆえに求道者にとって慎重・謙虚であることは重要な美徳であり、資質の一つです。それらを踏まえた上で改めて自らの見解の起源と妥当性と暫定性をよく自覚するならば、より教えについての発言における謙虚さが増大し、傲慢な発言の減少が期待されるものであると思います。「これは自分が体験して確認した。これはまだ体験せず確認していない。これは読んだこと聞いたこと。これは読んだことではない。聞いたことではない。これは類推したこと。これは類推したことではない。これは確信をもって言えること。これはまだ自信をもって言えないこと」というように自らの見解と自分が話す内容の根拠が自他ともに明瞭明白にするように勤めることです。
謙虚さは他者に向けられた三行において現れますが、特に語行は耳に聞こえ、身行は眼で見ることができるものです。語行をよく左右するところの自らの見解の内実をよく自覚して押さえておけば、失言は減少すると思います。正語を得ようと思えばどうしても自らの思考と見解の再検討をせざるを得なくなり、見解の再検討はつまるところ自己の最奥である心の設計図の成り立ち自体の探索となります。そしてそれが見解の生滅知へと導き、その生滅の知を原因として見解への執着である見取が滅するという成果も獲得できます。一つの善法を追求すればそれに関連する善法も付随して来ます。善循環をうまく使えば修行も楽になります。
たとえ圧倒的な力を持つ光輝く存在からの啓示であっても鵜呑みにはせず、「この神はこのように言う。この神の啓示を受けるこの人はこのように言ったと覚えておこう。それが真実か否かはいずれ自分が確認しよう」という堅実な立場で物事を判断・保留・検証することが求道者に相応しい態度です。
それとは逆に「この神はすごい力を持っている。だからこの神の言うことは全て真実だ。そしてこの神の言うことに逆らう人は全て間違っている。そしてこの神を認める私は出来が良く、この神を認めない人は駄目な人だ」というのは粗野で早急な判断です。そうではなくて、「この神はすごい力を持っている。さらにこの神は嘘を言うことはないと考えられる。しかしこの神の知見にも足りないところがあり、この神にも間違いがある可能性があるということは道理にかなう。全てはよく調べられ確認されるべきだ。真偽がわからないものに飛びつき信じ込むのは危険だ。それらは全て検証されるべきだ」と見ます。それから検証法について自ら十全に検討し、検証に着手します。
多くの人は自分より優れている人や組織や人間ならざる存在からの考え方を鵜呑みにします。子供は親の言うことを素直に信じ、生徒は教師の言うことに従い、人間関係で劣位にある者は優位にある者の考え方に流され、会社員は会社の見解と社風の影響を受け、企業や政治家は世論に左右され、世論はこれら全ての社会の構成員たちと非人たちにより左右されています。社会が大きくなればなるほど、人と人との結びつきが広がれば広がるほど集団の力が増大し、個人の力が相対的に弱くなります。その分、人々は互いに互いを恐れ合います。莫大な力を所有している人は除いて。
それぞれの業界が支流のように流れ、それらが合流し世間一般の最も大きな通念を大河として形成しています。それぞれの川がそれぞれの業界であり分野であり共同体であり風土であるとすれば、川に住む生き物はそれらの見解と趣味嗜好と方向性に長期間住する人々です。川も色々、一つの川の中に住む生物も色々、複数の川に出入りできる人もいればその川から出ると死んでしまう繊細な人もいるということです。
その見解と思念が渦巻く地上界において何らかの目的を持って働きかけるのがデーヴァでありアスラでありマーラでありブラフマーであり如来たちであると考えられます。神も悪魔も川に住む人間を餌で釣るでしょうが、それぞれ目的が異なっています。阿羅漢も餌は使いますが、釣り針という暴力は使わないと思います。
彼らの啓示・神示・悪魔の閃き・聖者っぽい人の発言・学界の定説・古典聖典経典古文書の類い・各地に残る伝説と伝承、これらはいずれも喜んで受け取られるべきものではないし、非難されるべきものでもないと見ます。人間ならざるものたちから下されたもの、それは鵜呑みにされるべきものでもないし、検討されずに拒絶されるものではなく、まさにそれを受け取る個人個人が自らの実体験において自ら調べ確認され検証されるべきです。また検証に至る道も検討され、計画的に組まれるべきです。
それが行なえない人は自らよくわからないものに従うという危険な選択と言動を日々続けることになります。そしてその選択が自己に不利益をもたらす間違った選択である可能性が非常に高くなります。また検証意識の欠如により方向転換が困難になります。信じ込めば頑固になり、自分の考え方や生き方の再検討に心が進まなくなります。求道者は検証します。検証できない分は保留します。道理からあり得ることとあり得ないことを推察し、今取るべき堅実な行動を限られた情報から導き出します。信頼できる優先順位を自らの実体験を中心にして再構築して、慎重に道を選び取ります。そして過ちが明白となれば方向を変えます。それが真実を求める者にとって相応しいことです。
それとは逆に「この神はすごい力を持っている。だからこの神の言うことは全て真実だ。そしてこの神の言うことに逆らう人は全て間違っている。そしてこの神を認める私は出来が良く、この神を認めない人は駄目な人だ」というのは粗野で早急な判断です。そうではなくて、「この神はすごい力を持っている。さらにこの神は嘘を言うことはないと考えられる。しかしこの神の知見にも足りないところがあり、この神にも間違いがある可能性があるということは道理にかなう。全てはよく調べられ確認されるべきだ。真偽がわからないものに飛びつき信じ込むのは危険だ。それらは全て検証されるべきだ」と見ます。それから検証法について自ら十全に検討し、検証に着手します。
多くの人は自分より優れている人や組織や人間ならざる存在からの考え方を鵜呑みにします。子供は親の言うことを素直に信じ、生徒は教師の言うことに従い、人間関係で劣位にある者は優位にある者の考え方に流され、会社員は会社の見解と社風の影響を受け、企業や政治家は世論に左右され、世論はこれら全ての社会の構成員たちと非人たちにより左右されています。社会が大きくなればなるほど、人と人との結びつきが広がれば広がるほど集団の力が増大し、個人の力が相対的に弱くなります。その分、人々は互いに互いを恐れ合います。莫大な力を所有している人は除いて。
それぞれの業界が支流のように流れ、それらが合流し世間一般の最も大きな通念を大河として形成しています。それぞれの川がそれぞれの業界であり分野であり共同体であり風土であるとすれば、川に住む生き物はそれらの見解と趣味嗜好と方向性に長期間住する人々です。川も色々、一つの川の中に住む生物も色々、複数の川に出入りできる人もいればその川から出ると死んでしまう繊細な人もいるということです。
その見解と思念が渦巻く地上界において何らかの目的を持って働きかけるのがデーヴァでありアスラでありマーラでありブラフマーであり如来たちであると考えられます。神も悪魔も川に住む人間を餌で釣るでしょうが、それぞれ目的が異なっています。阿羅漢も餌は使いますが、釣り針という暴力は使わないと思います。
彼らの啓示・神示・悪魔の閃き・聖者っぽい人の発言・学界の定説・古典聖典経典古文書の類い・各地に残る伝説と伝承、これらはいずれも喜んで受け取られるべきものではないし、非難されるべきものでもないと見ます。人間ならざるものたちから下されたもの、それは鵜呑みにされるべきものでもないし、検討されずに拒絶されるものではなく、まさにそれを受け取る個人個人が自らの実体験において自ら調べ確認され検証されるべきです。また検証に至る道も検討され、計画的に組まれるべきです。
それが行なえない人は自らよくわからないものに従うという危険な選択と言動を日々続けることになります。そしてその選択が自己に不利益をもたらす間違った選択である可能性が非常に高くなります。また検証意識の欠如により方向転換が困難になります。信じ込めば頑固になり、自分の考え方や生き方の再検討に心が進まなくなります。求道者は検証します。検証できない分は保留します。道理からあり得ることとあり得ないことを推察し、今取るべき堅実な行動を限られた情報から導き出します。信頼できる優先順位を自らの実体験を中心にして再構築して、慎重に道を選び取ります。そして過ちが明白となれば方向を変えます。それが真実を求める者にとって相応しいことです。
求道者にとって特に重要なことは「恩ある者の見解と自らの見解とを別々のこととする」ことです。また「力ある者の見解と自らの見解とも別々のこととする」ことです。真実の探求と現世的な利益を与える存在者との関係を区別して混同しないことです。
恩恵を与えてもらっていることとその恩恵を与える者に唯々諾々と従うこと、これは別々のことです。利益を与えてもらっていることとその利益を与える者の命に従うこと、これも別々のことです。感謝すべき人や存在と彼らが主張する考えを受け入れること、これらは別々のことです。このような目上、お上、専門家、学界、世間、天界、神界、聖者からの見解・指示・方針・考え方の提示・指導・世界観の教授・命令・指令は求道とは特に意識的に区別され別のものとして考えられるべきだと思います。たとえば以下のように考えます。
「両親から利益と恩恵を受けた分は恩に感じて恩を知り、機会があれば感謝の意を三行によって伝えてその分の見解を同じくし、双方の信頼関係を向上させることに労を払い、余力があればその恩に報いる三行を為すけれども、両親の言いなりにはならず、両親が為せと言うことを為すわけでもなく、為すなと言うことを為さないわけでもない。
両親の見解と言葉に二つあり、その見解と言葉に従えば実際に利益が生じるものと、利益が生じないものとである。利益が生じない見解と言葉に従えば、自他双方のいずれかを害することになって自らの不利益と苦になると見るがゆえに、両親の見解に一方的に従うわけではない。両親の見解のうち現実に対応し実際に利益が生じるものにはこれに従い、実際に利益が生じないものには従わない。そしてその見解が両者いずれに分類されるかを正確に判断するために常時の熟慮と確認と検証作業を怠らない。人と人との相互の関係性の軽重と、物事の真偽、見解の正邪は別の問題であると見るから。
同様に世間から利益を受けた分は知恩感恩・謝辞・報恩しても世間の言いなりになるわけでもない。世間の見解に真偽、利益不利益を生じる二つがあり、善には従うも悪には従わない。悪事の片棒を担いで悪業の報いがこちらに降り掛かることを怖れて。
同様に神々から利益を受けた分も知恩感恩・謝辞・報恩しても神々の啓示内容を鵜呑みにするわけでもない。神々にも勘違いがあり、至らぬところがあり、知らず達さないところがあると見るから。その示される見解の真偽は常にこの現実において試され確認されるべきものであると考える。神示だから啓示だから黙示だからと言って、その言うところに従って不利益と苦が自らに結果することを考慮して。
同様にブッダが語った、如来が語った、原始仏典に書いてある、信頼できる経典に書いてある内容だからと言って鵜呑みにするわけでもない。伝承と伝達も間違っているかも知れず、彼はブッダでもなく如来でもなく悟ってもいないかも知れず、その教えの創始者が実際のところ真理にも真実にも知恵にも力にも達していないかも知れないから。伝聞や書籍によって知られるところの全ての情報は常時確認されるべきであり、再度検証されるべきものであると考えて用心する。
同様に聖者と言われている人が言うことも鵜呑みにはせず追随するわけでもない。検証されるまでは「この人はこう言った。さて実際はどうか確かめてみよう」という態度を堅持する。
何事も盲信を避けて、常にこの現実に立脚し、この現実において真実を追求し、この現実において現に確認できる事実に依拠すること。もし自らの見解がこの現実において一致しないところが見つかり、この現実・事実・真実から自らの見解が逸脱しているようなことが確認されれば直ちにこの現実に沿った見解へと自らの見解を変更し更新し改定すること。このようにすれば自らの見解は常に真実とともにあり、事実とともにあり、今ここにおいて見いだされるこの現実とともにあることになる。そうすれば、新しい現実が現れれば現れるほど、自らの見解と知力は向上を続けることになるだろう」。
恩恵を与えてもらっていることとその恩恵を与える者に唯々諾々と従うこと、これは別々のことです。利益を与えてもらっていることとその利益を与える者の命に従うこと、これも別々のことです。感謝すべき人や存在と彼らが主張する考えを受け入れること、これらは別々のことです。このような目上、お上、専門家、学界、世間、天界、神界、聖者からの見解・指示・方針・考え方の提示・指導・世界観の教授・命令・指令は求道とは特に意識的に区別され別のものとして考えられるべきだと思います。たとえば以下のように考えます。
「両親から利益と恩恵を受けた分は恩に感じて恩を知り、機会があれば感謝の意を三行によって伝えてその分の見解を同じくし、双方の信頼関係を向上させることに労を払い、余力があればその恩に報いる三行を為すけれども、両親の言いなりにはならず、両親が為せと言うことを為すわけでもなく、為すなと言うことを為さないわけでもない。
両親の見解と言葉に二つあり、その見解と言葉に従えば実際に利益が生じるものと、利益が生じないものとである。利益が生じない見解と言葉に従えば、自他双方のいずれかを害することになって自らの不利益と苦になると見るがゆえに、両親の見解に一方的に従うわけではない。両親の見解のうち現実に対応し実際に利益が生じるものにはこれに従い、実際に利益が生じないものには従わない。そしてその見解が両者いずれに分類されるかを正確に判断するために常時の熟慮と確認と検証作業を怠らない。人と人との相互の関係性の軽重と、物事の真偽、見解の正邪は別の問題であると見るから。
同様に世間から利益を受けた分は知恩感恩・謝辞・報恩しても世間の言いなりになるわけでもない。世間の見解に真偽、利益不利益を生じる二つがあり、善には従うも悪には従わない。悪事の片棒を担いで悪業の報いがこちらに降り掛かることを怖れて。
同様に神々から利益を受けた分も知恩感恩・謝辞・報恩しても神々の啓示内容を鵜呑みにするわけでもない。神々にも勘違いがあり、至らぬところがあり、知らず達さないところがあると見るから。その示される見解の真偽は常にこの現実において試され確認されるべきものであると考える。神示だから啓示だから黙示だからと言って、その言うところに従って不利益と苦が自らに結果することを考慮して。
同様にブッダが語った、如来が語った、原始仏典に書いてある、信頼できる経典に書いてある内容だからと言って鵜呑みにするわけでもない。伝承と伝達も間違っているかも知れず、彼はブッダでもなく如来でもなく悟ってもいないかも知れず、その教えの創始者が実際のところ真理にも真実にも知恵にも力にも達していないかも知れないから。伝聞や書籍によって知られるところの全ての情報は常時確認されるべきであり、再度検証されるべきものであると考えて用心する。
同様に聖者と言われている人が言うことも鵜呑みにはせず追随するわけでもない。検証されるまでは「この人はこう言った。さて実際はどうか確かめてみよう」という態度を堅持する。
何事も盲信を避けて、常にこの現実に立脚し、この現実において真実を追求し、この現実において現に確認できる事実に依拠すること。もし自らの見解がこの現実において一致しないところが見つかり、この現実・事実・真実から自らの見解が逸脱しているようなことが確認されれば直ちにこの現実に沿った見解へと自らの見解を変更し更新し改定すること。このようにすれば自らの見解は常に真実とともにあり、事実とともにあり、今ここにおいて見いだされるこの現実とともにあることになる。そうすれば、新しい現実が現れれば現れるほど、自らの見解と知力は向上を続けることになるだろう」。
こう考えて、恩があるからと言って親の言いなりにも、世間の言いなりにも、神々の言いなりにも、聖者とされる人の言いなりにもならず、ただこの現実、即ち現在生じている六触処の内容、つまり今自分の意識内容に生じて持続している物事とそれを再自覚するこの意識の継続、これこそ最初で最後の立脚点にして拠り所にして帰依所であり、これを州として灯明として島として生きていくならば、それが真の求道者であり、正念分の正知に基づく正見から始まる八正道に住する真正の沙門である、そのように考えます。
そのような者は遅かれ早かれ楽苦の感受の現実とその前後の因果の現実の認識に達し、それが四諦知に転じるとともに流れに入り、四諦知ある者の四諦知を原因として生じる結果の流れの必然としてやがては漏尽力を円満して無執着の心解脱に達すると見るからです。
限りなく話を簡単にすれば「何事も自分で考えて自分で確認して自分で判断しましょう。盲信は厳禁。間違っていたら危険だから」というだけの話です。求道以前に「自分で考えて自分で判断する」、これができている人は少なく実際実践はなかなかに難しい、けれどもこれができるようになったとき始めて自分の足で立ったと言え、また言い換えればそれが自己を州として自己に帰依するということになると思います。さらにそこで、あるいはその過程において四諦知を自ら見ればそれを原因として聖性に入ると考えられます。
そのような者は遅かれ早かれ楽苦の感受の現実とその前後の因果の現実の認識に達し、それが四諦知に転じるとともに流れに入り、四諦知ある者の四諦知を原因として生じる結果の流れの必然としてやがては漏尽力を円満して無執着の心解脱に達すると見るからです。
限りなく話を簡単にすれば「何事も自分で考えて自分で確認して自分で判断しましょう。盲信は厳禁。間違っていたら危険だから」というだけの話です。求道以前に「自分で考えて自分で判断する」、これができている人は少なく実際実践はなかなかに難しい、けれどもこれができるようになったとき始めて自分の足で立ったと言え、また言い換えればそれが自己を州として自己に帰依するということになると思います。さらにそこで、あるいはその過程において四諦知を自ら見ればそれを原因として聖性に入ると考えられます。
やはり唯一最高・全知全能・絶対神は存在しないと考えたほうが自分の経験に即しても道理にかなうと思いました。
原始仏典でもラッタパーラがコーラヴヤ王に言っています。「先生はこう言いました。この世界は無護、無主であると。たとえば王が病気で苦しむとき親族友人にその苦しみを分けて減らすことはできません。この世界は無護、無主であるからです」というふうに。
この世界に最高の支配者が存在するならば、悪および苦しみがこの世界には存在しなかったであろうと思います。しかし現実にこの世界には悪と苦と不幸があるということ、それが全知全能の支配者が存在しないことを証明しています。しかし、あくまでも至高者を信じる人々はこう言うことが予期されます。「悪と苦と不幸が存在することによって至高者なる神の善と栄光と至福とがより一層明確になり、引き立てられ、それを被造物が認識することによってその被造物はさらなる恩恵に浴する」と。しかしこれは間違っています。
なぜなら無益なる悪と苦が存在するからです。悪にも苦にも二種類あります。その悪や苦を原因として利益と楽を結果するものと、その悪や苦を原因としてさらなる不利益と苦を結果するものとがあります。計画的に創造された悪と苦であるならば、その全ての悪苦は必ずそれを原因として利益と楽を結果するはずです。しかしこの現実の世界においては悪苦の悪循環に陥り、悪苦からさらなる悪苦への堕落に無限に堕ちて行くような流れを現に見ます。そしてそこからさらなる災厄が他者にも及んでいます。その二種類ある悪苦は計画的というよりは恣意的にして無秩序に世界にばらまかれ、生ける者たちはその中で右往左往しています。それは最高自在者により計画的に創造された悪苦ではないからと見るのが道理にかないます。
しかし唯一神信仰の擁護者である人々や神々はこう言うかも知れません。「それは一時的な物の見方だ。無限に無限の時間が経過したとき全ての悪はやがては善となる。それもまた神の計画のうち」。しかし彼らはそう信じているだけです。いまだ無限に無限の時間が経過して全ての悪が善となったことを彼らは確かめていません。彼らは唯一神を見たこともありません。ただ「そうなればいいな」という希望で語っているだけです。一方で、現実に毒物が無毒化されるのは化学的な原因があるからであり、また悪人が善人に改心するときも心を改心させるような原因があるからであり、それらの悪が善に変化する現実を考察するに、そのときに超越者なる絶対神の介在を確認することはありません。ただ法則に従っているだけに見えます。原因があれば結果があるので、似たようなこと、同様のことが再現性をもって確認されることになります。ゆえに神が悪を善に変えていくのではなく、法則に則って原因あるときに悪が善に変化していくだけと見るのが正しいように思われます。
それでもあくまでもマハーブラフマー即全知全能且つ宇宙法則同体説を擁護する人はこう言うことが予期されます。「神は人間に自由意志を与えておられる。それでこそ恩恵は全うされるからだ。それでこそ善と悪といずれかを選択するかによってもっとも公平なる結末に至るからだ」と。しかしこれも間違っています。神はすでに全知ですが、一方の人間は無知から始まります。ゆえに神は善悪も知り為すべきことも知っていますが、人間は善悪も知らず為すべきことも知りません。それならば善悪も為すべきことも知らない人間が過ちを犯し悪を選択し続けるのも必定、それを予期しない神ではないのに、それでもって自由を与えると言う。そしてその因果の流れの上の非常に限られた力の分の自由などはほとんど自由の範疇に入るものでもないのに、そこで悪を犯した者に対して「私は自由を与え、汝はその自由によって罪を犯した。これは私の責任ではなくお前の責任なのだ」と罰を要求するなどということは真の正義にかなっていません。適切な教育が施されていないからです。たとえば腹を空かせた肉食獣を草食動物がいる柵の中に入れて、実際に殺して肉食したとして、その草食動物を殺した罪を人間が肉食獣に問うようなものです。ここでも業の報いや自在者の罰としての報いに二つあり、即ち利と楽を結果する苦と不利と苦を結果する苦があることによって恩恵が全うされていないことになります。
原始仏典でもラッタパーラがコーラヴヤ王に言っています。「先生はこう言いました。この世界は無護、無主であると。たとえば王が病気で苦しむとき親族友人にその苦しみを分けて減らすことはできません。この世界は無護、無主であるからです」というふうに。
この世界に最高の支配者が存在するならば、悪および苦しみがこの世界には存在しなかったであろうと思います。しかし現実にこの世界には悪と苦と不幸があるということ、それが全知全能の支配者が存在しないことを証明しています。しかし、あくまでも至高者を信じる人々はこう言うことが予期されます。「悪と苦と不幸が存在することによって至高者なる神の善と栄光と至福とがより一層明確になり、引き立てられ、それを被造物が認識することによってその被造物はさらなる恩恵に浴する」と。しかしこれは間違っています。
なぜなら無益なる悪と苦が存在するからです。悪にも苦にも二種類あります。その悪や苦を原因として利益と楽を結果するものと、その悪や苦を原因としてさらなる不利益と苦を結果するものとがあります。計画的に創造された悪と苦であるならば、その全ての悪苦は必ずそれを原因として利益と楽を結果するはずです。しかしこの現実の世界においては悪苦の悪循環に陥り、悪苦からさらなる悪苦への堕落に無限に堕ちて行くような流れを現に見ます。そしてそこからさらなる災厄が他者にも及んでいます。その二種類ある悪苦は計画的というよりは恣意的にして無秩序に世界にばらまかれ、生ける者たちはその中で右往左往しています。それは最高自在者により計画的に創造された悪苦ではないからと見るのが道理にかないます。
しかし唯一神信仰の擁護者である人々や神々はこう言うかも知れません。「それは一時的な物の見方だ。無限に無限の時間が経過したとき全ての悪はやがては善となる。それもまた神の計画のうち」。しかし彼らはそう信じているだけです。いまだ無限に無限の時間が経過して全ての悪が善となったことを彼らは確かめていません。彼らは唯一神を見たこともありません。ただ「そうなればいいな」という希望で語っているだけです。一方で、現実に毒物が無毒化されるのは化学的な原因があるからであり、また悪人が善人に改心するときも心を改心させるような原因があるからであり、それらの悪が善に変化する現実を考察するに、そのときに超越者なる絶対神の介在を確認することはありません。ただ法則に従っているだけに見えます。原因があれば結果があるので、似たようなこと、同様のことが再現性をもって確認されることになります。ゆえに神が悪を善に変えていくのではなく、法則に則って原因あるときに悪が善に変化していくだけと見るのが正しいように思われます。
それでもあくまでもマハーブラフマー即全知全能且つ宇宙法則同体説を擁護する人はこう言うことが予期されます。「神は人間に自由意志を与えておられる。それでこそ恩恵は全うされるからだ。それでこそ善と悪といずれかを選択するかによってもっとも公平なる結末に至るからだ」と。しかしこれも間違っています。神はすでに全知ですが、一方の人間は無知から始まります。ゆえに神は善悪も知り為すべきことも知っていますが、人間は善悪も知らず為すべきことも知りません。それならば善悪も為すべきことも知らない人間が過ちを犯し悪を選択し続けるのも必定、それを予期しない神ではないのに、それでもって自由を与えると言う。そしてその因果の流れの上の非常に限られた力の分の自由などはほとんど自由の範疇に入るものでもないのに、そこで悪を犯した者に対して「私は自由を与え、汝はその自由によって罪を犯した。これは私の責任ではなくお前の責任なのだ」と罰を要求するなどということは真の正義にかなっていません。適切な教育が施されていないからです。たとえば腹を空かせた肉食獣を草食動物がいる柵の中に入れて、実際に殺して肉食したとして、その草食動物を殺した罪を人間が肉食獣に問うようなものです。ここでも業の報いや自在者の罰としての報いに二つあり、即ち利と楽を結果する苦と不利と苦を結果する苦があることによって恩恵が全うされていないことになります。
もしも絶対者が存在しないのであるならば、力に基づく自由分における意志の行使を原因とする自業自得は理にかなったことです。しかし絶対者が自由を与えたのに、その自由を原因として生じた悪なる結果を絶対者自身が負わずにその造られた者にのみ罪の全てを負わせるのは、実に無慈悲にして悪なる神です。
絶対者を擁護する論理は全てを第一原因なる絶対者に行き着かせます。その論理においては、この世界に存在する一貫性や整合性、その法則や自然界に見られる精妙にして秩序正しい性質、それらは全て絶対者が存在する証拠となってしまいます。そこには論理の飛躍があります。なぜなら、「この世界はその法則や秩序において完璧である。そしてただその事実だけが観測される」で終えても問題はないからです。そこに加えて「この世界を貫く一貫性という意味において世界が完璧であるというのは、絶対者が存在するからだ」というのは論理の飛躍です。
つまり「調べる限り宇宙の法則は完璧であるように思われる。その法則に人格的恣意的な配慮はなく徹底的に無慈悲なまでに透徹した一貫性を持っている」というのは可です。なぜなら実際に宇宙法則に人間的にして人格的な恣意性を見いださないからです。それゆえに無人格的な宇宙法則には人格はないであろうと予期するのは道理です。
しかし「調べる限り宇宙の法則は完璧であるように思われる。これこそ神が実在する証拠だ」というのは不可です。以前も述べたように因果の法則が生じる原因を問うているからです。因果の法則がないとき、そこには因果の法則が見いだされる事象もありません。それなのに、因果の法則を生じさせる神がまずいて、その神を原因として因果の法則は生じたとすれば、因果律を生じさせる前に神は因果に縛られていることになり背理です。またもし「それは因果律や時間的順序が成立する以前の話であり、論理的順序さえも成立する以前の不可思議世界での出来事なのだ」と主張する人がいたとしても、それは自説の擁護のために強引に作り出された見解に過ぎず、理性に反発する極めて不可解な仮説です。
また「宇宙法則と神は同一である」と言ったところで、それは単なる言葉に過ぎません。その神が意味するところは宇宙法則以外の何ものでもないのですから。その「神」という言葉のうちに人格的要素を加味して「宇宙法則と神は同一である」と言っているとすれば、それも背理です。宇宙法則にもこの現実にも人格を誰も見いださないからです。
また「宇宙法則には人格と意志と感情とがある」と言ったところでそれを認めることはできません。これまた極めて無慈悲な現実を見るからです。また「宇宙法則は神である」と言ったところで、「神とは宇宙法則そのものである」という再定義に過ぎず、別名の創作に過ぎなくなってしまいます。「神」という単語の多義性によって問題の本質が曖昧になっているだけの論拠が常住論者には多いです。
人はその感受を伴う心において楽を求め苦を厭いやすい因果連鎖の持ち主です。それゆえに、もしも神がいるならばこの世界は正義と善と美とに溢れているはずだと考えるのが自然な流れです。それを受けて絶対神を信じる人々はこのように疑問を思わざるを得ません。「なぜ世界に悪があるのか」と。「それは絶対神が存在しないからではないだろうか」と返答してあげるのが適切だと思うのですが、彼らにとってその発言・そのアイデア・その発想はタブーです。絶対神に関する否定的発言を絶対神を信じる集団の中ですること、絶対神を信じる集団に依存している自分がそのように発言することは自殺行為だからです。そうであるとすればどれだけ多くの人々と神々が「この身とこの命を惜しむことを原因として自らの見解を自らに設定しているか」ということ、想像に余るところがあります。
いずれにしてもこの「悪がなぜ存在するのか」という問題、これは霊界通信においても高位の天使たちや神々の間でも疑い迷い、議論される重要な問題であると書いてあります。しかしこの「悪の存在理由」という神学の高等教理も、シンプルに「全知全能の至高者がいないから」という仮説を立てれば解決する話です。真実はいつもシンプルだと思うのですが、実際に物事を複雑にしているのは現実に対応しない考えを現実に無理矢理適合させようとするから複雑な神学が出来上がるだけの話なのだと思います。
ただ僕も「絶対に絶対神はいない」とは断言しません。場合によってはいるかも知れないとは思います。しかし、今この現実において物事を洞察し観察するとき、絶対神云々ではなく、これがあるときこれがある、これがないときこれがないという原因と結果の流れ、ただそれだけを見るというだけです。それと絶対神とは関係がないと考えたほうが道理にかない理性が納得すると思うのです。
絶対者を擁護する論理は全てを第一原因なる絶対者に行き着かせます。その論理においては、この世界に存在する一貫性や整合性、その法則や自然界に見られる精妙にして秩序正しい性質、それらは全て絶対者が存在する証拠となってしまいます。そこには論理の飛躍があります。なぜなら、「この世界はその法則や秩序において完璧である。そしてただその事実だけが観測される」で終えても問題はないからです。そこに加えて「この世界を貫く一貫性という意味において世界が完璧であるというのは、絶対者が存在するからだ」というのは論理の飛躍です。
つまり「調べる限り宇宙の法則は完璧であるように思われる。その法則に人格的恣意的な配慮はなく徹底的に無慈悲なまでに透徹した一貫性を持っている」というのは可です。なぜなら実際に宇宙法則に人間的にして人格的な恣意性を見いださないからです。それゆえに無人格的な宇宙法則には人格はないであろうと予期するのは道理です。
しかし「調べる限り宇宙の法則は完璧であるように思われる。これこそ神が実在する証拠だ」というのは不可です。以前も述べたように因果の法則が生じる原因を問うているからです。因果の法則がないとき、そこには因果の法則が見いだされる事象もありません。それなのに、因果の法則を生じさせる神がまずいて、その神を原因として因果の法則は生じたとすれば、因果律を生じさせる前に神は因果に縛られていることになり背理です。またもし「それは因果律や時間的順序が成立する以前の話であり、論理的順序さえも成立する以前の不可思議世界での出来事なのだ」と主張する人がいたとしても、それは自説の擁護のために強引に作り出された見解に過ぎず、理性に反発する極めて不可解な仮説です。
また「宇宙法則と神は同一である」と言ったところで、それは単なる言葉に過ぎません。その神が意味するところは宇宙法則以外の何ものでもないのですから。その「神」という言葉のうちに人格的要素を加味して「宇宙法則と神は同一である」と言っているとすれば、それも背理です。宇宙法則にもこの現実にも人格を誰も見いださないからです。
また「宇宙法則には人格と意志と感情とがある」と言ったところでそれを認めることはできません。これまた極めて無慈悲な現実を見るからです。また「宇宙法則は神である」と言ったところで、「神とは宇宙法則そのものである」という再定義に過ぎず、別名の創作に過ぎなくなってしまいます。「神」という単語の多義性によって問題の本質が曖昧になっているだけの論拠が常住論者には多いです。
人はその感受を伴う心において楽を求め苦を厭いやすい因果連鎖の持ち主です。それゆえに、もしも神がいるならばこの世界は正義と善と美とに溢れているはずだと考えるのが自然な流れです。それを受けて絶対神を信じる人々はこのように疑問を思わざるを得ません。「なぜ世界に悪があるのか」と。「それは絶対神が存在しないからではないだろうか」と返答してあげるのが適切だと思うのですが、彼らにとってその発言・そのアイデア・その発想はタブーです。絶対神に関する否定的発言を絶対神を信じる集団の中ですること、絶対神を信じる集団に依存している自分がそのように発言することは自殺行為だからです。そうであるとすればどれだけ多くの人々と神々が「この身とこの命を惜しむことを原因として自らの見解を自らに設定しているか」ということ、想像に余るところがあります。
いずれにしてもこの「悪がなぜ存在するのか」という問題、これは霊界通信においても高位の天使たちや神々の間でも疑い迷い、議論される重要な問題であると書いてあります。しかしこの「悪の存在理由」という神学の高等教理も、シンプルに「全知全能の至高者がいないから」という仮説を立てれば解決する話です。真実はいつもシンプルだと思うのですが、実際に物事を複雑にしているのは現実に対応しない考えを現実に無理矢理適合させようとするから複雑な神学が出来上がるだけの話なのだと思います。
ただ僕も「絶対に絶対神はいない」とは断言しません。場合によってはいるかも知れないとは思います。しかし、今この現実において物事を洞察し観察するとき、絶対神云々ではなく、これがあるときこれがある、これがないときこれがないという原因と結果の流れ、ただそれだけを見るというだけです。それと絶対神とは関係がないと考えたほうが道理にかない理性が納得すると思うのです。
wikipediaの「神の存在証明」の項目などを少し読みました。先に書いたことは目的論的証明や宇宙論的証明に相当するようです。
原始仏教では「諸法は因より生ず」、何事も原因があって生じるとしています。律蔵から引用します。
「時に遊行者サーリプッタは尊者アッサジに言った。
「それならば、少しでもいいから説いてください。ただ意義だけを説いて下さい。私が求めるところはただ意義のみです。多くの言葉があってもどうしましょう」。
時に尊者アッサジは遊行者サーリプッタにこの法門を説いた。
もろもろの法は原因があって生じる
如来はその原因を説く
もろもろの法の滅をもまた
大沙門はこのように説く
時に遊行者サーリプッタはこの法門を聞いて遠塵離垢の法眼を得た。
「集法を有するものはすべてこれ、滅法を有する」
「もしただこれだけであるとしても、これは正しく法です。あなたたちはすでに憂いなきところを悟っています。数万の劫の中にも見ないところです」 」
・律蔵「ゴータマ伝6」 サーリプッタとモッガーラナ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25524830&comm_id=951429
サーリプッタはこの詩を聞いただけで法眼、ダンマチャックを得ました。全てに因ありと言うならば、苦にも因がありその因が滅すれば苦は滅する。また輪廻にも因がありその因が滅すれば輪廻も滅する。それが苦滅であり不死であるとサーリプッタは一を知って十を知ったのだと思います。
そして後はその因が自らの正しい努力を原因として滅するものであるのかどうか確認すればそれで道は得たと言えます。そして苦因にして輪廻の因である執着は執着対象への無常・苦・無我他の如実知見・正知がある分は滅する、即ち無明の滅に連鎖して執着の滅があると見るがゆえに、正精進による苦滅も死の超克も可能であると知る、そういう流れであると思います。
話を戻して「諸法は因より生ず」、しかしこの全世界全宇宙界、それらの第一原因の有無の決め手となる時間が有限か無限か、空間が有限か無限かという問題に対してゴータマは無記を決め込んでいます。なぜ説かないのかというその理由は有名な毒矢のたとえです。中部経典第63経です。さわりだけ紹介します。
「マールンキャ・プッタよ、毒矢に刺さった者がいてこう言うとする。
「私に刺さったこの毒矢を放ったのが誰か知るまでは治療してくれるな。あとその者の名字と名前も。あと肌の色とか住んでるところとか弓の材料とか他にも色々。それら全部を知るまでは治療してくれるな」
「そんなの関係ない。治療させなさい」
「嫌だ」
そして彼は死ぬ。
マールンキャ・プッタよ、あなたはこう言っている。
「この宇宙が時間的に永遠か無常か、空間的に無限か有限かを先生が教えてくれるまで私は修行しません」
「私はそれを説かない」
「嫌です。それならば修行しません」
そうしてマールンキャ・プッタ、あなたは死ぬ。
これらの見解と関係なく苦はありその苦を滅するための修行がある。
私が説かないことは説かないままに覚えておき、説いたことは説いたこととして覚えておき、正しく苦を滅するために修行しなさい。」
という話です。神の存在証明もそれと同じです。もしマールンキャ・プッタのような人がいるとすればこう言うかも知れません。「神の存在証明を終えるまでは自分の苦しみをなくす修行なんてしたくありません」。そして彼は神の存在を証明し続けて途中で死にます。それもまた本人の自由です。
原始仏教では「諸法は因より生ず」、何事も原因があって生じるとしています。律蔵から引用します。
「時に遊行者サーリプッタは尊者アッサジに言った。
「それならば、少しでもいいから説いてください。ただ意義だけを説いて下さい。私が求めるところはただ意義のみです。多くの言葉があってもどうしましょう」。
時に尊者アッサジは遊行者サーリプッタにこの法門を説いた。
もろもろの法は原因があって生じる
如来はその原因を説く
もろもろの法の滅をもまた
大沙門はこのように説く
時に遊行者サーリプッタはこの法門を聞いて遠塵離垢の法眼を得た。
「集法を有するものはすべてこれ、滅法を有する」
「もしただこれだけであるとしても、これは正しく法です。あなたたちはすでに憂いなきところを悟っています。数万の劫の中にも見ないところです」 」
・律蔵「ゴータマ伝6」 サーリプッタとモッガーラナ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25524830&comm_id=951429
サーリプッタはこの詩を聞いただけで法眼、ダンマチャックを得ました。全てに因ありと言うならば、苦にも因がありその因が滅すれば苦は滅する。また輪廻にも因がありその因が滅すれば輪廻も滅する。それが苦滅であり不死であるとサーリプッタは一を知って十を知ったのだと思います。
そして後はその因が自らの正しい努力を原因として滅するものであるのかどうか確認すればそれで道は得たと言えます。そして苦因にして輪廻の因である執着は執着対象への無常・苦・無我他の如実知見・正知がある分は滅する、即ち無明の滅に連鎖して執着の滅があると見るがゆえに、正精進による苦滅も死の超克も可能であると知る、そういう流れであると思います。
話を戻して「諸法は因より生ず」、しかしこの全世界全宇宙界、それらの第一原因の有無の決め手となる時間が有限か無限か、空間が有限か無限かという問題に対してゴータマは無記を決め込んでいます。なぜ説かないのかというその理由は有名な毒矢のたとえです。中部経典第63経です。さわりだけ紹介します。
「マールンキャ・プッタよ、毒矢に刺さった者がいてこう言うとする。
「私に刺さったこの毒矢を放ったのが誰か知るまでは治療してくれるな。あとその者の名字と名前も。あと肌の色とか住んでるところとか弓の材料とか他にも色々。それら全部を知るまでは治療してくれるな」
「そんなの関係ない。治療させなさい」
「嫌だ」
そして彼は死ぬ。
マールンキャ・プッタよ、あなたはこう言っている。
「この宇宙が時間的に永遠か無常か、空間的に無限か有限かを先生が教えてくれるまで私は修行しません」
「私はそれを説かない」
「嫌です。それならば修行しません」
そうしてマールンキャ・プッタ、あなたは死ぬ。
これらの見解と関係なく苦はありその苦を滅するための修行がある。
私が説かないことは説かないままに覚えておき、説いたことは説いたこととして覚えておき、正しく苦を滅するために修行しなさい。」
という話です。神の存在証明もそれと同じです。もしマールンキャ・プッタのような人がいるとすればこう言うかも知れません。「神の存在証明を終えるまでは自分の苦しみをなくす修行なんてしたくありません」。そして彼は神の存在を証明し続けて途中で死にます。それもまた本人の自由です。
しかし今ここに苦があってその苦を滅するための修行が今ここで自分でできる、そのとき神も時空の有限無限も関係ない、ならば苦滅のために修行をしたほうが利益があります。
たとえば、これも原始仏典でゴータマが出しているたとえ話ですが、好きな人がいて自分以外の人とその人が楽しく喋っていて自分はそれを見て嫉妬で苦しむとする。そのとき嫉妬で苦しむ人は「あの人が好きだから今苦しい。だからこの思いを捨てよう」と努力し念じて捨にいたって楽になる。こういう話です。このとき絶対神の介在などを確認することはありません。自分で努力して一つの苦は滅したわけです。
この論理で全ての執着対象に同様の捨を修習するとします。「何かに執着していればそれが変化したりなくなったときに心が苦しい。それならば全世界のあらゆるものへの執着、自分自身の心と身体への執着、そして執着を捨てることへの執着も含めて、全部の執着を完全に捨てよう」と努力し念じて実際に捨てるとします。
そのときは何がどう変化しても「こうなったか」ぐらいなのだと思います。もちろん不愉快なことを言われれば不愉快であり、身体が傷つけば痛いですが「身体があるまでの話だ」と思うのだと思います。そして執着がないので執着がない心は再度獲得する身体がないとされます。先に心が憂いなき境地に達して、後で死ぬことによって身体の煩いもなくなって完全に涅槃します。その後の不死界がどうなっているかは謎にして無記です。
これら一連の流れの中にはただ自分の努力だけがあり、絶対神からの干渉はありません。修行を邪魔するマーラはいるかも知れませんが。
この論理を援用することによって「絶対神がいないことを証明することはできない」という悪魔の証明のような論理を排除することができます。即ち「現に苦があり、現に自分の努力を原因としてこの苦を滅することができる。その苦から苦滅への一連の流れへの超越的干渉を見ない今、神の存在証明に関する論議・探求・努力に時間と労力を費やす利益は極めて軽微である。一方で現に可能であると考えられる苦滅のために時間と労力を費やすことは大利である。ゆえに神の存在証明を捨てて苦滅道の実践を取る」と言うことができます。このような論理を「苦滅の優先性」「人間における苦滅の最優先性」と名付けてもよいと思います。
また人体の精巧さや太陽系の機構などをもって「これに設計者が存在しないわけがない。その設計者、建築者、アーキテクトが即ち神である」とする論理があります。これにはこのように言えます。
「人体や太陽系や銀河系を設計し作り出した存在者がいることはあり得る。しかし同時にそのような存在は無数にいてもおかしくはない。ゆえに彼らは絶対神ではない。即ちそれぞれの銀河創造主は絶対神ではない。生じて滅する宇宙内存在であるとするほうが道理にかなう。そして銀河を創造することと全宇宙を創造することとはまったく異なる。全宇宙を創造したり宇宙法則を設定することと、宇宙内存在者が宇宙の一部分である銀河などを創造することを同義として扱うことはできない。ゆえに宇宙の一部分的な設計者をもって神にすることはできない。それは言ってみれば、『この大教会を設計し建築したのは私である。ゆえに私は神である』と主張することに等しい。そこには一部の因果連鎖の操作をもって因果律自体の設定者とみなす異なる問題の混同がある。太陽系を作った者を絶対神であるとする論理はこれと同じことを別の文章で言っていることになる」
また別の論理を持ち出す人がいるかも知れません。「美徳ある善人はただ美徳ある善人であるだけでなく、幸福と快楽もその美徳によって獲得しなければ不十分である。その道徳に従い善と徳ある者が幸福であるためには必然的に神が必要であり、神によりその美徳と快楽の比例関係は保証される」とする論理です。これに対してはこのように言えます。
「業の報いという法則があり、ある存在者が善であれ悪であれ何であれ他者に与えた影響を後になって形を変えるが完全な整合性のもとにその本人は相続するとする。作用反作用の法則になぞらえられるかの法則である。この業の報いという法則があるならば、善人の幸福を保証するための絶対神は不要となる。そして絶対神により善人の幸福が保証されるという論理よりも、業の報いという無慈悲な法則によって一切業に相続性を付与するほうがより一層合理的にして整合的である。ゆえに超越的人格存在によって善人の幸福が保証されるとする仮説のほうが不十分である」と言えます。
たとえば、これも原始仏典でゴータマが出しているたとえ話ですが、好きな人がいて自分以外の人とその人が楽しく喋っていて自分はそれを見て嫉妬で苦しむとする。そのとき嫉妬で苦しむ人は「あの人が好きだから今苦しい。だからこの思いを捨てよう」と努力し念じて捨にいたって楽になる。こういう話です。このとき絶対神の介在などを確認することはありません。自分で努力して一つの苦は滅したわけです。
この論理で全ての執着対象に同様の捨を修習するとします。「何かに執着していればそれが変化したりなくなったときに心が苦しい。それならば全世界のあらゆるものへの執着、自分自身の心と身体への執着、そして執着を捨てることへの執着も含めて、全部の執着を完全に捨てよう」と努力し念じて実際に捨てるとします。
そのときは何がどう変化しても「こうなったか」ぐらいなのだと思います。もちろん不愉快なことを言われれば不愉快であり、身体が傷つけば痛いですが「身体があるまでの話だ」と思うのだと思います。そして執着がないので執着がない心は再度獲得する身体がないとされます。先に心が憂いなき境地に達して、後で死ぬことによって身体の煩いもなくなって完全に涅槃します。その後の不死界がどうなっているかは謎にして無記です。
これら一連の流れの中にはただ自分の努力だけがあり、絶対神からの干渉はありません。修行を邪魔するマーラはいるかも知れませんが。
この論理を援用することによって「絶対神がいないことを証明することはできない」という悪魔の証明のような論理を排除することができます。即ち「現に苦があり、現に自分の努力を原因としてこの苦を滅することができる。その苦から苦滅への一連の流れへの超越的干渉を見ない今、神の存在証明に関する論議・探求・努力に時間と労力を費やす利益は極めて軽微である。一方で現に可能であると考えられる苦滅のために時間と労力を費やすことは大利である。ゆえに神の存在証明を捨てて苦滅道の実践を取る」と言うことができます。このような論理を「苦滅の優先性」「人間における苦滅の最優先性」と名付けてもよいと思います。
また人体の精巧さや太陽系の機構などをもって「これに設計者が存在しないわけがない。その設計者、建築者、アーキテクトが即ち神である」とする論理があります。これにはこのように言えます。
「人体や太陽系や銀河系を設計し作り出した存在者がいることはあり得る。しかし同時にそのような存在は無数にいてもおかしくはない。ゆえに彼らは絶対神ではない。即ちそれぞれの銀河創造主は絶対神ではない。生じて滅する宇宙内存在であるとするほうが道理にかなう。そして銀河を創造することと全宇宙を創造することとはまったく異なる。全宇宙を創造したり宇宙法則を設定することと、宇宙内存在者が宇宙の一部分である銀河などを創造することを同義として扱うことはできない。ゆえに宇宙の一部分的な設計者をもって神にすることはできない。それは言ってみれば、『この大教会を設計し建築したのは私である。ゆえに私は神である』と主張することに等しい。そこには一部の因果連鎖の操作をもって因果律自体の設定者とみなす異なる問題の混同がある。太陽系を作った者を絶対神であるとする論理はこれと同じことを別の文章で言っていることになる」
また別の論理を持ち出す人がいるかも知れません。「美徳ある善人はただ美徳ある善人であるだけでなく、幸福と快楽もその美徳によって獲得しなければ不十分である。その道徳に従い善と徳ある者が幸福であるためには必然的に神が必要であり、神によりその美徳と快楽の比例関係は保証される」とする論理です。これに対してはこのように言えます。
「業の報いという法則があり、ある存在者が善であれ悪であれ何であれ他者に与えた影響を後になって形を変えるが完全な整合性のもとにその本人は相続するとする。作用反作用の法則になぞらえられるかの法則である。この業の報いという法則があるならば、善人の幸福を保証するための絶対神は不要となる。そして絶対神により善人の幸福が保証されるという論理よりも、業の報いという無慈悲な法則によって一切業に相続性を付与するほうがより一層合理的にして整合的である。ゆえに超越的人格存在によって善人の幸福が保証されるとする仮説のほうが不十分である」と言えます。
哲学者たちや神学者たちは様々な仮説を立てて最後の結論は常に「ゆえに神は存在する」で締めて来ました。しかし最初に結論ありきの求道はもはや求道にあらずと言えます。その最初の結論にして前提は自分の生活を支えてくれるスポンサーによって決まるものです。人は自分の生計と名誉の源泉に対して非常に弱い生き物です。人間だけでなく神々でさえも自分よりもさらに上の神々の意向に弱い生き物であると、霊界通信を読む限りはそのように類推されます。「深く突っ込んで問うな」という記述はよく見られます。
人は自分の生計と名誉の維持のためなら邪見になってでも、邪語になってでも雇い主の言う通りに働きます。そしてその繰り返しによりそういう思考回路が堅く明確に形成され、抜け出せなくなります。保身という自らの身体と命を惜しみ五欲を惜しむその執着の分だけ、求道は困難となり五蓋は厚くなり物事が見えず正しい道理を聞くことを厭うようになります。本人にもどうしようもない因果連鎖です。その顕著な結果が東西の様々な煩瑣宗学です。
こういった哲学的な議論と、教会や寺院で祀られている霊的存在・神的存在は別だと僕は思っています。日本のお寺で祀られている諸仏諸尊が大乗経典の奥義をマスターしているとは僕には思えません。僕は超常の力はないので類推ですが、如来が鎮護国家とか現世利益とか違うと思うのです。教会もマリア様ですから実際聖書と関係ないです。それで大概の宗教施設とその宗教思想の真髄との連絡は極めて適当なものであると思っています。だからある宗教施設に出入りすることを原因として自分の利益が増え、不利益が減るのであれば可であると思っています。出入りすることによって不利益が増大する建物への出入りは推奨しませんが、その判断がなかなかに難しいとは思います。
実際の宗教組織と教義上の内容に乖離があることから、教会や寺院や神社の建築様式や祭祀様式を評して、「この象徴はこれこれ。この霊的影響を考慮した作りはこれこれ。この儀式にはこのような影響が見られる。これらからこの宗教の本当の教えが知られる云々」と言います。教義よりも建築や祭祀、伝統を重要視する向きです。こういった研究ももちろん非常に大切で利益があると思います。多分、神々や精霊の顕現がそのような装置や儀礼により促進され、利益ある影響力をより効果的に行使することができるようになるのだと思います。いずれにしても教義と実際を双方から研究するに越したことはありません。
しかし美徳の輝きを幾分知った者が、自己をより善なるものへと再構築する自己錬磨の修行よりも外界の建築物や所作を伴う儀式などをより重要視するということはあり得ません。宗教施設に神はいるかも知れません。あるいはその施設に降りてきたり昇ったりしているかも知れません。しかし神々の美徳、神の心を獲得した者こそがすでに神であると考えます。転生時における身体の獲得はその心の状態に対応すると見るならばそうなります。そしてその上に漏尽の阿羅漢、不死者にして聖者の称号があるわけです。もちろん恩義ある非人や神々には礼儀として年々歳々挨拶には出向きます。しかしいたずらに彼らにへつらい、自らを貶めるわけでもありません。かつて小さかった者が今は大いなる者となる。それゆえに原始仏教のテーマの一つに「神々を越えて」というものがあります。「天の寿命を恥じよ。天の容姿を恥じよ。天の楽を恥じよ。(お前たちは解脱せよ)」という立場です。『南伝』の増支部経典1巻に書いてあります。
人は自分の生計と名誉の維持のためなら邪見になってでも、邪語になってでも雇い主の言う通りに働きます。そしてその繰り返しによりそういう思考回路が堅く明確に形成され、抜け出せなくなります。保身という自らの身体と命を惜しみ五欲を惜しむその執着の分だけ、求道は困難となり五蓋は厚くなり物事が見えず正しい道理を聞くことを厭うようになります。本人にもどうしようもない因果連鎖です。その顕著な結果が東西の様々な煩瑣宗学です。
こういった哲学的な議論と、教会や寺院で祀られている霊的存在・神的存在は別だと僕は思っています。日本のお寺で祀られている諸仏諸尊が大乗経典の奥義をマスターしているとは僕には思えません。僕は超常の力はないので類推ですが、如来が鎮護国家とか現世利益とか違うと思うのです。教会もマリア様ですから実際聖書と関係ないです。それで大概の宗教施設とその宗教思想の真髄との連絡は極めて適当なものであると思っています。だからある宗教施設に出入りすることを原因として自分の利益が増え、不利益が減るのであれば可であると思っています。出入りすることによって不利益が増大する建物への出入りは推奨しませんが、その判断がなかなかに難しいとは思います。
実際の宗教組織と教義上の内容に乖離があることから、教会や寺院や神社の建築様式や祭祀様式を評して、「この象徴はこれこれ。この霊的影響を考慮した作りはこれこれ。この儀式にはこのような影響が見られる。これらからこの宗教の本当の教えが知られる云々」と言います。教義よりも建築や祭祀、伝統を重要視する向きです。こういった研究ももちろん非常に大切で利益があると思います。多分、神々や精霊の顕現がそのような装置や儀礼により促進され、利益ある影響力をより効果的に行使することができるようになるのだと思います。いずれにしても教義と実際を双方から研究するに越したことはありません。
しかし美徳の輝きを幾分知った者が、自己をより善なるものへと再構築する自己錬磨の修行よりも外界の建築物や所作を伴う儀式などをより重要視するということはあり得ません。宗教施設に神はいるかも知れません。あるいはその施設に降りてきたり昇ったりしているかも知れません。しかし神々の美徳、神の心を獲得した者こそがすでに神であると考えます。転生時における身体の獲得はその心の状態に対応すると見るならばそうなります。そしてその上に漏尽の阿羅漢、不死者にして聖者の称号があるわけです。もちろん恩義ある非人や神々には礼儀として年々歳々挨拶には出向きます。しかしいたずらに彼らにへつらい、自らを貶めるわけでもありません。かつて小さかった者が今は大いなる者となる。それゆえに原始仏教のテーマの一つに「神々を越えて」というものがあります。「天の寿命を恥じよ。天の容姿を恥じよ。天の楽を恥じよ。(お前たちは解脱せよ)」という立場です。『南伝』の増支部経典1巻に書いてあります。
超常の力がない限りの、類推によって到達し得る限りの限界まで類推することによって少しでもより堅実な道が取れるようになるものであると僕は考えています。「謎は全て解けた」と名探偵が宣言したら、トリックの真相と真犯人を明らかにします。自分が類推した仮説はすべからく自分自身の手によって実証されなければなりません。実際に自分で努力して力を獲得していつもの自分の生活を本当に変えるということです。もちろん類推の力だけでなく超常の力も獲得するに越したことはないと思います。五感による情報だけでなく超常の知覚を得て、しかも最高の推理力を得るならば、自分の気に入らないことを減らしていくことにより資すると考えるからです。
まず知って実証は後です。推理してから検証します。「法住知は先にして涅槃知は後である」(法住知 dhamma ṭhiti ñāṇa。涅槃知 nibbāne ñāṇa。南伝13 P180)と書いてある通りです。訓練法を知ってから、後に実際に訓練によって力を得るのと同義だと思います。
それぞれの人が持つ見解と意見には必ずそれが生じた原因があります。大多数の人は雇い主という「人間の意見」を自らの意見の原因としており、真実の探求に向けられた六根のフル稼働を原因としていないことが多いです。多くの人には求道する理由も動機もないからです。翻って今一度自分の意見と見解がなぜこうなったのかという原因を訪ねるときは、さらに自分の枠を破って利益ある見解にも思いにも発言にも達することができると思います。求道と修行とは短期間のうちに自らの人格を善なる方向へと劇的に改変するところにその成果が求められるべきであると思うからです。
まず知って実証は後です。推理してから検証します。「法住知は先にして涅槃知は後である」(法住知 dhamma ṭhiti ñāṇa。涅槃知 nibbāne ñāṇa。南伝13 P180)と書いてある通りです。訓練法を知ってから、後に実際に訓練によって力を得るのと同義だと思います。
それぞれの人が持つ見解と意見には必ずそれが生じた原因があります。大多数の人は雇い主という「人間の意見」を自らの意見の原因としており、真実の探求に向けられた六根のフル稼働を原因としていないことが多いです。多くの人には求道する理由も動機もないからです。翻って今一度自分の意見と見解がなぜこうなったのかという原因を訪ねるときは、さらに自分の枠を破って利益ある見解にも思いにも発言にも達することができると思います。求道と修行とは短期間のうちに自らの人格を善なる方向へと劇的に改変するところにその成果が求められるべきであると思うからです。
「神々を越えて」に関連する原始仏典の記述を原始仏典コミュニティのほうに書きました。以下です。法住知と涅槃知の記述は「五神通なくても阿羅漢になれるのか。なれる慧解脱だから」という重要なテーマを扱っていて、それは因縁相応に書いてあるのですが少し長いのでまた別の機会にしたいと思います。
(『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P186−187 に相当)
増支部経典一集>第二 車匠品
「 第八 天世
18.比丘たちよ、もしあなたたちに他(の教え)に住する者である遍歴者たちがこのように問うとする。
「友よ、神々の世界に生まれるために沙門ゴータマの梵行に住しているのか」と。
比丘たちよ、あなたたちはこのように問われて愧ずかしくないか。慚ずかしくないか。厭わないのか。
そうです(恥ずかしいです)、先生。
比丘たちよ、このように実にあなたたちは神の寿命を愧じ慚じ厭いなさい。
神の容姿を愧じ慚じ厭いなさい。
神の楽を愧じ慚じ厭いなさい。
神の名誉を愧じ慚じ厭いなさい。
神の権能を愧じ慚じ厭いなさい。
ましてや比丘たちよ、なおさらあなたたちは身悪行を愧じ慚じ厭いなさい。
語悪行を愧じ慚じ厭いなさい。
意悪行を愧じ慚じ厭いなさい。」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P186−187 に相当
(『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P186−187 に相当)
増支部経典一集>第二 車匠品
「 第八 天世
18.比丘たちよ、もしあなたたちに他(の教え)に住する者である遍歴者たちがこのように問うとする。
「友よ、神々の世界に生まれるために沙門ゴータマの梵行に住しているのか」と。
比丘たちよ、あなたたちはこのように問われて愧ずかしくないか。慚ずかしくないか。厭わないのか。
そうです(恥ずかしいです)、先生。
比丘たちよ、このように実にあなたたちは神の寿命を愧じ慚じ厭いなさい。
神の容姿を愧じ慚じ厭いなさい。
神の楽を愧じ慚じ厭いなさい。
神の名誉を愧じ慚じ厭いなさい。
神の権能を愧じ慚じ厭いなさい。
ましてや比丘たちよ、なおさらあなたたちは身悪行を愧じ慚じ厭いなさい。
語悪行を愧じ慚じ厭いなさい。
意悪行を愧じ慚じ厭いなさい。」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P186−187 に相当
念のために古い神学者の方々を擁護しますが、極論にして根本問題である「神の存在証明」については僕は以上のような見解を持っていますが、これをもって彼らや彼らと同様の見解を持つ人々を全否定しているわけではありません。僕はキリスト教圏やイスラム教圏の、特に古代や中世の神学者の人たちにはその誠実さや探求心などの善法において好意を持っているからです。
それぞれの見解についての諸論とその見解の保持者たちへの評価とはまた別の問題であると思っています。また各人への評価が仮に悪いものであっても優しさや哀れむべき対象から外すべきだとも考えません。預流以上の人々は最上の福の田んぼだと思いますが、原始仏教以外の見解を持つ人々もまた福の田んぼであると考えるからです。基本的に全宇宙は広大な田んぼであると思います。悪業の種を蒔けば毒麦と害虫にたとえられる苦の報いが発生するとは思いますが、世界は自らの業を増大させるものであることには違いありません。
同様に今日の唯一神教を奉じる人々の信・勤・念・定・慧が全て無駄であるとは考えていません。それぞれの人にはそれぞれの善法と悪法があり、一概に判断されるべきではないと考えるからです。宗派の教義への評価と、実際にその宗派に所属している人々個人への評価は混同されるべきではないと考えています。各個人で俗なる信勤念定慧に大いに相違があるからです。取り上げるべきは個々人への評価ではなく、より重要で根本的であると思われる問題に関しての真実を探求し検証することであると思っています。サーリプッタもよく異学の者たちのところへ行っていました。
同様に「この人は原始仏教への信も勤も念定慧もないから駄目だ」と思うべきではないと思います。その人にはただ原始仏教や苦滅などよりも優先している何かがあり、そうすることになる原因が内にあるのだと思います。またそれはその人の自由でもあります。またその人には必ず何らかの善法もあるはずです。というのも、もしその人が悪法一色ならば速やかにデーヴァダッタのように破滅しているでしょうから。生きているかぎりは誰でも何かしら長所があり、その善法にもとづく三行によって何らか利益を世間に与え、その利益の流れを自分は部分的に享受していると思えばいたずらに見解が違うというだけで人を敵対視することは利益になりません。また自分も原始仏教の奥義をその身に体現したわけではないので、場合によってはそうかも知れないとも思い、より修行に精を出す原因にもできます。
僕は本当に役に立たない人間や世間に害悪しか垂れ流さない人というのは世間にはほとんどいないと思っています。実際嫌がらせをされれば僕もその人のことを嫌いになり距離を取りますが、嫌って距離を取ってもその人の存在を全否定するわけではありません。ただこちらに不利益が生じるから距離を取り言路を閉ざすだけであり、その人を全否定しないのは現にその人が存在し現に因果連鎖の一鎖である事実があるのに部分を取って全体に及ぼす全否定は正見からの逸脱となり、自分にも相手にも不利益な邪思となるであろうと思ってのことです。真実を尊重する人であるならば、性格が悪い人を嫌っても避けても、性格が悪いその人は確かに存在するという真実だけは尊重するはずです。
それぞれの人にはそれぞれの原因があって今現にこうなっていると思えば、他者への早急な判断を保留しておくことができます。また実際にその他者のことは多く知らないからです。焦らず地道にその人とその人がそうなった原因を念じて考察していくと生じる知見があると思います。外の心念処に近い修習になると思います。
考え方が違う者同士であっても互いに傷付けない範囲で、且つ互いに利益が生じる関係を構築することは可能であると思います。「利害の一致」まで距離を取り、そこに住しつつ利害の一致の増大をじっくりと計っていく形になると思います。惑星の公転軌道のような付かず離れずの関係がベストだと思います。周期的に会える彗星や一度限りで二度と会うことがないような彗星のような人間関係も含めて。衝突にたとえられる有害行為を聖者は称賛しないと思います。
互いを傷付けない範囲まで距離を取ることとその無害範囲の中でさらに相手との付き合いから利益を引き出すことは難しいですが、念頭においておくとこの能力もゆっくりと日々向上していくのではないかと思います。利益が増大する距離と不利益が増大する距離について日頃から念じるとよいかも知れません。人間関係の技術は原始仏教以外からでも色々学べますので、その上で慈心などを併用すると強いと思います。
それぞれの見解についての諸論とその見解の保持者たちへの評価とはまた別の問題であると思っています。また各人への評価が仮に悪いものであっても優しさや哀れむべき対象から外すべきだとも考えません。預流以上の人々は最上の福の田んぼだと思いますが、原始仏教以外の見解を持つ人々もまた福の田んぼであると考えるからです。基本的に全宇宙は広大な田んぼであると思います。悪業の種を蒔けば毒麦と害虫にたとえられる苦の報いが発生するとは思いますが、世界は自らの業を増大させるものであることには違いありません。
同様に今日の唯一神教を奉じる人々の信・勤・念・定・慧が全て無駄であるとは考えていません。それぞれの人にはそれぞれの善法と悪法があり、一概に判断されるべきではないと考えるからです。宗派の教義への評価と、実際にその宗派に所属している人々個人への評価は混同されるべきではないと考えています。各個人で俗なる信勤念定慧に大いに相違があるからです。取り上げるべきは個々人への評価ではなく、より重要で根本的であると思われる問題に関しての真実を探求し検証することであると思っています。サーリプッタもよく異学の者たちのところへ行っていました。
同様に「この人は原始仏教への信も勤も念定慧もないから駄目だ」と思うべきではないと思います。その人にはただ原始仏教や苦滅などよりも優先している何かがあり、そうすることになる原因が内にあるのだと思います。またそれはその人の自由でもあります。またその人には必ず何らかの善法もあるはずです。というのも、もしその人が悪法一色ならば速やかにデーヴァダッタのように破滅しているでしょうから。生きているかぎりは誰でも何かしら長所があり、その善法にもとづく三行によって何らか利益を世間に与え、その利益の流れを自分は部分的に享受していると思えばいたずらに見解が違うというだけで人を敵対視することは利益になりません。また自分も原始仏教の奥義をその身に体現したわけではないので、場合によってはそうかも知れないとも思い、より修行に精を出す原因にもできます。
僕は本当に役に立たない人間や世間に害悪しか垂れ流さない人というのは世間にはほとんどいないと思っています。実際嫌がらせをされれば僕もその人のことを嫌いになり距離を取りますが、嫌って距離を取ってもその人の存在を全否定するわけではありません。ただこちらに不利益が生じるから距離を取り言路を閉ざすだけであり、その人を全否定しないのは現にその人が存在し現に因果連鎖の一鎖である事実があるのに部分を取って全体に及ぼす全否定は正見からの逸脱となり、自分にも相手にも不利益な邪思となるであろうと思ってのことです。真実を尊重する人であるならば、性格が悪い人を嫌っても避けても、性格が悪いその人は確かに存在するという真実だけは尊重するはずです。
それぞれの人にはそれぞれの原因があって今現にこうなっていると思えば、他者への早急な判断を保留しておくことができます。また実際にその他者のことは多く知らないからです。焦らず地道にその人とその人がそうなった原因を念じて考察していくと生じる知見があると思います。外の心念処に近い修習になると思います。
考え方が違う者同士であっても互いに傷付けない範囲で、且つ互いに利益が生じる関係を構築することは可能であると思います。「利害の一致」まで距離を取り、そこに住しつつ利害の一致の増大をじっくりと計っていく形になると思います。惑星の公転軌道のような付かず離れずの関係がベストだと思います。周期的に会える彗星や一度限りで二度と会うことがないような彗星のような人間関係も含めて。衝突にたとえられる有害行為を聖者は称賛しないと思います。
互いを傷付けない範囲まで距離を取ることとその無害範囲の中でさらに相手との付き合いから利益を引き出すことは難しいですが、念頭においておくとこの能力もゆっくりと日々向上していくのではないかと思います。利益が増大する距離と不利益が増大する距離について日頃から念じるとよいかも知れません。人間関係の技術は原始仏教以外からでも色々学べますので、その上で慈心などを併用すると強いと思います。
自分の生き方を変えてしまうような考え方を学ぶ際は非常に慎重にならなければならないという思いを今回の件(戒禁取)でより一層強くしました。
誰にとってもまずは「今の自分の考え方」が不完全ですが慣れたものとしてあります。しかし新しい経験や外からの情報がその今の自分の考え方で咀嚼し切れない場合があります。このとき葛藤や悩み、疑蓋が生じます。それはとても自然で必然的なことです。
問題は、その戦いの末に生じた自分の新しい考え方が良いものなのか悪いものなのか、邪見か正見か、利益を生み出すものなのか不利益を生み出すものなのかです。原始仏教も含めて、書店に並ぶ精神世界書籍から一般の雑誌の類いの考え方も含めて、テレビ・ラジオ・ネットも含めて、家族友人から吹き込まれる考えも含めて、「その考え方を原因として何が結果するか」です。
結局、検証が必要になります。あらゆるアイデアは検証されない限りは良いものかも知れず、悪いものかも知れず、一部良く一部悪いものかも知れません。それらアイデア、考え方、生き方の試金石として最も重要なものが「自分自身による実験と観察」であると繰り返し書いてきました。
しかし実験に疲れて苦悩が増すということもあります。時間と資金が足りなかったり、実験成果が出る前に不安に押しつぶされてしまいそうになることもあります。そこで取り急ぎ精神の安定を図るために、とりあえずの暫定的ではあるが堅実な見解を確保するために僕が取る手段が「自分の過去の経験の想起」です。
現在検証中の仮説も含めて、もう一度自分の人生の全記憶を思い出せる限り思い出してみて、「実際どうだったのか」と今の悩み事などと摺り合わせてみます。そうすると「今の自分の考え方」になってきた由来とともに、「とりあえずこれは事実だ」という足場を得ます。自分の実体験の記憶とはかくも頼もしいものであると思います。しかし人間の経験が選択されなかった選択肢の行く末においてまで、円満するということはありません。「もし」を予測しても予測して切れません。従って常に自分の実体験は情報不足の面があります。しかし経験分の事実は足場を確保されます。その足場に立って、新たなる見解の境地を求めることができます。
今日、冬至のこの日に僕は原始仏教という考えの枠組みを外した上で、もう一度自分の今までの人生の流れと実体験の連続の事実を思い出し考え直してみて、再度今後の目標を「原始仏教の理想とは関係なく」自分の心に建立することができたような気がします。「原始仏教は関係ない。今まで生きて来た自分として、それでもこれを欲する」という感じです。
ですからこれを読んでおられる方も「自分の今までの人生における経験というものは確かに不十分なものではあるが、しかしこれを経験したという事実は確かに事実であるのだからそれを尊重して反省し直しつつ、その経験に立って新しい何かを求めていこう」と考えるのは利益が多いと思います。
誰にとってもまずは「今の自分の考え方」が不完全ですが慣れたものとしてあります。しかし新しい経験や外からの情報がその今の自分の考え方で咀嚼し切れない場合があります。このとき葛藤や悩み、疑蓋が生じます。それはとても自然で必然的なことです。
問題は、その戦いの末に生じた自分の新しい考え方が良いものなのか悪いものなのか、邪見か正見か、利益を生み出すものなのか不利益を生み出すものなのかです。原始仏教も含めて、書店に並ぶ精神世界書籍から一般の雑誌の類いの考え方も含めて、テレビ・ラジオ・ネットも含めて、家族友人から吹き込まれる考えも含めて、「その考え方を原因として何が結果するか」です。
結局、検証が必要になります。あらゆるアイデアは検証されない限りは良いものかも知れず、悪いものかも知れず、一部良く一部悪いものかも知れません。それらアイデア、考え方、生き方の試金石として最も重要なものが「自分自身による実験と観察」であると繰り返し書いてきました。
しかし実験に疲れて苦悩が増すということもあります。時間と資金が足りなかったり、実験成果が出る前に不安に押しつぶされてしまいそうになることもあります。そこで取り急ぎ精神の安定を図るために、とりあえずの暫定的ではあるが堅実な見解を確保するために僕が取る手段が「自分の過去の経験の想起」です。
現在検証中の仮説も含めて、もう一度自分の人生の全記憶を思い出せる限り思い出してみて、「実際どうだったのか」と今の悩み事などと摺り合わせてみます。そうすると「今の自分の考え方」になってきた由来とともに、「とりあえずこれは事実だ」という足場を得ます。自分の実体験の記憶とはかくも頼もしいものであると思います。しかし人間の経験が選択されなかった選択肢の行く末においてまで、円満するということはありません。「もし」を予測しても予測して切れません。従って常に自分の実体験は情報不足の面があります。しかし経験分の事実は足場を確保されます。その足場に立って、新たなる見解の境地を求めることができます。
今日、冬至のこの日に僕は原始仏教という考えの枠組みを外した上で、もう一度自分の今までの人生の流れと実体験の連続の事実を思い出し考え直してみて、再度今後の目標を「原始仏教の理想とは関係なく」自分の心に建立することができたような気がします。「原始仏教は関係ない。今まで生きて来た自分として、それでもこれを欲する」という感じです。
ですからこれを読んでおられる方も「自分の今までの人生における経験というものは確かに不十分なものではあるが、しかしこれを経験したという事実は確かに事実であるのだからそれを尊重して反省し直しつつ、その経験に立って新しい何かを求めていこう」と考えるのは利益が多いと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
原始仏教 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏教のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人