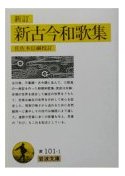251 鵜かひ舟あはれとぞ見るもののふの
八十(やそ)宇治川の夕闇の空 慈円
初め「もののふ」を武士と読み、宇治川で
鵜飼い舟を眺めながら源平が同じ川で血を流した
ことが昨日のように思い出されあわれさを思うと
いう意味かと、ストレートに理解しました。
宇治川と言えば、源三位頼政が平家に反旗を
翻して敗れた戦さや木曽義仲が源義経に
破れた戦さが思い出されるからです。
しかし、この解釈は間違いでした。
この歌をそのように解釈するのは、歌のつくり
として誤解なのです。
「もののふ」は手元の古語辞典(学研)にはこう
あります。
『もののふは朝廷に仕える文武百官。
もののふの「氏」の数が多いところから「八十(やそ)」
「五十(い)」にかかり(中略)「氏」「宇治川」に
かかる。』
つまり、「もののふの八十」は宇治川への序詞
であり、連想しがちな武士という意味合いは
直接には含んでいないのです。
この歌は、柿本人麻呂の
もののふの八十(やそ)宇治川の 網代木(あじろぎ)に
いさよふ波の 行へ知らずも
という歌を踏まえているのだとか。
人麻呂の歌は「宇治川に仕掛けられた網代の木の
まわりで漂う波はどこへ流れていくのだろう」と
いう意味でしょう。
慈円は人麻呂の歌を言外に響かせながら、歌は
あくまで鵜飼いの景色をあはれと詠んでいるわけ
です。
あはれとは、これも注釈によれば、そこに仏教的な
思いが加わるのだとか。
鵜飼といえば、当時でも昔をしのぶ風物詩となるの
ですが、当時は鵜飼い舟とはいえ魚を採ることに
仏教で言う殺生を生業にする罪深さを感じ取って
いたというのです。
注釈から慈円の歌の言葉をたどっていけば
「(いさり火を灯しながら)
鵜飼舟が宇治川で漁をしている。
罪深い殺生を行う漁師たちが気の毒に
思われ、さみしい夕闇の空の下に
一層気持ちが沈んでいく」という歌に
なるのでしょう。
しかし、話をひっくりかえすようですが、慈円は
実際には宇治川の戦いから平家の滅亡に至る戦乱と
そこで命を失った多くの魂を、かがり火の向こうに
悼んで詠んでいるのだと思います。
壇ノ浦の後に編まれた千載和歌集にしても、
その20年後に成った新古今和歌集にも
保元・平治から源平の戦に触れた歌は皆無に
近いといってよいでしょう。
歌として詠むには現実に近すぎたとも
いえますし、花鳥風月恋を詠むのが
当時の歌づくりの基調でしたから、
慈円のこの歌は異例と言ってよい歌です。
この歌が詠まれた際、周囲はこの歌に息を呑み、
涙にくれたのではないでしょうか。
源平の戦いは宮廷人を横断的に巻き込んだ
戦であり、当時の誰もが深刻な傷を自身に
あるいは周囲に抱えていたはずです。
慈円が一見するとあくまで鵜飼を詠んだ歌に
仕上げたのもその微妙さを意識したものでしょう。
この歌は建久四年(1193年)九条良経が
摂政太政大臣であった頃に催した百首歌合せで
詠まれた歌ですから、壇ノ浦の戦い(1185)に
至る源平の戦いはまだ記憶に生々しかった
頃です。
当代きっての宗教家・知識人・歌人であり、権力の
中枢に位置していた慈円だからこそ許された歌
だと思います。
八十(やそ)宇治川の夕闇の空 慈円
初め「もののふ」を武士と読み、宇治川で
鵜飼い舟を眺めながら源平が同じ川で血を流した
ことが昨日のように思い出されあわれさを思うと
いう意味かと、ストレートに理解しました。
宇治川と言えば、源三位頼政が平家に反旗を
翻して敗れた戦さや木曽義仲が源義経に
破れた戦さが思い出されるからです。
しかし、この解釈は間違いでした。
この歌をそのように解釈するのは、歌のつくり
として誤解なのです。
「もののふ」は手元の古語辞典(学研)にはこう
あります。
『もののふは朝廷に仕える文武百官。
もののふの「氏」の数が多いところから「八十(やそ)」
「五十(い)」にかかり(中略)「氏」「宇治川」に
かかる。』
つまり、「もののふの八十」は宇治川への序詞
であり、連想しがちな武士という意味合いは
直接には含んでいないのです。
この歌は、柿本人麻呂の
もののふの八十(やそ)宇治川の 網代木(あじろぎ)に
いさよふ波の 行へ知らずも
という歌を踏まえているのだとか。
人麻呂の歌は「宇治川に仕掛けられた網代の木の
まわりで漂う波はどこへ流れていくのだろう」と
いう意味でしょう。
慈円は人麻呂の歌を言外に響かせながら、歌は
あくまで鵜飼いの景色をあはれと詠んでいるわけ
です。
あはれとは、これも注釈によれば、そこに仏教的な
思いが加わるのだとか。
鵜飼といえば、当時でも昔をしのぶ風物詩となるの
ですが、当時は鵜飼い舟とはいえ魚を採ることに
仏教で言う殺生を生業にする罪深さを感じ取って
いたというのです。
注釈から慈円の歌の言葉をたどっていけば
「(いさり火を灯しながら)
鵜飼舟が宇治川で漁をしている。
罪深い殺生を行う漁師たちが気の毒に
思われ、さみしい夕闇の空の下に
一層気持ちが沈んでいく」という歌に
なるのでしょう。
しかし、話をひっくりかえすようですが、慈円は
実際には宇治川の戦いから平家の滅亡に至る戦乱と
そこで命を失った多くの魂を、かがり火の向こうに
悼んで詠んでいるのだと思います。
壇ノ浦の後に編まれた千載和歌集にしても、
その20年後に成った新古今和歌集にも
保元・平治から源平の戦に触れた歌は皆無に
近いといってよいでしょう。
歌として詠むには現実に近すぎたとも
いえますし、花鳥風月恋を詠むのが
当時の歌づくりの基調でしたから、
慈円のこの歌は異例と言ってよい歌です。
この歌が詠まれた際、周囲はこの歌に息を呑み、
涙にくれたのではないでしょうか。
源平の戦いは宮廷人を横断的に巻き込んだ
戦であり、当時の誰もが深刻な傷を自身に
あるいは周囲に抱えていたはずです。
慈円が一見するとあくまで鵜飼を詠んだ歌に
仕上げたのもその微妙さを意識したものでしょう。
この歌は建久四年(1193年)九条良経が
摂政太政大臣であった頃に催した百首歌合せで
詠まれた歌ですから、壇ノ浦の戦い(1185)に
至る源平の戦いはまだ記憶に生々しかった
頃です。
当代きっての宗教家・知識人・歌人であり、権力の
中枢に位置していた慈円だからこそ許された歌
だと思います。
|
|
|
|
|
|
|
|
新古今和歌集私撰:百人の歌人 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
新古今和歌集私撰:百人の歌人のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31945人