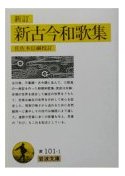1802木枯らしの風にもみじて人知れず
憂き言の葉の積もるころかな
「木の葉が木枯らしに吹かれて紅葉するように
こころの中で辛い思いを嘆く言葉が積み重なっていく」
という歌であろう。
(小町集では「木枯らしの風にも散らで」とある。
「もみじて」とはいかにも新古今好みであり、
後代の手が加わっているのだろう。)
小野小町は新古今に6首採られている。古今には18首。
八代集抄も18首を載せている。
*
小野小町は古今集の次の歌がよく知られている。
花の色はうつりにけりないたづらに
我身世にふるながめせしまに(古今113)
小町集でも巻頭に挙げられているから当時もよく知られた
歌だったのだろう。
百人一首に採られている歌の中で今人々がなにかの折に
思い出し口にするほとんど唯一の歌といっていい。
小町は9世紀半ばを生きた人だから、おおげさな言い方を
すれば、1000年の時間を耐えて歌の命を持ち続けている
数少ない歌である。
小町には晩年に落魄して各地を流浪したという伝説が
あり、謡曲にも謡われている。小町のものと言われる
墓が各地にあるとされるのも、もとをたどればこの歌に
たどり着くのではなかろうか。
一見すると、年を経て容色が衰えたことを
詠んでいるように読める。そこから人々は恋多き女が
最後に男から相手にされなくなった末路という、
いつの時代にも関心を惹くドラマの筋書きを読み
込んで来たのだろう。
「小町集」の100首余りの歌を読んでこの歌を
ふり返れば小町が詠んでいるのは無常感であり、
「老い」はその中に包まれていることに気づく。
この歌は「小町集」では「花を眺めて」という短い
前書きがある。
「色みえでうつろふものは世の中の人の心の花にぞ
ありける」と詠んだこの詩人が「花」という言葉に
深いため息と複雑な思いをもっていたことは知って
おいたほうがいい。
小町小町は「無常感」をモチーフにした歌の
多くを若い時代から詠んだ気配がある。
小学館本は小町の生没年を不詳とし、幾つくらい
まで生きていたのかはっきりしないが、
かなり早い時期から無常を詠んでいたのだと思う。
無常を詠んだ歌に見える感性はやわらかい。
小町の無常感は次のような歌に彼女自身の
信条となって結実している。
色みえでうつろふものは世の中の
人の心の花にぞありける(小町集20)
あはれてふことこそうたて世の中を
思ひはなれぬほだしなりけれ(小町集107)
露の命はかなきものを朝夕に
いきたるかぎりあひみてしがな(小町集47)
新古今に「無常」を詠んだ歌は少なくないが
その多くは当時の常識としての無常感に
よりかかったところで作られたものである。
常識としての無常感を踏まえた感傷や
美的な感慨の歌という性格が強い。
小町は思想家ではなく、宗教家でもないが、
詩人としての感性が「無常」に揺さぶられている
という意味では平安期の「無常」という思想の
すぐ近くにいた人とさえ言っていいかもしれない。
小町で興味深いのは小町が出家した記述がどこにも
見当たらないことである。
その無常感にも関わらずである。
小町が晩年に落魄したと捉えた謡曲が多いのは、その
無常感にも関わらず信仰の道に入らなかったことで、
小町の魂が晩年まで救われなかったという見方が
あるのかもしれない。
小町集を開くと、小町伝説とは別の顔が伺える。
日ぐらしの鳴く山里の夕暮れは
風より外に訪ふ人ぞなき(小町集42)
色も香もなつかしき哉蛙鳴く
井出のわたりの山吹の花(小町集61)
しどけなく寝くたれ髪を見せじとや
はた隠れたる今朝の朝顔(小町集96)
いつとても恋しからずはあらねども
あやしかりけり秋の夕暮れ(小町集100)
古今も新古今も八代集抄もこれらの歌を採っていないが、
小町の素顔が伺われる歌である。
小町伝説は小町のもつ感性の柔らかさ、かわいらしさを
消してしまっている。
*資料
「小町集」室城英之:和歌文学大系18巻(明治書院)
憂き言の葉の積もるころかな
「木の葉が木枯らしに吹かれて紅葉するように
こころの中で辛い思いを嘆く言葉が積み重なっていく」
という歌であろう。
(小町集では「木枯らしの風にも散らで」とある。
「もみじて」とはいかにも新古今好みであり、
後代の手が加わっているのだろう。)
小野小町は新古今に6首採られている。古今には18首。
八代集抄も18首を載せている。
*
小野小町は古今集の次の歌がよく知られている。
花の色はうつりにけりないたづらに
我身世にふるながめせしまに(古今113)
小町集でも巻頭に挙げられているから当時もよく知られた
歌だったのだろう。
百人一首に採られている歌の中で今人々がなにかの折に
思い出し口にするほとんど唯一の歌といっていい。
小町は9世紀半ばを生きた人だから、おおげさな言い方を
すれば、1000年の時間を耐えて歌の命を持ち続けている
数少ない歌である。
小町には晩年に落魄して各地を流浪したという伝説が
あり、謡曲にも謡われている。小町のものと言われる
墓が各地にあるとされるのも、もとをたどればこの歌に
たどり着くのではなかろうか。
一見すると、年を経て容色が衰えたことを
詠んでいるように読める。そこから人々は恋多き女が
最後に男から相手にされなくなった末路という、
いつの時代にも関心を惹くドラマの筋書きを読み
込んで来たのだろう。
「小町集」の100首余りの歌を読んでこの歌を
ふり返れば小町が詠んでいるのは無常感であり、
「老い」はその中に包まれていることに気づく。
この歌は「小町集」では「花を眺めて」という短い
前書きがある。
「色みえでうつろふものは世の中の人の心の花にぞ
ありける」と詠んだこの詩人が「花」という言葉に
深いため息と複雑な思いをもっていたことは知って
おいたほうがいい。
小町小町は「無常感」をモチーフにした歌の
多くを若い時代から詠んだ気配がある。
小学館本は小町の生没年を不詳とし、幾つくらい
まで生きていたのかはっきりしないが、
かなり早い時期から無常を詠んでいたのだと思う。
無常を詠んだ歌に見える感性はやわらかい。
小町の無常感は次のような歌に彼女自身の
信条となって結実している。
色みえでうつろふものは世の中の
人の心の花にぞありける(小町集20)
あはれてふことこそうたて世の中を
思ひはなれぬほだしなりけれ(小町集107)
露の命はかなきものを朝夕に
いきたるかぎりあひみてしがな(小町集47)
新古今に「無常」を詠んだ歌は少なくないが
その多くは当時の常識としての無常感に
よりかかったところで作られたものである。
常識としての無常感を踏まえた感傷や
美的な感慨の歌という性格が強い。
小町は思想家ではなく、宗教家でもないが、
詩人としての感性が「無常」に揺さぶられている
という意味では平安期の「無常」という思想の
すぐ近くにいた人とさえ言っていいかもしれない。
小町で興味深いのは小町が出家した記述がどこにも
見当たらないことである。
その無常感にも関わらずである。
小町が晩年に落魄したと捉えた謡曲が多いのは、その
無常感にも関わらず信仰の道に入らなかったことで、
小町の魂が晩年まで救われなかったという見方が
あるのかもしれない。
小町集を開くと、小町伝説とは別の顔が伺える。
日ぐらしの鳴く山里の夕暮れは
風より外に訪ふ人ぞなき(小町集42)
色も香もなつかしき哉蛙鳴く
井出のわたりの山吹の花(小町集61)
しどけなく寝くたれ髪を見せじとや
はた隠れたる今朝の朝顔(小町集96)
いつとても恋しからずはあらねども
あやしかりけり秋の夕暮れ(小町集100)
古今も新古今も八代集抄もこれらの歌を採っていないが、
小町の素顔が伺われる歌である。
小町伝説は小町のもつ感性の柔らかさ、かわいらしさを
消してしまっている。
*資料
「小町集」室城英之:和歌文学大系18巻(明治書院)
|
|
|
|
|
|
|
|
新古今和歌集私撰:百人の歌人 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
新古今和歌集私撰:百人の歌人のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208320人
- 3位
- 酒好き
- 170698人