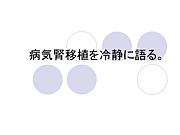一般医療としての病気腎移植は禁止され、やるなら臨床研究で、というのが現状ですが、さて、この臨床研究の範囲に相当する病気腎移植というのはどの辺りのことを指すのか、考えてみると少々曖昧です。
例えば、親族間の生体腎移植を準備中に、ドナーに病気が見つかった時、全ての場合において臨床研究にしなければならないのか、程度問題なのか、それとも最初から移植するつもりでやっていることなので病気が見つかっても全然OKなのか、保険は使えるのか、もし摘出手術中に病変が見つかったらそこでアウトなのか、或いは死体腎移植の場合でも、ドナーの腎臓に病気が見つかったらこれは臨床研究にしなければならないのか、人により意見が違うのではないかと思います。
そこらへん、話し合ってみませんか。
例えば、親族間の生体腎移植を準備中に、ドナーに病気が見つかった時、全ての場合において臨床研究にしなければならないのか、程度問題なのか、それとも最初から移植するつもりでやっていることなので病気が見つかっても全然OKなのか、保険は使えるのか、もし摘出手術中に病変が見つかったらそこでアウトなのか、或いは死体腎移植の場合でも、ドナーの腎臓に病気が見つかったらこれは臨床研究にしなければならないのか、人により意見が違うのではないかと思います。
そこらへん、話し合ってみませんか。
|
|
|
|
コメント(13)
生体移植の場合、ドナー側は最初から摘出には同意しているので、ドナー側の病気治療のオプションとして腎臓を温存することは考えなくて良いわけですよね。だから、病気の腎臓を(修復した上で)移植“されても”大丈夫かというレシピエント側の事情だけを考えればよい、と。そう考えると、通常は倫理委員会に諮る必要も無く当事者間の合意だけで可能な親族間の生体腎移植で病気が見つかった場合こそ、実は“病気腎移植”のモデルケースなのかも知れません。レシピエントの意向をどのくらい尊重するべきなのか、だけにフォーカスして考えることが出来ます。
幾ら死んでも良いから移植して欲しい、と口では言っていても、病気の程度が重くて修復しても移植された腎臓が機能することなく、結局摘出しなければならなくなった、なんていうのはレシピエントとしても許容出来ないでしょう。手術するだけ無駄な苦しみですから、これは論外だと思われます。
そこから考えると、ドナーの体内に残してもそこで充分に機能するもの、ドナーが普通の患者なら普通は摘出など考えない程度、部分切除しか考えない程度の病変ならOK、というのが一つのボーダーラインになりうるように思います。
この基準で行くと、小径腎細胞癌は部分切除が第一オプションで、かつ再発の虞も摘出した場合と残した場合とで大差無いということですから、生体腎移植の場合は倫理委員会に諮ることなく医師の裁量と患者(レシピエント)への充分な説明で、臨床研究としなくても可能なのではないか、と(一瞬)思われます。
が、やはり移植を受ける人は免疫抑制剤を飲むというのがネックになるのではないでしょうか。癌以外の病気なら問題にはならないでしょうけれども、免疫系の働きが通常人とは異なるという移植のレシピエントの特殊性が、やはり通常医療としてはすんなり認められない根拠になりそうに思います。
また、
> 小腎細胞癌の場合は大丈夫らしいという知見
に関しては、私は半信半疑です。リスクを計算するにはまだ事例数が足りないと思います。が、絶対駄目というほど危なくは無いらしい、くらいな見方です。透析だって長いこと続けていると癌を発症するリスクは普通の人の何十倍も高くなるそうですし、それと比べて同じか低い発症確率なら、問題視するには当たらないだろうとも思います。
確率を計算するにはもっと事例を蓄積する必要があり、そのためには臨床例を増やす必要がありますが、移植学会が「担癌臓器の移植は駄目」という見解であれば、これは臨床研究にせざるを得ないのではないかと思います。生体腎移植の場合も、癌の腎臓の移植は臨床研究にしないと駄目、なのではないかと。
でも、そもそもそういうケース自体、希でしょうねえ。
幾ら死んでも良いから移植して欲しい、と口では言っていても、病気の程度が重くて修復しても移植された腎臓が機能することなく、結局摘出しなければならなくなった、なんていうのはレシピエントとしても許容出来ないでしょう。手術するだけ無駄な苦しみですから、これは論外だと思われます。
そこから考えると、ドナーの体内に残してもそこで充分に機能するもの、ドナーが普通の患者なら普通は摘出など考えない程度、部分切除しか考えない程度の病変ならOK、というのが一つのボーダーラインになりうるように思います。
この基準で行くと、小径腎細胞癌は部分切除が第一オプションで、かつ再発の虞も摘出した場合と残した場合とで大差無いということですから、生体腎移植の場合は倫理委員会に諮ることなく医師の裁量と患者(レシピエント)への充分な説明で、臨床研究としなくても可能なのではないか、と(一瞬)思われます。
が、やはり移植を受ける人は免疫抑制剤を飲むというのがネックになるのではないでしょうか。癌以外の病気なら問題にはならないでしょうけれども、免疫系の働きが通常人とは異なるという移植のレシピエントの特殊性が、やはり通常医療としてはすんなり認められない根拠になりそうに思います。
また、
> 小腎細胞癌の場合は大丈夫らしいという知見
に関しては、私は半信半疑です。リスクを計算するにはまだ事例数が足りないと思います。が、絶対駄目というほど危なくは無いらしい、くらいな見方です。透析だって長いこと続けていると癌を発症するリスクは普通の人の何十倍も高くなるそうですし、それと比べて同じか低い発症確率なら、問題視するには当たらないだろうとも思います。
確率を計算するにはもっと事例を蓄積する必要があり、そのためには臨床例を増やす必要がありますが、移植学会が「担癌臓器の移植は駄目」という見解であれば、これは臨床研究にせざるを得ないのではないかと思います。生体腎移植の場合も、癌の腎臓の移植は臨床研究にしないと駄目、なのではないかと。
でも、そもそもそういうケース自体、希でしょうねえ。
例えばドナーが持っているのが良性疾患だったとして、親族でない第三者間の生体移植になる場合はこれも臨床試験扱いにしないといけないのでしょうかね。例えば、そういう病気で入院・通院している患者が是非ともこの自分の病気の腎臓を修復して知り合いのあの人に移植してくれと頼んだ場合とか、要するに親族間の生体移植なら問題視されない程度の病気腎で、ドナーの意志が完全に確認できる場合、です。
親族以外の移植は絶対禁止という訳ではなくて、移植学会の倫理指針によれば倫理委員会で承認されればOKということにはなってますから、病変部位を取り除けば全然オッケーな“病気腎”まで臨床研究にしないといけない(=保険が効かない)というのは理不尽な気がしますけれども。
親族以外の移植は絶対禁止という訳ではなくて、移植学会の倫理指針によれば倫理委員会で承認されればOKということにはなってますから、病変部位を取り除けば全然オッケーな“病気腎”まで臨床研究にしないといけない(=保険が効かない)というのは理不尽な気がしますけれども。
> 4 なとろむ さん
基本的な考え方は同じかと思いますが、もう少し具体的に掘り下げてみようと思います。
> 健康な腎臓を提供するのには抵抗があっても、メスを入れなければならないのであれば、部分切除ではなく全摘出して家族に移植して欲しい、という人がいてもおかしくはないでしょう。
まさに、そのあたりがグレーゾーンという気がします。
> 5,6 Canorus さん
> 移植のために摘出するのであれば、現在のところ倫理委員会の判断になるでしょう。
倫理委員会の判断で済むなら、必ずしも臨床研究扱いにはしなくていい、ということになりませんかね。
あと、別にかぶっても構わないんでどんどん書いて下さいませ。せっかくトピを立てたのに、閑古鳥が鳴いていたんでは寂しいです(苦笑)。
基本的な考え方は同じかと思いますが、もう少し具体的に掘り下げてみようと思います。
> 健康な腎臓を提供するのには抵抗があっても、メスを入れなければならないのであれば、部分切除ではなく全摘出して家族に移植して欲しい、という人がいてもおかしくはないでしょう。
まさに、そのあたりがグレーゾーンという気がします。
> 5,6 Canorus さん
> 移植のために摘出するのであれば、現在のところ倫理委員会の判断になるでしょう。
倫理委員会の判断で済むなら、必ずしも臨床研究扱いにはしなくていい、ということになりませんかね。
あと、別にかぶっても構わないんでどんどん書いて下さいませ。せっかくトピを立てたのに、閑古鳥が鳴いていたんでは寂しいです(苦笑)。
いろいろなケースで考えてみましょう。
ドナー候補は、透析センターで働いている掃除のおばさん、とでもしておきましょうか。とにかくレシピエントになる人とは親族関係がない人、です。このおばさんが、
Case A.
... 透析センターに通ってくる別のおばさんととても仲良くなり、「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めて非親族間で生体移植をすることになって、倫理委員会も通り、準備を進めている最中に腎臓に良性腫瘍が見つかってしまいました。腫瘍を取り除けば腎機能には問題ありませんが、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case B.
... 胆石で入院することになりました。どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から非親族間の生体移植を勧めました。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、準備を進めている最中に腎臓に良性腫瘍が見つかってしまいました。腫瘍を取り除けば腎機能には問題ありませんが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case C.
... 腎臓の良性腫瘍で入院することになりました。治療に当たって摘出の必要はありませんが、どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めました。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case D.
... 腎臓の良性腫瘍で入院することになりました。手術は一旦腎臓を取り出してから病巣を取り除く必要がありますが、自家腎移植も充分に可能です。しかしながら自家腎移植は手術の時間がとても長くなるのでおばさんは怖いと思い、摘出手術を希望しました。ついでに、どうせ捨てるならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から移植を勧めました。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case E.
... Case Dと同じ症例ですが、おばさんに“捨てる腎臓を仲良しのおばさんに移植すること”を勧めたのは自家腎移植のリスクを説明した担当の医師でした。さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case F.
... ネフローゼで入院することになりました。どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の病気の腎臓で良ければあげるから移植しなさいよ」と自分から勧めました。ネフローゼの腎臓はおばさんの体内では充分に機能していません。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case G.
... 小径腎細胞癌で入院することになりました。どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めて第三者間で生体移植を希望しました。倫理委員会ではおばさんの意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case H.
... 透析センターに通ってくる別のおばさんととても仲良くなり、「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めて第三者間で生体移植をすることになって、倫理委員会も通り、準備を進めている最中にこのおばさんが肝臓癌であることが分かってしまいました。今のところ腎臓には何も問題ありませんが、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
皆様のご意見、お待ちしております。
ドナー候補は、透析センターで働いている掃除のおばさん、とでもしておきましょうか。とにかくレシピエントになる人とは親族関係がない人、です。このおばさんが、
Case A.
... 透析センターに通ってくる別のおばさんととても仲良くなり、「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めて非親族間で生体移植をすることになって、倫理委員会も通り、準備を進めている最中に腎臓に良性腫瘍が見つかってしまいました。腫瘍を取り除けば腎機能には問題ありませんが、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case B.
... 胆石で入院することになりました。どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から非親族間の生体移植を勧めました。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、準備を進めている最中に腎臓に良性腫瘍が見つかってしまいました。腫瘍を取り除けば腎機能には問題ありませんが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case C.
... 腎臓の良性腫瘍で入院することになりました。治療に当たって摘出の必要はありませんが、どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めました。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case D.
... 腎臓の良性腫瘍で入院することになりました。手術は一旦腎臓を取り出してから病巣を取り除く必要がありますが、自家腎移植も充分に可能です。しかしながら自家腎移植は手術の時間がとても長くなるのでおばさんは怖いと思い、摘出手術を希望しました。ついでに、どうせ捨てるならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から移植を勧めました。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case E.
... Case Dと同じ症例ですが、おばさんに“捨てる腎臓を仲良しのおばさんに移植すること”を勧めたのは自家腎移植のリスクを説明した担当の医師でした。さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case F.
... ネフローゼで入院することになりました。どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の病気の腎臓で良ければあげるから移植しなさいよ」と自分から勧めました。ネフローゼの腎臓はおばさんの体内では充分に機能していません。倫理委員会ではおばさん達の意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case G.
... 小径腎細胞癌で入院することになりました。どうせ手術するならと思い立ち、透析センターに通っている仲良しのおばさんに「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めて第三者間で生体移植を希望しました。倫理委員会ではおばさんの意志は充分に確認できましたが、さて、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
Case H.
... 透析センターに通ってくる別のおばさんととても仲良くなり、「私の腎臓あげるから移植しなさいよ」と自分から勧めて第三者間で生体移植をすることになって、倫理委員会も通り、準備を進めている最中にこのおばさんが肝臓癌であることが分かってしまいました。今のところ腎臓には何も問題ありませんが、このケースは“臨床研究”行きでしょうか?
皆様のご意見、お待ちしております。
Case A. 、Case B.は、通常の第三者間の生体移植に準じることになるでしょう。
Case C. については、腎臓の良性腫瘍で「どうせ手術するなら」となる理由がよくわかりませんので保留です。
Case D.、Case E.は、臨床研究扱いでしょうか。Case E.に関しては、別の医師から改めて自家腎移植のリスク、メリットについて説明が必要でしょう。倫理委員会でOKが出るということは、十分な説明がなされているのは前提として考えてよいと思います。
Case F.は臨床研究でもアウトだと思います。現時点では、ネフローゼ症候群ドナーからの病腎移植は臨床研究でもNGでしょう。なぜなら、腎摘出のメリットが少なすぎるからです。私の知る限りでは、万波医師のグループ以外で、ネフローゼ症候群ドナーからの病腎移植の例はありません。
Case G. は、普通に臨床研究扱いでしょう。
Case H. は、倫理委員会に通らないと思います。肝臓癌ではなく、もうちょっと軽症の疾患、たとえば脂肪肝とかコントロール良好な糖尿病とかであれば、医学的にドナーになれるか倫理委員会が判定することになるでしょう。
Case C. については、腎臓の良性腫瘍で「どうせ手術するなら」となる理由がよくわかりませんので保留です。
Case D.、Case E.は、臨床研究扱いでしょうか。Case E.に関しては、別の医師から改めて自家腎移植のリスク、メリットについて説明が必要でしょう。倫理委員会でOKが出るということは、十分な説明がなされているのは前提として考えてよいと思います。
Case F.は臨床研究でもアウトだと思います。現時点では、ネフローゼ症候群ドナーからの病腎移植は臨床研究でもNGでしょう。なぜなら、腎摘出のメリットが少なすぎるからです。私の知る限りでは、万波医師のグループ以外で、ネフローゼ症候群ドナーからの病腎移植の例はありません。
Case G. は、普通に臨床研究扱いでしょう。
Case H. は、倫理委員会に通らないと思います。肝臓癌ではなく、もうちょっと軽症の疾患、たとえば脂肪肝とかコントロール良好な糖尿病とかであれば、医学的にドナーになれるか倫理委員会が判定することになるでしょう。
>8
私の見方ですが。
私はA〜Dまでは臨床研究にする必要は無いと思います。ドナーの意志が一点の曇りもなく証明できるなら、現時点においても倫理委員会の承認のみで良い、保険診療の対象となる通常医療の範囲の生体移植として良いと考えます。
Eは自発性をどう証明できるかという点で問題がありますが、それさえ証明できれば外形的にはDと同じなので、臨床研究にする必要は無いと考えます。ただ、倫理委員会が認めない可能性も高いでしょう。
Fは移植後に本当に腎臓が機能するようになるかという点で、Gはドナー腎が悪性腫瘍を持っているという点で、Hはドナーに転移の可能性がある癌があるという点で“新しい医療”に該当すると思われ、従って臨床研究にせざるを得ないと思います。
私の見方ですが。
私はA〜Dまでは臨床研究にする必要は無いと思います。ドナーの意志が一点の曇りもなく証明できるなら、現時点においても倫理委員会の承認のみで良い、保険診療の対象となる通常医療の範囲の生体移植として良いと考えます。
Eは自発性をどう証明できるかという点で問題がありますが、それさえ証明できれば外形的にはDと同じなので、臨床研究にする必要は無いと考えます。ただ、倫理委員会が認めない可能性も高いでしょう。
Fは移植後に本当に腎臓が機能するようになるかという点で、Gはドナー腎が悪性腫瘍を持っているという点で、Hはドナーに転移の可能性がある癌があるという点で“新しい医療”に該当すると思われ、従って臨床研究にせざるを得ないと思います。
>9 なとろむさん
“通常移植の範囲”で同じ見方は、AとB。
“臨床研究の範囲”で同じ見方は、Gだけ。
私は“通常移植の範囲”、なとろむさんは“臨床研究の範囲”と見るのが、DとE。
私は“臨床研究の範囲”、なとろむさんは“やっちゃだめ”と見るのが、FとH。
ですか。
Cについて補足すると、自分が入院したことをきっかけとして、「部分切除で全然OKなんだけど、どうせお腹を切るなら全部取っちゃってあの人に使って貰おう」という“100%の善意”が芽生えた、という設定です。
Fのネフローゼの場合、摘出は“病気の治療のため”ではないという前提です。“他人に移植するとネフローゼは治ることがある”ということをどこかで聞きかじったオバサンが、“100%の善意”であの人に使ってあげてくれ、と言いだしたという設定。あくまで気持ちは“第三者間の生体移植”です。
Hは、腎臓そのものの癌はOKかも知れないのに、腎臓は何ともなくても他の臓器の癌があるとダメ、というところがちょっと素人的に理解が難しいですね。過去にそれで失敗した事例がある、ということでしょうか?
他の方も、気になるケースだけでも構いませんので、是非ご意見お聞かせ下さい。
“通常移植の範囲”で同じ見方は、AとB。
“臨床研究の範囲”で同じ見方は、Gだけ。
私は“通常移植の範囲”、なとろむさんは“臨床研究の範囲”と見るのが、DとE。
私は“臨床研究の範囲”、なとろむさんは“やっちゃだめ”と見るのが、FとH。
ですか。
Cについて補足すると、自分が入院したことをきっかけとして、「部分切除で全然OKなんだけど、どうせお腹を切るなら全部取っちゃってあの人に使って貰おう」という“100%の善意”が芽生えた、という設定です。
Fのネフローゼの場合、摘出は“病気の治療のため”ではないという前提です。“他人に移植するとネフローゼは治ることがある”ということをどこかで聞きかじったオバサンが、“100%の善意”であの人に使ってあげてくれ、と言いだしたという設定。あくまで気持ちは“第三者間の生体移植”です。
Hは、腎臓そのものの癌はOKかも知れないのに、腎臓は何ともなくても他の臓器の癌があるとダメ、というところがちょっと素人的に理解が難しいですね。過去にそれで失敗した事例がある、ということでしょうか?
他の方も、気になるケースだけでも構いませんので、是非ご意見お聞かせ下さい。
>Cについて補足すると、自分が入院したことをきっかけとして、「部分切除で全然OKなんだけど、どうせお腹を切るなら全部取っちゃってあの人に使って貰おう」という“100%の善意”が芽生えた、という設定です
となると、Bと同じ扱いになりますね。
>Fのネフローゼの場合、摘出は“病気の治療のため”ではないという前提です。“他人に移植するとネフローゼは治ることがある”ということをどこかで聞きかじったオバサンが、“100%の善意”であの人に使ってあげてくれ、と言いだしたという設定。あくまで気持ちは“第三者間の生体移植”です。
ネフローゼ症候群の人は腎機能が低下している、あるいは今後低下する可能性が高いので、生体腎移植のドナーにはなれません。個人的にもネフローゼ症候群ドナーからの移植は行うべきではないと考えます。
>Hは、腎臓そのものの癌はOKかも知れないのに、腎臓は何ともなくても他の臓器の癌があるとダメ、というところがちょっと素人的に理解が難しいですね。過去にそれで失敗した事例がある、ということでしょうか?
担癌患者は生体移植のドナーになれません。癌の持ち込みリスクおよびドナーの治療に影響するためです。癌の治療を行い治癒したと考えられればOKです。治癒見込みのある癌患者はドナーになることより自分の治療を優先させるべきだと考えます。治癒見込みのない癌患者の場合は、ドナーになることで命を縮めることになりかねませんし、癌が進行していればそれだけ持ち込みのリスクが増します。
以下、生体腎移植のガイドラインより引用します。
生体腎移植ガイドライン
http://www.asas.or.jp/jst/pdf/guideline_002jinishoku..pdf
I.腎移植希望者(レシピエント)適応基準
1.末期腎不全患者であること
透析を続けなければ生命維持が困難であるか、または近い将来に透析に
導入する必要に迫られている保存期慢性腎不全である
2.全身感染症がないこと
3.活動性肝炎がないこと
4.悪性腫瘍がないこと
II. 腎臓提供者(ドナー)適応基準
1.以下の疾患または状態を伴わないこととする
a. 全身性の活動性感染症
b. HIV抗体陽性
c. クロイツフェルト・ヤコブ病
d. 悪性腫瘍(原発性脳腫瘍及び治癒したと考えられるものを除く)
2.以下の疾患または状態が存在する場合は、慎重に適応を決定する
a. 器質的腎疾患の存在(疾患の治療上の必要から摘出されたものは移植
の対象から除く)
b. 70 歳以上
3.腎機能が良好であること
FのケースはII-3に、HのケースはII-1-dにそれぞれ引っ掛かります。
となると、Bと同じ扱いになりますね。
>Fのネフローゼの場合、摘出は“病気の治療のため”ではないという前提です。“他人に移植するとネフローゼは治ることがある”ということをどこかで聞きかじったオバサンが、“100%の善意”であの人に使ってあげてくれ、と言いだしたという設定。あくまで気持ちは“第三者間の生体移植”です。
ネフローゼ症候群の人は腎機能が低下している、あるいは今後低下する可能性が高いので、生体腎移植のドナーにはなれません。個人的にもネフローゼ症候群ドナーからの移植は行うべきではないと考えます。
>Hは、腎臓そのものの癌はOKかも知れないのに、腎臓は何ともなくても他の臓器の癌があるとダメ、というところがちょっと素人的に理解が難しいですね。過去にそれで失敗した事例がある、ということでしょうか?
担癌患者は生体移植のドナーになれません。癌の持ち込みリスクおよびドナーの治療に影響するためです。癌の治療を行い治癒したと考えられればOKです。治癒見込みのある癌患者はドナーになることより自分の治療を優先させるべきだと考えます。治癒見込みのない癌患者の場合は、ドナーになることで命を縮めることになりかねませんし、癌が進行していればそれだけ持ち込みのリスクが増します。
以下、生体腎移植のガイドラインより引用します。
生体腎移植ガイドライン
http://www.asas.or.jp/jst/pdf/guideline_002jinishoku..pdf
I.腎移植希望者(レシピエント)適応基準
1.末期腎不全患者であること
透析を続けなければ生命維持が困難であるか、または近い将来に透析に
導入する必要に迫られている保存期慢性腎不全である
2.全身感染症がないこと
3.活動性肝炎がないこと
4.悪性腫瘍がないこと
II. 腎臓提供者(ドナー)適応基準
1.以下の疾患または状態を伴わないこととする
a. 全身性の活動性感染症
b. HIV抗体陽性
c. クロイツフェルト・ヤコブ病
d. 悪性腫瘍(原発性脳腫瘍及び治癒したと考えられるものを除く)
2.以下の疾患または状態が存在する場合は、慎重に適応を決定する
a. 器質的腎疾患の存在(疾患の治療上の必要から摘出されたものは移植
の対象から除く)
b. 70 歳以上
3.腎機能が良好であること
FのケースはII-3に、HのケースはII-1-dにそれぞれ引っ掛かります。
>12
> ネフローゼ症候群の人は腎機能が低下している、あるいは今後低下する可能性が高いので、生体腎移植のドナーにはなれません。
ああ、なるほど。片方の腎臓を取ってしまうことで腎不全になってしまう可能性があるような人は、ドナーにはなれない、ということですか。
でも、残す方の腎臓が充分に機能している場合はどうでしょう?
生体移植の場合、移植に使うのは「相対的に機能が劣る方の腎臓」ですよね。その場合も、摘出してはいけないのでしょうか?
> 担癌患者は生体移植のドナーになれません。癌の持ち込みリスクおよびドナーの治療に影響するためです。
これはやはり、小径腎細胞癌だけは特別だ、ということなんでしょうか?
しかし考えてみると確かに、タダさえ弱っているだろう患者から関係ない臓器まで摘出してしまうなんていうのは、おかしなことですね。治療上の必要性どころか治療の邪魔をする可能性が高い。だから許されない、ですか。
移植に使う腎臓自体が病気を持っている場合というのは例外的にドナーに追加の不利益をもたらさない、特別なケースなのですね。
こちらは納得です。
> ネフローゼ症候群の人は腎機能が低下している、あるいは今後低下する可能性が高いので、生体腎移植のドナーにはなれません。
ああ、なるほど。片方の腎臓を取ってしまうことで腎不全になってしまう可能性があるような人は、ドナーにはなれない、ということですか。
でも、残す方の腎臓が充分に機能している場合はどうでしょう?
生体移植の場合、移植に使うのは「相対的に機能が劣る方の腎臓」ですよね。その場合も、摘出してはいけないのでしょうか?
> 担癌患者は生体移植のドナーになれません。癌の持ち込みリスクおよびドナーの治療に影響するためです。
これはやはり、小径腎細胞癌だけは特別だ、ということなんでしょうか?
しかし考えてみると確かに、タダさえ弱っているだろう患者から関係ない臓器まで摘出してしまうなんていうのは、おかしなことですね。治療上の必要性どころか治療の邪魔をする可能性が高い。だから許されない、ですか。
移植に使う腎臓自体が病気を持っている場合というのは例外的にドナーに追加の不利益をもたらさない、特別なケースなのですね。
こちらは納得です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
病気腎移植を冷静に語る 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
病気腎移植を冷静に語るのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89533人