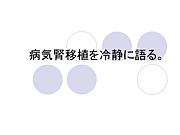|
|
|
|
コメント(22)
(透析と移植の余命比較 その1)
透析と移植の余命について、WEBでよく見掛けるデータがあります。例えば↓のサイトのように、数字を示した上で、透析患者は移植者の半分しか生きられない、と主張する際に“裏付け”として使われているようですが、肝心の出典を示しているものはほぼ皆無です。
透析、移植を経験した一患者の日記:移植と透析の年代別平均寿命
http://blog.livedoor.jp/arrow620/archives/51307749.html
−−−−−
僕が、ある移植外科の先生からこの事実を知らされたときびっくりしました。
(一応、データを書いてみますが、透析されてる方はみたくなければ見ないほうがいいかもしれません・・・)
年齢 血液透析(平均生存年数) 移植(平均生存年数)
15歳〜19歳 男24.8年 女24.6年 男46.1年 女47.0年
20歳〜24歳 男21.5年 女21.6年 男41.9年 女43.0年
25歳〜29歳 男18.5年 女18.9年 男37.6年 女38.9年
30歳〜34歳 男15.5年 女16.3年 男33.3年 女34.7年
35歳〜39歳 男13.0年 女13.8年 男29.2年 女30.9年
40歳〜44歳 男10.8年 女11.8年 男25.3年 女27.3年
45歳〜49歳 男9.0年 女9.9年 男21.8年 女23.8年
50歳〜54歳 男7.4年 女8.1年 男18.5年 女20.5年
55歳〜59歳 男6.2年 女6.7年 男15.7年 女17.8年
60歳〜64歳 男5.2年 女5.6年 男13.2年 女15.2年
65歳〜69歳 男4.4年 女4.8年 男11.0年 女13.2年
.......
−−−−−
このデータを孫引きしているサイトは他にも幾つかありますが、又聞きや孫引きで説得力があると思っているのも人が良いというか井戸端会議のノリで随分お気楽に断定的なことを書くものだという気がして不思議なのですけれども、まあそれは置いておくとして、この数字自体は確かに透析よりも移植の方がかなり有利だということを示しています。それは本当でしょうか?
出典の明示されていない数字など無視しても良いのですけれども、上記の数字を元に検索を掛けてみたところ、たぶんここが国内の発信源(の一つ)だろうというサイトのドキュメントを見付けました。
腎移植提供者の健康な生活の送り方
http://www.nagoya2.jrc.or.jp/kidney-center/topics/DonorSlide2004.11.23.pdf
このスライドの 7 ページ目に、
「血液透析と腎移植の期待される生存年数の違い」
というのがあり、この表に載っているデータの Asian の欄の数字が、上記のデータと全く同じです。図としてコピぺしておきます。(数字をマルで囲んでいるのは元々のスライドがそうなっています)
ではこの表の元になっているデータは何なのかというと、White とか Black とか N Am (Native Amarican?) とか、どうもアメリカのデータであることは間違いなさそうです。右下の「2003 USRDS」というのがヒントでしょう。
(つづく)
透析と移植の余命について、WEBでよく見掛けるデータがあります。例えば↓のサイトのように、数字を示した上で、透析患者は移植者の半分しか生きられない、と主張する際に“裏付け”として使われているようですが、肝心の出典を示しているものはほぼ皆無です。
透析、移植を経験した一患者の日記:移植と透析の年代別平均寿命
http://blog.livedoor.jp/arrow620/archives/51307749.html
−−−−−
僕が、ある移植外科の先生からこの事実を知らされたときびっくりしました。
(一応、データを書いてみますが、透析されてる方はみたくなければ見ないほうがいいかもしれません・・・)
年齢 血液透析(平均生存年数) 移植(平均生存年数)
15歳〜19歳 男24.8年 女24.6年 男46.1年 女47.0年
20歳〜24歳 男21.5年 女21.6年 男41.9年 女43.0年
25歳〜29歳 男18.5年 女18.9年 男37.6年 女38.9年
30歳〜34歳 男15.5年 女16.3年 男33.3年 女34.7年
35歳〜39歳 男13.0年 女13.8年 男29.2年 女30.9年
40歳〜44歳 男10.8年 女11.8年 男25.3年 女27.3年
45歳〜49歳 男9.0年 女9.9年 男21.8年 女23.8年
50歳〜54歳 男7.4年 女8.1年 男18.5年 女20.5年
55歳〜59歳 男6.2年 女6.7年 男15.7年 女17.8年
60歳〜64歳 男5.2年 女5.6年 男13.2年 女15.2年
65歳〜69歳 男4.4年 女4.8年 男11.0年 女13.2年
.......
−−−−−
このデータを孫引きしているサイトは他にも幾つかありますが、又聞きや孫引きで説得力があると思っているのも人が良いというか井戸端会議のノリで随分お気楽に断定的なことを書くものだという気がして不思議なのですけれども、まあそれは置いておくとして、この数字自体は確かに透析よりも移植の方がかなり有利だということを示しています。それは本当でしょうか?
出典の明示されていない数字など無視しても良いのですけれども、上記の数字を元に検索を掛けてみたところ、たぶんここが国内の発信源(の一つ)だろうというサイトのドキュメントを見付けました。
腎移植提供者の健康な生活の送り方
http://www.nagoya2.jrc.or.jp/kidney-center/topics/DonorSlide2004.11.23.pdf
このスライドの 7 ページ目に、
「血液透析と腎移植の期待される生存年数の違い」
というのがあり、この表に載っているデータの Asian の欄の数字が、上記のデータと全く同じです。図としてコピぺしておきます。(数字をマルで囲んでいるのは元々のスライドがそうなっています)
ではこの表の元になっているデータは何なのかというと、White とか Black とか N Am (Native Amarican?) とか、どうもアメリカのデータであることは間違いなさそうです。右下の「2003 USRDS」というのがヒントでしょう。
(つづく)
(透析と移植の余命比較 その2 USRDS)
USRDS というのは United States Renal Data System の略で、下記に WEB サイトがあります。
http://www.usrds.org/
直訳すれば、全米腎臓データシステム、数字は充分に信用がおけるものだと思われます。アメリカの成績としては、ですが。
さりながら、では、ということで2003年の年次報告(Anual Data Report)を読んでみると、あれ? と思わされます。下記の表(コピぺしておきます)が対応すると思うのですけれども、大筋でさほど違わないのですが、細かい数字が違うのですね。
http://www.usrds.org/2003/pdf/06_hosp_morte_03.pdf
Quick Links --> OUTCOMES: HOSPITALIZATION & MORTALITY
6.a Expected remaining lifetimes(years) or the general U.S. population, & of prevalent dialysis & tranplant patients
前後の年のデータも調べてみましたが、ジャストフィットというのはありませんでした。
どうも怪しげですが、とりあえず、この辺のデータを元に作成されていることは間違いないと思います。つまり、提示されているのは米国における成績に基づくデータです。
しかしながら、日本の透析の成績は世界一と言われています。アメリカは、たぶん、最低です。このデータだけで日本の透析患者の余命(運命)を語るのは適当とは思われません。
(つづく)
USRDS というのは United States Renal Data System の略で、下記に WEB サイトがあります。
http://www.usrds.org/
直訳すれば、全米腎臓データシステム、数字は充分に信用がおけるものだと思われます。アメリカの成績としては、ですが。
さりながら、では、ということで2003年の年次報告(Anual Data Report)を読んでみると、あれ? と思わされます。下記の表(コピぺしておきます)が対応すると思うのですけれども、大筋でさほど違わないのですが、細かい数字が違うのですね。
http://www.usrds.org/2003/pdf/06_hosp_morte_03.pdf
Quick Links --> OUTCOMES: HOSPITALIZATION & MORTALITY
6.a Expected remaining lifetimes(years) or the general U.S. population, & of prevalent dialysis & tranplant patients
前後の年のデータも調べてみましたが、ジャストフィットというのはありませんでした。
どうも怪しげですが、とりあえず、この辺のデータを元に作成されていることは間違いないと思います。つまり、提示されているのは米国における成績に基づくデータです。
しかしながら、日本の透析の成績は世界一と言われています。アメリカは、たぶん、最低です。このデータだけで日本の透析患者の余命(運命)を語るのは適当とは思われません。
(つづく)
(透析と移植の余命比較 その3 日本におけるデータ)
では日本の透析患者と移植患者の余命を解析したデータは存在しないのか? というと、透析患者の余命については日本透析医学会によるものが存在します。
2004年末調査項目に関する予後解析
(1) 透析人工における平均余命(図表37)
http://docs.jsdt.or.jp/overview/pdf2006/p43.pdf
一般人口に対する平均余命の割合として「ほぼ半分」という残念な数字が出ていますが、「移植を受けた人の半分」ではありませんし、米国のデータに比べれば遥かに長い(倍近い、つまり米国で移植を受けた人と同じくらいの)余命となっています。掲載されている表は細かすぎるので、比較のために年齢別の余命だけ抜粋しておきます。
年齢 透析 一般
男性 女性 男性 女性
30歳 27.36 30.35 49.23 55.97
35歳 23.72 26.47 44.43 51.08
40歳 20.54 23.19 39.67 46.22
45歳 17.30 20.10 35.01 41.41
50歳 14.55 16.74 30.47 36.68
55歳 12.06 13.92 26.12 32.04
60歳 9.87 11.31 21.98 27.49
65歳 7.86 9.04 18.02 23.04
70歳 6.24 7.11 14.35 18.75
75歳 4.77 5.67 11.09 14.72
日本における移植者の余命に関する統計解析データは存在しないようです。移植学会は生存率、生着率の方を重視しているように思われます。
私見ですが、移植の場合は15年生着率が50%を切っていることから分かるように透析に戻ることになる患者が多いので、平均余命を計算することにあまり意味が無いのではないかと考えられます。一度移植を受けたからと言ってそのまま死ぬまでその腎臓が機能する人というのは、かなりラッキーと言って差し支えないと思います。
(この項終わり)
では日本の透析患者と移植患者の余命を解析したデータは存在しないのか? というと、透析患者の余命については日本透析医学会によるものが存在します。
2004年末調査項目に関する予後解析
(1) 透析人工における平均余命(図表37)
http://docs.jsdt.or.jp/overview/pdf2006/p43.pdf
一般人口に対する平均余命の割合として「ほぼ半分」という残念な数字が出ていますが、「移植を受けた人の半分」ではありませんし、米国のデータに比べれば遥かに長い(倍近い、つまり米国で移植を受けた人と同じくらいの)余命となっています。掲載されている表は細かすぎるので、比較のために年齢別の余命だけ抜粋しておきます。
年齢 透析 一般
男性 女性 男性 女性
30歳 27.36 30.35 49.23 55.97
35歳 23.72 26.47 44.43 51.08
40歳 20.54 23.19 39.67 46.22
45歳 17.30 20.10 35.01 41.41
50歳 14.55 16.74 30.47 36.68
55歳 12.06 13.92 26.12 32.04
60歳 9.87 11.31 21.98 27.49
65歳 7.86 9.04 18.02 23.04
70歳 6.24 7.11 14.35 18.75
75歳 4.77 5.67 11.09 14.72
日本における移植者の余命に関する統計解析データは存在しないようです。移植学会は生存率、生着率の方を重視しているように思われます。
私見ですが、移植の場合は15年生着率が50%を切っていることから分かるように透析に戻ることになる患者が多いので、平均余命を計算することにあまり意味が無いのではないかと考えられます。一度移植を受けたからと言ってそのまま死ぬまでその腎臓が機能する人というのは、かなりラッキーと言って差し支えないと思います。
(この項終わり)
万波さん他の論文
万波さんについてのトピックでも紹介しましたが。
American Journal of Transplantation の2008年の4月号に載った、万波さん他の論文です。
一般の人もサイトで読めるようになっています。
Last Resort for Renal Transplant Recipients, 'Restored Kidneys' from Living Donors/Patients
M. Mannami, R. Mannami, N. Mitsuhata, M. Nishi, Y. Tsutsumi, K. Nanba and S. Fujita
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119424314/HTMLSTART
“Received 30 October 2007, revised 11 December 2007”とあるのは、最初の投稿後、インフォームドコンセントに関する査読者からの質問に対応したことを反映しているようですね。
これもあちらでも紹介しましたが。
同年11月号には移植学会の高原さん達による突っ込みが、編集者へのレターとして掲載されています。
Living Unrelated Kidney Transplantation from a Donor with Ureteral Cancer Jeopardizes Survival of Donor and Recipient
S. Takahara, T. Nakatani, K. Yoshida and S. Teraoka
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121433658/HTMLSTART
万波さんについてのトピックでも紹介しましたが。
American Journal of Transplantation の2008年の4月号に載った、万波さん他の論文です。
一般の人もサイトで読めるようになっています。
Last Resort for Renal Transplant Recipients, 'Restored Kidneys' from Living Donors/Patients
M. Mannami, R. Mannami, N. Mitsuhata, M. Nishi, Y. Tsutsumi, K. Nanba and S. Fujita
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119424314/HTMLSTART
“Received 30 October 2007, revised 11 December 2007”とあるのは、最初の投稿後、インフォームドコンセントに関する査読者からの質問に対応したことを反映しているようですね。
これもあちらでも紹介しましたが。
同年11月号には移植学会の高原さん達による突っ込みが、編集者へのレターとして掲載されています。
Living Unrelated Kidney Transplantation from a Donor with Ureteral Cancer Jeopardizes Survival of Donor and Recipient
S. Takahara, T. Nakatani, K. Yoshida and S. Teraoka
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121433658/HTMLSTART
(移植の生存率と生着率 日本のデータ)
2008年の移植学会のファクトブックの↓のページに数字が出ています。
腎臓
8.腎移植成績
http://www.asas.or.jp/jst/factbook/2008/fact06_03_2.html
−−−−−
●生存率:14,165例(生体腎移植10,644例、献腎移植3,521例)について生存率を調査しています。生体腎移植では1年95.3%、5年90.7%、10年84.8%、15年79.4%、20年73.0%です。また、献腎移植では1年90.4%、5年83.4%、10年76.5%、15年69.5%、20年63.4%です(図4)。
●生着率:13,614例(生体腎移植10,175例、献腎移植3,439例)について生着率を調査しています。生体腎移植では1年93.4%、5年81.7%、10年65.6%、15年51.8%、20年40.3%です。また、献腎移植では1年82.8%、5年65.8%、10年50.2%、15年38.8%、20年31.1%です(図5)。
−−−−−
2008年の移植学会のファクトブックの↓のページに数字が出ています。
腎臓
8.腎移植成績
http://www.asas.or.jp/jst/factbook/2008/fact06_03_2.html
−−−−−
●生存率:14,165例(生体腎移植10,644例、献腎移植3,521例)について生存率を調査しています。生体腎移植では1年95.3%、5年90.7%、10年84.8%、15年79.4%、20年73.0%です。また、献腎移植では1年90.4%、5年83.4%、10年76.5%、15年69.5%、20年63.4%です(図4)。
●生着率:13,614例(生体腎移植10,175例、献腎移植3,439例)について生着率を調査しています。生体腎移植では1年93.4%、5年81.7%、10年65.6%、15年51.8%、20年40.3%です。また、献腎移植では1年82.8%、5年65.8%、10年50.2%、15年38.8%、20年31.1%です(図5)。
−−−−−
(臓器移植ガイドライン改定時の経緯)
病気腎移植は臨床研究以外禁止、という方針になった会議の議事録です。
07/04/23 第25回臓器移植委員会議事録について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/txt/s0423-2.txt
関連資料は下記から落とせます。
第25回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会資料(平成19年4月23日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/
中でも↓の資料は、役に立つと思います。
資料1:臓器の移植に関する法律違反事件について
資料2:病腎移植に係る調査等の状況について
資料3:病腎移植に関する学会声明について(概要)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/$FILE/20070425_4shiryou1~3.pdf
参考資料4:患者から摘出された腎臓の移植に関する調査班報告書
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/$FILE/20070425_4sankou4.pdf
参考資料5:病気腎移植に係る調査委員会報告書(香川労災病院)
参考資料6:市立宇和島病院で実施された病腎移植における生存率・生着率について
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/$FILE/20070425_4sankou5~6.pdf
病気腎移植は臨床研究以外禁止、という方針になった会議の議事録です。
07/04/23 第25回臓器移植委員会議事録について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/txt/s0423-2.txt
関連資料は下記から落とせます。
第25回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会資料(平成19年4月23日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/
中でも↓の資料は、役に立つと思います。
資料1:臓器の移植に関する法律違反事件について
資料2:病腎移植に係る調査等の状況について
資料3:病腎移植に関する学会声明について(概要)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/$FILE/20070425_4shiryou1~3.pdf
参考資料4:患者から摘出された腎臓の移植に関する調査班報告書
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/$FILE/20070425_4sankou4.pdf
参考資料5:病気腎移植に係る調査委員会報告書(香川労災病院)
参考資料6:市立宇和島病院で実施された病腎移植における生存率・生着率について
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/555df304e3d74013492572c800215580/$FILE/20070425_4sankou5~6.pdf
(ニコル教授の研究レポート)
小さな癌を取り除いた腎臓の移植は“安全である”ということでよく引合いに出されるオーストラリアのニコル教授による研究レポートです。
Kidneys from patients with small renal tumours: a novel source of kidneys for transplantation
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119879083/HTMLSTART
David L. Nicol, John M. Preston, Daryl R. Wall, Anthony D. Griffin, Scott B. Campbell, Nicole M. Isbel, Carmel M. Hawley and David W. Johnson
リンク先はアブストラクトだけでなく本文も読めます。
少し解説しておきますと、ニコル教授らは病気腎を使うことのリスクを考慮していて、レシピエントは高齢か又は重い併存疾患があるなどの、死体腎の提供を待っていたのではその間(豪州では3〜4年くらい)に亡くなってしまう可能性が高い人に限られています。術後のレシピエントのフォローアップは3ヶ月に一回の割合で実施されています。
43人中4人は移植とは関係ない病気で死亡、移植した腎臓の生着が確認されている期間は中央値が25ヶ月、平均が32ヶ月、一人は移植の9年後に癌を再発するも経過観察18ヶ月で生存中です。
推測ですが、癌が一人しか再発していないのはまだ移植されてからの期間が長い人自体が少ないことによるのかも知れません。この論文は1996年から2007年の症例の記録ですから、9年で癌発症してその後1年半経過観察という方はほとんど第1号の移植者の筈です。生着確認期間の平均値/中央値の短さから見て、症例の多くは比較的最近になって実施されているということなのでしょう。
この論文の後ろには(なとろむさんも随所で紹介されている通り)少々辛口の EDTIORIAL COMMENT が付いています。この論文でのレシピエントのリスク評価は妥当であり、かつドナーに対する著者らの説明や治療にかけた労力は賞賛されるべきとしながらも、“These patients are primarily 'kidney tumour patients' first and part of the expanded criteria for living donors only secondarily.”と注意を喚起しています。
コメントの最後は、“Failure to proceed in what is perceived as an ethically justifiable manner might disrupt public trust in the transplantation system, with far reaching adverse affects.”で締められています。倫理的に疑念を持たれるようなうかつなことをやると移植医療自体の信頼を無くすという懸念は、洋の東西(日豪だと南北?)を問わないようです。
小さな癌を取り除いた腎臓の移植は“安全である”ということでよく引合いに出されるオーストラリアのニコル教授による研究レポートです。
Kidneys from patients with small renal tumours: a novel source of kidneys for transplantation
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119879083/HTMLSTART
David L. Nicol, John M. Preston, Daryl R. Wall, Anthony D. Griffin, Scott B. Campbell, Nicole M. Isbel, Carmel M. Hawley and David W. Johnson
リンク先はアブストラクトだけでなく本文も読めます。
少し解説しておきますと、ニコル教授らは病気腎を使うことのリスクを考慮していて、レシピエントは高齢か又は重い併存疾患があるなどの、死体腎の提供を待っていたのではその間(豪州では3〜4年くらい)に亡くなってしまう可能性が高い人に限られています。術後のレシピエントのフォローアップは3ヶ月に一回の割合で実施されています。
43人中4人は移植とは関係ない病気で死亡、移植した腎臓の生着が確認されている期間は中央値が25ヶ月、平均が32ヶ月、一人は移植の9年後に癌を再発するも経過観察18ヶ月で生存中です。
推測ですが、癌が一人しか再発していないのはまだ移植されてからの期間が長い人自体が少ないことによるのかも知れません。この論文は1996年から2007年の症例の記録ですから、9年で癌発症してその後1年半経過観察という方はほとんど第1号の移植者の筈です。生着確認期間の平均値/中央値の短さから見て、症例の多くは比較的最近になって実施されているということなのでしょう。
この論文の後ろには(なとろむさんも随所で紹介されている通り)少々辛口の EDTIORIAL COMMENT が付いています。この論文でのレシピエントのリスク評価は妥当であり、かつドナーに対する著者らの説明や治療にかけた労力は賞賛されるべきとしながらも、“These patients are primarily 'kidney tumour patients' first and part of the expanded criteria for living donors only secondarily.”と注意を喚起しています。
コメントの最後は、“Failure to proceed in what is perceived as an ethically justifiable manner might disrupt public trust in the transplantation system, with far reaching adverse affects.”で締められています。倫理的に疑念を持たれるようなうかつなことをやると移植医療自体の信頼を無くすという懸念は、洋の東西(日豪だと南北?)を問わないようです。
47NEWSに2006年頃の、万波さん絡みの記事が幾つか残っています。
万波医師、“密室”手術 腎移植、グループ3人で
http://www.47news.jp/CN/200611/CN2006110901000104.html
−−−−−(一部引用)
当時の院長によると、院長は03年初め、移植医療の後継者が育たないのを心配し、泌尿器科の科長だった万波医師に3人による閉鎖的な手術の中止、患者の同意書の作成や日本移植学会への加入など、5項目を勧告したという。勧告後、同意をめぐる患者とのやりとりは若い医師が記録するようになり改善されたが、万波医師は、手術については「3人にしかできない」と言って従わず、学会にも加入しなかった。万波医師は04年3月、定年まで約2年を残して、30年以上勤めた同病院を辞め、翌月開業した宇和島徳洲会に移った。万波医師は「基本的に(派遣された)愛媛大の医師と手術をしていた。大きな手術のときは弟に応援を頼んだ」と閉鎖性を否定している。
−−−−−
「病気腎移植知っていた」 市立病院の元同僚ら証言
http://www.47news.jp/CN/200611/CN2006111701000015.html
−−−−(一部引用)
50代の元看護師は「一例しか知らないが、泌尿器科は多くの看護師が知っていた」と振り返った。「戻せる腎臓は(摘出した患者に)戻さないと。したらいかん」。こう忠告したこともあったが、万波医師は「この人では駄目だけど、別の人に植えたら再生する可能性がある」と言い、ためらいはなかったという。「患者を助けたい一心だったのでは」と話した。一方、市立病院に医師を派遣していた愛媛大の元医師は「派遣医を通じ、大学でも万波医師の病気腎移植は知られていた」と明かした。「最初に聞いた時は『本当にいいの』と思った。反対意見はなかなか言いにくいと思う。治療方針に文句を言ったら手術や診断をさせてもらえなくなる」と話した。
−−−−−
万波医師の退任を要求 03年、市立病院に愛媛大
http://www.47news.jp/CN/200611/CN2006111301000005.html
−−−−−(一部引用)
大学側は「病気腎移植は適当ではない。万波医師とは意見が合わない。辞めさせないと医師の派遣はしない」と迫った。大学側は、万波医師が派遣された若い医師の教育に熱心でなく、後継者を育てないことも問題点として挙げたという。これを受けて当時の院長は、万波医師に手術態勢の改善などを勧告したが、万波医師は聞き入れなかったという。万波医師は当時、腎移植の多くを弟の廉介医師(60)や呉共済病院(広島県呉市)の光畑直喜医師(58)と行い、大学の派遣医師らは縫合などを担当していた。大学側は派遣を終えて戻った医師らを通じ、病気腎移植の事実を知ったとみられる。
−−−−−
一番上の記事によれば、移植学会への入会は断っていたのというのが真相みたいです。学会に加入したら学会員として生体移植の倫理指針に従う必要が出てきますから、好き放題やりたい人にとっては加入するメリットは少ないでしょう。巷間言われているように「会費を納めないでいたら云々」というのも過去に退会した時の事情としては本当なのでしょうけど、それだけではないのではないかと思います。
また、院長の話と万波さんの話とは随分ニュアンスが違いますが、下の記事の同僚の方の発言や愛媛大の医師引き揚げの件も含めて整合的なのは、私は院長の話の方だと思います。院長からも、愛媛大学からも、2003年当時から、その閉鎖性や病気腎移植の実施について問題視されていた、ということでしょう。
万波医師、“密室”手術 腎移植、グループ3人で
http://www.47news.jp/CN/200611/CN2006110901000104.html
−−−−−(一部引用)
当時の院長によると、院長は03年初め、移植医療の後継者が育たないのを心配し、泌尿器科の科長だった万波医師に3人による閉鎖的な手術の中止、患者の同意書の作成や日本移植学会への加入など、5項目を勧告したという。勧告後、同意をめぐる患者とのやりとりは若い医師が記録するようになり改善されたが、万波医師は、手術については「3人にしかできない」と言って従わず、学会にも加入しなかった。万波医師は04年3月、定年まで約2年を残して、30年以上勤めた同病院を辞め、翌月開業した宇和島徳洲会に移った。万波医師は「基本的に(派遣された)愛媛大の医師と手術をしていた。大きな手術のときは弟に応援を頼んだ」と閉鎖性を否定している。
−−−−−
「病気腎移植知っていた」 市立病院の元同僚ら証言
http://www.47news.jp/CN/200611/CN2006111701000015.html
−−−−(一部引用)
50代の元看護師は「一例しか知らないが、泌尿器科は多くの看護師が知っていた」と振り返った。「戻せる腎臓は(摘出した患者に)戻さないと。したらいかん」。こう忠告したこともあったが、万波医師は「この人では駄目だけど、別の人に植えたら再生する可能性がある」と言い、ためらいはなかったという。「患者を助けたい一心だったのでは」と話した。一方、市立病院に医師を派遣していた愛媛大の元医師は「派遣医を通じ、大学でも万波医師の病気腎移植は知られていた」と明かした。「最初に聞いた時は『本当にいいの』と思った。反対意見はなかなか言いにくいと思う。治療方針に文句を言ったら手術や診断をさせてもらえなくなる」と話した。
−−−−−
万波医師の退任を要求 03年、市立病院に愛媛大
http://www.47news.jp/CN/200611/CN2006111301000005.html
−−−−−(一部引用)
大学側は「病気腎移植は適当ではない。万波医師とは意見が合わない。辞めさせないと医師の派遣はしない」と迫った。大学側は、万波医師が派遣された若い医師の教育に熱心でなく、後継者を育てないことも問題点として挙げたという。これを受けて当時の院長は、万波医師に手術態勢の改善などを勧告したが、万波医師は聞き入れなかったという。万波医師は当時、腎移植の多くを弟の廉介医師(60)や呉共済病院(広島県呉市)の光畑直喜医師(58)と行い、大学の派遣医師らは縫合などを担当していた。大学側は派遣を終えて戻った医師らを通じ、病気腎移植の事実を知ったとみられる。
−−−−−
一番上の記事によれば、移植学会への入会は断っていたのというのが真相みたいです。学会に加入したら学会員として生体移植の倫理指針に従う必要が出てきますから、好き放題やりたい人にとっては加入するメリットは少ないでしょう。巷間言われているように「会費を納めないでいたら云々」というのも過去に退会した時の事情としては本当なのでしょうけど、それだけではないのではないかと思います。
また、院長の話と万波さんの話とは随分ニュアンスが違いますが、下の記事の同僚の方の発言や愛媛大の医師引き揚げの件も含めて整合的なのは、私は院長の話の方だと思います。院長からも、愛媛大学からも、2003年当時から、その閉鎖性や病気腎移植の実施について問題視されていた、ということでしょう。
(難波紘二教授の文章)
「瀬戸内グループ」による病腎移植成績の予備解析結果について
(☆宇和島事件で気づいたこと)
http://www.kenkoude.com/ishoku/dr_nanba.htm
なぜか漬物屋さんのサイトに置いてあるのですが、Google 検索ではトップに来ます。
下記は広島県医師会速報に載っている特別寄稿です。
私は病理学者・生命倫理学者として「病腎移植」を支持する(I)
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/2007/0425/1973_020.pdf
(第1973号 2007年4月25日)
私は病理学者・生命倫理学者として「病腎移植」を支持する(II)
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/2007/0515/1975_017.pdf
(第1975号 2007年5月15日)
「瀬戸内グループ」による病腎移植成績の予備解析結果について
(☆宇和島事件で気づいたこと)
http://www.kenkoude.com/ishoku/dr_nanba.htm
なぜか漬物屋さんのサイトに置いてあるのですが、Google 検索ではトップに来ます。
下記は広島県医師会速報に載っている特別寄稿です。
私は病理学者・生命倫理学者として「病腎移植」を支持する(I)
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/2007/0425/1973_020.pdf
(第1973号 2007年4月25日)
私は病理学者・生命倫理学者として「病腎移植」を支持する(II)
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/2007/0515/1975_017.pdf
(第1975号 2007年5月15日)
BBCニュースより
'Risky donor' kidney transplants prove successful
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8398770.stm
ボルチモアのメリーランド大学で病腎移植。n=5。腫瘍径は1cm〜2.3cm。3つが癌、2つが良性腫瘍。5人中1人が病気とは無関係な事故で死亡。4人は生存。観察期間は9〜41ヶ月。
"controversial transplant technique"と表現されています。「海外では病腎移植は普通に行われている」とときに主張されることがありますが、誤りです。
"It is important though that the potential risks and benefits are fully discussed with the donor and recipient"。当たり前ですね。
毎度のことですが、こういうニュースのたびに、万波医師擁護と日本移植学会批判がなされるのですが、こういった海外の病腎移植と、万波医師による移植の何が違っていたのか、いまだにご理解されていないのでしょうね。
'Risky donor' kidney transplants prove successful
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8398770.stm
ボルチモアのメリーランド大学で病腎移植。n=5。腫瘍径は1cm〜2.3cm。3つが癌、2つが良性腫瘍。5人中1人が病気とは無関係な事故で死亡。4人は生存。観察期間は9〜41ヶ月。
"controversial transplant technique"と表現されています。「海外では病腎移植は普通に行われている」とときに主張されることがありますが、誤りです。
"It is important though that the potential risks and benefits are fully discussed with the donor and recipient"。当たり前ですね。
毎度のことですが、こういうニュースのたびに、万波医師擁護と日本移植学会批判がなされるのですが、こういった海外の病腎移植と、万波医師による移植の何が違っていたのか、いまだにご理解されていないのでしょうね。
病腎移植再開のニュースです。
万波医師ら執刀、臨床研究で病気腎移植再開(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091231-OYT1T00376.htm?from=rss&ref=rssad
===========
病気で摘出した腎臓を他人に移植する「病気腎移植」を、宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師(69)らが臨床研究として再開した、と徳洲会グループが31日発表した。
病気腎移植の再開は2006年9月以来。徳洲会は今後5年以内に5件を行い、保険適用をめざすという。厚生労働省は「臨床研究のルールに従い、双方の患者に十分な説明をして同意を得たのか、事情を聞きたい」としている。
徳洲会によると、提供者は呉共済病院(広島県呉市)に入院中の50歳代男性。片方の腎臓に直径4センチ以下の小さめのがんがあり、がんの部位を切除した上で万波医師が30日、40歳代の腎臓病の男性に移植した。
提供者は腎臓の一部だけ切除する方法の選択肢も示されたうえで摘出に同意したという。一方、移植された男性は、外部委員を含む「修復腎検討委員会」の審査で、登録した26人から選ばれた。
===========
「やっと正しい形に戻ったな」というブックマークコメントがついていました。私も同感です。きちんと手続きを踏んで、実績を積み上げていってほしいです。
万波医師ら執刀、臨床研究で病気腎移植再開(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091231-OYT1T00376.htm?from=rss&ref=rssad
===========
病気で摘出した腎臓を他人に移植する「病気腎移植」を、宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師(69)らが臨床研究として再開した、と徳洲会グループが31日発表した。
病気腎移植の再開は2006年9月以来。徳洲会は今後5年以内に5件を行い、保険適用をめざすという。厚生労働省は「臨床研究のルールに従い、双方の患者に十分な説明をして同意を得たのか、事情を聞きたい」としている。
徳洲会によると、提供者は呉共済病院(広島県呉市)に入院中の50歳代男性。片方の腎臓に直径4センチ以下の小さめのがんがあり、がんの部位を切除した上で万波医師が30日、40歳代の腎臓病の男性に移植した。
提供者は腎臓の一部だけ切除する方法の選択肢も示されたうえで摘出に同意したという。一方、移植された男性は、外部委員を含む「修復腎検討委員会」の審査で、登録した26人から選ばれた。
===========
「やっと正しい形に戻ったな」というブックマークコメントがついていました。私も同感です。きちんと手続きを踏んで、実績を積み上げていってほしいです。
病腎移植再開 万波医師が記者会見 「捨てる腎臓の再利用であり、いいことだ」(産経)
万波医師ら執刀、臨床研究で病気腎移植再開(読売新聞)
http://sankei.jp.msn.com/science/science/091231/scn0912311944001-n1.htm
===========
「修復腎(病腎)移植は捨てる腎臓の再利用であり、いいことだ」。約3年半ぶりの病腎移植手術から一夜明けた31日、執刀医の宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師は記者会見でこう語り、病腎移植への決意を改めて示した。
平成18年10月、臓器移植法違反容疑で愛媛県警に逮捕された患者の腎臓移植手術の執刀が発覚したことを契機に、学会などから医学的妥当性を否定され続けた万波医師。この日の記者会見には白衣姿で臨み、臨床研究第1例目となる病腎移植手術を実施したことを公表し、「患者の容体は問題ありません」などと移植の意義を強調した。
病院によると、移植手術を受けた40代の男性患者は術後の経過は良好で、すでに集中治療室から一般病棟へと移り、早ければ3〜4週間で退院できるという。
===========
産経ではこんな感じです。レシピエントの術後の経過は良好とのことで喜ばしいことです。レシピエント側の問題としては癌の持ち込み再発の確率が本当に低いのかが、これからの課題でしょう。
万波医師ら執刀、臨床研究で病気腎移植再開(読売新聞)
http://sankei.jp.msn.com/science/science/091231/scn0912311944001-n1.htm
===========
「修復腎(病腎)移植は捨てる腎臓の再利用であり、いいことだ」。約3年半ぶりの病腎移植手術から一夜明けた31日、執刀医の宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師は記者会見でこう語り、病腎移植への決意を改めて示した。
平成18年10月、臓器移植法違反容疑で愛媛県警に逮捕された患者の腎臓移植手術の執刀が発覚したことを契機に、学会などから医学的妥当性を否定され続けた万波医師。この日の記者会見には白衣姿で臨み、臨床研究第1例目となる病腎移植手術を実施したことを公表し、「患者の容体は問題ありません」などと移植の意義を強調した。
病院によると、移植手術を受けた40代の男性患者は術後の経過は良好で、すでに集中治療室から一般病棟へと移り、早ければ3〜4週間で退院できるという。
===========
産経ではこんな感じです。レシピエントの術後の経過は良好とのことで喜ばしいことです。レシピエント側の問題としては癌の持ち込み再発の確率が本当に低いのかが、これからの課題でしょう。
FAQですが、「なぜ移植学会は病腎移植を推進しようとしないのか?」という質問に対する答えの一つ。
[病気腎移植の行方―臨床研究を前に](7)保険適用 規制の壁 承認へ道遠く
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/zokibaibai/ren101200910283132.html
===========
また、今回ゴーサインが出た臨床研究で対象となる提供腎臓の小さながん(4センチ以下)の治療法が変化し、対象腎臓自体が出なくなるとの指摘もある。県内のある泌尿器科医は「総合病院ではここ3年、小さながんは全摘出ではなく内視鏡などによる部分切除が主流で、今後広がるだろう。全摘の方がリスクが高く、きちんと説明をすれば、全摘を選択する患者はほとんどいなくなるのでは」と話し、一般的な医療としての普及には懐疑的な見方を示した。
===========
10年前ならともかく、部分切除のほうが予後がよさそうだという知見が集積しつつある現在、病腎移植ドナーとなりうる片腎全摘症例はかなり減ってきています。
[病気腎移植の行方―臨床研究を前に](7)保険適用 規制の壁 承認へ道遠く
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/zokibaibai/ren101200910283132.html
===========
また、今回ゴーサインが出た臨床研究で対象となる提供腎臓の小さながん(4センチ以下)の治療法が変化し、対象腎臓自体が出なくなるとの指摘もある。県内のある泌尿器科医は「総合病院ではここ3年、小さながんは全摘出ではなく内視鏡などによる部分切除が主流で、今後広がるだろう。全摘の方がリスクが高く、きちんと説明をすれば、全摘を選択する患者はほとんどいなくなるのでは」と話し、一般的な医療としての普及には懐疑的な見方を示した。
===========
10年前ならともかく、部分切除のほうが予後がよさそうだという知見が集積しつつある現在、病腎移植ドナーとなりうる片腎全摘症例はかなり減ってきています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
病気腎移植を冷静に語る 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
病気腎移植を冷静に語るのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170671人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人