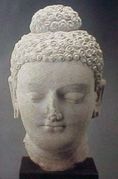(続き)
6.無上士 如来・阿羅漢・三摩三仏陀
無上士:アヌッタラ、anuttara、「無上の人」。ウッタラ(より上の、uttara)の否定形。より上がない。最高の。
原始仏典における定義で「アヌッタラ」そのものに相当する定義はないのですが、ほとんどそれの解説であるような記述を紹介します。最高者を意味する「アッガ(agga)」です。
「174.比丘たちよ、一人が世に生まれるのは二つなく、仲間なく、似るものなく、同等のものなく、対抗するものなく、比肩者なく、等しいものなく、等しく同じものがない二足中の最高者が生まれて来るのである。誰が一人か。
如来・阿羅漢・三摩三仏陀である。
比丘たちよ、この一人が世に生まれるのは二つなく、仲間なく、似るものなく、同等のものなく、対抗するものなく、比肩者なく、等しいものなく、等しく同じものがない二足中の最高者が生まれて来るのである」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P32 に相当
7.調御丈夫 有学を順序よく学ばせて行く者
調御丈夫:プリサ・ダンマ・サーラティ、purisa damma sārathi、「調御されるべき人の調御者」。プリサは「人」、ダンマは「調御されるべき」(ダンマティ、dammati「馴らされる」の未来受動・義務)、サーラティは「御者・調御者」。
原始仏典における定義で「プリサ・ダンマ・サーラティ」そのものに相当する定義はないのですが、それに近い記述を紹介します。
「 中部経典 第107経 算術家モッガーラナ経[ガナカ・モッガーラナ・スッタ]
・・・省略・・・
バラモン、この法・律においても順序のある学があり、順序のある行があり、順序のある行道を設定することができる。
バラモン、たとえば熟練した馬の調教者(ダンマカ、dammaka)は吉祥な良い生まれの馬を獲得して、最初にくつわをはめてから、さらにより上のことを為す。
バラモン、このように如来は調御されるべき人(プリサダンマ)を獲得して最初にこのように調伏する(ヴィネーティ、vineti、訓練指導する、制御する、律[vinaya]の関連語)。
「比丘よ、さああなたは戒を具足し、パーティモッカ律儀に律儀されて住し、行と行境を具足して、微細な罪にも恐怖を見て、学足を取って学びなさい」と。
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは根を防護し・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは食において量を知り・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは眠らないことと結合して住し・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは念・自覚を成就して・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは遠離の座臥を受用し・・・(断五蓋・四禅の記述)・・・」
『南伝大蔵経11上 中部経典3』大蔵出版 P348−355 に相当
このように順序ある調伏・制御を続けて、「これらの教えは有学においては無上の安穏との結合に資するし、無学の阿羅漢においては現法楽住と念自覚に資する」と続きます。つまり、阿羅漢になっても修行は有益だということです。
さらにバラモンが質問します(会話内容は僕が省略して書いています)。
「卿ゴータマ、どうしてある者は涅槃を得て、ある者は涅槃を得ないのでしょうか」
「バラモン、あなたはラージャガハへの道を知るか」
「卿ゴータマ、知っています」
「バラモン、ラージャガハに行きたい人があなたに道を聞き、あなたは道を教えるが彼はあなたが教えたのと違う方向へ行く。
もう一人が同じようにあなたに道を聞くが、彼はあなたが教えた通りの方向へ行き無事にラージャガハに着く。
バラモン、ラージャガハは確かに存在するし、ラージャガハへの道も確かに存在するし、あなたは確かに正しく導く者である。
バラモン、それなのに何が原因で一人はラージャガハに着かず、別の一人は無事にラージャガハに着くのか」
「卿ゴータマ、私に何ができるでしょうか。卿ゴータマ、私は道を教えるだけなのです」
「バラモン、まさにそのように涅槃は確かに存在し、涅槃に行く道も確かに存在し、私は確かに正しく導くものである。
そして私の弟子たちはこのように教誡されるが、ある者は涅槃を得ず、ある者は涅槃を得る。
バラモン、これを私はどうするのか。バラモン、私は道を教えるのみなのだ」
中部経典第65経「バッダーリ・スッタ」の後半も馬の調教にたとえて、比丘が完全に調教されると無学の十法(無学の正見正思・・・正定正智正解脱)を成就するという記述があります。無学になれば調教する必要はありません。また凡夫は「学ぶべきでもなく、学ぶ必要がないのでもない者」なので調御丈夫の調教対象ではありません。調御丈夫というのは凡夫を調教する人ではなく「有学を調教する人」です。
中部経典第125経「ダンタブーミ・スッタ(調御地経)」も比丘を象や牛の調教にたとえて、繰り返し「その彼を如来はさらに調御する」という記述が出て来ます(南伝11下P154−168)。その中で「漏が尽きていない比丘→調御されていない」、「漏が尽きた比丘→調御されている」と表現されていますので、「調教=漏尽のため」ということがわかります。漏尽に達すれば、とりあえず調教は終わりです。
8.天人師 神々と人々の師
天人師:サッター・デーヴァマヌッサーナム、satthar devamanussānaṃ、「神々と人々の師」。サッターは「師、大師、教師、教主」、デーヴァマヌッサで「神と人」。
原始仏典における定義で「天人師」そのものの記述はありません。ただ多くの神々が帰依し、多くの人々が帰依しているという記述は随所にあります。
9.仏陀 独力で覚った者
仏陀:ブッダ、buddha、「覚った人」。
原始仏典における定義は以下の通りです。
「比丘たちよ、これら二人はブッダである。誰が二人か。
如来・阿羅漢・三摩三仏陀と、単独仏陀(独覚)である。
比丘たちよ、これら二人はブッダである」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P119 に相当
単独仏陀の原語は「パッチェーカ・ブッダ(pacceka buddha)」。パッチェーカは「単独、独一」という意味。僕は「ブッダ」という原語を際立たせたいので「単独仏陀」と訳しています。「単独梵天」(pacceka brahmā)という言葉もあります。上の記述から「ブッダ」という言葉は、「独力で覚った人」という意味合いが強いと思います。そうすると「三摩三仏陀」は「独力で覚り且つ他者を導く者」という意味になります。
聖者 >阿羅漢>ブッダ >サンマー・サンブッダ(男性のみ) 調御丈夫
>パッチェーカ・ブッダ(性別の記述なし)調御しない者
>如来弟子>比丘 調御された人
>比丘尼 調御された人
>有学 >如来弟子>比丘 調御されるべき人
>比丘尼 調御されるべき人
>優婆塞 調御されるべき人
>優婆夷 調御されるべき人
(非人も含めるべきかも知れません)
凡夫 >正見者→輪廻に導く正見がある外の者、いわゆる「外道」。
梵身天などへの転生者あり。たとえばイエスなど。
菩薩になる前のゴータマも外道だった。
>邪見者→地獄・畜生に行くしかない邪見者、あえて名付けるなら「邪道」。
凡夫を二種類に分ける分類は原始仏典にはなく、僕が原始仏典の記述から凡夫を善人と勝手に分けました。原始仏典では「凡夫」と一括りです。
10.先生 バガヴァント
先生:バガヴァント、bhagavant、薄伽梵とも音写。バガ(bhaga)が「幸運、福運」でヴァントで「人」。バッダ(bhadda)が「賢い、吉祥の」。吉祥なる人。
従来は「世尊」と訳され、呼びかける語形では「大徳」(バンテー bhante)と訳されていました。「大徳」と呼ばれるのはブッダだけではなく、新参比丘が長老比丘を呼びかけるときも「大徳(先生)」と呼ばれます。原始仏典における定義で「バガヴァント」そのものの記述はなかったように思います。また見つけたらアップしようと思います。
・訳語 『世尊・大徳』→『先生』に変更
http://
00.如来 その通りに覚り、語り、行い、実現する者
如来:タターガタ、tathāgata、「その通りに行く者」。タターは「かく、その如くに」。ガタは「行った」。
原始仏典における定義は以下の通りです。
「 第三 世
23.比丘たちよ、如来は世間を覚り、如来は世間から離結する。
比丘たちよ、如来は世間の集を覚り、如来は世間の集を断つ。
比丘たちよ、如来は世間の滅を覚り、如来は世間の滅を実証する。
比丘たちよ、如来は世間の滅に行く道を覚り、如来は世間の滅に行く道を修習する。
比丘たちよ、神々とマーラとブラフマーと沙門婆羅門とともである世間に生まれた者たちと神々と人々が見たもの、聞いたもの、思ったこと、認識したこと、得たもの、求めたもの、意によって随伺したもの、その一切を如来は覚る。それゆえに「如来」と言われる。
比丘たちよ、如来が無上の正しい覚りを覚った夜から、無余依の涅槃界に涅槃する夜までのこの間に説き、話し、解説する一切はまさにその通りのことであって、他のことではない。それゆえに「如来」と言われる。
比丘たちよ、如来は言う通りにその通りに行い、行う通りにその通りに言う。この言う通りにその通りに行い、行う通りにその通りに言うこと。それゆえに「如来」と言われる。
比丘たちよ、神々とマーラとブラフマーと沙門婆羅門とともである世間に生まれた者たちと神々と人々に如来は勝利し、勝利されず、全てを見て、自在である。それゆえに「如来」と言われる。
一切の世間を超知し 一切の世間においてその通りである
一切の世間を離結し 一切の世間を取ることがない
彼は一切に勝利する勇者であり 一切の縛から解放されている
・・・(偈は続きます)」
『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P42 に相当
「比丘たちよ、『沙門』[サマナ samaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『婆羅門』[ブラーフマナ brāhmaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『明知者』[ヴェーダグー vedagū]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『医者』[ビサッカ bhisakka]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『無垢者』[ニンマラ nimmala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『離垢者』[ヴィマラ vimala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『知者』[ニャーニン ñāṇin]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『解脱者』[ヴィムッタ vimutta]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
沙門として得るべきもの、婆羅門が完成すべきもの
明知者として得るべきもの、医者として無上の者
無垢者として得るべきもの、離垢者が清浄とすべきもの
そして知者として得るべきもの、解脱者として無上の者
その私は戦に勝利し、私は束縛から脱して解脱した
私は最上に調御された象であり、般涅槃した無学である」
『南伝大蔵経21 増支部経典5』大蔵出版 P305−306 に相当
事実・現実・真実の通りにそれを覚ることが一つ目。
説法内容が完全に真実の通りであることが二つ目。
言行一致であることが三つ目。
自在者であるゆえにその通りに実現できるということで四つ目。
これが如来と言われるゆえんであるということです。
後半の引用は如来・阿羅漢・三摩三仏陀の八つの別名で増支部経典八集にあります。
・如来転生法 大人二十戒 → 三十二相+出家 → 成仏
長部経典第30経「ラッカナ・スッタ(相経、あるいは三十二相経)」に如来に転生する方法に関する記述があります。僕が重要視する記述は以下の記述です。
「修行僧のみなさん、このような偉人の三十二の大人相は、異教(外教)の仙人たちも具えています。しかしかれらは、これこれの行為をすることによって、これこれの相を獲得するということを知りません」
『原始仏典 第三巻 長部経典3』春秋社 P200
上の記述から「この教えは三十二相獲得法である」ということが明らかです。この記述に続いて、二十の行いが記述されます。これが戒であるとは書いていませんが、僕はこれを勝手に「大人二十戒」と名付けました。大人は「マハープリサ、偉大なる者」を意味します。適切でないと思われる方は「二十大人法」などでもよいと思います。三十二戒でないのは、一つの戒で複数の大人相を獲得することができる戒もあるからです。
この「ラッカナ・スッタ」は偉大なる者に転生する方法に関する教えです。三十二相を獲得した者は在家にいれば転輪王になり、出家すれば如来となります。「三十二相を獲得しなければ絶対に転輪王・如来にはなれない」という記述を僕は読んだことがありませんので、場合によっては三十二相がなくても可能なのかも知れません。しかし、「手堅く」転輪王・如来に転生したい方はこの大人二十戒を成就し、三十二相を獲得することをおすすめします。
また偉大なる者になりたくない人であっても、この戒律を守ると非常に容姿が美しくなるので、美を追求する人にもおすすめできます。
如来になる最低条件は不明ですが、少なくとも三十二相を獲得して出家すれば必然的に如来になるしかないというのが経典の記述です。そこで「とりあえず三十二相を獲得して出家すれば如来になれるだろう」と考えることができます。では、「どうすれば三十二相を獲得できるか」と思って経典を探すとこのラッカナ経に行き着き、そこに「こうすれば三十二相が獲得できる」と書いてあるのを読みます。その行いに二十あり、とりあえず「大人二十戒」と名付けておきます。その戒の中に四諦知はありません。転輪王になる可能性があるからです(もっとも今度出現するメッテーヤ・ブッダ[弥勒仏]の弟子になるはずの転輪王は転輪王でありながら出家して悟ることになりますが)。この大人二十戒を獲得し、さらに四諦知まで獲得すれば如来になる可能性はますます高まります。
たとえばゴータマ・シッダッタが一つ前のブッダであるカッサパ・ブッダのもとで出家したように。ゴータマがいつ「私は如来になる!」と発心したかはわかりませんが、間違いなく彼はこの大人二十戒を獲得するための意図的な努力を積んだ者です。今ここに大人二十戒は明らかにされています。宗派を問わずに、大人二十戒の一つでも成就することは善い行いですので、志のある方はぜひこの善戒を学ぶと大変大きな利益があると思います。以下がその大人二十戒の記述のある経典です。
・第30経 『三十二相経』 如来転生法 (原仏3 P191–239)
1 http://
2 http://
3 http://
・如来についての追記
1.「八十種好」は原始仏典の記述に存在しない
伝統的に如来の特徴を「三十二相八十種好」と言いますが、八十種好は原始仏典に記述がありません。律蔵と経蔵四部経典に書いてありません。三十二相は原始仏典に記述がありますが、八十種好の記述はまったく存在していません。
2.転輪王も仏像と同じ三十二相だが髪型と服装は異なる
公には言われませんが「三十二相=如来」という考えが広まっていますが、正しくは「三十二相=如来or転輪王」です。従って、「三十二相の転輪王」もイメージしてください。転輪王はもちろん「髪を剃っていないし、パンチパーマでもありません」。三十二相を成就する転輪王には髪がちゃんとある程度まで伸びており、袈裟をまとうことはなく、在家者であり、しかも三十二相を備えた立派な容姿の持ち主です。信じるならば。
そして、その三十二相を備えた立派な容姿の転輪王は教えを聞かない限りは「凡夫」なのです。三十二相を備えていてもなお凡夫であるということは可能です。そして、三十二相を備えていなくてもなお聖者であるということも可能です。四諦を事実の通りに少量でも知るならば、聖者の一員です。三十二相とは「世を摂事する美徳の完成形」です。「如来と同じ容姿でありながら、しかも悟っていないことはあり得る」ということです。
3.「正覚」と「転輪」は別物
ブッダになることと「輪を転じること」は別です。ブッダには如来と単独仏陀の二種類があるからです。後者のパッチェーカ・ブッダ(単独仏陀・独覚)は、「輪を転じません」。単独仏陀は、転輪を行ないません。しかし、転輪王はブッダではないのに輪を転じることができます。「聖なる輪を転じる務め」の定義が原始仏典に記述されていますが、それは簡単に言えば領土内のあらゆる生ける者たちに適切な保護と防御と安全、まとめれば利益増大を提供すること、これが「聖転輪法」であると父親の転輪王が息子に教えています。もっとも如来の転輪と転輪王の転輪ではレベルが違い過ぎますが。
また、ゴータマが無上正覚に達したときは「まだ転輪していない状態」です。無上正覚に達して、ブラフマー・サハンパティから勧請を受けて後に、五比丘に教えを初めて説いたとき、その時こそが「初転法輪」です。この例でわかるように「輪を転じる」とは、「他者のために法にかなうことを実行すること」、これを「転輪」と名付けていることがわかります。
転輪王の転輪は「外界の悪からの防御」です。暴力などです。如来の転輪は「内界の悪からの防御」です。十悪業道を生み出す三毒の根絶です。「サーリプッタは私が転じた輪をその通りに転じる」と称賛されていました。このことから、如来や転輪王のように三十二相がなくとも努力によって正法転輪の智慧弁舌の境地に達することが可能だと言うことがわかります。しかし、たとえ転輪ができるとしても「阿羅漢よりも単独仏陀の方が優れている」というのが原始仏典の記述です。力の有無と利他の有無は、別々の領域のことです。従って「正覚に達していながら、しかも転輪しないことはあり得る」ということです。
また三十二相の一つである「足下二輪相」、これは前世において「多くの人々に楽をもたらした。不安と戦慄と恐怖の除去者であり、法の者でもあり、守護と覆いと防護の整備者であり、眷属たちを持つ者でもあり、布施を与える者であった」という業によって獲得できます。このことからも、「輪(チャッカ)を転じる(ヴァッティ)」ことは、「実際に多くの人々の楽と利益になる行ない」であることがわかると思います。ただ口先だけ「世のため人のため」と言うだけでは多分駄目で、「実際に利益をもたらす行を積むこと」が大事だと思います。「聖なる輪を転じる務め」の記述そのものについてはまた引用したいと思います。
以上で如来の十号を僕の記憶の範囲で、何とか紹介しました。この内容を覚えておくと、三十七道の「信根」「信力」の実践に便利です。また「念仏」「仏信」の修行も同様です。いわゆる「これによってもやはり、かの世尊は阿羅漢・三摩三仏陀・明行足・善逝・世間解・無上士・調御丈夫・天人師・仏陀・先生である」という修行です。
如来十号 完
6.無上士 如来・阿羅漢・三摩三仏陀
無上士:アヌッタラ、anuttara、「無上の人」。ウッタラ(より上の、uttara)の否定形。より上がない。最高の。
原始仏典における定義で「アヌッタラ」そのものに相当する定義はないのですが、ほとんどそれの解説であるような記述を紹介します。最高者を意味する「アッガ(agga)」です。
「174.比丘たちよ、一人が世に生まれるのは二つなく、仲間なく、似るものなく、同等のものなく、対抗するものなく、比肩者なく、等しいものなく、等しく同じものがない二足中の最高者が生まれて来るのである。誰が一人か。
如来・阿羅漢・三摩三仏陀である。
比丘たちよ、この一人が世に生まれるのは二つなく、仲間なく、似るものなく、同等のものなく、対抗するものなく、比肩者なく、等しいものなく、等しく同じものがない二足中の最高者が生まれて来るのである」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P32 に相当
7.調御丈夫 有学を順序よく学ばせて行く者
調御丈夫:プリサ・ダンマ・サーラティ、purisa damma sārathi、「調御されるべき人の調御者」。プリサは「人」、ダンマは「調御されるべき」(ダンマティ、dammati「馴らされる」の未来受動・義務)、サーラティは「御者・調御者」。
原始仏典における定義で「プリサ・ダンマ・サーラティ」そのものに相当する定義はないのですが、それに近い記述を紹介します。
「 中部経典 第107経 算術家モッガーラナ経[ガナカ・モッガーラナ・スッタ]
・・・省略・・・
バラモン、この法・律においても順序のある学があり、順序のある行があり、順序のある行道を設定することができる。
バラモン、たとえば熟練した馬の調教者(ダンマカ、dammaka)は吉祥な良い生まれの馬を獲得して、最初にくつわをはめてから、さらにより上のことを為す。
バラモン、このように如来は調御されるべき人(プリサダンマ)を獲得して最初にこのように調伏する(ヴィネーティ、vineti、訓練指導する、制御する、律[vinaya]の関連語)。
「比丘よ、さああなたは戒を具足し、パーティモッカ律儀に律儀されて住し、行と行境を具足して、微細な罪にも恐怖を見て、学足を取って学びなさい」と。
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは根を防護し・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは食において量を知り・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは眠らないことと結合して住し・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは念・自覚を成就して・・・
・・・やがて如来はより上の調伏をし、「比丘よ、さああなたは遠離の座臥を受用し・・・(断五蓋・四禅の記述)・・・」
『南伝大蔵経11上 中部経典3』大蔵出版 P348−355 に相当
このように順序ある調伏・制御を続けて、「これらの教えは有学においては無上の安穏との結合に資するし、無学の阿羅漢においては現法楽住と念自覚に資する」と続きます。つまり、阿羅漢になっても修行は有益だということです。
さらにバラモンが質問します(会話内容は僕が省略して書いています)。
「卿ゴータマ、どうしてある者は涅槃を得て、ある者は涅槃を得ないのでしょうか」
「バラモン、あなたはラージャガハへの道を知るか」
「卿ゴータマ、知っています」
「バラモン、ラージャガハに行きたい人があなたに道を聞き、あなたは道を教えるが彼はあなたが教えたのと違う方向へ行く。
もう一人が同じようにあなたに道を聞くが、彼はあなたが教えた通りの方向へ行き無事にラージャガハに着く。
バラモン、ラージャガハは確かに存在するし、ラージャガハへの道も確かに存在するし、あなたは確かに正しく導く者である。
バラモン、それなのに何が原因で一人はラージャガハに着かず、別の一人は無事にラージャガハに着くのか」
「卿ゴータマ、私に何ができるでしょうか。卿ゴータマ、私は道を教えるだけなのです」
「バラモン、まさにそのように涅槃は確かに存在し、涅槃に行く道も確かに存在し、私は確かに正しく導くものである。
そして私の弟子たちはこのように教誡されるが、ある者は涅槃を得ず、ある者は涅槃を得る。
バラモン、これを私はどうするのか。バラモン、私は道を教えるのみなのだ」
中部経典第65経「バッダーリ・スッタ」の後半も馬の調教にたとえて、比丘が完全に調教されると無学の十法(無学の正見正思・・・正定正智正解脱)を成就するという記述があります。無学になれば調教する必要はありません。また凡夫は「学ぶべきでもなく、学ぶ必要がないのでもない者」なので調御丈夫の調教対象ではありません。調御丈夫というのは凡夫を調教する人ではなく「有学を調教する人」です。
中部経典第125経「ダンタブーミ・スッタ(調御地経)」も比丘を象や牛の調教にたとえて、繰り返し「その彼を如来はさらに調御する」という記述が出て来ます(南伝11下P154−168)。その中で「漏が尽きていない比丘→調御されていない」、「漏が尽きた比丘→調御されている」と表現されていますので、「調教=漏尽のため」ということがわかります。漏尽に達すれば、とりあえず調教は終わりです。
8.天人師 神々と人々の師
天人師:サッター・デーヴァマヌッサーナム、satthar devamanussānaṃ、「神々と人々の師」。サッターは「師、大師、教師、教主」、デーヴァマヌッサで「神と人」。
原始仏典における定義で「天人師」そのものの記述はありません。ただ多くの神々が帰依し、多くの人々が帰依しているという記述は随所にあります。
9.仏陀 独力で覚った者
仏陀:ブッダ、buddha、「覚った人」。
原始仏典における定義は以下の通りです。
「比丘たちよ、これら二人はブッダである。誰が二人か。
如来・阿羅漢・三摩三仏陀と、単独仏陀(独覚)である。
比丘たちよ、これら二人はブッダである」
『南伝大蔵経17 増支部経典1』大蔵出版 P119 に相当
単独仏陀の原語は「パッチェーカ・ブッダ(pacceka buddha)」。パッチェーカは「単独、独一」という意味。僕は「ブッダ」という原語を際立たせたいので「単独仏陀」と訳しています。「単独梵天」(pacceka brahmā)という言葉もあります。上の記述から「ブッダ」という言葉は、「独力で覚った人」という意味合いが強いと思います。そうすると「三摩三仏陀」は「独力で覚り且つ他者を導く者」という意味になります。
聖者 >阿羅漢>ブッダ >サンマー・サンブッダ(男性のみ) 調御丈夫
>パッチェーカ・ブッダ(性別の記述なし)調御しない者
>如来弟子>比丘 調御された人
>比丘尼 調御された人
>有学 >如来弟子>比丘 調御されるべき人
>比丘尼 調御されるべき人
>優婆塞 調御されるべき人
>優婆夷 調御されるべき人
(非人も含めるべきかも知れません)
凡夫 >正見者→輪廻に導く正見がある外の者、いわゆる「外道」。
梵身天などへの転生者あり。たとえばイエスなど。
菩薩になる前のゴータマも外道だった。
>邪見者→地獄・畜生に行くしかない邪見者、あえて名付けるなら「邪道」。
凡夫を二種類に分ける分類は原始仏典にはなく、僕が原始仏典の記述から凡夫を善人と勝手に分けました。原始仏典では「凡夫」と一括りです。
10.先生 バガヴァント
先生:バガヴァント、bhagavant、薄伽梵とも音写。バガ(bhaga)が「幸運、福運」でヴァントで「人」。バッダ(bhadda)が「賢い、吉祥の」。吉祥なる人。
従来は「世尊」と訳され、呼びかける語形では「大徳」(バンテー bhante)と訳されていました。「大徳」と呼ばれるのはブッダだけではなく、新参比丘が長老比丘を呼びかけるときも「大徳(先生)」と呼ばれます。原始仏典における定義で「バガヴァント」そのものの記述はなかったように思います。また見つけたらアップしようと思います。
・訳語 『世尊・大徳』→『先生』に変更
http://
00.如来 その通りに覚り、語り、行い、実現する者
如来:タターガタ、tathāgata、「その通りに行く者」。タターは「かく、その如くに」。ガタは「行った」。
原始仏典における定義は以下の通りです。
「 第三 世
23.比丘たちよ、如来は世間を覚り、如来は世間から離結する。
比丘たちよ、如来は世間の集を覚り、如来は世間の集を断つ。
比丘たちよ、如来は世間の滅を覚り、如来は世間の滅を実証する。
比丘たちよ、如来は世間の滅に行く道を覚り、如来は世間の滅に行く道を修習する。
比丘たちよ、神々とマーラとブラフマーと沙門婆羅門とともである世間に生まれた者たちと神々と人々が見たもの、聞いたもの、思ったこと、認識したこと、得たもの、求めたもの、意によって随伺したもの、その一切を如来は覚る。それゆえに「如来」と言われる。
比丘たちよ、如来が無上の正しい覚りを覚った夜から、無余依の涅槃界に涅槃する夜までのこの間に説き、話し、解説する一切はまさにその通りのことであって、他のことではない。それゆえに「如来」と言われる。
比丘たちよ、如来は言う通りにその通りに行い、行う通りにその通りに言う。この言う通りにその通りに行い、行う通りにその通りに言うこと。それゆえに「如来」と言われる。
比丘たちよ、神々とマーラとブラフマーと沙門婆羅門とともである世間に生まれた者たちと神々と人々に如来は勝利し、勝利されず、全てを見て、自在である。それゆえに「如来」と言われる。
一切の世間を超知し 一切の世間においてその通りである
一切の世間を離結し 一切の世間を取ることがない
彼は一切に勝利する勇者であり 一切の縛から解放されている
・・・(偈は続きます)」
『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P42 に相当
「比丘たちよ、『沙門』[サマナ samaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『婆羅門』[ブラーフマナ brāhmaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『明知者』[ヴェーダグー vedagū]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『医者』[ビサッカ bhisakka]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『無垢者』[ニンマラ nimmala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『離垢者』[ヴィマラ vimala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『知者』[ニャーニン ñāṇin]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『解脱者』[ヴィムッタ vimutta]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
沙門として得るべきもの、婆羅門が完成すべきもの
明知者として得るべきもの、医者として無上の者
無垢者として得るべきもの、離垢者が清浄とすべきもの
そして知者として得るべきもの、解脱者として無上の者
その私は戦に勝利し、私は束縛から脱して解脱した
私は最上に調御された象であり、般涅槃した無学である」
『南伝大蔵経21 増支部経典5』大蔵出版 P305−306 に相当
事実・現実・真実の通りにそれを覚ることが一つ目。
説法内容が完全に真実の通りであることが二つ目。
言行一致であることが三つ目。
自在者であるゆえにその通りに実現できるということで四つ目。
これが如来と言われるゆえんであるということです。
後半の引用は如来・阿羅漢・三摩三仏陀の八つの別名で増支部経典八集にあります。
・如来転生法 大人二十戒 → 三十二相+出家 → 成仏
長部経典第30経「ラッカナ・スッタ(相経、あるいは三十二相経)」に如来に転生する方法に関する記述があります。僕が重要視する記述は以下の記述です。
「修行僧のみなさん、このような偉人の三十二の大人相は、異教(外教)の仙人たちも具えています。しかしかれらは、これこれの行為をすることによって、これこれの相を獲得するということを知りません」
『原始仏典 第三巻 長部経典3』春秋社 P200
上の記述から「この教えは三十二相獲得法である」ということが明らかです。この記述に続いて、二十の行いが記述されます。これが戒であるとは書いていませんが、僕はこれを勝手に「大人二十戒」と名付けました。大人は「マハープリサ、偉大なる者」を意味します。適切でないと思われる方は「二十大人法」などでもよいと思います。三十二戒でないのは、一つの戒で複数の大人相を獲得することができる戒もあるからです。
この「ラッカナ・スッタ」は偉大なる者に転生する方法に関する教えです。三十二相を獲得した者は在家にいれば転輪王になり、出家すれば如来となります。「三十二相を獲得しなければ絶対に転輪王・如来にはなれない」という記述を僕は読んだことがありませんので、場合によっては三十二相がなくても可能なのかも知れません。しかし、「手堅く」転輪王・如来に転生したい方はこの大人二十戒を成就し、三十二相を獲得することをおすすめします。
また偉大なる者になりたくない人であっても、この戒律を守ると非常に容姿が美しくなるので、美を追求する人にもおすすめできます。
如来になる最低条件は不明ですが、少なくとも三十二相を獲得して出家すれば必然的に如来になるしかないというのが経典の記述です。そこで「とりあえず三十二相を獲得して出家すれば如来になれるだろう」と考えることができます。では、「どうすれば三十二相を獲得できるか」と思って経典を探すとこのラッカナ経に行き着き、そこに「こうすれば三十二相が獲得できる」と書いてあるのを読みます。その行いに二十あり、とりあえず「大人二十戒」と名付けておきます。その戒の中に四諦知はありません。転輪王になる可能性があるからです(もっとも今度出現するメッテーヤ・ブッダ[弥勒仏]の弟子になるはずの転輪王は転輪王でありながら出家して悟ることになりますが)。この大人二十戒を獲得し、さらに四諦知まで獲得すれば如来になる可能性はますます高まります。
たとえばゴータマ・シッダッタが一つ前のブッダであるカッサパ・ブッダのもとで出家したように。ゴータマがいつ「私は如来になる!」と発心したかはわかりませんが、間違いなく彼はこの大人二十戒を獲得するための意図的な努力を積んだ者です。今ここに大人二十戒は明らかにされています。宗派を問わずに、大人二十戒の一つでも成就することは善い行いですので、志のある方はぜひこの善戒を学ぶと大変大きな利益があると思います。以下がその大人二十戒の記述のある経典です。
・第30経 『三十二相経』 如来転生法 (原仏3 P191–239)
1 http://
2 http://
3 http://
・如来についての追記
1.「八十種好」は原始仏典の記述に存在しない
伝統的に如来の特徴を「三十二相八十種好」と言いますが、八十種好は原始仏典に記述がありません。律蔵と経蔵四部経典に書いてありません。三十二相は原始仏典に記述がありますが、八十種好の記述はまったく存在していません。
2.転輪王も仏像と同じ三十二相だが髪型と服装は異なる
公には言われませんが「三十二相=如来」という考えが広まっていますが、正しくは「三十二相=如来or転輪王」です。従って、「三十二相の転輪王」もイメージしてください。転輪王はもちろん「髪を剃っていないし、パンチパーマでもありません」。三十二相を成就する転輪王には髪がちゃんとある程度まで伸びており、袈裟をまとうことはなく、在家者であり、しかも三十二相を備えた立派な容姿の持ち主です。信じるならば。
そして、その三十二相を備えた立派な容姿の転輪王は教えを聞かない限りは「凡夫」なのです。三十二相を備えていてもなお凡夫であるということは可能です。そして、三十二相を備えていなくてもなお聖者であるということも可能です。四諦を事実の通りに少量でも知るならば、聖者の一員です。三十二相とは「世を摂事する美徳の完成形」です。「如来と同じ容姿でありながら、しかも悟っていないことはあり得る」ということです。
3.「正覚」と「転輪」は別物
ブッダになることと「輪を転じること」は別です。ブッダには如来と単独仏陀の二種類があるからです。後者のパッチェーカ・ブッダ(単独仏陀・独覚)は、「輪を転じません」。単独仏陀は、転輪を行ないません。しかし、転輪王はブッダではないのに輪を転じることができます。「聖なる輪を転じる務め」の定義が原始仏典に記述されていますが、それは簡単に言えば領土内のあらゆる生ける者たちに適切な保護と防御と安全、まとめれば利益増大を提供すること、これが「聖転輪法」であると父親の転輪王が息子に教えています。もっとも如来の転輪と転輪王の転輪ではレベルが違い過ぎますが。
また、ゴータマが無上正覚に達したときは「まだ転輪していない状態」です。無上正覚に達して、ブラフマー・サハンパティから勧請を受けて後に、五比丘に教えを初めて説いたとき、その時こそが「初転法輪」です。この例でわかるように「輪を転じる」とは、「他者のために法にかなうことを実行すること」、これを「転輪」と名付けていることがわかります。
転輪王の転輪は「外界の悪からの防御」です。暴力などです。如来の転輪は「内界の悪からの防御」です。十悪業道を生み出す三毒の根絶です。「サーリプッタは私が転じた輪をその通りに転じる」と称賛されていました。このことから、如来や転輪王のように三十二相がなくとも努力によって正法転輪の智慧弁舌の境地に達することが可能だと言うことがわかります。しかし、たとえ転輪ができるとしても「阿羅漢よりも単独仏陀の方が優れている」というのが原始仏典の記述です。力の有無と利他の有無は、別々の領域のことです。従って「正覚に達していながら、しかも転輪しないことはあり得る」ということです。
また三十二相の一つである「足下二輪相」、これは前世において「多くの人々に楽をもたらした。不安と戦慄と恐怖の除去者であり、法の者でもあり、守護と覆いと防護の整備者であり、眷属たちを持つ者でもあり、布施を与える者であった」という業によって獲得できます。このことからも、「輪(チャッカ)を転じる(ヴァッティ)」ことは、「実際に多くの人々の楽と利益になる行ない」であることがわかると思います。ただ口先だけ「世のため人のため」と言うだけでは多分駄目で、「実際に利益をもたらす行を積むこと」が大事だと思います。「聖なる輪を転じる務め」の記述そのものについてはまた引用したいと思います。
以上で如来の十号を僕の記憶の範囲で、何とか紹介しました。この内容を覚えておくと、三十七道の「信根」「信力」の実践に便利です。また「念仏」「仏信」の修行も同様です。いわゆる「これによってもやはり、かの世尊は阿羅漢・三摩三仏陀・明行足・善逝・世間解・無上士・調御丈夫・天人師・仏陀・先生である」という修行です。
如来十号 完
|
|
|
|
コメント(4)
如来の別名が増支部経典の八集にありましたので、以下の文章を如来の項目に追加しました。
「比丘たちよ、『沙門』[サマナ samaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『婆羅門』[ブラーフマナ brāhmaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『明知者』[ヴェーダグー vedagū]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『医者』[ビサッカ bhisakka]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『無垢者』[ニンマラ nimmala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『離垢者』[ヴィマラ vimala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『知者』[ニャーニン ñāṇin]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『解脱者』[ヴィムッタ vimutta]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
沙門として得るべきもの、婆羅門が完成すべきもの
明知者として得るべきもの、医者として無上の者
無垢者として得るべきもの、離垢者が清浄とすべきもの
そして知者として得るべきもの、解脱者として無上の者
その私は戦に勝利し、私は束縛から脱して解脱した
私は最上に調御された象であり、般涅槃した無学である」
(『南伝大蔵経21 増支部経典5』大蔵出版 P305−306)
「比丘たちよ、『沙門』[サマナ samaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『婆羅門』[ブラーフマナ brāhmaṇa]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『明知者』[ヴェーダグー vedagū]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『医者』[ビサッカ bhisakka]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『無垢者』[ニンマラ nimmala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『離垢者』[ヴィマラ vimala]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『知者』[ニャーニン ñāṇin]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
比丘たちよ、『解脱者』[ヴィムッタ vimutta]とは如来・阿羅漢・三摩三仏陀の別名である。
沙門として得るべきもの、婆羅門が完成すべきもの
明知者として得るべきもの、医者として無上の者
無垢者として得るべきもの、離垢者が清浄とすべきもの
そして知者として得るべきもの、解脱者として無上の者
その私は戦に勝利し、私は束縛から脱して解脱した
私は最上に調御された象であり、般涅槃した無学である」
(『南伝大蔵経21 増支部経典5』大蔵出版 P305−306)
以下の記述を編集して追加しました。
・如来についての追記
1.「八十種好」は原始仏典の記述に存在しない
伝統的に如来の特徴を「三十二相八十種好」と言いますが、八十種好は原始仏典に記述がありません。律蔵と経蔵四部経典に書いてありません。三十二相は原始仏典に記述がありますが、八十種好の記述はまったく存在していません。
2.転輪王も仏像と同じ三十二相だが髪型と服装は異なる
「三十二相=如来」という考えがちですが、正しくは「三十二相=如来or転輪王」です。従って、「三十二相の転輪王」もイメージしてください。転輪王はもちろん「髪を剃っていないし、パンチパーマでもありません」。三十二相を成就する転輪王には髪がちゃんとある程度まで伸びており、袈裟をまとうことはなく、在家者であり、しかも三十二相を備えた立派な容姿の持ち主です。信じるならば。そして、その三十二相を備えた立派な容姿の転輪王は教えを聞かない限りは「凡夫」なのです。三十二相を備えていてもなお凡夫であるということは可能です。そして、三十二相を備えていなくてもなお聖者であるということも可能です。四諦を事実の通りに少量でも知るならば、聖者の一員です。三十二相とは「世を摂事する美徳の完成形」です。「如来と同じ容姿でありながら、しかも悟っていないことはあり得る」ということです。
3.「正覚」と「転輪」は別物
ブッダになることと「輪を転じること」は別です。ブッダには如来と単独仏陀の二種類があるからです。後者のパッチェーカ・ブッダ(単独仏陀・独覚)は、「輪を転じません」。単独仏陀は、転輪を行ないません。しかし、転輪王はブッダではないのに輪を転じることができます。「聖なる輪を転じる務め」の定義が原始仏典に記述されていますが、それは簡単に言えば領土内のあらゆる生ける者たちに適切な保護と防御と安全、まとめれば利益増大を提供すること、これが「聖転輪法」であると父親の転輪王が息子に教えています。
また、ゴータマが無上正覚に達したときは「まだ転輪していない状態」です。無上正覚に達して、ブラフマー・サハンパティから勧請を受けて後に、五比丘に教えを初めて説いたとき、その時こそが「初転法輪」です。この例でわかるように「輪を転じる」とは、「他者のために法にかなうことを実行すること」、これを「転輪」と名付けていることがわかります。転輪王の転輪は「外界の悪からの防御」です。暴力などです。如来の転輪は「内界の悪からの防御」です。十悪業道を生み出す三毒の根絶です。「サーリプッタは私が転じた輪をその通りに転じる」と称賛されていました。このことから、如来や転輪王のように三十二相がなくとも努力によって正法転輪の智慧弁舌の境地に達することが可能だと言うことがわかります。しかし、たとえ転輪ができるとしても「阿羅漢よりも単独仏陀の方が優れている」というのが原始仏典の記述です。力の有無と利他の有無は、別々の領域のことです。従って「正覚に達していながら、しかも転輪しないことはあり得る」ということです。
また三十二相の一つである「足下二輪相」、これは前世において「多くの人々に楽をもたらした。不安と戦慄と恐怖の除去者であり、法の者でもあり、守護と覆いと防護の整備者であり、眷属たちを持つ者でもあり、布施を与える者であった」という業によって獲得できます。このことからも、「輪(チャッカ)を転じる(ヴァッティ)」ことは、「実際に多くの人々の楽と利益になる行ない」であることがわかると思います。ただ口先だけ「世のため人のため」と言うだけでは多分駄目で、「実際に利益をもたらす行を積むこと」が大事だと思います。「聖なる輪を転じる務め」の記述そのものについてはまた引用したいと思います。
以上です。
・如来についての追記
1.「八十種好」は原始仏典の記述に存在しない
伝統的に如来の特徴を「三十二相八十種好」と言いますが、八十種好は原始仏典に記述がありません。律蔵と経蔵四部経典に書いてありません。三十二相は原始仏典に記述がありますが、八十種好の記述はまったく存在していません。
2.転輪王も仏像と同じ三十二相だが髪型と服装は異なる
「三十二相=如来」という考えがちですが、正しくは「三十二相=如来or転輪王」です。従って、「三十二相の転輪王」もイメージしてください。転輪王はもちろん「髪を剃っていないし、パンチパーマでもありません」。三十二相を成就する転輪王には髪がちゃんとある程度まで伸びており、袈裟をまとうことはなく、在家者であり、しかも三十二相を備えた立派な容姿の持ち主です。信じるならば。そして、その三十二相を備えた立派な容姿の転輪王は教えを聞かない限りは「凡夫」なのです。三十二相を備えていてもなお凡夫であるということは可能です。そして、三十二相を備えていなくてもなお聖者であるということも可能です。四諦を事実の通りに少量でも知るならば、聖者の一員です。三十二相とは「世を摂事する美徳の完成形」です。「如来と同じ容姿でありながら、しかも悟っていないことはあり得る」ということです。
3.「正覚」と「転輪」は別物
ブッダになることと「輪を転じること」は別です。ブッダには如来と単独仏陀の二種類があるからです。後者のパッチェーカ・ブッダ(単独仏陀・独覚)は、「輪を転じません」。単独仏陀は、転輪を行ないません。しかし、転輪王はブッダではないのに輪を転じることができます。「聖なる輪を転じる務め」の定義が原始仏典に記述されていますが、それは簡単に言えば領土内のあらゆる生ける者たちに適切な保護と防御と安全、まとめれば利益増大を提供すること、これが「聖転輪法」であると父親の転輪王が息子に教えています。
また、ゴータマが無上正覚に達したときは「まだ転輪していない状態」です。無上正覚に達して、ブラフマー・サハンパティから勧請を受けて後に、五比丘に教えを初めて説いたとき、その時こそが「初転法輪」です。この例でわかるように「輪を転じる」とは、「他者のために法にかなうことを実行すること」、これを「転輪」と名付けていることがわかります。転輪王の転輪は「外界の悪からの防御」です。暴力などです。如来の転輪は「内界の悪からの防御」です。十悪業道を生み出す三毒の根絶です。「サーリプッタは私が転じた輪をその通りに転じる」と称賛されていました。このことから、如来や転輪王のように三十二相がなくとも努力によって正法転輪の智慧弁舌の境地に達することが可能だと言うことがわかります。しかし、たとえ転輪ができるとしても「阿羅漢よりも単独仏陀の方が優れている」というのが原始仏典の記述です。力の有無と利他の有無は、別々の領域のことです。従って「正覚に達していながら、しかも転輪しないことはあり得る」ということです。
また三十二相の一つである「足下二輪相」、これは前世において「多くの人々に楽をもたらした。不安と戦慄と恐怖の除去者であり、法の者でもあり、守護と覆いと防護の整備者であり、眷属たちを持つ者でもあり、布施を与える者であった」という業によって獲得できます。このことからも、「輪(チャッカ)を転じる(ヴァッティ)」ことは、「実際に多くの人々の楽と利益になる行ない」であることがわかると思います。ただ口先だけ「世のため人のため」と言うだけでは多分駄目で、「実際に利益をもたらす行を積むこと」が大事だと思います。「聖なる輪を転じる務め」の記述そのものについてはまた引用したいと思います。
以上です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
原始仏教 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏教のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37863人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人