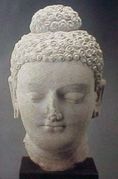『中部経典 第41経 薩羅村婆羅門経[サーレッヤカ・スッタ]』から引用しました。
・十悪業道
01.ここにある者は生き物を殺す。
凶暴であり、血のある生き物を殺戮することを続け、生き物に憐れみを起こすことがない者である。
02.また与えられていないのに取る。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを村に行き、林に行き、それを与えられていないのに取り、盗みと言われることをする。
03.また欲において邪行をする。
母に守られ、父に守られ、母父に守られ、兄弟に守られ、姉妹に守られ、親族に守られ、一族に守られ、法に守られ、夫のある者、刑罰のある者、ないし華鬘・アクセサリーで飾られた者など、そのような者と会って行じる。
04.ここにある者は妄語をする。
集会に行き、あるいは集団に行き、あるいは親族の中に行き、あるいは組合の中に行き、証人として引き出され、「さあ、あなたはあなたが知っていることを語りなさい」と尋問され、彼はあるいは知らないのに「私は知っています」と言い、あるいは知っているのに「私は知りません」と言い、あるいは見ていないのに「私は見ました」と言い、あるいは見たのに「私は見ていません」と言う。このようにあるいは自己を原因として、あるいは他者を原因として、あるいは何らかの財産を原因として、自覚しながら偽りを語る。
05.また割れる語をする。
こちらから聞いてあちらに告げてこちらと分裂させ、あちらから聞いてこちらに告げてあちらと分裂させる。このようにあるいは和合を分裂させ、あるいは分裂を助長し、不和合を愛好し、不和合を楽しみ、不和合を喜び、不和合を作す言葉を語る。
06.また不快語をする。
睾丸(下品)であり、粗暴であり、他者を刺激し、他者を煩わせ、忿と隣り合わせであり、三摩地に転じない、そのような言葉を語る。
07.また雑な駄弁をする(混ざったもみがら)。
時でないのに語り、事実でないのに語り、利益のないことを語り、非法を語り、非律を語る。時でなく、筋が通らず、際限なく語り、利益を伴わず、覚える価値のない言葉を語る。
08.ここにある者は貪求する。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを「ああ、実に他者のものが私のものになるように」と貪求する。
09.また怒りのある心であり、意思が汚れている。
「この生ける者は害され、あるいは殺され、あるいは切断され、あるいは消え、あるいは無くなり、あるいは存在しないように」と。
10.また邪見であり、転倒して見る。
「布施は存在せず、供儀は存在せず、献供は存在しない。善作悪作の業の果が熟すること(異熟、結熟、結果)は存在しない。この世は存在せず、他の世は存在しない。母は存在せず、父は存在しない。化生の生ける者は存在しない。世間において正しく行き、正しく行道し、この世と他の世を自ら超知し、実証し、説く沙門婆羅門は存在しない」と。
・十善業道
01.ここにある者は生き物を殺すことを断ち、生き物を殺すことから離れている。
杖を置き、刀を置き、恥を知り、憐れみを起こし、一切の生き物の益を哀愍して住する。
02.また与えられていないのに取ることを断ち、与えられていないのに取ることから離れている。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを村に行き、林に行き、それを与えられていないのに取り、盗みと言われることをしない。
03.また欲における邪行を断ち、欲における邪行から離れている。
母に守られ、父に守られ、母父に守られ、兄弟に守られ、姉妹に守られ、親族に守られ、一族に守られ、法に守られ、夫のある者、刑罰のある者、ないし華鬘・アクセサリーで飾られた者など、そのような者と会って行じない。
04.ここにある者は妄語を断ち、妄語から離れている。
集会に行き、あるいは集団に行き、あるいは親族の中に行き、あるいは組合の中に行き、証人として引き出され、「さあ、あなたはあなたが知っていることを語りなさい」と尋問され、彼はあるいは知らないのに「私は知っています」と言い、あるいは知っているのに「私は知りません」と言い、あるいは見ていないのに「私は見ました」と言い、あるいは見たのに「私は見ていません」と言う。このようにあるいは自己を原因として、あるいは他者を原因として、あるいは何らかの財産を原因として、自覚しながら偽りを語ることがない。
05.また割れる語を断ち、割れる語から離れている。
こちらから聞いてあちらに告げてこちらと分裂させることがなく、あちらから聞いてこちらに告げてあちらと分裂させることがない。このようにあるいは分裂を和合させ、あるいは和合を助長し、和合を愛好し、和合を楽しみ、和合を喜び、和合を作す言葉を語る。
06.また不快語を断ち、不快語から離れている。
聾でなく、耳に楽であり、愛すべきであり、心に入り、上品であり、多くの人が好み、多くの人の意にかなう、そのような言葉を語る。
07.また雑な駄弁を断ち、雑な駄弁から離れている。
時にかなって語り、事実を語り、利益のあることを語り、法を語り、律を語る。時にかない、筋が通り、際限があって語り、利益を伴い、覚える価値のある言葉を語る。
08.ここにある者は貪求しない。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを「ああ、実に他者のものが私のものになるように」と貪求しない。
09.また怒りのない心であり、意思が汚れていない。
「この生ける者は怨みなく、悩害なく、動転することなく、楽であり、自分を大事にするように」と。
10.また正見であり、転倒せずに見る。
「布施は存在し、供儀は存在し、献供は存在する。善作悪作の業の果が熟することは存在する。この世は存在し、他の世は存在する。母は存在し、父は存在する。化生の生ける者は存在する。世間において正しく行き、正しく行道し、この世と他の世を自ら超知し、実証し、説く沙門婆羅門は存在する」と。
『南伝大蔵経10 中部経典2』大蔵出版 P3−7
この経典の内容はサーラー村のバラモンたちとゴータマの問答です。簡単に書くと以下の通りです。会話の内容は僕が省略して書いています。
バラモン:「何が原因で地獄に行き、何が原因で天界に行くのか」。
ゴータマ:「悪業を原因として地獄に行き、善業を原因として天界に行く」。
バラモン:「省略されていてわかりませんので、解説してください」
ゴータマ:
「十悪業である三の身悪行・四の語悪行・三の意悪行。これが原因で地獄に行く。
十善業である三の身善行・四の語善行・三の意善行。これが原因で天界に行く。
十善を作す者が金持ちの貴族に転生したいと願えば、転生できる。法行者・正行者だから。
十善を作す者が金持ちの婆羅門に転生したいと願えば、転生できる。法行者・正行者だから。
・・・金持ちの居士に転生したいと願えば、転生できる。
・・・四大王天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・三十三天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・ヤーマ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・トゥシタ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・ニンマーナラティ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・パラニンミタ・ヴァサヴァッティ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・ブラフマカーイカ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・少光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・無量光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・極光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・少浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・無量浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・遍浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・アヴィハ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・アタッパ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・スダッサ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・スダッシン天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・アカニッタ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・空無辺処天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・識無辺処天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・無所有処天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・非想非非想処天に転生したいと願えば、転生できる。
十善を作す者が倶分解脱したいと願えば、倶分解脱できる。法行者・正行者だから。
バラモン:「ゴータマ、素晴らしい。今日から私たちはあなたに帰依し、法に帰依し、サンガに帰依します」 (終)
以前書いた「善き来世への転生」のトピックは、信戒聞捨慧の五財から転生する話でしたが、これは十善業道から転生する話です。転生先の詳細さにも若干の違いがあります。
十悪を断ち、十善を作せばそれで地獄に行かずに天国に行けるなら、「よし、とりあえずこれをやろう」と思えてきます。そこでこれを実践するときに少し気をつけたいのは以下のことです。つまり、「不快な言葉をやめれば、即、上品で優雅で人が喜ぶ言葉が語れるわけではない」ということです。不快な言葉をやめることは不快な言葉をやめることとして一つの努力が必要です。それとは別で、上品な言葉遣いになったり、相手が喜ぶ言葉を探す能力というのは、これもまた別の努力によって獲得する必要があります。それで、この修行を実践したい人は「十のことをやればいいのだ」と考えるよりも、「まず十悪を断って、それから十善を修めるという二十のことをやろう」と考えるとより一層円満だと思います。人は誰しも「誰かには不快なことを言って、誰かには相手が喜ぶことを言っているものだから」です。意の三悪行である貪求と瞋りは「他者を害さなければとりあえずよし」でいいと思います。「まず他者を害する貪りを断って、その次に自己を害する貪りを断つ」というのがやりやすいと思います。怒りは他者を害するものですから、怒りは断ちます。その次に「他者は害さないが、自己を害する動かしがたい不快感を断つ」という流れがやりやすいと思います。
「俺は十善をやってるから、酒を飲んでもいいんだ」と言う人もいるかと思いますが、その場合はとりあえず今はお酒を飲んでもいいと思います。戒律を守るのはその人の自由なので、段々にゆっくり上を目指していけばいいので。もちろん、お酒を飲むよりもお酒を飲まない方が悪を作す機会は激減すると思いますし、もしお酒をやめる方がいればその人はブッダの言葉と律を尊重していて立派です。
この経典の最後に「法行者が解脱したいと願えば、解脱できる」と書いてあります。ゴータマの意図はもちろん「お前たちは修行を完成させなさい」というのが本音だとは思います。ただ解脱するしないも個人の自由ですし、苦しみの不利益性をよく観じないかぎりは「苦滅がどうしてそんなに推奨されるのかよくわからない」のは当然なので、最上の境地を求める義務は誰にもありません。ただ十善業道はそれだけ善いものだということです。最後の正見を輪廻に導く正見から四諦を観じる聖なる正見に持って行けば、確かに解脱ができるという道理です。十悪がないので他者を害することがなく、他者を害さないので後悔せず、後悔しないので心が乱されることがなく、心が乱されることがないので心が集中し、心が集中するので四諦を知る努力ができ、四諦を知る努力を十分為したときは四諦を完全に知り尽くし、四諦を完全に知り尽くしたときは心が自然に苦因を断ち苦滅道を修さないわけにはいかなくなって、ついに完成に到るということです。十善さえあれば、どこにでも転生できるというのは善い教えだと思います。
これは意行(正思・正見)が入っているので、戒(正語・正業・正命)とは少し違うのですが、でも僕はこれを「戒」としてまとめて考えて修行しています。その方が覚え易いので。また五財(信戒聞捨慧)の戒をこの十善とみなすと、より包括的に修行ができていいです。
この「断十悪」と「修十善」ができたら、さらに新しい戒を学ぶのも楽しいことだと思います。例えば「殴らない」などです。暴力を振るわなければ、来世は健康な身体が手に入るぞというのは楽しいことです。また例えば「慈眼」です。「メデューサの邪眼」が有名ですがその逆で「幸せになれ」という慈心を伴ってまっすぐに相手を見るという戒です。これをマスターすると美しいまつげと美しい瞳が手に入るということです。どんどん戒を学んで行く「増上戒学」というのは三学の最初ですが、それを尊重するのは善いことです。戒律を守るモチベーションを高めるためにしばしばその利益を考えます。「十悪がある人間は人に認められないし、愛されない。十悪がある人間と付き合いたくない。しかし、十善がある人間は人に認められるし、愛されるに違いない。十善がある人間の方が高く評価されるし、多くの人に愛される。そうだ、もっと人に愛される人間になってみてはどうか。きっといいだろう」と考えてください。
具体的にどのように実践するのかというと、僕のおすすめはやはり朝起きたときと夜寝るときです。そのときに、
「殺さず哀れむ。
盗まず清浄。
不倫をしない、心でも。
嘘つかずに信用される。
仲間割れさせず、仲良くさせる。
不快なことを言わず、優しく上品に。
無駄話せずに、利益ある言葉。
人のものを欲しがらずに、少欲。
人の不幸を願わなず、慈心。
邪に見ずに、まっすぐに見る」
これを一日一回でも続けて、一ヶ月とか二ヶ月経つと案外、身に付いて来ます。身に付いてくると安心感が出て来て、「戒律っていいなぁ」と思うようになると思います。身に付いていないと戒律に対して苦手意識があるものですが、身に付けば好きになります。原始仏典の記述を信じる人はぜひやってみてください。少なくとも確実に十善がある人になれば、今よりも愛されるようになりますから。
・十悪業道
01.Idha, gahapatayo, ekacco pāṇātipātī hoti, luddo [luddo dāruṇo (ka.) ṭīkā oloketabbā] lohitapāṇi hatappahate niviṭṭho adayāpanno pāṇabhūtesu [sabbapāṇabhūtesu (syā. kaṃ. ka.)].
02.‘‘Adinnādāyī kho pana hoti. Yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ, gāmagataṃ vā araññagataṃ vā, taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti.
03.‘‘Kāmesumicchācārī kho pana hoti. Yā tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā bhāturakkhitā bhaginirakkhitā ñātirakkhitā gottarakkhitā dhammarakkhitā sassāmikā saparidaṇḍā antamaso mālāguḷaparikkhittāpi, tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti.
04.Idha, gahapatayo, ekacco musāvādī hoti. Sabhāgato vā parisāgato vā, ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā, abhinīto sakkhipuṭṭho – ‘ehambho purisa, yaṃ jānāsi taṃ vadehī’ti , so ajānaṃ vā āha – ‘jānāmī’ti, jānaṃ vā āha – ‘na jānāmī’ti, apassaṃ vā āha – ‘passāmī’ti, passaṃ vā āha – ‘na passāmī’ti [so āha ajānaṃ vā ahaṃ jānāmīti jānaṃ vā ahaṃ na jānāmīti apassaṃ vā ahaṃ passāmīti passaṃ vā ahaṃ na passāmīti (ka.)]. Iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā sampajānamusā bhāsitā hoti.
05.‘‘Pisuṇavāco kho pana hoti. Ito sutvā amutra akkhātā imesaṃ bhedāya, amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya. Iti samaggānaṃ vā bhettā [bhedakā (ka.), bhedetā (syā. kaṃ.), tadaṭṭhakathāyaṃ pana bhettāti dissati], bhinnānaṃ vā anuppadātā, vaggārāmo vaggarato vagganandī vaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
06.‘‘Pharusavāco kho pana hoti. Yā sā vācā aṇḍakā [kaṇḍakā (ka.)] kakkasā parakaṭukā parābhisajjanī kodhasāmantā asamādhisaṃvattanikā , tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
07.‘‘Samphappalāpī kho pana hoti. Akālavādī abhūtavādī anatthavādī adhammavādī avinayavādī. Anidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti akālena anapadesaṃ apariyantavatiṃ anatthasaṃhitaṃ.
08.Idha, gahapatayo, ekacco abhijjhālu hoti, yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ abhijjhātā hoti – ‘aho vata yaṃ parassa taṃ mamassā’’’ti!
09.‘‘Byāpannacitto kho pana hoti paduṭṭhamanasaṅkappo – ‘ime sattā haññantu vā vajjhantu vā ucchijjantu vā vinassantu vā mā vā ahesu’’’nti [mā vā ahesuṃ iti vāti (sī. pī. ka.)].
10.‘‘Micchādiṭṭhiko kho pana hoti viparītadassano – ‘natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi hutaṃ, natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, natthi ayaṃ loko natthi paro loko, natthi mātā natthi pitā, natthi sattā opapātikā , natthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentī’ti.
・十善業道
01.Idha, gahapatayo, ekacco pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato hoti, nihitadaṇḍo nihitasattho lajjī dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati.
02.‘‘Adinnādānaṃ pahāya adinnādānā paṭivirato hoti. Yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ, gāmagataṃ vā araññagataṃ vā, taṃ nādinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti.
03.‘‘Kāmesumicchācāraṃ pahāya kāmesumicchācārā paṭivirato hoti. Yā tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā bhāturakkhitā bhaginirakkhitā ñātirakkhitā gottarakkhitā dhammarakkhitā sassāmikā saparidaṇḍā antamaso mālāguḷaparikkhittāpi, tathārūpāsu na cārittaṃ āpajjitā hoti.
04.‘‘Idha, gahapatayo, ekacco musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti. Sabhāgato vā parisāgato vā, ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā, abhinīto sakkhipuṭṭho – ‘ehambho purisa, yaṃ jānāsi taṃ vadehī’ti, so ajānaṃ vā āha – ‘na jānāmī’ti, jānaṃ vā āha – ‘jānāmī’ti, apassaṃ vā āha – ‘na passāmī’ti, passaṃ vā āha – ‘passāmī’ti. Iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā na sampajānamusā bhāsitā hoti.
05.‘‘Pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti, ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya, amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya. Iti bhinnānaṃ vā sandhātā, sahitānaṃ vā anuppadātā, samaggārāmo samaggarato samagganandī samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
06.‘‘Pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti. Yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā – tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
07.‘‘Samphappalāpaṃ pahāya samphappalāpā paṭivirato hoti. Kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasaṃhitaṃ.
08.‘‘Idha, gahapatayo, ekacco anabhijjhālu hoti, yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ nābhijjhātā hoti – ‘aho vata yaṃ parassa taṃ mamassā’ti!
09.‘‘Abyāpannacitto kho pana hoti appaduṭṭhamanasaṅkappo – ‘ime sattā averā abyābajjhā anīghā sukhī attānaṃ pariharantū’ti.
10.‘‘Sammādiṭṭhiko kho pana hoti aviparītadassano – ‘atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ, atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, atthi ayaṃ loko atthi paro loko, atthi mātā atthi pitā, atthi sattā opapātikā, atthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentī’ti.
・十悪業道
01.ここにある者は生き物を殺す。
凶暴であり、血のある生き物を殺戮することを続け、生き物に憐れみを起こすことがない者である。
02.また与えられていないのに取る。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを村に行き、林に行き、それを与えられていないのに取り、盗みと言われることをする。
03.また欲において邪行をする。
母に守られ、父に守られ、母父に守られ、兄弟に守られ、姉妹に守られ、親族に守られ、一族に守られ、法に守られ、夫のある者、刑罰のある者、ないし華鬘・アクセサリーで飾られた者など、そのような者と会って行じる。
04.ここにある者は妄語をする。
集会に行き、あるいは集団に行き、あるいは親族の中に行き、あるいは組合の中に行き、証人として引き出され、「さあ、あなたはあなたが知っていることを語りなさい」と尋問され、彼はあるいは知らないのに「私は知っています」と言い、あるいは知っているのに「私は知りません」と言い、あるいは見ていないのに「私は見ました」と言い、あるいは見たのに「私は見ていません」と言う。このようにあるいは自己を原因として、あるいは他者を原因として、あるいは何らかの財産を原因として、自覚しながら偽りを語る。
05.また割れる語をする。
こちらから聞いてあちらに告げてこちらと分裂させ、あちらから聞いてこちらに告げてあちらと分裂させる。このようにあるいは和合を分裂させ、あるいは分裂を助長し、不和合を愛好し、不和合を楽しみ、不和合を喜び、不和合を作す言葉を語る。
06.また不快語をする。
睾丸(下品)であり、粗暴であり、他者を刺激し、他者を煩わせ、忿と隣り合わせであり、三摩地に転じない、そのような言葉を語る。
07.また雑な駄弁をする(混ざったもみがら)。
時でないのに語り、事実でないのに語り、利益のないことを語り、非法を語り、非律を語る。時でなく、筋が通らず、際限なく語り、利益を伴わず、覚える価値のない言葉を語る。
08.ここにある者は貪求する。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを「ああ、実に他者のものが私のものになるように」と貪求する。
09.また怒りのある心であり、意思が汚れている。
「この生ける者は害され、あるいは殺され、あるいは切断され、あるいは消え、あるいは無くなり、あるいは存在しないように」と。
10.また邪見であり、転倒して見る。
「布施は存在せず、供儀は存在せず、献供は存在しない。善作悪作の業の果が熟すること(異熟、結熟、結果)は存在しない。この世は存在せず、他の世は存在しない。母は存在せず、父は存在しない。化生の生ける者は存在しない。世間において正しく行き、正しく行道し、この世と他の世を自ら超知し、実証し、説く沙門婆羅門は存在しない」と。
・十善業道
01.ここにある者は生き物を殺すことを断ち、生き物を殺すことから離れている。
杖を置き、刀を置き、恥を知り、憐れみを起こし、一切の生き物の益を哀愍して住する。
02.また与えられていないのに取ることを断ち、与えられていないのに取ることから離れている。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを村に行き、林に行き、それを与えられていないのに取り、盗みと言われることをしない。
03.また欲における邪行を断ち、欲における邪行から離れている。
母に守られ、父に守られ、母父に守られ、兄弟に守られ、姉妹に守られ、親族に守られ、一族に守られ、法に守られ、夫のある者、刑罰のある者、ないし華鬘・アクセサリーで飾られた者など、そのような者と会って行じない。
04.ここにある者は妄語を断ち、妄語から離れている。
集会に行き、あるいは集団に行き、あるいは親族の中に行き、あるいは組合の中に行き、証人として引き出され、「さあ、あなたはあなたが知っていることを語りなさい」と尋問され、彼はあるいは知らないのに「私は知っています」と言い、あるいは知っているのに「私は知りません」と言い、あるいは見ていないのに「私は見ました」と言い、あるいは見たのに「私は見ていません」と言う。このようにあるいは自己を原因として、あるいは他者を原因として、あるいは何らかの財産を原因として、自覚しながら偽りを語ることがない。
05.また割れる語を断ち、割れる語から離れている。
こちらから聞いてあちらに告げてこちらと分裂させることがなく、あちらから聞いてこちらに告げてあちらと分裂させることがない。このようにあるいは分裂を和合させ、あるいは和合を助長し、和合を愛好し、和合を楽しみ、和合を喜び、和合を作す言葉を語る。
06.また不快語を断ち、不快語から離れている。
聾でなく、耳に楽であり、愛すべきであり、心に入り、上品であり、多くの人が好み、多くの人の意にかなう、そのような言葉を語る。
07.また雑な駄弁を断ち、雑な駄弁から離れている。
時にかなって語り、事実を語り、利益のあることを語り、法を語り、律を語る。時にかない、筋が通り、際限があって語り、利益を伴い、覚える価値のある言葉を語る。
08.ここにある者は貪求しない。
他者のものであり、他者の財産・資財であるものを「ああ、実に他者のものが私のものになるように」と貪求しない。
09.また怒りのない心であり、意思が汚れていない。
「この生ける者は怨みなく、悩害なく、動転することなく、楽であり、自分を大事にするように」と。
10.また正見であり、転倒せずに見る。
「布施は存在し、供儀は存在し、献供は存在する。善作悪作の業の果が熟することは存在する。この世は存在し、他の世は存在する。母は存在し、父は存在する。化生の生ける者は存在する。世間において正しく行き、正しく行道し、この世と他の世を自ら超知し、実証し、説く沙門婆羅門は存在する」と。
『南伝大蔵経10 中部経典2』大蔵出版 P3−7
この経典の内容はサーラー村のバラモンたちとゴータマの問答です。簡単に書くと以下の通りです。会話の内容は僕が省略して書いています。
バラモン:「何が原因で地獄に行き、何が原因で天界に行くのか」。
ゴータマ:「悪業を原因として地獄に行き、善業を原因として天界に行く」。
バラモン:「省略されていてわかりませんので、解説してください」
ゴータマ:
「十悪業である三の身悪行・四の語悪行・三の意悪行。これが原因で地獄に行く。
十善業である三の身善行・四の語善行・三の意善行。これが原因で天界に行く。
十善を作す者が金持ちの貴族に転生したいと願えば、転生できる。法行者・正行者だから。
十善を作す者が金持ちの婆羅門に転生したいと願えば、転生できる。法行者・正行者だから。
・・・金持ちの居士に転生したいと願えば、転生できる。
・・・四大王天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・三十三天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・ヤーマ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・トゥシタ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・ニンマーナラティ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・パラニンミタ・ヴァサヴァッティ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・ブラフマカーイカ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・少光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・無量光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・極光天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・少浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・無量浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・遍浄天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・アヴィハ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・アタッパ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・スダッサ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・スダッシン天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・アカニッタ天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・空無辺処天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・識無辺処天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・無所有処天に転生したいと願えば、転生できる。
・・・非想非非想処天に転生したいと願えば、転生できる。
十善を作す者が倶分解脱したいと願えば、倶分解脱できる。法行者・正行者だから。
バラモン:「ゴータマ、素晴らしい。今日から私たちはあなたに帰依し、法に帰依し、サンガに帰依します」 (終)
以前書いた「善き来世への転生」のトピックは、信戒聞捨慧の五財から転生する話でしたが、これは十善業道から転生する話です。転生先の詳細さにも若干の違いがあります。
十悪を断ち、十善を作せばそれで地獄に行かずに天国に行けるなら、「よし、とりあえずこれをやろう」と思えてきます。そこでこれを実践するときに少し気をつけたいのは以下のことです。つまり、「不快な言葉をやめれば、即、上品で優雅で人が喜ぶ言葉が語れるわけではない」ということです。不快な言葉をやめることは不快な言葉をやめることとして一つの努力が必要です。それとは別で、上品な言葉遣いになったり、相手が喜ぶ言葉を探す能力というのは、これもまた別の努力によって獲得する必要があります。それで、この修行を実践したい人は「十のことをやればいいのだ」と考えるよりも、「まず十悪を断って、それから十善を修めるという二十のことをやろう」と考えるとより一層円満だと思います。人は誰しも「誰かには不快なことを言って、誰かには相手が喜ぶことを言っているものだから」です。意の三悪行である貪求と瞋りは「他者を害さなければとりあえずよし」でいいと思います。「まず他者を害する貪りを断って、その次に自己を害する貪りを断つ」というのがやりやすいと思います。怒りは他者を害するものですから、怒りは断ちます。その次に「他者は害さないが、自己を害する動かしがたい不快感を断つ」という流れがやりやすいと思います。
「俺は十善をやってるから、酒を飲んでもいいんだ」と言う人もいるかと思いますが、その場合はとりあえず今はお酒を飲んでもいいと思います。戒律を守るのはその人の自由なので、段々にゆっくり上を目指していけばいいので。もちろん、お酒を飲むよりもお酒を飲まない方が悪を作す機会は激減すると思いますし、もしお酒をやめる方がいればその人はブッダの言葉と律を尊重していて立派です。
この経典の最後に「法行者が解脱したいと願えば、解脱できる」と書いてあります。ゴータマの意図はもちろん「お前たちは修行を完成させなさい」というのが本音だとは思います。ただ解脱するしないも個人の自由ですし、苦しみの不利益性をよく観じないかぎりは「苦滅がどうしてそんなに推奨されるのかよくわからない」のは当然なので、最上の境地を求める義務は誰にもありません。ただ十善業道はそれだけ善いものだということです。最後の正見を輪廻に導く正見から四諦を観じる聖なる正見に持って行けば、確かに解脱ができるという道理です。十悪がないので他者を害することがなく、他者を害さないので後悔せず、後悔しないので心が乱されることがなく、心が乱されることがないので心が集中し、心が集中するので四諦を知る努力ができ、四諦を知る努力を十分為したときは四諦を完全に知り尽くし、四諦を完全に知り尽くしたときは心が自然に苦因を断ち苦滅道を修さないわけにはいかなくなって、ついに完成に到るということです。十善さえあれば、どこにでも転生できるというのは善い教えだと思います。
これは意行(正思・正見)が入っているので、戒(正語・正業・正命)とは少し違うのですが、でも僕はこれを「戒」としてまとめて考えて修行しています。その方が覚え易いので。また五財(信戒聞捨慧)の戒をこの十善とみなすと、より包括的に修行ができていいです。
この「断十悪」と「修十善」ができたら、さらに新しい戒を学ぶのも楽しいことだと思います。例えば「殴らない」などです。暴力を振るわなければ、来世は健康な身体が手に入るぞというのは楽しいことです。また例えば「慈眼」です。「メデューサの邪眼」が有名ですがその逆で「幸せになれ」という慈心を伴ってまっすぐに相手を見るという戒です。これをマスターすると美しいまつげと美しい瞳が手に入るということです。どんどん戒を学んで行く「増上戒学」というのは三学の最初ですが、それを尊重するのは善いことです。戒律を守るモチベーションを高めるためにしばしばその利益を考えます。「十悪がある人間は人に認められないし、愛されない。十悪がある人間と付き合いたくない。しかし、十善がある人間は人に認められるし、愛されるに違いない。十善がある人間の方が高く評価されるし、多くの人に愛される。そうだ、もっと人に愛される人間になってみてはどうか。きっといいだろう」と考えてください。
具体的にどのように実践するのかというと、僕のおすすめはやはり朝起きたときと夜寝るときです。そのときに、
「殺さず哀れむ。
盗まず清浄。
不倫をしない、心でも。
嘘つかずに信用される。
仲間割れさせず、仲良くさせる。
不快なことを言わず、優しく上品に。
無駄話せずに、利益ある言葉。
人のものを欲しがらずに、少欲。
人の不幸を願わなず、慈心。
邪に見ずに、まっすぐに見る」
これを一日一回でも続けて、一ヶ月とか二ヶ月経つと案外、身に付いて来ます。身に付いてくると安心感が出て来て、「戒律っていいなぁ」と思うようになると思います。身に付いていないと戒律に対して苦手意識があるものですが、身に付けば好きになります。原始仏典の記述を信じる人はぜひやってみてください。少なくとも確実に十善がある人になれば、今よりも愛されるようになりますから。
・十悪業道
01.Idha, gahapatayo, ekacco pāṇātipātī hoti, luddo [luddo dāruṇo (ka.) ṭīkā oloketabbā] lohitapāṇi hatappahate niviṭṭho adayāpanno pāṇabhūtesu [sabbapāṇabhūtesu (syā. kaṃ. ka.)].
02.‘‘Adinnādāyī kho pana hoti. Yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ, gāmagataṃ vā araññagataṃ vā, taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti.
03.‘‘Kāmesumicchācārī kho pana hoti. Yā tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā bhāturakkhitā bhaginirakkhitā ñātirakkhitā gottarakkhitā dhammarakkhitā sassāmikā saparidaṇḍā antamaso mālāguḷaparikkhittāpi, tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti.
04.Idha, gahapatayo, ekacco musāvādī hoti. Sabhāgato vā parisāgato vā, ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā, abhinīto sakkhipuṭṭho – ‘ehambho purisa, yaṃ jānāsi taṃ vadehī’ti , so ajānaṃ vā āha – ‘jānāmī’ti, jānaṃ vā āha – ‘na jānāmī’ti, apassaṃ vā āha – ‘passāmī’ti, passaṃ vā āha – ‘na passāmī’ti [so āha ajānaṃ vā ahaṃ jānāmīti jānaṃ vā ahaṃ na jānāmīti apassaṃ vā ahaṃ passāmīti passaṃ vā ahaṃ na passāmīti (ka.)]. Iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā sampajānamusā bhāsitā hoti.
05.‘‘Pisuṇavāco kho pana hoti. Ito sutvā amutra akkhātā imesaṃ bhedāya, amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya. Iti samaggānaṃ vā bhettā [bhedakā (ka.), bhedetā (syā. kaṃ.), tadaṭṭhakathāyaṃ pana bhettāti dissati], bhinnānaṃ vā anuppadātā, vaggārāmo vaggarato vagganandī vaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
06.‘‘Pharusavāco kho pana hoti. Yā sā vācā aṇḍakā [kaṇḍakā (ka.)] kakkasā parakaṭukā parābhisajjanī kodhasāmantā asamādhisaṃvattanikā , tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
07.‘‘Samphappalāpī kho pana hoti. Akālavādī abhūtavādī anatthavādī adhammavādī avinayavādī. Anidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti akālena anapadesaṃ apariyantavatiṃ anatthasaṃhitaṃ.
08.Idha, gahapatayo, ekacco abhijjhālu hoti, yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ abhijjhātā hoti – ‘aho vata yaṃ parassa taṃ mamassā’’’ti!
09.‘‘Byāpannacitto kho pana hoti paduṭṭhamanasaṅkappo – ‘ime sattā haññantu vā vajjhantu vā ucchijjantu vā vinassantu vā mā vā ahesu’’’nti [mā vā ahesuṃ iti vāti (sī. pī. ka.)].
10.‘‘Micchādiṭṭhiko kho pana hoti viparītadassano – ‘natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi hutaṃ, natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, natthi ayaṃ loko natthi paro loko, natthi mātā natthi pitā, natthi sattā opapātikā , natthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentī’ti.
・十善業道
01.Idha, gahapatayo, ekacco pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato hoti, nihitadaṇḍo nihitasattho lajjī dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati.
02.‘‘Adinnādānaṃ pahāya adinnādānā paṭivirato hoti. Yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ, gāmagataṃ vā araññagataṃ vā, taṃ nādinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti.
03.‘‘Kāmesumicchācāraṃ pahāya kāmesumicchācārā paṭivirato hoti. Yā tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā bhāturakkhitā bhaginirakkhitā ñātirakkhitā gottarakkhitā dhammarakkhitā sassāmikā saparidaṇḍā antamaso mālāguḷaparikkhittāpi, tathārūpāsu na cārittaṃ āpajjitā hoti.
04.‘‘Idha, gahapatayo, ekacco musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti. Sabhāgato vā parisāgato vā, ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā, abhinīto sakkhipuṭṭho – ‘ehambho purisa, yaṃ jānāsi taṃ vadehī’ti, so ajānaṃ vā āha – ‘na jānāmī’ti, jānaṃ vā āha – ‘jānāmī’ti, apassaṃ vā āha – ‘na passāmī’ti, passaṃ vā āha – ‘passāmī’ti. Iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā na sampajānamusā bhāsitā hoti.
05.‘‘Pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti, ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya, amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya. Iti bhinnānaṃ vā sandhātā, sahitānaṃ vā anuppadātā, samaggārāmo samaggarato samagganandī samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
06.‘‘Pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti. Yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā – tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
07.‘‘Samphappalāpaṃ pahāya samphappalāpā paṭivirato hoti. Kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasaṃhitaṃ.
08.‘‘Idha, gahapatayo, ekacco anabhijjhālu hoti, yaṃ taṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ nābhijjhātā hoti – ‘aho vata yaṃ parassa taṃ mamassā’ti!
09.‘‘Abyāpannacitto kho pana hoti appaduṭṭhamanasaṅkappo – ‘ime sattā averā abyābajjhā anīghā sukhī attānaṃ pariharantū’ti.
10.‘‘Sammādiṭṭhiko kho pana hoti aviparītadassano – ‘atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ, atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko, atthi ayaṃ loko atthi paro loko, atthi mātā atthi pitā, atthi sattā opapātikā, atthi loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentī’ti.
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏教 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏教のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人