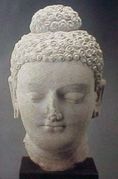中部経典の第120経『行生経』を解説します。
・中部経典 第120経 『行生経』 転生方法 全訳
http://
・経名と法門名
行生:サンカールパパッティ、saṅkhārupapatti、サンカーラ(行)とウパパッティ(再生・転生)で「行によって再生すること」
・教え
「比丘たちよ、ここに比丘は信を具足しており、戒を具足しており、聞を具足しており、捨を具足しており、慧を具足している。彼にはこうある。『ああ、実に身が破れ死して後、(カッティヤの大家・・・)との共住に再生しよう』と。彼はその心を定め、その心を依拠とし、その心を修習する。彼はその行と住をこのように修習し、このように多く作せば、そこに再生することに転じる。比丘たちよ、この道この道跡はそこに再生することに転じる」
ここにIdha, 比丘たちよbhikkhave, 比丘はbhikkhu 信saddhāya 具足samannāgato しておりhoti, 戒sīlena samannāgato hoti, 聞sutena samannāgato hoti, 捨cāgena samannāgato hoti, 慧paññāya samannāgato hoti.
彼にはTassa これがevaṃ あるhoti – ‘ああaho 実にvatāhaṃ 身がkāyassa 破れbhedā 後paraṃ 死してmaraṇā カッティヤ大家とのkhattiyamahāsālānaṃ 共住にsahabyataṃ 再生しようupapajjeyya’とnti.
彼はSo そのtaṃ 心をcittaṃ 定めdahati, そのtaṃ 心をcittaṃ 依拠としadhiṭṭhāti, そのtaṃ 心をcittaṃ 修習するbhāveti .
彼はTassa そのte 行saṅkhārā とca 住vihārā とをca このようにevaṃ 修習しbhāvitā このようにevaṃ 多く作せばbahulīkatā そこに再生することにtatrupapattiyā 転じるsaṃvattanti.
このAyaṃ, 比丘たちよbhikkhave, 道maggo このayaṃ 道跡はpaṭipadā そこに転生することにtatrupapattiyā 転じるsaṃvattati.
・五財
信具足:サッダー(信)サマンナーガタ(具足)、ホーティ(ある)saddhāya samannāgato hoti, 、
戒具足:シーラ(戒)sīlena samannāgato hoti,
聞具足:スタ(聞)sutena samannāgato hoti,
捨具足:チャーガ(捨・布施)cāgena samannāgato hoti,
慧具足:パンニャ(慧)paññāya samannāgato hoti.
・転生先
カッティヤ大家・ブラーフマナ大家・ガハパティ大家
四大王天・三十三天・夜摩天・都卒天・化楽天・他化自在天
千梵・二千梵・三千梵・四千梵・五千梵・一万梵・十万梵
光天・少光天・無量光天・極光天
浄天・少浄天・無量浄天・遍浄天
広果天・五浄居天(無煩・無熱・善見・善現・アカニッタ)[無想天はここではなし]
空無辺処天・識無辺処天・無所有処天・非想非非想処天
阿羅漢(転生超越・真の誕生)
wikipediaの「三界」の説明は大部分が北伝文献をもとにしていて、南伝文献には記述のないものが多いです。注意が必要です。ここでは原始仏典に依拠して解説していきます。論の内容は含んでいません。また神々に関する包括的な説明は記述が膨大なので大変なのでまた別の機会にしたいと思います。
01 カッティヤ大家 khattiyamahāsālānaṃ
02 婆羅門大家 brāhmaṇamahāsālānaṃ
03 居士大家 gahapatimahāsālānaṃ
以上、人間の三つの善い転生先。
04 四大王天 チャートゥ(四)マハー(大)ラージカー(王)デーヴァー(神々)cātumahārājikā devā
05 三十三天 ターヴァ(三十)ティンサー(三)tāvatiṃsā devā
06 ヤーマ天 yāmā devā 当時人間であったヤーマ、一般名詞では「yāma 禁制、禁戒;夜分」。そこから僕は「禁戒ある神々」「夜の神々」とも考えています。人間であったヤーマも禁戒を保持していたと考えられます。また古代ギリシャでは「夜は至福なる神々のものである」と言われていました。夜と言えば月です。あるいは先祖に関わるのかも知れません。「先祖が布施したから私も布施しよう、と布施する者はヤーマ天に行く」という内容の記述があります。
07 トゥシタ天 tusitā devā 「tussati 満足する、喜ぶ」から僕は「満足する神々」「喜ぶ神々」とも考えています。如来の前世と菩薩の母の死後がトゥシタ天という記述は原始仏典にも見え、信頼できる情報です。
08 化楽天 ニンマーナラティ、nimmānaratī devā。「nimmāna ①化作、創造 ②慢なき」「rati 楽、喜楽」から「楽を化作する神々」「快楽を創造する神々」です。長部経典33経から参考になる箇所を引用します。サーリプッタの説法で三法からです。
「三つの欲の発生がある。友よ、生ける者たちに欲(の対象)が現に生じていて、彼は現に生じている欲に対して自在を行使する。たとえば一部の人々、一部の神々、一部の堕処者である。これが第一の欲の発生である。友よ、生ける者たちが欲を化作し、彼は化作し化作した欲に対して自在を行使する。たとえば化楽天である。これが第二の欲の発生である。友よ、生ける者たちが他者に対して欲を化作し、彼は他者に対して化作した欲に対して自在を行使する。たとえば他化自在天である。これが第三の欲の発生である」(南伝8 P297に相当、ここでは僕が訳してます)。
この記述が化楽天に関する最も重要な記述です。化楽天という単語は出てきませんが別の箇所では、女性が夫に尽くして転生する可意衆天(欲しい色・声・楽の三つを自在に手に入れる)に関する記述があって、これもまた化楽天の一群だと推測できます。
09 他化自在天 パラニンミタ・ヴァサヴァッティ、paranimmitavasavattī devā。「para ①向こうに、超えて、彼方に ②他の、彼方の、上の」「nimmita 化作の、化人、化神」「vasa 自在、力、権力、影響(vasavattin 自在力ある)」。上でも引用しましたが、この第三の欲生がもっとも解釈が難しいのですが、文章の主語が「他化自在天」であるということを念頭において読まれれば理解できると思います。ある訳では「他者が化作した欲望の対象を享受する」とありますが、それでは魔王が快楽を得るために誰かに魔王の欲望の対象を化作してもらわなければならなくなるので背理です。従って「他化自在天が他者に対して(パラ)欲を(カーマ)化作する(ニンミタ)」と考えなければ通じません。人間はすでに生じた欲望の対象しか自由にできません。しかし化楽天はすでに生じた欲望の対象だけでなく、自分でも欲望の対象を創造できます。さらに他化自在天はこの二者に加えて、他者が楽しむ欲望の対象を創造できます。他化自在天は、自由に他者の快楽の対象を創造するのですが、それによって他化自在天が快楽を感じなければならないわけではないということです(魔女三姉妹が様々な欲をゴータマに化作しましたがいずれも無駄に終わっています)。第一の欲生では、目の前に欲望の対象があって人はそれを手に入れて好きにして楽しむ。つまり、「自分は何もしていないけれども、世の中に自分の愛好する欲望の対象がすでに出現してました。しかも手に入れたからそれに何をしようとこちらの自由」というのが第一の欲生。第二の欲生では、化楽天が自分で創り出します。この欲の対象は化楽天が自由に創造し破壊できますし、他の人間もそれを享受できます。アヌルッダに舞いを見せた可意衆天のように。しかし、アヌルッダはそれを味わわなかったので彼にとっては欲の対象ではありませんでした。化楽天と他化自在天の相違は、化楽天は自分の快楽対象を好きに創造できるけれども、他者の快楽対象を自由には創造できないところにあります。第三の欲生では、他化自在天が他者の快楽対象を好きに創造するので、可意衆天がアヌルッダを誘惑するよりも本格的な攻撃になります。化楽天は自分の意にかなうものしか創造できないが、他化自在天は自分の意にかなうものだけでなく他者の意にかなうものまで創造できます。だからこそ、それによって人々を支配できるわけです。いわば、自分の好きな曲しか作曲できない芸術家と、自分は好きではないが他者が愛好する曲を作曲できるプロの職人としての作曲家の違いのようなものだと思います。もし、化楽天が人の喜ぶものを創造できるなら、それはもはや他化自在天に格が上がっているのです。身は化楽天でしょうが。そして、他者を支配できるからこそ、他者の欲求をコントロールして人々に強烈な解脱への欲求を起こさせようということを考える他化自在天の存在も考えられるわけです。そして、そのような善である他化自在天はかつて人としてブッダの聖弟子であった人々が転生した他化自在天に多いに違いないとも推測できます。ところでサタンの頭領であるルシファーは神に嫉妬して堕ちましたが、原始仏教におけるマーラ・パーピマンがルシファーであるとは一概に断言できません。マーラ・パーピマンがマハーブラフマンに嫉妬しているという確定的な証拠がないからです。ただやはり、欲望によって人々を支配しようと意図するところは同じです。
以上、善い転生先である六欲天。
10 千梵 サハッソー・ブラフマー sahasso brahmā 「sahassa 千」 千世界(sahassilokadhātuṃ)を遍満pharitvāして勝解adhimuccitvāして住するviharati梵天です。手の平の円にたとえられています。一世界は一つの太陽と月が照らす範囲ですから、この太陽系ほどと思っていいと思います。星々は遠くの太陽ですが、この地球を照らしきれていませんから。そこで千世界とは千の恒星とそこを巡る惑星群であると考えられます。
11 二千梵 ドヴィサハッソー・ブラフマー dvisahasso brahmā 「dvi 二」 二つの円です。
12 三千梵 ティサハッソー・ブラフマー tisahasso brahmā 「ti 三」
13 四千梵 チャトゥサハッソー・ブラフマー catusahasso brahmā 「catu 四」
14 五千梵 パンチャサハッソー・ブラフマー pañcasahasso brahmā 「pañca 五」
15 十千梵 ダササハッソー・ブラフマー dasasahasso brahmā 「dasa 十」「sahassa 千」で一万。一万世界は八角形の宝石に譬えられています。円盤ではないようです。
16 百千梵 サタサハッソー・ブラフマー satasahasso brahmā 「sata 百、多くの」「sahassa 千」で十万。十万世界は「nikkha 首飾、金環、金貨」に譬えられています。もっとも輝く金に象徴される円盤状のもののようなので銀河でしょうか。これが梵が支配する世界としては大きな区切りなのだと思います。
梵天は、初禅を愛好する者、慈心解脱を愛好する者が転生します。無聞の凡夫は梵天から没した後に悪趣に行くこともありますが、有聞の聖弟子はそのまま進歩して般涅槃します。寿命は1劫です。
以上、善い転生先である七段階の梵天。
17 光天 アーバー・デーヴァー ābhā devā 「ābhā 光、光明」「ābhāti 光る、輝く」 光る神々、輝く神々。少光天・無量光天・極光天の総称だと思います。
18 少光天 パリッターバー parittābhā devā 「paritta 小さい、少ない」 小さく光る神々、少なく光る神々。
19 無量光天 アッパマーナ―バー appamāṇābhā devā 「appamāna 無量、無量の」 無量に光る神々。四無量心の無量と同じ語です。
20 極光天 アーバッサラー ābhassarā devā 「ābhassara 光音、極光」 saraが音をも意味するから光音天と言われ、他の箇所でも「pabhasara」などと使われますが、音を意味する文脈は一度も出て来ないので、またさらにこの経の文脈でも光の究極として出されていると思われるので「極光」と訳すのが適切だと思います。北伝では言葉を発する必要がなく光が音になるから光音天と呼ぶ云々の説が出ていますが、南伝にはそのような記述はありません。
アヌルッダが輝きの大きさは心の大きさであり、一樹下の範囲にまで心を広げる心よりも、二三の樹下、一の村、二三の村、一の国、二三の国、海岸に至るまで心を広げれる心の方が輝きが大きいという修行法を語っています。またぼんやりした光は意識が蒙昧な心、透き通った光は意識がはっきりした心から生じると語っています。多分、五蓋の程度を指しているのだと思います。この色界第二禅天である光天は、第二禅を愛好する者、悲心解脱を愛好する者が転生します。無聞の凡夫と有聞の聖弟子の差異は梵天と同じです。光天の寿命は2劫です。
21 浄天 スバー subhā devā 「subha 浄、清浄の、美しい、幸福の」 欲への意欲を生じる浄相もこの語。三毒の貪を断つための不浄を修習せよという浄もこの語です。
22 少浄天 パリッタスバー parittasubhā devā 少光天と同じ語義です。
23 無量浄天 アッパマーナスバー appamāṇasubhā devā 無量光天と同じ語義です。
24 遍浄天 スバキンナー subhakiṇnā devā 「subhakiṇṇa 遍浄[第三禅天の最上位]」「kiṇṇa 酵母」ですが、全体を発酵させるというところから転じて「遍く清浄な」という語で漢訳したのだと思います。文脈から見ても遍浄で問題ないと思います。極光天に対応させれば「極浄」でもいいかも知れませんが。浄天は、第三禅を愛好する者、喜心解脱を愛好する者が転生します。凡夫と聖弟子の差異は上と同じです。浄天の寿命は4劫です。
25 広果天 ヴェーハッパラー vehapphalā devā 「veha」は「vepulla 広大、方広、成満」から、「phala 果、果実、結果」で「広大な果報を持つ神々」です。詳しい解説は原始仏典ではなされていません。広果天の寿命は500劫です。この経典では「無想有情」(想がないけれど色がある神々)が書いてありません。無想天は適切な転生先の候補ではないようです。
26 無煩天 アヴィハー avihā devā 「aviha 無煩[天]」としか辞書には書いていないのですが、僕は「avihimsā 不害、無害、不殺生」から「害することのない神々」と訳したいです。無煩天をはじめとする浄居天について原始仏典に詳しい解説はまったくありません。名前から推測するしかない状況です。
27 無熱天 アタッパー atappā devā 「atappa 無熱の」。「tappati 焼ける、苦しむ、悩む」に「a」がついて否定形です。「苦しみがない神々」「悩まない神々」です。
28 善見天 スダッサー sudassā devā 「su よき、善き、良き、妙なる、易き、極めて」「dassati 見る、認める、理解する」「dassana 見、見ること」
29 善現天 スダッシン sudassin devā 善見天とほとんど同じ語ですが、僕は「スダッサ」をまだ動的に見ている段階ととらえ、「スダッシン」をすでに見られた、理解されたととらえ善現天を「善解天」であると考えています。詳細は原始仏典上では不明です。
30 アカニッタ天 アカニッター akaniṭṭhā devā 「akaniṭṭha アカニッタ、色究竟、有頂」とありますが色究竟は教義からの解釈ですし、有頂は非想非非想処に到達した神々とも取れますので適切な訳ではありません。「a」は否定形ですので問題はカニッタです。辞書には「kaniṭṭha 形容詞 [kanīnaの最上級]若い、最も若い、劣れる」とあります。これの否定形ですので「若くない、最も若くない、劣っていない」、そこから僕は「最も古き神々」と解釈します。「最も優れた神々」と解釈すると空無辺処以上に到達した神々の地位がおかしくなるからです。詳細は述べられていない神々です。あるサッカは「自分はアカニッタに行き、最終的には涅槃する」と断言しています。浄居天の寿命は不明です。広果天は聖弟子も凡夫も行くところで寿命は500劫と書いてありますが、浄居天は聖弟子しか行けないところで四禅や四無量心中に五取蘊の生滅を観じる者が行くと書いてあるだけで、寿命に関する記述がありません。
以上、色界の神々。
31 空無辺処天 アーカーサーナンチャーヤタヌーパガー ākāsānañcāyatanūpagā devā 「ākāsa虚空、空」「anañcā」は「ananta 無辺の、無限の、無量の」だと思います。「āyatana 処、入、入処」「upaga 到る、達する、経験する、属する」。無辺の空の処に到達した神々。今までの「長寿、美貌、多楽」の記述がここから「長寿、久住、多楽」の記述に変更されます。無色界ですから「色」がありません。自他双方によらずに自らの身を獲得するものとして非想非非想処天がサーリプッタとの問答によって説かれています。ここから「本当に非想非非想処天は非想非非想処に八万劫とどまり続けていること」が明らかです。寿命は1万劫です。
32 識無辺処天 ヴィンニャーナ viññāṇañcāyatanūpagā devā 「viññāṇa 識、分ち知ること、識神、意識」。無辺の識の処に到達した神々。寿命は2万劫です。
33 無所有処天 アーキンチャンナ ākiñcaññāyatanūpagā devā 「ākiñcañña 無所有」「kiñcana 何か、何ものか、障碍、障」。無所有の処に到達した神々。寿命は4万劫です。
34 非想非非想処天 ネーヴァサンニャー・ナーサンニャー nevasaññānāsaññāyatanūpagā devā 「neva・・・na・・・ ・・・にも非ず・・・にも非ず」「sañña 想、想念、概念、表象」「neva・sañña・na・asañña」。(有)想でもなく無想でもない処に到達した神々。寿命は8万劫です。
以上、無色到達の神々。
35 阿羅漢 So āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati.
「彼は諸漏を尽くして無漏の心解脱・慧解脱を現実に自ら勝智し実証し具足して住する」。阿羅漢の定型文です。
So彼は āsavānaṃ諸漏を khayā尽くして anāsavaṃ無漏の cetovimuttiṃ心解脱 paññāvimuttiṃ慧解脱 diṭṭheva現 dhamme法 sayaṃ自ら abhiññā勝智し sacchikatvā実証し upasampajja具足して viharati住する.
転生の超越が不死なので、最高の行き先、善逝が行った善趣です。
「また比丘たちよ、ここに比丘は信を具足しており、戒を具足しており、聞を具足しており、捨を具足しており、慧を具足している。彼にはこうある。「ああ、実に漏を尽くして無漏の心解脱・慧解脱を現実に自ら勝智し実証し具足して住そう」と。彼は漏を尽くして無漏の心解脱・慧解脱を自ら勝智し実証し具足して住する。比丘たちよ、この比丘はどこにも再生しない。」
と書いてありますので、阿羅漢は転生ではないですが話の流れからして、五財を具足して「解脱を手に入れたい」と願えばそうなるという教えだと思います。「そう願えばそうなる」。それが行生経の教えです。
・中部経典 第120経 『行生経』 転生方法 全訳
http://
・経名と法門名
行生:サンカールパパッティ、saṅkhārupapatti、サンカーラ(行)とウパパッティ(再生・転生)で「行によって再生すること」
・教え
「比丘たちよ、ここに比丘は信を具足しており、戒を具足しており、聞を具足しており、捨を具足しており、慧を具足している。彼にはこうある。『ああ、実に身が破れ死して後、(カッティヤの大家・・・)との共住に再生しよう』と。彼はその心を定め、その心を依拠とし、その心を修習する。彼はその行と住をこのように修習し、このように多く作せば、そこに再生することに転じる。比丘たちよ、この道この道跡はそこに再生することに転じる」
ここにIdha, 比丘たちよbhikkhave, 比丘はbhikkhu 信saddhāya 具足samannāgato しておりhoti, 戒sīlena samannāgato hoti, 聞sutena samannāgato hoti, 捨cāgena samannāgato hoti, 慧paññāya samannāgato hoti.
彼にはTassa これがevaṃ あるhoti – ‘ああaho 実にvatāhaṃ 身がkāyassa 破れbhedā 後paraṃ 死してmaraṇā カッティヤ大家とのkhattiyamahāsālānaṃ 共住にsahabyataṃ 再生しようupapajjeyya’とnti.
彼はSo そのtaṃ 心をcittaṃ 定めdahati, そのtaṃ 心をcittaṃ 依拠としadhiṭṭhāti, そのtaṃ 心をcittaṃ 修習するbhāveti .
彼はTassa そのte 行saṅkhārā とca 住vihārā とをca このようにevaṃ 修習しbhāvitā このようにevaṃ 多く作せばbahulīkatā そこに再生することにtatrupapattiyā 転じるsaṃvattanti.
このAyaṃ, 比丘たちよbhikkhave, 道maggo このayaṃ 道跡はpaṭipadā そこに転生することにtatrupapattiyā 転じるsaṃvattati.
・五財
信具足:サッダー(信)サマンナーガタ(具足)、ホーティ(ある)saddhāya samannāgato hoti, 、
戒具足:シーラ(戒)sīlena samannāgato hoti,
聞具足:スタ(聞)sutena samannāgato hoti,
捨具足:チャーガ(捨・布施)cāgena samannāgato hoti,
慧具足:パンニャ(慧)paññāya samannāgato hoti.
・転生先
カッティヤ大家・ブラーフマナ大家・ガハパティ大家
四大王天・三十三天・夜摩天・都卒天・化楽天・他化自在天
千梵・二千梵・三千梵・四千梵・五千梵・一万梵・十万梵
光天・少光天・無量光天・極光天
浄天・少浄天・無量浄天・遍浄天
広果天・五浄居天(無煩・無熱・善見・善現・アカニッタ)[無想天はここではなし]
空無辺処天・識無辺処天・無所有処天・非想非非想処天
阿羅漢(転生超越・真の誕生)
wikipediaの「三界」の説明は大部分が北伝文献をもとにしていて、南伝文献には記述のないものが多いです。注意が必要です。ここでは原始仏典に依拠して解説していきます。論の内容は含んでいません。また神々に関する包括的な説明は記述が膨大なので大変なのでまた別の機会にしたいと思います。
01 カッティヤ大家 khattiyamahāsālānaṃ
02 婆羅門大家 brāhmaṇamahāsālānaṃ
03 居士大家 gahapatimahāsālānaṃ
以上、人間の三つの善い転生先。
04 四大王天 チャートゥ(四)マハー(大)ラージカー(王)デーヴァー(神々)cātumahārājikā devā
05 三十三天 ターヴァ(三十)ティンサー(三)tāvatiṃsā devā
06 ヤーマ天 yāmā devā 当時人間であったヤーマ、一般名詞では「yāma 禁制、禁戒;夜分」。そこから僕は「禁戒ある神々」「夜の神々」とも考えています。人間であったヤーマも禁戒を保持していたと考えられます。また古代ギリシャでは「夜は至福なる神々のものである」と言われていました。夜と言えば月です。あるいは先祖に関わるのかも知れません。「先祖が布施したから私も布施しよう、と布施する者はヤーマ天に行く」という内容の記述があります。
07 トゥシタ天 tusitā devā 「tussati 満足する、喜ぶ」から僕は「満足する神々」「喜ぶ神々」とも考えています。如来の前世と菩薩の母の死後がトゥシタ天という記述は原始仏典にも見え、信頼できる情報です。
08 化楽天 ニンマーナラティ、nimmānaratī devā。「nimmāna ①化作、創造 ②慢なき」「rati 楽、喜楽」から「楽を化作する神々」「快楽を創造する神々」です。長部経典33経から参考になる箇所を引用します。サーリプッタの説法で三法からです。
「三つの欲の発生がある。友よ、生ける者たちに欲(の対象)が現に生じていて、彼は現に生じている欲に対して自在を行使する。たとえば一部の人々、一部の神々、一部の堕処者である。これが第一の欲の発生である。友よ、生ける者たちが欲を化作し、彼は化作し化作した欲に対して自在を行使する。たとえば化楽天である。これが第二の欲の発生である。友よ、生ける者たちが他者に対して欲を化作し、彼は他者に対して化作した欲に対して自在を行使する。たとえば他化自在天である。これが第三の欲の発生である」(南伝8 P297に相当、ここでは僕が訳してます)。
この記述が化楽天に関する最も重要な記述です。化楽天という単語は出てきませんが別の箇所では、女性が夫に尽くして転生する可意衆天(欲しい色・声・楽の三つを自在に手に入れる)に関する記述があって、これもまた化楽天の一群だと推測できます。
09 他化自在天 パラニンミタ・ヴァサヴァッティ、paranimmitavasavattī devā。「para ①向こうに、超えて、彼方に ②他の、彼方の、上の」「nimmita 化作の、化人、化神」「vasa 自在、力、権力、影響(vasavattin 自在力ある)」。上でも引用しましたが、この第三の欲生がもっとも解釈が難しいのですが、文章の主語が「他化自在天」であるということを念頭において読まれれば理解できると思います。ある訳では「他者が化作した欲望の対象を享受する」とありますが、それでは魔王が快楽を得るために誰かに魔王の欲望の対象を化作してもらわなければならなくなるので背理です。従って「他化自在天が他者に対して(パラ)欲を(カーマ)化作する(ニンミタ)」と考えなければ通じません。人間はすでに生じた欲望の対象しか自由にできません。しかし化楽天はすでに生じた欲望の対象だけでなく、自分でも欲望の対象を創造できます。さらに他化自在天はこの二者に加えて、他者が楽しむ欲望の対象を創造できます。他化自在天は、自由に他者の快楽の対象を創造するのですが、それによって他化自在天が快楽を感じなければならないわけではないということです(魔女三姉妹が様々な欲をゴータマに化作しましたがいずれも無駄に終わっています)。第一の欲生では、目の前に欲望の対象があって人はそれを手に入れて好きにして楽しむ。つまり、「自分は何もしていないけれども、世の中に自分の愛好する欲望の対象がすでに出現してました。しかも手に入れたからそれに何をしようとこちらの自由」というのが第一の欲生。第二の欲生では、化楽天が自分で創り出します。この欲の対象は化楽天が自由に創造し破壊できますし、他の人間もそれを享受できます。アヌルッダに舞いを見せた可意衆天のように。しかし、アヌルッダはそれを味わわなかったので彼にとっては欲の対象ではありませんでした。化楽天と他化自在天の相違は、化楽天は自分の快楽対象を好きに創造できるけれども、他者の快楽対象を自由には創造できないところにあります。第三の欲生では、他化自在天が他者の快楽対象を好きに創造するので、可意衆天がアヌルッダを誘惑するよりも本格的な攻撃になります。化楽天は自分の意にかなうものしか創造できないが、他化自在天は自分の意にかなうものだけでなく他者の意にかなうものまで創造できます。だからこそ、それによって人々を支配できるわけです。いわば、自分の好きな曲しか作曲できない芸術家と、自分は好きではないが他者が愛好する曲を作曲できるプロの職人としての作曲家の違いのようなものだと思います。もし、化楽天が人の喜ぶものを創造できるなら、それはもはや他化自在天に格が上がっているのです。身は化楽天でしょうが。そして、他者を支配できるからこそ、他者の欲求をコントロールして人々に強烈な解脱への欲求を起こさせようということを考える他化自在天の存在も考えられるわけです。そして、そのような善である他化自在天はかつて人としてブッダの聖弟子であった人々が転生した他化自在天に多いに違いないとも推測できます。ところでサタンの頭領であるルシファーは神に嫉妬して堕ちましたが、原始仏教におけるマーラ・パーピマンがルシファーであるとは一概に断言できません。マーラ・パーピマンがマハーブラフマンに嫉妬しているという確定的な証拠がないからです。ただやはり、欲望によって人々を支配しようと意図するところは同じです。
以上、善い転生先である六欲天。
10 千梵 サハッソー・ブラフマー sahasso brahmā 「sahassa 千」 千世界(sahassilokadhātuṃ)を遍満pharitvāして勝解adhimuccitvāして住するviharati梵天です。手の平の円にたとえられています。一世界は一つの太陽と月が照らす範囲ですから、この太陽系ほどと思っていいと思います。星々は遠くの太陽ですが、この地球を照らしきれていませんから。そこで千世界とは千の恒星とそこを巡る惑星群であると考えられます。
11 二千梵 ドヴィサハッソー・ブラフマー dvisahasso brahmā 「dvi 二」 二つの円です。
12 三千梵 ティサハッソー・ブラフマー tisahasso brahmā 「ti 三」
13 四千梵 チャトゥサハッソー・ブラフマー catusahasso brahmā 「catu 四」
14 五千梵 パンチャサハッソー・ブラフマー pañcasahasso brahmā 「pañca 五」
15 十千梵 ダササハッソー・ブラフマー dasasahasso brahmā 「dasa 十」「sahassa 千」で一万。一万世界は八角形の宝石に譬えられています。円盤ではないようです。
16 百千梵 サタサハッソー・ブラフマー satasahasso brahmā 「sata 百、多くの」「sahassa 千」で十万。十万世界は「nikkha 首飾、金環、金貨」に譬えられています。もっとも輝く金に象徴される円盤状のもののようなので銀河でしょうか。これが梵が支配する世界としては大きな区切りなのだと思います。
梵天は、初禅を愛好する者、慈心解脱を愛好する者が転生します。無聞の凡夫は梵天から没した後に悪趣に行くこともありますが、有聞の聖弟子はそのまま進歩して般涅槃します。寿命は1劫です。
以上、善い転生先である七段階の梵天。
17 光天 アーバー・デーヴァー ābhā devā 「ābhā 光、光明」「ābhāti 光る、輝く」 光る神々、輝く神々。少光天・無量光天・極光天の総称だと思います。
18 少光天 パリッターバー parittābhā devā 「paritta 小さい、少ない」 小さく光る神々、少なく光る神々。
19 無量光天 アッパマーナ―バー appamāṇābhā devā 「appamāna 無量、無量の」 無量に光る神々。四無量心の無量と同じ語です。
20 極光天 アーバッサラー ābhassarā devā 「ābhassara 光音、極光」 saraが音をも意味するから光音天と言われ、他の箇所でも「pabhasara」などと使われますが、音を意味する文脈は一度も出て来ないので、またさらにこの経の文脈でも光の究極として出されていると思われるので「極光」と訳すのが適切だと思います。北伝では言葉を発する必要がなく光が音になるから光音天と呼ぶ云々の説が出ていますが、南伝にはそのような記述はありません。
アヌルッダが輝きの大きさは心の大きさであり、一樹下の範囲にまで心を広げる心よりも、二三の樹下、一の村、二三の村、一の国、二三の国、海岸に至るまで心を広げれる心の方が輝きが大きいという修行法を語っています。またぼんやりした光は意識が蒙昧な心、透き通った光は意識がはっきりした心から生じると語っています。多分、五蓋の程度を指しているのだと思います。この色界第二禅天である光天は、第二禅を愛好する者、悲心解脱を愛好する者が転生します。無聞の凡夫と有聞の聖弟子の差異は梵天と同じです。光天の寿命は2劫です。
21 浄天 スバー subhā devā 「subha 浄、清浄の、美しい、幸福の」 欲への意欲を生じる浄相もこの語。三毒の貪を断つための不浄を修習せよという浄もこの語です。
22 少浄天 パリッタスバー parittasubhā devā 少光天と同じ語義です。
23 無量浄天 アッパマーナスバー appamāṇasubhā devā 無量光天と同じ語義です。
24 遍浄天 スバキンナー subhakiṇnā devā 「subhakiṇṇa 遍浄[第三禅天の最上位]」「kiṇṇa 酵母」ですが、全体を発酵させるというところから転じて「遍く清浄な」という語で漢訳したのだと思います。文脈から見ても遍浄で問題ないと思います。極光天に対応させれば「極浄」でもいいかも知れませんが。浄天は、第三禅を愛好する者、喜心解脱を愛好する者が転生します。凡夫と聖弟子の差異は上と同じです。浄天の寿命は4劫です。
25 広果天 ヴェーハッパラー vehapphalā devā 「veha」は「vepulla 広大、方広、成満」から、「phala 果、果実、結果」で「広大な果報を持つ神々」です。詳しい解説は原始仏典ではなされていません。広果天の寿命は500劫です。この経典では「無想有情」(想がないけれど色がある神々)が書いてありません。無想天は適切な転生先の候補ではないようです。
26 無煩天 アヴィハー avihā devā 「aviha 無煩[天]」としか辞書には書いていないのですが、僕は「avihimsā 不害、無害、不殺生」から「害することのない神々」と訳したいです。無煩天をはじめとする浄居天について原始仏典に詳しい解説はまったくありません。名前から推測するしかない状況です。
27 無熱天 アタッパー atappā devā 「atappa 無熱の」。「tappati 焼ける、苦しむ、悩む」に「a」がついて否定形です。「苦しみがない神々」「悩まない神々」です。
28 善見天 スダッサー sudassā devā 「su よき、善き、良き、妙なる、易き、極めて」「dassati 見る、認める、理解する」「dassana 見、見ること」
29 善現天 スダッシン sudassin devā 善見天とほとんど同じ語ですが、僕は「スダッサ」をまだ動的に見ている段階ととらえ、「スダッシン」をすでに見られた、理解されたととらえ善現天を「善解天」であると考えています。詳細は原始仏典上では不明です。
30 アカニッタ天 アカニッター akaniṭṭhā devā 「akaniṭṭha アカニッタ、色究竟、有頂」とありますが色究竟は教義からの解釈ですし、有頂は非想非非想処に到達した神々とも取れますので適切な訳ではありません。「a」は否定形ですので問題はカニッタです。辞書には「kaniṭṭha 形容詞 [kanīnaの最上級]若い、最も若い、劣れる」とあります。これの否定形ですので「若くない、最も若くない、劣っていない」、そこから僕は「最も古き神々」と解釈します。「最も優れた神々」と解釈すると空無辺処以上に到達した神々の地位がおかしくなるからです。詳細は述べられていない神々です。あるサッカは「自分はアカニッタに行き、最終的には涅槃する」と断言しています。浄居天の寿命は不明です。広果天は聖弟子も凡夫も行くところで寿命は500劫と書いてありますが、浄居天は聖弟子しか行けないところで四禅や四無量心中に五取蘊の生滅を観じる者が行くと書いてあるだけで、寿命に関する記述がありません。
以上、色界の神々。
31 空無辺処天 アーカーサーナンチャーヤタヌーパガー ākāsānañcāyatanūpagā devā 「ākāsa虚空、空」「anañcā」は「ananta 無辺の、無限の、無量の」だと思います。「āyatana 処、入、入処」「upaga 到る、達する、経験する、属する」。無辺の空の処に到達した神々。今までの「長寿、美貌、多楽」の記述がここから「長寿、久住、多楽」の記述に変更されます。無色界ですから「色」がありません。自他双方によらずに自らの身を獲得するものとして非想非非想処天がサーリプッタとの問答によって説かれています。ここから「本当に非想非非想処天は非想非非想処に八万劫とどまり続けていること」が明らかです。寿命は1万劫です。
32 識無辺処天 ヴィンニャーナ viññāṇañcāyatanūpagā devā 「viññāṇa 識、分ち知ること、識神、意識」。無辺の識の処に到達した神々。寿命は2万劫です。
33 無所有処天 アーキンチャンナ ākiñcaññāyatanūpagā devā 「ākiñcañña 無所有」「kiñcana 何か、何ものか、障碍、障」。無所有の処に到達した神々。寿命は4万劫です。
34 非想非非想処天 ネーヴァサンニャー・ナーサンニャー nevasaññānāsaññāyatanūpagā devā 「neva・・・na・・・ ・・・にも非ず・・・にも非ず」「sañña 想、想念、概念、表象」「neva・sañña・na・asañña」。(有)想でもなく無想でもない処に到達した神々。寿命は8万劫です。
以上、無色到達の神々。
35 阿羅漢 So āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati.
「彼は諸漏を尽くして無漏の心解脱・慧解脱を現実に自ら勝智し実証し具足して住する」。阿羅漢の定型文です。
So彼は āsavānaṃ諸漏を khayā尽くして anāsavaṃ無漏の cetovimuttiṃ心解脱 paññāvimuttiṃ慧解脱 diṭṭheva現 dhamme法 sayaṃ自ら abhiññā勝智し sacchikatvā実証し upasampajja具足して viharati住する.
転生の超越が不死なので、最高の行き先、善逝が行った善趣です。
「また比丘たちよ、ここに比丘は信を具足しており、戒を具足しており、聞を具足しており、捨を具足しており、慧を具足している。彼にはこうある。「ああ、実に漏を尽くして無漏の心解脱・慧解脱を現実に自ら勝智し実証し具足して住そう」と。彼は漏を尽くして無漏の心解脱・慧解脱を自ら勝智し実証し具足して住する。比丘たちよ、この比丘はどこにも再生しない。」
と書いてありますので、阿羅漢は転生ではないですが話の流れからして、五財を具足して「解脱を手に入れたい」と願えばそうなるという教えだと思います。「そう願えばそうなる」。それが行生経の教えです。
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏教 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏教のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37864人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人