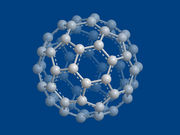こんばんわ。
勝手にトピックを立ててしまい、申し訳ありません。
どなたかプラズマ発光分析に詳しい方、ご意見お願いします。
ICP−AESを用いて、銅の検量線作成をしました。
ブランク(超純水)〜1ppmまでの標準溶液(0.1M硝酸酸性)を、0.2ppm間隔で測定し、検量線を作成したところ、R^2=0.998の検量線ができました。(6点検量)
ところが、範囲を20ppmまで拡大し再度測定したところ、R^2=0.865という、全く直線性のないものになってしまいました。
このとき、1,2,3,4,5,10,20ppmの標準溶液を調整し、測りました。5ppmまでは直線性があったものの、10、20ppmで発光強度が跳ね上がってしまいました。
グラフで言うと、二次関数のようなデータになってしまいました。
高濃度のものを分析すると、装置の検出限界を超えて、真の値よりも低くなってしまうということは知っているのですが、高くなってしまいました。ちなみに、全ての標準溶液は元となる100ppmの標準溶液を希釈して作っているので、取り違えなどはありません。
自分でも原因を調べているのですが、未だに解明できません。
雑文ながら、どなたかお力添えお願いいたします。
勝手にトピックを立ててしまい、申し訳ありません。
どなたかプラズマ発光分析に詳しい方、ご意見お願いします。
ICP−AESを用いて、銅の検量線作成をしました。
ブランク(超純水)〜1ppmまでの標準溶液(0.1M硝酸酸性)を、0.2ppm間隔で測定し、検量線を作成したところ、R^2=0.998の検量線ができました。(6点検量)
ところが、範囲を20ppmまで拡大し再度測定したところ、R^2=0.865という、全く直線性のないものになってしまいました。
このとき、1,2,3,4,5,10,20ppmの標準溶液を調整し、測りました。5ppmまでは直線性があったものの、10、20ppmで発光強度が跳ね上がってしまいました。
グラフで言うと、二次関数のようなデータになってしまいました。
高濃度のものを分析すると、装置の検出限界を超えて、真の値よりも低くなってしまうということは知っているのですが、高くなってしまいました。ちなみに、全ての標準溶液は元となる100ppmの標準溶液を希釈して作っているので、取り違えなどはありません。
自分でも原因を調べているのですが、未だに解明できません。
雑文ながら、どなたかお力添えお願いいたします。
|
|
|
|
|
|
|
|
化学の道 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-