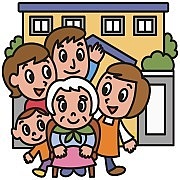|
|
|
|
コメント(9)
倉敷市文化振興課からイベント情報が届きました
◇◆◇ 第18回倉敷邦楽日舞名流選 ◇◆◇
日時/12月12日(日) 10時30分〜
場所/倉敷市芸文館
入場料/3500円
和の音楽と、和の舞。日本の伝統美の舞台です。
◇◆◇ 薄田泣菫没後65周年記念展 ◇◆◇
日時/12月14日(火)〜19日(日)
場所/倉敷市立美術館
入場料/無料
連島出身の詩人・薄田泣菫の直筆の原稿・書簡などを展示します。
◇◆◇ 吉備真備杯くらしき囲碁大会 ◇◆◇
日時/1月9日(日) 9時30分〜
場所/マービーふれあいセンター
参加料/無料
申込締切/12月15日(水)必着
プロ棋士による入門教室、一般の部、小中学生以下の部で争う吉備真備杯戦を用意しています。
◇◆◇ 第44回新春かるた会 ◇◆◇
日時/1月9日(日) 9時40分〜16時
場所/新渓園(倉敷中央1−1−20)
参加料/一般1000円・高校生以下500円・ちらしどりのみ参加300円
申込締切/12月20日(月)必着
クラスわけで行う「競技かるた」、皆でわきあいあいと行う「ちらしどり」。新春といえば、かるた。参加してみませんか。
◇◆◇ 第18回倉敷邦楽日舞名流選 ◇◆◇
日時/12月12日(日) 10時30分〜
場所/倉敷市芸文館
入場料/3500円
和の音楽と、和の舞。日本の伝統美の舞台です。
◇◆◇ 薄田泣菫没後65周年記念展 ◇◆◇
日時/12月14日(火)〜19日(日)
場所/倉敷市立美術館
入場料/無料
連島出身の詩人・薄田泣菫の直筆の原稿・書簡などを展示します。
◇◆◇ 吉備真備杯くらしき囲碁大会 ◇◆◇
日時/1月9日(日) 9時30分〜
場所/マービーふれあいセンター
参加料/無料
申込締切/12月15日(水)必着
プロ棋士による入門教室、一般の部、小中学生以下の部で争う吉備真備杯戦を用意しています。
◇◆◇ 第44回新春かるた会 ◇◆◇
日時/1月9日(日) 9時40分〜16時
場所/新渓園(倉敷中央1−1−20)
参加料/一般1000円・高校生以下500円・ちらしどりのみ参加300円
申込締切/12月20日(月)必着
クラスわけで行う「競技かるた」、皆でわきあいあいと行う「ちらしどり」。新春といえば、かるた。参加してみませんか。
県立玉野高校の3年生有志が、15日、一人暮らしのお年寄りに届ける正月用のお飾りを、手作りしました。
この取り組みは、日ごろお世話になっている地域の人たちへ感謝の気持ちを伝えようと、10年ほど前から行っています。学校の周辺には、一人暮らしのお年寄りが多いことから、お年寄りのために、正月用の注連飾りを届けています。取り組みに参加したのは、3年生の有志およそ70人。先生の手ほどきで、およそ1時間、気持ちを込めて、注連飾りを作りました。手作りした注連飾りは、70個。終業式の行われる今月24日に、学校周辺に住む一人暮らしのお年寄りの自宅に届けることにしています。
http://tv.kct.jp/news/detail.php?to=list&id=OKAHKDHROOSK
この取り組みは、日ごろお世話になっている地域の人たちへ感謝の気持ちを伝えようと、10年ほど前から行っています。学校の周辺には、一人暮らしのお年寄りが多いことから、お年寄りのために、正月用の注連飾りを届けています。取り組みに参加したのは、3年生の有志およそ70人。先生の手ほどきで、およそ1時間、気持ちを込めて、注連飾りを作りました。手作りした注連飾りは、70個。終業式の行われる今月24日に、学校周辺に住む一人暮らしのお年寄りの自宅に届けることにしています。
http://tv.kct.jp/news/detail.php?to=list&id=OKAHKDHROOSK
「質の高い医療普及へ努力」
岡山協立病院、創立50周年で講演会
谷口院長が今後の方針について述べた創立50周年記念の講演会
岡山協立病院(岡山市中区赤坂本町)創立50周年を記念した講演会が19日、岡山市北区表町の岡山シンフォニーホールで開かれた。
医療関係者、市民ら1200人が参加。谷口英人院長が講演し「今後も救急やリハビリテーションなど質の高い医療を、誰もが安心して受けられるよう努めたい」と述べた。
「いのちを大切にする」と題し講演した旭山動物園(北海道旭川市)の小菅正夫・前園長は、カバの夫婦愛やオオカミの子育てなどを紹介。「動物は命を次の世代につなぐために生きている。命は自分だけのものではないことを認識し、大切にしなければならない」と話した。
25絃(げん)箏ユニット・心花(ここはな)のコンサートなどもあった。
同病院は1960(昭和35)年、岡山医療生活協同組合が開設。現在は内科、外科など21科318床の総合病院として市民の健康づくりに寄与している。
http://iryo.sanyo.oni.co.jp/news_s/d/c2010122011100793?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=sanyo_news
岡山協立病院、創立50周年で講演会
谷口院長が今後の方針について述べた創立50周年記念の講演会
岡山協立病院(岡山市中区赤坂本町)創立50周年を記念した講演会が19日、岡山市北区表町の岡山シンフォニーホールで開かれた。
医療関係者、市民ら1200人が参加。谷口英人院長が講演し「今後も救急やリハビリテーションなど質の高い医療を、誰もが安心して受けられるよう努めたい」と述べた。
「いのちを大切にする」と題し講演した旭山動物園(北海道旭川市)の小菅正夫・前園長は、カバの夫婦愛やオオカミの子育てなどを紹介。「動物は命を次の世代につなぐために生きている。命は自分だけのものではないことを認識し、大切にしなければならない」と話した。
25絃(げん)箏ユニット・心花(ここはな)のコンサートなどもあった。
同病院は1960(昭和35)年、岡山医療生活協同組合が開設。現在は内科、外科など21科318床の総合病院として市民の健康づくりに寄与している。
http://iryo.sanyo.oni.co.jp/news_s/d/c2010122011100793?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=sanyo_news
下記の記事中でクーリングオフの話あたりは、今後の動向を見ておかないと思わぬ落とし穴になりそうな気がしますので、読んでいただきたいと思います。
有老と高専賃セミナーレポート
株式会社インターネットインフィニティーは12月14日、ケアマネジャーをはじめ、介護従事者向けセミナー「有料老人ホームと高専賃の基礎知識」を船橋市で開催した。講師は同社日本有料老人ホーム紹介センター チーフアドバイザーの武谷美奈子氏。
介護力不足などで在宅での生活が限界に来ていて、でも特養には入れない。行き場のない高齢者から施設の要望が高まる中で、増加の一途をたどる“有料老人ホーム”と最近よく耳にする“高専賃”。武谷氏は2つの違いを挙げながら、介護従事者として知っておきたい基礎知識として、主に「有料老人ホーム・高専賃の種類」「権利形態」「入居のタイミング」「チェックポイント」のテーマにしぼって解説した。
有料老人ホームには健常者向けと要介護者向けの2タイプがある。自立した生活が送れるよう食事、生活支援、入浴、排泄、健康管理を行っているので、自己の身体状況に合わせ、必要に応じて個々のホームを選ぶことが重要だ。
特定施設の指定を受けていれば、施設内もしくは外部のスタッフが常時介護にあたることができるので安心な面もある。しかし、入居金、月額利用料など予算はいくらかかるのか、費用負担の面で平均余命などの将来を考えながらホームを考える必要がある。
一方、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は高齢者に限定して賃貸している住宅である。費用については有老より少ない負担(敷金、礼金など)で入居可能であるため、楽に住み替えられる反面、自立した生活が送れることが基本であるため、要介護度が高くなり、日々の介護に大きな負担が出てくると、住み替えを考えなければならないといった面もある。しかし、最近は「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、食事や介護等のサービスを提供する高専賃もある。
入居を考えている高齢者にとって気になるのは、その費用であるが、武谷氏は「入居金、月額費用、その他月々にかかる費用順では、在宅介護、高専賃、介護者向けホーム、健常者向けホームの順に金額が大きくなる」と述べた。また、契約時の注意点の一つとして、有老、高専賃にもクーリングオフ制度があるものの、まだ法律化されていないため、契約書にきちんとうたわれているのか確認しないと、クーリングオフ期間中に退去したいと思っても、入居金が戻ってこないこともあるので注意する必要があると指摘した。
武谷氏によると、有料老人ホームはこの10年、高専賃はここ3年ほどで急激に増え、種類も様々である。本やTVの情報だけではなかなか理解しにくく、実際に見学、体験入居を行ってから入居することが大事なことではないか。介護従事者は、こうしたセミナーを機により多くの情報を収集し、終の住みかに迷う高齢者支援の一助にしてほしい」と語った。
セミナー終了後、参加者からは「資料も説明もわかりやすく、勉強になった。しかし法律などは難しい」「今まで自分でも勉強していたが頭の中で整理できず困っていた。今回のセミナーで整理できた気がする」「有料老人ホームや高専賃は生活の中身(どんな生活を送られているか)がわからなくて心配」などの意見が寄せられた。同社はこれらの意見を参考に、今後もさまざまな機会にセミナーの機会を設け、介護従事者により多くの情報を提供していくという。
http://wakarukaigo.jp/archives/1176 (会員登録が必要かもしれません)
有老と高専賃セミナーレポート
株式会社インターネットインフィニティーは12月14日、ケアマネジャーをはじめ、介護従事者向けセミナー「有料老人ホームと高専賃の基礎知識」を船橋市で開催した。講師は同社日本有料老人ホーム紹介センター チーフアドバイザーの武谷美奈子氏。
介護力不足などで在宅での生活が限界に来ていて、でも特養には入れない。行き場のない高齢者から施設の要望が高まる中で、増加の一途をたどる“有料老人ホーム”と最近よく耳にする“高専賃”。武谷氏は2つの違いを挙げながら、介護従事者として知っておきたい基礎知識として、主に「有料老人ホーム・高専賃の種類」「権利形態」「入居のタイミング」「チェックポイント」のテーマにしぼって解説した。
有料老人ホームには健常者向けと要介護者向けの2タイプがある。自立した生活が送れるよう食事、生活支援、入浴、排泄、健康管理を行っているので、自己の身体状況に合わせ、必要に応じて個々のホームを選ぶことが重要だ。
特定施設の指定を受けていれば、施設内もしくは外部のスタッフが常時介護にあたることができるので安心な面もある。しかし、入居金、月額利用料など予算はいくらかかるのか、費用負担の面で平均余命などの将来を考えながらホームを考える必要がある。
一方、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は高齢者に限定して賃貸している住宅である。費用については有老より少ない負担(敷金、礼金など)で入居可能であるため、楽に住み替えられる反面、自立した生活が送れることが基本であるため、要介護度が高くなり、日々の介護に大きな負担が出てくると、住み替えを考えなければならないといった面もある。しかし、最近は「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、食事や介護等のサービスを提供する高専賃もある。
入居を考えている高齢者にとって気になるのは、その費用であるが、武谷氏は「入居金、月額費用、その他月々にかかる費用順では、在宅介護、高専賃、介護者向けホーム、健常者向けホームの順に金額が大きくなる」と述べた。また、契約時の注意点の一つとして、有老、高専賃にもクーリングオフ制度があるものの、まだ法律化されていないため、契約書にきちんとうたわれているのか確認しないと、クーリングオフ期間中に退去したいと思っても、入居金が戻ってこないこともあるので注意する必要があると指摘した。
武谷氏によると、有料老人ホームはこの10年、高専賃はここ3年ほどで急激に増え、種類も様々である。本やTVの情報だけではなかなか理解しにくく、実際に見学、体験入居を行ってから入居することが大事なことではないか。介護従事者は、こうしたセミナーを機により多くの情報を収集し、終の住みかに迷う高齢者支援の一助にしてほしい」と語った。
セミナー終了後、参加者からは「資料も説明もわかりやすく、勉強になった。しかし法律などは難しい」「今まで自分でも勉強していたが頭の中で整理できず困っていた。今回のセミナーで整理できた気がする」「有料老人ホームや高専賃は生活の中身(どんな生活を送られているか)がわからなくて心配」などの意見が寄せられた。同社はこれらの意見を参考に、今後もさまざまな機会にセミナーの機会を設け、介護従事者により多くの情報を提供していくという。
http://wakarukaigo.jp/archives/1176 (会員登録が必要かもしれません)
介護に欠かせないツールとして紙おむつがあると思います。子供のオムツと同様に使いすぎは依存につながってしまい良くないだろう、とは思いながらもついつい実際は使ってしまうと思います。
そんな紙おむつについて毎日新聞が『福祉ナビ:普及が進む大人用紙おむつ。使用時の注意点は。』というタイトルで記事を掲載しています。
http://mainichi.jp/life/health/fukushi/news/20101229ddm013100135000c.html
介護職にある人も開発に携わっている人も記事中に掲載されている、実際に自分で履いてみて、そこに排泄したらどういう感触があり、精神的にどういう状態になるかまではなかなか試そうとは思わないのではないでしょうか。そうした意味でこの記事の中に出てくる金沢福祉用具情報プラザの安田秀一館長の試みには敬意を越えて感動すら覚えました。
一方、オムツを開発しているメーカーはどこまで踏み込んで開発しているのか知りたいと思い検索エンジンで検索してみましたが、そこまで突っ込んでの話は掲載されていませんでした。擬似排泄物くらいは使って開発しているのでしょうか?
最近、身重の方感覚を知るために胎児と同じ重さの錘を腹部に装着して生活したり、高齢者の感覚を知るために専用めがねで視界をさえぎったり体を動きにくくして生活する体験が普及しつつあります。おむつの間接的ユーザである介護家族、介護職の方も擬似排泄物でもかまわないので一度体験するとオムツに対する見方が変わるかもしれませんね。
そんな紙おむつについて毎日新聞が『福祉ナビ:普及が進む大人用紙おむつ。使用時の注意点は。』というタイトルで記事を掲載しています。
http://mainichi.jp/life/health/fukushi/news/20101229ddm013100135000c.html
介護職にある人も開発に携わっている人も記事中に掲載されている、実際に自分で履いてみて、そこに排泄したらどういう感触があり、精神的にどういう状態になるかまではなかなか試そうとは思わないのではないでしょうか。そうした意味でこの記事の中に出てくる金沢福祉用具情報プラザの安田秀一館長の試みには敬意を越えて感動すら覚えました。
一方、オムツを開発しているメーカーはどこまで踏み込んで開発しているのか知りたいと思い検索エンジンで検索してみましたが、そこまで突っ込んでの話は掲載されていませんでした。擬似排泄物くらいは使って開発しているのでしょうか?
最近、身重の方感覚を知るために胎児と同じ重さの錘を腹部に装着して生活したり、高齢者の感覚を知るために専用めがねで視界をさえぎったり体を動きにくくして生活する体験が普及しつつあります。おむつの間接的ユーザである介護家族、介護職の方も擬似排泄物でもかまわないので一度体験するとオムツに対する見方が変わるかもしれませんね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
岡山県介護とシニアの情報交換 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-