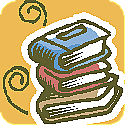〔目次〕(番号は、コメントの左側に表記されている書き込み順を表すものです)
1〜4 『悩む力』と『悩むチカラ』
姜尚中『悩む力』集英社新書
伊藤友宣の『「悩むチカラ」ほんとうのプラス思考』 PHP新書
5〜8 『私が出あった世にも不思議な出来事』
鳩山 幸・池田明子(インタビュー) 学研
9〜10 シャーリー・マクレーンの著書
『アウト・オン・ア・リム』『オール・イン・ザ・プレイング』
『カミーノ』 山川紘矢・山川亜希子/訳 角川書店
『風を追いかけて』山川紘矢・山川亜希子/訳 地湧社
11 北山耕平の著書・訳書
12〜15 『江原啓之 神紀行』 江原啓之・著 マガジンハウス
16 『原因と結果の法則』 ジェームズ・アレン/著 坂本貢一/訳 サンマーク出版
『生き方』 稲盛和夫・著 サンマーク出版
17〜18 『神道 見えないものの力』 葉室頼昭・著 春秋社
19 『道元を語る』(かまくら春秋社)
20 『<神道>のこころ』 葉室頼昭・著 春秋社
21 『神道と日本人』 葉室頼昭・著 春秋社
22 『生命のメッセージ』 佐藤初女・著 主婦の友社
『五十歳からの成熟した生き方』 天外 伺朗・著 海竜社
23 『世界を救う13人のおばあちゃんの言葉』 キャロル・シェーファー・著
ゴマブックス
24 『美しいお経』 瀬戸内寂聴・著 嶋中書店(初版)、中央公論新社(改訂版)
25 『成熟し、人はますます若くなる』 佐藤友美子・編著 NTT出版
|
|
|
|
コメント(26)
もうひとつの『悩むチカラ』ほんとうのプラス思考
楽しいミクシーの場に、このような題名の本をどうかと迷いましたが、タイムリーな話題なので。
姜尚中さんの「悩む力」が反響を呼んでいます。新聞で紹介されたばかりだというのに、図書館で検索したところ、すでに大変多くの予約が入っていました。同じ題名で、伊藤友宣・著 PHP新書の『「悩むチカラ」 ほんとうのプラス思考』(2005年)というのがあったので、こちらも読んでみたくて借りてきました。悩める人間のひとりとして求め、読んだ本なので、えらそうな紹介は出来ないのですが。
「悩む力」がきっかけで、もうひとつの「悩むチカラ」にも出会うことができ、大変特をした気持ちです。伊藤友宣さんは、現在、神戸心療親子研究室を主宰。ご自身は、『自由な発想を大事にしたいがため、どこにも属さず、自分一人のカウンセリング・ルームを自営してきたことで、世間に吹いている風の匂いや色あいの、その時々の微妙な変化が、いちいち痛く響く』と述べられています。
“まえがき”より抜粋させていただくと、
《この二、三十年の間、とても気になることは、悩むことをしなくなった若い世代のこと。社会のあらゆる面でマニュアル化が進み、効率第一で、立ち止まって、これはどうも腑に落ちない、気になるなどと悩んでいたら、置いてきぼりを喰ったりはずされてしまうだけである。なんでも出来合いのものですましているうちに、ついどんなことでも、もともとの成り立ちなど斟酌しておれなくて、手っ取り早く事をすますことに慣れるようになる。ほぐしてばらしてもとの仕組みを確認するなどという丹念でくどくどしいが、それがおもしろいのだというこだわり方などは、すべて素通りしてしまうことに慣れてゆく。
悩むこともなくいきなり破綻にだけ襲われる。精神科、神経科に通う患者の数が年々増加の一方である。
悩むことを常習にしているからこそ却って、心と体も平衡を保っていられるといえるのかもしれない。
今の世の中、ともすれば「悩むチカラ」に欠ける傾向が目立ちすぎる。それがとても気になる。
こんな世の中だからこそ「悩むチカラ」で、悩みの先にあるプラスイメージをつかみ慣れていかねばならないと思う。
どうも惑わされすぎているのではないかと思うのは、報道されることだけが今日明日の問題のすべてであるかのように思いこむ習慣が、いつのまにか出来ていることだ。報道の異常さや不安定さに、自分の日常の情緒や思考が引き寄せられる傾向が現在人には強すぎる。
つまり、うっかりすると、不確かな揺れ動きに身をまかせて、心がちゃんと大地に根づいていないという、心の不安定さを、それが常態と思い込みがちではないか。
「悩むチカラ」とは自分個人の根づきのよさを確認する力でもある。
「悩むチカラ」こそが、しなやかで、したたかな根づきのよい生き方の原動力なのである。》
長くなってしまいますので、今日はここまで。こりないでおつきあい願えるなら、また次回に
楽しいミクシーの場に、このような題名の本をどうかと迷いましたが、タイムリーな話題なので。
姜尚中さんの「悩む力」が反響を呼んでいます。新聞で紹介されたばかりだというのに、図書館で検索したところ、すでに大変多くの予約が入っていました。同じ題名で、伊藤友宣・著 PHP新書の『「悩むチカラ」 ほんとうのプラス思考』(2005年)というのがあったので、こちらも読んでみたくて借りてきました。悩める人間のひとりとして求め、読んだ本なので、えらそうな紹介は出来ないのですが。
「悩む力」がきっかけで、もうひとつの「悩むチカラ」にも出会うことができ、大変特をした気持ちです。伊藤友宣さんは、現在、神戸心療親子研究室を主宰。ご自身は、『自由な発想を大事にしたいがため、どこにも属さず、自分一人のカウンセリング・ルームを自営してきたことで、世間に吹いている風の匂いや色あいの、その時々の微妙な変化が、いちいち痛く響く』と述べられています。
“まえがき”より抜粋させていただくと、
《この二、三十年の間、とても気になることは、悩むことをしなくなった若い世代のこと。社会のあらゆる面でマニュアル化が進み、効率第一で、立ち止まって、これはどうも腑に落ちない、気になるなどと悩んでいたら、置いてきぼりを喰ったりはずされてしまうだけである。なんでも出来合いのものですましているうちに、ついどんなことでも、もともとの成り立ちなど斟酌しておれなくて、手っ取り早く事をすますことに慣れるようになる。ほぐしてばらしてもとの仕組みを確認するなどという丹念でくどくどしいが、それがおもしろいのだというこだわり方などは、すべて素通りしてしまうことに慣れてゆく。
悩むこともなくいきなり破綻にだけ襲われる。精神科、神経科に通う患者の数が年々増加の一方である。
悩むことを常習にしているからこそ却って、心と体も平衡を保っていられるといえるのかもしれない。
今の世の中、ともすれば「悩むチカラ」に欠ける傾向が目立ちすぎる。それがとても気になる。
こんな世の中だからこそ「悩むチカラ」で、悩みの先にあるプラスイメージをつかみ慣れていかねばならないと思う。
どうも惑わされすぎているのではないかと思うのは、報道されることだけが今日明日の問題のすべてであるかのように思いこむ習慣が、いつのまにか出来ていることだ。報道の異常さや不安定さに、自分の日常の情緒や思考が引き寄せられる傾向が現在人には強すぎる。
つまり、うっかりすると、不確かな揺れ動きに身をまかせて、心がちゃんと大地に根づいていないという、心の不安定さを、それが常態と思い込みがちではないか。
「悩むチカラ」とは自分個人の根づきのよさを確認する力でもある。
「悩むチカラ」こそが、しなやかで、したたかな根づきのよい生き方の原動力なのである。》
長くなってしまいますので、今日はここまで。こりないでおつきあい願えるなら、また次回に
テレビのニュースによると、多くの自殺者の数もさることさがら、その原因の第一位は、鬱病などの心の病だということに、今さらながらに愕然とさせられます。
「悩むチカラ」は、街角から時代を見続けたカウンセラーが、世を憂う思いを胸に送られたメッセージです。
第2章では、第二次世界大戦後の、命じられてできた民主主義、混乱を極めた戦後の学校改革、経済的発展のみの未成熟社会などについて書かれ、論理ばかりを優先する感性の欠如についての項では、こう述べられています。
“子に問われて絶句する時代である。「なぜ人が人を殺してはいけないの」 そして、現実に、「人を殺してみたかったから殺した」と動機を語る未成年の殺人犯が現れる時代である。論理をいちいち求める感性の欠如は、深刻である。自律感覚が育っておれば、人を殺すことは自己を殺すことだと直覚できる。生命を否定するものは生命ではない”
第3章では、『心の捉え方』について。“フロイトによると、「心は三つある」 aは我(エゴイズム)で、自分の欲を晴らし、自己の可能性を追求してやまない心である。 bは超自我(スーパーエゴ)で、人を気づかい、人に認められてこそ充足できる心である。
aとbは互いに反発しあいながら常に対立と葛藤をくりかえしてこそ、幅のある人格cが育つ。つまり、「自我が確立する」というのはこのことを指している。
心aと心bがそれぞれそっぽを向き、自我が確立し得ないと、人間として破綻せざるを得ないのが、昔人間の状態だったといっていい。
つまり、心は「悩むチカラ」の装置といえる。”
第4章の<二面相剋が自我を確立させる>では、この箇所が一番心に残りました。
《第3章でも述べたように、心には、我(エゴイズム)と超自我(スーパーエゴ)と自我(エゴ)と三つあるのだよと、子どものうちから教えられていたら、心の二面性を気にしてどうにも立ちゆかないなどという思いつめなどしなくてもすむのにと、私は三十年間のカウンセリングの仕事のなかで、ずっとそればかりを考えてきた。
訳語がどれも似ていてまぎらわしいので、心理分析なんて専門家のみの操れる知識などと一般には敬遠されてしまい、三つの心の理解は戦後半世紀以上経っても、つまりフロイト以後半世紀以上経ってもほんとうに進んでいない。
早い話が、学校の教員でも我と超自我と自我の三つの心の説明がしっかりできる人は、驚くほど少ないのがげんじょうである。
自我と我なんて、同じものだぐらいに混乱している中学校の校長なんかざらにいる。》
《どうでも勝たねばならない。負けられない。そういうときに「悩むツカラ」はいらない。勝つための頑張りだけがいる。
勝つのでもない、負けるのでもない、一緒になんとかやっていくしかない。そういうときにこそ「悩むチカラ」が必須なのである。
左脳は知識を使って論理を組み上げる働きを司る。それに対して、右脳は、感覚やイメージの世界を領分としている。
明治以来、学校教育は左脳教育一辺倒だったのだとつくづく思う。
教育の形骸化の原因の一つは、ここにありはしないか。
悩むべきときには、静かに明るく深く悩む。クヨクヨしたりげっそりして悩みに負けてしまわない。心の中のイメージを輝かせて。
そのためには、いわば悩み通すことで悩みを脱するちから、つまり、悩みに打ち克つ自身に満ちた十分な「悩むチカラ」を、とにもかくにも普段からプラスイメージとして身につけるトレーニングを愉しく気軽に重ねていけばいいのである。
「悩むチカラ」なんて今の常用語にはない。なのに、これこそ平和の恒常のために、必須なものである。》
第5章<発育不全の世界中のがたつき>、第6章<本音も立前も必然である>、第7章<人類のホメオステーシス>と続きますが、長くなるので省略します。
最後にあとがきより
《なにからでもプラスを得ようとする、明るいプラスイメージのあるなし一つで、生き方が変わるのである。
互いにただ生きている、そのことが神秘な現実だ、神秘そのものの存在同士だという右脳全開の感性が働けば、それぞれ一人ひとりの内なる心で、フロイトのイメージした我と超自我という二つの心の対立葛藤がもたらす自我が、またもや練られてゆかないわけはない。
滅多なことでは「悩むチカラ」は揺るがない。だって、おもしろいのだものという意欲。
身内が火照る。
そんな大人が世に満てればよい。
人間同士だからこそ、いつだって清新な輝きを互いに感じあわずにはいられないといった素朴な健康さを、誰だって内に秘めているもので、そう確信できることが「悩むチカラ」の源泉なのだと思う。》
《自分一個のなにもかもを、もっともっとよく知ることが、そのまま自己を取り巻くすべての人、人、人……つまり、世界をよく知ることにつながる。
人の人生とは、その喜びの道程である。》
著者の伊藤友宣さんは、この本を、神戸の街の片隅で、自営のカウンセリングを続けてきた、自分なりの「カウンセリング人生の芯」である、と述べられています。
情報ネットワークや市場経済圏の拡大にともなう猛烈な変化に対して、多くの人々がストレスを感じています。格差は広がり、自殺者も増加。そんな中でどう生きれば良いのだろうか。本書も悩むことを肯定し、こうした苦しみを百年前に直視した夏目漱石とマックス・ウェーバーをヒントに、最後まで「悩み」を手放すことなく、真の強さを掴み取る生き方を提唱する。(表紙カバー裏の紹介より)
この本の中で、一番心に残ったのは「まじめたれ」という項でした。
《他者との相互承認の中でしか自我は成立しないと私は言いましたが、では、他者とつながりたい、きちんと認めあいたいと思うとき、いったいどうしたらいいのでしょうか。私には「正解はこれだ」という力はありません。が、『心』の中で、漱石は一つ、とても大事なことをおしえてくれています。
それは「まじめ」ということです。「まじめ」といjのは、「中途半端」の対極にある言葉ではないでしょうか〜》
もう少し詳しくご紹介したいですが、長くなりますのでこの辺で…。
二つの「悩むちから」に出会えて、今回この欄の紹介のため、またざっと読みなおすことが出来て、嬉しく思いました。
科学の力では解明されないことが、まだまだ沢山あるのではないかということを言う人の数が、増えてきているようです。この種の本もいろいろ出ていて、何冊か読みました。こういった話は、興味のある人と、ちょっとという人とがあると思うので、紹介するかどうか少し迷ったのですが…。
題名から想像して、俗っぽいものがあるかな、まあ、中身を見て面白いようならと、図書館で予約を入れました。
 『私が出あった世にも不思議な出来事』 学研(2008年8月)1300円+税
『私が出あった世にも不思議な出来事』 学研(2008年8月)1300円+税
この本は、鳩山幸(みゆき)さん<ご主人は政治家の鳩山由紀夫氏>と、池田明子さん<ご主人は俳優の梅沢登美男氏>のお二人のインタビュー、コーディネイトによるものです。24人の著名人の体験を通して、考え方、行き方に触れることができて、いろいろ発見がありました。
その中に、「マクロビオティック」の世界的権威である久司道夫さんもいらっしゃり、今までの彼の本に書かれていなかったことも語られていて、興味深く読みました。
他に、作家の佐藤愛子さん、桐島洋子さん、玄侑宗久さん、渡辺昇一さん(英文学者・評論家)、高江州薫さん(獣医師・ヒーラー)、クリスチャン・ペイジさん(医師)、鈴木秀子さん(文学博士・聖心会シスター)、五日市剛さん(工学博士)、芸能関係では、作詞家、俳優、歌手、脚本家など、様々な分野で活躍されている方々、第23話、24話では聞き手のお二人のご主人も登場され、興味深いものがありました。
次回へと続きます。気が向けば開いてみてください。
題名から想像して、俗っぽいものがあるかな、まあ、中身を見て面白いようならと、図書館で予約を入れました。
この本は、鳩山幸(みゆき)さん<ご主人は政治家の鳩山由紀夫氏>と、池田明子さん<ご主人は俳優の梅沢登美男氏>のお二人のインタビュー、コーディネイトによるものです。24人の著名人の体験を通して、考え方、行き方に触れることができて、いろいろ発見がありました。
その中に、「マクロビオティック」の世界的権威である久司道夫さんもいらっしゃり、今までの彼の本に書かれていなかったことも語られていて、興味深く読みました。
他に、作家の佐藤愛子さん、桐島洋子さん、玄侑宗久さん、渡辺昇一さん(英文学者・評論家)、高江州薫さん(獣医師・ヒーラー)、クリスチャン・ペイジさん(医師)、鈴木秀子さん(文学博士・聖心会シスター)、五日市剛さん(工学博士)、芸能関係では、作詞家、俳優、歌手、脚本家など、様々な分野で活躍されている方々、第23話、24話では聞き手のお二人のご主人も登場され、興味深いものがありました。
次回へと続きます。気が向けば開いてみてください。
24人の方のお話は、みなそれぞれに興味深いものでしたが、全部載せると長くなりますので、何人かのお話から、印象に残ったところなどを中心にご紹介していきたいとおもいます。
子どものころから神社に惹かれ、八歳のころから毎日のように神社に通い、社殿で正座して、瞑想みたいなことを自然にやった。十六歳のときに不思議なことが起こった。朝早く行って瞑想していると、突然、光が差し込んできて、全身を包んだ。ふとあたりを見ると、境内の樹木や石段も光り輝いていた。唖然として家に帰ってきたときに、「すべての物は光だ。すべての物の起源は同じで、永久の命を持っている」と体で感じた。
そして、これは他の本にも書かれていて有名な話ですが、世界を平和にするためにはどうすればよいか、そのためには世界連邦をつくろうと、アメリカのコロンビア大学で政治学を学ばれた。しかし、人間が抱く憎しみや恨みは、政治だけでは解決できないと感じ、人間性が向上しなければ本当の平和はこない。そのために何をすればよいのか、それを自分で見つけるしかないと思い、政治学を投げうち、ニューヨークの五番街やタイムズ・スクエアで、朝から晩まで人間をながめた。二ヵ月半の間、何千何万という人を眺め、あるときパッと思いついたのが、環境が人間を支配するということだった。
自然も人工的な物も含めた環境。中でも決定的な要因をなすのは食べ物である。その思いから、人間性を向上させる食べ物の研究を始めた。
困難な病気を治された例も興味深かったです。
三十代半ばの数理学の天才は、一方、社会常識がなく、働くことはおろか、挨拶もできないという状態。「卵とチーズとレモンを食べないように」と言ったら、母親が「幼稚園のときからずっと、毎朝ゆで卵とチーズにレモンをかけて食べている」と驚いて答えたということです。卵、レモン、チーズは左脳を発達させるが、左脳ばかり発達しすぎたので、左右のバランスが崩れたということだそうです。
他にも不思議な体験の話がいろいろ。UFOのお話もありましたが、長くなりますのでこのへんで。
毎日だと、読んでくださる方もしんどいかもしれないし、一日おきくらいにと思ったのですが、図書館の返却が迫っていて。二週間の貸し出し期間の間に読んで、紹介もとなると、少々きついときがあります。私は急いで書き込みますが、読まれるのはいつでも気が向いたときにゆっくり読んでください。
さて、次はどの方を紹介しようかなと考えると、紹介したい方ばかり。それも、何行かだけでは紹介しきれない内容。もっと知りたい方は、図書館で借りるか、購入してくださるかをお薦めします。
私が玄侑さんの作品で初めて読んだのは、「アミターバ」で、次に「中陰の花」でした。お坊さんでなければ書けない作品の世界に、新鮮な思いでした。「アミターバ」は阿弥陀様のことで、この物語に出てくるお坊さんのお姑さんが、癌で死期が近づき、肉体から自由になって、いろいろな時空間や、あちらの世界らしきところをくり返し行き来する場面もあります。
玄侑さんは通夜やお葬式の席などで、不思議な出来事を体験されたこともいろいろおありです。檀家の方が体験された不思議な出来事も、事実だとはっきり言うことはできないが、実感していることを否定はできない、と語られています。
チャクラと癒しに関する著書もおありだということ。チャクラとは、エネルギーの流れをつくる中枢のことだそうです。以前本で図解入りの説明を見たことがありますが、主要なものは七つあり、大小合計すると二十四のチャクラがあるということです。ここを通して宇宙のエネルギーが出たりはいったりするということが書いてあったように思います。
26歳のとき、運勢のどん底にあったという五日市さんは、単身イスラエルへ旅行を決意。現地で不思議なおばあさんに出会い、「ありがとう」「感謝します」という「魔法の言葉」を教えてもらいました。
その時の体験を、奇跡的な出来事とともに紹介した講演録『ツキを呼ぶ魔法の言葉』が大ベストセラーになりました。
新聞では、“お金がはいる”というようなことが強調された見出しで紹介されていたので、読む気になれずに来ていましたが、「私が出あった…」の中のお話を読み、浮ついたものではなかったことがわかり、その講演録を読みたくなって、図書館で予約しました。
イスラエルのおばあさんに言わせると、「言葉は口から出た瞬間に魂を持つ。勝手に手足がはえて歩き出すから、きれいな言葉をつかいなさい」ということです。
終りに、五日市さんが教えてくださった“マイナスの思いを消す方法”をご紹介します。心の中のことって、消しゴムで消せると思うんですって。
寝る前に、その日にあった良い事を5つ思い出してから休むというのと、同じですよね。
「なんだかうれしい」とも、プラス思考という点では共通しています。
シャーリー・マクレーンさんの著書 (2009年1月13日)
 シャーリー・マクレーンさんは、アメリカの演技派女優として知られ。アカデミー主演女優賞も受賞されていますが、それ以上のことは知りませんでした。昨年紹介した「わたしが出会った世にも不思議な出来事」の中に、「アウト・オン・ア・リム」という本の名が出ていたことで、神秘的な体験を本に書かれているということを知り、借りて読んでみました。
シャーリー・マクレーンさんは、アメリカの演技派女優として知られ。アカデミー主演女優賞も受賞されていますが、それ以上のことは知りませんでした。昨年紹介した「わたしが出会った世にも不思議な出来事」の中に、「アウト・オン・ア・リム」という本の名が出ていたことで、神秘的な体験を本に書かれているということを知り、借りて読んでみました。
女優さんが書いた本から描くイメージとは大きく違った内容に驚くとともに、すごいなあと思いました。他にもう一冊読み、今三冊目を読んでいるところですが、これらの本の内容を簡単にご紹介するには、あまりにスケールが大きく、また、霊的な世界のことが書かれているので、この欄でご紹介することをずいぶん迷いました。感動の一端を書くことのみに留めたいと思いますが、もし興味があり、読んでみたい方は、やはり最初に書かれた「アウト・オン・ア・リム」から入られるのがいいと思います。
「アウト・オン・ア・リム」とは、“枝の先の果物を取るには、危険をおかして進まなければならない”という意味だそうです。巻末の著書紹介によると、“行動派で知られる人気女優の著者が、数々の神秘的な体験をきっかけとして本当の自分、神、宇宙について知りゆく過程を綴る。その勇気ある試みは、来たるべき新しい時代の幕あけを予感させる。”とあります。14カ国語に訳されたベストセラーであり、後にテレビで5時間に及ぶドラマとして、シャリー自身が本人の役で出演しました。放映に至るまでの過程(役者選び、苛酷なロケなど)を含む話は、「オール・イン・ザ・プレイング」の中に書かれています。
今は「カミーノ」―魂の旅路 を読んでいる途中です。「アウト・オン・ア・リム」から15年。シャーリーはスペインの“サンチャゴ巡礼路(サンチャゴ・デ・コンポステーラ・カミーノ)”と呼ばれて、何世紀にもわたり、多くの人がたどった有名な巡礼の道をたどり、自己探求の旅をはじめます。(カミーノは道という意味)
シヤーリーが本の中で書いていることの中に、“世の中を平和に導くのは、経済的、物質的な政策より、人間一人ひとりのの霊性を高めることが先だ”という箇所があります。これからの時代は、男性的な波動に偏らず、女性的な波動が必要とされているとも描かれています。東城先生の女性の底力のお手紙(カムカム会だよりに掲載)と共通しているように思います。
私の心は、シャリーのこれらの著書に出会って、大きく揺り動かされる思いでした。いろんな要素を含んだ本ですので、深刻にならず、女優さんとしてのシャーリーをもっと知りたいという思いだけでも、面白く読むことが可能ではと思います。
またまた今回もアメリカの本でした。不思議です。
女優さんが書いた本から描くイメージとは大きく違った内容に驚くとともに、すごいなあと思いました。他にもう一冊読み、今三冊目を読んでいるところですが、これらの本の内容を簡単にご紹介するには、あまりにスケールが大きく、また、霊的な世界のことが書かれているので、この欄でご紹介することをずいぶん迷いました。感動の一端を書くことのみに留めたいと思いますが、もし興味があり、読んでみたい方は、やはり最初に書かれた「アウト・オン・ア・リム」から入られるのがいいと思います。
「アウト・オン・ア・リム」とは、“枝の先の果物を取るには、危険をおかして進まなければならない”という意味だそうです。巻末の著書紹介によると、“行動派で知られる人気女優の著者が、数々の神秘的な体験をきっかけとして本当の自分、神、宇宙について知りゆく過程を綴る。その勇気ある試みは、来たるべき新しい時代の幕あけを予感させる。”とあります。14カ国語に訳されたベストセラーであり、後にテレビで5時間に及ぶドラマとして、シャリー自身が本人の役で出演しました。放映に至るまでの過程(役者選び、苛酷なロケなど)を含む話は、「オール・イン・ザ・プレイング」の中に書かれています。
今は「カミーノ」―魂の旅路 を読んでいる途中です。「アウト・オン・ア・リム」から15年。シャーリーはスペインの“サンチャゴ巡礼路(サンチャゴ・デ・コンポステーラ・カミーノ)”と呼ばれて、何世紀にもわたり、多くの人がたどった有名な巡礼の道をたどり、自己探求の旅をはじめます。(カミーノは道という意味)
シヤーリーが本の中で書いていることの中に、“世の中を平和に導くのは、経済的、物質的な政策より、人間一人ひとりのの霊性を高めることが先だ”という箇所があります。これからの時代は、男性的な波動に偏らず、女性的な波動が必要とされているとも描かれています。東城先生の女性の底力のお手紙(カムカム会だよりに掲載)と共通しているように思います。
私の心は、シャリーのこれらの著書に出会って、大きく揺り動かされる思いでした。いろんな要素を含んだ本ですので、深刻にならず、女優さんとしてのシャーリーをもっと知りたいという思いだけでも、面白く読むことが可能ではと思います。
またまた今回もアメリカの本でした。不思議です。
『カミーノ』の残りを読み終え、『風を追いかけて」』を昨日読み終えました。
それは自分の内面に向かっての問いかけ、発見の旅でした。日本の四国巡礼などと歩く距離も、泊まる環境も違い、苛酷な状況になんども遭遇します。巡礼が進む方向を示す黄色い矢印は、時として違う方向を示していたり、ときにはなかなか見つけられないこともあります。おまけにシャーリーは背中の荷物の他にもう一つ、有名人という重い荷物をしょっているのです。いたるところで報道人が待ちかまえ、シャワーを浴びていようが、カーテンを開けて無遠慮に写真を撮ろうとしたりします。お話の最後の方の“レムリア”“アトランティス”の項は圧巻。著者のメッセージが込められています。
苛酷なカミーノの旅を最後までやり通したシャーリーの精神力は、世界のあちこちを旅し、厳しい状況も乗り越えてきた経験によっても培われてきたのだと感じました。
『風を追いかけて』は1970年にアメリカで発表された当時、大きな反響があったそうですが、大ベストセラー「アウト・オン・ザ・リム」を発表してから、また改めて読まれ始めたということです。私もこの本は大変興味深く、面白く読むことができました。夫スティーブ・パーカー、娘のサチとともに、日本での生活への深いかかわりも書かれており、興味深いです。サチ・パーカーさんは「西の魔女が死んだ」で主人公のおばあさん役で出演され、話題になりましたね。
北山耕平さんの著書・訳書 (2009年1月29日)
 〔うれしい顔していましょう〕
〔うれしい顔していましょう〕
うれしさは
生きていく上での大きなパワーです。
いつもうれしい顔ができるように
自分の部屋とかバスルームに
なにかおかしな写真や絵を
ぜひ貼っておきましょう。
それを見ると
思わず笑ってしまうようなものを。
 〔ベンジャミン・フランクリン氏の健康の法則〕
〔ベンジャミン・フランクリン氏の健康の法則〕
足をあたたかく、頭をつめたく、
腸はからっぽに、こころをきれいに。
これらのことばは、北山耕平さんの著書『自然のレッスン』の中に載っています。初版が角川書店から出版されてから15年。数多くの人たちから、この本の復刻を望む声多くがあり、2001年に新装版が太田出版から出されました。新書を少し大きくしたような、手に取りやすい感じの本です。
 あとがきによると、この本に書いてあることは、著者が70年代後半から80年代後半にかけて、長い放浪の旅の途中で学んだことを書きとめられたものだそうです。アメリカ大陸南西部に広がる広大な砂漠のなかで、「自分の頭の中が空っぽになるような体験」をなんども持ち、そうした旅のなかで、自分の生き方を見つめなおすときのために、この『自然のレッスン』に収録された詩を書きとめていかれたということです。「自分がなにも知らないということを知っている自分」、言い換えれば「無垢な精神」から与えられた鏡のようなものだと述べられています。
あとがきによると、この本に書いてあることは、著者が70年代後半から80年代後半にかけて、長い放浪の旅の途中で学んだことを書きとめられたものだそうです。アメリカ大陸南西部に広がる広大な砂漠のなかで、「自分の頭の中が空っぽになるような体験」をなんども持ち、そうした旅のなかで、自分の生き方を見つめなおすときのために、この『自然のレッスン』に収録された詩を書きとめていかれたということです。「自分がなにも知らないということを知っている自分」、言い換えれば「無垢な精神」から与えられた鏡のようなものだと述べられています。
第一部は「こころのレッスン」、第二部「からだのレッスン」、第三部「食べもののレッスン」となっていますが、著者がマクロビオティックを日々の生活に取り入れられていることがわかります。あとがきの中に、久司道夫さんの名前もでてきます。
北山さんは、ネイティブ・アメリカンの精神を日本の次の世代に伝え、日本列島のネイティブ・スピリットの根っ子を探るワークをされているそうです。先住民文化―とりわけストーリー・テリングの―研究家であり、新しい生き方の探求者でもあられるということです。
 著書に『ネイティブ・マインド』(地湧社)『ネイティブ・タイム』(地湧社)、インディアンの言い伝えなどを題材にした絵本をいろいろ訳したりもされています。
著書に『ネイティブ・マインド』(地湧社)『ネイティブ・タイム』(地湧社)、インディアンの言い伝えなどを題材にした絵本をいろいろ訳したりもされています。
 絵本の題名を少しご紹介しておきます。
絵本の題名を少しご紹介しておきます。
『愛の笛』『野うまになったむすめ』『嵐のティピー』など
以前『世界を救う13人のおばあちゃんの言葉』という本を読みました。地球のあちこちの様々な先住民の生き方、グランドマザーの智恵の中に、これからの時代を救うヒントを求めています。こういった本もいろいろ出てきているようです。天外伺朗さんの著書もそうだったと思います。これからもこういった本に注目していきたいと思います。
うれしさは
生きていく上での大きなパワーです。
いつもうれしい顔ができるように
自分の部屋とかバスルームに
なにかおかしな写真や絵を
ぜひ貼っておきましょう。
それを見ると
思わず笑ってしまうようなものを。
足をあたたかく、頭をつめたく、
腸はからっぽに、こころをきれいに。
これらのことばは、北山耕平さんの著書『自然のレッスン』の中に載っています。初版が角川書店から出版されてから15年。数多くの人たちから、この本の復刻を望む声多くがあり、2001年に新装版が太田出版から出されました。新書を少し大きくしたような、手に取りやすい感じの本です。
第一部は「こころのレッスン」、第二部「からだのレッスン」、第三部「食べもののレッスン」となっていますが、著者がマクロビオティックを日々の生活に取り入れられていることがわかります。あとがきの中に、久司道夫さんの名前もでてきます。
北山さんは、ネイティブ・アメリカンの精神を日本の次の世代に伝え、日本列島のネイティブ・スピリットの根っ子を探るワークをされているそうです。先住民文化―とりわけストーリー・テリングの―研究家であり、新しい生き方の探求者でもあられるということです。
『愛の笛』『野うまになったむすめ』『嵐のティピー』など
以前『世界を救う13人のおばあちゃんの言葉』という本を読みました。地球のあちこちの様々な先住民の生き方、グランドマザーの智恵の中に、これからの時代を救うヒントを求めています。こういった本もいろいろ出てきているようです。天外伺朗さんの著書もそうだったと思います。これからもこういった本に注目していきたいと思います。
仏教関係の本に比べて、神道の本は数が少ないのでしょうか。これまで知る機会もなく来てしまいましたが、この間、てくてくさんから紹介していただいた『<神道>のこころ』を読ませていただき、大変嬉しかったです。
この「江原啓之 神紀行」は?〜?のシリーズになっていて、マガジンハウスから出版されています。予約していた本の連絡がまだで、それまでの間読む本をさがしていて、見つけました。雑誌に毎月掲載されていたものに、加筆されて出版されたものです。『<神道>のこころ』も、やさしく書かれていて読みやすかったですが、こちらのシリーズの内容も、かたくるしくなく、楽しみながら読めるようになっていてうれしいです。
江原啓之(えはらひろゆき)さんは、幼い頃から霊能力が強かったので、いろいろな神秘体験をされたそうです。人に見えないものが視え、聞こえないものが聞こえる。オカルト趣味の人からすると、おもしろいことのように思われることが、当人にとってはつらい毎日で、自分の霊能力に振り回されて、とても苦しい思いをしておられたそうです。
こうした苦しみから逃れられたのは、滝行などの修行を続け、霊能力をコントロールする力を身につけることができたからだということです。
このシリーズは、単なる観光ガイド本と違い、そんな江原さんならではの内容になっています。
私が借りているのは、シリーズの中の?と??で、他は残念ながら貸し出し中でした。
?は「伊勢・熊野・奈良」です。カラー写真とともに紹介される各聖地についての文も彼ならではの内容で、間に宿泊施設やお食事処が掲載されているページもあります。また、巻末には、<たましいに響くお参りの方法、特別に教えます>というのがあり、写真入りで分かりやすく説明されていて、いろいろ発見がありました。
鳥居や神殿の中央部分は、神様の通り道なので、人間はまん中を行かず、左右どちらかに遠慮しなくてはならないそうです。私は今までそんなことを考えずどこでも通っていました。鳥居をくぐるときには、まず一礼する。一歩鳥居をくぐれば、そこは神様の領域なので、心を落ち着け、厳粛な気持ちを持って境内に入ります。
境内に入ったら、最初に必ず手水を使う。神聖な神域に入るわけですから、御神殿に進む前に、まず手や口を清める必要があります。
そして“お参り”です。手順として覚えるのではなく、動作の意味を理解しましょう、とあります。
神社の境内を歩いていて、どこか心惹かれるものを感じた木があったら、手で触れて、そのパワーを取り込むといいそうです。人が見ていなかったら抱きついてもいい。そして、せっかく神社に行ったのだから、少なくとも1時間は境内にいて、ご神気を浴びるのが望ましいそうです。
『江原啓之 神紀行』 二回目です (2009年3月24日)
 江原さんの神紀行のシリーズでは、神社だけでなく、神霊の気配の漂う神聖な土地―スピリチュアル・サンクチュアリが紹介されています。
江原さんの神紀行のシリーズでは、神社だけでなく、神霊の気配の漂う神聖な土地―スピリチュアル・サンクチュアリが紹介されています。
?は「四国・出雲・広島」です。
四国編では、八十八箇所の巡礼寺と金刀比羅宮が紹介されています。
巨大な島でもある四国は、どこか一か所が突出しているのではなく、全体が霊的な磁場としての力を持っているように感じる、とあります。四国の霊場を開いたといわれる空海は、偉大な宗教家であると同時に、さまざまな伝説に彩られた霊能力者でもありました。本書では、八十八箇所のうち、一番から九番までが紹介されています。
筆者は、“ただ厳しいばかりがお遍路の旅ではない、お伊勢参りがそうだったように、昔の人たちにとって、お遍路も娯楽としての側面をもっていた。現代のお遍路も、札所を順にお参りするだけでなく、おおらかに楽しむ時間があってもいいと思う。例えば、讃岐うどんを食べる「うどんツアー」と組み合わせても楽しいかも”ともおっしゃっています。空海の「同行二人」の思いさえ忘れなければ、十分だと。
「出雲」は、いわずと知れた、神話に彩られた伝説の国です。
ここでは、「須佐神社」「出雲大社」「八重垣神社」「神魂(かもす)神社」が紹介されています。
江原さんは、「須佐神社」を、これこそ日本の神社だとおっしゃっています。いわゆる観光スポットでもなく、のどかな田園風景のなかに、ひっそりと建っているこの小さな神社は、個人的なランキングをつけさせていただくなら、日本一の神社だと思っていると書いておられます。神社名からもわかるとおり、スサノヲノミコトがお祀りされています。
筆者は、単行本化するにあたり、須佐神社を紹介するべきかどうか、かなり迷われたそうです。いたずらに観光地化してしまい、慎みのない参拝者の存在によって冒涜されてしまったりしたら、日本の宝のひとつを損なう結果にもなりかねないと危惧されたのです。
「広島」編では「厳島神社」が紹介されています。
江原さんは、広島は、とても重い意味のあるところだとおっしゃっています。「神の島」とも呼ばれる宮島をいだくサンクチュアリであると同時に、原爆の被爆地・ヒロシマとしての歴史を背負わされているからです。
「厳島神社」のご祭神は、イチキシマヒメノミコト・タゴリヒメノミコト・タキツヒメのミコトという女神様で、一般には「宗像の三女神」と呼ばれている神々です。それだけに、やわらかく包み込んでくれるような雰囲気を持っています。まさに癒しの空間なのです。
 次回に続きます。
次回に続きます。
?は「四国・出雲・広島」です。
四国編では、八十八箇所の巡礼寺と金刀比羅宮が紹介されています。
巨大な島でもある四国は、どこか一か所が突出しているのではなく、全体が霊的な磁場としての力を持っているように感じる、とあります。四国の霊場を開いたといわれる空海は、偉大な宗教家であると同時に、さまざまな伝説に彩られた霊能力者でもありました。本書では、八十八箇所のうち、一番から九番までが紹介されています。
筆者は、“ただ厳しいばかりがお遍路の旅ではない、お伊勢参りがそうだったように、昔の人たちにとって、お遍路も娯楽としての側面をもっていた。現代のお遍路も、札所を順にお参りするだけでなく、おおらかに楽しむ時間があってもいいと思う。例えば、讃岐うどんを食べる「うどんツアー」と組み合わせても楽しいかも”ともおっしゃっています。空海の「同行二人」の思いさえ忘れなければ、十分だと。
「出雲」は、いわずと知れた、神話に彩られた伝説の国です。
ここでは、「須佐神社」「出雲大社」「八重垣神社」「神魂(かもす)神社」が紹介されています。
江原さんは、「須佐神社」を、これこそ日本の神社だとおっしゃっています。いわゆる観光スポットでもなく、のどかな田園風景のなかに、ひっそりと建っているこの小さな神社は、個人的なランキングをつけさせていただくなら、日本一の神社だと思っていると書いておられます。神社名からもわかるとおり、スサノヲノミコトがお祀りされています。
筆者は、単行本化するにあたり、須佐神社を紹介するべきかどうか、かなり迷われたそうです。いたずらに観光地化してしまい、慎みのない参拝者の存在によって冒涜されてしまったりしたら、日本の宝のひとつを損なう結果にもなりかねないと危惧されたのです。
「広島」編では「厳島神社」が紹介されています。
江原さんは、広島は、とても重い意味のあるところだとおっしゃっています。「神の島」とも呼ばれる宮島をいだくサンクチュアリであると同時に、原爆の被爆地・ヒロシマとしての歴史を背負わされているからです。
「厳島神社」のご祭神は、イチキシマヒメノミコト・タゴリヒメノミコト・タキツヒメのミコトという女神様で、一般には「宗像の三女神」と呼ばれている神々です。それだけに、やわらかく包み込んでくれるような雰囲気を持っています。まさに癒しの空間なのです。
図書館で借りてきているこのシリーズは、?〜?までが貸し出し中だったので、今日の紹介は?の『北海道・東北・北陸』になります。昨日また図書館にいったら、?があったので借りて帰りました。?は「京都」です。だらだら長くなっても、と思って?で終わりにするつもりだったのですが、「京都」なら地元ですので、入れなくてはと思いますし、次回にその紹介をして終りたいと思います。
「北海道」編
もともと北海道は、アイヌの神が君臨し、自然のパワーと調和のとれた独自の文化を育んできた土地でした。江原さんは、この先住民族の文化と神性を尊重する気持ちは絶対に忘れてはならないと書いておられます。
ここでは、美瑛、知床、摩周湖、阿寒湖、洞爺湖が紹介されています。
江原さんにとって、美瑛は第二の故郷だそうです。そして、知床五湖や摩周湖、阿寒湖、洞爺湖などの湖。湖はもともと浄化のエネルギーを持っているものですが、それぞれの湖の素晴らしさを語っておられます。
「東北」編
スピリチュアルな観点から見ると、厳しい自然環境にさらされた土地には、特別な「学び」があります。また東北は修験道を中心とした信仰が息づいている土地柄でもあります。ここでは「出羽三山」―(羽黒山・月山・湯殿山)が紹介されています。
「北陸」編
北陸の人たちに苛酷な試練を与えているのが、雪の存在です。ただし、暮らしの障害となる豪雪は、豊かな水源となり、清らかな水が稲を育てます。江原さんは、自然の厳しさと向き合うことで、たましいを磨きながら、その自然の恵みを受ける…。神々の叡智は、高いところから、人々の成長を助けるカリキュラムを用意してくださっているのではないか、と語られています。
北陸の中で、江原さんが選ばれたのは、ただ一つの神社だけです。霊峰・弥彦山の麓にある越後の一宮、彌彦神社です。
“このシリーズは、聖地巡礼のガイドブックではなく、それぞれのサンクチュアリで、ぼくがどのように感じ、どのようなことを伝えたかったのかお話することが、刊行の目的です。だからこそ、聖地の数を増やすよりも、じっくり言葉を重ねることで、大切な何かを理解していただけるのではないかと考えたのです。聖地巡礼の旅をする上で大切なのは、「自分だけのサンクチュアリ」を見つけることです。”
最終回は『京都』(京都市内とその近辺の聖地)です。
市内では、醍醐寺・八坂神社・上賀茂神社・下賀茂神社・地主神社・今宮神社、市外では、亀岡市の出雲大神宮、八幡市の石清水八幡宮、宇治神社、そして天橋立と坂本〜比叡山が紹介されています。
長くなりますので、詳しい紹介は出来ません。京都については、江原さんのこの文章を引用したいと思います。
膨大な数の観光客を魅了する観光都市でありながら、京都の街には、至る所にサンクチュアリがあります。そうした不滅の強さと神秘性こそが、京都の本当の価値だといっていいのではないでしょうか。
厳しい自然のなかに隠されたサンクチュアリを目指し、無理をしながら参拝することだけが、聖地巡礼ではありません。ぼくたちの日常に、優しく寄り添ってくれるような、京都のあり方に改めて注目してほしいと思います。>
日本三景のひとつとして知られる天橋立は、数々の神話に彩られたサンクチュアリでもあります。
「丹後風土記」によると、天橋立は天への架け橋であり、イザナギノミコトとイザナミノミコトが、天への上り下りに使われた浮橋だったと記されているそうです。ある日、イザナギノミコトが昼ねをしているうちに橋が倒れて、それが天橋立になったとか。
また、素晴らしい景観であることから、天橋立の景色には、見る人や場所の名をつけた「〜観」という言葉が使われています。
歴史的な絵師として有名な雪舟が見た天橋立なら「雪舟観」、天橋立の展望台から一望する景色が、まるで龍が飛び立っているように見えることから「飛龍観」、というようにです。
江原さんがたどられた天橋立への道は、まず籠神社にお参りされることからでした。元伊勢のひとつでもある非常に社格の高い神社で、アマテラスオオミカミが祀られているということです。
坂本駅から参道を登っていくと、日吉大社があります。京都の表鬼門にあたることから、国家鎮護・方除けの神様として祀られています。
日吉大社から比叡山に登っていくと、延暦寺のご神域が広がっています。山中に点在する堂塔は二百以上にも達します。
とてもいい本ですね。謎の部分が多い著者について書かれているあとがきも興味深かったです。
他に、予約していて同時に届いたので読んでいる本があるのですが、「原因と結果の法則」と同じことを言っておられるので、不思議な気がしました。
その本は『生き方』(稲盛和夫 著 サンマーク出版)です。
稲盛さんはご存知のように、京セラを設立、84年には稲盛財団を設立し、京都賞を創設された方ですが、『原因と結果の法則』の内容と同じことを書いておられて、もしかしたらこの本を読まれているのかも知れない、いや、そうでなくても、立派な方だから正しい生き方の道すじが見えてらっしゃるのだと思ったりしました。
経営者の相次ぐ不祥事が問題になっていますが、稲盛さんは、それはリーダーの選び方自体に問題があると述べておられます。(組織のリーダーというものを、人格よりも才覚や能力を基準に選ぶことをくり返してきたから、人格というあいまいなものより、才覚という成果に直結しやすい要素を重視して自分たちのリーダーを選ぶ傾向が強かったから。才あれども徳に乏しい人間を自分たちの長としていただきたがる…)
“徳”というと、孔子の論語を思い出しますね
また、稲盛さんは幼少のころから、仏様に手を合わせる環境で育たれ、長じては仏門に入り得度されているということもこの本ではじめて知りました。いろいろ感銘を受けました。
(2009年9月5日)
 『神道 見えないものの力』 葉室頼昭・著 春秋社
『神道 見えないものの力』 葉室頼昭・著 春秋社
『神道のこころ』は、てくてくさんに教えていただいて読ませていただきましたが、これはそのあと書かれた『神道と日本人』に続き、第三冊目として出版された本です。
『神道のこころ』を読み、とても感銘を受け、葉室さんの著書をもっと知りたいと思っていたのですが、なかなか読めずにきていました。二冊目の『神道と日本人』はまだ読んでいなくて、こちらの方が先になってしまいました。
図書館で検索して出たのが資料室の本で、出していただいたら、大活字本で、二分冊になっていました。これは目が疲れなくて助かると、ありがたく借りて帰りました。この拡大写本を製作したのは、京都市上京区の社団法人「霞会館 福祉事業委員会」というところで、春秋社の許可を得て、平成20年に発行した非売品です。そんなわけで、この大活字本に関しては、もしかしたらあちこちにはないかもしれません。
最初に読んだ『神道のこころ』もそうでしたが、今回もまた、読んでいくうちに、心が洗われるような気持ちになりました。
会話体で書かれ、とてもわかりやすく助かりました。
“神道の心”とは宗教のことではなく、広い意味での“日本人の心”のことだそうです。
 <序章・見えないものの力>の「古事記のこころと宇宙のはじまり」など、
<序章・見えないものの力>の「古事記のこころと宇宙のはじまり」など、 <第一章・時間と空間>の「宇宙の時間とわれわれの時間」「祖先とつながるいのち」など、
<第一章・時間と空間>の「宇宙の時間とわれわれの時間」「祖先とつながるいのち」など、 <第二章・日本語について>の「本当の日本語」「おとぎばなしについて」など、
<第二章・日本語について>の「本当の日本語」「おとぎばなしについて」など、 <第三章・生命の不思議>の「誕生と往生について」など、
<第三章・生命の不思議>の「誕生と往生について」など、 <第四章・真実の人生とは>の「バランスと真実の健康」など、
<第四章・真実の人生とは>の「バランスと真実の健康」など、 <第五章・こころをたもつ>など、どのお話もすばらしく、今まで疑問に思ってきたこと、腑に落ちなかったことが解け、晴ればれとした気持ちにもなりました。
<第五章・こころをたもつ>など、どのお話もすばらしく、今まで疑問に思ってきたこと、腑に落ちなかったことが解け、晴ればれとした気持ちにもなりました。
 つづきは次回に。
つづきは次回に。
『神道のこころ』は、てくてくさんに教えていただいて読ませていただきましたが、これはそのあと書かれた『神道と日本人』に続き、第三冊目として出版された本です。
『神道のこころ』を読み、とても感銘を受け、葉室さんの著書をもっと知りたいと思っていたのですが、なかなか読めずにきていました。二冊目の『神道と日本人』はまだ読んでいなくて、こちらの方が先になってしまいました。
図書館で検索して出たのが資料室の本で、出していただいたら、大活字本で、二分冊になっていました。これは目が疲れなくて助かると、ありがたく借りて帰りました。この拡大写本を製作したのは、京都市上京区の社団法人「霞会館 福祉事業委員会」というところで、春秋社の許可を得て、平成20年に発行した非売品です。そんなわけで、この大活字本に関しては、もしかしたらあちこちにはないかもしれません。
最初に読んだ『神道のこころ』もそうでしたが、今回もまた、読んでいくうちに、心が洗われるような気持ちになりました。
会話体で書かれ、とてもわかりやすく助かりました。
“神道の心”とは宗教のことではなく、広い意味での“日本人の心”のことだそうです。
(2009年9月8日)
 『神道 見えないものの力』 葉室頼明・著
『神道 見えないものの力』 葉室頼明・著
続きです。
67歳で春日大社の宮司になられた葉室さんが、第一章<時間と空間>の中の「宇宙の時間とわれわれの時間」で述べられた言葉に、とても力づけられました。
“春日大社の宮司に行きつくまでの道程は、人間の頭で考えるなら、回り道であった。遠回りして、医者をさんざんやって春日大社の宮司としてきた、これが神さまのお考えになるいちばん短い時間である。われわれの考えている時間と神の時間とは違う。理屈でこの道を行ったらいちばん短いだろうと考える道は、必ずしも正しくない。神さまの時間に沿って生きることが、いちばんの最短距離である。”
 また、第二章<日本語について>の中の「おとぎばなしについて」は、おとぎばなしの中に込められた、深い意味について語られており、気づかされることがいろいろありました。
また、第二章<日本語について>の中の「おとぎばなしについて」は、おとぎばなしの中に込められた、深い意味について語られており、気づかされることがいろいろありました。
“むずかしい真実の話をやさしく物語ふうに書いたというのが、おとぎばなしである。
物語の最初に、おじいちゃんとおばあちゃんが出てくる。決して、お父さんとお母さんではない。
なぜおじいちゃん、おばあちゃんかというと、結局、本当の歴史、命というものは、おじいちゃん、おばあちゃんから伝わるものだということを、昔の人は知っていたということだ。
 「花咲かじじい」の話にしても、灰をまいたらさくらが咲いたとか、そんな話があるかと言うけれども、本当だと思う。
「花咲かじじい」の話にしても、灰をまいたらさくらが咲いたとか、そんな話があるかと言うけれども、本当だと思う。
この話で語られているのは、我欲のない素直さということ。そうすると、花が開くというのは、神が現れるという意味だと思う。
灰というのは、「はい」という返事の言葉と同じ意味だろうと思う。
「は」というのはよみがえるという意味。葉っぱの葉のこと。あれは炭酸ガスを葉緑素で酸素によみがえらせている。「い」というのは命だから、命がよみがえるという神さまの言葉なのだ。ここでは、それを木にまく「灰」になぞらえているのだと思う。
「はは」と言ったらお母さんになる。「は」が二つくっついたら、本当に子供を産む、命をよみがえらせる。日本語とは全部そういう言葉である。一字一字に意味があるというのが日本語なのだ”
他にもいろいろ書かれていましたが、書ききれないので、興味のある方はどうぞ本を手に取ってごらんになってください。
続きです。
67歳で春日大社の宮司になられた葉室さんが、第一章<時間と空間>の中の「宇宙の時間とわれわれの時間」で述べられた言葉に、とても力づけられました。
“春日大社の宮司に行きつくまでの道程は、人間の頭で考えるなら、回り道であった。遠回りして、医者をさんざんやって春日大社の宮司としてきた、これが神さまのお考えになるいちばん短い時間である。われわれの考えている時間と神の時間とは違う。理屈でこの道を行ったらいちばん短いだろうと考える道は、必ずしも正しくない。神さまの時間に沿って生きることが、いちばんの最短距離である。”
“むずかしい真実の話をやさしく物語ふうに書いたというのが、おとぎばなしである。
物語の最初に、おじいちゃんとおばあちゃんが出てくる。決して、お父さんとお母さんではない。
なぜおじいちゃん、おばあちゃんかというと、結局、本当の歴史、命というものは、おじいちゃん、おばあちゃんから伝わるものだということを、昔の人は知っていたということだ。
この話で語られているのは、我欲のない素直さということ。そうすると、花が開くというのは、神が現れるという意味だと思う。
灰というのは、「はい」という返事の言葉と同じ意味だろうと思う。
「は」というのはよみがえるという意味。葉っぱの葉のこと。あれは炭酸ガスを葉緑素で酸素によみがえらせている。「い」というのは命だから、命がよみがえるという神さまの言葉なのだ。ここでは、それを木にまく「灰」になぞらえているのだと思う。
「はは」と言ったらお母さんになる。「は」が二つくっついたら、本当に子供を産む、命をよみがえらせる。日本語とは全部そういう言葉である。一字一字に意味があるというのが日本語なのだ”
他にもいろいろ書かれていましたが、書ききれないので、興味のある方はどうぞ本を手に取ってごらんになってください。
(2006.5 とものひろば まっちゃん)
また道元の話になります。「道元を語る」(かまくら春秋社)には、道元について、いろいろな方のエッセーやインタビューなどが載っているのですが、その中に辰巳芳子さんの『「典座教訓」のはなし』というのがありました。典座(てんぞ)というのは禅宗のお坊さんの、一番大切な修行であるとされている、料理を作る役目をする人のことです。
道元さまの書かれた「典座教訓」について、辰巳さんは、道元は一見雑務に見える台所の仕事の中に哲学的な意味づけをしてくれているという内容のことをおっしゃっています。
以下、辰巳さんの言葉。『人生を全うするのに70パーセントが家事の力だと思う。良い家事の無い所に良い文化は生まれない。健康も経済も愛もそれをはぐくむのは家事。家事がなだらかでトゲトゲしくなく行われないと人は晴朗には生きられません。世の中の学問、芸術、仕事を支えているのは万全な家事です。そのありがたさ、意味合いが忘れられてしまっている。家事の存在を過小評価したことで人間は多くを失った、なかでもかっ克己心を失ってきました。昔の人は取るに足らないものの積み重ねが人生であるということを、家事を通して学んでいたのです。』とあります。
また道元の話になります。「道元を語る」(かまくら春秋社)には、道元について、いろいろな方のエッセーやインタビューなどが載っているのですが、その中に辰巳芳子さんの『「典座教訓」のはなし』というのがありました。典座(てんぞ)というのは禅宗のお坊さんの、一番大切な修行であるとされている、料理を作る役目をする人のことです。
道元さまの書かれた「典座教訓」について、辰巳さんは、道元は一見雑務に見える台所の仕事の中に哲学的な意味づけをしてくれているという内容のことをおっしゃっています。
以下、辰巳さんの言葉。『人生を全うするのに70パーセントが家事の力だと思う。良い家事の無い所に良い文化は生まれない。健康も経済も愛もそれをはぐくむのは家事。家事がなだらかでトゲトゲしくなく行われないと人は晴朗には生きられません。世の中の学問、芸術、仕事を支えているのは万全な家事です。そのありがたさ、意味合いが忘れられてしまっている。家事の存在を過小評価したことで人間は多くを失った、なかでもかっ克己心を失ってきました。昔の人は取るに足らないものの積み重ねが人生であるということを、家事を通して学んでいたのです。』とあります。
人は何の目的のために生きているんだろう? そういう疑問がわいたときにお薦めの一冊です。
著者の葉室頼昭さんは学生時代に重い肺結核が「突如消えうせる」神秘体験のあと40年間形成外科の医師として過ごし、春日大社の宮司となられた方です。
神道は日本人古来からの物の考え方、生活習慣の事。宗教ではありませんと語られています。
この本には宇宙の成り立ちから「真実とはなにか」、その他今を生きていく知恵がいっぱいつまっています。対話形式なので読みやすいと思います。
この本は沢山の人に読んでいただきたい。そして、次代に神道を理解していってもらいたいのです。かつて神国といって戦争に入っていった時代があったのでわたしは神道を敬遠していました。同じような思いの人は多いのではないでしょうか。
名古屋の「フラワードーム2009」に青春18切符で行ってきました。東京ドームほどの規模ではありませんでしたが、一人で十分楽しんできました。その往復でこの本を読み返しました。
今、私がもっとも必要な答えが見つかりました。
紹介したい内容は沢山あるのですが、まず読んでいただきたいと思いました。皆さんの感想などお聞かせいただけたらうれしいですね。
日記で紹介してから、そうえつさんからも、葉室さんの本を読んでいますとのコメントをいただき、『神道 感謝のこころ』(春秋社)のことも教えていただきました。外出するとき、カバンに入れて持ち歩いていらっしゃるとのことです。
(2009年10月22日)
 『神道と日本人』 葉室頼昭・著 春秋社(1999年第一刷)
『神道と日本人』 葉室頼昭・著 春秋社(1999年第一刷)
 一冊目の『<神道>のこころ』についで出版された本。
一冊目の『<神道>のこころ』についで出版された本。
さきにご紹介した『神道 見えないものの力』は三冊目になります。(どれから先に読まなくてはならないということはありませんが)
 まず、目次を簡単にご紹介すると、第一章 日本人と神道、第二章 自然のこころ、第三章 滅びの日本社会、第四章 これからの時代 ― 二十一世紀に向けて、となっています。
まず、目次を簡単にご紹介すると、第一章 日本人と神道、第二章 自然のこころ、第三章 滅びの日本社会、第四章 これからの時代 ― 二十一世紀に向けて、となっています。
日本の国は、戦争に負けて、その時から日本の歴史や伝統を否定し、子供におしえなくなった。
そのために子供は、昔のことは関係ないとか、おじいちゃんやおばあちゃんの話は古いとか言って聞かなくなり、自分が日本人である自覚も、誇りも持たない若者がたくさんいる。
命というものには、個人個人の命だけでなく、代々受け継がれてきた民族の命、伝統の命というものもあるのだ。アメリカやヨーロッパなどのまねをして、外国人の命を持ってきたから、日本人がおかしくなった。
日本人の祖先が代々伝えてきたすばらしい伝統、智恵が忘れ去られている。ただ、政治とか、経済とか、科学とか、それだけでやろうとしているが、そんな表面的なことだけで解決しようとするのは間違いである。
世界の国の歴史を見れば分かるように、その国の歴史や民族の誇りを失った国は必ず滅びる。このままでは日本は滅びの道をたどっていると思われる。
今こそ原点にたちかえり、みんなが、日本人であるという自覚と誇りに目覚めて欲しいと書かれています。
書きたいことはたくさんあるのですが、長くなってしまいますので、<第四章 これからの時代ー二十一世紀に向けて>の中から一箇所ご紹介するにとどめます。
 「体のバランスを整えるその根本は、生かされているということに感謝する心を持つことだと思うのです。そうすると、脳から正しい指令が出て、体のバランスが整う。これをしないでバランスが崩れたまま、いくらジョギングをしようと、栄養のあるものを食べようと、そんなことは真の健康には全然役立たない。健康にするのではなくて、もともと持っている健康の状態に戻ることが大切。
「体のバランスを整えるその根本は、生かされているということに感謝する心を持つことだと思うのです。そうすると、脳から正しい指令が出て、体のバランスが整う。これをしないでバランスが崩れたまま、いくらジョギングをしようと、栄養のあるものを食べようと、そんなことは真の健康には全然役立たない。健康にするのではなくて、もともと持っている健康の状態に戻ることが大切。
それには、まず第一に心のバランスです。自分の力で生きていると考えることは、共生という本来の姿を忘れた我欲であって、もうすでにバランスが崩れているのです。生かされていることを知り、ひたすら感謝することが、我をなくす精神状態ですから、そういうふうになれば、おのずから体も整ってくるのです。」
こうして書いていると、堅苦しい内容のようですが、対話形式の話し言葉で書かれているので、むずかしく感じません。忘れているようでも、自分の中にある日本人の遺伝子
 が感知してくれるのではないでしょうか。いつも葉室さんの本を読むと、読後なんともいえず清々しい気持ちになれるのです。
が感知してくれるのではないでしょうか。いつも葉室さんの本を読むと、読後なんともいえず清々しい気持ちになれるのです。
さきにご紹介した『神道 見えないものの力』は三冊目になります。(どれから先に読まなくてはならないということはありませんが)
日本の国は、戦争に負けて、その時から日本の歴史や伝統を否定し、子供におしえなくなった。
そのために子供は、昔のことは関係ないとか、おじいちゃんやおばあちゃんの話は古いとか言って聞かなくなり、自分が日本人である自覚も、誇りも持たない若者がたくさんいる。
命というものには、個人個人の命だけでなく、代々受け継がれてきた民族の命、伝統の命というものもあるのだ。アメリカやヨーロッパなどのまねをして、外国人の命を持ってきたから、日本人がおかしくなった。
日本人の祖先が代々伝えてきたすばらしい伝統、智恵が忘れ去られている。ただ、政治とか、経済とか、科学とか、それだけでやろうとしているが、そんな表面的なことだけで解決しようとするのは間違いである。
世界の国の歴史を見れば分かるように、その国の歴史や民族の誇りを失った国は必ず滅びる。このままでは日本は滅びの道をたどっていると思われる。
今こそ原点にたちかえり、みんなが、日本人であるという自覚と誇りに目覚めて欲しいと書かれています。
書きたいことはたくさんあるのですが、長くなってしまいますので、<第四章 これからの時代ー二十一世紀に向けて>の中から一箇所ご紹介するにとどめます。
それには、まず第一に心のバランスです。自分の力で生きていると考えることは、共生という本来の姿を忘れた我欲であって、もうすでにバランスが崩れているのです。生かされていることを知り、ひたすら感謝することが、我をなくす精神状態ですから、そういうふうになれば、おのずから体も整ってくるのです。」
こうして書いていると、堅苦しい内容のようですが、対話形式の話し言葉で書かれているので、むずかしく感じません。忘れているようでも、自分の中にある日本人の遺伝子
『世界を救う13人のおばあちゃんの言葉』
キャロル・シェーファー 著 ゴマブックス(2007年) 1600円+税
 2004年ニューヨークにて、世界各地の伝統ある部族の代表であり、それぞれの部族の生ける伝説である13人のグランマザーたちによる会議が開かれました。世界のそれぞれの地域から集まった智恵を平和のための力とするために。
2004年ニューヨークにて、世界各地の伝統ある部族の代表であり、それぞれの部族の生ける伝説である13人のグランマザーたちによる会議が開かれました。世界のそれぞれの地域から集まった智恵を平和のための力とするために。
 マザー達の写真と生い立ち、民族の歴史にも触れ、また、どのマザー達の言葉も、自然の声を聞くことの大切さを呼びさまし、文明とともに人々が忘れてきた大切なことに気づかせるメッセージを投げかけています。
マザー達の写真と生い立ち、民族の歴史にも触れ、また、どのマザー達の言葉も、自然の声を聞くことの大切さを呼びさまし、文明とともに人々が忘れてきた大切なことに気づかせるメッセージを投げかけています。
マザー達の顔が誇り高く堂々としていて、とても素敵でした。
年をとっても、次代を担う人達に大切なことを伝えていけるようなおばあちゃんになれたらと思います。
キャロル・シェーファー 著 ゴマブックス(2007年) 1600円+税
マザー達の顔が誇り高く堂々としていて、とても素敵でした。
年をとっても、次代を担う人達に大切なことを伝えていけるようなおばあちゃんになれたらと思います。
「美しいお経」 瀬戸内寂聴 著 嶋中書店 (952円+税)
<はじめに>より引用
いつの頃からか、こういうスタイルの、こういう内容の本を書きたいという想いが湧いていた。
どこへでも持ち運べて、いつでも気軽に開いたら、どのページにも短い美しいお経や詩歌の言葉が囁きかけてくれる。疲れた時、淋しい時、心に屈託をかかえている時、孤独で泣きたい時、あるいは幸福感で心が満ち足りて思わず誰かに話しかけたいような時、こっそり開いてみたら、自分の心を見透かしたような、なつかしい美しいお経や詩の短い言葉が応えてくれている。 (中略)
また、この本には、本来のお経の他に、私たちの祖先が伝えてきた美しい詩歌、日本の宗祖たちや高僧たちの、美しい言葉も加えてみた。
瀬戸内さんの願いどおり、声に出してくり返し口ずさむだけで、心がおだやかになるような本です。
(嶋本書店から初版が出ましたが、その後、改訂版が出ています。確か中央公論社だったと思います。)
<はじめに>より引用
いつの頃からか、こういうスタイルの、こういう内容の本を書きたいという想いが湧いていた。
どこへでも持ち運べて、いつでも気軽に開いたら、どのページにも短い美しいお経や詩歌の言葉が囁きかけてくれる。疲れた時、淋しい時、心に屈託をかかえている時、孤独で泣きたい時、あるいは幸福感で心が満ち足りて思わず誰かに話しかけたいような時、こっそり開いてみたら、自分の心を見透かしたような、なつかしい美しいお経や詩の短い言葉が応えてくれている。 (中略)
また、この本には、本来のお経の他に、私たちの祖先が伝えてきた美しい詩歌、日本の宗祖たちや高僧たちの、美しい言葉も加えてみた。
瀬戸内さんの願いどおり、声に出してくり返し口ずさむだけで、心がおだやかになるような本です。
(嶋本書店から初版が出ましたが、その後、改訂版が出ています。確か中央公論社だったと思います。)
(2009年7月23日)
図書館で予約していた本が、二冊同時に来てしまいました。
 『成熟し、人はますます若くなる』 佐藤友美子(サントリー文化財団上席フェロー)編著 NTT出版(2008年) 1600円+税
『成熟し、人はますます若くなる』 佐藤友美子(サントリー文化財団上席フェロー)編著 NTT出版(2008年) 1600円+税
 『絵本を語る』 マーシャ・ブラウン/著 上條由美子/訳 ブック・グローブ社(1994年第一刷) 1800円
『絵本を語る』 マーシャ・ブラウン/著 上條由美子/訳 ブック・グローブ社(1994年第一刷) 1800円
どちらの本も中身が濃く、食べ物が身につくように、よく噛んでいただくようにして読んでいるので、なかなか先へ進みません とうとう今日返却の日になってしまいました。次に予約がはいっていなければ、もう二週間借りようと思っています。
『成熟し、人はますます若くなる』
まえがきにはこう書かれています。“「成熟するにつれて人はますます若くなる」とは、ヘルマン・ヘッセの言葉である。年齢を重ねても成熟するのは容易なことではない。しかし、柔軟な心や好奇心を保つことはそれ以上に難しい。
21世紀に日本が目指すべきは、どんな社会であり、ライフスタイルであるのか。次世代に引き継ぐべきは何なのか。目先の利益ではなく、もっと長い目で、もっと大きく高い視座から導いて欲しい。そんな思いから、「21世紀の不易をたずねる」という研究テーマを設定し、各界の19人先達の口述から探ることにした。そのインタビューのエッセンスをまとめたのがこの本である。”
19人全員をご紹介することは、とてもできませんので、お一人だけ、辰巳芳子さんのお話から少し紹介するに留めます。
「食べ方というのは、人生そのものです」と、タイトルにあります。
21世紀は「慎みの世紀」、「人間の分際をわきまえること」、が何より大事だ。珍しい料理をつくったり、お金をかけたりすることでもない。質素でも、心がこもっていれば、それは「よく生きること」に通じるのである。食を預ることを誇りに思う気持ち、それは現代の人が忘れているものの一つである。
日本のお米の問題でも、国の政策が第一ではなく、現在私たちがどのようにお米を食べていくかにかかっている。朝ご飯をお味噌汁と一緒に食べる。しっかりしたおむすびをつくって弁当を持たせてやれる。疲れて帰ってきた人におじやをさっと出してあげられる。そういうことが日本の米を守ると思う。
台所の片隅から、有機無農薬・ポストハーベスト・原燃問題・憲法九条を洞察し、誇り高く台所仕事をする。
風土と人間の関係は、親よりも深い、自分の身体の反応を観察できる人にならねば、など、読んでいて、まだまだ中途半端な自分をかえりみ、目が覚めるようでした。
『絵本を語る』についても、またご紹介できたらと思っています。
長くなりますので、今日はこのあたりで。(『絵本を語る』は外国文学のコーナーに入れることにします。)
図書館で予約していた本が、二冊同時に来てしまいました。
どちらの本も中身が濃く、食べ物が身につくように、よく噛んでいただくようにして読んでいるので、なかなか先へ進みません とうとう今日返却の日になってしまいました。次に予約がはいっていなければ、もう二週間借りようと思っています。
『成熟し、人はますます若くなる』
まえがきにはこう書かれています。“「成熟するにつれて人はますます若くなる」とは、ヘルマン・ヘッセの言葉である。年齢を重ねても成熟するのは容易なことではない。しかし、柔軟な心や好奇心を保つことはそれ以上に難しい。
21世紀に日本が目指すべきは、どんな社会であり、ライフスタイルであるのか。次世代に引き継ぐべきは何なのか。目先の利益ではなく、もっと長い目で、もっと大きく高い視座から導いて欲しい。そんな思いから、「21世紀の不易をたずねる」という研究テーマを設定し、各界の19人先達の口述から探ることにした。そのインタビューのエッセンスをまとめたのがこの本である。”
19人全員をご紹介することは、とてもできませんので、お一人だけ、辰巳芳子さんのお話から少し紹介するに留めます。
「食べ方というのは、人生そのものです」と、タイトルにあります。
21世紀は「慎みの世紀」、「人間の分際をわきまえること」、が何より大事だ。珍しい料理をつくったり、お金をかけたりすることでもない。質素でも、心がこもっていれば、それは「よく生きること」に通じるのである。食を預ることを誇りに思う気持ち、それは現代の人が忘れているものの一つである。
日本のお米の問題でも、国の政策が第一ではなく、現在私たちがどのようにお米を食べていくかにかかっている。朝ご飯をお味噌汁と一緒に食べる。しっかりしたおむすびをつくって弁当を持たせてやれる。疲れて帰ってきた人におじやをさっと出してあげられる。そういうことが日本の米を守ると思う。
台所の片隅から、有機無農薬・ポストハーベスト・原燃問題・憲法九条を洞察し、誇り高く台所仕事をする。
風土と人間の関係は、親よりも深い、自分の身体の反応を観察できる人にならねば、など、読んでいて、まだまだ中途半端な自分をかえりみ、目が覚めるようでした。
『絵本を語る』についても、またご紹介できたらと思っています。
長くなりますので、今日はこのあたりで。(『絵本を語る』は外国文学のコーナーに入れることにします。)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
元気な本棚 ほっこり 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-