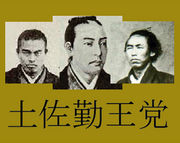土佐勤王党の血盟同志は約200名にのぼります。
そんな彼らの足跡をたどるべく石碑などを訪門しているのですが・・・
幕末土佐の四天王と言われる武市半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎、吉村虎太郎らは史跡も複数存在しますが、
その他の200名近くの血盟同志に関する史跡などはほとんど存在しません。
そう、そこでその他の血盟同志ゆかりの地といえば、
彼らの眠る地・・・
墓所しかありませんでした!!!
ここでは、そんな有名な血盟同志から無名の血盟同志まで、
ほとんどの同志にとっては唯一と言っていい史跡(墓所)の紹介や情報交換の場にできたらと思います。
訪れようと思っている方は国のために命をかけて奔走した先人達への尊敬と感謝の念をもって静かに手を合わせてきてください。
そしてまずはやはり土佐勤王党盟主、武市半平太の墓所を。
瑞山神社の境内に先祖や夫人の富と共に静かに眠っています。
余談ですが「龍馬伝」で龍馬役の福山雅治も高知ロケの際にはここを訪れたとの事です。
そんな彼らの足跡をたどるべく石碑などを訪門しているのですが・・・
幕末土佐の四天王と言われる武市半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎、吉村虎太郎らは史跡も複数存在しますが、
その他の200名近くの血盟同志に関する史跡などはほとんど存在しません。
そう、そこでその他の血盟同志ゆかりの地といえば、
彼らの眠る地・・・
墓所しかありませんでした!!!
ここでは、そんな有名な血盟同志から無名の血盟同志まで、
ほとんどの同志にとっては唯一と言っていい史跡(墓所)の紹介や情報交換の場にできたらと思います。
訪れようと思っている方は国のために命をかけて奔走した先人達への尊敬と感謝の念をもって静かに手を合わせてきてください。
そしてまずはやはり土佐勤王党盟主、武市半平太の墓所を。
瑞山神社の境内に先祖や夫人の富と共に静かに眠っています。
余談ですが「龍馬伝」で龍馬役の福山雅治も高知ロケの際にはここを訪れたとの事です。
|
|
|
|
コメント(26)
<上田 官吉>うえた かんきち
天保4年(1833年)〜慶応4年(1868年)
天保4年高知城下浦戸町に上田保之の子として生まれます。
名を正秋。
官吉は親戚であった上田宗児とともに75番目に土佐勤王党に血判連書して国事に奔走ます。
戊辰戦争には土佐藩兵として従軍、迅衝隊の4番隊に所属して東征軍にしたがい関東から奥州方面に転戦しましたが、会津若松城追手口の戦いで戦死しています。享年30歳。
墓所は高知市薊野の真宗寺山で岡田以蔵の墓所のすぐ近くで、以蔵の墓を記す看板のある中須を少し進むと左側の茂みの中にあります。
官吉の墓は何故か真宗寺山の地図にも記載されてなかったと思います。
天保4年(1833年)〜慶応4年(1868年)
天保4年高知城下浦戸町に上田保之の子として生まれます。
名を正秋。
官吉は親戚であった上田宗児とともに75番目に土佐勤王党に血判連書して国事に奔走ます。
戊辰戦争には土佐藩兵として従軍、迅衝隊の4番隊に所属して東征軍にしたがい関東から奥州方面に転戦しましたが、会津若松城追手口の戦いで戦死しています。享年30歳。
墓所は高知市薊野の真宗寺山で岡田以蔵の墓所のすぐ近くで、以蔵の墓を記す看板のある中須を少し進むと左側の茂みの中にあります。
官吉の墓は何故か真宗寺山の地図にも記載されてなかったと思います。
<川原塚 茂太郎>かわらづか しげたろう
天保元年(1830年)〜明治9年(1876年)
高知城下南奉公人町(高知市上町)徒士の川原塚堅作の子として誕生。
名を重幸。
土佐勤王党には11番目の加盟。
参政吉田東洋暗殺を計画した際には、別働隊としてこれに加わっていました。
土佐勤王党への弾圧が始まると、茂太郎は門田為之助や望月清平らとともに城下の同志代表として会合に出席し、釈放を要求する建白書を藩庁に提出。
戊辰戦争では軍事掛徒目付として北越戦争に従軍した。
維新後は讃州金陵会議結、川之江民政局副参事、教部省に出仕し、明治8年辞職した。
その後は土佐に帰り元勤王党同志大石弥太郎の古勤王党に所属して有力党員として茂太郎は活躍しましたが明治9年に国事犯として警視庁に抑留され、そのまま獄死しています。
茂太郎の姉・千野は、坂本龍馬の兄・権平に嫁いでいた事から坂本家とは深い繋がりだったようです。
墓所は高知県高知市平和町の小高坂山で、勤王党幹部の弘瀬健太らの墓所のある墓域から山に向かって伸びる道を登りきったらすぐ発見できると思います。
天保元年(1830年)〜明治9年(1876年)
高知城下南奉公人町(高知市上町)徒士の川原塚堅作の子として誕生。
名を重幸。
土佐勤王党には11番目の加盟。
参政吉田東洋暗殺を計画した際には、別働隊としてこれに加わっていました。
土佐勤王党への弾圧が始まると、茂太郎は門田為之助や望月清平らとともに城下の同志代表として会合に出席し、釈放を要求する建白書を藩庁に提出。
戊辰戦争では軍事掛徒目付として北越戦争に従軍した。
維新後は讃州金陵会議結、川之江民政局副参事、教部省に出仕し、明治8年辞職した。
その後は土佐に帰り元勤王党同志大石弥太郎の古勤王党に所属して有力党員として茂太郎は活躍しましたが明治9年に国事犯として警視庁に抑留され、そのまま獄死しています。
茂太郎の姉・千野は、坂本龍馬の兄・権平に嫁いでいた事から坂本家とは深い繋がりだったようです。
墓所は高知県高知市平和町の小高坂山で、勤王党幹部の弘瀬健太らの墓所のある墓域から山に向かって伸びる道を登りきったらすぐ発見できると思います。
<弘瀬 健太>ひろせ けんた
天保7年(1836年)〜文久3年(1863年)
高知城下井口村の用人の弘瀬喜代助の長男として誕生。
名を年定。
土佐勤王党には13番目に加盟しており、『至高沈着の人』と呼ばれ、勤王党の幹部として活躍しています。
同じく幹部の間崎哲馬は土佐藩の藩風を一新しようと、土佐最高の権力者の元12代目土佐藩主山内豊資を味方に付ける事を考え、豊資を動かす為に青蓮院宮に土佐藩に藩政改革を迫る令旨の下賜を要請し、間崎哲馬と平井収二郎と共に青蓮院宮に拝謁して令旨を貰う事に成功しています。
しかし、この事が山内容堂の逆鱗に触れてしまい、郷士の身分で藩を動かした罪で、平井収二郎、間崎哲馬と共に切腹を命じられてしまいます。
「男は腹が見事に斬れるかどうかで値打ちが決まる」
健太は常々この言葉が口癖だったそうで、介錯の必要のない壮絶な切腹をおこなったと伝わります。
墓所は高知市平和町の県住の横の墓所で廣井磐之助(藩政期最期の仇討ちを果たしたとゆう人で、この仇討ちには坂本龍馬、勝海舟も関わったらしいです。墓碑は勝海舟によるものです)の墓の後ろにあります。
こちらはお墓とゆうか碑ですね。
本当の弘瀬健太の墓は高知市の一宮の山にあったらしいですが、道路を造るために撤去されてしまったようです…
天保7年(1836年)〜文久3年(1863年)
高知城下井口村の用人の弘瀬喜代助の長男として誕生。
名を年定。
土佐勤王党には13番目に加盟しており、『至高沈着の人』と呼ばれ、勤王党の幹部として活躍しています。
同じく幹部の間崎哲馬は土佐藩の藩風を一新しようと、土佐最高の権力者の元12代目土佐藩主山内豊資を味方に付ける事を考え、豊資を動かす為に青蓮院宮に土佐藩に藩政改革を迫る令旨の下賜を要請し、間崎哲馬と平井収二郎と共に青蓮院宮に拝謁して令旨を貰う事に成功しています。
しかし、この事が山内容堂の逆鱗に触れてしまい、郷士の身分で藩を動かした罪で、平井収二郎、間崎哲馬と共に切腹を命じられてしまいます。
「男は腹が見事に斬れるかどうかで値打ちが決まる」
健太は常々この言葉が口癖だったそうで、介錯の必要のない壮絶な切腹をおこなったと伝わります。
墓所は高知市平和町の県住の横の墓所で廣井磐之助(藩政期最期の仇討ちを果たしたとゆう人で、この仇討ちには坂本龍馬、勝海舟も関わったらしいです。墓碑は勝海舟によるものです)の墓の後ろにあります。
こちらはお墓とゆうか碑ですね。
本当の弘瀬健太の墓は高知市の一宮の山にあったらしいですが、道路を造るために撤去されてしまったようです…
<小畑 孫三郎>おばた まござぶろう
天保8年(1837年)〜慶応2年(1866年)
土佐郡一宮村の土佐藩郷士小畑美穂の三男として誕生。
名を和。正路。
兄に維新後に男爵までなった小畑美稲がいます。
土佐勤王党が結成されると兄の孫次郎(美稲)と共に22番目に加盟しています。
孫三郎は河野万寿弥や弘瀬健太ら数名の同志と共に京で三条実美や中山忠能らと接触して工作を行い、藩主豊範入京を実現させ、土佐藩は国事周旋や京都警衛の朝命を受けるに至った。
その後、三条実美の衛士となり京で活動します。
勤王党への弾圧がはじまると山田獄舎に捕えられ厳しい詮議の後、永牢処分を受けた孫三郎は獄中で病気となり三日後に病死しました。
墓所は先にもコメントした川原塚茂太郎の墓所の前の中須を西に少し歩いた右側の斜面下にあります。
天保8年(1837年)〜慶応2年(1866年)
土佐郡一宮村の土佐藩郷士小畑美穂の三男として誕生。
名を和。正路。
兄に維新後に男爵までなった小畑美稲がいます。
土佐勤王党が結成されると兄の孫次郎(美稲)と共に22番目に加盟しています。
孫三郎は河野万寿弥や弘瀬健太ら数名の同志と共に京で三条実美や中山忠能らと接触して工作を行い、藩主豊範入京を実現させ、土佐藩は国事周旋や京都警衛の朝命を受けるに至った。
その後、三条実美の衛士となり京で活動します。
勤王党への弾圧がはじまると山田獄舎に捕えられ厳しい詮議の後、永牢処分を受けた孫三郎は獄中で病気となり三日後に病死しました。
墓所は先にもコメントした川原塚茂太郎の墓所の前の中須を西に少し歩いた右側の斜面下にあります。
<平井 収二郎>ひらい しゅうじろう
天保6年(1835年)〜文久3年(1863年)
高知城下井口村の新留守居組平井伝八直澄の長男として誕生。
名を幾馬、徳助、志敏、義比。
雅号が隈山(わいざん)。
平井収二郎は坂本龍馬と同じ年で親交が深かった事で知られ、また妹の加尾は坂本龍馬の初恋の相手とも伝わり、龍馬の姉乙女とは一弦琴仲間でもあり、兄妹とも坂本家と親しい仲であったようです。
土佐勤王党には157番目に加盟し幹部として活躍します。
土佐の藩政改革を目論み、青蓮院宮から信頼を得ていた立場を利用して土佐藩に改革を迫る令旨を出させるように工作をした。
また、その他の幹部としての尊王攘夷活動が容堂の知るところとなり、
土佐で投獄されてしまいます。
武市半平太の必死の釈放嘆願も聞き入れられず
弘瀬健太、間崎哲馬と共に切腹。
獄中での爪書きの辞世『嗚呼悲しき哉』は藩吏により削り取られますが、明治維新後に加尾の手により復刻されています。
墓所は坂本龍馬の家族も眠る丹中山にあります。
天保6年(1835年)〜文久3年(1863年)
高知城下井口村の新留守居組平井伝八直澄の長男として誕生。
名を幾馬、徳助、志敏、義比。
雅号が隈山(わいざん)。
平井収二郎は坂本龍馬と同じ年で親交が深かった事で知られ、また妹の加尾は坂本龍馬の初恋の相手とも伝わり、龍馬の姉乙女とは一弦琴仲間でもあり、兄妹とも坂本家と親しい仲であったようです。
土佐勤王党には157番目に加盟し幹部として活躍します。
土佐の藩政改革を目論み、青蓮院宮から信頼を得ていた立場を利用して土佐藩に改革を迫る令旨を出させるように工作をした。
また、その他の幹部としての尊王攘夷活動が容堂の知るところとなり、
土佐で投獄されてしまいます。
武市半平太の必死の釈放嘆願も聞き入れられず
弘瀬健太、間崎哲馬と共に切腹。
獄中での爪書きの辞世『嗚呼悲しき哉』は藩吏により削り取られますが、明治維新後に加尾の手により復刻されています。
墓所は坂本龍馬の家族も眠る丹中山にあります。
<佐井 寅次郎>さい とらじろう
天保13年(1842年)〜明治4年(1871年)
幡多郡中村(現:四万十市)の岡村家に誕生。
後に佐井和之助の養子となりました。
名を忍吉、正敏。
土佐勤王党には153番目に加盟。
寅次郎は郡奉行下役となり郡治に尽力しており、それが認められて徒士目付として寅次郎は高知城下へ移っています。
慶応3年には山内容堂の側役となり、佐々木高行、中山佐衛士と共に四国、九州方面に出て諸藩の動きを探ったりています。
明治維新後は、山内容堂の推薦があり三条実美の側役を務めますが、
明治3年5月には病気の為に辞職して土佐へ帰国し、翌年に病死しています。
墓所は高知市の小高坂山にある三の丸霊園の山頂付近の開発を受けずに済んだ区域にあります。
天保13年(1842年)〜明治4年(1871年)
幡多郡中村(現:四万十市)の岡村家に誕生。
後に佐井和之助の養子となりました。
名を忍吉、正敏。
土佐勤王党には153番目に加盟。
寅次郎は郡奉行下役となり郡治に尽力しており、それが認められて徒士目付として寅次郎は高知城下へ移っています。
慶応3年には山内容堂の側役となり、佐々木高行、中山佐衛士と共に四国、九州方面に出て諸藩の動きを探ったりています。
明治維新後は、山内容堂の推薦があり三条実美の側役を務めますが、
明治3年5月には病気の為に辞職して土佐へ帰国し、翌年に病死しています。
墓所は高知市の小高坂山にある三の丸霊園の山頂付近の開発を受けずに済んだ区域にあります。
<柳井 健次>やない けんじ
天保13年(1842年)〜元治元年(1864年)
土佐郡小高坂村の家老深尾家家臣柳井俊蔵の二男として誕生。
名を友政。
土佐勤王党が結成されると6番目に加盟。
山内容堂警護のため結成された五十人組には伍長として参加しています。
土佐勤王党への弾圧が始まると健次は身の危険を感じ土佐を脱藩して長州へ向かい三田尻の招賢閣に入ります。
そのまま長州の浪人と行動をともにし過激派浪士で忠勇隊を結成し、隊長は同じく土佐脱藩の松山深蔵と真木外記(和泉の弟)が務めていました。
そして禁門の変に忠勇隊士として参戦し、堺町門の戦闘で彦根藩兵らと戦いで銃弾を受け自決しました。
墓所は高知市福井町(平井収二郎生誕地を少し西に向かう)の団地?の階段横のフェンス外側にあります。
天保13年(1842年)〜元治元年(1864年)
土佐郡小高坂村の家老深尾家家臣柳井俊蔵の二男として誕生。
名を友政。
土佐勤王党が結成されると6番目に加盟。
山内容堂警護のため結成された五十人組には伍長として参加しています。
土佐勤王党への弾圧が始まると健次は身の危険を感じ土佐を脱藩して長州へ向かい三田尻の招賢閣に入ります。
そのまま長州の浪人と行動をともにし過激派浪士で忠勇隊を結成し、隊長は同じく土佐脱藩の松山深蔵と真木外記(和泉の弟)が務めていました。
そして禁門の変に忠勇隊士として参戦し、堺町門の戦闘で彦根藩兵らと戦いで銃弾を受け自決しました。
墓所は高知市福井町(平井収二郎生誕地を少し西に向かう)の団地?の階段横のフェンス外側にあります。
兄<望月 清平>もちづき せいべえ
生没不明
弟<望月 亀弥太>もちづき かめやた
天保8年(1837年)〜元治元年(1864年)
土佐郡小高坂村西町に白札郷士望月団右衛門真澄の子として二人は生まれています。
清平は、坂本龍馬とは深い友情で結ばれている親友で、亀弥太は龍馬の紹介から勝海舟に入門し神戸海軍塾などで航海術を学ぶなど、兄弟揃って坂本龍馬とは縁がありました。
土佐勤王党には清平は20番目に加盟しています。
亀弥太も共に加盟したとのことですが、何らしかの理由により名簿から削除されたようです。
清平は龍馬が最期の時まで手紙のやりとりをしていたとゆうことからその信頼関係がうかがえます。
龍馬暗殺の後には新居留守組へ昇格しますが活躍などについてはよくわかっていないようです。
亀弥太は海軍塾を抜け北添佶麿と京を占拠するとゆう企てに参加するも新撰組の察知され、旅籠池田屋で会合中に新撰組の襲撃を受け亀弥太は新撰組隊士2名を斬り倒して包囲網を抜けるも力尽き加賀藩邸前で切腹。(池田屋事件)
二人の墓所は高知市横内の水源地山とゆう山にあります。
亀弥太の墓の後ろには説明板がたっていますが、ここに至るまでの道しるべなどは何もありませんので訪れる人も少ないのではと…
生没不明
弟<望月 亀弥太>もちづき かめやた
天保8年(1837年)〜元治元年(1864年)
土佐郡小高坂村西町に白札郷士望月団右衛門真澄の子として二人は生まれています。
清平は、坂本龍馬とは深い友情で結ばれている親友で、亀弥太は龍馬の紹介から勝海舟に入門し神戸海軍塾などで航海術を学ぶなど、兄弟揃って坂本龍馬とは縁がありました。
土佐勤王党には清平は20番目に加盟しています。
亀弥太も共に加盟したとのことですが、何らしかの理由により名簿から削除されたようです。
清平は龍馬が最期の時まで手紙のやりとりをしていたとゆうことからその信頼関係がうかがえます。
龍馬暗殺の後には新居留守組へ昇格しますが活躍などについてはよくわかっていないようです。
亀弥太は海軍塾を抜け北添佶麿と京を占拠するとゆう企てに参加するも新撰組の察知され、旅籠池田屋で会合中に新撰組の襲撃を受け亀弥太は新撰組隊士2名を斬り倒して包囲網を抜けるも力尽き加賀藩邸前で切腹。(池田屋事件)
二人の墓所は高知市横内の水源地山とゆう山にあります。
亀弥太の墓の後ろには説明板がたっていますが、ここに至るまでの道しるべなどは何もありませんので訪れる人も少ないのではと…
<矢野川 龍右衛門>やのかわ りゅうえもん
文政元年(1818年)〜慶応4年(1868年)
幡多郡布村の郷士矢野川利三郎の長男として誕生。
白札郷士矢野川喜平次の養子となる。
名を為雄。
土佐勤王党が結成されると89番目に加盟しています。
朝廷から幕府への攘夷督促の際は勅使三条実美の衛士として江戸へ随行し、その働きが三条実美の目にとなることろとなり、実美より紋付麻上下、和歌を賜ったそうです。
また弟の真左衛門と共に諸藩の志士と交流し、中国・九州方面に情報収集へ出るなど国事に奔走しました。
戊辰戦争の頃には龍右衛門は病気にかかってしまい、長男正雄と次男長正を代役として土佐藩兵として従軍して見事役割を果たしたそうです。
しかし龍右衛門は体調が回復する事もなく病没しています。
墓所は高知市の岩ヶ淵の山中にあります。
墓所までは道もなく斜面を登ると桜の木の側に奥様の墓とあります。
文政元年(1818年)〜慶応4年(1868年)
幡多郡布村の郷士矢野川利三郎の長男として誕生。
白札郷士矢野川喜平次の養子となる。
名を為雄。
土佐勤王党が結成されると89番目に加盟しています。
朝廷から幕府への攘夷督促の際は勅使三条実美の衛士として江戸へ随行し、その働きが三条実美の目にとなることろとなり、実美より紋付麻上下、和歌を賜ったそうです。
また弟の真左衛門と共に諸藩の志士と交流し、中国・九州方面に情報収集へ出るなど国事に奔走しました。
戊辰戦争の頃には龍右衛門は病気にかかってしまい、長男正雄と次男長正を代役として土佐藩兵として従軍して見事役割を果たしたそうです。
しかし龍右衛門は体調が回復する事もなく病没しています。
墓所は高知市の岩ヶ淵の山中にあります。
墓所までは道もなく斜面を登ると桜の木の側に奥様の墓とあります。
<伊藤 甲之助>いとう こうのすけ
弘化元年(1844)〜元治元年(1864)
高知城下浦戸町に郷士伊藤和兌の長男として誕生。
名を和義。
土佐勤王党には68番目に加盟しています。
朝廷が幕府に対して攘夷督促の勅使を東下させる事になった時には衛士として東下に随行し、後には姉小路公知卿や三条実美卿の護衛の任務につきました。
公武合体派の会津藩や薩摩藩のクーデターで、三条実美ら急進派公卿は都落ちすると甲之助はそのまま三条実美の衛士として随行して長州三田尻に入っています。
その頃土佐では土佐勤王党に対する弾圧がはじまり。
甲之助はそのまま残り脱藩の身となっています。
長州藩の浪人部隊忠勇隊が結成されると、甲之助は忠勇隊士として禁門の変に参加し甲之助は重症を負い、同志の大利鼎吉に介錯させ自刀しました。
墓所は高速道路を造る際に移動させられたようで、現在は高知市薊野の薊野霊園の頂上付近に綺麗に整備された一族のお墓と共に並んでいます。
弘化元年(1844)〜元治元年(1864)
高知城下浦戸町に郷士伊藤和兌の長男として誕生。
名を和義。
土佐勤王党には68番目に加盟しています。
朝廷が幕府に対して攘夷督促の勅使を東下させる事になった時には衛士として東下に随行し、後には姉小路公知卿や三条実美卿の護衛の任務につきました。
公武合体派の会津藩や薩摩藩のクーデターで、三条実美ら急進派公卿は都落ちすると甲之助はそのまま三条実美の衛士として随行して長州三田尻に入っています。
その頃土佐では土佐勤王党に対する弾圧がはじまり。
甲之助はそのまま残り脱藩の身となっています。
長州藩の浪人部隊忠勇隊が結成されると、甲之助は忠勇隊士として禁門の変に参加し甲之助は重症を負い、同志の大利鼎吉に介錯させ自刀しました。
墓所は高速道路を造る際に移動させられたようで、現在は高知市薊野の薊野霊園の頂上付近に綺麗に整備された一族のお墓と共に並んでいます。
<間崎 哲馬>まさき てつま
天保5年(1834)〜文久3年(1863)
高知城下下種崎町に開業医間崎総之亮則忠の子として誕生。
名を則弘。士毅。号は滄浪(そうろう)。
岩崎馬之助、細川潤次郎とならび『土佐の三奇童』と呼ばれた。
江戸で幕臣山岡鉄舟や志士の清河八郎ら諸藩の士と交流を持ち、3年の修行を終えて土佐へ帰国すると私塾を開き、吉村虎太郎、中岡慎太郎、能勢達太郎、沢村惣之丞ら多くの門弟が集まりました。
土佐勤王党には4番目に加盟し幹部として活躍しています。
土佐藩の藩風を一新しようと、土佐最高の権力者の元12代目土佐藩主山内豊資を味方に付ける事を考え、豊資を動かす為に青蓮院宮に土佐藩に藩政改革を迫る令旨の下賜を要請し、弘瀬健太と平井収二郎と共に青蓮院宮に拝謁して令旨を貰う事に成功しています。
しかし、この事が山内容堂の逆鱗に触れてしまい、郷士の身分で藩を動かした罪で、平井収二郎、弘瀬健太と共に切腹を命じられてしまいます。
天保5年(1834)〜文久3年(1863)
高知城下下種崎町に開業医間崎総之亮則忠の子として誕生。
名を則弘。士毅。号は滄浪(そうろう)。
岩崎馬之助、細川潤次郎とならび『土佐の三奇童』と呼ばれた。
江戸で幕臣山岡鉄舟や志士の清河八郎ら諸藩の士と交流を持ち、3年の修行を終えて土佐へ帰国すると私塾を開き、吉村虎太郎、中岡慎太郎、能勢達太郎、沢村惣之丞ら多くの門弟が集まりました。
土佐勤王党には4番目に加盟し幹部として活躍しています。
土佐藩の藩風を一新しようと、土佐最高の権力者の元12代目土佐藩主山内豊資を味方に付ける事を考え、豊資を動かす為に青蓮院宮に土佐藩に藩政改革を迫る令旨の下賜を要請し、弘瀬健太と平井収二郎と共に青蓮院宮に拝謁して令旨を貰う事に成功しています。
しかし、この事が山内容堂の逆鱗に触れてしまい、郷士の身分で藩を動かした罪で、平井収二郎、弘瀬健太と共に切腹を命じられてしまいます。
<吉井 之光>よしい ゆきみつ
天保6年(1835)〜明治元年(1868)
土佐郡久万村で誕生。
名を茂市、則行、顕蔵。
土佐勤王党には19番目に加盟しています。
慶応4年に山内家親族の旗本松本嘉兵衛の付き人となり、鳥羽伏見で戦闘がはじまると之光は主家の松本嘉兵衛に対して尊皇論を説いて入れられ伊豆国で活躍します。
のち箱根山付近で討幕軍の組織に参加します。
之光は沼津にいた幕府軍の討伐に参戦して活躍しています。
しかしここで小田原藩の裏切りにあってしまい、戦闘で重傷を負いながらも味方であるはずの小田原城まで行き、軍監三浦為一郎に面会を求めます。
しかし面会を拒否されて、この時初めて茂市は小田原藩の寝返りを知ったのでした。
そして之光は小田原城へ斬り込みをかけ敵の銃弾を受けて戦死しています。
墓所は高知市東久万の間崎哲馬の墓所入口の少し西側にあります。
天保6年(1835)〜明治元年(1868)
土佐郡久万村で誕生。
名を茂市、則行、顕蔵。
土佐勤王党には19番目に加盟しています。
慶応4年に山内家親族の旗本松本嘉兵衛の付き人となり、鳥羽伏見で戦闘がはじまると之光は主家の松本嘉兵衛に対して尊皇論を説いて入れられ伊豆国で活躍します。
のち箱根山付近で討幕軍の組織に参加します。
之光は沼津にいた幕府軍の討伐に参戦して活躍しています。
しかしここで小田原藩の裏切りにあってしまい、戦闘で重傷を負いながらも味方であるはずの小田原城まで行き、軍監三浦為一郎に面会を求めます。
しかし面会を拒否されて、この時初めて茂市は小田原藩の寝返りを知ったのでした。
そして之光は小田原城へ斬り込みをかけ敵の銃弾を受けて戦死しています。
墓所は高知市東久万の間崎哲馬の墓所入口の少し西側にあります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
土佐勤王党 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
土佐勤王党のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170661人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89524人