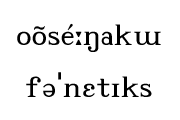現在、グルジア語を勉強しています。
大学時代に放出音の存在を知って以来、ずっと勉強したかった言語です。えらそうに「はじめまして」で書いたように、これまであまり個々の音の発音で苦労したことはありませんでした。(声調言語はちょっと苦手、というか不慣れ)
さて、放出音は、大学の時には、「声門を閉じた状態で横隔膜を上げ、閉じ込められた肺からの気流の密度が高まったところで、調音点を破裂させることによって、直接音とは違ったくぐもった音になる」と習いました。今、記憶に頼って書いたので正確な用語ではないと思いますが、大筋はあっていると思います。
ところが、トビリシ生まれのネイティブ講師の発音は、まるでクリックのような声門のあたりから、ポコとかペコみたいな音を伴います。また、講師の解説も、対立する非放出音は、中国語の有気音のように息をもらすが、放出音は全くださないか、強く短く一回だけと説明しています。すくなくとも、くぐもった不明瞭な音という印象はありません。弁別的特長は、有気と無気ということでよさそうなのですが、他のコーカサス諸語には、有気、無気、放出と3系統持つことばもあると聞いています。実際には何を持って放出音とみなしているのか、どなたか解説していただけないでしょうか。
また、韓国語の濃音とある程度似た音だと思っていたのですが(クリックみたいな音はのぞいて)、濃音のポイントは喉頭の瞬間的な緊張だと、wikipedia に書いてありました。また、日本語の促音(声門閉鎖音)と違って、拍を持たないそれだけで発音できる音だとも書いてありました。
では、実際のところ、3者の違いは何?区別して発音できるためにはどのような練習、注意があるの?これが質問です。
3つの音を持つ単一言語が(たぶん)ない以上、最小対としての厳密な定義はできないのかもしれませんが、どなたか賢察いただけるとありがたいです。
長々と失礼いたしました。
大学時代に放出音の存在を知って以来、ずっと勉強したかった言語です。えらそうに「はじめまして」で書いたように、これまであまり個々の音の発音で苦労したことはありませんでした。(声調言語はちょっと苦手、というか不慣れ)
さて、放出音は、大学の時には、「声門を閉じた状態で横隔膜を上げ、閉じ込められた肺からの気流の密度が高まったところで、調音点を破裂させることによって、直接音とは違ったくぐもった音になる」と習いました。今、記憶に頼って書いたので正確な用語ではないと思いますが、大筋はあっていると思います。
ところが、トビリシ生まれのネイティブ講師の発音は、まるでクリックのような声門のあたりから、ポコとかペコみたいな音を伴います。また、講師の解説も、対立する非放出音は、中国語の有気音のように息をもらすが、放出音は全くださないか、強く短く一回だけと説明しています。すくなくとも、くぐもった不明瞭な音という印象はありません。弁別的特長は、有気と無気ということでよさそうなのですが、他のコーカサス諸語には、有気、無気、放出と3系統持つことばもあると聞いています。実際には何を持って放出音とみなしているのか、どなたか解説していただけないでしょうか。
また、韓国語の濃音とある程度似た音だと思っていたのですが(クリックみたいな音はのぞいて)、濃音のポイントは喉頭の瞬間的な緊張だと、wikipedia に書いてありました。また、日本語の促音(声門閉鎖音)と違って、拍を持たないそれだけで発音できる音だとも書いてありました。
では、実際のところ、3者の違いは何?区別して発音できるためにはどのような練習、注意があるの?これが質問です。
3つの音を持つ単一言語が(たぶん)ない以上、最小対としての厳密な定義はできないのかもしれませんが、どなたか賢察いただけるとありがたいです。
長々と失礼いたしました。
|
|
|
|
コメント(13)
放出音の定義が、私の知るものとはちょっと異なるように思えます。
挙げていただいた定義ですと、「横隔膜を上げることによって、閉じた声門と肺との間の気圧を上げる」ことになっていますが、私の理解では「声門を閉じた状態で声帯を持ち上げることによって、声門と調音点との間の気圧を上げて発する音」です。これは、下記の Wikipedia の定義とも一致します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%87%BA%E9%9F%B3
男性が発音すると、調音の瞬間に喉仏が持ち上がるのが分かるはずです。もし、ネイティブの先生が男性でしたら、喉に注目してみてください。
調音の瞬間には声門が閉じている(=肺からの気流がない)状態ですので、原理的に有気音にはなり得ないと思います。テキストベースなので判断が難しいですが、「ポコ」という音は、放出音の調音完了後に声門を開放する音かと思われます。
私はグルジア語を知らないのであまり断定的なことは言えませんが、有気・無気が弁別的特徴であるというよりは、上記のように調音の仕方そのものが異なりますので、肺からの呼気を用いる非放出音と、(呼気は用いず)声門・調音点間の圧変化による弱い気流を用いる放出音との対立だと考えた方がよろしいかと。
私も一応調音できますので、ご希望がある場合はメッセージなど頂ければ、少々恥ずかしいですが私の発音をお聞かせすることもできるかと思います。
なお、上記 Wikipedia にも記載がありますが、似た発音記号で表記されることはあるものの、朝鮮語/韓国語の濃音とは別個の発音です。
挙げていただいた定義ですと、「横隔膜を上げることによって、閉じた声門と肺との間の気圧を上げる」ことになっていますが、私の理解では「声門を閉じた状態で声帯を持ち上げることによって、声門と調音点との間の気圧を上げて発する音」です。これは、下記の Wikipedia の定義とも一致します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%87%BA%E9%9F%B3
男性が発音すると、調音の瞬間に喉仏が持ち上がるのが分かるはずです。もし、ネイティブの先生が男性でしたら、喉に注目してみてください。
調音の瞬間には声門が閉じている(=肺からの気流がない)状態ですので、原理的に有気音にはなり得ないと思います。テキストベースなので判断が難しいですが、「ポコ」という音は、放出音の調音完了後に声門を開放する音かと思われます。
私はグルジア語を知らないのであまり断定的なことは言えませんが、有気・無気が弁別的特徴であるというよりは、上記のように調音の仕方そのものが異なりますので、肺からの呼気を用いる非放出音と、(呼気は用いず)声門・調音点間の圧変化による弱い気流を用いる放出音との対立だと考えた方がよろしいかと。
私も一応調音できますので、ご希望がある場合はメッセージなど頂ければ、少々恥ずかしいですが私の発音をお聞かせすることもできるかと思います。
なお、上記 Wikipedia にも記載がありますが、似た発音記号で表記されることはあるものの、朝鮮語/韓国語の濃音とは別個の発音です。
LILIN さん、書き込みありがとうございます。
今は亡き、チェコ語の千野先生は確かに横隔膜と言っていたのですが、声帯だったんですね。ただどちらにしても、わたしは持ち上げるやり方がわかりません。
グルジア語の先生は残念ながら、女性です。また、トビリシ生まれのネイティブですが、言語学や音声学のトレーニングは受けていないように思います。そのため、解説が時としてあいまいで本人の感覚によることがあるため、不正確になることは否めません。ただ、彼女は講座の間、非放出音の呼気を強調することが多いですね。
わたしも、横隔膜という理解は間違っていたにしても、くぐもった非呼気の音を出すことはできます。先日グルジアにも言ってきたのですが、わたしのイメージしていた放出音はほとんど聞かなかったので、今回の質問となりました。
本題とは外れますが、今もうひとつ困っているのは pharyngeal stop の放出音もあることで、先に書いたように声帯近辺のコントロールが意識してはできていないので、咽頭と声帯を同時に使うことは現時点で不可能なんです。のどの奥の方だと思ってしまうと母音自体が後舌化する上に、k の放出音まで引きずられて、後ろよりの調音になってしまいます。
チェコ語のハーチェク付きのRもチベット語のそり舌Rの無声音もできるのに、咽頭と声帯は不得手なのかなぁと若干がっかりしています。
今は亡き、チェコ語の千野先生は確かに横隔膜と言っていたのですが、声帯だったんですね。ただどちらにしても、わたしは持ち上げるやり方がわかりません。
グルジア語の先生は残念ながら、女性です。また、トビリシ生まれのネイティブですが、言語学や音声学のトレーニングは受けていないように思います。そのため、解説が時としてあいまいで本人の感覚によることがあるため、不正確になることは否めません。ただ、彼女は講座の間、非放出音の呼気を強調することが多いですね。
わたしも、横隔膜という理解は間違っていたにしても、くぐもった非呼気の音を出すことはできます。先日グルジアにも言ってきたのですが、わたしのイメージしていた放出音はほとんど聞かなかったので、今回の質問となりました。
本題とは外れますが、今もうひとつ困っているのは pharyngeal stop の放出音もあることで、先に書いたように声帯近辺のコントロールが意識してはできていないので、咽頭と声帯を同時に使うことは現時点で不可能なんです。のどの奥の方だと思ってしまうと母音自体が後舌化する上に、k の放出音まで引きずられて、後ろよりの調音になってしまいます。
チェコ語のハーチェク付きのRもチベット語のそり舌Rの無声音もできるのに、咽頭と声帯は不得手なのかなぁと若干がっかりしています。
先ほど、そちらのプロフィールを拝見しました。年齢的にも近いようですし、千野先生に習われたことがあるということは、今はなきあのキャンパスのどこかで、お互い気付かずにすれ違っていたかも知れませんね。
私の放出音(ejective)は、学生時代に優秀な同期(現在母校で助教授になっている)から習ったのですが、声門付近に意識を集中して練習していたところ、何ヶ月か経ったある日、突然できるようになりました。
このような声門の使い方をする音が日本語にない関係上、ピンとくるような説明がどうしてもできずもどかしいのですが、私の場合はまず glottal stop を調音した際の声門閉鎖を維持しながら、喉仏のあたりに軽く指を添えるようにして、声帯の上下を意識して練習しました。恐らくすでにご自覚かとは存じますが、調音点が後ろ寄りだと声門に近くて調音の内省がしにくいので、最初のうちは両唇音の [p'] で練習なさるのがよろしいかと存じます。
声帯の上下自体は、ご存じのように声の上げ下げ(歌の音程、声調言語の声調等)に連動していますので、さほど苦労せずできるのではないでしょうか。あとは肺からの呼気ではなく、閉じた声門で内圧・気流を制御する感覚が体得できれば、恐らく私同様、ある日突然できるようになると思います。私の場合は、放出音ができるようになると同時に、ちょうど逆の原理で調音する入破音(implosive)もできるようになりました。
できるようになった日の、狐につままれたような感覚と、そして嬉しさは、今でも鮮明に覚えています。
そのできるようになるまでがもどかしいのですが、どうか諦めずに練習を継続なさって下さい。
私の放出音(ejective)は、学生時代に優秀な同期(現在母校で助教授になっている)から習ったのですが、声門付近に意識を集中して練習していたところ、何ヶ月か経ったある日、突然できるようになりました。
このような声門の使い方をする音が日本語にない関係上、ピンとくるような説明がどうしてもできずもどかしいのですが、私の場合はまず glottal stop を調音した際の声門閉鎖を維持しながら、喉仏のあたりに軽く指を添えるようにして、声帯の上下を意識して練習しました。恐らくすでにご自覚かとは存じますが、調音点が後ろ寄りだと声門に近くて調音の内省がしにくいので、最初のうちは両唇音の [p'] で練習なさるのがよろしいかと存じます。
声帯の上下自体は、ご存じのように声の上げ下げ(歌の音程、声調言語の声調等)に連動していますので、さほど苦労せずできるのではないでしょうか。あとは肺からの呼気ではなく、閉じた声門で内圧・気流を制御する感覚が体得できれば、恐らく私同様、ある日突然できるようになると思います。私の場合は、放出音ができるようになると同時に、ちょうど逆の原理で調音する入破音(implosive)もできるようになりました。
できるようになった日の、狐につままれたような感覚と、そして嬉しさは、今でも鮮明に覚えています。
そのできるようになるまでがもどかしいのですが、どうか諦めずに練習を継続なさって下さい。
千野先生ご自身、放出音の習得には苦労されたようで、著書などを読むと、できるようになったのは外語を退官される数年前だったように思われます。
「横隔膜を上げる」という説明をされたのだとすれば、それによって声門下圧が上がりますので、それで喉頭全体を押し上げるという理屈だったのかも知れません。
しかし、喉頭の上下動は、筋肉運動によって行うのが本来の姿です。最も簡単に実感するには、のとぼとけを指で触りながら、つばを飲み込んでみると良いでしょう。はっきりと持ち上がるのが分かると思います。
もちろん、放出音の時につばを飲み込むわけではないので、それによって喉頭の上下動の感覚を掴み、つばを飲み込むことなしに喉頭を上下させる練習を積めばいいのではないでしょうか。
「横隔膜を上げる」という説明をされたのだとすれば、それによって声門下圧が上がりますので、それで喉頭全体を押し上げるという理屈だったのかも知れません。
しかし、喉頭の上下動は、筋肉運動によって行うのが本来の姿です。最も簡単に実感するには、のとぼとけを指で触りながら、つばを飲み込んでみると良いでしょう。はっきりと持ち上がるのが分かると思います。
もちろん、放出音の時につばを飲み込むわけではないので、それによって喉頭の上下動の感覚を掴み、つばを飲み込むことなしに喉頭を上下させる練習を積めばいいのではないでしょうか。
こんにちは。 2: 似非英国紳士さんのコメントの本題に外れているというpharyngeal stopに関連してコメントします。
Catfordの_A Practical Introduction to Phonetics, 2nd Ed._の5章7節(96ページ)では、咽頭(下部の喉頭蓋)音の閉鎖音は、「Chechen語などのカフカスの言語のいくつかでもみられるようだ」ということが書いてあります。
Chechen語では咽頭閉鎖音の放出音があるということでしょうか。放出音という気流機構のために閉じ込められる空気のスペースが非常に狭いですね。
調音点が咽頭の場合、前後の母音が強く咽頭音化するのはさけられないと思います。
それとも、似非英国紳士さんが書かれたのは、調音点が咽頭でないどこか別の放出音の、咽頭音化した(調音点での狭めに次ぐ狭めが咽頭にある)ものでしょうか。この場合も、前後の母音が咽頭音化するのはさけられないと思います。
Catfordの_A Practical Introduction to Phonetics, 2nd Ed._の5章7節(96ページ)では、咽頭(下部の喉頭蓋)音の閉鎖音は、「Chechen語などのカフカスの言語のいくつかでもみられるようだ」ということが書いてあります。
Chechen語では咽頭閉鎖音の放出音があるということでしょうか。放出音という気流機構のために閉じ込められる空気のスペースが非常に狭いですね。
調音点が咽頭の場合、前後の母音が強く咽頭音化するのはさけられないと思います。
それとも、似非英国紳士さんが書かれたのは、調音点が咽頭でないどこか別の放出音の、咽頭音化した(調音点での狭めに次ぐ狭めが咽頭にある)ものでしょうか。この場合も、前後の母音が咽頭音化するのはさけられないと思います。
一つ、気づいたことがあるので追加します。
あまり正調のやり方ではないかも知れませんが、今 PC の前で少し自分の放出音を内省しながら試してみたところ、顔を上向けた状態から頷くような感じで顎を引きながら発音すると、多少は放出音が出やすいようです。このようにして喉を縮めながら調音することによって、声門から調音点までの空間を圧縮する(=その部分の内圧を強制的に高くする)ことになりますから、声門と調音点の閉鎖がきちんとできていれば、これである程度声門を持ち上げるのと同様な効果を得られるのではないかと考えます。
なお、逆に顔を俯けた状態から上向けつつ発音すると、ひどく放出音が出にくくなり(少なくとも私はまったく出せなくなる)、逆に入破音が出やすくなるようです。
単なる素人考えの思いつきで恐縮ですが、よろしければお試しを。
あまり正調のやり方ではないかも知れませんが、今 PC の前で少し自分の放出音を内省しながら試してみたところ、顔を上向けた状態から頷くような感じで顎を引きながら発音すると、多少は放出音が出やすいようです。このようにして喉を縮めながら調音することによって、声門から調音点までの空間を圧縮する(=その部分の内圧を強制的に高くする)ことになりますから、声門と調音点の閉鎖がきちんとできていれば、これである程度声門を持ち上げるのと同様な効果を得られるのではないかと考えます。
なお、逆に顔を俯けた状態から上向けつつ発音すると、ひどく放出音が出にくくなり(少なくとも私はまったく出せなくなる)、逆に入破音が出やすくなるようです。
単なる素人考えの思いつきで恐縮ですが、よろしければお試しを。
皆様、いろいろとご意見アドバイスありがとうございます。
昨日はグルジア語の講座があったので、喉仏を押さえながら、つばを飲み込んで、上下動を意識する方法を学友に話していたら、グルジア人の先生が、「わたしは女性だけど、喉仏がある」と話しかけてきました。一同でグルジア語は咽頭、喉頭などよく使うから女性でも発達するのかと笑い話になりました。
グルジア語の困ったところはこれらの単発でもむずかしい発音が、母音なしで連続するところで、平気で3個以上の子音が連続して現れます。ですので、単音で練習して身につけないと2年たっても文章をスムーズに発音できないわたし(たち)のようになってしまいます。
わたしのお気に入りの単語の一つは、「私は話す」という意味の vlap'alak'ob で、音の並びのせいか放出音が出やすい気がしています。
昨日はグルジア語の講座があったので、喉仏を押さえながら、つばを飲み込んで、上下動を意識する方法を学友に話していたら、グルジア人の先生が、「わたしは女性だけど、喉仏がある」と話しかけてきました。一同でグルジア語は咽頭、喉頭などよく使うから女性でも発達するのかと笑い話になりました。
グルジア語の困ったところはこれらの単発でもむずかしい発音が、母音なしで連続するところで、平気で3個以上の子音が連続して現れます。ですので、単音で練習して身につけないと2年たっても文章をスムーズに発音できないわたし(たち)のようになってしまいます。
わたしのお気に入りの単語の一つは、「私は話す」という意味の vlap'alak'ob で、音の並びのせいか放出音が出やすい気がしています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
音声学 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-