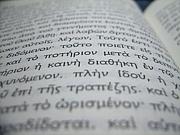日本語聖書勉強会の準備をしていたとき、次のような箇所に当たりました。
“Πολλοί ουν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν επίστευσαν εις αυτόν· τινές δε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπαν αυτοίς α εποίησεν Ιησούς.”(Κατά Ιωάννην, 11.45-6)
これを読んだとき、“Πολλοί ουν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν”を、「ユダヤ人の中で、マリアのところに来てキリストの行ったことを目の当たりにしたたくさんの人々」と読んでいました。なぜなら、ギリシア語は同格で挟み込む形式が多いので、“Πολλοί”と“οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν”が同格だと思ったのです。
それで私は、イエス様のことを信じた人たちが、なぜ敵であるファリサイ派のところへ報告に行ってしまったのか、という質問を書きました。
ところが、『新共同訳聖書』を見ると、この箇所は次のように訳されているのです。
「マリアのところに来て、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くは、イエスを信じた。しかし、中には、ファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。」(「ヨハネによる福音書」11章45〜46節)
この訳では、イエス様の奇蹟を見たあと、信じた人たちと、信じないでファリサイ派のもとへ通報しに行った人たちとがいた、という意味になっていて、私の質問は意味をなさなくなってしまいました。それで、私は質問を書きかえるはめになったのです。
『新共同訳』の解釈では、“Πολλοί”は“εκ των Ιουδαίων οι ...”に修飾されているかのように解釈されています。私の考えでは、こういう場合、“εκ των Ιουδαίων των ελθόντων προς την Μαριάμ και θεασαμένων α εποίησεν”としなければならないのではないかと思うのですが、まあ、以上のような訳だったわけです。
この訳が気になって、他の訳も見てみました。なんせ、私の質問を無にした訳だったのですから、多少恨みがあります。(笑)
まず、『新改訳聖書』です。
「そこで、マリヤのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人が、イエスを信じた。しかし、そのうちの幾人かは、パリサイ人たちのところへ行って、イエスのなさったことを告げた。」(「ヨハネの福音書」11章45〜46節)
これは、私が読んで解釈したのと同じ解釈です。うれしいことです。
次に、現代ギリシア語訳です。
“Πολλοί από τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν έλθει εις την Μαρίαν και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, επίστεψαν σ΄ αυτόν· αλλά μερικοί απ΄ αυτούς επήγαν εις τους Φαρισαίους και τους είπαν τι είχε κάνει ο Ιησούς.”(Κατά Ιωάννην, 11.45-6)
この訳では、“Ιουδαίους”と“οι οποίοι ...”の間にコンマがあるので、私の解釈と同じく、“Πολλοί”と“οι οποίοι είχαν έλθει εις την Μαρίαν και είδαν τι έκανε ο Ιησούς”とを同格で扱っていることが明白です。2対1。
次に、欽定訳聖書です。
“Then many of the Jews which come to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him. But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.”(John, 11:45-6)
これもやはり、私と同じ解釈です。3対1!
次に、欽定訳の次にたくさん読まれているという、NIV(New International Version)です。
“Therefore many of the Jews who had come to visit Mary, and had seen what Jesus did, put their faith in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done.”(John, 11:45-6)
これも私の解釈と同じ。4対1!
もういいでしょう。このぐらいにしておきます。
問題は、なぜ『新共同訳』で、上のような訳をしたのかということです。しかし、これについて私が判断する能力はありません。この訳は理解できない、というしかありません。
“Πολλοί ουν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν επίστευσαν εις αυτόν· τινές δε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπαν αυτοίς α εποίησεν Ιησούς.”(Κατά Ιωάννην, 11.45-6)
これを読んだとき、“Πολλοί ουν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν”を、「ユダヤ人の中で、マリアのところに来てキリストの行ったことを目の当たりにしたたくさんの人々」と読んでいました。なぜなら、ギリシア語は同格で挟み込む形式が多いので、“Πολλοί”と“οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν”が同格だと思ったのです。
それで私は、イエス様のことを信じた人たちが、なぜ敵であるファリサイ派のところへ報告に行ってしまったのか、という質問を書きました。
ところが、『新共同訳聖書』を見ると、この箇所は次のように訳されているのです。
「マリアのところに来て、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くは、イエスを信じた。しかし、中には、ファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。」(「ヨハネによる福音書」11章45〜46節)
この訳では、イエス様の奇蹟を見たあと、信じた人たちと、信じないでファリサイ派のもとへ通報しに行った人たちとがいた、という意味になっていて、私の質問は意味をなさなくなってしまいました。それで、私は質問を書きかえるはめになったのです。
『新共同訳』の解釈では、“Πολλοί”は“εκ των Ιουδαίων οι ...”に修飾されているかのように解釈されています。私の考えでは、こういう場合、“εκ των Ιουδαίων των ελθόντων προς την Μαριάμ και θεασαμένων α εποίησεν”としなければならないのではないかと思うのですが、まあ、以上のような訳だったわけです。
この訳が気になって、他の訳も見てみました。なんせ、私の質問を無にした訳だったのですから、多少恨みがあります。(笑)
まず、『新改訳聖書』です。
「そこで、マリヤのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人が、イエスを信じた。しかし、そのうちの幾人かは、パリサイ人たちのところへ行って、イエスのなさったことを告げた。」(「ヨハネの福音書」11章45〜46節)
これは、私が読んで解釈したのと同じ解釈です。うれしいことです。
次に、現代ギリシア語訳です。
“Πολλοί από τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν έλθει εις την Μαρίαν και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, επίστεψαν σ΄ αυτόν· αλλά μερικοί απ΄ αυτούς επήγαν εις τους Φαρισαίους και τους είπαν τι είχε κάνει ο Ιησούς.”(Κατά Ιωάννην, 11.45-6)
この訳では、“Ιουδαίους”と“οι οποίοι ...”の間にコンマがあるので、私の解釈と同じく、“Πολλοί”と“οι οποίοι είχαν έλθει εις την Μαρίαν και είδαν τι έκανε ο Ιησούς”とを同格で扱っていることが明白です。2対1。
次に、欽定訳聖書です。
“Then many of the Jews which come to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him. But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.”(John, 11:45-6)
これもやはり、私と同じ解釈です。3対1!
次に、欽定訳の次にたくさん読まれているという、NIV(New International Version)です。
“Therefore many of the Jews who had come to visit Mary, and had seen what Jesus did, put their faith in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done.”(John, 11:45-6)
これも私の解釈と同じ。4対1!
もういいでしょう。このぐらいにしておきます。
問題は、なぜ『新共同訳』で、上のような訳をしたのかということです。しかし、これについて私が判断する能力はありません。この訳は理解できない、というしかありません。
|
|
|
|
コメント(19)
私も45節に関しては、ijustat様の読み方に全面的に賛成です。
ところで、
>イエス様のことを信じた人たちが、なぜ敵であるファリサイ派のところへ報告に行ってしまったのか
に関してですが、46節目の“τινές ... εξ αυτών”の“αυτών”が「イエス様のことを信じた人たち」を指していると考えると、たしかにそうした疑問が浮かんで来ると思います。
ですが、私としては、この“αυτών”が単に“των Ιουδαίων”を指していると考えて、「ユダヤ人の中にはファリサイ派のところへ報告に行く者たちもいた」と解釈すれば、先の疑問は解消するように思うのですが、いかがでしょうか?
もちろん、その場合に“τινές ... εξ αυτών”(ユダヤ人たちのうちの或る者たち)と呼ばれている人たちも、「報告した」というからには、当然「マリアのところに来てキリストの行ったことを目の当たりにした」はずですが、だからといって、新共同訳のように45節の“οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν”を“των Ιουδαίων”と同格に読むのは、いささか訳しすぎではないかと思います。
ところで、
>イエス様のことを信じた人たちが、なぜ敵であるファリサイ派のところへ報告に行ってしまったのか
に関してですが、46節目の“τινές ... εξ αυτών”の“αυτών”が「イエス様のことを信じた人たち」を指していると考えると、たしかにそうした疑問が浮かんで来ると思います。
ですが、私としては、この“αυτών”が単に“των Ιουδαίων”を指していると考えて、「ユダヤ人の中にはファリサイ派のところへ報告に行く者たちもいた」と解釈すれば、先の疑問は解消するように思うのですが、いかがでしょうか?
もちろん、その場合に“τινές ... εξ αυτών”(ユダヤ人たちのうちの或る者たち)と呼ばれている人たちも、「報告した」というからには、当然「マリアのところに来てキリストの行ったことを目の当たりにした」はずですが、だからといって、新共同訳のように45節の“οι ελθόντες προς την Μαριάμ και θεασάμενοι α εποίησεν”を“των Ιουδαίων”と同格に読むのは、いささか訳しすぎではないかと思います。
>iktysさま
実は、ご指摘の“τινές ... εξ αυτών”の“αυτών”が“των Ιουδαίων”を指している可能性は、疑念として心の片隅にありました。実際、“τινές”に“δε”が付いているのが、その疑念を感じさせる部分ではあります。また、“Πολλοί ... εκ των Ιουδαίων”と“τινές ... εξ αυτών”が形式的に対をなしているという点も、疑念を感じさせる部分でした。
ただ、私は単純に読んで、前文の名詞句にある中心の語が“Πολλοί”だったので、“τινές ... εξ αυτών”の“αυτών”をそこにつなげて解釈してみたのです。もちろん、素人の読みですので、ちょっとした一撃でポシャってしまう可能性は、いつでもあります。(笑)
ちなみに、ヨハネの福音書は統語的に不明瞭な部分が点在するので、明瞭に解釈しようと思うと、とても骨が折れます。
実は、ご指摘の“τινές ... εξ αυτών”の“αυτών”が“των Ιουδαίων”を指している可能性は、疑念として心の片隅にありました。実際、“τινές”に“δε”が付いているのが、その疑念を感じさせる部分ではあります。また、“Πολλοί ... εκ των Ιουδαίων”と“τινές ... εξ αυτών”が形式的に対をなしているという点も、疑念を感じさせる部分でした。
ただ、私は単純に読んで、前文の名詞句にある中心の語が“Πολλοί”だったので、“τινές ... εξ αυτών”の“αυτών”をそこにつなげて解釈してみたのです。もちろん、素人の読みですので、ちょっとした一撃でポシャってしまう可能性は、いつでもあります。(笑)
ちなみに、ヨハネの福音書は統語的に不明瞭な部分が点在するので、明瞭に解釈しようと思うと、とても骨が折れます。
手元に和英対照新約聖書があるのですが、
和文は新共同訳で、英文はToday's English Versionw (American Bible Society)です。
ここでは、
Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they believed in him.
But some of them returned to the Pharisees and told them to what Jesus had done.
と英訳されています。
ここで、注意すべき重要なことがあります。
それは、新約聖書に限らず古代の聖典は、写本によって伝承され続けたため、現代的な意味での唯一の正しい原典が存在しないということを、知っておく必要があります。
つまり、写本の数だけ異なった原典があるに等しいということです。
特に、新約聖書のギリシャ語写本は、連続書法(スクリプトゥオ・コンティヌア)によって書かれているそうで、ほとんどの部分に句読点がなく、単語の間のスペースすら無いそうです。
したがって、この部分の解釈の問題は、翻訳の問題では無く、どの系統の写本を原典として使用し、その写本にどう句読点やスペースを入れるかという問題であることを認識した上で、日本語における意味を考えることが必要だと思います。
和文は新共同訳で、英文はToday's English Versionw (American Bible Society)です。
ここでは、
Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they believed in him.
But some of them returned to the Pharisees and told them to what Jesus had done.
と英訳されています。
ここで、注意すべき重要なことがあります。
それは、新約聖書に限らず古代の聖典は、写本によって伝承され続けたため、現代的な意味での唯一の正しい原典が存在しないということを、知っておく必要があります。
つまり、写本の数だけ異なった原典があるに等しいということです。
特に、新約聖書のギリシャ語写本は、連続書法(スクリプトゥオ・コンティヌア)によって書かれているそうで、ほとんどの部分に句読点がなく、単語の間のスペースすら無いそうです。
したがって、この部分の解釈の問題は、翻訳の問題では無く、どの系統の写本を原典として使用し、その写本にどう句読点やスペースを入れるかという問題であることを認識した上で、日本語における意味を考えることが必要だと思います。
>☆‥ゝさま
書き込みありがとうございます。
実は、「注意すべき重要なこと」とおっしゃった内容は、たしかに重要ではありますが、この箇所については、該当しないのです。なぜなら、この箇所に関してだけ言えば、Textus Receptus を含め、現在存在している校訂本に、意味を変えるほどの異同がないからです。
Nestle-Alandでは“α εποίησεν”しかないところに Textus Receptus では“α εποίησεν ο Ιησούς”となっていますが、Nestle-Alandの“α εποίησεν”は“ο Ιησούς”を意味上の主語としているので、結局は解釈に違いをもたらしません。
また、Textus Receptus の方が読点をたくさん打っていますが、それは単にテキストを読みやすくしただけで、解釈の違いをもたらすほどのものではありません。
したがって、「この部分の解釈の問題は、翻訳の問題では無く、どの系統の写本を原典として使用し、その写本にどう句読点やスペースを入れるかという問題であることを認識した上で、日本語における意味を考えることが必要だ」とおっしゃったのは、原則としては正しいけれども、この箇所に関して言えば、残念ながら、全く推測によっておっしゃったことで、事実に即して発言された内容ではありません。
せっかく書いてくださった内容に水を差すようで申し訳ありませんでしたが、これに懲りず、これからも思ったことを書き込んでいただければ幸いです。
書き込みありがとうございます。
実は、「注意すべき重要なこと」とおっしゃった内容は、たしかに重要ではありますが、この箇所については、該当しないのです。なぜなら、この箇所に関してだけ言えば、Textus Receptus を含め、現在存在している校訂本に、意味を変えるほどの異同がないからです。
Nestle-Alandでは“α εποίησεν”しかないところに Textus Receptus では“α εποίησεν ο Ιησούς”となっていますが、Nestle-Alandの“α εποίησεν”は“ο Ιησούς”を意味上の主語としているので、結局は解釈に違いをもたらしません。
また、Textus Receptus の方が読点をたくさん打っていますが、それは単にテキストを読みやすくしただけで、解釈の違いをもたらすほどのものではありません。
したがって、「この部分の解釈の問題は、翻訳の問題では無く、どの系統の写本を原典として使用し、その写本にどう句読点やスペースを入れるかという問題であることを認識した上で、日本語における意味を考えることが必要だ」とおっしゃったのは、原則としては正しいけれども、この箇所に関して言えば、残念ながら、全く推測によっておっしゃったことで、事実に即して発言された内容ではありません。
せっかく書いてくださった内容に水を差すようで申し訳ありませんでしたが、これに懲りず、これからも思ったことを書き込んでいただければ幸いです。
ijustat さま。
そうですか、もうしわけありません。
イエスの言行録として、スタートとして共同訳の福音書を読み始めてから、上記の和英対訳を読んだところ、英語からストレートに意味をとって読むと、和訳とかなり意味が異なるので、結局英語とギリシャ語の対訳を読み始めるしかないかと思って、ギリシャ語原典に関する調べを進めていたら、ほかの教典の世界と同様の問題があることを知り、はてさてどの本を当面の指針にしようかと思っていたのです。
ふと、今日思いついてコミュを検索したところ、このコミュをみつけ、挨拶がわりに、ちょっと書き込ませてもらいました。
議論の次元が見えないのであれば、本来は、質問形式で書くべきだったのですが、当面の自分の課題なので、断定文になったのは反省しています。
そうですか、もうしわけありません。
イエスの言行録として、スタートとして共同訳の福音書を読み始めてから、上記の和英対訳を読んだところ、英語からストレートに意味をとって読むと、和訳とかなり意味が異なるので、結局英語とギリシャ語の対訳を読み始めるしかないかと思って、ギリシャ語原典に関する調べを進めていたら、ほかの教典の世界と同様の問題があることを知り、はてさてどの本を当面の指針にしようかと思っていたのです。
ふと、今日思いついてコミュを検索したところ、このコミュをみつけ、挨拶がわりに、ちょっと書き込ませてもらいました。
議論の次元が見えないのであれば、本来は、質問形式で書くべきだったのですが、当面の自分の課題なので、断定文になったのは反省しています。
>☆‥ゝさま
こちらこそ、ストレートに書いてしまって失礼だったかと反省しています。^^;
聖書の訳による違いは、原典の異同によるものというよりは、解釈の問題であることがほとんどだと思います。多義語が用いられている文脈がどちらにも取れてしまったり、この箇所のように、代名詞の指しているものが何なのか明らかでなかったり、いろいろな問題があります。
私のような初心者は、文脈を見て最初に思いついた意味に左右されてしまいがちですが、2千年近い研究の背景があるわけですから、その解釈に関する議論は、たいへんな深さを持っていると言えます。
ギリシア語の原典としていちばん売れているのは、Nestle-Aland 版のようですが、世界で訳されている聖書の原本として用いられることが多いのは、このコミュニティのホームページの写真にもある、United Bible Societies 版のようです。
Nestle-Aland 版は、英語との対訳と、ラテン語との対訳があります。また、United Bible Societies 版は、希英辞典が巻末についていて、便利です。
ちなみに、好みの問題になりますが、活字の美しさという点では、Nestle-Aland 版が評価が高いようですが、目への優しさという点では、校訂注のあまり煩雑でない、United Bible Societies 版の方がいいような気がします。両者には異同があるのですが、それは微々たるものだといえます。新共同訳は、後者を忠実に訳しています。
Textus Receptus は、校訂注が全く付いていないので、テキストの異同について悩むことなく読めるかもしれませんが、現在訳されている聖書にはほとんど用いられていないようだし、時には話の筋に微妙な影響を与える異同もあるので、このテキストをお読みになるなら、それを考慮に入れての上で使用されるとよいと思います。
私たち一般人が原典を読むとき、写本を読むことは滅多になく、普通は校訂本を読むことになります。写本が気になる場合は、Nestle-Aland 版を見れば、脚注として校訂注がびっしりと記されています。私にはそこに記された記号が何を表すのか、ほとんどわかりませんが、そこに挙げられた異動を見ていると、いろいろと考えさせられます。
私はテキスト批評にはあまり関心がないのですが、原典を読むようになると、テキストの異同について無視しているわけにはいかず、その概要はいつも念頭においている必要が出てきます。それでというわけではないけれど、現在4種類の違うテキストを持っています。しかし、どれが優れているかというのは私には分からないことなので、どのテキストも同等に、大切にしています。
こちらこそ、ストレートに書いてしまって失礼だったかと反省しています。^^;
聖書の訳による違いは、原典の異同によるものというよりは、解釈の問題であることがほとんどだと思います。多義語が用いられている文脈がどちらにも取れてしまったり、この箇所のように、代名詞の指しているものが何なのか明らかでなかったり、いろいろな問題があります。
私のような初心者は、文脈を見て最初に思いついた意味に左右されてしまいがちですが、2千年近い研究の背景があるわけですから、その解釈に関する議論は、たいへんな深さを持っていると言えます。
ギリシア語の原典としていちばん売れているのは、Nestle-Aland 版のようですが、世界で訳されている聖書の原本として用いられることが多いのは、このコミュニティのホームページの写真にもある、United Bible Societies 版のようです。
Nestle-Aland 版は、英語との対訳と、ラテン語との対訳があります。また、United Bible Societies 版は、希英辞典が巻末についていて、便利です。
ちなみに、好みの問題になりますが、活字の美しさという点では、Nestle-Aland 版が評価が高いようですが、目への優しさという点では、校訂注のあまり煩雑でない、United Bible Societies 版の方がいいような気がします。両者には異同があるのですが、それは微々たるものだといえます。新共同訳は、後者を忠実に訳しています。
Textus Receptus は、校訂注が全く付いていないので、テキストの異同について悩むことなく読めるかもしれませんが、現在訳されている聖書にはほとんど用いられていないようだし、時には話の筋に微妙な影響を与える異同もあるので、このテキストをお読みになるなら、それを考慮に入れての上で使用されるとよいと思います。
私たち一般人が原典を読むとき、写本を読むことは滅多になく、普通は校訂本を読むことになります。写本が気になる場合は、Nestle-Aland 版を見れば、脚注として校訂注がびっしりと記されています。私にはそこに記された記号が何を表すのか、ほとんどわかりませんが、そこに挙げられた異動を見ていると、いろいろと考えさせられます。
私はテキスト批評にはあまり関心がないのですが、原典を読むようになると、テキストの異同について無視しているわけにはいかず、その概要はいつも念頭においている必要が出てきます。それでというわけではないけれど、現在4種類の違うテキストを持っています。しかし、どれが優れているかというのは私には分からないことなので、どのテキストも同等に、大切にしています。
ijustat さま。
詳しいご紹介ありがとうごさいます。
写本問題を考えるきっかけは、共同訳のマルコで、イエス復活後の行動描写の部分全部が、後代の加筆と見るのが一般的であることを示す、〔 〕記号で囲まれているのに気付いた時からです。
カルチャー・ショックでしたね。
それじゃあ、原マルコの文書は、どのような復活を伝えようとしたのか?
その辺から、新約聖書におけるテキスト批評の現状を調べ始めたのでした。
しかし、原マルコが同定出来たとして、ijustat さまの言うとおり、ギリシャ語も自然言語である限り、解釈の問題はテキスト批評で解決される次元の問題ではないのですよね。
このトピで該当する、ラザロ復活という(間接的・直接的な)奇跡体験と、人の信じるということと、人の行動の関係、3者関係についてどう解釈するか。
これは直接的に、イエスとは何か? 奇跡(復活)とは何か? について自分の(仮定的であっても)解釈なしには、読むことは出来ないことでしょう。
そして、奇跡を経験した人間は、どのような行動をとるのかという、自分の人間理解もまた、解釈のプロセスで照らし出されていくのでしょうね。
そういった意味で、イエスの言行を語る新約聖書の諸文書とつきあうことは、自分の世界観や人間観を、新約という一つの鏡に映し出すようなものであると思います。
詳しいご紹介ありがとうごさいます。
写本問題を考えるきっかけは、共同訳のマルコで、イエス復活後の行動描写の部分全部が、後代の加筆と見るのが一般的であることを示す、〔 〕記号で囲まれているのに気付いた時からです。
カルチャー・ショックでしたね。
それじゃあ、原マルコの文書は、どのような復活を伝えようとしたのか?
その辺から、新約聖書におけるテキスト批評の現状を調べ始めたのでした。
しかし、原マルコが同定出来たとして、ijustat さまの言うとおり、ギリシャ語も自然言語である限り、解釈の問題はテキスト批評で解決される次元の問題ではないのですよね。
このトピで該当する、ラザロ復活という(間接的・直接的な)奇跡体験と、人の信じるということと、人の行動の関係、3者関係についてどう解釈するか。
これは直接的に、イエスとは何か? 奇跡(復活)とは何か? について自分の(仮定的であっても)解釈なしには、読むことは出来ないことでしょう。
そして、奇跡を経験した人間は、どのような行動をとるのかという、自分の人間理解もまた、解釈のプロセスで照らし出されていくのでしょうね。
そういった意味で、イエスの言行を語る新約聖書の諸文書とつきあうことは、自分の世界観や人間観を、新約という一つの鏡に映し出すようなものであると思います。
ijustatさん>
ijustatさんの言葉にはちょっと御幣があると思いますので、横から失礼します。
>両者には異同があるのですが、それは微々たるものだと
>いえます。新共同訳は、後者を忠実に訳しています。
とありますが、United Bible Societies はテクストに関してはネストレに基づいていますので、もし相違があった場合、それはネストレの版同士の相違になるはずです(お手元のUnited Bible Societiesがネストレのどの版に従っているかはIntroductionのtextのところに載っています)。基本的にUnited Bible Societies は聖書翻訳作業の為に作られているので、異読(写本による読みの違いのことで、ijustatさんが記すところの異同のこと。専門家の間では異読という場合が多いかと思います)がネストレに比べて削られていたりなどします。
☆‥ゝ さん>
御存知かもしれませんが、マルコ福音書は元来16章8節で終わっていた、つまり復活顕現物語は無かった、というのが現在の研究者の大体一致した見解です。
因みに原マルコはアラム語であったなどという説もありまして、ナカナカ面白い領域ですから、何かしら発見がありましたら教えてください。(一応)マルコ福音書研究者として、興味がありますゆえ。
ijustatさんの言葉にはちょっと御幣があると思いますので、横から失礼します。
>両者には異同があるのですが、それは微々たるものだと
>いえます。新共同訳は、後者を忠実に訳しています。
とありますが、United Bible Societies はテクストに関してはネストレに基づいていますので、もし相違があった場合、それはネストレの版同士の相違になるはずです(お手元のUnited Bible Societiesがネストレのどの版に従っているかはIntroductionのtextのところに載っています)。基本的にUnited Bible Societies は聖書翻訳作業の為に作られているので、異読(写本による読みの違いのことで、ijustatさんが記すところの異同のこと。専門家の間では異読という場合が多いかと思います)がネストレに比べて削られていたりなどします。
☆‥ゝ さん>
御存知かもしれませんが、マルコ福音書は元来16章8節で終わっていた、つまり復活顕現物語は無かった、というのが現在の研究者の大体一致した見解です。
因みに原マルコはアラム語であったなどという説もありまして、ナカナカ面白い領域ですから、何かしら発見がありましたら教えてください。(一応)マルコ福音書研究者として、興味がありますゆえ。
ijustat さん(>#8)
シノブ さん(>#10)
既にシノブさんがご指摘くださっていますが、NAとUBSは、それぞれの前版(NA26、UBS3)以後、同じテキストを採用しています。
あと、UBSの脚注は、教父名などは省略されずフルスペリングで書かれていますので、余計な略語を覚えなくて済むという利点がありますが、私はあの全編イタリックの本文が嫌いです。
なお、次のような、新約聖書に29回未満しか現れていない単語の意味を脚注に並べてくれている便利なギリシア語聖書もあります。これはNIVの翻訳委員会が採用した独自のテキストを出版したものです。本文批評についても注も最小限ですが含まれています。
Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski, _A Reader's Greek New Testament_ (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2003). ISBN 0-310-24888-4
シノブ さん(>#10)
既にシノブさんがご指摘くださっていますが、NAとUBSは、それぞれの前版(NA26、UBS3)以後、同じテキストを採用しています。
あと、UBSの脚注は、教父名などは省略されずフルスペリングで書かれていますので、余計な略語を覚えなくて済むという利点がありますが、私はあの全編イタリックの本文が嫌いです。
なお、次のような、新約聖書に29回未満しか現れていない単語の意味を脚注に並べてくれている便利なギリシア語聖書もあります。これはNIVの翻訳委員会が採用した独自のテキストを出版したものです。本文批評についても注も最小限ですが含まれています。
Richard J. Goodrich and Albert L. Lukaszewski, _A Reader's Greek New Testament_ (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2003). ISBN 0-310-24888-4
>☆‥ゝさま
「解釈の問題はテキスト批評で解決される次元の問題ではない」とおっしゃったのは、本当にそうだと思います。同じテキストから訳しているはずなのに、解釈がずいぶん違うこともありますから。
もっとも、原典に異読(“異同”とは言わないんだそうですね。今後“異読”と言うことにします)があって、それが翻訳に現れる場合もあります。ですから、翻訳だけを対照してみても、なぜ両者が違うのかは分かりかねることが多いのではないかと思います。
ところで、本屋でパラパラとめくって見た新約聖書の研究書には、聖書箇所の解釈をめぐって議論しているとき、写本の違いについても言及しているものがありました。いきなり他の写本の異読を持ち出して、そっちの方がいい、と言っているので面食らいましたが、現在出版されている校訂本に無条件で従うのは、研究者の態度ではないということは、言えるかもしれません。
イエスの言行を語る新約聖書の諸文書とつきあうことは、
自分の世界観や人間観を、新約という一つの鏡に映し出す
ようなものであると思います。
私も早く、文法や単語の意味と格闘することなく、聖書から御言葉の恵みをダイレクトに受取る幸福に与りたいと願っています。
>シノブさま
United Bible Societies はテクストに関してはネストレ
に基づいていますので、もし相違があった場合、それはネ
ストレの版同士の相違になるはずです。
それは気が付きませんでした。どうりでよく似ていると思いました。私が“違い”について言ったのは、Nestle-Aland 版の希英対訳聖書で、英訳にあって原文にない語があって、英訳に関する説明を見ると、UBS 版を底本に訳しているという説明があったので、ははあ、なるほど、Nestle-Aland と UBS は別々のテキストなんだな、と早合点してしまったのです。
>りけるけさま
私はあの全編イタリックの本文が嫌いです。
なるほど、ギリシア語を読み慣れた人にとっては、あのイタリックは目障りなのかもしれません。私は、トノスが大きくて見やすいので、目に優しいと感じていました。
ちなみに、手元にある原語と現代ギリシア語訳との対訳聖書を見ると、現代ギリシア語訳の方は、Textus Receptus で使用している書体を用いていますが、原典の方ではイタリックを用いています。
日常もっぱらギリシア語を目にするギリシア人にとって、これらの文字がどのように見えるのかは、気になるところです。
なお、次のような、新約聖書に29回未満しか現れていない
単語の意味を脚注に並べてくれている便利なギリシア語聖
書もあります。これはNIVの翻訳委員会が採用した独自の
テキストを出版したものです。本文批評についても注も最
小限ですが含まれています。
NIV が「独自のテキスト」から翻訳されたとは、知りませんでした。NIV は韓国で最もたくさん読まれている英訳聖書です。この NIV と日本語の聖書とで合わない部分があったとき、それは原典の異読による可能性もあるということですね。
いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。^^
「解釈の問題はテキスト批評で解決される次元の問題ではない」とおっしゃったのは、本当にそうだと思います。同じテキストから訳しているはずなのに、解釈がずいぶん違うこともありますから。
もっとも、原典に異読(“異同”とは言わないんだそうですね。今後“異読”と言うことにします)があって、それが翻訳に現れる場合もあります。ですから、翻訳だけを対照してみても、なぜ両者が違うのかは分かりかねることが多いのではないかと思います。
ところで、本屋でパラパラとめくって見た新約聖書の研究書には、聖書箇所の解釈をめぐって議論しているとき、写本の違いについても言及しているものがありました。いきなり他の写本の異読を持ち出して、そっちの方がいい、と言っているので面食らいましたが、現在出版されている校訂本に無条件で従うのは、研究者の態度ではないということは、言えるかもしれません。
イエスの言行を語る新約聖書の諸文書とつきあうことは、
自分の世界観や人間観を、新約という一つの鏡に映し出す
ようなものであると思います。
私も早く、文法や単語の意味と格闘することなく、聖書から御言葉の恵みをダイレクトに受取る幸福に与りたいと願っています。
>シノブさま
United Bible Societies はテクストに関してはネストレ
に基づいていますので、もし相違があった場合、それはネ
ストレの版同士の相違になるはずです。
それは気が付きませんでした。どうりでよく似ていると思いました。私が“違い”について言ったのは、Nestle-Aland 版の希英対訳聖書で、英訳にあって原文にない語があって、英訳に関する説明を見ると、UBS 版を底本に訳しているという説明があったので、ははあ、なるほど、Nestle-Aland と UBS は別々のテキストなんだな、と早合点してしまったのです。
>りけるけさま
私はあの全編イタリックの本文が嫌いです。
なるほど、ギリシア語を読み慣れた人にとっては、あのイタリックは目障りなのかもしれません。私は、トノスが大きくて見やすいので、目に優しいと感じていました。
ちなみに、手元にある原語と現代ギリシア語訳との対訳聖書を見ると、現代ギリシア語訳の方は、Textus Receptus で使用している書体を用いていますが、原典の方ではイタリックを用いています。
日常もっぱらギリシア語を目にするギリシア人にとって、これらの文字がどのように見えるのかは、気になるところです。
なお、次のような、新約聖書に29回未満しか現れていない
単語の意味を脚注に並べてくれている便利なギリシア語聖
書もあります。これはNIVの翻訳委員会が採用した独自の
テキストを出版したものです。本文批評についても注も最
小限ですが含まれています。
NIV が「独自のテキスト」から翻訳されたとは、知りませんでした。NIV は韓国で最もたくさん読まれている英訳聖書です。この NIV と日本語の聖書とで合わない部分があったとき、それは原典の異読による可能性もあるということですね。
いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。^^
iyustatさん>
聖書箇所の解釈をめぐって議論しているとき、写本の違いについても言及しているものがありました。いきなり他の写本の異読を持ち出して、そっちの方がいい、と言っているので面食らいましたが
確かに、最初は戸惑うかもしれませんが、一応どの写本の読みが良いと判断するかの基準はあるのです。例えば、シナイ写本(ヘブライ語のアレフであらわされます)とバチカン写本(B)、アレキサンドリア写本(A)の読みは優先されるものですし、パピルス断片(p)の一部も同様とか。それと、読み・解釈が困難な方を選ぶべし(後の書記が分かりやすく改ざんしたと考えられるので)等々。これらを詳細に論じた本があるのですが、タイトルを忘れました。。。すいません。確か、日本語のものがあったはずなのですが・・・。夜勤明けで頭がぼーとしているのでして。。。
聖書箇所の解釈をめぐって議論しているとき、写本の違いについても言及しているものがありました。いきなり他の写本の異読を持ち出して、そっちの方がいい、と言っているので面食らいましたが
確かに、最初は戸惑うかもしれませんが、一応どの写本の読みが良いと判断するかの基準はあるのです。例えば、シナイ写本(ヘブライ語のアレフであらわされます)とバチカン写本(B)、アレキサンドリア写本(A)の読みは優先されるものですし、パピルス断片(p)の一部も同様とか。それと、読み・解釈が困難な方を選ぶべし(後の書記が分かりやすく改ざんしたと考えられるので)等々。これらを詳細に論じた本があるのですが、タイトルを忘れました。。。すいません。確か、日本語のものがあったはずなのですが・・・。夜勤明けで頭がぼーとしているのでして。。。
>シノブさま
一応どの写本の読みが良いと判断するかの基準はあるので
す。例えば、シナイ写本(ヘブライ語のアレフであらわさ
れます)とバチカン写本(B)、アレキサンドリア写本
(A)の読みは優先されるものですし、パピルス断片(p)
の一部も同様とか。
ということは、異読の中からどれを取るかという基準は、テキストを校訂するときと、解釈をするときとで違うということなんでしょうか。あるいは、上に挙げられた写本は、校訂本と同等な立場で検討するに値する、ということなのでしょうか。または、研究者は校訂本を用いず、必ず写本を用いて研究すべきである、ということなのでしょうか。どれもありそうな感じがしますね。
それと、読み・解釈が困難な方を選ぶべし(後の書記が分
かりやすく改ざんしたと考えられるので)等々。
これは、人情の機微を穿った取り決めですね。ついうっかり勘違いをして単語を入れ替えてしまったり別の表現をしてしまったりするとき、たいていは、単純化されたり、平易になったり、平凡になったりしますから。
面白そうな本なので、ぜひご紹介いただけるとありがたいと思います。でも、あのう、日本語ですよね。^^;
一応どの写本の読みが良いと判断するかの基準はあるので
す。例えば、シナイ写本(ヘブライ語のアレフであらわさ
れます)とバチカン写本(B)、アレキサンドリア写本
(A)の読みは優先されるものですし、パピルス断片(p)
の一部も同様とか。
ということは、異読の中からどれを取るかという基準は、テキストを校訂するときと、解釈をするときとで違うということなんでしょうか。あるいは、上に挙げられた写本は、校訂本と同等な立場で検討するに値する、ということなのでしょうか。または、研究者は校訂本を用いず、必ず写本を用いて研究すべきである、ということなのでしょうか。どれもありそうな感じがしますね。
それと、読み・解釈が困難な方を選ぶべし(後の書記が分
かりやすく改ざんしたと考えられるので)等々。
これは、人情の機微を穿った取り決めですね。ついうっかり勘違いをして単語を入れ替えてしまったり別の表現をしてしまったりするとき、たいていは、単純化されたり、平易になったり、平凡になったりしますから。
面白そうな本なので、ぜひご紹介いただけるとありがたいと思います。でも、あのう、日本語ですよね。^^;
ijustatさん>
忘れてはならないのは、オリジナルのテクストを再構成するのも人間なので、そこには何らかの解釈が入り込んでいる、ということです。ですから、写本・パピルスの文字の確定がなされ、次に写本の系統(例えば写本1と写本2があった場合、両者は関係があるのか、無いのか等々)がどうなっているのかが確定できても、尚どの写本の読みを採るかは場合によっては、解釈によるのです(マルコ福音書1章4節では、重要な写本の読みが全く割れているので、手がかりをどこに求めるべきなのか全く迷ってしまいます)。ですから、現在私たちが手にしているネストレは、オリジナルはこれだ、という解釈の一つなのです(なので、ネストレも版によってどの異読をとっているかが異なっています)。ですから、オリジナルテクストの復元は、様々な異読が生まれた背景を解釈する作業だともいえるかもしれません。
私だと舌足らずなので、この分野の参考書としてですが、
蛭沼寿雄『新約本文批評』、山本書店
か
B.M. Metzger, The Text of the New Testament, Oxford Univ. Press(橋本滋男訳、『新約聖書の本文批評』、日本基督教団出版局)
があげられるはずです。「はずです」というのも、私も本文批評はお作法として学んだだけでこれらの本が現在手元に無く、確かこれらが日本語での入門書だった、と記憶を頼りに書いているのでして・・・。購入なされる前に、図書館や御友人に確認為された方が良いかと思います。不確かな情報で申し訳ないです。
忘れてはならないのは、オリジナルのテクストを再構成するのも人間なので、そこには何らかの解釈が入り込んでいる、ということです。ですから、写本・パピルスの文字の確定がなされ、次に写本の系統(例えば写本1と写本2があった場合、両者は関係があるのか、無いのか等々)がどうなっているのかが確定できても、尚どの写本の読みを採るかは場合によっては、解釈によるのです(マルコ福音書1章4節では、重要な写本の読みが全く割れているので、手がかりをどこに求めるべきなのか全く迷ってしまいます)。ですから、現在私たちが手にしているネストレは、オリジナルはこれだ、という解釈の一つなのです(なので、ネストレも版によってどの異読をとっているかが異なっています)。ですから、オリジナルテクストの復元は、様々な異読が生まれた背景を解釈する作業だともいえるかもしれません。
私だと舌足らずなので、この分野の参考書としてですが、
蛭沼寿雄『新約本文批評』、山本書店
か
B.M. Metzger, The Text of the New Testament, Oxford Univ. Press(橋本滋男訳、『新約聖書の本文批評』、日本基督教団出版局)
があげられるはずです。「はずです」というのも、私も本文批評はお作法として学んだだけでこれらの本が現在手元に無く、確かこれらが日本語での入門書だった、と記憶を頼りに書いているのでして・・・。購入なされる前に、図書館や御友人に確認為された方が良いかと思います。不確かな情報で申し訳ないです。
ijustat さん(>#14)
昨日の午後に#13のシノブさんのコメントを承けてシノブさんが#15でご紹介くださっているメツガーの邦訳をご紹介するコメントを書き込んだのですが、なぜかうまく登録されていなかったようです。
そうですね。どちらも優れた本です。メツガーのもののほうが射程が広く包括的ですね。分厚いですし。7,930円(税込)くらいでしたかね。翻訳も、若干口語的な部分はありますが、全体的に読みやすかったと記憶しています。
蛭沼のものは、日本人による書き下ろしという点が長所なのだと思いますが、なにぶん古いので現時点で手に入るかどうか。私が10年ほど前に購入した際も古書店でだったと思います。
ま、四の五の言わず、とにかく読んでみてください。NA27などをはじめとするどれかをひたすら読むというのでなく、ijustatさんのように複数の、写本と言わずとも、校訂本をついつい比較したくなるタイプの方が新約をじっくり原典で読もうと思えば、本文批評の基礎を押さえてからでなければ始まりませんq(^ ^)p。
昨日の午後に#13のシノブさんのコメントを承けてシノブさんが#15でご紹介くださっているメツガーの邦訳をご紹介するコメントを書き込んだのですが、なぜかうまく登録されていなかったようです。
そうですね。どちらも優れた本です。メツガーのもののほうが射程が広く包括的ですね。分厚いですし。7,930円(税込)くらいでしたかね。翻訳も、若干口語的な部分はありますが、全体的に読みやすかったと記憶しています。
蛭沼のものは、日本人による書き下ろしという点が長所なのだと思いますが、なにぶん古いので現時点で手に入るかどうか。私が10年ほど前に購入した際も古書店でだったと思います。
ま、四の五の言わず、とにかく読んでみてください。NA27などをはじめとするどれかをひたすら読むというのでなく、ijustatさんのように複数の、写本と言わずとも、校訂本をついつい比較したくなるタイプの方が新約をじっくり原典で読もうと思えば、本文批評の基礎を押さえてからでなければ始まりませんq(^ ^)p。
>シノブさま、りけるけさま
早速アマゾンで調べてみました。「メツガー」の方はとても高く、「蛭沼」の方は検出すらされませんでした。でも、いずれ読んでみたいですね。
横道に逸れますが、ふと、テキスト批評について学ぶと有利なのは、どの言語のテキストについても使えることではないか、と思いました。
たとえば、韓国語の「春香伝」は、数々の異本がありますが、聖書のテキスト批評を学んでからそれを校合してみるのも面白いかなあ、なんて思いました。まあ、現代韓国語だけで手一杯の私が、それをやるとは思えませんが。
というわけで、しばらくは四の五の言っているかもしれませんが、なるべくその期間を短縮したいと思います。(笑)
早速アマゾンで調べてみました。「メツガー」の方はとても高く、「蛭沼」の方は検出すらされませんでした。でも、いずれ読んでみたいですね。
横道に逸れますが、ふと、テキスト批評について学ぶと有利なのは、どの言語のテキストについても使えることではないか、と思いました。
たとえば、韓国語の「春香伝」は、数々の異本がありますが、聖書のテキスト批評を学んでからそれを校合してみるのも面白いかなあ、なんて思いました。まあ、現代韓国語だけで手一杯の私が、それをやるとは思えませんが。
というわけで、しばらくは四の五の言っているかもしれませんが、なるべくその期間を短縮したいと思います。(笑)
ijustat さん(>#17)
昨日はこともあろうかクリスマスの晩に、夜の8時からオフィスでのこぎりを手に月曜大工を始め、シンデレラの12時までかかって6段の本棚を作っていました。結局、語学関係のテキストや参考書専用の棚になってしまいましたが、おかげでかなり床の見える幸せな空間になってきました。
で、朝の6時までごそごそと片づけをする中で、いろいろと良い資料が出てきました。ちょっとコピーの仕方が悪くて出典がわからないのですが、いのちのことば社だったでしょうか、福音派の出している旧約6巻、新約3巻の注解書セットの中の新約本文批評や正典化やその他いくつかの項目のコピーをファイルしたものなどです。どこかの聖書辞典からのものもあります。
で、四の五の言わずに、と言った手前(^ ^)、よろしければこれらから適当なものを見繕ってコピーを取り、郵便ででもお送りしようかと思うのですが、よろしければご住所を教えてください。何度も言うように出典が明らかでないので、どこかで引用するなどの資料としては使いにくいのですが、基礎的な知識を得るためには十分有用なものです。ijustatさんに限らず、他の方々も、お入り用な方はどうぞ。
ただ、国内にいらっしゃれば、教会や図書館などでも手軽に閲覧できる、その程度の(あくまでアクセスのしやすさという意味で)資料です。ijustatさんは韓国にいらっしゃるので、もしかすると日本語のキリスト教関係の文献に関しては不便な環境にいらっしゃるかと思い、このようなアイデアを思いつきました。お気軽にお申しつけください。
昨日はこともあろうかクリスマスの晩に、夜の8時からオフィスでのこぎりを手に月曜大工を始め、シンデレラの12時までかかって6段の本棚を作っていました。結局、語学関係のテキストや参考書専用の棚になってしまいましたが、おかげでかなり床の見える幸せな空間になってきました。
で、朝の6時までごそごそと片づけをする中で、いろいろと良い資料が出てきました。ちょっとコピーの仕方が悪くて出典がわからないのですが、いのちのことば社だったでしょうか、福音派の出している旧約6巻、新約3巻の注解書セットの中の新約本文批評や正典化やその他いくつかの項目のコピーをファイルしたものなどです。どこかの聖書辞典からのものもあります。
で、四の五の言わずに、と言った手前(^ ^)、よろしければこれらから適当なものを見繕ってコピーを取り、郵便ででもお送りしようかと思うのですが、よろしければご住所を教えてください。何度も言うように出典が明らかでないので、どこかで引用するなどの資料としては使いにくいのですが、基礎的な知識を得るためには十分有用なものです。ijustatさんに限らず、他の方々も、お入り用な方はどうぞ。
ただ、国内にいらっしゃれば、教会や図書館などでも手軽に閲覧できる、その程度の(あくまでアクセスのしやすさという意味で)資料です。ijustatさんは韓国にいらっしゃるので、もしかすると日本語のキリスト教関係の文献に関しては不便な環境にいらっしゃるかと思い、このようなアイデアを思いつきました。お気軽にお申しつけください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ギリシア語原典で聖書を読む 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ギリシア語原典で聖書を読むのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37864人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人