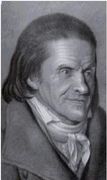http://
どうも皆さん御久し振りです。久し振りで、いきなりトピを立てて申し訳ないですm(__)m
つい最近↑のニュースがありましたよね。皆さんは、どう思います?別にチェック表を作るとかは構わないんですけど、そのチェック項目を実際現場の先生達がクリアしていくには厳しい現実が在ると思うんですよね。ITの活用に関しても、活用できれば優秀な先生ですかね?学校は(高校の情報処理科や商業高校は別にして)パソコン教室ではないですからね。
御役人や見識者の皆様は、どうも本来のポイントを勘違いされているのではないかと思ってしまいます。
↑のニュースをきっかけに、皆さんで学校教育に本当に必要なものや、教員の評価方法の是非について意見を聞いてみたいのですが、よろしくお願いします。
どうも皆さん御久し振りです。久し振りで、いきなりトピを立てて申し訳ないですm(__)m
つい最近↑のニュースがありましたよね。皆さんは、どう思います?別にチェック表を作るとかは構わないんですけど、そのチェック項目を実際現場の先生達がクリアしていくには厳しい現実が在ると思うんですよね。ITの活用に関しても、活用できれば優秀な先生ですかね?学校は(高校の情報処理科や商業高校は別にして)パソコン教室ではないですからね。
御役人や見識者の皆様は、どうも本来のポイントを勘違いされているのではないかと思ってしまいます。
↑のニュースをきっかけに、皆さんで学校教育に本当に必要なものや、教員の評価方法の是非について意見を聞いてみたいのですが、よろしくお願いします。
|
|
|
|
コメント(14)
えーと、コレですね。
------------------------------
文部科学省は19日、教員のIT活用・指導能力を測るチェックリストを発表した。教員に対するチェックリスト作成は初めてで、小学校版と中学校・高校版の2種類がある。文科省はチェックリストの100%達成を目標に掲げている。
リストは5分類の計18項目。「教材研究・指導の準備、評価」「児童への指導」「情報モラルの指導」「校務」の5分類での指導・活用能力を4段階の自己評価で行う。
06年1月に決まった国のIT新改革戦略で、教員のIT活用・指導能力の基準作りが盛り込まれたことを受け、文科省は同10月、検討会を設置していた。リストは今週中にも文科省ホームページで掲載される。【高山純二】
◇チェックリスト抜粋(小学校版)◇
・教材研究・指導の準備、評価
授業で使う教材や資料などを集めるため、インターネットなどを活用する。
・授業中
わかりやすく説明するため、コンピューターや映写機などを活用する。
・児童への指導
児童がコンピューターなどを利用し、情報収集、選択ができるよう指導する。
・情報モラルの指導
児童が行動に責任を持ち、相手のことを考えた情報のやりとりができるよう指導する。
・校務
校内での担務に必要な情報をインターネットで集め、表計算ソフトなどで資料を作成する。
------------------------------
ウーム、こりゃ某パソコン教室ですなw学校総ア○バ化(苦笑)
IT、ITって、こうやって情報に弄ばれている方がよっぽど問題です。そりゃ勿論、使えないよりも使えた方が良いに決まっています。しかし、使えなきゃ教員として使い物にならないと言う発想は行き過ぎと言わざる得ないでしょう。
学校はあくまで「学問」を教える場である事をシッカリと認識してほしいと思います。ただ、現今の状況を見ると学校で「社会規範」を教えなければならないと言う議論があります。この点を考えれば、暢気に「学問」等と言ってはいられない事になるだろうとも思いますが…(特に情報モラル指導の点)。
それにしても、ITの有効活用とは一線を隔した領域の議論であることは明白ですね。
------------------------------
文部科学省は19日、教員のIT活用・指導能力を測るチェックリストを発表した。教員に対するチェックリスト作成は初めてで、小学校版と中学校・高校版の2種類がある。文科省はチェックリストの100%達成を目標に掲げている。
リストは5分類の計18項目。「教材研究・指導の準備、評価」「児童への指導」「情報モラルの指導」「校務」の5分類での指導・活用能力を4段階の自己評価で行う。
06年1月に決まった国のIT新改革戦略で、教員のIT活用・指導能力の基準作りが盛り込まれたことを受け、文科省は同10月、検討会を設置していた。リストは今週中にも文科省ホームページで掲載される。【高山純二】
◇チェックリスト抜粋(小学校版)◇
・教材研究・指導の準備、評価
授業で使う教材や資料などを集めるため、インターネットなどを活用する。
・授業中
わかりやすく説明するため、コンピューターや映写機などを活用する。
・児童への指導
児童がコンピューターなどを利用し、情報収集、選択ができるよう指導する。
・情報モラルの指導
児童が行動に責任を持ち、相手のことを考えた情報のやりとりができるよう指導する。
・校務
校内での担務に必要な情報をインターネットで集め、表計算ソフトなどで資料を作成する。
------------------------------
ウーム、こりゃ某パソコン教室ですなw学校総ア○バ化(苦笑)
IT、ITって、こうやって情報に弄ばれている方がよっぽど問題です。そりゃ勿論、使えないよりも使えた方が良いに決まっています。しかし、使えなきゃ教員として使い物にならないと言う発想は行き過ぎと言わざる得ないでしょう。
学校はあくまで「学問」を教える場である事をシッカリと認識してほしいと思います。ただ、現今の状況を見ると学校で「社会規範」を教えなければならないと言う議論があります。この点を考えれば、暢気に「学問」等と言ってはいられない事になるだろうとも思いますが…(特に情報モラル指導の点)。
それにしても、ITの有効活用とは一線を隔した領域の議論であることは明白ですね。
そうなんですよね。主眼を置く所がずれてしまってると思うんですよ。IT(PCの活用)と教員の評価とは別の問題だと思いますしね。
技術を使いこなす事が優秀な証で、それが評価基準になるのであれば、そういった専門職の人は教員として優秀と言う事にもなる(少し短絡的な意見かもしれませんが)。でも、加学究さんの仰っている通り、学校は『学問』を学ぶ場所であるはずです。そこには心(モラルとか)を学ぶ事も入っていると思っています。それを教えるのが学校であり教員です。
ですがIT(PC)は有効な技術手段では有るが、それそのものは学校学問とは一線を画すと思っています。そして、それ自体が教員指導能力評価に直結する事はおかしな流れではないかと思っています。
そして今回の内容に関して疑問点が有ります。それは週休二日と、ゆとり教育に伴って中学校での技術の授業時間削減などが在る事が無視されている点です。(技能系教科全般に言える事なのですが、今回は敢えて技術をとりあげました。)
そんなにITが大事であるならば、技術の授業時間を増やし教育すれば良いだけではないでしょうか。技術の時間を削る方向に向けておきながら、ITを推進し教員の評価基準に用いるなど本末転倒ではないでしょうか?
技術を使いこなす事が優秀な証で、それが評価基準になるのであれば、そういった専門職の人は教員として優秀と言う事にもなる(少し短絡的な意見かもしれませんが)。でも、加学究さんの仰っている通り、学校は『学問』を学ぶ場所であるはずです。そこには心(モラルとか)を学ぶ事も入っていると思っています。それを教えるのが学校であり教員です。
ですがIT(PC)は有効な技術手段では有るが、それそのものは学校学問とは一線を画すと思っています。そして、それ自体が教員指導能力評価に直結する事はおかしな流れではないかと思っています。
そして今回の内容に関して疑問点が有ります。それは週休二日と、ゆとり教育に伴って中学校での技術の授業時間削減などが在る事が無視されている点です。(技能系教科全般に言える事なのですが、今回は敢えて技術をとりあげました。)
そんなにITが大事であるならば、技術の授業時間を増やし教育すれば良いだけではないでしょうか。技術の時間を削る方向に向けておきながら、ITを推進し教員の評価基準に用いるなど本末転倒ではないでしょうか?
変なの…
そんな事に時間を費やす暇はないですよね。
技術があることがプラスにはなると思いますが…
まず、「モラル」という、加学究様のお話、本当に大事だと思います。
それがないと、人と人とのつながりにも問題が出てくると思います。(飛びすぎ?)
教員はまず、PCの使い方よりも大事なことを教えなければいけないと思います。小さい子供に対してなら尚更のこと。
PCってすごいなって思います。
小学生でも、月に2度、学習していて、私以上に上手に使いこなしています;;
でも、まだ私はそれだけではいけないと思います。
外で遊ぶこと、色鉛筆で色を塗ること。
「あるものの範囲内である限り、出来る範囲内で出来る限り、をして遊ぶこと」って、大事ではないでしょうか。
話しがずれていくなぁ
成績だって、点数だけでぴっとでる訳ではないと思います。
それで良いんでしょうか。そういうことなのでしょうか…
私が間違っているのかなぁ。
指導力って、PC技術力なら、PCの学校に通うのが手っ取り早い…
そんなんで指導力を評価されるなら、私の評価はすっごくすっごく低いですよ。
出来るようにはなりたいんです。でも、そのための環境が整いません・・・(時間も、頭の空きも…)
記事に気付いておらず、久しぶりにのぞいて、
マブさんのトピを見て…
今から仕事ですが、落ち込みました(´Д⊂
評価は別にして、少しずつ何とかするべき時なのでしょうか…
そんな事に時間を費やす暇はないですよね。
技術があることがプラスにはなると思いますが…
まず、「モラル」という、加学究様のお話、本当に大事だと思います。
それがないと、人と人とのつながりにも問題が出てくると思います。(飛びすぎ?)
教員はまず、PCの使い方よりも大事なことを教えなければいけないと思います。小さい子供に対してなら尚更のこと。
PCってすごいなって思います。
小学生でも、月に2度、学習していて、私以上に上手に使いこなしています;;
でも、まだ私はそれだけではいけないと思います。
外で遊ぶこと、色鉛筆で色を塗ること。
「あるものの範囲内である限り、出来る範囲内で出来る限り、をして遊ぶこと」って、大事ではないでしょうか。
話しがずれていくなぁ
成績だって、点数だけでぴっとでる訳ではないと思います。
それで良いんでしょうか。そういうことなのでしょうか…
私が間違っているのかなぁ。
指導力って、PC技術力なら、PCの学校に通うのが手っ取り早い…
そんなんで指導力を評価されるなら、私の評価はすっごくすっごく低いですよ。
出来るようにはなりたいんです。でも、そのための環境が整いません・・・(時間も、頭の空きも…)
記事に気付いておらず、久しぶりにのぞいて、
マブさんのトピを見て…
今から仕事ですが、落ち込みました(´Д⊂
評価は別にして、少しずつ何とかするべき時なのでしょうか…
>りんしおんさん
御久し振りですm(__)m
そんなに気にしなくも良いのではないでしょうか。自分の母親は小学校の教師ですが、長い時間(何年も)をかけて学級通信などは、ある程度自力で作れるようになりましたが、だからといって使いこなしている訳ではないですし。それ自身は道具でしかない訳で、本来評価の対象になるものでもないと思いますよ。
PCが使えれば便利かもしれません。仕事ではかどる事も有るとは思います。でも、使いこなせたからといって、どうなんでしょう?教師に求められる物とは本来違うと思いますよ。
だから、気にする事はないのではないでしょうか?(^.^)と、私は思うのですが。
こんなニュースが出る事で尚更に、もっと教えるべき大事な事が有る事を再認識しました。大事なのは道具や手段ではない。大事なのは、それらを用いる時の気持ち(心がけやモラル)であると。
御久し振りですm(__)m
そんなに気にしなくも良いのではないでしょうか。自分の母親は小学校の教師ですが、長い時間(何年も)をかけて学級通信などは、ある程度自力で作れるようになりましたが、だからといって使いこなしている訳ではないですし。それ自身は道具でしかない訳で、本来評価の対象になるものでもないと思いますよ。
PCが使えれば便利かもしれません。仕事ではかどる事も有るとは思います。でも、使いこなせたからといって、どうなんでしょう?教師に求められる物とは本来違うと思いますよ。
だから、気にする事はないのではないでしょうか?(^.^)と、私は思うのですが。
こんなニュースが出る事で尚更に、もっと教えるべき大事な事が有る事を再認識しました。大事なのは道具や手段ではない。大事なのは、それらを用いる時の気持ち(心がけやモラル)であると。
マブ様へ
ありがとうございます。
いえ、私は結局何を言っても手書きの方が好きなんです^^;。(書道をしています。全然上手ではないです、何度もやめようとしたほどですから^^;)
前の仕事で書類を作るためにパソコンは勉強しました、独学で。
文字は打てますが、それ以外は全くと言っても良いですがダメです。(前の仕事でも、表でさえWordで作っていたほどです…)
仕事がはかどる程度には出来るようになりたいな、と言う気持ちなのですが…
だからこそ、それで評価されるのは悲しいなと思って落ち込んだのです。。。
大事なことは何か。
気持ちである、という言葉に大賛成。
気持ちを込めて、毎日頑張ります^^いってきま〜す!
(ちょっと元気でましたw)
ありがとうございます。
いえ、私は結局何を言っても手書きの方が好きなんです^^;。(書道をしています。全然上手ではないです、何度もやめようとしたほどですから^^;)
前の仕事で書類を作るためにパソコンは勉強しました、独学で。
文字は打てますが、それ以外は全くと言っても良いですがダメです。(前の仕事でも、表でさえWordで作っていたほどです…)
仕事がはかどる程度には出来るようになりたいな、と言う気持ちなのですが…
だからこそ、それで評価されるのは悲しいなと思って落ち込んだのです。。。
大事なことは何か。
気持ちである、という言葉に大賛成。
気持ちを込めて、毎日頑張ります^^いってきま〜す!
(ちょっと元気でましたw)
はじめまして。
文章を書く能力が低いために読みにくいかと思いますが、ご了承ください。
難しいコトはワカリマセンが、先生方もパンクをする状態。
小学校では、教えることが多すぎる。
でも、本当に教えるべき物とは物の大切さや、人と人とのつながりなのでは?
真実を教えるべきだと…。
あと、自分で考えさせ行動をさせるべきと思う。学力ばかりに目をとられてモラルもなにもない人間をこのまま作るのか?ってなカンジ。
勉強なんて自分でやりたくなったらやるし、その方法さえ教えればいいと思う。押し付けが多い大人だらけだから、子どもが子どもらしく生きられてない。
小学1年から毎日習い事。心の余裕がない。
人の痛みがわからない子どもが増える。
ちょっとしたケガの時まで対処がわからない。転んだだけで保健室。
今までの教員も全員否定は出来ないが、今までの先生が傲慢過ぎたのだと思う。だから、先生批判やら先生の評価や何もかも厳しい。そもそも教員が社会を知らずに教員になったりするのがおかしい。
やっぱり学力社会だから?そこが、今の日本の歪みだとも思える。結局は他人は関係ない!自分さえ良ければいい!って言う情もなにもなくなって正直者がバカを見る世界デショ上に従えばカワイイ人間?
頭のいい子(学力)が平気で先生をバカにする。
親が子どもと一緒になって先生批判する。
しつけを学校に任せる。
こんなの日常茶飯事。
真実を教えるべき先生が、偽る。巨像の世界。
結局は自分を守るため。
変な縦社会だ。
私たち人間が決めた法律で更に自分たちが首を絞めている。
『ゆとり教育』って心のゆとりがないんです。
だから反対に学力低下にも繋がると思う。
子どもにPC使わせるならば判断能力がない時期からはやらせない方がいい。
情報社会でこれ以上模倣犯を増やすな!と思う。
とにかく、難しいコトはわからないケド大変。
まぁ、世の中が真実を隠すからいけないけどそろそろ不正ばかりしていたら痛い目見る時代だろーね。
読みにくくてスミマセンでした( ̄〜 ̄;)
文章を書く能力が低いために読みにくいかと思いますが、ご了承ください。
難しいコトはワカリマセンが、先生方もパンクをする状態。
小学校では、教えることが多すぎる。
でも、本当に教えるべき物とは物の大切さや、人と人とのつながりなのでは?
真実を教えるべきだと…。
あと、自分で考えさせ行動をさせるべきと思う。学力ばかりに目をとられてモラルもなにもない人間をこのまま作るのか?ってなカンジ。
勉強なんて自分でやりたくなったらやるし、その方法さえ教えればいいと思う。押し付けが多い大人だらけだから、子どもが子どもらしく生きられてない。
小学1年から毎日習い事。心の余裕がない。
人の痛みがわからない子どもが増える。
ちょっとしたケガの時まで対処がわからない。転んだだけで保健室。
今までの教員も全員否定は出来ないが、今までの先生が傲慢過ぎたのだと思う。だから、先生批判やら先生の評価や何もかも厳しい。そもそも教員が社会を知らずに教員になったりするのがおかしい。
やっぱり学力社会だから?そこが、今の日本の歪みだとも思える。結局は他人は関係ない!自分さえ良ければいい!って言う情もなにもなくなって正直者がバカを見る世界デショ上に従えばカワイイ人間?
頭のいい子(学力)が平気で先生をバカにする。
親が子どもと一緒になって先生批判する。
しつけを学校に任せる。
こんなの日常茶飯事。
真実を教えるべき先生が、偽る。巨像の世界。
結局は自分を守るため。
変な縦社会だ。
私たち人間が決めた法律で更に自分たちが首を絞めている。
『ゆとり教育』って心のゆとりがないんです。
だから反対に学力低下にも繋がると思う。
子どもにPC使わせるならば判断能力がない時期からはやらせない方がいい。
情報社会でこれ以上模倣犯を増やすな!と思う。
とにかく、難しいコトはわからないケド大変。
まぁ、世の中が真実を隠すからいけないけどそろそろ不正ばかりしていたら痛い目見る時代だろーね。
読みにくくてスミマセンでした( ̄〜 ̄;)
☆きぃガチャたん様
初めまして。よろしくお願い致します。
文章に自信がないのは私も同じなんです^^;。
そして、私もきぃガチャたん様と同じ気持ちで、このコミュを見つけて、のぞかせていただいております。
「心」を教える事ってとっても難しいなぁと実感しています。
が、それが一番大切なんだ、と思っています。
「常識」も、それに伴って生まれてくるんじゃないかな、、、と思っています。
私自身、親としての立場も持ち合わせています。
まだ子供が小さいので、いろいろ見て、悩みながら、子育てをしております。
熱い気持ちや意気込みを持って、今も頑張っているつもりですが、
今は対子供でも、後ろに大きく親の存在がある状態。
昔もそうだったのかも知れませんが、
なかなかすべての児童に対応しようとするのが難しい時代になっていますね。
どの子も幸せに、成長することを願うばかりです。
彼らの人生の中のほんのちょこっと(なんと言ってもほんの数時間担当ですから)にしか触れられませんが、ほんの少しでも「心」を伝えられることがあればなぁと思っています。
PCの世界じゃないのに、PCで能力を推し量られるような時代、それに負けないように、信念を持って、頑張っていきたいですね。
みなさんの意見が、勇気になります。
私だけじゃないんだなって。
これからもよろしくお願いします。
初めまして。よろしくお願い致します。
文章に自信がないのは私も同じなんです^^;。
そして、私もきぃガチャたん様と同じ気持ちで、このコミュを見つけて、のぞかせていただいております。
「心」を教える事ってとっても難しいなぁと実感しています。
が、それが一番大切なんだ、と思っています。
「常識」も、それに伴って生まれてくるんじゃないかな、、、と思っています。
私自身、親としての立場も持ち合わせています。
まだ子供が小さいので、いろいろ見て、悩みながら、子育てをしております。
熱い気持ちや意気込みを持って、今も頑張っているつもりですが、
今は対子供でも、後ろに大きく親の存在がある状態。
昔もそうだったのかも知れませんが、
なかなかすべての児童に対応しようとするのが難しい時代になっていますね。
どの子も幸せに、成長することを願うばかりです。
彼らの人生の中のほんのちょこっと(なんと言ってもほんの数時間担当ですから)にしか触れられませんが、ほんの少しでも「心」を伝えられることがあればなぁと思っています。
PCの世界じゃないのに、PCで能力を推し量られるような時代、それに負けないように、信念を持って、頑張っていきたいですね。
みなさんの意見が、勇気になります。
私だけじゃないんだなって。
これからもよろしくお願いします。
>マブ様・りんしおん様
えーとですね。道具ってのは「使うもん」です。決して「使われるもん」ではありません。日本人のイケナイ癖です。諸外国はまた別の議論として、日本人の特性を考えた時に…
「便利な道具を手に入れる」
↓
「仕事の効率化を図る」
↓
「効率化を図った分だけまた仕事する」
↓
「また忙しくなる」
↓
「更に便利な道具を開発する」
と言う構図があると思います。つまり、今まで1時間かかっていた仕事が30分で出来るのなら、後の30分は自分の時間として使えば良いのです。しかし、それをしない。余った30分も仕事してしまう。結果次々忙しくなる。この連鎖を絶ち切る事がある意味で一番重要なことかもしれません。これが社会的にも、また教育的にも大きな意味を持つ事になると私は考えます。
携帯電話・PC・インターネット…新しい技術は確かに便利です。使えるようになれば新しい世界が広がります。しかし、その新しい世界が必ず幸せな世界かと言えば、それは、道具の使用者に関わる問題です。道具はその使用者によって如何様にも使い、使われる。そう言うもののはずです。
ですから、りんしおんさん、何も気に病む事は無いと思います。要は自分の仕事に対して、自分がどれだけの心を傾けたかが問題であって、そこにどんな技術を用いたかは二の次の問題と考えます。これは、如何に最先端を必要とする現場でも同様と思います。
それに、書の妙味はPCでは出せません。私も十数年間書の道に携わりましたので、その事はよく理解しているつもりです。あと、PCを独学でってのはナカナカしんどいですよ。私もPCいじって15年になりますが、やはり分かる人が居たから出来ました。それは確かです。
そう、この件に関しては、マブさんの書込みに「技術科で教えたら良い」と言うのがありましたが、私はこの点は反対です。そして、技術科の時間を減らす方向にあるのも反対です。
まず、技術科の時間にIT関連の技術を教えることになぜ反対か?それは、IT技術は変化する技術だからです。変化する技術は学校で教えるのには向きません。お金も時間もかかり過ぎます。それより、「コノギリの使い方」や「カンナのかけ方」「刃物の研ぎ方」を教えるべきです。私はこうした基礎的な「変化しない」技術こそ軽視せずに教えるべきだと考えます。そして、こうした技術を根幹とした処に人間本来のイマジネーションの発露があると思うのです。
ちょっと長くなりましたねw
続きはまたにします〜。
えーとですね。道具ってのは「使うもん」です。決して「使われるもん」ではありません。日本人のイケナイ癖です。諸外国はまた別の議論として、日本人の特性を考えた時に…
「便利な道具を手に入れる」
↓
「仕事の効率化を図る」
↓
「効率化を図った分だけまた仕事する」
↓
「また忙しくなる」
↓
「更に便利な道具を開発する」
と言う構図があると思います。つまり、今まで1時間かかっていた仕事が30分で出来るのなら、後の30分は自分の時間として使えば良いのです。しかし、それをしない。余った30分も仕事してしまう。結果次々忙しくなる。この連鎖を絶ち切る事がある意味で一番重要なことかもしれません。これが社会的にも、また教育的にも大きな意味を持つ事になると私は考えます。
携帯電話・PC・インターネット…新しい技術は確かに便利です。使えるようになれば新しい世界が広がります。しかし、その新しい世界が必ず幸せな世界かと言えば、それは、道具の使用者に関わる問題です。道具はその使用者によって如何様にも使い、使われる。そう言うもののはずです。
ですから、りんしおんさん、何も気に病む事は無いと思います。要は自分の仕事に対して、自分がどれだけの心を傾けたかが問題であって、そこにどんな技術を用いたかは二の次の問題と考えます。これは、如何に最先端を必要とする現場でも同様と思います。
それに、書の妙味はPCでは出せません。私も十数年間書の道に携わりましたので、その事はよく理解しているつもりです。あと、PCを独学でってのはナカナカしんどいですよ。私もPCいじって15年になりますが、やはり分かる人が居たから出来ました。それは確かです。
そう、この件に関しては、マブさんの書込みに「技術科で教えたら良い」と言うのがありましたが、私はこの点は反対です。そして、技術科の時間を減らす方向にあるのも反対です。
まず、技術科の時間にIT関連の技術を教えることになぜ反対か?それは、IT技術は変化する技術だからです。変化する技術は学校で教えるのには向きません。お金も時間もかかり過ぎます。それより、「コノギリの使い方」や「カンナのかけ方」「刃物の研ぎ方」を教えるべきです。私はこうした基礎的な「変化しない」技術こそ軽視せずに教えるべきだと考えます。そして、こうした技術を根幹とした処に人間本来のイマジネーションの発露があると思うのです。
ちょっと長くなりましたねw
続きはまたにします〜。
昨日の続きです〜。
さて、では、IT関連の技術はどこで学ぶか?と言う問題ですが、これはやはり各自での働きかけ次第とするのが最も妥当でしょう。ただ、りんしおんさんの要に独学で学ぶのは効率的ではありません。IT関連の技術を学べる環境にある人はその環境を利用すればよいのですが、そういった環境の無い人には「パソコン教室」や「専門学校」の利用によって環境を確保するのが一番得策だと考えます。また、これらの場所を利用する際には、利用しやすいような制度を国や地方で確立しておく事も勿論重要ですが…。
私がこう言った方向を示すのには、ハッキリとした理由があります。それはPCの活用法には各人により大きな開きがあり、その後の技術的な進歩に対する使用者の態度にも大きな違いがあると言う事が最も大きな理由です。
つまり、PCが無ければ仕事が成立しない人から、ゲームやネットだけ出来ればイイやと言う人から、年末に年賀状しか作らないしと言う人まで、その格差は余りに大きい。こう言った事を他の教科と同様に「教養」として「学校」で教えると言う事には、少なくとも私は積極的にはなれません。
やはり、IT関連知識・技術の習得は「各人の必要に応じて各人で」行うべきだろうと考えるのです。私は今までに多くの人からPCやネットに関する相談を受けました。その度に感じる事を解決する方法は、決して学校教育でのIT関連授業では無いと考えます。
ちなみに、学校と言う場所を利用した課外授業的なものでこう言った事柄を取り扱う事に関しては一定の理解を示しますが、やはり、技術の進歩の事を考えると設備のあり方など多くの問題を残します。
私なら会費を集め、それで数台のDOS/V機を組ませ、翌年バラしてまた組むと言う方法をとるかな〜。新しい部品は新しい会員の会費で買い、古い部品を使いまわせるだけ使いまわす。すると、新しい部品の役割と、古い部品の再利用価値とを教えることが同時に出来るかと思いますが…。
さて、では、IT関連の技術はどこで学ぶか?と言う問題ですが、これはやはり各自での働きかけ次第とするのが最も妥当でしょう。ただ、りんしおんさんの要に独学で学ぶのは効率的ではありません。IT関連の技術を学べる環境にある人はその環境を利用すればよいのですが、そういった環境の無い人には「パソコン教室」や「専門学校」の利用によって環境を確保するのが一番得策だと考えます。また、これらの場所を利用する際には、利用しやすいような制度を国や地方で確立しておく事も勿論重要ですが…。
私がこう言った方向を示すのには、ハッキリとした理由があります。それはPCの活用法には各人により大きな開きがあり、その後の技術的な進歩に対する使用者の態度にも大きな違いがあると言う事が最も大きな理由です。
つまり、PCが無ければ仕事が成立しない人から、ゲームやネットだけ出来ればイイやと言う人から、年末に年賀状しか作らないしと言う人まで、その格差は余りに大きい。こう言った事を他の教科と同様に「教養」として「学校」で教えると言う事には、少なくとも私は積極的にはなれません。
やはり、IT関連知識・技術の習得は「各人の必要に応じて各人で」行うべきだろうと考えるのです。私は今までに多くの人からPCやネットに関する相談を受けました。その度に感じる事を解決する方法は、決して学校教育でのIT関連授業では無いと考えます。
ちなみに、学校と言う場所を利用した課外授業的なものでこう言った事柄を取り扱う事に関しては一定の理解を示しますが、やはり、技術の進歩の事を考えると設備のあり方など多くの問題を残します。
私なら会費を集め、それで数台のDOS/V機を組ませ、翌年バラしてまた組むと言う方法をとるかな〜。新しい部品は新しい会員の会費で買い、古い部品を使いまわせるだけ使いまわす。すると、新しい部品の役割と、古い部品の再利用価値とを教えることが同時に出来るかと思いますが…。
>きぃガチャたん様
お返事が遅くなりました。色々とご意見を賜りましてありがとうございます。私は「勉強なんて自分でやりたくなったらやるし、その方法さえ教えればいいと思う」とのご意見に強く頷くものです。
全くその通りです。学校は「学問」を教えるところです。しかし、実質的・本来的には「学問をしたい人にその方法論を説き門戸を開く」場所であるべきだと私は考えています。
つまり、「数学やりたい」と思う。ならば「どうしたら」それが出来るかと言う、その「どうしたら」の部分を教えるだけで良いと思うのです。後は、各自で勝手に進めればよいではありませんか。そして、教員はその「各人の勝手」にそっと手を貸せばよいのです。私は、学校と言う場の理想形をこう考えています。
そして、こう言った思想の上に立って小・中学校では徹底した「詰め込み教育」をするべきだとも考えています。誤解をされるかもしれません。確かに私は「小・中学校での詰め込み教育」を大いに奨励します。しかし、これには条件がいくつもあります。「学問する方法論として必要な知識の徹底的な抽出」「その知識を効率的に伝達するのに最良な方法の確立」そして「詰め込める能力応じた授業方法」等です。
特に最後の「詰め込める能力応じた授業方法」は私の目指す「ゆとり教育」に最も必要な議論です。ある人が理科では適正を発揮できなければ、最低限の知識の確認で済ませ、理科での負担を取り除く。しかし、国語での適正を発揮すれば授業内容の100%を詰め込み、更にその上を目指させる。こう言った柔軟性が最も必要であろうと思うし、この柔軟性を確立することは、実は全く難しい事ではないはずなのだと考えています。
それと、「正直者がバカを見る」と言う事は本当に残念です。私にとっても、この数年この言葉が最も気にかかる言葉の一つです。こと教育に絞って考えれば、「正直な先生」「正直な生徒」こう言った人たちが一番ワリを喰っている。これは本当に悲しい現実です。
お返事が遅くなりました。色々とご意見を賜りましてありがとうございます。私は「勉強なんて自分でやりたくなったらやるし、その方法さえ教えればいいと思う」とのご意見に強く頷くものです。
全くその通りです。学校は「学問」を教えるところです。しかし、実質的・本来的には「学問をしたい人にその方法論を説き門戸を開く」場所であるべきだと私は考えています。
つまり、「数学やりたい」と思う。ならば「どうしたら」それが出来るかと言う、その「どうしたら」の部分を教えるだけで良いと思うのです。後は、各自で勝手に進めればよいではありませんか。そして、教員はその「各人の勝手」にそっと手を貸せばよいのです。私は、学校と言う場の理想形をこう考えています。
そして、こう言った思想の上に立って小・中学校では徹底した「詰め込み教育」をするべきだとも考えています。誤解をされるかもしれません。確かに私は「小・中学校での詰め込み教育」を大いに奨励します。しかし、これには条件がいくつもあります。「学問する方法論として必要な知識の徹底的な抽出」「その知識を効率的に伝達するのに最良な方法の確立」そして「詰め込める能力応じた授業方法」等です。
特に最後の「詰め込める能力応じた授業方法」は私の目指す「ゆとり教育」に最も必要な議論です。ある人が理科では適正を発揮できなければ、最低限の知識の確認で済ませ、理科での負担を取り除く。しかし、国語での適正を発揮すれば授業内容の100%を詰め込み、更にその上を目指させる。こう言った柔軟性が最も必要であろうと思うし、この柔軟性を確立することは、実は全く難しい事ではないはずなのだと考えています。
それと、「正直者がバカを見る」と言う事は本当に残念です。私にとっても、この数年この言葉が最も気にかかる言葉の一つです。こと教育に絞って考えれば、「正直な先生」「正直な生徒」こう言った人たちが一番ワリを喰っている。これは本当に悲しい現実です。
皆様へ。
本当に、いちいち頷きながら読んでしまいました。
(いつものことなのですけれども…^^;)
「独学で」とつい言ってしまったのですが、確かに無理ですね;;。これからの作業は、と言っておいた方が良いかも知れませんが。
以前は今と全く違った職種で働いていました。
パソコンは電源の入れ方と切り方、位しか知らなかったので、習わないといけないかな?と思い、上司に聞いた所、
「大丈夫!わしも使えないから!!あっはははは」
と笑い飛ばされ、かなり驚きました…仕方なく、ワードで文章を打つ仕事(パソコン自体はその位の利用)のため、所長&私しかいない職場だったので、することがない時は、何でもパソコンで打つようにしていました。
文書を作るのが仕事で、文字をそれなりの速度で打つことが必要だったからです。
おおらかなのに、細かい心遣いの所長を今でもとても尊敬しています。
ほんの二日ほど前、とうとう私のデスクにも、PCが置かれました。
最新型?っぽい、ステキなノートパソコンです。
でも、今の仕事でパソコンを使ってしたいことは、前にしていた文書作りとは違います。
仕事でパソコンを使うのは、おいおい、人に聞きつつ、何とかしていかないと無理だと思っています。
また、前の仕事と違い、聞く人がいると言うことだけでもある意味助かるのですけれども^^;
少しでも黒板がにぎやかになるように、
子供達が楽しく学習するために、
手書きも大事にして、せっかくなので文明の利器の力も借りて、頑張っていきたいなと思っています。
「道具は使うもので使われるものではない。」
本当に、大事な言葉ですね。
忙しくするために、道具を使っている訳ではない、と言うお話、本当にそうですね。。。
今まではゲームとネット、年賀状をパソコンでしてきましたが、唯一、年賀状は返って私には面倒くさい作業でした。。。
去年届いた年賀状を見て、今年書けば良い!と、字を書くことがそう嫌いでない私は思ってしまうのです…。
こういう選択を一つ一つ、自分に合ったようにしていけば良い、と言うことだと、はっとしました。
どこまで何を使うかは、人それぞれ。
そこにある「心」を失わぬようにしていきたいと思います。
そして、最後に、
加学究様の言うように、
『基礎的な「変化しない」技術こそ軽視せずに教えるべきだ』
には、心から賛成します。
仕事柄みなさんより幼い児童を相手に考えてしまうのですが、同じ事を書いたつもりです。
自分の手から生まれることをまず知っていって欲しい。
私は決してPC技術自体が大事だ、と書いたつもりはないのです。
教員の力を、PCを扱う技術力だけで判断するなんて、以ての外だと思っています。
ただ、時代に沿って、必要になるものもあり、
その力が全くない(ゲームやネットじゃ仕事に生かせないので^^;)のはいけない、先生たる者は、幅広く、いろんな事に興味を持って、良い所、悪い所を見極めつつ、取り入れる所は取り入れていかなくてはいけないと思います。
偉そうなことは言えませんが、駄目なことは絶対に「ダメだ!」と言わなくてはいけないこともあるけれど、
頑なに「ゲームなんてダメだ!」みたいに言う先生を良いとも思えないんです。
またうまく言えなくなってきました^^;
でも、本当に、皆さんの意見、参考になります。
心に刻む言葉もいっぱいあります。
私は明日で一旦勤務が終了しますが、また、4月から新たな気持ちで頑張っていけるようにしたいと思います。
これからもご指導よろしくお願い致します。
内容が定まらず、その上長文になったのにお付き合いいただいてありがとうございました。
本当に、いちいち頷きながら読んでしまいました。
(いつものことなのですけれども…^^;)
「独学で」とつい言ってしまったのですが、確かに無理ですね;;。これからの作業は、と言っておいた方が良いかも知れませんが。
以前は今と全く違った職種で働いていました。
パソコンは電源の入れ方と切り方、位しか知らなかったので、習わないといけないかな?と思い、上司に聞いた所、
「大丈夫!わしも使えないから!!あっはははは」
と笑い飛ばされ、かなり驚きました…仕方なく、ワードで文章を打つ仕事(パソコン自体はその位の利用)のため、所長&私しかいない職場だったので、することがない時は、何でもパソコンで打つようにしていました。
文書を作るのが仕事で、文字をそれなりの速度で打つことが必要だったからです。
おおらかなのに、細かい心遣いの所長を今でもとても尊敬しています。
ほんの二日ほど前、とうとう私のデスクにも、PCが置かれました。
最新型?っぽい、ステキなノートパソコンです。
でも、今の仕事でパソコンを使ってしたいことは、前にしていた文書作りとは違います。
仕事でパソコンを使うのは、おいおい、人に聞きつつ、何とかしていかないと無理だと思っています。
また、前の仕事と違い、聞く人がいると言うことだけでもある意味助かるのですけれども^^;
少しでも黒板がにぎやかになるように、
子供達が楽しく学習するために、
手書きも大事にして、せっかくなので文明の利器の力も借りて、頑張っていきたいなと思っています。
「道具は使うもので使われるものではない。」
本当に、大事な言葉ですね。
忙しくするために、道具を使っている訳ではない、と言うお話、本当にそうですね。。。
今まではゲームとネット、年賀状をパソコンでしてきましたが、唯一、年賀状は返って私には面倒くさい作業でした。。。
去年届いた年賀状を見て、今年書けば良い!と、字を書くことがそう嫌いでない私は思ってしまうのです…。
こういう選択を一つ一つ、自分に合ったようにしていけば良い、と言うことだと、はっとしました。
どこまで何を使うかは、人それぞれ。
そこにある「心」を失わぬようにしていきたいと思います。
そして、最後に、
加学究様の言うように、
『基礎的な「変化しない」技術こそ軽視せずに教えるべきだ』
には、心から賛成します。
仕事柄みなさんより幼い児童を相手に考えてしまうのですが、同じ事を書いたつもりです。
自分の手から生まれることをまず知っていって欲しい。
私は決してPC技術自体が大事だ、と書いたつもりはないのです。
教員の力を、PCを扱う技術力だけで判断するなんて、以ての外だと思っています。
ただ、時代に沿って、必要になるものもあり、
その力が全くない(ゲームやネットじゃ仕事に生かせないので^^;)のはいけない、先生たる者は、幅広く、いろんな事に興味を持って、良い所、悪い所を見極めつつ、取り入れる所は取り入れていかなくてはいけないと思います。
偉そうなことは言えませんが、駄目なことは絶対に「ダメだ!」と言わなくてはいけないこともあるけれど、
頑なに「ゲームなんてダメだ!」みたいに言う先生を良いとも思えないんです。
またうまく言えなくなってきました^^;
でも、本当に、皆さんの意見、参考になります。
心に刻む言葉もいっぱいあります。
私は明日で一旦勤務が終了しますが、また、4月から新たな気持ちで頑張っていけるようにしたいと思います。
これからもご指導よろしくお願い致します。
内容が定まらず、その上長文になったのにお付き合いいただいてありがとうございました。
「ゲームなんてダメだ!」と言う話題についてですが、この話題は他のコミュでも繰り広げられた議論なのですが、ちょっと私の考えを書いておきたいと思います。
私はいわゆる「ゲーム世代」です。ファミコンに小学校2〜3年生の時に出会い、その後はずっとゲームと一緒に成長しました。今でも時間があればゲームして遊びます(遊ぶ時間も少なくなりましたが…)。
では、私にとって、「ゲーム」とは何か?それは「知識形成のキッカケ」に他なりません。勿論、やってて面白い「遊び」でもあったわけですが…。
まあ月並みですが、『三国志(光栄)』で中国史のキッカケを、『信長の野望(光栄)』で日本の中世と日本地理、『維新の嵐(光栄)』で幕末、『大航海時代(光栄)』で世界史・世界地理、『女神転生(ナムコ)』で各国の神話や宗教と言った具合ですw嗚呼、月並みだなあ〜w
現在の私の持つ知識の多くは、これらのゲームによってもたらされた知識をキッカケとして得られたわけです。すると、今の私はゲーム無しには存在しなかったと言っても過言では無いのですね。だから、ゲームは私にとって非常に「有用」なものであったワケですから、私が「ゲーム」の教育に与える影響を考えた時、どうしても好意的に捉えてしまいがちです。
ただ、昨今は私が考えるような「単純な」理由でコトを考えていられなくなって来たように思います。例えば、さっきの「『三国志(光栄)』で中国史」と言う事例を考えて見たいと思います。すると、「三国志」を舞台としたゲームは今でも沢山あります。しかし、生徒達に聞いてみると、不思議な事にここから派生しないのです。
私達の頃、「三国志」をゲームでやれば、当然といって良いくらい「横山光輝の三国志」を読みました。更に吉川英治の「三国志」があり、更に更に立間祥介や村上知行の「三国志」があり、行きつく先には今鷹真らによる「正史三国志」があったワケです。まあ、ここまできたら大した物ですが、しかしながら中学生で「横光三国志」読破は特異な例では無かった様に思います。
ところがです、今の高校生に聞いてみると「横光三国志」すら読んでいないと言う子が大半です。
ゲームはやっている。
↓
三国志ネタのゲームも当然やっている。
↓
でも、三国志は知らない。
と言う構図です。そして、この構図は他のゲームでもそうなんです。神話を主題にしたゲームをしてもその神話を知らないと言うんですね。そして、ここが非常に不思議なんですが、その「知らないと言う状態」に違和感を覚えないと言うんですね。一体この精神構造はどう言う物かと言う事ですね。
ちょっと長くなりました。
続きはまた、後ほど。
私はいわゆる「ゲーム世代」です。ファミコンに小学校2〜3年生の時に出会い、その後はずっとゲームと一緒に成長しました。今でも時間があればゲームして遊びます(遊ぶ時間も少なくなりましたが…)。
では、私にとって、「ゲーム」とは何か?それは「知識形成のキッカケ」に他なりません。勿論、やってて面白い「遊び」でもあったわけですが…。
まあ月並みですが、『三国志(光栄)』で中国史のキッカケを、『信長の野望(光栄)』で日本の中世と日本地理、『維新の嵐(光栄)』で幕末、『大航海時代(光栄)』で世界史・世界地理、『女神転生(ナムコ)』で各国の神話や宗教と言った具合ですw嗚呼、月並みだなあ〜w
現在の私の持つ知識の多くは、これらのゲームによってもたらされた知識をキッカケとして得られたわけです。すると、今の私はゲーム無しには存在しなかったと言っても過言では無いのですね。だから、ゲームは私にとって非常に「有用」なものであったワケですから、私が「ゲーム」の教育に与える影響を考えた時、どうしても好意的に捉えてしまいがちです。
ただ、昨今は私が考えるような「単純な」理由でコトを考えていられなくなって来たように思います。例えば、さっきの「『三国志(光栄)』で中国史」と言う事例を考えて見たいと思います。すると、「三国志」を舞台としたゲームは今でも沢山あります。しかし、生徒達に聞いてみると、不思議な事にここから派生しないのです。
私達の頃、「三国志」をゲームでやれば、当然といって良いくらい「横山光輝の三国志」を読みました。更に吉川英治の「三国志」があり、更に更に立間祥介や村上知行の「三国志」があり、行きつく先には今鷹真らによる「正史三国志」があったワケです。まあ、ここまできたら大した物ですが、しかしながら中学生で「横光三国志」読破は特異な例では無かった様に思います。
ところがです、今の高校生に聞いてみると「横光三国志」すら読んでいないと言う子が大半です。
ゲームはやっている。
↓
三国志ネタのゲームも当然やっている。
↓
でも、三国志は知らない。
と言う構図です。そして、この構図は他のゲームでもそうなんです。神話を主題にしたゲームをしてもその神話を知らないと言うんですね。そして、ここが非常に不思議なんですが、その「知らないと言う状態」に違和感を覚えないと言うんですね。一体この精神構造はどう言う物かと言う事ですね。
ちょっと長くなりました。
続きはまた、後ほど。
前の書き込みで「後ほど」とか言っておきながら…(苦笑)。
-------------------------------------
教員給与に残業手当=教職調整額見直しの方向−勤務時間管理など課題も・文科省
(時事通信社 - 02月09日 15:01)
文部科学省は9日、公立小中学校の教員給与に、時間外勤務手当を導入する方向で検討に入った。仕事のどこからが残業かを明確に区分することが難しい教員については現行、給与月額の4%を残業分とみなした「教職調整額」が一律支給されているが、同省は勤務実態に応じた公平な配分に改める方針だ。
手当支給により教員の勤務意識に大きな変化が生じることが予想されるほか、学校側が残業時間を厳密に管理できるかといった課題もあり、議論を呼ぶのは必至。同省は、今夏の2009年度予算概算要求までに結論をまとめる。
教職現場では「教員の勤務は自発的なもの」との理念の下、「残業」という概念がない。調整額は、繁忙時でも休職中でも一律支給になっている。同省は昨年、勤務の負担に応じて調整額を増減させる改革案を検討したが、法的な問題から断念。時間外勤務手当に転換する案を軸に、再検討することにした。
-------------------------------------
本日、上記のような記事がニュースに上がりました。日記の書き込みは予想通り「賛否両論」です。ただ、今回のこの記事の書き込みを一通り読んでみて感じた事があります。それは、以前と比べて同種のニュースに対する皆さんの反応が随分と質の高いものになった、そして心無い書き込みは減ったと思います。
「賛成」を言うにも「反対」を言うにも、それなりに根拠を持ち、思わず考えさせられる意見が多く見受けられるように感じました。
確かに、この様なかたちでの残業代の支給は、おかしな歪みをもたらす恐れもあるわけですが、現今の教員を取巻く労働環境を考えれば当然だと言う意見も、片方に勿論あるわけです。また、日記の書き込みの中には「教育予算」の問題に踏み込んだものもあり、確かに「財源確保」をどうするかと言う議論も重要だろうと思います。
しばらくここも沈静化してしまっています(ま、まあ、私が悪いんですが…汗)。お考えをお聞かせ願えれば幸いです。
-------------------------------------
教員給与に残業手当=教職調整額見直しの方向−勤務時間管理など課題も・文科省
(時事通信社 - 02月09日 15:01)
文部科学省は9日、公立小中学校の教員給与に、時間外勤務手当を導入する方向で検討に入った。仕事のどこからが残業かを明確に区分することが難しい教員については現行、給与月額の4%を残業分とみなした「教職調整額」が一律支給されているが、同省は勤務実態に応じた公平な配分に改める方針だ。
手当支給により教員の勤務意識に大きな変化が生じることが予想されるほか、学校側が残業時間を厳密に管理できるかといった課題もあり、議論を呼ぶのは必至。同省は、今夏の2009年度予算概算要求までに結論をまとめる。
教職現場では「教員の勤務は自発的なもの」との理念の下、「残業」という概念がない。調整額は、繁忙時でも休職中でも一律支給になっている。同省は昨年、勤務の負担に応じて調整額を増減させる改革案を検討したが、法的な問題から断念。時間外勤務手当に転換する案を軸に、再検討することにした。
-------------------------------------
本日、上記のような記事がニュースに上がりました。日記の書き込みは予想通り「賛否両論」です。ただ、今回のこの記事の書き込みを一通り読んでみて感じた事があります。それは、以前と比べて同種のニュースに対する皆さんの反応が随分と質の高いものになった、そして心無い書き込みは減ったと思います。
「賛成」を言うにも「反対」を言うにも、それなりに根拠を持ち、思わず考えさせられる意見が多く見受けられるように感じました。
確かに、この様なかたちでの残業代の支給は、おかしな歪みをもたらす恐れもあるわけですが、現今の教員を取巻く労働環境を考えれば当然だと言う意見も、片方に勿論あるわけです。また、日記の書き込みの中には「教育予算」の問題に踏み込んだものもあり、確かに「財源確保」をどうするかと言う議論も重要だろうと思います。
しばらくここも沈静化してしまっています(ま、まあ、私が悪いんですが…汗)。お考えをお聞かせ願えれば幸いです。
----------------
<中教審>全大学で職業指導 来年度からの導入を目指す
(毎日新聞 - 07月15日 15:03)
就職後すぐに離職する若者が増えるなど、学生の職業・勤労観形成が課題になっているとして、中央教育審議会大学分科会は、すべての大学や短大で「職業指導(キャリアガイダンス)」の授業を導入する方向で検討を始めた。科目として義務化するか、各大学に努力義務を課すにとどめるかなど、具体的な制度設計を急ぎ、早ければ来年度からの導入を目指す。【加藤隆寛】
同分科会の作業部会が「社会人として必要な資質能力を高めるためにも、職業指導を教育課程に位置付けることが必要」と提案し、14日の会議で大筋了承された。
分科会の委員からは「大学には本来(職業について)何らかの意図を持って入るはず」との意見も出されたが、「将来が見通しにくい社会構造になっている」などとして、入学してから職業意識の形成を図ることや、自分の適性を考えることの必要性を認める意見が大勢を占めた。
1〜2年次の選択科目などを想定しており、大学設置基準の改正なども視野に議論する。文部科学省によると、既に74%の大学が職業意識に関する何らかの科目を設置済み。分科会では、これらの授業内容を分析した上で、適切な授業のあり方などを探る。厚生労働省のまとめでは、05年の大学卒業者の入社3年以内の離職率は35.9%。
----------------
こりゃ…、教員免許更新制度並みにダメな方針打ち出したな。
百害あって一利無し、と言うのが正直な感想です。
これでは解決すべき問題が何も解決できない。
<中教審>全大学で職業指導 来年度からの導入を目指す
(毎日新聞 - 07月15日 15:03)
就職後すぐに離職する若者が増えるなど、学生の職業・勤労観形成が課題になっているとして、中央教育審議会大学分科会は、すべての大学や短大で「職業指導(キャリアガイダンス)」の授業を導入する方向で検討を始めた。科目として義務化するか、各大学に努力義務を課すにとどめるかなど、具体的な制度設計を急ぎ、早ければ来年度からの導入を目指す。【加藤隆寛】
同分科会の作業部会が「社会人として必要な資質能力を高めるためにも、職業指導を教育課程に位置付けることが必要」と提案し、14日の会議で大筋了承された。
分科会の委員からは「大学には本来(職業について)何らかの意図を持って入るはず」との意見も出されたが、「将来が見通しにくい社会構造になっている」などとして、入学してから職業意識の形成を図ることや、自分の適性を考えることの必要性を認める意見が大勢を占めた。
1〜2年次の選択科目などを想定しており、大学設置基準の改正なども視野に議論する。文部科学省によると、既に74%の大学が職業意識に関する何らかの科目を設置済み。分科会では、これらの授業内容を分析した上で、適切な授業のあり方などを探る。厚生労働省のまとめでは、05年の大学卒業者の入社3年以内の離職率は35.9%。
----------------
こりゃ…、教員免許更新制度並みにダメな方針打ち出したな。
百害あって一利無し、と言うのが正直な感想です。
これでは解決すべき問題が何も解決できない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
非常勤講師、無責任に教育を語る 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
非常勤講師、無責任に教育を語るのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82977人
- 2位
- 暮らしを楽しむ
- 77062人
- 3位
- 福岡 ソフトバンクホークス
- 42915人