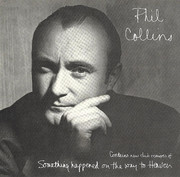|
|
|
|
コメント(20)
1982年に、大ヒットが期待されながら何故か売れなかった曲が、スティーヴ・ウィンウッドの"Valerie"「♪青空のヴァレリー」という曲でした。同曲は1982年にUK51位、米ビルボード・ホット100でピーク70位と不発に終わりました。
この曲の2年前、ウィンウッドの1980年のシングル"While You See A Chance"「♪ユー・シー・ア・チャンス」は、UK45位と英では不発でしたが、米ではビルボード・ホット100でピーク7位と好成績だったので、「♪…ヴァレリー」も同様にアメリカではヒットするだろうと思われたのですが…。
アメリカのシンガー・ソングライター:ヴァレリー・カーターに捧げられたとされるこの曲、「♪ユー・シー・ア・チャンス」と同系統の高揚感のあるポップ曲でしたが米での大ヒットを継続できませんでした。しかし5年後に大復活する事になります。
まず、82年のヒットしなかったバージョンを先に載せますね。<左>は日本盤ジャケット。清涼感のあるシンセ・ポップでした。
STEVE WINWOOD - VALERIE (1982 official video HD)
https://www.youtube.com/watch?v=Sr4T0glu9Kc&ab_channel=80sRec
この曲の2年前、ウィンウッドの1980年のシングル"While You See A Chance"「♪ユー・シー・ア・チャンス」は、UK45位と英では不発でしたが、米ではビルボード・ホット100でピーク7位と好成績だったので、「♪…ヴァレリー」も同様にアメリカではヒットするだろうと思われたのですが…。
アメリカのシンガー・ソングライター:ヴァレリー・カーターに捧げられたとされるこの曲、「♪ユー・シー・ア・チャンス」と同系統の高揚感のあるポップ曲でしたが米での大ヒットを継続できませんでした。しかし5年後に大復活する事になります。
まず、82年のヒットしなかったバージョンを先に載せますね。<左>は日本盤ジャケット。清涼感のあるシンセ・ポップでした。
STEVE WINWOOD - VALERIE (1982 official video HD)
https://www.youtube.com/watch?v=Sr4T0glu9Kc&ab_channel=80sRec
この後、ウィンウッドは1986年の「♪ハイヤー・ラヴ」の全米No.1と、収録アルバムの「バック・イン・ザ・ハイ・ライフ」の1986年の大成功のお陰でグラミー賞を受賞、1987年にはキャリア初のソロ・ベスト盤「クロニクルズ」を発表、そこからの1stシングルとして"Valerie"のリミックス版「♪青空のヴァレリー'87」<左>を発表します。
こちらのバージョンはUK19位、米ビルボード・ホット100でピーク9位とヒットを記録します。両曲を聴き比べてみると、ボーカル自体には一切手を加えておらず、ドラムやベースのリズム隊を重乗して厚目にしてあります。これはトム・ロード=アルジのリミックスによるものです。
ここに、1982年頃の軽いシンセ・ポップの流行と、1987年頃の、分厚い重低音を押し出したサウンドの流行の趨勢の違いを見ることが出来ます。
上記の5年間で、ヒット・ポップスに求められる音質(音楽スタイルに非ず)が確実に変化していたことを指し示す例として一番分かり易い例を挙げました。
Steve Winwood - Valerie (1987 Version)
https://www.youtube.com/watch?v=xOTjkQMdF6o
一旦ここでお休みします。
こちらのバージョンはUK19位、米ビルボード・ホット100でピーク9位とヒットを記録します。両曲を聴き比べてみると、ボーカル自体には一切手を加えておらず、ドラムやベースのリズム隊を重乗して厚目にしてあります。これはトム・ロード=アルジのリミックスによるものです。
ここに、1982年頃の軽いシンセ・ポップの流行と、1987年頃の、分厚い重低音を押し出したサウンドの流行の趨勢の違いを見ることが出来ます。
上記の5年間で、ヒット・ポップスに求められる音質(音楽スタイルに非ず)が確実に変化していたことを指し示す例として一番分かり易い例を挙げました。
Steve Winwood - Valerie (1987 Version)
https://www.youtube.com/watch?v=xOTjkQMdF6o
一旦ここでお休みします。
1982年と1987年のそれぞれの年のフリートウッド・マックのアルバムの1stシングルを比較してみて、どうでしょうか?作者がクリスティン・マクヴィーからリンジー・バッキンガムに変わったものの、大きく気づかされるのは「ヒット曲のマイナー調化」という事だと思います。
この傾向は1982年のヒット曲から、1987年の多くのヒット曲に起きた現象で、以前も書きましたが、80sのトレンド・セッターだったマイケル・ジャクソンやマドンナの大ヒット曲を中心に、ポップス界全体に起きていた現象と捉えることが出来ます。
なにぶん、1982年から1987年にかけての5年間に、続けてヒット曲を出し続けられるアーティストは限られて来ますから、米ビルボード誌にランクインした全てのアーティストでなく、ヒット曲を出し続けられた、限られた幸運なアクトは探すと限られて来るのですが、単発のヒット曲しか出せなかったアクトに付いてもこの傾向は言える事だと思います。つまり各々のアクトだけでなく、ビルボード誌のトップ40にランクインした、だいたいのアクトのヒット曲たちに言えることです。
まとめますと、1982→1987年の5年間に起きたヒット曲の傾向の変化として
・リズム・セクション(特にドラム)の深度の拡大(エコー音の増大など)
・マイナー調化
この2つの大きな変化が挙げられると思います。
この傾向は1982年のヒット曲から、1987年の多くのヒット曲に起きた現象で、以前も書きましたが、80sのトレンド・セッターだったマイケル・ジャクソンやマドンナの大ヒット曲を中心に、ポップス界全体に起きていた現象と捉えることが出来ます。
なにぶん、1982年から1987年にかけての5年間に、続けてヒット曲を出し続けられるアーティストは限られて来ますから、米ビルボード誌にランクインした全てのアーティストでなく、ヒット曲を出し続けられた、限られた幸運なアクトは探すと限られて来るのですが、単発のヒット曲しか出せなかったアクトに付いてもこの傾向は言える事だと思います。つまり各々のアクトだけでなく、ビルボード誌のトップ40にランクインした、だいたいのアクトのヒット曲たちに言えることです。
まとめますと、1982→1987年の5年間に起きたヒット曲の傾向の変化として
・リズム・セクション(特にドラム)の深度の拡大(エコー音の増大など)
・マイナー調化
この2つの大きな変化が挙げられると思います。
上記の5年間に起きた変化の直接の原因として、ヒット曲のエンジニアの存在が挙げられると思います。>>[2]に挙げたトム・ロード=アルジ<左>や、ロッド・スチュワートやスティーヴィー・ニックスのヒット曲に、エンジニアとしては勿論、インタースコープ・レーベルの社長になってしまったジミー・アイオヴィンと共にプロデュースにも関わったエンジニア兼共同プロデューサーのボブ・クリアマウンテン<右>などの人材の名前が挙げられます。
他にも、こうしたポップ音楽の趨勢の変化をヒット・チャートにもたらしたプロデューサーとして、アナログの側からは元シックのバーナード・エドワース、デジタルの側からは元ザ・タイムのジミー・ジャム&テリー・ルイスと云った人たちの名前が挙げられると思います。
他にも、こうしたポップ音楽の趨勢の変化をヒット・チャートにもたらしたプロデューサーとして、アナログの側からは元シックのバーナード・エドワース、デジタルの側からは元ザ・タイムのジミー・ジャム&テリー・ルイスと云った人たちの名前が挙げられると思います。
>>[7]、スティーヴ・ウィンウッドは一番有名なのがその「♪ハイヤー・ラヴ」で、チャカ・カーンのコーラスやナイル・ロジャースのギター参加など、PVがまるで、ウィンウッドのファン大会みたいになってましたね、
それ以前のヒット、お書きの「♪ヴァレリー」のソロヒットは、1982年の打ち込みサウンドで、ポップだけど少しチープな感じがしましたね。前者が5年後の1987年に、お書きのようにバンド・サウンドでヒットしてみごと雪辱を果たしたという感じでした。
この人も経歴が長いんですよね。60sはスペンサー・デイヴィス・グループ、70sはトラフィックというバンドでそれぞれヒットを持っていますし、2025年現在まだ現役で、オリジナル・メンバーで復活したどぅービー・ブラザーズと一緒にツアーをしたそうですから、相当に息の長い第一線活動をしてる一人だと思いますね。
それ以前のヒット、お書きの「♪ヴァレリー」のソロヒットは、1982年の打ち込みサウンドで、ポップだけど少しチープな感じがしましたね。前者が5年後の1987年に、お書きのようにバンド・サウンドでヒットしてみごと雪辱を果たしたという感じでした。
この人も経歴が長いんですよね。60sはスペンサー・デイヴィス・グループ、70sはトラフィックというバンドでそれぞれヒットを持っていますし、2025年現在まだ現役で、オリジナル・メンバーで復活したどぅービー・ブラザーズと一緒にツアーをしたそうですから、相当に息の長い第一線活動をしてる一人だと思いますね。
バーナード・エドワーズの仕事と、ジャム&ルイスの仕事を比較できる一番の好例が有りました。
まず後者のプロデュースによるデジタル・ビートの一例として、シェレール(Cherrelle)の"I Didn't Mean To Turn You On"「♪ターン・ユー・オン」のPVを貼ります。同曲は1984年米ビルボード・ホット100でピーク79位、米R&Bチャートでピーク8位でした。
1984年の時点でデジタル・ビートを扱っていたジャム&ルイスは、やがて1980年代後半にはジャネット・ジャクソンの一連の大ヒットでセンセーションを巻き起こします。
画像は収録盤「フラジャイル」の日本盤CDです。
Cherrelle - I didn't Mean to Turn You On
https://www.youtube.com/watch?v=8BV1Ft4BQ1o&ab_channel=lozleo
まず後者のプロデュースによるデジタル・ビートの一例として、シェレール(Cherrelle)の"I Didn't Mean To Turn You On"「♪ターン・ユー・オン」のPVを貼ります。同曲は1984年米ビルボード・ホット100でピーク79位、米R&Bチャートでピーク8位でした。
1984年の時点でデジタル・ビートを扱っていたジャム&ルイスは、やがて1980年代後半にはジャネット・ジャクソンの一連の大ヒットでセンセーションを巻き起こします。
画像は収録盤「フラジャイル」の日本盤CDです。
Cherrelle - I didn't Mean to Turn You On
https://www.youtube.com/watch?v=8BV1Ft4BQ1o&ab_channel=lozleo
このジャム&ルイス制作のシェレールの曲を、ロバート・パーマーがカバーして大ヒットさせました、1984年の収録盤「リップタイド」<左>から、何と5弾目のシングルとして1986年に米ビルボード・ホット100でピーク2位の大ヒットになりました。
デジタル・ビートのシェレールの方が前で、人力演奏のロバート・パーマー版が後で…と時間的には倒錯してるカバーでしたが、それだけ1980年代のサウンド・プロダクションはプロデューサー戦国時代にあったとも言えそうですね。
Robert Palmer - I Didn't Mean To Turn You On (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=lyNa-ReeZc8&ab_channel=RobertPalmerVEVO
デジタル・ビートのシェレールの方が前で、人力演奏のロバート・パーマー版が後で…と時間的には倒錯してるカバーでしたが、それだけ1980年代のサウンド・プロダクションはプロデューサー戦国時代にあったとも言えそうですね。
Robert Palmer - I Didn't Mean To Turn You On (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=lyNa-ReeZc8&ab_channel=RobertPalmerVEVO
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
80's MANIACS (Gay Only) 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-