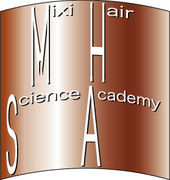ちょっとお聞きしたいのですか、某メーカーは、薬剤の容器にチオ濃度、PH、アルカリ度の順で694みたいな感じで、書いてあります。還元剤の濃度やPHは、比較的色々なメーカーは、書いてあったり教えてくれたりしますが、アルカリ度や酸度は、基本的に表記されていません。このアルカリ度や酸度ってあまり重要ではないのですか?。また、知り合いが水100ccに対して1グラムのクエン酸を入れると酸度1になると言って、アルカリ度4の薬剤にクエン酸を添加して、アルカリ度が3になると言って使い、中性のシステアミン等も、同じように酸度がいくつという感覚で、PHがどう変化しているかわからないのに使用しています。アルカリ度や酸度だけで薬剤の特性を判断して良いものなのか?僕は、疑問です。アルカリ度や酸度の重要性、それにともないPHの重要性を、わかりやすく教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
|
|
|
|
コメント(10)
すいません。質問の意味がよくわからないのですが、、、、、
酸度とかアルカリ度ってphの事じゃないのですか?
アルカリにするのも酸性にするのも色々薬剤ありますよね?
メーカーの自主規制では、化粧品登録の場合、チオ濃度換算で2%までとなってます。
医薬部外品では6%を越えるチオ濃度の物も多々あります。
化粧品登録の薬剤であれば、スピエラ2,5%、シスアミ1.6%チオ2%となります。
アルカリに向けるのに、モノエタとかアルギニンとか、酸性ならクエン酸、ホウ酸、
それぞれの特性により濃度は変わりますよね?
だから、あまりアルカリ度、酸度に過敏にならなくてもいいと思います。
phの重要性は、アルカリ軟化と関係してきます。phが高ければチオ濃度が多少低くて
も還元力は高いです。
髪質にもよりますが、濃度と還元力は密接に関係して来ます。
最近のシスアミとかチオグリセリン、スピエラ見たいに中性から酸性で還元力が出る
薬剤が出てきて、濃度で還元力って考えた方がわかりやすいかも?です。
酸度とかアルカリ度ってphの事じゃないのですか?
アルカリにするのも酸性にするのも色々薬剤ありますよね?
メーカーの自主規制では、化粧品登録の場合、チオ濃度換算で2%までとなってます。
医薬部外品では6%を越えるチオ濃度の物も多々あります。
化粧品登録の薬剤であれば、スピエラ2,5%、シスアミ1.6%チオ2%となります。
アルカリに向けるのに、モノエタとかアルギニンとか、酸性ならクエン酸、ホウ酸、
それぞれの特性により濃度は変わりますよね?
だから、あまりアルカリ度、酸度に過敏にならなくてもいいと思います。
phの重要性は、アルカリ軟化と関係してきます。phが高ければチオ濃度が多少低くて
も還元力は高いです。
髪質にもよりますが、濃度と還元力は密接に関係して来ます。
最近のシスアミとかチオグリセリン、スピエラ見たいに中性から酸性で還元力が出る
薬剤が出てきて、濃度で還元力って考えた方がわかりやすいかも?です。
メーカー名をだしますが、エルコスの商品は、きちんと表記されています。ちなみに、アルカリ度とPHは、別物だと教わりました。だから、その重要性を知りたいのです。ただ、エルコス以外はアルカリ度数に対してあまり触れないので、気になっているわけです。ちなみに、先にも書きましたが、694の薬剤を単純に水で二倍希釈すれば、チオ濃度や、アルカリ度は、半分になります。しかし、PHは、9のままになり、392という強さの薬剤が出来上がるわけです。つまり、アルカリ度とPHは、別ということです。つまり、クエン酸等でアルカリ度をコントロールしても、PHがどう変化したかわからないわけです。僕が言いたいのは、PHよりアルカリ度や酸度を重要視する必要があるのかということです。文章にすると、伝えたいことがうまく書けなくてすいません。
アルカリ度はここで
http://www5b.biglobe.ne.jp/~y_kodama/marineaquarium/science/contents/alkarido.html
アルカリ度とpHの関係はここ
http://www.littlewaves.info/marine/waterquality/wq_c_equilibrium.htm
これ説明しにくい毛髪科学の本の方がいいかもしれない。
バッファ剤の酸とアルカリの使用濃度のバランスでpHの値はでても
本当に酸性方向へ落ちるかはアルカリ度が使用薬液で高いとpH数値が低いだけのバッファ剤じゃ,アルカリは取りきれない。ガサの量的にも濃度的にも時間的概念なしに
これ使用規定でアルカリ度がありますね。
単純に水の量の多く流すだけでもアルカリ度は下がるはずです。
髪自体にpHはないので毛に浸透している溶液のアルカリ剤の残留度や粘性度合いでも
違ってくるのだと思います。クエン酸などの濃度に依存せずに
水の量など多めにして本来、ガサが必要なのですが、使用時間や量もpHも下げ気味で使うのでpHコントロールが実際にできてない場合がおおいのではと思います。
アルカリ度がこうだからどう処理したらいいかって事が一番問題なのでしょうね。
理想的パーマの論文を読むと我々が普段やっている処理とはいろいろな数値が書かれていてかなりかけ離れているように感じます。
水素イオン濃度のpH下がれば中和した事でこれ酸化とはまた別。
同じようにアルカリ度が高い還元剤が入りやすくなるからかかりが早い概念
還元剤濃度が低ければ、還元しないという基本的にすべてバランスなので
どれを重視するではなくてどれもバランス的に問題ではないでしょうか?
それとパーマ液の規定内でもの凄い差があるわけではなくて
その後に使う酸リンスやバッファ剤が意外と1剤に対して
使用範囲がいい加減なのかもしれません。
本来、タンパク質が大きくpH値の違う物同士を受け入れることが良い事ではないので
あまりpHが下がり過ぎなくていいわけなのは確かです。これカラーにも言える
下げ過ぎてあまりいいことないのが髪です。大量の水で流すのは
いいとして、だからいい加減なのかもしれません(笑)
また酸もアルカリも人に使うのでだいたいこのくらいの使用範囲で押さえて
おきましょうって事も書かれてます。>これが使用規定なのでしょう。
あまり答えになってなくてごめんなさい。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~y_kodama/marineaquarium/science/contents/alkarido.html
アルカリ度とpHの関係はここ
http://www.littlewaves.info/marine/waterquality/wq_c_equilibrium.htm
これ説明しにくい毛髪科学の本の方がいいかもしれない。
バッファ剤の酸とアルカリの使用濃度のバランスでpHの値はでても
本当に酸性方向へ落ちるかはアルカリ度が使用薬液で高いとpH数値が低いだけのバッファ剤じゃ,アルカリは取りきれない。ガサの量的にも濃度的にも時間的概念なしに
これ使用規定でアルカリ度がありますね。
単純に水の量の多く流すだけでもアルカリ度は下がるはずです。
髪自体にpHはないので毛に浸透している溶液のアルカリ剤の残留度や粘性度合いでも
違ってくるのだと思います。クエン酸などの濃度に依存せずに
水の量など多めにして本来、ガサが必要なのですが、使用時間や量もpHも下げ気味で使うのでpHコントロールが実際にできてない場合がおおいのではと思います。
アルカリ度がこうだからどう処理したらいいかって事が一番問題なのでしょうね。
理想的パーマの論文を読むと我々が普段やっている処理とはいろいろな数値が書かれていてかなりかけ離れているように感じます。
水素イオン濃度のpH下がれば中和した事でこれ酸化とはまた別。
同じようにアルカリ度が高い還元剤が入りやすくなるからかかりが早い概念
還元剤濃度が低ければ、還元しないという基本的にすべてバランスなので
どれを重視するではなくてどれもバランス的に問題ではないでしょうか?
それとパーマ液の規定内でもの凄い差があるわけではなくて
その後に使う酸リンスやバッファ剤が意外と1剤に対して
使用範囲がいい加減なのかもしれません。
本来、タンパク質が大きくpH値の違う物同士を受け入れることが良い事ではないので
あまりpHが下がり過ぎなくていいわけなのは確かです。これカラーにも言える
下げ過ぎてあまりいいことないのが髪です。大量の水で流すのは
いいとして、だからいい加減なのかもしれません(笑)
また酸もアルカリも人に使うのでだいたいこのくらいの使用範囲で押さえて
おきましょうって事も書かれてます。>これが使用規定なのでしょう。
あまり答えになってなくてごめんなさい。
同じアルカリ度でもアルカリ剤の種類によってはウェーブ差があります。
パーマのかかりはどちらかと言うとアルカリ度よりもpHに依存します。
アルカリ度が高いからといって、パーマ作用が強いとはいえません。
アルカリ度とはパーマ剤1剤1ml中に存在する遊離のアルカリを中和するのに
必要な0・1mol/lの塩酸(約0・32%の塩酸水溶液)の量を言います。
アルカリ度とウェーブ力にあまり関連はなく、どちらかと言えば安定した製品供給のため、品質管理的な意味合いで用いられている値である。
と以上 アリミノ発行のプロのケア力4200円に書いてありました。
間違っていたらどなたかご指摘ください。
パーマのかかりはどちらかと言うとアルカリ度よりもpHに依存します。
アルカリ度が高いからといって、パーマ作用が強いとはいえません。
アルカリ度とはパーマ剤1剤1ml中に存在する遊離のアルカリを中和するのに
必要な0・1mol/lの塩酸(約0・32%の塩酸水溶液)の量を言います。
アルカリ度とウェーブ力にあまり関連はなく、どちらかと言えば安定した製品供給のため、品質管理的な意味合いで用いられている値である。
と以上 アリミノ発行のプロのケア力4200円に書いてありました。
間違っていたらどなたかご指摘ください。
ビーカー内の溶液同士を酸とアルカリでpH値を決める緩衝液の事が説明としてはいいですかね
http://www.an.shimadzu.co.jp/support/lib/lctalk/38/38lab.htm
ここを見て実際に緩衝液を作ってみるといいかなと思います。
僕は数年前にここのデーターを元に作ってpHメーターで計ったり
pH試験紙などでも計りわずかなコントロールしてみました。
二水和物や三水和物でないと水に溶けにくいので
そういった試薬を使います。
ビーカー内で確実にアルカリに酸の容器が混ざり合うのでない髪に振りかける
流れ落ちるのと本来はかなり違いがありますからアバウトです。
洗い流す・流れ落ちるといった概念が付いてくるので
ある一定の量を断続的にやるか本来は水で流してから塗布したり
逆に例えば1L中の混合比は同じでも頭皮に安全な範囲で両者の量を多めに入れる
本来は頭皮の事を考えて薬液量は少ないので300ml位を断続的
塗布しないとpH下がらないといった感じみたいです。
実際には濃く作って量は少なめだったり断続的に洗い出す概念ではなかったりもするのでやや濃いめだったるするようです。論文によって見解が少しちがったりもしてます。
基本的に今のダメージ毛に対してバッファ剤はあまり必要ではないpH設定をして大量に使う>これ水洗に近い話です。
かなり昔は酸リンスだけで緩衝液といった物は使ってなかったですが、
今はバッファ剤(緩衝液)ですから急激に酸性方向に持っていかない方法ですね。
こら大量に使わないと指定したpHまで落ちない。流れ落ちて毛髪内の薬液量が少ないからですね。特に健康毛に近いほど落ちにくい。
http://www.an.shimadzu.co.jp/support/lib/lctalk/38/38lab.htm
ここを見て実際に緩衝液を作ってみるといいかなと思います。
僕は数年前にここのデーターを元に作ってpHメーターで計ったり
pH試験紙などでも計りわずかなコントロールしてみました。
二水和物や三水和物でないと水に溶けにくいので
そういった試薬を使います。
ビーカー内で確実にアルカリに酸の容器が混ざり合うのでない髪に振りかける
流れ落ちるのと本来はかなり違いがありますからアバウトです。
洗い流す・流れ落ちるといった概念が付いてくるので
ある一定の量を断続的にやるか本来は水で流してから塗布したり
逆に例えば1L中の混合比は同じでも頭皮に安全な範囲で両者の量を多めに入れる
本来は頭皮の事を考えて薬液量は少ないので300ml位を断続的
塗布しないとpH下がらないといった感じみたいです。
実際には濃く作って量は少なめだったり断続的に洗い出す概念ではなかったりもするのでやや濃いめだったるするようです。論文によって見解が少しちがったりもしてます。
基本的に今のダメージ毛に対してバッファ剤はあまり必要ではないpH設定をして大量に使う>これ水洗に近い話です。
かなり昔は酸リンスだけで緩衝液といった物は使ってなかったですが、
今はバッファ剤(緩衝液)ですから急激に酸性方向に持っていかない方法ですね。
こら大量に使わないと指定したpHまで落ちない。流れ落ちて毛髪内の薬液量が少ないからですね。特に健康毛に近いほど落ちにくい。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
MHSA 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
MHSAのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170662人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89525人