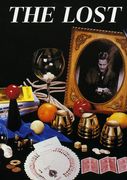TARBELL COURSE IN MAGIC
ハーラン・ターベル(1890〜1960年)師による究極のマジックコースと呼ばれているマジック百科事典。
最初の出版は1926年の昭和元年。
今から80年もの昔のものでありながら、現在においてもこれを越えるマジック教本はない、と断言出来る。
マジックを覚え、マジシャンを目指す人間は必ずこれを通るべきである、と思う。
もとは、メイルオーダー、すなわち通信講座であった。
初期の頃は単に小冊子だけではなく道具も付属していた。
のちにルー・タネンが権利を買い取り、本として出版。
本来は全6巻であり、1972年に刊行された7巻目はターベルの死後、ハリー・ローレインによるものであり本来のコースとはまた違ったものである。
1〜5巻まではラルフ・リード、第6巻はブルース・エリオットがそれぞれを編集している。
1993年に出版された第8巻は、それらに収録されていなかった埋もれていた作品を集めたもので、まぎれもなくターベルコースである。この8巻、本来は日本人による日本人の作品によって制作される、という話もあったが、結果的に立ち消えになっている。
1950年代には、ターベル博士と直接親交のあった石田天海師が日本語版版権を譲り受け、親しかった天洋(現テンヨー)とともに日本においての出版を望んでいた、という。
天海師の死後それを受け継いだのが、日本を代表するマジックメーカーに成長していた(株)テンヨー(旧、天洋)である。
第1巻が1975年に翻訳出版され、現在8巻まで刊行されており、現在でも入手出来る。
マリック師曰くは、テンヨーの日本における最大の功績は日本語版ターベルコースを出版したことだ、といみじくも語っていたそうだが、あながち大げさな事ではないような気がする。
関連コミュニティ
http://
関連トピック「ハーラン・ターベル」
http://
ハーラン・ターベル(1890〜1960年)師による究極のマジックコースと呼ばれているマジック百科事典。
最初の出版は1926年の昭和元年。
今から80年もの昔のものでありながら、現在においてもこれを越えるマジック教本はない、と断言出来る。
マジックを覚え、マジシャンを目指す人間は必ずこれを通るべきである、と思う。
もとは、メイルオーダー、すなわち通信講座であった。
初期の頃は単に小冊子だけではなく道具も付属していた。
のちにルー・タネンが権利を買い取り、本として出版。
本来は全6巻であり、1972年に刊行された7巻目はターベルの死後、ハリー・ローレインによるものであり本来のコースとはまた違ったものである。
1〜5巻まではラルフ・リード、第6巻はブルース・エリオットがそれぞれを編集している。
1993年に出版された第8巻は、それらに収録されていなかった埋もれていた作品を集めたもので、まぎれもなくターベルコースである。この8巻、本来は日本人による日本人の作品によって制作される、という話もあったが、結果的に立ち消えになっている。
1950年代には、ターベル博士と直接親交のあった石田天海師が日本語版版権を譲り受け、親しかった天洋(現テンヨー)とともに日本においての出版を望んでいた、という。
天海師の死後それを受け継いだのが、日本を代表するマジックメーカーに成長していた(株)テンヨー(旧、天洋)である。
第1巻が1975年に翻訳出版され、現在8巻まで刊行されており、現在でも入手出来る。
マリック師曰くは、テンヨーの日本における最大の功績は日本語版ターベルコースを出版したことだ、といみじくも語っていたそうだが、あながち大げさな事ではないような気がする。
関連コミュニティ
http://
関連トピック「ハーラン・ターベル」
http://
|
|
|
|
コメント(43)
ふと思ったのですが、良い本の情報を広めたり、
あるいはどういった内容を期待している人には、
この本が良い等々、書籍のレビュートピ等があると良い気がします。
〜は〜に出てるよという引用だけでは、価値が伝わらなかったり、
そのカラーが分かりにくい。
以前、コミュで話題になったPallbearers Reviewですが、
おそらくこのコミュの参加者の皆さんは、探しもしなかった
のではないでしょうか?
なんと、東京駅八重洲のトリックスに全巻山積みになって
ホコリを被り、日に焼けて色あせていました。
(各国の古本屋を探した自分がバカのようです。)
すぐに近しい人々に連絡し、欲しい人は確保を呼びかけました
ので、今はおそらく2〜3巻しか無いはずですが、
欲しい方はトリックスに連絡してみてください。
(この本は、資料価値が恐ろしく高い物ではありましたが、
目的無しに買っても面白くもなんともない本かもしれません。
念のため。)
やはりその本の内容が、購入者の興味と合致しないと
購入の動機には繋がらないでしょうし、内容のレビューがあると、
なにかと便利ではないか?と思うのです。
あるいはどういった内容を期待している人には、
この本が良い等々、書籍のレビュートピ等があると良い気がします。
〜は〜に出てるよという引用だけでは、価値が伝わらなかったり、
そのカラーが分かりにくい。
以前、コミュで話題になったPallbearers Reviewですが、
おそらくこのコミュの参加者の皆さんは、探しもしなかった
のではないでしょうか?
なんと、東京駅八重洲のトリックスに全巻山積みになって
ホコリを被り、日に焼けて色あせていました。
(各国の古本屋を探した自分がバカのようです。)
すぐに近しい人々に連絡し、欲しい人は確保を呼びかけました
ので、今はおそらく2〜3巻しか無いはずですが、
欲しい方はトリックスに連絡してみてください。
(この本は、資料価値が恐ろしく高い物ではありましたが、
目的無しに買っても面白くもなんともない本かもしれません。
念のため。)
やはりその本の内容が、購入者の興味と合致しないと
購入の動機には繋がらないでしょうし、内容のレビューがあると、
なにかと便利ではないか?と思うのです。
やはりその本の内容が、購入者の興味と合致しないと
購入の動機には繋がらないでしょうし、
、、、そうなんだよね。実にそのとおりで、ベアラーズなどはその際たるものだと思う。イビデムとか。いわゆるブックレビューにふさわしいのは、こうした類の本なのだ。
しかーし!!ターベルはそんなレビューを必要としない、マジックを研究しようとする人は「もっていなくてはならない」本です。その最大の理由は、汲めども尽きぬ妙味にあるのではなく(もちろんあるけど)、この時代のマジックの全体像を、このシリーズだけで包括的に俯瞰しうるということなのです。こんな本はほかに、あっただろうか?グレイターだって、イリュージョンまでは入ってなかったと思う。
購入の動機には繋がらないでしょうし、
、、、そうなんだよね。実にそのとおりで、ベアラーズなどはその際たるものだと思う。イビデムとか。いわゆるブックレビューにふさわしいのは、こうした類の本なのだ。
しかーし!!ターベルはそんなレビューを必要としない、マジックを研究しようとする人は「もっていなくてはならない」本です。その最大の理由は、汲めども尽きぬ妙味にあるのではなく(もちろんあるけど)、この時代のマジックの全体像を、このシリーズだけで包括的に俯瞰しうるということなのです。こんな本はほかに、あっただろうか?グレイターだって、イリュージョンまでは入ってなかったと思う。
グレーターマジックはまさにグレートです。
しかしそれでもなお言いたいです。
たとえ完全邦訳版が出ていたとしてもグレーターマジックよりターベルコースの方が優れている、と。
グレーターマジックはやはりマジックの専門家(ヒリヤードだけではなく、ヒューガードやボボ、などなど)が書いただけあって多分に専門的です。
ただこれがあまりに専門的すぎるのです。一つの技法や一つの演目に対するこだわりがありすぎます。理解しマスターするのが本当に大変です。
対してターベルコースはターベル博士自身が全てを書き、博士自身の考えに統一されています。
そしてなによりも分かりやすいのです。
やはり通信講座であったのが、良い方向に作用したのでしょうか。
しかしそれでもなお言いたいです。
たとえ完全邦訳版が出ていたとしてもグレーターマジックよりターベルコースの方が優れている、と。
グレーターマジックはやはりマジックの専門家(ヒリヤードだけではなく、ヒューガードやボボ、などなど)が書いただけあって多分に専門的です。
ただこれがあまりに専門的すぎるのです。一つの技法や一つの演目に対するこだわりがありすぎます。理解しマスターするのが本当に大変です。
対してターベルコースはターベル博士自身が全てを書き、博士自身の考えに統一されています。
そしてなによりも分かりやすいのです。
やはり通信講座であったのが、良い方向に作用したのでしょうか。
一人の人によるコンピレーション、という美点はターベルを特徴付ける大きな要因だと思う。
ついでに、グレーターの専門的に過ぎる偏向性が、どのような方向を向いたものかを、印象でかまわないのでお願いします。それによっては、もしかしたらグレーターにも手を出すかもしれない(出さないかも)。
よく言われる、ターベルによる「心得」の類は、そしてグレイターにはあるのでしょうか。
カードの部分のみ独立したカードマジック、という本になっていることは有名で、モハメドベイの超傑作2品があるだけで、すごい本だと知れるが、こんな感じのほかにも挙げられるグレイターの特徴も。
これらによって、いわば「背後から照らされた」ターベルの長所を把握しうるものと考えます。
ついでに、グレーターの専門的に過ぎる偏向性が、どのような方向を向いたものかを、印象でかまわないのでお願いします。それによっては、もしかしたらグレーターにも手を出すかもしれない(出さないかも)。
よく言われる、ターベルによる「心得」の類は、そしてグレイターにはあるのでしょうか。
カードの部分のみ独立したカードマジック、という本になっていることは有名で、モハメドベイの超傑作2品があるだけで、すごい本だと知れるが、こんな感じのほかにも挙げられるグレイターの特徴も。
これらによって、いわば「背後から照らされた」ターベルの長所を把握しうるものと考えます。
『グレーターマジック』を読んで気がついたのは、ヒリヤードはその30年前に記した『アートオブマジック』を完璧にしたい、と考えていた事でしょう。
『アートオブ〜』とほぼ同じ構成なんです。
びっくりしました。
そしてその30年間、いかにマジックが進歩したのかを教えてくれます。
ターベル博士がヒリヤードの影響を受けたのは単にマジックのネタや技術という事だけではありません。
ヒリヤード自身はトランプの歴史やマジックそのものの由来まで調べ上げそれらをまとめているのです。
それぞれのカテゴリー(カード、コイン、ロープ、シルク、メンタル、イリュージョンなどなど)を分類して分けてあるのも特徴です。
そしてこの時代のマジックそのものがほぼ完璧な状態で記されているのです。逆に言えばマジックそのものは現代的ではないのです。
邦訳されなかった後半はフーマンチュウのインタビューなどが収められ、プロとしての心構えから、プロとしての売り込みの仕方まで書かれているようです。
ヒリヤード自身がサーストンと言うプロ中のプロと親しかったばかりでなく、アンネマン、バーノンなどの当時一級の腕前のマジシャンやSHシャープなどの研究家との交流があったのもその影響が見られます。
そしてヒリヤード自身が当時最高の研究家だった、という事でしょう。『妖術の開示』に対してもこれほど深く研究した人はいないのではないでしょうか。それに関しても『グレーター〜』に記されています。
ターベルコースと双璧、と言われるのもうなずけるのです。
『グレーター〜』を補う上での『ターベル〜』とも言えるのです。
マストバイです。
可能ならば…。
私も欲しいです、原著を手に入れたいです。
『アートオブ〜』とほぼ同じ構成なんです。
びっくりしました。
そしてその30年間、いかにマジックが進歩したのかを教えてくれます。
ターベル博士がヒリヤードの影響を受けたのは単にマジックのネタや技術という事だけではありません。
ヒリヤード自身はトランプの歴史やマジックそのものの由来まで調べ上げそれらをまとめているのです。
それぞれのカテゴリー(カード、コイン、ロープ、シルク、メンタル、イリュージョンなどなど)を分類して分けてあるのも特徴です。
そしてこの時代のマジックそのものがほぼ完璧な状態で記されているのです。逆に言えばマジックそのものは現代的ではないのです。
邦訳されなかった後半はフーマンチュウのインタビューなどが収められ、プロとしての心構えから、プロとしての売り込みの仕方まで書かれているようです。
ヒリヤード自身がサーストンと言うプロ中のプロと親しかったばかりでなく、アンネマン、バーノンなどの当時一級の腕前のマジシャンやSHシャープなどの研究家との交流があったのもその影響が見られます。
そしてヒリヤード自身が当時最高の研究家だった、という事でしょう。『妖術の開示』に対してもこれほど深く研究した人はいないのではないでしょうか。それに関しても『グレーター〜』に記されています。
ターベルコースと双璧、と言われるのもうなずけるのです。
『グレーター〜』を補う上での『ターベル〜』とも言えるのです。
マストバイです。
可能ならば…。
私も欲しいです、原著を手に入れたいです。
このターベルコース、元はターベルコースという名前で出版される予定ではありませんでした。
出版社のグラント・クック氏とウォルター・ジョーダン氏は、ターベル博士の為に5万ドル、という1926年当時で言えばまさに大金といえるだけの資金を用意しました。
現在でも5万ドルは大金です。
はたして、なぜ出資者はたかがマジックにそれだけの大金を無名の人につぎ込んだのでしょう?
それは、本来このコースのタイトルが、『フーディニ・コース』だったからです。
出資者たちは当時世界的知名度を誇るハリー・フーディニのマジック通信講座を開設しようとしていました。
残念ながら肝心のフーディニ師とはもめてしまい、計画が宙に浮いてしまったのです。
そこでたまたま白羽の矢を立てられたのがターベル博士だったのです。
手品に詳しくて、絵もかけるよ、程度だったのかも知れません。
結果的にマジックの歴史においてはこれが正解でした。
まあ、もっともフーディニ・コースとなったとしてもゴーストライターが書く事になったのでしょうけれど…。
出版社のグラント・クック氏とウォルター・ジョーダン氏は、ターベル博士の為に5万ドル、という1926年当時で言えばまさに大金といえるだけの資金を用意しました。
現在でも5万ドルは大金です。
はたして、なぜ出資者はたかがマジックにそれだけの大金を無名の人につぎ込んだのでしょう?
それは、本来このコースのタイトルが、『フーディニ・コース』だったからです。
出資者たちは当時世界的知名度を誇るハリー・フーディニのマジック通信講座を開設しようとしていました。
残念ながら肝心のフーディニ師とはもめてしまい、計画が宙に浮いてしまったのです。
そこでたまたま白羽の矢を立てられたのがターベル博士だったのです。
手品に詳しくて、絵もかけるよ、程度だったのかも知れません。
結果的にマジックの歴史においてはこれが正解でした。
まあ、もっともフーディニ・コースとなったとしてもゴーストライターが書く事になったのでしょうけれど…。
ターベルの数々の文章はさておき、道具の図面は案外いい加減な印象を受けます。学生時代シャドウボックスを本の図面どおり作った所、ネタ場から入る事はできてもネタ場が閉められない事を発見!おいおい、ターベルさんよ〜と心の中で突っ込んだ記憶が有ります。ボリュームを増やす為に本人がやった事の無いマジックを取り込んだ結果との事。そんな経験ございませんか〜?
微妙なターベルの挿絵にも随分悩まされた経験もあります。
しかしながら、未だにバイブルである事は間違いありません。数年前クラシックパスの練習中行き詰まり、ふと一巻を読み返してみると必要な事は全てそこに書かれていました。哲学的な部分も含めて私は小学生の頃、完全に読み飛ばしてました。学ぶべき所はいまだに多い本です。
既に書き込まれているようにグレーターマジックはプロ向けを前提に記述されているので、ターベルコース程アメリカでも普及はしなかったのでしょう。しかし、グレーターも素晴らしい本です。その昔ユニコンが5巻に分冊されて出版された物を翻訳出版しましたが、完結しなかったのは残念な事です。コンスタントに版を重ねるターベルに比べ、グレーターはカウフマンが10年程前に原著を復刻出版して以来、またまた絶版状態が続いてますね。
微妙なターベルの挿絵にも随分悩まされた経験もあります。
しかしながら、未だにバイブルである事は間違いありません。数年前クラシックパスの練習中行き詰まり、ふと一巻を読み返してみると必要な事は全てそこに書かれていました。哲学的な部分も含めて私は小学生の頃、完全に読み飛ばしてました。学ぶべき所はいまだに多い本です。
既に書き込まれているようにグレーターマジックはプロ向けを前提に記述されているので、ターベルコース程アメリカでも普及はしなかったのでしょう。しかし、グレーターも素晴らしい本です。その昔ユニコンが5巻に分冊されて出版された物を翻訳出版しましたが、完結しなかったのは残念な事です。コンスタントに版を重ねるターベルに比べ、グレーターはカウフマンが10年程前に原著を復刻出版して以来、またまた絶版状態が続いてますね。
>学生時代シャドウボックスを本の図面どおり作った
すごいですね〜。
正直イリュージョンの部分ってふんふんととばしてしまうもんなのにちゃんと作ってしまうとは!
>ターベルさんよ〜と心の中で突っ込んだ記憶が有ります。
それはある意味、発見ですよね。
ターベル博士でさえいい加減(?)だった、という事は。
やっぱり全てのマジックを網羅するのは難しいのでしょう。
誰だって得手不得手があるんですね。
安心しました。
>グレーターはカウフマンが10年程前に原著を復刻出版して以来、またまた絶版状態が続いてますね。
この復刻版は最後の章に原本になかったものが付け加えられているそうなんですが、どういった事が書かれているのでしょう。
教えていただけないでしょうか?
すごいですね〜。
正直イリュージョンの部分ってふんふんととばしてしまうもんなのにちゃんと作ってしまうとは!
>ターベルさんよ〜と心の中で突っ込んだ記憶が有ります。
それはある意味、発見ですよね。
ターベル博士でさえいい加減(?)だった、という事は。
やっぱり全てのマジックを網羅するのは難しいのでしょう。
誰だって得手不得手があるんですね。
安心しました。
>グレーターはカウフマンが10年程前に原著を復刻出版して以来、またまた絶版状態が続いてますね。
この復刻版は最後の章に原本になかったものが付け加えられているそうなんですが、どういった事が書かれているのでしょう。
教えていただけないでしょうか?
今更ながらカウフマンの再版は1994年で12年も前だった事に驚きました。ざっと目を通してみますと。
完全に独立した状態で、More Greater MAGICとして約300ページが加筆されております。まさにアーカイブスの様を呈してます。
ターベルコースで言えば新たに追加された8巻と同じと言えます。前後してカウフマンはターベルの出版にも関わっているのでうなづけます。
グレーターマジックが成立した背景を中心にはじまり、執筆に使用された原案者と執筆者とのやりとりの手紙、割愛された文章、各雑誌での書評等。日本語版の冒頭に使用され、元々本体とは別に付けられた小冊子の各章の概要部分。ヒリヤードの下書きとなったノートからの抜粋等です。いずれにしても、掲載されている作品のどれもが当時のトップばかりなのが驚きです。本編の第30章の指し絵の基となった道具類の写真等も紹介されています。
執筆に当たって何度も文章を練り直している事からも筆者の熱意を感じられます。
ヒリヤードのノートブックに関しては膨大なのでカウフマンは後日このノートブックを別に出版しています。ただし、大半がヒリヤード本人の手書きで注釈が加筆されているだけです。従いましてタイピングされていないので、読みにくいです。
完全に独立した状態で、More Greater MAGICとして約300ページが加筆されております。まさにアーカイブスの様を呈してます。
ターベルコースで言えば新たに追加された8巻と同じと言えます。前後してカウフマンはターベルの出版にも関わっているのでうなづけます。
グレーターマジックが成立した背景を中心にはじまり、執筆に使用された原案者と執筆者とのやりとりの手紙、割愛された文章、各雑誌での書評等。日本語版の冒頭に使用され、元々本体とは別に付けられた小冊子の各章の概要部分。ヒリヤードの下書きとなったノートからの抜粋等です。いずれにしても、掲載されている作品のどれもが当時のトップばかりなのが驚きです。本編の第30章の指し絵の基となった道具類の写真等も紹介されています。
執筆に当たって何度も文章を練り直している事からも筆者の熱意を感じられます。
ヒリヤードのノートブックに関しては膨大なのでカウフマンは後日このノートブックを別に出版しています。ただし、大半がヒリヤード本人の手書きで注釈が加筆されているだけです。従いましてタイピングされていないので、読みにくいです。
>グレーターマジックが成立した背景を中心にはじまり、
それは大変興味深いです。
このグレーターマジックを出版するにあたってヒリヤードの前作アートオブマジックを語らずにはいられません。そしてそのアートオブ〜からおよそ35年も後にこのグレーターがなぜ出版されるに至ったのか、という点が知りたいです。
この2冊の間隔である35年の間にアメリカにおけるマジックの進歩は凄まじいものがあり、ヒリヤードはそのさらに進化した部分を加えたマジック百科事典を書きたかったのでは、と自分は推測しています。
>執筆に使用された原案者と執筆者とのやりとりの手紙、
特に挿絵を描いていたターベルとは、どんなやり取りがあったのでしょう?
今と違い電話やネットで、というわけにはいかず、手紙でマジックを説明し、表現していたはずです。
こうしたやり取りにおいてターベル博士がそうした能力を磨いていたのでは、と思うのですが。
それは大変興味深いです。
このグレーターマジックを出版するにあたってヒリヤードの前作アートオブマジックを語らずにはいられません。そしてそのアートオブ〜からおよそ35年も後にこのグレーターがなぜ出版されるに至ったのか、という点が知りたいです。
この2冊の間隔である35年の間にアメリカにおけるマジックの進歩は凄まじいものがあり、ヒリヤードはそのさらに進化した部分を加えたマジック百科事典を書きたかったのでは、と自分は推測しています。
>執筆に使用された原案者と執筆者とのやりとりの手紙、
特に挿絵を描いていたターベルとは、どんなやり取りがあったのでしょう?
今と違い電話やネットで、というわけにはいかず、手紙でマジックを説明し、表現していたはずです。
こうしたやり取りにおいてターベル博士がそうした能力を磨いていたのでは、と思うのですが。
まず、執筆が始まった背景に関しては本巻の最初に経緯の説明が有ります。それに関しては、後で書き込みます。
成立の背景というのは、私の表現が足りない性もあり誤解されてしまったようで、すみません。原稿作りから出版までの作業という事です。従いまして、加筆された部分の大半はヒリヤードの原稿を基に執筆したヒューガードと編集者のカール ジョーンズとのやり取り、詳細を原案車に尋ねるヒューガードの手紙等です。著者名はヒリヤードで出版されていますが、初版の出された1938年の3年前に本人は亡くなっており、彼の意志を継ぐという意味で著者名に据えられています。大半の原稿が整理されていなかった為編集発行までに約3年を要しました。ヒューガードは編集人として名を連ねていますが、実質的な執筆者というのは、読み返すまで私の意識に全くありませんでした。
本巻に書かれている成立した背景は、ざっと以下のようなかんじです。
この本の実質の発案者はカール ジョーンズで、アートオブマジック以降、時代の最先端を行くマジックの本が出版されていない事を憂いており、最適な執筆者を捜していたようです。
一方、アートオブマジックのゴーストライターだったヒリヤードはサーストンに随行して、マジックの記事を専門誌に執筆していました。その間7年間にマジックに関して熱心な性格から多くの原稿をしたためていたようです。しかしながら、それを出版するに見合う資金提供者がいなかったようです。
そんなヒリヤードの噂をサーストンから聞きつけたジョーンズは、サーストンと共にヒリヤードに資金提供する旨を申し出て、本格的なこの本の為の執筆が始まります。その志半ばヒリヤードは亡くなってしまいます。そして、サーストンも本の完成を見ずにこの世を去ります。
当時のトッププロから多くの作品を引き出す事は並大抵の事ではなかったでしょうが、それはヒリヤードの人柄だからこそできた偉業だと思います。
挿絵の作業をターベルに依頼するのはジョーンズで、ターベルコースの挿絵を見て白羽の矢を点てたようです。実際にはヒューガードが原稿を基にポーズをとり、それをターベルが描くという作業が中心だったようです。2ヶ月間缶詰作業で仕上げたと記録されてました。
以上疑問に答えられたかどうか不安ですが、流し読みなのでまた何かお気づきのことがあったら突っ込んで下さい。
成立の背景というのは、私の表現が足りない性もあり誤解されてしまったようで、すみません。原稿作りから出版までの作業という事です。従いまして、加筆された部分の大半はヒリヤードの原稿を基に執筆したヒューガードと編集者のカール ジョーンズとのやり取り、詳細を原案車に尋ねるヒューガードの手紙等です。著者名はヒリヤードで出版されていますが、初版の出された1938年の3年前に本人は亡くなっており、彼の意志を継ぐという意味で著者名に据えられています。大半の原稿が整理されていなかった為編集発行までに約3年を要しました。ヒューガードは編集人として名を連ねていますが、実質的な執筆者というのは、読み返すまで私の意識に全くありませんでした。
本巻に書かれている成立した背景は、ざっと以下のようなかんじです。
この本の実質の発案者はカール ジョーンズで、アートオブマジック以降、時代の最先端を行くマジックの本が出版されていない事を憂いており、最適な執筆者を捜していたようです。
一方、アートオブマジックのゴーストライターだったヒリヤードはサーストンに随行して、マジックの記事を専門誌に執筆していました。その間7年間にマジックに関して熱心な性格から多くの原稿をしたためていたようです。しかしながら、それを出版するに見合う資金提供者がいなかったようです。
そんなヒリヤードの噂をサーストンから聞きつけたジョーンズは、サーストンと共にヒリヤードに資金提供する旨を申し出て、本格的なこの本の為の執筆が始まります。その志半ばヒリヤードは亡くなってしまいます。そして、サーストンも本の完成を見ずにこの世を去ります。
当時のトッププロから多くの作品を引き出す事は並大抵の事ではなかったでしょうが、それはヒリヤードの人柄だからこそできた偉業だと思います。
挿絵の作業をターベルに依頼するのはジョーンズで、ターベルコースの挿絵を見て白羽の矢を点てたようです。実際にはヒューガードが原稿を基にポーズをとり、それをターベルが描くという作業が中心だったようです。2ヶ月間缶詰作業で仕上げたと記録されてました。
以上疑問に答えられたかどうか不安ですが、流し読みなのでまた何かお気づきのことがあったら突っ込んで下さい。
はい。勉強になります。
>挿絵の作業をターベルに依頼するのはジョーンズで、ターベルコースの挿絵を見て白羽の矢を点てたようです。
年代的に考えてみればターベルコースの方が古く、そのターベルコースによって白羽の矢が、という事にとても納得します。
ヒューガードとターベルの付き合いはこの頃から何でしょうか?
そしてボボも。
>当時のトッププロから多くの作品を引き出す事は並大抵の事ではなかったでしょうが、それはヒリヤードの人柄だからこそできた偉業だと思います。
多くの人が関わりあう中であえてヒリヤードの功績にしたのが、その人柄だからこそ、という点も面白く感じます。
ぜひ続きをお聞かせください。
>挿絵の作業をターベルに依頼するのはジョーンズで、ターベルコースの挿絵を見て白羽の矢を点てたようです。
年代的に考えてみればターベルコースの方が古く、そのターベルコースによって白羽の矢が、という事にとても納得します。
ヒューガードとターベルの付き合いはこの頃から何でしょうか?
そしてボボも。
>当時のトッププロから多くの作品を引き出す事は並大抵の事ではなかったでしょうが、それはヒリヤードの人柄だからこそできた偉業だと思います。
多くの人が関わりあう中であえてヒリヤードの功績にしたのが、その人柄だからこそ、という点も面白く感じます。
ぜひ続きをお聞かせください。
RYUSEIさん
>ぜひ続きをお聞かせください。
成立背景は書き込んだ通りで、それ以上は他の資料をあたるしかなさそうです。しかしながら、古典作品の出版年代をたどって人間関係を推察するのも面白いですね。
話題からは逸れますが、願わくば、名だたる古典の名作を現代人にわかりやすい日本語で翻訳出版して欲しいというのが本音です。高校の頃よく数学の教師が言っていました『基本を押さえれば応用は簡単だ』と。
ターベルコースの内容が古いとか言わずに、せめて、マジシャンを自称するなら最低各巻一冊は揃えて読破して欲しい本です。そして、連綿と続くマジックの歴史の重みを実感して欲しいと思います。
Magusさん、りょうさん
このコミュが無ければ再読する機会は無かったと思います。マジック界も情報過多なので、互いに不足部分はフォローし合っていきましょう。
>ぜひ続きをお聞かせください。
成立背景は書き込んだ通りで、それ以上は他の資料をあたるしかなさそうです。しかしながら、古典作品の出版年代をたどって人間関係を推察するのも面白いですね。
話題からは逸れますが、願わくば、名だたる古典の名作を現代人にわかりやすい日本語で翻訳出版して欲しいというのが本音です。高校の頃よく数学の教師が言っていました『基本を押さえれば応用は簡単だ』と。
ターベルコースの内容が古いとか言わずに、せめて、マジシャンを自称するなら最低各巻一冊は揃えて読破して欲しい本です。そして、連綿と続くマジックの歴史の重みを実感して欲しいと思います。
Magusさん、りょうさん
このコミュが無ければ再読する機会は無かったと思います。マジック界も情報過多なので、互いに不足部分はフォローし合っていきましょう。
うちのターベルコースはボロボロです。
「古いか古くないか」で、S原氏と良く議論を戦わせたものです。
そうそう、シャドウボックスですが、おそらく当時の人々の
体の大きさも関係がありそうです。
ターベル氏や当時のマジシャン達は、あまり体が大きくなかった
のだと思います。フーディニの小ささは良く話題になりますが、
颯爽と燕尾服を着こなしていたようなイメージのある
サーストンですら、160センチ台だったと記憶しています。
同じ寸法では、我々がドアを通れないのも無理もありません(笑)
自分も大学時代に作り、実演までしたのですが、その時は
ドアは一切作らず、単に布(破かないので布にしました)
をダラリと下げるだけで行いました。
下端にはマグネットシートを通しておくと具合が良いです。
「古いか古くないか」で、S原氏と良く議論を戦わせたものです。
そうそう、シャドウボックスですが、おそらく当時の人々の
体の大きさも関係がありそうです。
ターベル氏や当時のマジシャン達は、あまり体が大きくなかった
のだと思います。フーディニの小ささは良く話題になりますが、
颯爽と燕尾服を着こなしていたようなイメージのある
サーストンですら、160センチ台だったと記憶しています。
同じ寸法では、我々がドアを通れないのも無理もありません(笑)
自分も大学時代に作り、実演までしたのですが、その時は
ドアは一切作らず、単に布(破かないので布にしました)
をダラリと下げるだけで行いました。
下端にはマグネットシートを通しておくと具合が良いです。
>うちのターベルコースはボロボロです。
素晴らしい!
Magusさんのマジックに対する愛情を感じます。
>体の大きさも関係がありそうです。
なるほど言われてみると、最近の商品のシャドウボックスは
図面にあるような立て長タイプは見掛けませんねぇ。みんな
立方体ですものね。
>下端にはマグネットシートを通しておくと具合が良いです。
小学生の頃見たインド大魔術団の物はまさにターベルの解説した
仕掛けそのものでした。最近のシャドウボックスのネタ場はウィ
ンドシェイドを利用して作られているものが多いです。その昔
ダグヘニングのシャドウボックスのカメラワークには感心しま
した。
始めてテンヨーのコーナーへ行った時にはまだ5巻までしか発刊
されていなくて、続巻を心待ちにしていたことを思い出します。
我が家には各巻2冊と、数ページが全く印刷されていないレア
物?もあります。←ただの落丁だって。
マジックにハマると金銭感覚は麻痺しますが、ペラペラのレク
チャーノートに比べればターベルコースは決して高くないと
思います。
素晴らしい!
Magusさんのマジックに対する愛情を感じます。
>体の大きさも関係がありそうです。
なるほど言われてみると、最近の商品のシャドウボックスは
図面にあるような立て長タイプは見掛けませんねぇ。みんな
立方体ですものね。
>下端にはマグネットシートを通しておくと具合が良いです。
小学生の頃見たインド大魔術団の物はまさにターベルの解説した
仕掛けそのものでした。最近のシャドウボックスのネタ場はウィ
ンドシェイドを利用して作られているものが多いです。その昔
ダグヘニングのシャドウボックスのカメラワークには感心しま
した。
始めてテンヨーのコーナーへ行った時にはまだ5巻までしか発刊
されていなくて、続巻を心待ちにしていたことを思い出します。
我が家には各巻2冊と、数ページが全く印刷されていないレア
物?もあります。←ただの落丁だって。
マジックにハマると金銭感覚は麻痺しますが、ペラペラのレク
チャーノートに比べればターベルコースは決して高くないと
思います。
うちのターベルコースはボロボロです。
「古いか古くないか」で、S原氏と良く議論を戦わせたものです。
いやー懐かしい。おれはそんなこといってたか?瞬時に思い出す記憶、確かに言っていた。この当時は確か、奇術研究も古い、といっていた。今にして思えば、その活字体、絵柄、文体が古い。「新作奇術で新年を向かえさっしゃりましょう」いつの日本語だ。「ハイドロジンとオキシジンです」どういうギャグだ。
この当時はすでにビデオの時代で、見るもの全てが新しく、それらのよってたつ基盤に目をやるような余裕がなかった。確かにそうした目で見ればターベルも奇術研究も「古い」。
しかしだんだん分かってくると、次々発表されるマジックが実は別にたいしたものではないものばかりだということが分かってくる。そこらへんまで塗れてみないと、それを生み出す基盤のすごさは分からない。
古典が古く見えるのは、単に初期の熱病だ。
「古いか古くないか」で、S原氏と良く議論を戦わせたものです。
いやー懐かしい。おれはそんなこといってたか?瞬時に思い出す記憶、確かに言っていた。この当時は確か、奇術研究も古い、といっていた。今にして思えば、その活字体、絵柄、文体が古い。「新作奇術で新年を向かえさっしゃりましょう」いつの日本語だ。「ハイドロジンとオキシジンです」どういうギャグだ。
この当時はすでにビデオの時代で、見るもの全てが新しく、それらのよってたつ基盤に目をやるような余裕がなかった。確かにそうした目で見ればターベルも奇術研究も「古い」。
しかしだんだん分かってくると、次々発表されるマジックが実は別にたいしたものではないものばかりだということが分かってくる。そこらへんまで塗れてみないと、それを生み出す基盤のすごさは分からない。
古典が古く見えるのは、単に初期の熱病だ。
久しぶりに長文を。
それにしても、東京堂という力強い味方はあるにせよ、ターベル廃刊はショック。考えてみれば、その東京堂からさえ、ステージまでも網羅した体系的なセットは出ていない。シルクマジック事典が近いとはいえ、あれは初心者が読んで勉強できるものではないし、やはり絶版。
ずいぶん前、竹下登が死んださい、私は自民党政治の終焉を感じた。そのとき考えたのが、将来の日本は「ハイロウズ」と化すだろう、ということだった。
つまり、一億総中流であった日本に、階級、階層が発生し、定着していくだろうということ。
案の定、その前後にデビッドブレインが出てきて、ストリートマジックなる分野が出てきた。言葉は悪いが、はっきり言って世間の底辺暮らしの若者が単に自慢でやっている手品だ。どうせ数年で辞めるに違いない。
と思っていると、廃刊間際の「ザ・マジック」に、ディズニーのショーで日本に来た若いマジシャンが、最近のアメリカはやりたがりの見せたがりが不意打ちのようにやり逃げしていくストリートマジックばかり、と嘆息する記事が載り、何だアメリカでも、口にされるほどの問題となっていたのかと驚いたのは記憶に新しい。
それでもまだ、西欧が恵まれているのは、母国語で読める文献が、日本と比べて段違いに多い、ということだ。「ハイズ」でさえも格が違って見えるのは、こうした基礎体力の差からくるものだろう。
日本におけるゆとり教育がどうだったかは別にして、一般的に次のような共通認識があるだろう事は疑いようがない。つまり「文字を読まない奴は馬鹿」。
社会構造や、貧富の差のみならず、ここにきてついにターベル廃刊となり、「ハイロウズ」の形はこんなところからも、もはやとめようのない流れとなっているように感じ、暗澹とすることであった。
しかし、実はそれさえも、どうでもいいといえば、いいのだ。
それは、ストリート、だったり、読まない人、たちが、どんなに増えて活況を呈して見えようとも、おそらくそうした人たちは、5年もしないでマジックから離れていくだろうからだ。
つまり、いてもいなくても、同じなのだ。
ブームの後には、それが過ぎ去る寂しさが避けられない。実際ここ数年でも、何らかの形でそうした波を感じることはあった。
だがしかし、そうした流れは、いわば本質的な部分には何の影響も及ぼさない。ブームが見せかけのものだと思えば、痛くもかゆくもない。
、、、といって、平静を保つばかりの、ターベル廃刊ニュースであった。
それにしても、東京堂という力強い味方はあるにせよ、ターベル廃刊はショック。考えてみれば、その東京堂からさえ、ステージまでも網羅した体系的なセットは出ていない。シルクマジック事典が近いとはいえ、あれは初心者が読んで勉強できるものではないし、やはり絶版。
ずいぶん前、竹下登が死んださい、私は自民党政治の終焉を感じた。そのとき考えたのが、将来の日本は「ハイロウズ」と化すだろう、ということだった。
つまり、一億総中流であった日本に、階級、階層が発生し、定着していくだろうということ。
案の定、その前後にデビッドブレインが出てきて、ストリートマジックなる分野が出てきた。言葉は悪いが、はっきり言って世間の底辺暮らしの若者が単に自慢でやっている手品だ。どうせ数年で辞めるに違いない。
と思っていると、廃刊間際の「ザ・マジック」に、ディズニーのショーで日本に来た若いマジシャンが、最近のアメリカはやりたがりの見せたがりが不意打ちのようにやり逃げしていくストリートマジックばかり、と嘆息する記事が載り、何だアメリカでも、口にされるほどの問題となっていたのかと驚いたのは記憶に新しい。
それでもまだ、西欧が恵まれているのは、母国語で読める文献が、日本と比べて段違いに多い、ということだ。「ハイズ」でさえも格が違って見えるのは、こうした基礎体力の差からくるものだろう。
日本におけるゆとり教育がどうだったかは別にして、一般的に次のような共通認識があるだろう事は疑いようがない。つまり「文字を読まない奴は馬鹿」。
社会構造や、貧富の差のみならず、ここにきてついにターベル廃刊となり、「ハイロウズ」の形はこんなところからも、もはやとめようのない流れとなっているように感じ、暗澹とすることであった。
しかし、実はそれさえも、どうでもいいといえば、いいのだ。
それは、ストリート、だったり、読まない人、たちが、どんなに増えて活況を呈して見えようとも、おそらくそうした人たちは、5年もしないでマジックから離れていくだろうからだ。
つまり、いてもいなくても、同じなのだ。
ブームの後には、それが過ぎ去る寂しさが避けられない。実際ここ数年でも、何らかの形でそうした波を感じることはあった。
だがしかし、そうした流れは、いわば本質的な部分には何の影響も及ぼさない。ブームが見せかけのものだと思えば、痛くもかゆくもない。
、、、といって、平静を保つばかりの、ターベル廃刊ニュースであった。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-