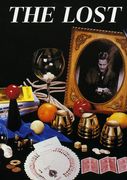柴田直光氏によって昭和26年12月20日初版発行。
発行は理工図書株式会社。
柴田氏は、土木工学に長け、応用数学の権威でもあった。
この本の影響を受けた日本のマジック研究家は多い。
趣味の本というよりは学術書のような雰囲気である。
第1編は、カードの奇術
第2編は、紐の奇術
第3編は、ボールの奇術
第4編は、銀貨の奇術
第5編は、ダイスの奇術
第6編は、数に関する奇術
第7編は、食卓の話題
第8編は、当て物
私自身が持っているものは、昭和45年のものである。昭和45年当時に定価250円。
この本自体は版を重ね、平成元年あたりまで一般書店で手に入るものであったことからも、本当のベストセラーであると言えよう。
現在でも古書専門店などで比較的入手しやすい。
発行は理工図書株式会社。
柴田氏は、土木工学に長け、応用数学の権威でもあった。
この本の影響を受けた日本のマジック研究家は多い。
趣味の本というよりは学術書のような雰囲気である。
第1編は、カードの奇術
第2編は、紐の奇術
第3編は、ボールの奇術
第4編は、銀貨の奇術
第5編は、ダイスの奇術
第6編は、数に関する奇術
第7編は、食卓の話題
第8編は、当て物
私自身が持っているものは、昭和45年のものである。昭和45年当時に定価250円。
この本自体は版を重ね、平成元年あたりまで一般書店で手に入るものであったことからも、本当のベストセラーであると言えよう。
現在でも古書専門店などで比較的入手しやすい。
|
|
|
|
コメント(9)
同感ですね。
日本のクロースアップマジック史においては重要な本であり、クラシック書としての価値も高いものと思います。
前半が『ロイヤルロード〜』ですが、この後半はいったい何の海外の本をベースにした本なのでしょうか?
それに前半も完全に『ロイヤルロード〜』とも思えない部分もあります。
例えば、パスの項目(62ページ)において原著では単純に"THE PASS"というだけです。しかし、この本においては”古典パス”と訳されているのです。
古典パスという事は、クラシックパスの訳だと思います。
なのに原著は単にパスなんです。
”片手パス”と”反転パス”の三種類のパスが述べられています。
原著ではいずれも解説されていません。
つまり、きっと柴田氏は他の本も併読しながら加筆したのでは、と思うんです。
特に”反転パス”は、これこそ、ターンノーバーパスの日本語訳かと思えます。が、しかし、内容はそうではなくむしろフラリッシュパスなのが不思議です。
日本のクロースアップマジック史においては重要な本であり、クラシック書としての価値も高いものと思います。
前半が『ロイヤルロード〜』ですが、この後半はいったい何の海外の本をベースにした本なのでしょうか?
それに前半も完全に『ロイヤルロード〜』とも思えない部分もあります。
例えば、パスの項目(62ページ)において原著では単純に"THE PASS"というだけです。しかし、この本においては”古典パス”と訳されているのです。
古典パスという事は、クラシックパスの訳だと思います。
なのに原著は単にパスなんです。
”片手パス”と”反転パス”の三種類のパスが述べられています。
原著ではいずれも解説されていません。
つまり、きっと柴田氏は他の本も併読しながら加筆したのでは、と思うんです。
特に”反転パス”は、これこそ、ターンノーバーパスの日本語訳かと思えます。が、しかし、内容はそうではなくむしろフラリッシュパスなのが不思議です。
第4編の「銀貨の奇術」は、ターベルコース・イン・マジックの第1巻の内容に近いので、それをベースにしているようにも思えます。ただし文章や挿絵は完全に一致する箇所はありませんので、戦前の国内文献や先人のマジシャンから得た情報などを織り交ぜて内容を独自のモノに構成したのではないでしょうか。
また、柴田直光氏は当時としては唯一のアマチュア・マジッククラブのTAMCの会員であったそうですから、そのクラブを通して得たマジックの情報が全編に渡り含まれているのだと思います。
私は、この本を購入した直後、興味本位で使い古しのカードを使用し“石鹸”をトライしました。滑りは良いのですが、直ぐに汚れが酷くなり短期でカードが痛んでしまったように記憶しています。
また、柴田直光氏は当時としては唯一のアマチュア・マジッククラブのTAMCの会員であったそうですから、そのクラブを通して得たマジックの情報が全編に渡り含まれているのだと思います。
私は、この本を購入した直後、興味本位で使い古しのカードを使用し“石鹸”をトライしました。滑りは良いのですが、直ぐに汚れが酷くなり短期でカードが痛んでしまったように記憶しています。
戦後の天洋(現テンヨー)ではファンカードにロウを塗って加工した状態で販売していたそうです。
松旭斎天暁先生は若い頃はそれを天洋先生に命じられ、アメ横でカードを買って来たらそれにロウを塗っていた、とおっしゃっていました。
石けんを塗る、という手法はいつの間にか廃れてしまいましたね。
やはりステアリン酸亜鉛(スライダー)がポピュラーになってからでしょうか。
ジョニー・ハート師は靴を買ったときの箱に入れて粉ごとシェイクしなさい、と言ってました。
ヒリヤードの『グレーターマジック』の頃はファンカードをする上で滑りが重要である事は述べてありますが、加工法までは書いておらず、新品を使う事、綺麗に扱う事、を優先しています。
そう考えるとカードにロウを塗るのは日本オリジナルなのかも知れません。
真田豊実氏の説では日本にはメンコなどにロウを塗って強度を上げる風習があり、そうした生活の知恵を誰かが応用したのではないか、と述べていました。
松旭斎天暁先生は若い頃はそれを天洋先生に命じられ、アメ横でカードを買って来たらそれにロウを塗っていた、とおっしゃっていました。
石けんを塗る、という手法はいつの間にか廃れてしまいましたね。
やはりステアリン酸亜鉛(スライダー)がポピュラーになってからでしょうか。
ジョニー・ハート師は靴を買ったときの箱に入れて粉ごとシェイクしなさい、と言ってました。
ヒリヤードの『グレーターマジック』の頃はファンカードをする上で滑りが重要である事は述べてありますが、加工法までは書いておらず、新品を使う事、綺麗に扱う事、を優先しています。
そう考えるとカードにロウを塗るのは日本オリジナルなのかも知れません。
真田豊実氏の説では日本にはメンコなどにロウを塗って強度を上げる風習があり、そうした生活の知恵を誰かが応用したのではないか、と述べていました。
昭和45年の石川雅章さんの本を読むと
「ファンカード用に工夫された専用のカードがあり、これには特性のパウダーも添えられているが、上質の粉石鹸か、スキー用のパラフィンなどを少量塗布する事によって、相当に滑らかになるものである。」
と書いてありました。
石川氏の本もタイトルを変え再販を重ねていますのでさらに年代をさかのぼれると思います。
いしけんさんは”石鹸”でしたが、私自身はこの石川氏の本をバイブルとしてましたのでスキー用のパラフィンにトライしました。
結果、固くて満足に塗れませんでした。
その後、スプレー式のパラフィンでトライしました。
結果、滑りが悪くなりました。
さすがに石鹸は試しませんでした。私の頃は石鹸と言えば固形であり、洗濯石けんも粉ではありましたが、塗るには大粒だったからです。
いしけんさんのご意見は実体験者として貴重だと思います。
「ファンカード用に工夫された専用のカードがあり、これには特性のパウダーも添えられているが、上質の粉石鹸か、スキー用のパラフィンなどを少量塗布する事によって、相当に滑らかになるものである。」
と書いてありました。
石川氏の本もタイトルを変え再販を重ねていますのでさらに年代をさかのぼれると思います。
いしけんさんは”石鹸”でしたが、私自身はこの石川氏の本をバイブルとしてましたのでスキー用のパラフィンにトライしました。
結果、固くて満足に塗れませんでした。
その後、スプレー式のパラフィンでトライしました。
結果、滑りが悪くなりました。
さすがに石鹸は試しませんでした。私の頃は石鹸と言えば固形であり、洗濯石けんも粉ではありましたが、塗るには大粒だったからです。
いしけんさんのご意見は実体験者として貴重だと思います。
「奇期一会・番外編、出会ったのは人ではない。昭和26年の12月、書店に並んだ一冊の本、柴田直光著『奇術種あかし』とだ。お値段が180円という廉価にも拘らず、今迄のものと比べ物にならない美しい内容なのだ。手に取ったとたん1,000ボルトの電流が走ったようなショックだった。
(中略)
100頁にわたってカード奇術の手練技法と演技が解説してあるのだ。坂本種芳さんの序文に”まさに昇天に慈雨の感があり…”と記しているが、まさにその通りで、この本『奇術種あかし』との出会いがなければ、きっと金策尽き果て、早々にカード・マジックとおさらばしていたことだろう。」
小野坂TON『リチャード・オルマナック特別増刊号』(1992年)
(中略)
100頁にわたってカード奇術の手練技法と演技が解説してあるのだ。坂本種芳さんの序文に”まさに昇天に慈雨の感があり…”と記しているが、まさにその通りで、この本『奇術種あかし』との出会いがなければ、きっと金策尽き果て、早々にカード・マジックとおさらばしていたことだろう。」
小野坂TON『リチャード・オルマナック特別増刊号』(1992年)
”第5編ダイスの奇術”(137〜140頁)とわざわざ章に分けてあります。
ダイスの手品だけを集めた章、というのはマジックの本としては大変珍しい事です。
とは言ってもたったの3種類だけです。
しかもたったの4頁しかありません。
1、変るダイスの目
良く知られている一種のフォールスターノーバーを使ってダイスを回転させ、裏と表の数が変っていく、というものです。
ダイスを一個だけではなく、二個使うとさらに効果的である、と述べられています。
島田晴夫さんがこのマジックを行っていたときはびっくりしました。二個のダイスを使って足し算をする、という演出でした。
2、3つのダイス
これが天海のスリーダイスの原形だと思います。
ところが現象そのものは表の目と裏の目が単に一致する、というものでありマジック的には?、疑問符がつきます。
あまり面白いものとは思えません。
そう考えると天海師は素晴らしい手順に昇華した、という事が再認識出来ます。
筆者自身も研究中である、と述べられカラーダイスにしたらどうだろうか、とかアイディアが書かれています。
以上の二つのマジックに関してはなぜかイラストが全て左手の状態で書かれているのが面白いところです。
筆者は自分の左手を見ながら絵を書いたんじゃないかと思えるからです。
3、数字のダイス
三桁の数字が書かれたダイスを制作しそれを用いるものです。
現象的には観客に3つのダイスを振らせ、即座に合計数を言う事が出来る、同時に裏の数字の合計も言える、というものです。
時代を経て、二川滋夫さんが、これを発展させたものを『日本語版ニューヨークシンポジウム』に発表したと記憶しています。
ダイスの手品だけを集めた章、というのはマジックの本としては大変珍しい事です。
とは言ってもたったの3種類だけです。
しかもたったの4頁しかありません。
1、変るダイスの目
良く知られている一種のフォールスターノーバーを使ってダイスを回転させ、裏と表の数が変っていく、というものです。
ダイスを一個だけではなく、二個使うとさらに効果的である、と述べられています。
島田晴夫さんがこのマジックを行っていたときはびっくりしました。二個のダイスを使って足し算をする、という演出でした。
2、3つのダイス
これが天海のスリーダイスの原形だと思います。
ところが現象そのものは表の目と裏の目が単に一致する、というものでありマジック的には?、疑問符がつきます。
あまり面白いものとは思えません。
そう考えると天海師は素晴らしい手順に昇華した、という事が再認識出来ます。
筆者自身も研究中である、と述べられカラーダイスにしたらどうだろうか、とかアイディアが書かれています。
以上の二つのマジックに関してはなぜかイラストが全て左手の状態で書かれているのが面白いところです。
筆者は自分の左手を見ながら絵を書いたんじゃないかと思えるからです。
3、数字のダイス
三桁の数字が書かれたダイスを制作しそれを用いるものです。
現象的には観客に3つのダイスを振らせ、即座に合計数を言う事が出来る、同時に裏の数字の合計も言える、というものです。
時代を経て、二川滋夫さんが、これを発展させたものを『日本語版ニューヨークシンポジウム』に発表したと記憶しています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-