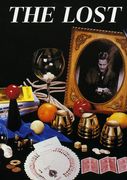|
|
|
|
コメント(53)
編集や、文章の作成はジョージ・スタークスです。
この人の本業はニューヨークの判事でした。
ホロウィッツにマジックを習い、クロースアップに造詣の深かった人だったようです。
デイリー博士の写真とこのスタークスによる文章によって『スターズオブマジック』が生まれたようです。
当時このシリーズは平均一冊3ドル。今の3ドルだと330円くらいですが、当時の金額にすればいかほどのものであった事でしょう。
戦後ほどなくの事ですから、1ドル360円の頃でしょう。
1000円くらいですが、当時の1000円です。
かなり高価なものと推察出来ます。
マリニの号に至っては、10ドルもしたと云います。
ただ、かなり詳しい写真入り、と詳細な解説は世界中でヒットしたようです。
この人の本業はニューヨークの判事でした。
ホロウィッツにマジックを習い、クロースアップに造詣の深かった人だったようです。
デイリー博士の写真とこのスタークスによる文章によって『スターズオブマジック』が生まれたようです。
当時このシリーズは平均一冊3ドル。今の3ドルだと330円くらいですが、当時の金額にすればいかほどのものであった事でしょう。
戦後ほどなくの事ですから、1ドル360円の頃でしょう。
1000円くらいですが、当時の1000円です。
かなり高価なものと推察出来ます。
マリニの号に至っては、10ドルもしたと云います。
ただ、かなり詳しい写真入り、と詳細な解説は世界中でヒットしたようです。
本筋とははずれますが・・・・
僕は、今から20数年前に合本で入手しました。
当時、まだマジックバーをやっていた根本さんから購入。
買うときに、2階に連れて行かれ、分冊で購入し、ファイリングされた彼のボロボロになった原本を見せられました。
(←こーゆーのを見るにつけ、例えCDで入手しても、本は処分できないですよねー。(笑))
「CULLさん、私がこれを買ったときは、社会人になったばかりのころで、それはもう高くて、何度も読み直したわ。」・・とのこと。
合本で、安価でしかも一気に入手できる喜びを感じました。
色々ある中で、僕が一番使っているのは何か、と考えると、
“Ross Bertram's Passing Halfbacks”
でした。
このCoins Acrossのバリエーションは、“4枚単純に移動する”という冗長な手順に、意外性のあるクライマックスを導入している、当時としては画期的なものだったと思われます。
僕は、今から20数年前に合本で入手しました。
当時、まだマジックバーをやっていた根本さんから購入。
買うときに、2階に連れて行かれ、分冊で購入し、ファイリングされた彼のボロボロになった原本を見せられました。
(←こーゆーのを見るにつけ、例えCDで入手しても、本は処分できないですよねー。(笑))
「CULLさん、私がこれを買ったときは、社会人になったばかりのころで、それはもう高くて、何度も読み直したわ。」・・とのこと。
合本で、安価でしかも一気に入手できる喜びを感じました。
色々ある中で、僕が一番使っているのは何か、と考えると、
“Ross Bertram's Passing Halfbacks”
でした。
このCoins Acrossのバリエーションは、“4枚単純に移動する”という冗長な手順に、意外性のあるクライマックスを導入している、当時としては画期的なものだったと思われます。
Card up the Sleeve はCULLさんの仰られるように
現代では確かに10枚という枚数は不向きかもしれませんね。
ですが手順があまりにも完成されているが為に、
枚数を減らすのが逆に困難に思ってしまいます。
Card up the Sleeve は一応レパートリーですが、
一般客の前で演じたことは未だ嘗て一度もありませんね。
どこまでいってもマジシャン向けと言いましょうか。
根本さんのCard up the Sleeve におけるスリービング、
初めて観た時、なるほどと感心しました。取り入れはしませんでしたが。
John Carney の方法は面白すぎますね。
正に現代風だと思いました。枚数もそうですし、
それらのジョークを取り入れている点なんて一般ウケしますよね。
一時期、Homing Card でそのジョークを取り入れている時がありありました。
現代では確かに10枚という枚数は不向きかもしれませんね。
ですが手順があまりにも完成されているが為に、
枚数を減らすのが逆に困難に思ってしまいます。
Card up the Sleeve は一応レパートリーですが、
一般客の前で演じたことは未だ嘗て一度もありませんね。
どこまでいってもマジシャン向けと言いましょうか。
根本さんのCard up the Sleeve におけるスリービング、
初めて観た時、なるほどと感心しました。取り入れはしませんでしたが。
John Carney の方法は面白すぎますね。
正に現代風だと思いました。枚数もそうですし、
それらのジョークを取り入れている点なんて一般ウケしますよね。
一時期、Homing Card でそのジョークを取り入れている時がありありました。
CULLさんへ
“Ross Bertram's Passing Halfbacks”
挫折したマジックの一つです。
どうしても3枚目から4枚目の手から手へ移行する部分が解読出来ませんでした。どうも分かりにくい。
ぜひ、今度お会いした時に見せていただけると嬉しいです。
コツを教えて下さい。お願いいたします。
自分自身は、同様の効果があるターベルコース第7巻にある『トラベラー』を好んで演じていました。
タネンのショップで演じていた、と記載されていたのでおそらくバートラムのバリエーションでしょう。
リバース現象、といってもいいこの劇的なクライマックスはこのバートラムが最初なんでしょうか?
ラブバニッシュもマルローではなく、バートラムが最初である、と聞いた事があります。実際にこのバートラムセクションの最初のマジック("Rub down")にラブバニッシュが用いられています。
年代的に言えばあり得る話ですが、確証がありません。
KENTAROさんへ
根本さんのカードアップザスリーブ、私は根本さんのビデオで見ました。
今、この題材も研究している最中なので、また書き込みをしたいと思っています。
私自身が好きなのは、バーノンの作品です。
今後もいろいろと教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
“Ross Bertram's Passing Halfbacks”
挫折したマジックの一つです。
どうしても3枚目から4枚目の手から手へ移行する部分が解読出来ませんでした。どうも分かりにくい。
ぜひ、今度お会いした時に見せていただけると嬉しいです。
コツを教えて下さい。お願いいたします。
自分自身は、同様の効果があるターベルコース第7巻にある『トラベラー』を好んで演じていました。
タネンのショップで演じていた、と記載されていたのでおそらくバートラムのバリエーションでしょう。
リバース現象、といってもいいこの劇的なクライマックスはこのバートラムが最初なんでしょうか?
ラブバニッシュもマルローではなく、バートラムが最初である、と聞いた事があります。実際にこのバートラムセクションの最初のマジック("Rub down")にラブバニッシュが用いられています。
年代的に言えばあり得る話ですが、確証がありません。
KENTAROさんへ
根本さんのカードアップザスリーブ、私は根本さんのビデオで見ました。
今、この題材も研究している最中なので、また書き込みをしたいと思っています。
私自身が好きなのは、バーノンの作品です。
今後もいろいろと教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
RYUSEIさん、実は・・
僕も、原著に書かれてる指の動きにはかなり無理があり、角度的に弱いのじゃないかと考え、実際には、おっしゃるとおり、Tarbellに書かれてるTannenのトラベラーの方法に似たやりかたを使っています。
・・・で、その後、Bertramのビデオで見ると、やってるんですね。問題の方法を。そして、これが完璧に機能してる。
要するに角度に弱い分、手と手がそれほど近付かない印象が残せ、効果が良いのです。
でも、この方法を採用する勇気がありません(涙)。
(RYUSEIさんと僕は、奇術の趣味が似ているだけでなく、到達点すら似ていることが多く驚かされます。 腹違いの双子?(笑))
僕も、原著に書かれてる指の動きにはかなり無理があり、角度的に弱いのじゃないかと考え、実際には、おっしゃるとおり、Tarbellに書かれてるTannenのトラベラーの方法に似たやりかたを使っています。
・・・で、その後、Bertramのビデオで見ると、やってるんですね。問題の方法を。そして、これが完璧に機能してる。
要するに角度に弱い分、手と手がそれほど近付かない印象が残せ、効果が良いのです。
でも、この方法を採用する勇気がありません(涙)。
(RYUSEIさんと僕は、奇術の趣味が似ているだけでなく、到達点すら似ていることが多く驚かされます。 腹違いの双子?(笑))
スターズオブマジックを読むにあたり、どうしてもすっ飛ばしてしまうのが、バートラムでした。
どうも行っている事が複雑すぎて理解しづらく、練習していても目標が見えにくかったからです。
ところが、私自身もバートラムご本人の映像をビデオで見た時、考えが変わりました。
現象はあまりにもシンプルなんです。
ゆっくりと優雅に魔法のようなマジックが繰り広げられて行くんです。
イメージする石田天海のマジックのようでした。
当時、天海師と親交が深かったバートラムも同じような考え方だったんだ、と気がつかされました。
マジックを演じる上で難しいマジックを難しそうに演じるのではなく、ごく自然にさりげなく難易度の高いマジックを行う事が、マジックに深みをもたらすのかも知れません。
このコインマジックを行う上で難しかったのは、最後の逆転現象を観客に理解させる事でした。
意外性がある事が、必ずしも一般客に受け入れられるわけではないからです。
コインスルーザテーブルにおいても4枚が一枚ずつテーブルの下に貫通した後、最後の一枚が貫通すると見せかけて下から上に貫通してしまう、という手順がありました。
しかし、一般客には、普通にコインスルーザテーブルを行った方が良いのです。
あまりにも予想外だと理解不能になり、どう反応して良いか分からない、という状態になってしまいがちです。
このバートラムのコインアクロスにおいて、自分はきちんと表現出来ませんでした。
それに比べて、タネンの『トラベラー』は、意外性という意味では表現しやすかったと思います。
4枚目のコインが、ではなく、3枚目のコインの時点で逆転現象が行われるからです。
といってもプロとして演じる上では、レパートリーから外れて行ってしまいました。
>(RYUSEIさんと僕は、奇術の趣味が似ているだけでなく、到達点すら似ていることが多く驚かされます。 腹違いの双子?(笑))
最高の褒め言葉です。ありがとうございます。
いろいろな方法論があるかとは思いますが、到達点は、一緒なんだな、と思います。
また違うマジックについての意見をお伺いしたいです。
よろしくお願いたします。
どうも行っている事が複雑すぎて理解しづらく、練習していても目標が見えにくかったからです。
ところが、私自身もバートラムご本人の映像をビデオで見た時、考えが変わりました。
現象はあまりにもシンプルなんです。
ゆっくりと優雅に魔法のようなマジックが繰り広げられて行くんです。
イメージする石田天海のマジックのようでした。
当時、天海師と親交が深かったバートラムも同じような考え方だったんだ、と気がつかされました。
マジックを演じる上で難しいマジックを難しそうに演じるのではなく、ごく自然にさりげなく難易度の高いマジックを行う事が、マジックに深みをもたらすのかも知れません。
このコインマジックを行う上で難しかったのは、最後の逆転現象を観客に理解させる事でした。
意外性がある事が、必ずしも一般客に受け入れられるわけではないからです。
コインスルーザテーブルにおいても4枚が一枚ずつテーブルの下に貫通した後、最後の一枚が貫通すると見せかけて下から上に貫通してしまう、という手順がありました。
しかし、一般客には、普通にコインスルーザテーブルを行った方が良いのです。
あまりにも予想外だと理解不能になり、どう反応して良いか分からない、という状態になってしまいがちです。
このバートラムのコインアクロスにおいて、自分はきちんと表現出来ませんでした。
それに比べて、タネンの『トラベラー』は、意外性という意味では表現しやすかったと思います。
4枚目のコインが、ではなく、3枚目のコインの時点で逆転現象が行われるからです。
といってもプロとして演じる上では、レパートリーから外れて行ってしまいました。
>(RYUSEIさんと僕は、奇術の趣味が似ているだけでなく、到達点すら似ていることが多く驚かされます。 腹違いの双子?(笑))
最高の褒め言葉です。ありがとうございます。
いろいろな方法論があるかとは思いますが、到達点は、一緒なんだな、と思います。
また違うマジックについての意見をお伺いしたいです。
よろしくお願いたします。
このスターズオブマジックにおけるトライアンフは、そのまんま日本語で読めます。
それは、東京堂出版の『カードマジック』(高木重朗著)です。
これに記載されているのは、まさしくスターズオブマジックのトライアンフなのです。
「これは、全ての奇術家の垂涎の的になると思われる革命的な技法を用いています。すなわち、あらゆるギャンブルの技法のうちで、一番至難な技法の一つと考えられている『プルスルーシャッフル』と同じ原理ではありますが、遥かに優しく行えるシャフルを用いています。」
プルスルーシャッフル。
じつは、この当時ギャンブラーの中で最高機密の技法の一つだったと思われます。
正確なやり方はあまり知られていなかったようです。
アードネスの本にさえも書かれていないのです。
それは、東京堂出版の『カードマジック』(高木重朗著)です。
これに記載されているのは、まさしくスターズオブマジックのトライアンフなのです。
「これは、全ての奇術家の垂涎の的になると思われる革命的な技法を用いています。すなわち、あらゆるギャンブルの技法のうちで、一番至難な技法の一つと考えられている『プルスルーシャッフル』と同じ原理ではありますが、遥かに優しく行えるシャフルを用いています。」
プルスルーシャッフル。
じつは、この当時ギャンブラーの中で最高機密の技法の一つだったと思われます。
正確なやり方はあまり知られていなかったようです。
アードネスの本にさえも書かれていないのです。
さて『トライアンフ』というタイトルは何故つけられたのでしょうか?
その意味は“勝利”です。
しかし、なぜ勝利なのでしょう。
自分は意地悪な観客が表と裏にバラバラにシャッフルして来た事に対しての勝利だと思っていました。
じつは理由はないんです。
???
編者のジョージ・スタークスにバーノンがこの作品を見せたところ、ぜひ小冊子に載せよう、という事になりました。
で、なんというタイトルなのか? という質問にバーノンは、
「いや、べつにないよ。」
と答えたのです。
まあ、こうした事は当時、よくある事で別にタイトルを考えたりはしてなかったりします。
じゃあ、どんなタイトルにしようか、と悩んでいると…。
「トライアンフでいいんじゃない?」
そばにいた幼きバーノンの息子が無邪気に言いました。
まあ、それでいいか、という事で、トライアンフに決まったのです。
その意味は“勝利”です。
しかし、なぜ勝利なのでしょう。
自分は意地悪な観客が表と裏にバラバラにシャッフルして来た事に対しての勝利だと思っていました。
じつは理由はないんです。
???
編者のジョージ・スタークスにバーノンがこの作品を見せたところ、ぜひ小冊子に載せよう、という事になりました。
で、なんというタイトルなのか? という質問にバーノンは、
「いや、べつにないよ。」
と答えたのです。
まあ、こうした事は当時、よくある事で別にタイトルを考えたりはしてなかったりします。
じゃあ、どんなタイトルにしようか、と悩んでいると…。
「トライアンフでいいんじゃない?」
そばにいた幼きバーノンの息子が無邪気に言いました。
まあ、それでいいか、という事で、トライアンフに決まったのです。
パター(口上)というものは後付けのような気がします。
考えてみれば、マジック自体の作品が出来上がる事によって、どういうセリフにしようか、と考えるものでしょう。
例えば、同著に収められている『カッティング・ジ・エーセス』も、考えてみれば不思議じゃありませんか。
片腕のギャンブラーと言いながら、実際の片手の動作は、あのワンハンドスリップカットの部分だけなんです。
あのパターはやはり、後から考えたのだ、と思います。
技法を正当化する為に…。
もしかすると『トライアンフ』というタイトルが決まったからこそ、そういうパターが作られたのかも。
裏表をバラバラに混ぜる、という現象自体はグラントの『チークトゥチーク』という作品にも見られます。
確か、こっちの方がトライアンフより古かったのでは。
考えてみれば、マジック自体の作品が出来上がる事によって、どういうセリフにしようか、と考えるものでしょう。
例えば、同著に収められている『カッティング・ジ・エーセス』も、考えてみれば不思議じゃありませんか。
片腕のギャンブラーと言いながら、実際の片手の動作は、あのワンハンドスリップカットの部分だけなんです。
あのパターはやはり、後から考えたのだ、と思います。
技法を正当化する為に…。
もしかすると『トライアンフ』というタイトルが決まったからこそ、そういうパターが作られたのかも。
裏表をバラバラに混ぜる、という現象自体はグラントの『チークトゥチーク』という作品にも見られます。
確か、こっちの方がトライアンフより古かったのでは。
プル・スルー・シャッフル(The Pull-Through Shuffle)は、別名プッシュ・スルー・シャッフル(The Push-Through Shuffle)と言います。
実際の用法を考えるとプルしてスルーというよりは、プッシュしてスルーの方が言葉としては適しているのかも知れません。
ちなみにプル・アウト・シャッフル(The Pull-Out Shuffle)はストリップ・アウト・シャッフル(The Strip-Out Shuffle)とも言います。
バーノン自身はプッシュスルーを使っていたとされています。が、しかし、グレート・トムソーニはバーノンはプルアウトを使っていた、と証言しています。
実際の用法を考えるとプルしてスルーというよりは、プッシュしてスルーの方が言葉としては適しているのかも知れません。
ちなみにプル・アウト・シャッフル(The Pull-Out Shuffle)はストリップ・アウト・シャッフル(The Strip-Out Shuffle)とも言います。
バーノン自身はプッシュスルーを使っていたとされています。が、しかし、グレート・トムソーニはバーノンはプルアウトを使っていた、と証言しています。
カンガルーコインを擁護する意見希望。いまやすっかりラッピングは影を潜め、コインスルーザテーブルすら立って行うという有様なのだが、座ってやってもおかしくなかった時期に、カンガルーコインはその秀逸さにもかかわらず、コインスルーザテーブルの陰に隠れる存在だったように見受けられた。コップを準備するのが大変だという最大の難関を乗り越えてまで、だからカンガルーコインはすごいと、教えてくれる方の意見をぜひとも聞きたいと思います。
ちなみに、ラッピング自体はすでに一世代前の技術となりつつあるが、私はこれを知らない、できない人は認めない。少なくとも、コインスルーザテーブルひとつまともにできないようでは、われわれの大好きな『マジック』に、顔向けができないではないか。
ちなみに、ラッピング自体はすでに一世代前の技術となりつつあるが、私はこれを知らない、できない人は認めない。少なくとも、コインスルーザテーブルひとつまともにできないようでは、われわれの大好きな『マジック』に、顔向けができないではないか。
僕はカンガルーコインをやるなら、
Krauseを始めとする、グラスを使わない4枚が1枚ずつ貫通する手順(Galloの『元に戻るクライマックス』を最後に使用してますが)か、
SlydiniのChinese Classicを選ぶのですが・・・・
というのは、やはり、そっちの方が受けるから。
ところで、カンガルーの特徴として『手順構成(ラップするタイミング)の巧妙さ』と『グラスによる音響効果』が強調されますが、僕はそれ以上に『グラスを持っていることによる手の不自由さ』ということがポイントになる、と考えています。
要するに、コインを受け取るべく、テーブルの下に回した手は、客からは見えなくなるので、ホントは何をしてるかわからないわけです。
ところが、その手にグラスを持つと、手がふさがるために細かいテクニックなどし難いような印象が与えられると思われます。
その効果を強調するために、なるべくグラスを持つときに、グラスの底辺付近を指先で持ち『指を使ってグラスの口からコインを入れた可能性』を感じにくくすることも、大切なんじゃないか、と考えています。
Krauseを始めとする、グラスを使わない4枚が1枚ずつ貫通する手順(Galloの『元に戻るクライマックス』を最後に使用してますが)か、
SlydiniのChinese Classicを選ぶのですが・・・・
というのは、やはり、そっちの方が受けるから。
ところで、カンガルーの特徴として『手順構成(ラップするタイミング)の巧妙さ』と『グラスによる音響効果』が強調されますが、僕はそれ以上に『グラスを持っていることによる手の不自由さ』ということがポイントになる、と考えています。
要するに、コインを受け取るべく、テーブルの下に回した手は、客からは見えなくなるので、ホントは何をしてるかわからないわけです。
ところが、その手にグラスを持つと、手がふさがるために細かいテクニックなどし難いような印象が与えられると思われます。
その効果を強調するために、なるべくグラスを持つときに、グラスの底辺付近を指先で持ち『指を使ってグラスの口からコインを入れた可能性』を感じにくくすることも、大切なんじゃないか、と考えています。
すばらしい!考えてみれば、普通に水を飲むかのごとくからのコップを持てば、後は傾けるしか動きの選択の余地がないように見える!これまた、やっとコップ使用の意味がわかった、つまり「机の下に行く手は怪しくない」ということ。
ギャロの、元に戻るクライマックス、と聞いて触手動かされた方は、正しい。現象を説明してしまいましょう、スルーザテーブルで、3枚目まで順当に机を抜けたところ、最後の一枚を、さてどうやって通すのかな、と思ってみていると案の定注目の集まる中なかなか落ちていかない。と、突然テーブルの下の3枚が、机の上のこぶしの中に「上がって」きて、再び4枚が机の上でそろってしまう、というもの。マイケルアマーのアンコール、という小冊子(私はなぜか日本語版で見た)と、マジックオブマイケルアマーという単行本の中にのっています。と、ここで解説を打ち切ってしまおうと思うのだけど、どうです、知らない人は、想像力の翼とどうしても知りたい欲望がひろがる事を感じますでしょう。そういうのが、とっても大事。
カンガルーといえば、コップを使うのがそれで、そうでなければスルーザテーブルだと思っていたのだけど、CULLさんの話ではグラスを使わないカンガルーとかいてあり(そのように読めてしまうということ)、そんなカンガルーなんて知らなかった、何が机とカンガルーを分ける条件なのでしょう。ついでに教えてください。
グラスに落ちる音響効果は言わずもがな、どれだけこの音がマジックに幅を持たせていることか、あるいはマジックの格を上げていることか。思わず、ハンキーパンキー(コインマジック事典、またはすでに絶版講談社現代新書の高木重郎本の中に記載あり)などという無視されがちなネタを思い出してしまった。
ギャロの、元に戻るクライマックス、と聞いて触手動かされた方は、正しい。現象を説明してしまいましょう、スルーザテーブルで、3枚目まで順当に机を抜けたところ、最後の一枚を、さてどうやって通すのかな、と思ってみていると案の定注目の集まる中なかなか落ちていかない。と、突然テーブルの下の3枚が、机の上のこぶしの中に「上がって」きて、再び4枚が机の上でそろってしまう、というもの。マイケルアマーのアンコール、という小冊子(私はなぜか日本語版で見た)と、マジックオブマイケルアマーという単行本の中にのっています。と、ここで解説を打ち切ってしまおうと思うのだけど、どうです、知らない人は、想像力の翼とどうしても知りたい欲望がひろがる事を感じますでしょう。そういうのが、とっても大事。
カンガルーといえば、コップを使うのがそれで、そうでなければスルーザテーブルだと思っていたのだけど、CULLさんの話ではグラスを使わないカンガルーとかいてあり(そのように読めてしまうということ)、そんなカンガルーなんて知らなかった、何が机とカンガルーを分ける条件なのでしょう。ついでに教えてください。
グラスに落ちる音響効果は言わずもがな、どれだけこの音がマジックに幅を持たせていることか、あるいはマジックの格を上げていることか。思わず、ハンキーパンキー(コインマジック事典、またはすでに絶版講談社現代新書の高木重郎本の中に記載あり)などという無視されがちなネタを思い出してしまった。
S原さん、こんにちは。
僕の書き方がまずかったので、誤解を生んでます。ごめんなさい。
『もしもCoin thru the Tableをやるならば、カンガルーを採用するよりも、普通のCoin thru the TableかSlydiniのハンピンチェンを使った方法を選択します』・・・という意味合いでした。
ちなみに『音響効果』という意味では、SlydiniのChinese Classicにおける、例の『パンパンパンッ!』という通り抜ける音(なのか?(笑))は、Close-Up Magic中最も印象に残る音の一つだと僕は思ってます。
実際、通常の古典的Coin thru the Tableにおいて、視覚的効果の部分というのは『ない』わけで、それを考えるに、Slydiniのあの音は、客に貫通した瞬間を『音によって見せる』という効果を発揮している、すばらしい演出だと思います。
僕の書き方がまずかったので、誤解を生んでます。ごめんなさい。
『もしもCoin thru the Tableをやるならば、カンガルーを採用するよりも、普通のCoin thru the TableかSlydiniのハンピンチェンを使った方法を選択します』・・・という意味合いでした。
ちなみに『音響効果』という意味では、SlydiniのChinese Classicにおける、例の『パンパンパンッ!』という通り抜ける音(なのか?(笑))は、Close-Up Magic中最も印象に残る音の一つだと僕は思ってます。
実際、通常の古典的Coin thru the Tableにおいて、視覚的効果の部分というのは『ない』わけで、それを考えるに、Slydiniのあの音は、客に貫通した瞬間を『音によって見せる』という効果を発揮している、すばらしい演出だと思います。
じつは『コインスルーザテーブル』そのものは、こちらで行っています。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5773306&comm_id=236730
スライディーニ式のバン!バン!チャリン、という音、自分も大好きです。
最も印象に残っているのは、昔テレビでジャック武田さんがマジックキャッスルでこのマジックを行っていたときの音です。
必要以上に大きな音でしたが、妙に印象に残っています。
カンガルーコインにおいてCULLさんのグラスの考察は大変興味深く思います。と同時に持ち運びの不便さも良く分かります。
S原さんのいうアマーのアンコールは私も読みました。しかしかつておっしゃっていたように自分も外道と考え、レパートリーから外れています。同じく『カンガルーコイン』もやはり亜流と考え、レパートリーから外れてしまっているのが現状です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5773306&comm_id=236730
スライディーニ式のバン!バン!チャリン、という音、自分も大好きです。
最も印象に残っているのは、昔テレビでジャック武田さんがマジックキャッスルでこのマジックを行っていたときの音です。
必要以上に大きな音でしたが、妙に印象に残っています。
カンガルーコインにおいてCULLさんのグラスの考察は大変興味深く思います。と同時に持ち運びの不便さも良く分かります。
S原さんのいうアマーのアンコールは私も読みました。しかしかつておっしゃっていたように自分も外道と考え、レパートリーから外れています。同じく『カンガルーコイン』もやはり亜流と考え、レパートリーから外れてしまっているのが現状です。
Coin thru the Table、トピックを立ち上げたのに
放置してすみません。。。
とか言いつつも、何だかこっちに書いた方が盛り上がりそうなので
続けてここに書きます(苦笑)
"Kangaroo Coin"、皆さん書いていることですが
キモはやはりあの『音』ですよね。
右手のタイミングとピッタリ合った時の効果は、もう筆舌に尽くしがたい。
というのを(最近の話ですが)他人の演技を見て確信しました。
Lapしたコインをスムーズに扱えさえ出来れば
(いや、それが難しくて、軽く断念してた訳ですが)
これはもう即戦力になると思って、手順をゴニョゴニョしている最近です。
>RYUSEIさん
そんなわけでKangaroo Coinに惚れ込んでいる僕ですが、
どの部分で引っかかってレパートリーから外されたんでしょうか?
参考までにお聞かせ下さると有難いです。
以下は、また古い話題。
"Cheek to Cheek"(よく考えると絶妙な命名!)が
"Triumph"より古い、というのは松田道弘氏の書籍にありましたね。
(どの本だったかはド忘れ。。。)
そうそう、前回のオフの時に
興味深いStrip-Out Shuffleを見せようと思っていたのに、
タイミングを逃して見せていないことを思い出しました。
それはまたの機会で。
放置してすみません。。。
とか言いつつも、何だかこっちに書いた方が盛り上がりそうなので
続けてここに書きます(苦笑)
"Kangaroo Coin"、皆さん書いていることですが
キモはやはりあの『音』ですよね。
右手のタイミングとピッタリ合った時の効果は、もう筆舌に尽くしがたい。
というのを(最近の話ですが)他人の演技を見て確信しました。
Lapしたコインをスムーズに扱えさえ出来れば
(いや、それが難しくて、軽く断念してた訳ですが)
これはもう即戦力になると思って、手順をゴニョゴニョしている最近です。
>RYUSEIさん
そんなわけでKangaroo Coinに惚れ込んでいる僕ですが、
どの部分で引っかかってレパートリーから外されたんでしょうか?
参考までにお聞かせ下さると有難いです。
以下は、また古い話題。
"Cheek to Cheek"(よく考えると絶妙な命名!)が
"Triumph"より古い、というのは松田道弘氏の書籍にありましたね。
(どの本だったかはド忘れ。。。)
そうそう、前回のオフの時に
興味深いStrip-Out Shuffleを見せようと思っていたのに、
タイミングを逃して見せていないことを思い出しました。
それはまたの機会で。
カンガルーがスルーザテーブルの亜流であるという出自からして、カンガルーが「くくり」のタイトルにはなれないような気がします。せいぜい「カンガルーのバリエーション」にしかなれないのでは。
コップを使うという意味で見回してみると、今度は「コイントゥザグラス」になってしまい、今度は机がなくなる。
4枚のコインアクロスを知っていると、その左手を単に毎回机の下にもっていくだけでスルーザテーブルに見えてしまうが、実際にはこの左手は隠す必要はない。同様に、トヒさんのアイデアは、机の下に手を持ってこないと、同時にグラスもなければ、別の形で表現できないという意味で、とても興味深いものだと思います。ということで、その核となるアイデアと、詳細を希望します!赤松さんの文章は東京堂本内に若干あるので、いいリファレンスがあればその関連を教えてください。
コップを使うという意味で見回してみると、今度は「コイントゥザグラス」になってしまい、今度は机がなくなる。
4枚のコインアクロスを知っていると、その左手を単に毎回机の下にもっていくだけでスルーザテーブルに見えてしまうが、実際にはこの左手は隠す必要はない。同様に、トヒさんのアイデアは、机の下に手を持ってこないと、同時にグラスもなければ、別の形で表現できないという意味で、とても興味深いものだと思います。ということで、その核となるアイデアと、詳細を希望します!赤松さんの文章は東京堂本内に若干あるので、いいリファレンスがあればその関連を教えてください。
たとえばコインを貫通させたくなるようないい感じの木のテーブルがあったらコインスルーザテーブルをやってみたい、とか、そこに飾りとしてグラスを使いたいとかは
、、、とても大事な要因だと思います。
どこかに書いたか、ダローの演技を生で見たときがあり、そのときの印象といえば、デイトブックの不可思議さと、コイントゥザグラスの際の思い切りよどみない動きと、グラスに落ちるるコインの音。確認したわけではないが、ダローはシルバーのコインと、クリスタルのコップを使っていた(模様、そう思えたばかりで実際はわからない)。グラスに落ちる音が、クシャンクシャンと、美しいことこの上なかった。クリスタルのカットグラスといえば、その宝飾のような美しさと、ただのガラスと異なる高貴な音が特徴だろう。こんなところからも、ダローが凡百のマニア衆とは格が違うことを思い知ったのだ。使うグラスがクリスタルというのは、だから(おそらくは)秘伝中の秘伝なのだと思う。こんな秘密は、めったなことで人に教えてはいけません(聞かれなければ)。
、、、とても大事な要因だと思います。
どこかに書いたか、ダローの演技を生で見たときがあり、そのときの印象といえば、デイトブックの不可思議さと、コイントゥザグラスの際の思い切りよどみない動きと、グラスに落ちるるコインの音。確認したわけではないが、ダローはシルバーのコインと、クリスタルのコップを使っていた(模様、そう思えたばかりで実際はわからない)。グラスに落ちる音が、クシャンクシャンと、美しいことこの上なかった。クリスタルのカットグラスといえば、その宝飾のような美しさと、ただのガラスと異なる高貴な音が特徴だろう。こんなところからも、ダローが凡百のマニア衆とは格が違うことを思い知ったのだ。使うグラスがクリスタルというのは、だから(おそらくは)秘伝中の秘伝なのだと思う。こんな秘密は、めったなことで人に教えてはいけません(聞かれなければ)。
さて、トヒさんの手順。なんといっても、4枚目をこのように行いたいための手順であり、そのために3枚目が普通に示されるところは、まるでTwisting the Aの3枚目のようで、いい流れだと思います。そのために、2枚目のところに、一番トリッキーな部分が来ているところも、グラスだからこそのハンピンチェンだし、マジックらしい表現で面白い。一枚目のひそかな移動も、赤松手順のエッセンスのようなやり方で、この手順の母体を暗示しているようなファンファーレになっていて、こうしてみるとどれ一つゆるがせにできないような引き締まった手順になっていて、よくできた手順だと思います。
4枚目を読んだとき、私はデビッドロスのパースアンドグラスを思い出しました。ラッピングとミスディレクションの、行き着くところといった感じ。
グラスを急激に動かして音を立てて一枚飛び込んだ振りをする、という部分は、ランドから出ているロベルトジョビー(あのジョビーだ)のレクチャーノートのなかの、コイントゥザグラスの中に同じ手を使っているのを思い出した。ここでは3枚しか使っていないから、使わずを得ずして使っている感じだった。カンガルーに使っているのは、トヒ手順ではじめてみました。こちらは、二川手順のようにはやらない、というところが余裕の美点だと思います。
4枚目を読んだとき、私はデビッドロスのパースアンドグラスを思い出しました。ラッピングとミスディレクションの、行き着くところといった感じ。
グラスを急激に動かして音を立てて一枚飛び込んだ振りをする、という部分は、ランドから出ているロベルトジョビー(あのジョビーだ)のレクチャーノートのなかの、コイントゥザグラスの中に同じ手を使っているのを思い出した。ここでは3枚しか使っていないから、使わずを得ずして使っている感じだった。カンガルーに使っているのは、トヒ手順ではじめてみました。こちらは、二川手順のようにはやらない、というところが余裕の美点だと思います。
Rouisさんへ
>どの部分で引っかかってレパートリーから外されたんでしょうか?
こんな事を言うのは自分だけかも知れませんが、カンガルーコインをレパートリーから外したのは、素晴らしすぎるからです。
あまりにも素晴らしい作品だからです。
自分の場合はコインマジックの最後は”ワンコインルーティン”です。
”カンガルーコイン”を行ってしまうと、それがフィニッシュになってしまう、すなわちクライマックスになってしまうのです。
とは言うもの昨日は久しぶりに”カンガルーコイン”を解禁しました。
通常の”コインスルーザテーブル”より現象的には美しくなっている事は観客の反応を見ても間違いありませんでした。
>どの部分で引っかかってレパートリーから外されたんでしょうか?
こんな事を言うのは自分だけかも知れませんが、カンガルーコインをレパートリーから外したのは、素晴らしすぎるからです。
あまりにも素晴らしい作品だからです。
自分の場合はコインマジックの最後は”ワンコインルーティン”です。
”カンガルーコイン”を行ってしまうと、それがフィニッシュになってしまう、すなわちクライマックスになってしまうのです。
とは言うもの昨日は久しぶりに”カンガルーコイン”を解禁しました。
通常の”コインスルーザテーブル”より現象的には美しくなっている事は観客の反応を見ても間違いありませんでした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-