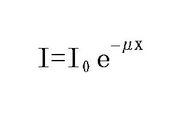|
|
|
|
コメント(8)
私も、へぼ担当様と同じ意見で、「最小努力」ということであれば弊機構の研修コースの教科書がよくできていると思いますが・・・、
「理想」を申し上げれば、それぞれの教科に応じた良い教科書を手に入れることをお薦めします。
以下、私が合格した際に、弊機構(旧原研時代)内で「アンチョコ」としてまとめるように指示されて、個人的にまとめたものですので、参考にしてください。
原子炉物理学:ラマーシュの「原子炉の初等理論」(吉岡書店)、ドゥデルスタット&ハミルトンの「原子炉の理論と解析」(現代工学社)
熱伝導・熱伝達及び流体力学:西川、藤田の「機械工学基礎講座/伝熱学」(理工学社)、「伝熱工学資料・改訂4版」(日本機械学会)
材料力学及び破壊力学:矢川、一宮の「原子炉構造設計」(培風館)
ウラン及びプルトニウムの化学等:、「原子力ハンドブック」(オーム社)と炉修のテキスト、特にプルトニウムについて素早くデータを集めたければ松岡理の「プルトニウムの安全性評価」(日刊工業新聞社)
構造材料及び冷却材の化学:炉修のテキストぐらいしか思いつきません。
電気工学、電子工学及び制御理論:あまり良い教科書がないですが「ニューラル・ネットワーク」とか「ファジイ制御」とか、実際の原子炉で使ってますか!?っていうような出題があったりします。要注意。
放射能と放射線:アイソトープ手帳(日本アイソトープ協会)、そのほかにも放射線取扱主任者試験用の教科書
放射線測定:放射線取扱主任者の教科書を利用できる。また、体系的に学習するにはノル(木村逸郎訳)の「放射線計測ハンドブック」(日刊工業新聞社)が完璧なデータを提供してくれる。
放射線の影響、管理及び評価:、「放射線施設のしゃへい計算・実務マニュアル」(原子力安全技術センター)、「原子力安全委員会安全審査指針集」(大成出版社)
こんなところですかね・・・。
学生さんにとって最大のハンディ・キャップは、実務経験により得られる知識をどうやって得るか? ということになります。へぼ担当様が挙げられている設置許可申請書は知識を反映した「最終案」となっていまして、試験で必要とされる知識は「最終案」の記載は何故そうなっているのか?ということが問われます。
別スレッドで応力腐食割れが話題になっていますが、ごく単純に「水冷却型動力炉は何故加圧されているのか?」という問いから発展して、安全性に関する本質的な議論になりますが、やはり、炉主任試験ではこのあたりの正確な知識が求められます。熱効率、冷却水温度、燃料温度、何故酸化物燃料か? 燃料ピンに何故ヘリウムが充填されているか? 燃焼が進んだときの燃料の挙動は? などなど、ぜーーんぶ関連してきます。
私は研究炉(しかも、臨界装置なので冷却の考慮さえない)畑なので、動力炉の知識は、電力会社殿の受験者さんに比べて格段に劣っていて、ハンディーを感じたものです。
特に、弊機構の研修において、演習の想定問答で愕然としました。研究炉畑の人間はBWRの炉心圧力はだいたい70気圧程度、なんて、ぼやーっと覚えているのですが、70気圧だけ? 75気圧だっけ? なんて言ってたら、電力会社からの研究生さんに「プっ」と笑われました。「あっというまにスクラムするぞ」ということで。
健闘をお祈りします。
「理想」を申し上げれば、それぞれの教科に応じた良い教科書を手に入れることをお薦めします。
以下、私が合格した際に、弊機構(旧原研時代)内で「アンチョコ」としてまとめるように指示されて、個人的にまとめたものですので、参考にしてください。
原子炉物理学:ラマーシュの「原子炉の初等理論」(吉岡書店)、ドゥデルスタット&ハミルトンの「原子炉の理論と解析」(現代工学社)
熱伝導・熱伝達及び流体力学:西川、藤田の「機械工学基礎講座/伝熱学」(理工学社)、「伝熱工学資料・改訂4版」(日本機械学会)
材料力学及び破壊力学:矢川、一宮の「原子炉構造設計」(培風館)
ウラン及びプルトニウムの化学等:、「原子力ハンドブック」(オーム社)と炉修のテキスト、特にプルトニウムについて素早くデータを集めたければ松岡理の「プルトニウムの安全性評価」(日刊工業新聞社)
構造材料及び冷却材の化学:炉修のテキストぐらいしか思いつきません。
電気工学、電子工学及び制御理論:あまり良い教科書がないですが「ニューラル・ネットワーク」とか「ファジイ制御」とか、実際の原子炉で使ってますか!?っていうような出題があったりします。要注意。
放射能と放射線:アイソトープ手帳(日本アイソトープ協会)、そのほかにも放射線取扱主任者試験用の教科書
放射線測定:放射線取扱主任者の教科書を利用できる。また、体系的に学習するにはノル(木村逸郎訳)の「放射線計測ハンドブック」(日刊工業新聞社)が完璧なデータを提供してくれる。
放射線の影響、管理及び評価:、「放射線施設のしゃへい計算・実務マニュアル」(原子力安全技術センター)、「原子力安全委員会安全審査指針集」(大成出版社)
こんなところですかね・・・。
学生さんにとって最大のハンディ・キャップは、実務経験により得られる知識をどうやって得るか? ということになります。へぼ担当様が挙げられている設置許可申請書は知識を反映した「最終案」となっていまして、試験で必要とされる知識は「最終案」の記載は何故そうなっているのか?ということが問われます。
別スレッドで応力腐食割れが話題になっていますが、ごく単純に「水冷却型動力炉は何故加圧されているのか?」という問いから発展して、安全性に関する本質的な議論になりますが、やはり、炉主任試験ではこのあたりの正確な知識が求められます。熱効率、冷却水温度、燃料温度、何故酸化物燃料か? 燃料ピンに何故ヘリウムが充填されているか? 燃焼が進んだときの燃料の挙動は? などなど、ぜーーんぶ関連してきます。
私は研究炉(しかも、臨界装置なので冷却の考慮さえない)畑なので、動力炉の知識は、電力会社殿の受験者さんに比べて格段に劣っていて、ハンディーを感じたものです。
特に、弊機構の研修において、演習の想定問答で愕然としました。研究炉畑の人間はBWRの炉心圧力はだいたい70気圧程度、なんて、ぼやーっと覚えているのですが、70気圧だけ? 75気圧だっけ? なんて言ってたら、電力会社からの研究生さんに「プっ」と笑われました。「あっというまにスクラムするぞ」ということで。
健闘をお祈りします。
>noferiaさん
炉主任で出題される範囲を全て網羅し、かつ理解し、試験で合格した範囲の分野に関して質問されれば答えれるだけの知識を身につける!
という事であれば、間違いなく、へぼ担当さんとけんたさんの書かれている内容で間違いないかと思います。
ただ、私は、実は、へぼ担当さんが挙げられた内容全てはやりきれませんでした。多分勉強量と知識の奥深さからいきますと、「運良く炉主任に受かったやつ」と「へぼ担当さんやけんたさんのように、全範囲の知識を確実なまでに理解されている方」のちょうど中間ぐらいだと思います。(お恥ずかしい)
最近の炉主任試験の傾向からいきますと、計算問題のようなアカデミックな問題はどんどん減少傾向にあり、そのぶん文章で説明する問題が増えている傾向にあると思います。つまり、言い換えれば、「受かる」だけに目標を据えると、計算問題を全て捨てて、暗記だけすることによって受かる事も可能となってしまいます。
実際に、過去問5年分の計算以外の問題を暗記し、まぁ簡単そうな計算問題の解き方を暗記し、難しい計算は全て捨て、3ヶ月の勉強で、受かったやつもいます。
ただ、炉主任試験の意味を考えると、受かることだけに目標を据える事は危険であり、かつ、炉主任ホルダーとなると、当然知っているだろうと思われる知識が欠如していると、後々恥をかくことも多々あるため、お勧めはしません。ただ、純粋に取ることだけが、目標であるなら、そういった方法も検討されてもいいような気はします。
では、私は、どうしたかと言いますと、お二人が言っておられる、
「原子力研究開発機構(JAEA)の研修コースで配布される教材」
は、友人にコピーさせてもらいました。その他、必要と考えられる、資料は、ありとあらゆる所からとりあえずコピーし、高価な教科書類は、買いませんでした。試験当日に持っていったこれらのコピー類は、大体5cmキングファイルで5冊といったところでしょうか。(ただ、全部を完全に熟読した訳ではありません)
教科毎に言いますと、
1、理論・・・原子核を大学で全くやってこなかった私にとっては、この分野が相当しんどかったです。多分勉強した全体量の6割ぐらいは炉物理に費やしたと思います。
?まず、大学時代遊びほうけていたため、微分方程式が全く分かりませんでしたので、数学の教科書を買いました。そして微分方程式の勉強をしました。(時間がないのであれば、炉主任で必要とされる微分方程式は決まっているので、飛ばしても構いません。属に言う、解き方を覚えるという方法でも対応可能です。ただ、私は個人的に数学ぐらいちょっとやっておかないと・・・と思ったので、やりました)
?「原子力研究開発機構(JAEA)の研修コースで配布される教材」の炉物理を読む。私が勉強をした時に講師をされている方の書かれたものと、その前の方が書かれたもの、それぞれが一長一短あったので、3冊読みました。
?同じく研修コースで配布されたという、炉物理の問題集を全部やりました。(計算問題のみのものです)
?過去問12年分ぐらいの計算問題を、???の資料+ラマーシュを駆使してとりあえず、解けるようにしました。(ラマーシュは読破すべきなのかもしれないですが、時間との兼ね合いで考えて、必要部分だけを読むようにしました)
?あとは、計算式を全てエクセルで一覧表にしたり、どういった時に、どういった式が必要なのかをまとめたりしました。
?あとは、知識ものですが、過去問で出題されたキーワードを中心に、参考書、ネット、知人など、色んな所からそのキーワード周辺の知識を仕入れて覚えました
理論は以上です。多分、大学で原子核をやっていないとこの科目が本当にしんどいです。
2、制御
?炉物理の科目と合わせて、動特性の(JAEA)の研修コースの参考書を読む。
?(JAEA)の研修コースで配布された問題を解く
?過去問12年分の全ての問題を解けるようにする
?あとは、知識をエクセル、ワードで整理
?知識系は炉物理同様。指針類は原子力安全委員会のHPからダウンロードして使いました。設計審査指針は、全部暗記し、評価審査指針、耐震・・・など、かなり覚える事が満載です。ただ、受かるためだけを目標にするなら、近年指針類の問題は減少傾向になるので、捨ててもかまいません。(覚え出すと、かなりの物量で、本当にしんどいです)
3、設計
?(JAEA)の研修コースの熱水力の参考書を読む、熱力、流体でわからない部分は、参考書を別途かって、ちょこちょこ読む。(全部読む時間はなかったので、辞書的に使いました。)
?材料、構造力学の問題は、一般的な参考書のみを使いました。(大学が材料だったので、この分野の参考書はそこそこ持っていて助かりました。)
?過去問12年分を全て解けるようにする
?他の科目同様同じく知識整理と暗記
4、燃料・材料
?(JAEA)の研修コースの参考書を読む。あと、パワーポイントがあるのですが、これがかなり使えます。
?過去問をとにかくやれるだけやる(はっきり言ってこの科目は知っていた者勝ちです。やれるだけやって知識をどんどん太くした方が良いと思います。私は、大体15〜20年分の問題を見ましたが、多分10年分ぐらいすれば、あとは、似たような問題が繰り返されるだけです。出題された問題のみを暗記するだけでなく、その周辺部分の理解が大切かと思います)
5、放射線
確かnoferiaさんは、RIの資格持ってますよね?あれ持っていれば楽勝です。最近、炉主任の放射線の問題はRIの資格に近くなってきているので、何も勉強しなくても良いくらいです。難易度はRIの試験の20%ぐらいの難易度しかありません。RIをもっているなら100点が狙える科目です。
過去問をやると、RI以外の問題として、原子力発電所の放射線管理的な問題が出ているのが分かると思いますので、そういったものだけ、ネット調べたりして、キーワードの周辺知識を太くしていけば楽勝です。
もしギリギリのボーダーでの合格を狙っているなら、是非100点をとっておきたい科目です。(他の科目を受験する時のプレッシャーが減ります)
6、法令
私は、法律の必要部分を暗記しました。暗記の仕方は色々工夫が必要かと思います。最近は選択式の問題が多いので、昔の炉主任より法律の難易度は下がっています。(昔は、丸丸記述させる問題が出ていました。私は、どの年代の問題が出ても100%受かる状態にしようと思ったので、かなり暗記しましたが、最近の法律の問題のみに的を絞るなら負担はかなり減ると思います。)
暗記すれば、満点取れるので、他の科目の負担を減らすために、頑張っておくと良いと思います。
以上です。
原子核を大学時代やってこられたなら、炉物理も大したことないらしいですが、私のように、全くの場合、炉物理が本当にしんどいです。
私は、計算問題に対して
研修コース(1cm弱)×3冊+問題集(1.5cmぐらい)1冊+過去問12年分+ラマーシュの必要部分のみ+数学の参考書2冊
といった感じですが、本当の奥深くまで理解されている方は、私の何倍もの参考書を読んでおられると思いますし、逆に、計算を捨てると、この勉強量がなくなるので、途端に半分以下の努力ですみます。目標とされる知識レベルを考えて選ばれればいいかと思います。
また、私は、トータルで、大体1年3ヶ月勉強してこの資格を取りましたので、2回受験しています。
1回目は3ヶ月の勉強で、前日は数学の参考書を読んでました。(笑)(当然受かる気はありませんでした)
炉物理、設計、制御の3科目しか勉強してなかったので、当然法律などは0点だったと思います。(放射線はRI持っていれば勉強しなくても合格ラインは堅いと思いますが)
2回目は受験前から、自信があったので、結構すんなり受かりましたが、それでも、炉主任を取った後に、
「そんなことも知らないで炉主任を取ったのか!」
とバカにされることもたまにありますので、取るよりも取った後の方がしんどいんだなぁと最近実感します。
取った後のことも考えて、勉強するとなると、結構しんどいとは思いますが、頑張ってください。
炉主任で出題される範囲を全て網羅し、かつ理解し、試験で合格した範囲の分野に関して質問されれば答えれるだけの知識を身につける!
という事であれば、間違いなく、へぼ担当さんとけんたさんの書かれている内容で間違いないかと思います。
ただ、私は、実は、へぼ担当さんが挙げられた内容全てはやりきれませんでした。多分勉強量と知識の奥深さからいきますと、「運良く炉主任に受かったやつ」と「へぼ担当さんやけんたさんのように、全範囲の知識を確実なまでに理解されている方」のちょうど中間ぐらいだと思います。(お恥ずかしい)
最近の炉主任試験の傾向からいきますと、計算問題のようなアカデミックな問題はどんどん減少傾向にあり、そのぶん文章で説明する問題が増えている傾向にあると思います。つまり、言い換えれば、「受かる」だけに目標を据えると、計算問題を全て捨てて、暗記だけすることによって受かる事も可能となってしまいます。
実際に、過去問5年分の計算以外の問題を暗記し、まぁ簡単そうな計算問題の解き方を暗記し、難しい計算は全て捨て、3ヶ月の勉強で、受かったやつもいます。
ただ、炉主任試験の意味を考えると、受かることだけに目標を据える事は危険であり、かつ、炉主任ホルダーとなると、当然知っているだろうと思われる知識が欠如していると、後々恥をかくことも多々あるため、お勧めはしません。ただ、純粋に取ることだけが、目標であるなら、そういった方法も検討されてもいいような気はします。
では、私は、どうしたかと言いますと、お二人が言っておられる、
「原子力研究開発機構(JAEA)の研修コースで配布される教材」
は、友人にコピーさせてもらいました。その他、必要と考えられる、資料は、ありとあらゆる所からとりあえずコピーし、高価な教科書類は、買いませんでした。試験当日に持っていったこれらのコピー類は、大体5cmキングファイルで5冊といったところでしょうか。(ただ、全部を完全に熟読した訳ではありません)
教科毎に言いますと、
1、理論・・・原子核を大学で全くやってこなかった私にとっては、この分野が相当しんどかったです。多分勉強した全体量の6割ぐらいは炉物理に費やしたと思います。
?まず、大学時代遊びほうけていたため、微分方程式が全く分かりませんでしたので、数学の教科書を買いました。そして微分方程式の勉強をしました。(時間がないのであれば、炉主任で必要とされる微分方程式は決まっているので、飛ばしても構いません。属に言う、解き方を覚えるという方法でも対応可能です。ただ、私は個人的に数学ぐらいちょっとやっておかないと・・・と思ったので、やりました)
?「原子力研究開発機構(JAEA)の研修コースで配布される教材」の炉物理を読む。私が勉強をした時に講師をされている方の書かれたものと、その前の方が書かれたもの、それぞれが一長一短あったので、3冊読みました。
?同じく研修コースで配布されたという、炉物理の問題集を全部やりました。(計算問題のみのものです)
?過去問12年分ぐらいの計算問題を、???の資料+ラマーシュを駆使してとりあえず、解けるようにしました。(ラマーシュは読破すべきなのかもしれないですが、時間との兼ね合いで考えて、必要部分だけを読むようにしました)
?あとは、計算式を全てエクセルで一覧表にしたり、どういった時に、どういった式が必要なのかをまとめたりしました。
?あとは、知識ものですが、過去問で出題されたキーワードを中心に、参考書、ネット、知人など、色んな所からそのキーワード周辺の知識を仕入れて覚えました
理論は以上です。多分、大学で原子核をやっていないとこの科目が本当にしんどいです。
2、制御
?炉物理の科目と合わせて、動特性の(JAEA)の研修コースの参考書を読む。
?(JAEA)の研修コースで配布された問題を解く
?過去問12年分の全ての問題を解けるようにする
?あとは、知識をエクセル、ワードで整理
?知識系は炉物理同様。指針類は原子力安全委員会のHPからダウンロードして使いました。設計審査指針は、全部暗記し、評価審査指針、耐震・・・など、かなり覚える事が満載です。ただ、受かるためだけを目標にするなら、近年指針類の問題は減少傾向になるので、捨ててもかまいません。(覚え出すと、かなりの物量で、本当にしんどいです)
3、設計
?(JAEA)の研修コースの熱水力の参考書を読む、熱力、流体でわからない部分は、参考書を別途かって、ちょこちょこ読む。(全部読む時間はなかったので、辞書的に使いました。)
?材料、構造力学の問題は、一般的な参考書のみを使いました。(大学が材料だったので、この分野の参考書はそこそこ持っていて助かりました。)
?過去問12年分を全て解けるようにする
?他の科目同様同じく知識整理と暗記
4、燃料・材料
?(JAEA)の研修コースの参考書を読む。あと、パワーポイントがあるのですが、これがかなり使えます。
?過去問をとにかくやれるだけやる(はっきり言ってこの科目は知っていた者勝ちです。やれるだけやって知識をどんどん太くした方が良いと思います。私は、大体15〜20年分の問題を見ましたが、多分10年分ぐらいすれば、あとは、似たような問題が繰り返されるだけです。出題された問題のみを暗記するだけでなく、その周辺部分の理解が大切かと思います)
5、放射線
確かnoferiaさんは、RIの資格持ってますよね?あれ持っていれば楽勝です。最近、炉主任の放射線の問題はRIの資格に近くなってきているので、何も勉強しなくても良いくらいです。難易度はRIの試験の20%ぐらいの難易度しかありません。RIをもっているなら100点が狙える科目です。
過去問をやると、RI以外の問題として、原子力発電所の放射線管理的な問題が出ているのが分かると思いますので、そういったものだけ、ネット調べたりして、キーワードの周辺知識を太くしていけば楽勝です。
もしギリギリのボーダーでの合格を狙っているなら、是非100点をとっておきたい科目です。(他の科目を受験する時のプレッシャーが減ります)
6、法令
私は、法律の必要部分を暗記しました。暗記の仕方は色々工夫が必要かと思います。最近は選択式の問題が多いので、昔の炉主任より法律の難易度は下がっています。(昔は、丸丸記述させる問題が出ていました。私は、どの年代の問題が出ても100%受かる状態にしようと思ったので、かなり暗記しましたが、最近の法律の問題のみに的を絞るなら負担はかなり減ると思います。)
暗記すれば、満点取れるので、他の科目の負担を減らすために、頑張っておくと良いと思います。
以上です。
原子核を大学時代やってこられたなら、炉物理も大したことないらしいですが、私のように、全くの場合、炉物理が本当にしんどいです。
私は、計算問題に対して
研修コース(1cm弱)×3冊+問題集(1.5cmぐらい)1冊+過去問12年分+ラマーシュの必要部分のみ+数学の参考書2冊
といった感じですが、本当の奥深くまで理解されている方は、私の何倍もの参考書を読んでおられると思いますし、逆に、計算を捨てると、この勉強量がなくなるので、途端に半分以下の努力ですみます。目標とされる知識レベルを考えて選ばれればいいかと思います。
また、私は、トータルで、大体1年3ヶ月勉強してこの資格を取りましたので、2回受験しています。
1回目は3ヶ月の勉強で、前日は数学の参考書を読んでました。(笑)(当然受かる気はありませんでした)
炉物理、設計、制御の3科目しか勉強してなかったので、当然法律などは0点だったと思います。(放射線はRI持っていれば勉強しなくても合格ラインは堅いと思いますが)
2回目は受験前から、自信があったので、結構すんなり受かりましたが、それでも、炉主任を取った後に、
「そんなことも知らないで炉主任を取ったのか!」
とバカにされることもたまにありますので、取るよりも取った後の方がしんどいんだなぁと最近実感します。
取った後のことも考えて、勉強するとなると、結構しんどいとは思いますが、頑張ってください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
三種の神器(原子力・放射線) 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-