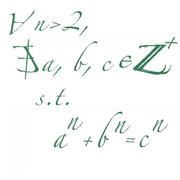|
|
|
|
コメント(105)
>無限を包み込む究極の無限はない・・・終わりなき無限 が 限りなく連鎖して続いてゆくという感じの理解でいいでしょうか?
うまく答えるのは難しいのですが、59のように順序数を「下から積み上げる」方法だと、アレフ1の濃度の順序数にすら行き着けません。
だから、公理的集合論では最初から、「集合全体」という概念を持ってきて、それらの対象(つまり集合)x,yに対して、x∈yが成り立つ か 成り立たないかのどちらかであるとします。
で、例えば、∃x:∀y:¬y∈x となる集合x(空集合)が存在するとか、こういう集合が存在するとか、集合から別の集合を作る方法が示されている。
そうすると、公理系から「こういう性質を持っている集合が存在する」とか、「こういう性質の集合は存在しない」ということが色々出てくる。
例えば、任意のxについて、x∈yとなるようなyは存在しない
とか、
選択公理とか連続体仮説は、いわば、両者の隙間の問題。
うまく答えるのは難しいのですが、59のように順序数を「下から積み上げる」方法だと、アレフ1の濃度の順序数にすら行き着けません。
だから、公理的集合論では最初から、「集合全体」という概念を持ってきて、それらの対象(つまり集合)x,yに対して、x∈yが成り立つ か 成り立たないかのどちらかであるとします。
で、例えば、∃x:∀y:¬y∈x となる集合x(空集合)が存在するとか、こういう集合が存在するとか、集合から別の集合を作る方法が示されている。
そうすると、公理系から「こういう性質を持っている集合が存在する」とか、「こういう性質の集合は存在しない」ということが色々出てくる。
例えば、任意のxについて、x∈yとなるようなyは存在しない
とか、
選択公理とか連続体仮説は、いわば、両者の隙間の問題。
>75:まこぴ〜@Free Tibet さん
アレフ[ほにゃらら]
で、「ほにゃらら」のところに入るのは「順序数」です。
「濃度」ではありません。
この点に注意しないと、つい:
アレフ[ω]= アレフ[ω+1]
のようなミスをしてしまいます。
ω と ω+1 では、その濃度は等しいですが、
( Card(ω)=Card(ω+1)=アレフ[0] )
順序数としては違います。
このあたりが、混乱の原因なのでは?と思ったのです。
いかがでしょうか,,,
(注)
アレフ[0],アレフ[1],...,アレフ[n],...(nは自然数を動く)
のどれよりも大きい濃度のうち最小のものを
アレフ[ω]
と書きます。
それより大きい順序数αに対しても(超限)帰納的に
アレフ[α]
は定義されます。
アレフ[ほにゃらら]
で、「ほにゃらら」のところに入るのは「順序数」です。
「濃度」ではありません。
この点に注意しないと、つい:
アレフ[ω]= アレフ[ω+1]
のようなミスをしてしまいます。
ω と ω+1 では、その濃度は等しいですが、
( Card(ω)=Card(ω+1)=アレフ[0] )
順序数としては違います。
このあたりが、混乱の原因なのでは?と思ったのです。
いかがでしょうか,,,
(注)
アレフ[0],アレフ[1],...,アレフ[n],...(nは自然数を動く)
のどれよりも大きい濃度のうち最小のものを
アレフ[ω]
と書きます。
それより大きい順序数αに対しても(超限)帰納的に
アレフ[α]
は定義されます。
>92:積分定数 さん
2^A
をクラスとして扱う以上は、
2^Aの元は集合でなければなりません。
(proper classはclassの元にならない)
ですから、2^Aというのは
「Aの部分クラスの集まり」ではなく
「『Aの部分クラスで集合になるもの』全体のなすクラス」であるべき
だと考えます。
一方で、
「Aの部分クラスの集まり」
自体は考えることが出来ると思いますが、この場合
これとAは比較できるようなものではなくなる
と思います。
,,,その上で
(2^Aを「『Aの部分クラスで集合になるもの』全体のなすクラス」とみなした上で)、
「2^A=Aが成り立つクラスがあるか」
という問題ですが,,,
これに関しては僕は具体例を考えたことがございません。
ありそうな気がするんだけど,,,
どうなんでしょう,,,
{x:A(x)}
という記法は
2^A
をクラスとして扱う以上は、
2^Aの元は集合でなければなりません。
(proper classはclassの元にならない)
ですから、2^Aというのは
「Aの部分クラスの集まり」ではなく
「『Aの部分クラスで集合になるもの』全体のなすクラス」であるべき
だと考えます。
一方で、
「Aの部分クラスの集まり」
自体は考えることが出来ると思いますが、この場合
これとAは比較できるようなものではなくなる
と思います。
,,,その上で
(2^Aを「『Aの部分クラスで集合になるもの』全体のなすクラス」とみなした上で)、
「2^A=Aが成り立つクラスがあるか」
という問題ですが,,,
これに関しては僕は具体例を考えたことがございません。
ありそうな気がするんだけど,,,
どうなんでしょう,,,
{x:A(x)}
という記法は
60に書いてあるように、順序数どうしで、全単射(順序同型でなくてもよい。というか、異なる2つの順序数は同型ではない)が存在するもの同士を集めてきて、そのなかで、順序として最小のものを「濃度」とします。
要するに、順序数のクラス全体に 「全単射が存在する」ということを、同値関係として、順序数のクラスを同値類に分割する。
「全単射が存在する」が、同値類の設定を満たす条件=反射律・推移律・もうひとつ何とか律、つまり
「A〜B ならば B〜A」
「A〜BかつB〜C ならば A〜C」
「A〜A」
などの条件を満たすことはすぐに示される。
で、こうして分けた同値類の中の最小値を代表元として、これを濃度とよぶ
ということです。
要するに、順序数のクラス全体に 「全単射が存在する」ということを、同値関係として、順序数のクラスを同値類に分割する。
「全単射が存在する」が、同値類の設定を満たす条件=反射律・推移律・もうひとつ何とか律、つまり
「A〜B ならば B〜A」
「A〜BかつB〜C ならば A〜C」
「A〜A」
などの条件を満たすことはすぐに示される。
で、こうして分けた同値類の中の最小値を代表元として、これを濃度とよぶ
ということです。
>積分定数さん
うーん、難しいですね。
順序数を、(全単射が存在するという点で)同値類に分類すると、同じ類の中には最小の順序があるということですね。
では、たくさんの濃度を集めてきたときに、それらに最小のものが存在するということはどこから出るのでしょうか。
感覚的には、自然数の濃度aleph_0よりも大きく、実数の濃度bet_1よりも小さい濃度があるとしても矛盾しないなら、そのような濃度(便宜上bet_(1/2)ということにする)があるとして、それよりも小さく自然数の濃度よりも大きいものがあるとしても矛盾しないような気がします。すなわちbet_(1/4)というものが存在してもよい。以下、bet_(1/8)、bet_(1/16)という風にどんどん小さい濃度を作れる(あっても矛盾しない)という気がしますが・・・。
その場合にも必ずどれかが一番小さいということなのでしょうか。
(連続体仮説がZFCと独立であることの証明など、よく理解していない部分が多いので的外れな質問かもしれませんが・・・)
うーん、難しいですね。
順序数を、(全単射が存在するという点で)同値類に分類すると、同じ類の中には最小の順序があるということですね。
では、たくさんの濃度を集めてきたときに、それらに最小のものが存在するということはどこから出るのでしょうか。
感覚的には、自然数の濃度aleph_0よりも大きく、実数の濃度bet_1よりも小さい濃度があるとしても矛盾しないなら、そのような濃度(便宜上bet_(1/2)ということにする)があるとして、それよりも小さく自然数の濃度よりも大きいものがあるとしても矛盾しないような気がします。すなわちbet_(1/4)というものが存在してもよい。以下、bet_(1/8)、bet_(1/16)という風にどんどん小さい濃度を作れる(あっても矛盾しない)という気がしますが・・・。
その場合にも必ずどれかが一番小さいということなのでしょうか。
(連続体仮説がZFCと独立であることの証明など、よく理解していない部分が多いので的外れな質問かもしれませんが・・・)
>では、たくさんの濃度を集めてきたときに、それらに最小のものが存在するということはどこから出るのでしょうか。
順序数全体が整列であるから、その部分クラスである濃度全体も整列です。
Aを濃度の部分クラスとすれば、それは順序の部分クラスでもあるので、最小値が存在します。
具体的にはわたやんさんの発言のように共通部分を取れば、それが最小値となります。
>以下、bet_(1/8)、bet_(1/16)という風にどんどん小さい濃度を作れる(あっても矛盾しない)という気がしますが・・・。
その場合にも必ずどれかが一番小さいということなのでしょうか。
整列順序の場合、そのような無限下降列を作ることが出来ません。
というのは、そのような下降列の全体も可算個の部分集合を形成するので、その中のどれかは、最小値のはずです。
a[1]>a[2]>a[3]>a[4]・・・・
このどれかが最小値のはずだから、それをa[n]とすれば、そこから先に
a[n]>a[n+1]と続けることは出来ません。
順序数全体が整列であるから、その部分クラスである濃度全体も整列です。
Aを濃度の部分クラスとすれば、それは順序の部分クラスでもあるので、最小値が存在します。
具体的にはわたやんさんの発言のように共通部分を取れば、それが最小値となります。
>以下、bet_(1/8)、bet_(1/16)という風にどんどん小さい濃度を作れる(あっても矛盾しない)という気がしますが・・・。
その場合にも必ずどれかが一番小さいということなのでしょうか。
整列順序の場合、そのような無限下降列を作ることが出来ません。
というのは、そのような下降列の全体も可算個の部分集合を形成するので、その中のどれかは、最小値のはずです。
a[1]>a[2]>a[3]>a[4]・・・・
このどれかが最小値のはずだから、それをa[n]とすれば、そこから先に
a[n]>a[n+1]と続けることは出来ません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
数学 更新情報
-
最新のアンケート