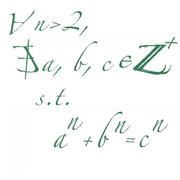みなさんは『フェルマーの最終定理』(新潮社)という本を読んだことはありますか?私は最近これを読んで大変感銘を受けました。もし読んだことがあるようでしたら、この本についての感想をお聞かせ下さい。
【目次】
序
はじめに
第?章:「ここで終わりにしたいと思います」
第?章:謎をかける人
第?章:数学の恥
第?章:抽象のかなたへ
第?章:背理法
第?章:秘密の計算
第?章:小さな問題
第?章:数学の大統一
補遺
1 ピュタゴラスの定理の証明
2 √2が無理数であることに対するエウクレイデスの証明
3 ディオファントスの年齢の謎
4 バシェの分銅の問題
5 ピュタゴラスの三つ組み数が無限に存在することに対するエウクレイデスの証明
6 点予想の証明
7 不合理に迷い込む
8 算術の公理
9 ゲーム理論とトルエル
10 帰納法による証明の例
訳者あとがき
【目次】
序
はじめに
第?章:「ここで終わりにしたいと思います」
第?章:謎をかける人
第?章:数学の恥
第?章:抽象のかなたへ
第?章:背理法
第?章:秘密の計算
第?章:小さな問題
第?章:数学の大統一
補遺
1 ピュタゴラスの定理の証明
2 √2が無理数であることに対するエウクレイデスの証明
3 ディオファントスの年齢の謎
4 バシェの分銅の問題
5 ピュタゴラスの三つ組み数が無限に存在することに対するエウクレイデスの証明
6 点予想の証明
7 不合理に迷い込む
8 算術の公理
9 ゲーム理論とトルエル
10 帰納法による証明の例
訳者あとがき
|
|
|
|
コメント(24)
>「…人が素朴に考えたりやってみたりした事は、どれもみな、ようするに、楕円方程式とモジュラー形式を分類してどちらも同じ数だけあることを示す事だ、とワイルスは言っています。しかし、問題は楕円方程式もモジュラー形式も無限に存在するという事で…」
対応する部分、見つけました 単行本にはこう書いてあります。
単行本にはこう書いてあります。
「人が素朴に考えたり、実際にやってみたりしたことはどれもみな、要するに楕円方程式とモジュラー形式をそれぞれ勘定して、どちらも同じ数だけあると示すことだったのです。しかしそれを簡単にやる方法は誰も見つけていなかった。第1の問題は、楕円方程式もモジュラー形式も無限に存在するということです」(P262)
対応する部分、見つけました
「人が素朴に考えたり、実際にやってみたりしたことはどれもみな、要するに楕円方程式とモジュラー形式をそれぞれ勘定して、どちらも同じ数だけあると示すことだったのです。しかしそれを簡単にやる方法は誰も見つけていなかった。第1の問題は、楕円方程式もモジュラー形式も無限に存在するということです」(P262)
やまとなでしこは素晴らしいドラマなのでおすすめです。
結婚式のスピーチではこんな感動的なスピーチもします。ドラマの重要なシーンです。このドラマのテーマは「お金では買えないたった一つの大切なもの」であり 結局この謎は明かされることなくドラマはフェードアウトしていきます。しかし視聴者の心の中にはひとつの謎としてずっと問いかけてゆくような仕掛けになっており、ある意味、フェルマーの最終定理のようにシンプルな問いでありながら、そこには限りない真理の深遠が拡がっています
===
物理学者のリチャード・ファイマンはこんな事を言っています。
『数学や物理というのは、神様のやっているチェスを横から眺めて、
そこにどんなルールがあるのか、どんな美しい法則があるのか、
探していくことだ。』と。
最初からそんな法則はないと思うことも出来ます。
この宇宙で起こっていることが全て、
でたらめで意味のない出来事の繰り返しばかりだとしたら、
数学者たちは、なにもすることがなくなってしまう。
そんな退屈な宇宙に住んでいること自体、嫌気がさしてしまう。
でも、岡本はチェスの謎を解くことをあきらめませんでした。
おまけに、ゆりさんの様な人と巡り会うことが出来た。
ひょっとしたら、人と人が出会うことも、
そのルールにのっとっているのかも知れません。
もし、そこに何かのルールがなかったら、
二人がどっかで出会っても、そのまますれ違って
関わり合うことも、言葉を交わすこともなかったはずなのに。
宇宙の片隅のこの会場で、僕たちがこうして集まることが出来たのも、
そして、僕たちがこんなにハッピーなのも、
岡本が、たった一人の女性と巡り会ってくれたおかげです。
運命といういちばん難しい謎を、今日、彼が解いてくれたような気がします。
おめでとう。
結婚式のスピーチではこんな感動的なスピーチもします。ドラマの重要なシーンです。このドラマのテーマは「お金では買えないたった一つの大切なもの」であり 結局この謎は明かされることなくドラマはフェードアウトしていきます。しかし視聴者の心の中にはひとつの謎としてずっと問いかけてゆくような仕掛けになっており、ある意味、フェルマーの最終定理のようにシンプルな問いでありながら、そこには限りない真理の深遠が拡がっています
===
物理学者のリチャード・ファイマンはこんな事を言っています。
『数学や物理というのは、神様のやっているチェスを横から眺めて、
そこにどんなルールがあるのか、どんな美しい法則があるのか、
探していくことだ。』と。
最初からそんな法則はないと思うことも出来ます。
この宇宙で起こっていることが全て、
でたらめで意味のない出来事の繰り返しばかりだとしたら、
数学者たちは、なにもすることがなくなってしまう。
そんな退屈な宇宙に住んでいること自体、嫌気がさしてしまう。
でも、岡本はチェスの謎を解くことをあきらめませんでした。
おまけに、ゆりさんの様な人と巡り会うことが出来た。
ひょっとしたら、人と人が出会うことも、
そのルールにのっとっているのかも知れません。
もし、そこに何かのルールがなかったら、
二人がどっかで出会っても、そのまますれ違って
関わり合うことも、言葉を交わすこともなかったはずなのに。
宇宙の片隅のこの会場で、僕たちがこうして集まることが出来たのも、
そして、僕たちがこんなにハッピーなのも、
岡本が、たった一人の女性と巡り会ってくれたおかげです。
運命といういちばん難しい謎を、今日、彼が解いてくれたような気がします。
おめでとう。
本日完読しました。
〜感想文〜
数学の本とは言えども、数学年史の中で代表される定理の紹介には、やたらと数式の記述があるわけで無く、むしろ関わった人物相関系やエピソードを中心的に書かれた内容でした。 理系が苦手な方でも、幅広く親しめる内容であると思いました。
最終定理が発表されてから証明迄360年であるけれども、そもそもピュタゴラスの時代から、2千5百年もの時間を数学者達をとりこにしてきた謎であるとも言えよう。
数式一つとっても、知れば知るほど謎が深まるもので、数学の世界には限りが無いと考えるべきであろうか。
証明か予想かと問われれば、それ自体が不可思議である。
一つの限界点(仮説)を立てる事で体系化できるものだとは思うのですが、少なからずともそうして確立した定理で、飛行機や人工衛星を飛ばしたりするのに役立てられているのであるから、完成理論というべきであろう。
されども、「数」の世界は無限な可能性と謎に満ちた世界があるほど魅力的なのである。
ただ言える事は、私はこの本を読んでますます「数」の世界にはまり込んだ事は間違い無い事実である。
「フェルマーはこの定理を世の人に発表することで、多くの人に「数」の世界への関心と、興味を持ち、勉学に励み、将来証明される日が来る事を願っていた。」
と思う。 これは私の仮説である。
そして、この本と、この本を通じて多くの人が感銘を受けた事実がその証明である。
〜感想文〜
数学の本とは言えども、数学年史の中で代表される定理の紹介には、やたらと数式の記述があるわけで無く、むしろ関わった人物相関系やエピソードを中心的に書かれた内容でした。 理系が苦手な方でも、幅広く親しめる内容であると思いました。
最終定理が発表されてから証明迄360年であるけれども、そもそもピュタゴラスの時代から、2千5百年もの時間を数学者達をとりこにしてきた謎であるとも言えよう。
数式一つとっても、知れば知るほど謎が深まるもので、数学の世界には限りが無いと考えるべきであろうか。
証明か予想かと問われれば、それ自体が不可思議である。
一つの限界点(仮説)を立てる事で体系化できるものだとは思うのですが、少なからずともそうして確立した定理で、飛行機や人工衛星を飛ばしたりするのに役立てられているのであるから、完成理論というべきであろう。
されども、「数」の世界は無限な可能性と謎に満ちた世界があるほど魅力的なのである。
ただ言える事は、私はこの本を読んでますます「数」の世界にはまり込んだ事は間違い無い事実である。
「フェルマーはこの定理を世の人に発表することで、多くの人に「数」の世界への関心と、興味を持ち、勉学に励み、将来証明される日が来る事を願っていた。」
と思う。 これは私の仮説である。
そして、この本と、この本を通じて多くの人が感銘を受けた事実がその証明である。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
数学 更新情報
-
最新のアンケート