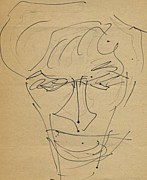この作品を讀む時に、この音樂を聞きながら鑑賞して下さい。
これは叔伯特(シユウベルト・1797-1828)の、
『TRIO 2nd MOV. Es-Dur D929』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は奈良にある、
『東大寺』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
二十六、『獅子』に就いて 『言苑』より
『獅子』に就いては以前にも簡單に述べた記憶があるが、近所のお祭で神輿(みこし)は普通に出た上に獅子舞も出たので、珍しさも手傳(てつだ)つてか強烈な印象が殘つたから、お浚ひの爲にもう一度それに就いて調べた事を書いて見ようと思ふ。
云ふまでもなく、現在では『獅子』とはライオンの事を指し、一般的に最も強い動物で百獣の王として世界で有名で、古くは後期舊石器時代からラスコオ洞窟などの洞窟畫に描かれてをり、彫刻や繪畫(くわいぐわ)とか國旗、現代の映畫や文學などでも廣く扱はれてゐ、日本でも任侠映畫で『昭和殘侠伝 唐獅子牡丹』が有名である。
また諺(ことわざ)にも、
獅子身中の蟲
獅子に鰭(ひれ)
獅子の子落し
獅子に牡丹
獅子の齒噛み
獅子の分け前
獅子は兔を撃つに全力を用う
などと幾つかあつて、『獅子』は日本人には河童や龍、天狗とか鬼のやうに馴染の深い動物であるやうに思はれる。
上記の諺のなかの「獅子の子落し」について、以前に、
「三、國立文樂劇場で『花弘會』を鑑賞して」
で書いた事があつて、その内容は、
「獅子は子を産んで三日を經る時、萬仞(ばんじん)の石壁より母これを投ぐるに、その獅子の機分あれば、教へざる中より身を飜して、死する事を得ずといへり」
といふもので、その出典は『太平記』にあると辭書(じしよ)にあつて、それが日本からのものだといふのには驚いてしまふ。
けれども、これは私見だから間違つてゐるかも知れないが、獅子は所謂(いはゆる)西洋の百獸の王のライオンの事ではなく、恐らくライオンを元にした想像上の靈獣の事であらうかと思つてゐる。
その論據(ろんきよ)を述べれば、古くは「しし」は猪(いのしし)や鹿(かのしし)のやうな動物を指し、それと區別していふ爲に中國傳來の獅子は「唐獅子」といつたと物の本にある。
一説に、中国の虎豹をも食ふといふ狻麑(さんげい)若しくは猊(げい)の事だといふとある。
また、神社にある對(つい)になつた獅子に似た靈獣の狛犬(こまいぬ)は、高麗則ち狛から來たといふ意味で、左右の狛犬のうち、角が無いもの或いは向つて右側が獅子であると言はれてゐる。
と、ここまでは既に述べた所であるが、神社や寺院にある狛犬について更に調べて見ると、獅子女(スフインクス)にも見られるやうに古代埃及(エジプト)や米蘇波他美亞(メソポタミア)での神域を守るライオンの像がその源流とされ、古代印度で佛の兩脇に守護の獸として獅子の像を置いたのが狛犬の起源となつて、日本へは中國の唐の時代の獅子が佛教と共に朝鮮半島を經て傳はつたとされてゐるとの事である。
高麗犬とも呼ばれるといふ狛犬の語義には諸説あるので一々それは取上げないし、角を持つという由來に就いても省略するが、その代りに阿形と吽形の狛犬に就いて述べて見たいと思ふ。
『宇津保物語』に、
「大いなる白銀(しろがね)の狛犬四つ」
と記述されてゐて、それは香爐を取附けて宮中の御帳の四隅に置いて使はれてゐたと言ひ、『枕草子』や『榮花物語』などにも調度品として「獅子」と「狛犬」の組合せが登場し、こちらは御簾(みす)や几帳(きちやう)を押さえるための重しとして使はれてゐた記録が殘されてゐるのだといふ。
さうして、その獅子と狛犬の配置については、獅子を左、狛犬を右に置くとの記述が『禁秘抄』と『類聚雑要抄』に共通してあるといふ。
『類聚雑要抄』では、さらにそれぞれの特徴を
「獅子は色黄にして口を開き、胡摩犬(狛犬)は色白く口を開かず、角あり」
と描いてゐて、獅子または狛犬は中國や韓國にも同樣のものがあるが、阿(あ)吽(うん)の形は日本で多く見られる特徴で、仁王像と同樣に日本における佛教觀を反映したものではないかと考へられてゐるさうで、一般的に向つて右側の獅子像が阿形(あぎやう)で口を開いてをり、左側の像が吽形(うんぎやう)で口を閉ぢてゐて古くは角を持つてゐたが、鎌倉時代後期以降になは樣式が簡略化されたものが出現され、昭和時代以降に作られた物は左右ともに角が無いものが多くなり、口の開き方以外に外見上の差異がなくなつてしまつたと言はれてゐる。
角を持たないものは本来「獅子」と呼ぶべきものであるが、今日では兩方の像を合せて「狛犬」と稱する事が通例となつてゐるやうだ。
この外にも、獅子・狛犬と同樣の役割を果たす神佛の守護獣としては、
「猪・龍・狐・狼」
などがあり、これらの動物は『神使』と呼ばれて神社によつて特定の動物が採用されてゐて、
「稲荷神に狐、春日神に鹿、弁財天に蛇」
などがその代表的な物である。
變はつた處では土地の傳承などに基づくものもあつて、例へば岩手県の一部の寺では河童傳説に基づいて狛犬の代はりに河童像が置かれてゐたり、また別の所では狛犬ならぬ狛猫像が置かれ、阿吽の配置も左右逆となつてゐたりするものもあるさうである。
先にも述べた「唐獅子牡丹」は、南禪寺の方丈から虎の兒渡しで有名な庭園を望む廣縁の頭上に、左甚五郎作の兩面透彫りの欄間があり、その圖柄は「牡丹に唐獅子、竹に虎」といふ繪圖で、獅子だけならば狩野永徳(かのうえいとく・1543-1590)の屏風圖がある。
これに類する圖柄は他にも、
「牡丹に唐獅子」「竹に虎」「麒麟に孔雀」
などがある。
『牡丹と獅子』の取合せには意味があつて、百獸に君臨する王と言はれるその無敵の獅子でさへただ一つだけ恐れるものがあり、それは我身の体毛の中に發生増殖し、やがて皮を破り肉に食らいつく害虫の獅子身中の蟲がある事で、この害蟲は牡丹の花から滴り落ちる夜露にあたると死んでしまひ、そこで獅子は夜に牡丹の花の下で休むのだといふ。
獅子にはそこが安住の地であるのだらう。
また『竹に虎』も、群をなした象には虎も流石に齒が立たず、その巨體と象牙に龜裂が入ると言はれてゐるゆゑに象は竹藪に入られないので、虎はそこへ逃げ込むのだといふ。
さて、これを書く切掛けになつた秋祭の『獅子舞』に就いてであるが、それはいふまでもなく傳統藝能の一つで、祭囃子にあわせて獅子が舞ひ踊るものである。
その起源は中國説や印度説などあり定かではなく、朝鮮半島や越南(ベトナム)にもあるさうで、日本の獅子舞は大きく分けて伎樂(ぎがく)系と風流(ふりう)系の獅子舞がある。
伎樂系(神樂系)の獅子舞は西日本を中心として胴體部分に入る人數で大獅子、中獅子、小獅子と區分され、大獅子では獅子を操作する人以外に囃子方も胴體に入つて演奏し、小獅子では獅子頭を操作する一人だけが胴體も兼ねる。
正月に見る獅子舞や神楽での獅子舞をはじめ、一般に獅子舞といふとこの系統の獅子舞を指す事が多く、中國獅子舞とも繋がるものと考へられてゐるといふ。
風流系の獅子舞は關東以北に分布してゐて、一人が一匹を擔當(たんたう)してそれぞれが腹に括(くく)りつけられた太鼓を打ちながら舞ふ。
東北の一部には七、八頭で一組の鹿踊もあるが、もつとも多いのは三匹一組の三匹獅子舞で、かつて武蔵國(東京・埼玉)と呼ばれた地域の農山村では一般的な郷土藝能となつてゐ、三匹の内の一匹は女獅子(雌獅子)と呼ばれ、雄獅子が雌獅子を奪ひ合ふ女獅子隱しといふ演目を持つところが多く、伴奏は篠笛と竹で出來た簓(ささら)という樂器である。
それを演奏する人は舞庭の四方に配置されるが、それを缺(か)いた三匹獅子舞もあるさうだ。
起源は西日本の太鼓踊り或いは陣役踊りといはれ、中心にゐる數人が頭上のかぶり物を獅子頭に變へたものが始まりだらうといふ説が優勢であるらしいが、東國の風流系の獅子舞はもつと古くからある日本古來の獅子舞で、獅子頭(ししがしら)も鹿や猪を模したものや、獅子以外に龍頭のものや鹿頭のものもあつたといふ説も根強いらしい。
因みに、中國の『漢書(禮樂志 卷22)』に、
「象人 若今戲魚蝦師子者也(象人は、今の魚蝦・獅子を戯するがごとき者也)」
とあり、これが最古の記録ではないかともいふが、現在演じられる形は清の時代に確立され、北方の北獅と南方の南獅の系統があり、獅子頭と前足に一人、後ろ足と背中に一人の二人と樂團で構成されてゐて、舊(きう)正月の祝ひで演じられるといふ。
ついでに言へば、筆者は知らないが本將棋以外に中將棋といふものがあつて、その將棋の駒の一つに獅子といふものがあるさうである。
ところで、ここで紹介をしてゐる叔伯特(シユウベルト・1797-1828)の音樂に使はれてゐる映像の、奈良懸の東大寺の門前にある仁王像であるが、これも阿吽像で二體を一對としてゐるが、本來は正面を向く筈のこの金剛力士は向合つてゐて、通常の仁王像とは異なつてゐる。
そればかりか、通常は門を向いて左側が阿形像で、門を向いて右側が吽形像なのだが、ここでは吽形像と阿形像の阿吽の位置が逆となつてゐるけれども、これは天平時代までは「儀軌」についてもそんなに煩はしくなく自由に制作や配置が出來、創建當初(たうしよ)の仁王像も「三月堂の仁王像」と同じやうに阿吽の位置が逆だつたりしてゐるからだといふ。
さうして、何故仁王像の彼らは向合つてゐるのかといふと、正面の南向きに据ゑられると激しい風雨に曝される爲に時の經過と共に風食で痛ましい姿となるので、風雨の被害を蒙るのを避けるといふ理由で仁王同士が對面しあふやうに安置され、南側は閉鎖して保護するやうにしたといふのだが、解つて見ればなんの事はないがつかりする程の謎解きである。
これと同じやうに、哺乳綱ネコ目(食肉目)ネコ科ヒヨウ屬に分類される食肉類のライオンは、百獸の王といはれながら亞細亞大陸の廣域に生存するといはれた虎と同樣に、將來には絶滅が心配されてゐる動物である。
人類はその百獸の王よりも強いといふ事なのだらうが、尤もヒトは獣ではないのだからこの限りではないのかも知れない。
芥川龍之介(1892-1927)流に言へば『人間獸』であらうが……。
參考資料
『廣辭苑第六版』・『Wikipedia』
續きをどうぞ
二十七囘 同音の漢字による書き替へ問題に就いて 『言苑』より
http://
始めからどうぞ
『言苑』 1、教育
http://
關聯記
三、國立文樂劇場で『花弘會』を鑑賞して 第二部
http://
これは叔伯特(シユウベルト・1797-1828)の、
『TRIO 2nd MOV. Es-Dur D929』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は奈良にある、
『東大寺』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
二十六、『獅子』に就いて 『言苑』より
『獅子』に就いては以前にも簡單に述べた記憶があるが、近所のお祭で神輿(みこし)は普通に出た上に獅子舞も出たので、珍しさも手傳(てつだ)つてか強烈な印象が殘つたから、お浚ひの爲にもう一度それに就いて調べた事を書いて見ようと思ふ。
云ふまでもなく、現在では『獅子』とはライオンの事を指し、一般的に最も強い動物で百獣の王として世界で有名で、古くは後期舊石器時代からラスコオ洞窟などの洞窟畫に描かれてをり、彫刻や繪畫(くわいぐわ)とか國旗、現代の映畫や文學などでも廣く扱はれてゐ、日本でも任侠映畫で『昭和殘侠伝 唐獅子牡丹』が有名である。
また諺(ことわざ)にも、
獅子身中の蟲
獅子に鰭(ひれ)
獅子の子落し
獅子に牡丹
獅子の齒噛み
獅子の分け前
獅子は兔を撃つに全力を用う
などと幾つかあつて、『獅子』は日本人には河童や龍、天狗とか鬼のやうに馴染の深い動物であるやうに思はれる。
上記の諺のなかの「獅子の子落し」について、以前に、
「三、國立文樂劇場で『花弘會』を鑑賞して」
で書いた事があつて、その内容は、
「獅子は子を産んで三日を經る時、萬仞(ばんじん)の石壁より母これを投ぐるに、その獅子の機分あれば、教へざる中より身を飜して、死する事を得ずといへり」
といふもので、その出典は『太平記』にあると辭書(じしよ)にあつて、それが日本からのものだといふのには驚いてしまふ。
けれども、これは私見だから間違つてゐるかも知れないが、獅子は所謂(いはゆる)西洋の百獸の王のライオンの事ではなく、恐らくライオンを元にした想像上の靈獣の事であらうかと思つてゐる。
その論據(ろんきよ)を述べれば、古くは「しし」は猪(いのしし)や鹿(かのしし)のやうな動物を指し、それと區別していふ爲に中國傳來の獅子は「唐獅子」といつたと物の本にある。
一説に、中国の虎豹をも食ふといふ狻麑(さんげい)若しくは猊(げい)の事だといふとある。
また、神社にある對(つい)になつた獅子に似た靈獣の狛犬(こまいぬ)は、高麗則ち狛から來たといふ意味で、左右の狛犬のうち、角が無いもの或いは向つて右側が獅子であると言はれてゐる。
と、ここまでは既に述べた所であるが、神社や寺院にある狛犬について更に調べて見ると、獅子女(スフインクス)にも見られるやうに古代埃及(エジプト)や米蘇波他美亞(メソポタミア)での神域を守るライオンの像がその源流とされ、古代印度で佛の兩脇に守護の獸として獅子の像を置いたのが狛犬の起源となつて、日本へは中國の唐の時代の獅子が佛教と共に朝鮮半島を經て傳はつたとされてゐるとの事である。
高麗犬とも呼ばれるといふ狛犬の語義には諸説あるので一々それは取上げないし、角を持つという由來に就いても省略するが、その代りに阿形と吽形の狛犬に就いて述べて見たいと思ふ。
『宇津保物語』に、
「大いなる白銀(しろがね)の狛犬四つ」
と記述されてゐて、それは香爐を取附けて宮中の御帳の四隅に置いて使はれてゐたと言ひ、『枕草子』や『榮花物語』などにも調度品として「獅子」と「狛犬」の組合せが登場し、こちらは御簾(みす)や几帳(きちやう)を押さえるための重しとして使はれてゐた記録が殘されてゐるのだといふ。
さうして、その獅子と狛犬の配置については、獅子を左、狛犬を右に置くとの記述が『禁秘抄』と『類聚雑要抄』に共通してあるといふ。
『類聚雑要抄』では、さらにそれぞれの特徴を
「獅子は色黄にして口を開き、胡摩犬(狛犬)は色白く口を開かず、角あり」
と描いてゐて、獅子または狛犬は中國や韓國にも同樣のものがあるが、阿(あ)吽(うん)の形は日本で多く見られる特徴で、仁王像と同樣に日本における佛教觀を反映したものではないかと考へられてゐるさうで、一般的に向つて右側の獅子像が阿形(あぎやう)で口を開いてをり、左側の像が吽形(うんぎやう)で口を閉ぢてゐて古くは角を持つてゐたが、鎌倉時代後期以降になは樣式が簡略化されたものが出現され、昭和時代以降に作られた物は左右ともに角が無いものが多くなり、口の開き方以外に外見上の差異がなくなつてしまつたと言はれてゐる。
角を持たないものは本来「獅子」と呼ぶべきものであるが、今日では兩方の像を合せて「狛犬」と稱する事が通例となつてゐるやうだ。
この外にも、獅子・狛犬と同樣の役割を果たす神佛の守護獣としては、
「猪・龍・狐・狼」
などがあり、これらの動物は『神使』と呼ばれて神社によつて特定の動物が採用されてゐて、
「稲荷神に狐、春日神に鹿、弁財天に蛇」
などがその代表的な物である。
變はつた處では土地の傳承などに基づくものもあつて、例へば岩手県の一部の寺では河童傳説に基づいて狛犬の代はりに河童像が置かれてゐたり、また別の所では狛犬ならぬ狛猫像が置かれ、阿吽の配置も左右逆となつてゐたりするものもあるさうである。
先にも述べた「唐獅子牡丹」は、南禪寺の方丈から虎の兒渡しで有名な庭園を望む廣縁の頭上に、左甚五郎作の兩面透彫りの欄間があり、その圖柄は「牡丹に唐獅子、竹に虎」といふ繪圖で、獅子だけならば狩野永徳(かのうえいとく・1543-1590)の屏風圖がある。
これに類する圖柄は他にも、
「牡丹に唐獅子」「竹に虎」「麒麟に孔雀」
などがある。
『牡丹と獅子』の取合せには意味があつて、百獸に君臨する王と言はれるその無敵の獅子でさへただ一つだけ恐れるものがあり、それは我身の体毛の中に發生増殖し、やがて皮を破り肉に食らいつく害虫の獅子身中の蟲がある事で、この害蟲は牡丹の花から滴り落ちる夜露にあたると死んでしまひ、そこで獅子は夜に牡丹の花の下で休むのだといふ。
獅子にはそこが安住の地であるのだらう。
また『竹に虎』も、群をなした象には虎も流石に齒が立たず、その巨體と象牙に龜裂が入ると言はれてゐるゆゑに象は竹藪に入られないので、虎はそこへ逃げ込むのだといふ。
さて、これを書く切掛けになつた秋祭の『獅子舞』に就いてであるが、それはいふまでもなく傳統藝能の一つで、祭囃子にあわせて獅子が舞ひ踊るものである。
その起源は中國説や印度説などあり定かではなく、朝鮮半島や越南(ベトナム)にもあるさうで、日本の獅子舞は大きく分けて伎樂(ぎがく)系と風流(ふりう)系の獅子舞がある。
伎樂系(神樂系)の獅子舞は西日本を中心として胴體部分に入る人數で大獅子、中獅子、小獅子と區分され、大獅子では獅子を操作する人以外に囃子方も胴體に入つて演奏し、小獅子では獅子頭を操作する一人だけが胴體も兼ねる。
正月に見る獅子舞や神楽での獅子舞をはじめ、一般に獅子舞といふとこの系統の獅子舞を指す事が多く、中國獅子舞とも繋がるものと考へられてゐるといふ。
風流系の獅子舞は關東以北に分布してゐて、一人が一匹を擔當(たんたう)してそれぞれが腹に括(くく)りつけられた太鼓を打ちながら舞ふ。
東北の一部には七、八頭で一組の鹿踊もあるが、もつとも多いのは三匹一組の三匹獅子舞で、かつて武蔵國(東京・埼玉)と呼ばれた地域の農山村では一般的な郷土藝能となつてゐ、三匹の内の一匹は女獅子(雌獅子)と呼ばれ、雄獅子が雌獅子を奪ひ合ふ女獅子隱しといふ演目を持つところが多く、伴奏は篠笛と竹で出來た簓(ささら)という樂器である。
それを演奏する人は舞庭の四方に配置されるが、それを缺(か)いた三匹獅子舞もあるさうだ。
起源は西日本の太鼓踊り或いは陣役踊りといはれ、中心にゐる數人が頭上のかぶり物を獅子頭に變へたものが始まりだらうといふ説が優勢であるらしいが、東國の風流系の獅子舞はもつと古くからある日本古來の獅子舞で、獅子頭(ししがしら)も鹿や猪を模したものや、獅子以外に龍頭のものや鹿頭のものもあつたといふ説も根強いらしい。
因みに、中國の『漢書(禮樂志 卷22)』に、
「象人 若今戲魚蝦師子者也(象人は、今の魚蝦・獅子を戯するがごとき者也)」
とあり、これが最古の記録ではないかともいふが、現在演じられる形は清の時代に確立され、北方の北獅と南方の南獅の系統があり、獅子頭と前足に一人、後ろ足と背中に一人の二人と樂團で構成されてゐて、舊(きう)正月の祝ひで演じられるといふ。
ついでに言へば、筆者は知らないが本將棋以外に中將棋といふものがあつて、その將棋の駒の一つに獅子といふものがあるさうである。
ところで、ここで紹介をしてゐる叔伯特(シユウベルト・1797-1828)の音樂に使はれてゐる映像の、奈良懸の東大寺の門前にある仁王像であるが、これも阿吽像で二體を一對としてゐるが、本來は正面を向く筈のこの金剛力士は向合つてゐて、通常の仁王像とは異なつてゐる。
そればかりか、通常は門を向いて左側が阿形像で、門を向いて右側が吽形像なのだが、ここでは吽形像と阿形像の阿吽の位置が逆となつてゐるけれども、これは天平時代までは「儀軌」についてもそんなに煩はしくなく自由に制作や配置が出來、創建當初(たうしよ)の仁王像も「三月堂の仁王像」と同じやうに阿吽の位置が逆だつたりしてゐるからだといふ。
さうして、何故仁王像の彼らは向合つてゐるのかといふと、正面の南向きに据ゑられると激しい風雨に曝される爲に時の經過と共に風食で痛ましい姿となるので、風雨の被害を蒙るのを避けるといふ理由で仁王同士が對面しあふやうに安置され、南側は閉鎖して保護するやうにしたといふのだが、解つて見ればなんの事はないがつかりする程の謎解きである。
これと同じやうに、哺乳綱ネコ目(食肉目)ネコ科ヒヨウ屬に分類される食肉類のライオンは、百獸の王といはれながら亞細亞大陸の廣域に生存するといはれた虎と同樣に、將來には絶滅が心配されてゐる動物である。
人類はその百獸の王よりも強いといふ事なのだらうが、尤もヒトは獣ではないのだからこの限りではないのかも知れない。
芥川龍之介(1892-1927)流に言へば『人間獸』であらうが……。
參考資料
『廣辭苑第六版』・『Wikipedia』
續きをどうぞ
二十七囘 同音の漢字による書き替へ問題に就いて 『言苑』より
http://
始めからどうぞ
『言苑』 1、教育
http://
關聯記
三、國立文樂劇場で『花弘會』を鑑賞して 第二部
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
小説・評論:孤城忍太郎の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-