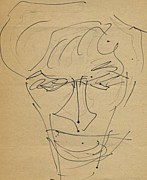この作品を讀む時に、この音樂を聞きながら鑑賞して下さい。
これは自作(オリジナル)の
『Motion1(Metamorphose・cembalo) 曲 高秋 美樹彦』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は東北の山形懸にある、
『立石寺』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
二十三、「ず」と「づ」に就いて 『言苑』より
前の店を疊んで新しい店に行つてから八箇月が過ぎた。
新しい店は二〇一二年九月十五日から新裝開店してゐたのだが、十二月末まで閉店でごたごたしてゐたので、妻と筆者との間にタイム・ラグが生じた譯である。
新しい店にも何とか慣れ、さうなると近所にも馴染が出來たりして、行附けの喫茶店で話も彈(はづ)まうといふものである。
その店は「コパン」と云つて、何でも親の後を繼いだ若い娘さんともう一人の女性とで切盛りしてゐるが、結構好奇心が強いらしくてあれこれと聞いて來られる、といふかこちらに合せてもらつてゐるのであらうが、さうすると私は私で我が意を得たりと調子に乘つてつい言はでもの事を口走る。
別けても日本語について會話には、肩の力が拔けた樂しい時間を過ごさせていただいてゐる。
その中で以前にも述べた事がある、「ず」と「づ」についての話題が上つた。
「携帶電話で「ちづ」と書込むと、地圖(ちづ)といふ漢字に變換(へんくわん)出來ない」
それはかういふものであつたが、それを聞いて、
「さうなんですよね。「圖(づ)」は『圖書(としよ)』と讀めるのですから「た行」若しくは「だ行」になつて、「ざ行」の「ず(圖)」では活用が異なつてしまひますから」
と應じて、「じやあ」は「では」の轉じたものだから、「ぢやあ」が本來ある可き表記法で、
「政治(せいじ)」の「治」は「治水(ちすい)」だから「せいぢ(政治)」
「地面(じめん)」の「地」は「大地(だいち)」だから「ぢめん(地面)」
とある可きだと話をつなげた。
かういふ問題が生じる原因となつたのは、一九四六年(昭和二十一)に從來の發音とずれてゐる、
『歴史的假名遣(れきしてきかなづかひ)』
が難しいとして、
「思ふ」が「思う」
や、
「てふ」が「ちょう」
のやうな發音に近い假名遣に改めた事によるものであるとし、この他に、國語を易しくする爲に日常使ふ漢字一八五〇字の漢字表を「當用漢字」として、義務教育教科書や公用文をこの範圍内で書くやうに内閣訓令の告示がされ、漢字の制限が實施されたのである。
この、
『當用漢字表』
は漢字を廢止する爲の當面の漢字として時の政府から「内閣訓令・告示」されたのだが、それがどのやうに變遷(へんせん)されて來たかといふと、かうである。
一九四八年(昭和二十三)に『當用漢字音訓表』で、
「觀」は「カン(くわん)」の音だけで「みる」の訓は認めず、
「認」は「ニン・みとめる」だけで「したためる」は認めない、
といふやうな當用漢字の一字ごとの讀み方を定めた。
一九四九年(昭和二十四)に『當用漢字字體表』として、
「區」は「区」、
「國」は「国」、
といふやうな新字體五百字餘が公式に定められた。
一九五一年(昭和二十六)に、
『人名用漢字別表』
として一九四七年の戸籍法施行規則で、子供の名前に使える漢字は當用漢字だけに限られてゐたが、更に九十二字を選んで人名用漢字として使へるようにした。
その後更に、一九五四年(昭和二十九)には當用漢字補正案が出されたが、實施は見送られた。
一九五九年(昭和三十四)に『送りがなのつけ方』として、
「終る」は「終わ(は)る」
「変(變)る」は「変(變は)わる」
を本則として、それまで統一されてゐなかつた送り假名の附け方を示した。
一九七三年(昭四十八)に『當用漢字改定音訓表』として、
「田舎」
「為(爲)替」
などの熟語としての讀み方(熟字訓)を「付表」として追加するとともに各漢字の音訓を増やした。
一九七三年(昭和四十八)に『改定送り假名の附け方』として、
「現わ(は)れ」・表わ(は)す・行なう(ふ)・断(斷)わる」
が本則であつたが、
「現れる・表す・行う・断(斷)る」
と改定された。
一九七六年(昭和五十一)に、
『人名用漢字追加表』
が、『人名用漢字別表』の九十二字ではまだ足りないとして二十八字を追加した。
一九八一年(昭和五十六)に、
『常用漢字表』
として、『當用漢字』だけでは不十分だといふので、九十五字を加へた千九百四十五字の漢字表が目安とされ、字體は當用漢字字體表に準じて新字體が採用された。
一九八一年(昭和五十六)には、
『人名用漢字別表』
として五十四字を追加され、名前につけられる字も常用漢字および人名用漢字となつた。
一九八六年(昭和六十一)に、
『改定現代假名遣』
として、助詞の、
「は、へ」を「わ、え」
と書く事も許容されてゐたが、實際には使はれてはゐないとして、この許容を外した。
一九九〇年(平成二)に、
『人名用漢字別表改定』
として、百十八字が一擧に追加された。
一九九一年(平成三)に、
『外來語の表記』
として、それまで公式に認めてゐなかつた「ヴ」の表記を認めた。
一九九七年(平成九)に、
『人名用漢字別表改定』
として、沖縄の人から「琉球」の「琉」が使へないといふ聲で一字が追加された。
二〇〇〇年(平成十二)の、
『表外漢字字體』
として、『常用漢字表』や『人名用漢字別表』にない漢字(表外漢字)千二十二字を選び、所謂(いはゆる)正字體を基準とするも、
「鴎、麹、曽、祷」
など二十二字は『簡易慣用字體』として許容し、また、
「之繞(しんねう)・示偏(しめすへん)・食偏(しよくへん)」
の三部首の、例へば、
「辻・祇・餅」
などが許容される事となつた。
その上、小学校の六年間に學習する事を文部科學省によつて定められた漢字の總稱である教育漢字が、教育の混亂(こんらん)をなくす爲に、
『當用漢字別表(収載字數八百八十一字)』
として一九四八年(昭和二十三年)に公布され、續いて一九五八年(昭和三十三年)に、
『筆順指導の手引』
を公布して、基本的な筆順が定められた。
その後、一九六八年(昭和四十三年)に、
『備考漢字(備考欄)』
を新たに設けて百十五字が追加され、一九七七年(昭和五十二年)の改定で正式に『教育漢字』に昇格して九百九十六字となつたが、やがて一九八九年(平成元年)に現在の千六字となつた。
かうして見ると、漢字を廢止するのが目的だつた漢字制限はなし崩し的に浸食されてしまつて、その意味は薄れてゐるどころか、漢字の有用性が深まつたと言つても良いのではないだらうか。
大體、秦の始皇帝ではあるまいし、權力者によつて國語を弄(いぢ)るのは感心できない。
確かに、「山茶花」が字義通りに「さんさか」だつたのが、江戸時代の學者が「さざんか」と讀み誤まつて人口に膾炙したといふ經緯(けいゐ)があるものの、これは「新しい」の「あらたしい」が「あたらしい」なつてしまつたのと同じやうに、少數の人の間違ひがいつの間にか多くの人に受容れられて今日に到つてゐるといふ事があつた。
しかしこの結果は、決して國家の權力によつて強制されたものではなく、時代の流れの中で緩やかに定着したものであるといふ事が重要な意味を持つてゐて、それは會議で有無を言はせず國民に押しつける場合と、改正しようと思へば議會での是非を問はなくても、いつでも容易に修正出來るといふ性質を有してゐるといふ差がある事に留意しなければならないと思はれるのである。
さうして、もう少し『現代假名遣』について調べた事を述べれば、
一九四六年(昭和二十一)の『内閣告示(第三三号)』及び『現代假名遣の實施に關する件(訓令第八號)』
といふ從來の『現代假名遣』は、
一九八六年(昭和六十一)の『内閣告示(第一号)』によつて廢止されたとある。
そこでは『「現代假名遣」ついて』として、
「法令・公用文書・新聞・雜誌・放送」
など、一般の社會生活において現代の國語を書き表すための「假名遣」の據所(よりどころ)を示すものであり、
「科學・技術・藝術」
その他の各種專門分野や個々人の表記にまで及ぼさうとするものではなく、また、固有名詞などでこれにより難いものや、特殊な音、外來語の音などの書き表し方を對象とするものではない事と、その規則の立て方を簡明にし、現代語の音韻に從つて書き表す原則(本文第一)と、表記の慣習を尊重した特例(第二)とから成るものとした。
『歴史的假名遣』は、明治以降『現代假名遣(昭和二十一年内閣告示第三十三號)』の行はれる以前には、社會一般の基準としてゐたものであり、今日においても、『歴史的假名遣』で書かれた文獻などを讀む機會は多く、我が國の歴史や文化に深い拘りを持つものとして、尊重されるべきことは言うまでもない。
また『現代假名遣』にも『歴史的假名遣』を受繼いでゐる所があり、『現代假名遣』の理解を深める上で、『歴史的假名遣』を知る事は有用である事から、附表を設けて『現代假名遣』と『歴史的假名遣』との對照を示し、從來の『現代假名遣(昭和二十一年内閣告示第三三號)』による表記と實際上は殆ど相違がない事と記した。
とここまで書いて、漸く「ぢ」と「づ」の話に戻る譯だが、『現代假名遣』では原則的に『だ行』の「ぢ」「づ」は用ゐず、『ざ行』の「じ」「ず」を用ゐるとした上で、次のやうな例外を擧げてゐて、それは同音の連呼によつて生じた「ぢ・づ」、
「ちぢむ(縮む)・つづく(續く)・つづみ(鼓)以下略」
それと二語の連合によつて生じた「ぢ・づ」、
「はなぢ(鼻+血)・そこぢから(底+ちから)・たけづつ(竹+筒)・みちづれ(道+連れ)以下略」
として、以上の事から語頭には『ぢ・づ』は來ないといふ事になる。
所が、次のような語は「二語の連合」ではあるけれども、「現代語の意識では二語に分解しにくいといふう理由で、當初一九四六年(昭和二十一)の内閣告示・訓令『現代假名遣』を補足した、一九五六年(昭和三十一)の國語審議會報告の『正書法について』では「じ・ず」と書く事になつてゐた、
「世界中(せかいじゅう)・稲妻(いなずま)・融通(ゆうずう)」
については、「現代語の意識では二語に分解しにくい」という理由が主觀的すぎるなどの批判があり、昭和六十一年の内閣告示・訓令では、上記のような語について、
「『じ』『ず』を用いて書くことを本則とし、『せかいぢゅう・いなづま・ゆうづう』のように『ぢ』『づ』を用いて書く事も出來る」
と、規範が緩められた。
國の政策としての規範は以上で終へるが、ここで問題にするべきは助動詞の打消しの、
「ず」
である。
これは例へば『歴史的假名遣』では、
「日出づる處の天子」
と本來は「づ」表記すべき所を、
「日出ずる處の天子」
と『現代假名遣』では「ず」としてしまつてゐる。
この「ず」と「づ」は、「出づ」は「いづ」と讀んでこの「づ」は出て行く事だが、「出ず」は「いでず」と讀んで出ない事となり、「ず」は出る事を打消してゐるのである。
これは『廣辭苑』でさへ「出(い)ず(イヅ)」で見出し語として檢索出來るのが驚きである。
發句の春の季語に、
「蛇穴を出づ」
といふ春の季語があるが、『大辭林』で調べた時、
「蛇穴を出ず」
とあつた。
これでは啓蟄(けいちつ)になつても、蛇が穴から出て來ない事だから春にはならなくなつてしまふが、遉(さすが)に『廣辭苑』は古文として扱つた爲かこれを受附けてはゐない。
けれども、
「いづこ・いづれ」が「いずこ・いずれ」
となり、
「愛(め)づる」が「愛ずる」
となつて、言葉は亂(みだ)れた儘となつてゐるのは、實(まこと)に無念の極みである。
何となれば、日本國憲法が歴史的假名遣で表記されてゐるのだから……。
二〇一三年六月二日午後五時十五分店にて記す
關聯記事
『言苑』8、「ヴ」に就いて
http://
16、「じ・ぢ」と「ず・づ」に就いて『言苑』より
http://
これは自作(オリジナル)の
『Motion1(Metamorphose・cembalo) 曲 高秋 美樹彦』
といふ曲で、YAMAHAの「QY100」で作りました。
映像は東北の山形懸にある、
『立石寺』
へ出かけた時のものです。
雰圍氣を味はつて戴ければ幸ひですが、ない方が良いといふ讀者は聞かなくても構ひませんので、ご自由にどうぞ。
二十三、「ず」と「づ」に就いて 『言苑』より
前の店を疊んで新しい店に行つてから八箇月が過ぎた。
新しい店は二〇一二年九月十五日から新裝開店してゐたのだが、十二月末まで閉店でごたごたしてゐたので、妻と筆者との間にタイム・ラグが生じた譯である。
新しい店にも何とか慣れ、さうなると近所にも馴染が出來たりして、行附けの喫茶店で話も彈(はづ)まうといふものである。
その店は「コパン」と云つて、何でも親の後を繼いだ若い娘さんともう一人の女性とで切盛りしてゐるが、結構好奇心が強いらしくてあれこれと聞いて來られる、といふかこちらに合せてもらつてゐるのであらうが、さうすると私は私で我が意を得たりと調子に乘つてつい言はでもの事を口走る。
別けても日本語について會話には、肩の力が拔けた樂しい時間を過ごさせていただいてゐる。
その中で以前にも述べた事がある、「ず」と「づ」についての話題が上つた。
「携帶電話で「ちづ」と書込むと、地圖(ちづ)といふ漢字に變換(へんくわん)出來ない」
それはかういふものであつたが、それを聞いて、
「さうなんですよね。「圖(づ)」は『圖書(としよ)』と讀めるのですから「た行」若しくは「だ行」になつて、「ざ行」の「ず(圖)」では活用が異なつてしまひますから」
と應じて、「じやあ」は「では」の轉じたものだから、「ぢやあ」が本來ある可き表記法で、
「政治(せいじ)」の「治」は「治水(ちすい)」だから「せいぢ(政治)」
「地面(じめん)」の「地」は「大地(だいち)」だから「ぢめん(地面)」
とある可きだと話をつなげた。
かういふ問題が生じる原因となつたのは、一九四六年(昭和二十一)に從來の發音とずれてゐる、
『歴史的假名遣(れきしてきかなづかひ)』
が難しいとして、
「思ふ」が「思う」
や、
「てふ」が「ちょう」
のやうな發音に近い假名遣に改めた事によるものであるとし、この他に、國語を易しくする爲に日常使ふ漢字一八五〇字の漢字表を「當用漢字」として、義務教育教科書や公用文をこの範圍内で書くやうに内閣訓令の告示がされ、漢字の制限が實施されたのである。
この、
『當用漢字表』
は漢字を廢止する爲の當面の漢字として時の政府から「内閣訓令・告示」されたのだが、それがどのやうに變遷(へんせん)されて來たかといふと、かうである。
一九四八年(昭和二十三)に『當用漢字音訓表』で、
「觀」は「カン(くわん)」の音だけで「みる」の訓は認めず、
「認」は「ニン・みとめる」だけで「したためる」は認めない、
といふやうな當用漢字の一字ごとの讀み方を定めた。
一九四九年(昭和二十四)に『當用漢字字體表』として、
「區」は「区」、
「國」は「国」、
といふやうな新字體五百字餘が公式に定められた。
一九五一年(昭和二十六)に、
『人名用漢字別表』
として一九四七年の戸籍法施行規則で、子供の名前に使える漢字は當用漢字だけに限られてゐたが、更に九十二字を選んで人名用漢字として使へるようにした。
その後更に、一九五四年(昭和二十九)には當用漢字補正案が出されたが、實施は見送られた。
一九五九年(昭和三十四)に『送りがなのつけ方』として、
「終る」は「終わ(は)る」
「変(變)る」は「変(變は)わる」
を本則として、それまで統一されてゐなかつた送り假名の附け方を示した。
一九七三年(昭四十八)に『當用漢字改定音訓表』として、
「田舎」
「為(爲)替」
などの熟語としての讀み方(熟字訓)を「付表」として追加するとともに各漢字の音訓を増やした。
一九七三年(昭和四十八)に『改定送り假名の附け方』として、
「現わ(は)れ」・表わ(は)す・行なう(ふ)・断(斷)わる」
が本則であつたが、
「現れる・表す・行う・断(斷)る」
と改定された。
一九七六年(昭和五十一)に、
『人名用漢字追加表』
が、『人名用漢字別表』の九十二字ではまだ足りないとして二十八字を追加した。
一九八一年(昭和五十六)に、
『常用漢字表』
として、『當用漢字』だけでは不十分だといふので、九十五字を加へた千九百四十五字の漢字表が目安とされ、字體は當用漢字字體表に準じて新字體が採用された。
一九八一年(昭和五十六)には、
『人名用漢字別表』
として五十四字を追加され、名前につけられる字も常用漢字および人名用漢字となつた。
一九八六年(昭和六十一)に、
『改定現代假名遣』
として、助詞の、
「は、へ」を「わ、え」
と書く事も許容されてゐたが、實際には使はれてはゐないとして、この許容を外した。
一九九〇年(平成二)に、
『人名用漢字別表改定』
として、百十八字が一擧に追加された。
一九九一年(平成三)に、
『外來語の表記』
として、それまで公式に認めてゐなかつた「ヴ」の表記を認めた。
一九九七年(平成九)に、
『人名用漢字別表改定』
として、沖縄の人から「琉球」の「琉」が使へないといふ聲で一字が追加された。
二〇〇〇年(平成十二)の、
『表外漢字字體』
として、『常用漢字表』や『人名用漢字別表』にない漢字(表外漢字)千二十二字を選び、所謂(いはゆる)正字體を基準とするも、
「鴎、麹、曽、祷」
など二十二字は『簡易慣用字體』として許容し、また、
「之繞(しんねう)・示偏(しめすへん)・食偏(しよくへん)」
の三部首の、例へば、
「辻・祇・餅」
などが許容される事となつた。
その上、小学校の六年間に學習する事を文部科學省によつて定められた漢字の總稱である教育漢字が、教育の混亂(こんらん)をなくす爲に、
『當用漢字別表(収載字數八百八十一字)』
として一九四八年(昭和二十三年)に公布され、續いて一九五八年(昭和三十三年)に、
『筆順指導の手引』
を公布して、基本的な筆順が定められた。
その後、一九六八年(昭和四十三年)に、
『備考漢字(備考欄)』
を新たに設けて百十五字が追加され、一九七七年(昭和五十二年)の改定で正式に『教育漢字』に昇格して九百九十六字となつたが、やがて一九八九年(平成元年)に現在の千六字となつた。
かうして見ると、漢字を廢止するのが目的だつた漢字制限はなし崩し的に浸食されてしまつて、その意味は薄れてゐるどころか、漢字の有用性が深まつたと言つても良いのではないだらうか。
大體、秦の始皇帝ではあるまいし、權力者によつて國語を弄(いぢ)るのは感心できない。
確かに、「山茶花」が字義通りに「さんさか」だつたのが、江戸時代の學者が「さざんか」と讀み誤まつて人口に膾炙したといふ經緯(けいゐ)があるものの、これは「新しい」の「あらたしい」が「あたらしい」なつてしまつたのと同じやうに、少數の人の間違ひがいつの間にか多くの人に受容れられて今日に到つてゐるといふ事があつた。
しかしこの結果は、決して國家の權力によつて強制されたものではなく、時代の流れの中で緩やかに定着したものであるといふ事が重要な意味を持つてゐて、それは會議で有無を言はせず國民に押しつける場合と、改正しようと思へば議會での是非を問はなくても、いつでも容易に修正出來るといふ性質を有してゐるといふ差がある事に留意しなければならないと思はれるのである。
さうして、もう少し『現代假名遣』について調べた事を述べれば、
一九四六年(昭和二十一)の『内閣告示(第三三号)』及び『現代假名遣の實施に關する件(訓令第八號)』
といふ從來の『現代假名遣』は、
一九八六年(昭和六十一)の『内閣告示(第一号)』によつて廢止されたとある。
そこでは『「現代假名遣」ついて』として、
「法令・公用文書・新聞・雜誌・放送」
など、一般の社會生活において現代の國語を書き表すための「假名遣」の據所(よりどころ)を示すものであり、
「科學・技術・藝術」
その他の各種專門分野や個々人の表記にまで及ぼさうとするものではなく、また、固有名詞などでこれにより難いものや、特殊な音、外來語の音などの書き表し方を對象とするものではない事と、その規則の立て方を簡明にし、現代語の音韻に從つて書き表す原則(本文第一)と、表記の慣習を尊重した特例(第二)とから成るものとした。
『歴史的假名遣』は、明治以降『現代假名遣(昭和二十一年内閣告示第三十三號)』の行はれる以前には、社會一般の基準としてゐたものであり、今日においても、『歴史的假名遣』で書かれた文獻などを讀む機會は多く、我が國の歴史や文化に深い拘りを持つものとして、尊重されるべきことは言うまでもない。
また『現代假名遣』にも『歴史的假名遣』を受繼いでゐる所があり、『現代假名遣』の理解を深める上で、『歴史的假名遣』を知る事は有用である事から、附表を設けて『現代假名遣』と『歴史的假名遣』との對照を示し、從來の『現代假名遣(昭和二十一年内閣告示第三三號)』による表記と實際上は殆ど相違がない事と記した。
とここまで書いて、漸く「ぢ」と「づ」の話に戻る譯だが、『現代假名遣』では原則的に『だ行』の「ぢ」「づ」は用ゐず、『ざ行』の「じ」「ず」を用ゐるとした上で、次のやうな例外を擧げてゐて、それは同音の連呼によつて生じた「ぢ・づ」、
「ちぢむ(縮む)・つづく(續く)・つづみ(鼓)以下略」
それと二語の連合によつて生じた「ぢ・づ」、
「はなぢ(鼻+血)・そこぢから(底+ちから)・たけづつ(竹+筒)・みちづれ(道+連れ)以下略」
として、以上の事から語頭には『ぢ・づ』は來ないといふ事になる。
所が、次のような語は「二語の連合」ではあるけれども、「現代語の意識では二語に分解しにくいといふう理由で、當初一九四六年(昭和二十一)の内閣告示・訓令『現代假名遣』を補足した、一九五六年(昭和三十一)の國語審議會報告の『正書法について』では「じ・ず」と書く事になつてゐた、
「世界中(せかいじゅう)・稲妻(いなずま)・融通(ゆうずう)」
については、「現代語の意識では二語に分解しにくい」という理由が主觀的すぎるなどの批判があり、昭和六十一年の内閣告示・訓令では、上記のような語について、
「『じ』『ず』を用いて書くことを本則とし、『せかいぢゅう・いなづま・ゆうづう』のように『ぢ』『づ』を用いて書く事も出來る」
と、規範が緩められた。
國の政策としての規範は以上で終へるが、ここで問題にするべきは助動詞の打消しの、
「ず」
である。
これは例へば『歴史的假名遣』では、
「日出づる處の天子」
と本來は「づ」表記すべき所を、
「日出ずる處の天子」
と『現代假名遣』では「ず」としてしまつてゐる。
この「ず」と「づ」は、「出づ」は「いづ」と讀んでこの「づ」は出て行く事だが、「出ず」は「いでず」と讀んで出ない事となり、「ず」は出る事を打消してゐるのである。
これは『廣辭苑』でさへ「出(い)ず(イヅ)」で見出し語として檢索出來るのが驚きである。
發句の春の季語に、
「蛇穴を出づ」
といふ春の季語があるが、『大辭林』で調べた時、
「蛇穴を出ず」
とあつた。
これでは啓蟄(けいちつ)になつても、蛇が穴から出て來ない事だから春にはならなくなつてしまふが、遉(さすが)に『廣辭苑』は古文として扱つた爲かこれを受附けてはゐない。
けれども、
「いづこ・いづれ」が「いずこ・いずれ」
となり、
「愛(め)づる」が「愛ずる」
となつて、言葉は亂(みだ)れた儘となつてゐるのは、實(まこと)に無念の極みである。
何となれば、日本國憲法が歴史的假名遣で表記されてゐるのだから……。
二〇一三年六月二日午後五時十五分店にて記す
關聯記事
『言苑』8、「ヴ」に就いて
http://
16、「じ・ぢ」と「ず・づ」に就いて『言苑』より
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
小説・評論:孤城忍太郎の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
小説・評論:孤城忍太郎の世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75494人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208290人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196028人