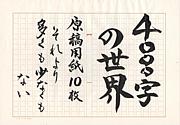景観というものは千変万化する。
姉から届いた手紙を見たとき、正造が思ったのはそういうことだった。
最後に姉の姿を見たのは、彼が高校生のときだった。彼女の書いた文字にいたっては、中学生のとき以来見たことがないはずだったが、すぐに姉の字だと見当がついた。
彼は机のうえに手紙をおいて、眉間の皺を指でもんだ。指の爪には、午前中にさわっていた土がかすかに残っていた。
正造の趣味はガーデニングである。週末の庭造りにささやかな喜びを見出している。誰かに習うわけでもない自己流だったが、先月遊びにきた会社の同僚がそれを見て感心し、雑誌社に勤める知り合いに話を通したらしく、園芸誌の取材がきて、彼を驚かせたことがあった。一応写真を撮ってはいたものの、本当に掲載されるかどうかは疑わしい、と正造は思っていたのだが、今月発売の号を見てみると、二ページにわたって紹介されていた。友人知人に気づかれることはなかったものの、うれしいような恥ずかしいような思いをしていたところ、どういった偶然か、その雑誌を読んだ姉が、出版社あてに手紙を書いてきたのである。
姉はいま福島にいて、子供をひとり育てているという。一緒に逃げたはずの男のことは、何も書かれていなかった。
正造は両親に電話しようかと、壁に貼られたメモ書きに目を走らせたが、父と母の、それぞれ違う電話番号がならんでいるのを見ると、その気はすぐに失せてしまった。
妻の呼ぶ声がしたので、手紙を手に持ったまま、彼は部屋を出て階下へ向かった。妻はむずかしい顔をしてノートを片手に持ち、キッチンに立っている。
「買い忘れた具材があったのよ。あなた暇なら、ちょっと買ってきてくれない?」
有名シェフが料理を教えてくれるというカルチャースクールに通う妻は、毎週日曜、先週末に習った料理を実践しなければならないのだった。
正造は姉のことを話そうかと思ったが、食事を終えてからにしようと思い直してうなずいた。
ふとリビングへ目を向けると、十歳になる息子が、フローリングの床にすわって、ぼんやりと窓の外に目を向けている。窓は開け放たれていて、カーテンが風に揺れていた。
正造も外に目を向けた。梅雨はすぎ去り、おおきな入道雲がひとつ、青空にもくもくと育っていた。
彼は姉の手紙をおりたたんで、ポケットに入れた。
景観は日々刻々と姿を変える。
そのうつりかわる様は実にあでやかで、えたいの知れない迫力のようなものを、正造の心に植えつけている。
彼がおさないころから未熟な目で見てきたさまざまなものは、いずれも劇的に表情を変えた。姉の出奔も、両親の離婚も、たえずまわりつづける万華鏡のようなものだと、彼は思う。
子供のころの正造は毎年、夏になると、母の実家へ連れられていった。それは彼の物心がつく前からくりかえされている習慣だった。
祖父の家にはよく手入れされたおおきな庭園があり、彼はふるびた縁側からその庭をながめることを、いつもの夏休みの日課としていた。祖父の用意してくれた蚊取り線香をかたわらに置いて、ゆるゆるとたちのぼる煙が、風向きによって顔にまとわりついてくるのをよけながら、彼は飽くことなく庭をながめた。
そこには花がいっさいなかった。
刈りこまれた芝生も、アスファルト敷きの玄関スロープと庭とを区切るツツジも、門のうえを真横にのびる松の枝も、ふかい緑に輝いていた。
太陽の光はすべてを焼きつくそうとしており、セミがいたるところで鳴いていて、正造はあまりの暑さに茹であがってしまいそうだったが、セミがうるさければうるさいほど、陽射しが強くなればなるほど、庭の緑は喜んでいるように見えた。
背後から、姉が祖父を呼ぶ声がする。
「じいちゃーん、じいちゃーん」
その年、姉は高校生になったばかりで、夏休みの恒例行事と化していた帰郷が、不満でしかたない様子だった。できたばかりの恋人と、夏休みのあいだに遊ぶ計画をいろいろとたてていたのだが、「家族の行事をないがしろにするのかっ」と父に一喝され、渋々ついてきたのだった。
正造の目から見て、その後の姉の人生は、父を否定することによって成り立っていたようだった。だが当時はまだ彼女も子供で、自分を閉じこめる殻から抜け出しきれていなかったし、そんな殻があること自体にも気づいていなかったのだ。
姉の祖父を呼ぶ声には、ぶつけるあてのない苛立ちがにじんでいた。彼女は朝食のあとにシャワーを浴びていたのだが、シャワーの水圧が弱すぎることを不服としているらしかった。
「あのシャワー壊れてるんじゃないの?」
姉はぬれた髪の毛をふきながら言った。
居間にいる祖父は、ことさら意に介す風でもなく、そうかそうかとつぶやきながら、新聞を読みこんでいる。祖父は毎年開催される夏の甲子園を楽しみにしていて、新聞に掲載されたトーナメント表を、赤ペンで染めあげていた。
居間の向こうの台所で、不満そうに水を飲む姉のかたわらには、祖母がいた。
彼の記憶にあるかぎり、祖母はつねに働いていた。床に正座をして、裏の畑でとれた夏野菜をひろげ、近所に配ってまわる分を小分けにしている。祖母の筋ばった手でならべられるトマトやキュウリやナスビなどは、いつでも力強く輝いていた。
「わがまま言わないの」
と姉にむかって言う母は、梨を食べながらテレビをながめている。ブラウン管のなかでは、通販番組をやっている。
我が家にいるときの母は、かならず台所で料理を作っていたし、家にいないときは仕事に出ずっぱりで、つねに何かやらなければならないことを探している様子だったのだが、実家に帰った途端、切れた輪ゴムのようにやる気なく、居間で寝転がっていることが多かった。
正造は母のその変化をいつも意外に感じながら、なぜそれが意外に感じられるのか分析することができず、ただ言いようのない不安を、ちいさな胸のなかで持てあますことしかできなかった。
父もまた、窓を開け放した和室で寝ているだけだった。襖をはずした二間の中央に蒲団をしいて横たわり、おおきなイビキをかいている。
父が寝ているのはいつものことだったので、疑問に思うことはなかった。家にいるときとの違いは何もない。休日の父はたいてい酔っぱらっていたし、ところかまわず眠ることができた。その部屋の縁側に坐っている正造は、背中にぶつかってくる父のイビキとセミの鳴き声とが、不思議な和音をかなでていることに気づいて面白がっていたが、父がたまに喉をつまらせると、そのたびにおそるおそる背後を確認した。呼吸を止めていた父は、しばらくすると、慌てふためくようにして大きく息を吸いこんだ。当時は無呼吸症候群という言葉もなく、そんなに苦しいんだったら息なんて止めなければ良いのにと、正造はそれを父の一風変わった趣味のようなものだと思いこんでいた。
やわらかくふいてきた風が、庭をながめる正造の顔をなでた。
風はそのまま、寝ている父の頬に触れ、居間でテレビを観ている母のうしろ髪や、祖父の読んでいる新聞を揺らし、台所にいる姉と、野菜に手を伸ばしている祖母の、汗ばんだ額や首をひやす。
彼らにとっての夏は、いつもそのようにしてすぎていった。
それはとても緩慢な日々で、ややもすると、永遠につづくのではないかと、正造は思っていた。
たかだか二十数年前の話だったが、遠い過去のような気がしていた。
床にすわる息子の丸い背中を、やけにいとおしく感じながら、彼は妻の走書きが記されたメモを片手に、玄関へ向かった。
あがり框にすわって靴を履く。その靴は去年、妻と息子が誕生日プレゼントに買ってくれたものだった。かたいトレッキングシューズで、最初は靴擦れになやんだが、いまではすっかり足にフィットしている。靴紐をむすんだ正造は立ちあがり、玄関の扉を押し開けた。
強烈な初夏の陽射しが、一瞬、すべての景色を白く焼いた。彼は手で庇をつくり、目をほそめた。外の景色がよみがえってくるまで、彼はまばゆい光を前に、しばらく立ち尽くしていた。
おわり
|
|
|
|
|
|
|
|
4000字の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
4000字の世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- カラオケ「町田オフ」
- 983人
- 2位
- 暮らしを楽しむ
- 75441人
- 3位
- 酒好き
- 170648人