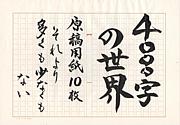三日前から風邪を患っていたのだが、いよいよ本格的にこじらせてしまった。
朝、ぼんやりとした顔でネクタイをしめていて、美津子から「お義父さん、顔赤いですよ」と指摘された。熱を測ってみると三十八度六分で、驚いた美津子が代理で会社に電話してくれた。そこまで大袈裟にすることもないとは思ったが、ここのところ休み無く働いていたのでちょうどいい。消化しなくてはならない有給休暇を使って、四日間ほど自宅療養することにした。
お粥を食べて和室に蒲団をしき、横たわる。
開け放した障子戸の向こうで、庭が朝日に輝いている。朝、美津子が芝生に水を浴びせたので、宝石を散りばめたように見える。
蝉が二、三匹鳴いていた。
まだ風は涼しい。部屋のふすまと、廊下の窓も開けているので、微風が室内をゆったりと移動して、白髪の多くなった前髪を揺らす。指でつまんでひっぱると、目がすこし隠れてしまう。
そろそろ床屋に行かなければ、と思う。私の父方の家系は代々禿げていたが、ありがたいことに、今年で還暦をむかえる私にはまだ、その兆候はなかった。母方の遺伝の方が強いのかもしれない。そういえば、私の顔も、父よりは母に似ている。
陽一は、私よりも、私の父に似ていた。禿げの遺伝子は私を一足飛びで抜かして、息子に伝わっていたかもしれない。生きていたころ、彼は猫毛だった。
向日葵が一輪、庭と道路とをへだてる塀の際に、すくすくと育っていた。
美津子が六月ごろから下の方の葉を切っているため、茎はまっすぐにぐいぐいと、真上から引っぱられるように伸びた。余計な芽も摘まれて、おおきな花が一輪だけ、堂々と咲き誇っている。私の身長よりも、塀よりも高い。
その様は力強く、熱でぼんやりとした私は、何とはなしに圧倒された。子供のころは大好きな花だったのだが、気後れするような、息づまるような、慎重な気分になった。何故か息を潜めなければならないような気がして、呼吸を浅くすると、咳が出た。
「大丈夫ですか?」
美津子が縁側から顔を出した。風邪薬を持ってきてくれたらしい。
「暑いでしょう」
枕もとに坐って、団扇をあおぎはじめる。私は上体を起こし、ああともうんともつかぬ曖昧な返事をして薬を飲み、また横たわった。美津子は坐したまま団扇であおぎ続ける。
私はクーラーの風が苦手で、彼女はそのことをよく知っていた。
「疲れるだろう。扇風機を持ってくればいいのに」
「気にしなくていいですよ」
「私が持って来ようか」
「病人でしょう。寝ててください」
亡き妻とも似たような会話を交わしたことがあった。私は天井をぼんやりと眺めながら、いつのことだったろうと考えたが、思い出せなかった。私はあまり身体が丈夫ではなかったため、風邪で寝こむこともたびたびあり、だからそうした会話も、何度となく繰り返されていた。
溜息をつき、溜息を聞かれやしなかったかと顔色をうかがったが、美津子はまったく気づかぬ風で、庭を眺めながらゆっくりと扇いでいる。
黒いレギンスに白いワンピースを着た姿は若い。先日、彼女の履くレギンスをスパッツと呼んで笑われたことを思い出す。もう四十路が近いはずだが、まだ二十代の半ばでも通じるような笑顔だった。
そう思いながらも、私は言わない。見え透いたお世辞のようで気がひけた。だが、何か言わなければならないような気がした。美津子は無造作に庭を眺めている。
「陽一は」
と思わず言って、口をつぐんだ。おそらく、この話題は違う。
だが、美津子はふり向いた。
「はい」
「……陽一はね、子供のころ、夏になると、その庭でビニール製のプールに入るのが好きだったんだよ」
「聞いたことがあります」と言って、美津子は笑った。
「夜になるまでプールで遊んで、お義父さんに叱られて意固地になって、プールの中で夜を明かしたって」
「そうだ、それで熱を出して寝こんだ。この部屋で。八つぐらいの時だったかな」
美津子はふふと笑って、また庭に顔を向けた。髪の毛に遮られて、表情が見えなくなった。
陽一は、彼女との間に子供も作らず、二年前にこの世を去った。
私から、息子の話を美津子にしたのは、以来はじめてのことだった。
「隣の青木さんから、西瓜をもらったんじゃないか」
私が言うと、彼女は「切ってきますね」と立ちあがり、部屋を出た。
美津子の足音が遠ざかり、静寂が広がった。
一瞬後、まるで思い出したように、蝉の鳴き声が私の耳に戻ってくる。
暑い。私はかけ蒲団を払いのけた。背中が汗で蒸れている。身体を起こした。
浴衣から伸び出る自分の脛が、力ない。片膝を立てて撫でると冷たかった。もう片方のダランと伸びた足をあらためて見て、青白さ、貧相さに驚いた。
ふと、壁かけ時計が目に入り、思い出す。もう九時半をまわっているが、美津子がパートへ行く時間はとっくにすぎていた。私のせいで休みをとったのかと気づいて、げんなりした。今から行けと諭しても、もう遅いのだろう。
彼女は最近、パート先のスーパーへ行くのを楽しみにしている様子だった。
そして、そんな自分を認めまいとしている。その様が手にとるようによくわかる。スーパーの従業員の中に、気になる相手がいるらしかった。そう断定してしまうにはまだ早いかもしれないが、食卓の席でうれしそうに、仕入れ担当であるらしい男とのエピソードを、私に語って聞かせることがある。そして、相槌を打つ私の顔を見るなり我に帰って、息を飲むシーンもたびたびあった。
美津子が西瓜を運んできた。私は彼女の顔を見るなり言った。
「仕事は休んだのか」
「いいんですよ、もう辞めますから。給料があんまりよくないんです」
せいせいする、とばかりに笑んで、美津子はまた団扇を扇ぎはじめた。ゆるやかな風が私の顔を撫でる。
心地良かった。
「そろそろ、家を出ればどうだ」
と、私は唐突に言った。
自然に口をついて出た。自分自身でも驚くほどだったが、もっと早く言わなければならなかったのだと、いまはじめて気がついた。
「善い人がいるんだろう。もう陽一はいないんだから、ここにいる必要もないよ」
美津子は黙ったまま、庭を眺めている。表情は見えない。陽一が死んだころも、しばらくそうして私に顔を見せなかった。
彼女はふり向きもせず、顔を隠したまま言った。
「陽一さんが淋しがりますよ。あの人は私がいないと……」
「もう、陽一はいないんだよ」
私は極力、無感情に言った。
美津子はしばらく黙った後、部屋を出て行った。
ふたたび、室内に蝉の鳴き声がうるさく響き渡る。
私は蒲団のうえで、自分の細い片膝をかかえて、庭を見る。陽射しが強く、芝生が青い。喉がかわく。妻がいれば、梨でも食べたいと我がままを言って、困らせてやるところなのに。そう考えて溜息をつき、枕もとに置かれた西瓜に手を伸ばした。
しゃるりと口に含み、あまりの冷たさに顔をしかめて、皿に戻す。冷蔵庫で冷やされすぎていて、食べられなかった。昔、川に浸していたころは、こうではなかったとおもう。この冷やされ方は、あまりに人工的過ぎた。私はもっと生ぬるい西瓜が好きだった。
陽一の嗜好は私に似ていて、西瓜にしろ梨にしろ、生ぬるいものを好んで食べた。その方がより強く甘みを感じられて良いのだと、一丁前に言っていた。それが私からの受け売りであることを、彼は覚えていただろうか。
彼が子供だったころには、よく縁側に並んで坐り、一緒に生ぬるい西瓜を食べた。どちらがより遠くまで種を飛ばせるか競争した。陽一の種は一メートルほどしか飛ばず、私の種は、塀にあたった。その様子を後ろから見ていた妻に叱られて、私たちはまた大人しく食べ、妻は溜息をつきながらも、猫背なのがそっくりね、と笑っていた。
昔、種を飛ばしたそこには、いま、蝉の死骸が転がっている。
脛がかゆい。見やると、蚊に食われてプックリと膨れあがっていた。
再び庭に目をやって、巨大な向日葵に、改めてギョッとした。青い空を背景に、どこまでも聳えてゆくようだった。堂々とした姿勢の良さに、私は何故か怯え、身震いした。
おわり
朝、ぼんやりとした顔でネクタイをしめていて、美津子から「お義父さん、顔赤いですよ」と指摘された。熱を測ってみると三十八度六分で、驚いた美津子が代理で会社に電話してくれた。そこまで大袈裟にすることもないとは思ったが、ここのところ休み無く働いていたのでちょうどいい。消化しなくてはならない有給休暇を使って、四日間ほど自宅療養することにした。
お粥を食べて和室に蒲団をしき、横たわる。
開け放した障子戸の向こうで、庭が朝日に輝いている。朝、美津子が芝生に水を浴びせたので、宝石を散りばめたように見える。
蝉が二、三匹鳴いていた。
まだ風は涼しい。部屋のふすまと、廊下の窓も開けているので、微風が室内をゆったりと移動して、白髪の多くなった前髪を揺らす。指でつまんでひっぱると、目がすこし隠れてしまう。
そろそろ床屋に行かなければ、と思う。私の父方の家系は代々禿げていたが、ありがたいことに、今年で還暦をむかえる私にはまだ、その兆候はなかった。母方の遺伝の方が強いのかもしれない。そういえば、私の顔も、父よりは母に似ている。
陽一は、私よりも、私の父に似ていた。禿げの遺伝子は私を一足飛びで抜かして、息子に伝わっていたかもしれない。生きていたころ、彼は猫毛だった。
向日葵が一輪、庭と道路とをへだてる塀の際に、すくすくと育っていた。
美津子が六月ごろから下の方の葉を切っているため、茎はまっすぐにぐいぐいと、真上から引っぱられるように伸びた。余計な芽も摘まれて、おおきな花が一輪だけ、堂々と咲き誇っている。私の身長よりも、塀よりも高い。
その様は力強く、熱でぼんやりとした私は、何とはなしに圧倒された。子供のころは大好きな花だったのだが、気後れするような、息づまるような、慎重な気分になった。何故か息を潜めなければならないような気がして、呼吸を浅くすると、咳が出た。
「大丈夫ですか?」
美津子が縁側から顔を出した。風邪薬を持ってきてくれたらしい。
「暑いでしょう」
枕もとに坐って、団扇をあおぎはじめる。私は上体を起こし、ああともうんともつかぬ曖昧な返事をして薬を飲み、また横たわった。美津子は坐したまま団扇であおぎ続ける。
私はクーラーの風が苦手で、彼女はそのことをよく知っていた。
「疲れるだろう。扇風機を持ってくればいいのに」
「気にしなくていいですよ」
「私が持って来ようか」
「病人でしょう。寝ててください」
亡き妻とも似たような会話を交わしたことがあった。私は天井をぼんやりと眺めながら、いつのことだったろうと考えたが、思い出せなかった。私はあまり身体が丈夫ではなかったため、風邪で寝こむこともたびたびあり、だからそうした会話も、何度となく繰り返されていた。
溜息をつき、溜息を聞かれやしなかったかと顔色をうかがったが、美津子はまったく気づかぬ風で、庭を眺めながらゆっくりと扇いでいる。
黒いレギンスに白いワンピースを着た姿は若い。先日、彼女の履くレギンスをスパッツと呼んで笑われたことを思い出す。もう四十路が近いはずだが、まだ二十代の半ばでも通じるような笑顔だった。
そう思いながらも、私は言わない。見え透いたお世辞のようで気がひけた。だが、何か言わなければならないような気がした。美津子は無造作に庭を眺めている。
「陽一は」
と思わず言って、口をつぐんだ。おそらく、この話題は違う。
だが、美津子はふり向いた。
「はい」
「……陽一はね、子供のころ、夏になると、その庭でビニール製のプールに入るのが好きだったんだよ」
「聞いたことがあります」と言って、美津子は笑った。
「夜になるまでプールで遊んで、お義父さんに叱られて意固地になって、プールの中で夜を明かしたって」
「そうだ、それで熱を出して寝こんだ。この部屋で。八つぐらいの時だったかな」
美津子はふふと笑って、また庭に顔を向けた。髪の毛に遮られて、表情が見えなくなった。
陽一は、彼女との間に子供も作らず、二年前にこの世を去った。
私から、息子の話を美津子にしたのは、以来はじめてのことだった。
「隣の青木さんから、西瓜をもらったんじゃないか」
私が言うと、彼女は「切ってきますね」と立ちあがり、部屋を出た。
美津子の足音が遠ざかり、静寂が広がった。
一瞬後、まるで思い出したように、蝉の鳴き声が私の耳に戻ってくる。
暑い。私はかけ蒲団を払いのけた。背中が汗で蒸れている。身体を起こした。
浴衣から伸び出る自分の脛が、力ない。片膝を立てて撫でると冷たかった。もう片方のダランと伸びた足をあらためて見て、青白さ、貧相さに驚いた。
ふと、壁かけ時計が目に入り、思い出す。もう九時半をまわっているが、美津子がパートへ行く時間はとっくにすぎていた。私のせいで休みをとったのかと気づいて、げんなりした。今から行けと諭しても、もう遅いのだろう。
彼女は最近、パート先のスーパーへ行くのを楽しみにしている様子だった。
そして、そんな自分を認めまいとしている。その様が手にとるようによくわかる。スーパーの従業員の中に、気になる相手がいるらしかった。そう断定してしまうにはまだ早いかもしれないが、食卓の席でうれしそうに、仕入れ担当であるらしい男とのエピソードを、私に語って聞かせることがある。そして、相槌を打つ私の顔を見るなり我に帰って、息を飲むシーンもたびたびあった。
美津子が西瓜を運んできた。私は彼女の顔を見るなり言った。
「仕事は休んだのか」
「いいんですよ、もう辞めますから。給料があんまりよくないんです」
せいせいする、とばかりに笑んで、美津子はまた団扇を扇ぎはじめた。ゆるやかな風が私の顔を撫でる。
心地良かった。
「そろそろ、家を出ればどうだ」
と、私は唐突に言った。
自然に口をついて出た。自分自身でも驚くほどだったが、もっと早く言わなければならなかったのだと、いまはじめて気がついた。
「善い人がいるんだろう。もう陽一はいないんだから、ここにいる必要もないよ」
美津子は黙ったまま、庭を眺めている。表情は見えない。陽一が死んだころも、しばらくそうして私に顔を見せなかった。
彼女はふり向きもせず、顔を隠したまま言った。
「陽一さんが淋しがりますよ。あの人は私がいないと……」
「もう、陽一はいないんだよ」
私は極力、無感情に言った。
美津子はしばらく黙った後、部屋を出て行った。
ふたたび、室内に蝉の鳴き声がうるさく響き渡る。
私は蒲団のうえで、自分の細い片膝をかかえて、庭を見る。陽射しが強く、芝生が青い。喉がかわく。妻がいれば、梨でも食べたいと我がままを言って、困らせてやるところなのに。そう考えて溜息をつき、枕もとに置かれた西瓜に手を伸ばした。
しゃるりと口に含み、あまりの冷たさに顔をしかめて、皿に戻す。冷蔵庫で冷やされすぎていて、食べられなかった。昔、川に浸していたころは、こうではなかったとおもう。この冷やされ方は、あまりに人工的過ぎた。私はもっと生ぬるい西瓜が好きだった。
陽一の嗜好は私に似ていて、西瓜にしろ梨にしろ、生ぬるいものを好んで食べた。その方がより強く甘みを感じられて良いのだと、一丁前に言っていた。それが私からの受け売りであることを、彼は覚えていただろうか。
彼が子供だったころには、よく縁側に並んで坐り、一緒に生ぬるい西瓜を食べた。どちらがより遠くまで種を飛ばせるか競争した。陽一の種は一メートルほどしか飛ばず、私の種は、塀にあたった。その様子を後ろから見ていた妻に叱られて、私たちはまた大人しく食べ、妻は溜息をつきながらも、猫背なのがそっくりね、と笑っていた。
昔、種を飛ばしたそこには、いま、蝉の死骸が転がっている。
脛がかゆい。見やると、蚊に食われてプックリと膨れあがっていた。
再び庭に目をやって、巨大な向日葵に、改めてギョッとした。青い空を背景に、どこまでも聳えてゆくようだった。堂々とした姿勢の良さに、私は何故か怯え、身震いした。
おわり
|
|
|
|
コメント(2)
>ハルチルさん
お読みいただきまして、ありがとうございました。
主人公が体温を持っている、という感想は、私を喜ばせるものです。ありがとうございます。モデルは、いると言えばいるし、いないと言えばいないのですが、今作の主人公に限っては、います。
笠智衆です。
私はあの爺さんが大好きなのです。特に「東京物語」の笠智衆ですね。あの枯れた演技は垂涎でした。
でも、こうして明らかな誰かを想定して書くということは、珍しいです。
たぶん、どんな人物を書こうとしても、自分の分身であったり、今まで見聞きしてきた人々の断片でしかないんでしょうけど……人間なんて、基本的にはみんな同じようなもんだろう、と思っているので、そういう考えが、あるいは普遍性を生み出すこともあるのかもしれないと、たまに考えてみたりもします。
自分としては、もっと際立った、読者の心にもっと深く迫り来るような、目の覚めるような話を書いてみたいと思うんですけど……なかなかうまいこといかないですね。
お読みいただきまして、ありがとうございました。
主人公が体温を持っている、という感想は、私を喜ばせるものです。ありがとうございます。モデルは、いると言えばいるし、いないと言えばいないのですが、今作の主人公に限っては、います。
笠智衆です。
私はあの爺さんが大好きなのです。特に「東京物語」の笠智衆ですね。あの枯れた演技は垂涎でした。
でも、こうして明らかな誰かを想定して書くということは、珍しいです。
たぶん、どんな人物を書こうとしても、自分の分身であったり、今まで見聞きしてきた人々の断片でしかないんでしょうけど……人間なんて、基本的にはみんな同じようなもんだろう、と思っているので、そういう考えが、あるいは普遍性を生み出すこともあるのかもしれないと、たまに考えてみたりもします。
自分としては、もっと際立った、読者の心にもっと深く迫り来るような、目の覚めるような話を書いてみたいと思うんですけど……なかなかうまいこといかないですね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
4000字の世界 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
4000字の世界のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170698人