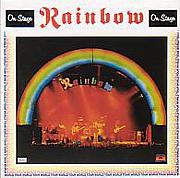|
|
|
|
コメント(65)
>で対策として思いつくのはコレなんだけど、なんとか使えないかなぁ。
う〜ん・・・どうかなぁ。
すぐには浮かばないけど・・・
一般にアーチ状の構造物では「アーチ橋」なんかが有名だけども
どれにも当てはまるのは、細めのものなら同じ大きさのアーチを
もう一つ使い、互いを筋交を使ってジョイントしているし、
別なケースでは奥行きをかなり多く取ることで「ねじれ」を回避
していると思われます。
現在のところ今回の虹アーチは櫛型の土台部分が躯体を兼ねること
で検討してますが、その部分の奥行きが無いゆえに「ねじれ」が
心配ってことなんです。
「天井にステイをとる」ことでどの程度回避可能か?
実際に組んでみないとその程度がどの位かが想像つかないんです。
本家のアーチも客席正面からの見えていない部分の奥側には
かなりの奥行きを使ってパイプが組み合わさってますからねぇ。
う〜ん・・・どうかなぁ。
すぐには浮かばないけど・・・
一般にアーチ状の構造物では「アーチ橋」なんかが有名だけども
どれにも当てはまるのは、細めのものなら同じ大きさのアーチを
もう一つ使い、互いを筋交を使ってジョイントしているし、
別なケースでは奥行きをかなり多く取ることで「ねじれ」を回避
していると思われます。
現在のところ今回の虹アーチは櫛型の土台部分が躯体を兼ねること
で検討してますが、その部分の奥行きが無いゆえに「ねじれ」が
心配ってことなんです。
「天井にステイをとる」ことでどの程度回避可能か?
実際に組んでみないとその程度がどの位かが想像つかないんです。
本家のアーチも客席正面からの見えていない部分の奥側には
かなりの奥行きを使ってパイプが組み合わさってますからねぇ。
まだトータルサイズは決定しておりませんが・・・
今日までの木工実験報告です。
当初、アーチを6分割案で考えておりましたが、色々やってみて
「5分割」にするのが良さそうなことが解ってきました。
やはりアーチのセンター部分でのジョイントは避けた方が無難かな(?)
という事と、ジョイント金具の♂♀のバランス、そして保管と運搬可能な
サイズを検討した結果であります。
3尺×6尺のベニア1枚から櫛型を2枚取る事ができましたので
これならベニアは3枚でイケます。
で、アーチの高さを2700ミリと仮定した実寸大の櫛型ベニヤを
試しに2枚切り出してみました。暇を見て補強材を入れてみますが、
実際に使うことを検討中の金具などを装着してみて強度なども
おいおい調べてみたいと思います。
それと発光体に電球もしくはLEDを使うにせよ、ほぼ完成形に
近いモノに装着した状態でのテストが必要になってくるでしょうから
なるべく早めに試作品になる(2枚だけですが)上記櫛型土台を
作ってしまおうと思います。
今日までの木工実験報告です。
当初、アーチを6分割案で考えておりましたが、色々やってみて
「5分割」にするのが良さそうなことが解ってきました。
やはりアーチのセンター部分でのジョイントは避けた方が無難かな(?)
という事と、ジョイント金具の♂♀のバランス、そして保管と運搬可能な
サイズを検討した結果であります。
3尺×6尺のベニア1枚から櫛型を2枚取る事ができましたので
これならベニアは3枚でイケます。
で、アーチの高さを2700ミリと仮定した実寸大の櫛型ベニヤを
試しに2枚切り出してみました。暇を見て補強材を入れてみますが、
実際に使うことを検討中の金具などを装着してみて強度なども
おいおい調べてみたいと思います。
それと発光体に電球もしくはLEDを使うにせよ、ほぼ完成形に
近いモノに装着した状態でのテストが必要になってくるでしょうから
なるべく早めに試作品になる(2枚だけですが)上記櫛型土台を
作ってしまおうと思います。
思いついたんで、忘れないうちに書き留めておきます。
本家の虹はステージを包み込むサイズ。
当然、アーチに照明が当たらないようにしてハレーションを防いでるはず。
でもこちらのは、複数の場所で使用可能にするとのことで、照明が当たることは免れない。
例えば聖地ならバックは黒いスクリーンなので、アーチの下地は黒にしとけば、照明が当たってもさほど目立たないけど、バックが黒じゃない場合は、虹が点灯してない時点では、もろに下地が見えるようになるです。
いつも点灯しとくようにしたとして、ハレーション(光位置が重なった部分は、とお互いの位置からだとなにも見えなくなる)は避けられない。
ましてハコの照明より強い発光体じゃないと、アーチの存在は薄れてしまうのではないかと、朝方思いました。
本家の虹はステージを包み込むサイズ。
当然、アーチに照明が当たらないようにしてハレーションを防いでるはず。
でもこちらのは、複数の場所で使用可能にするとのことで、照明が当たることは免れない。
例えば聖地ならバックは黒いスクリーンなので、アーチの下地は黒にしとけば、照明が当たってもさほど目立たないけど、バックが黒じゃない場合は、虹が点灯してない時点では、もろに下地が見えるようになるです。
いつも点灯しとくようにしたとして、ハレーション(光位置が重なった部分は、とお互いの位置からだとなにも見えなくなる)は避けられない。
ましてハコの照明より強い発光体じゃないと、アーチの存在は薄れてしまうのではないかと、朝方思いました。
呼ばれた。
そして、出遅れたw
基本「虹」は点灯が前提で仕込むものだと思います。
なぜなら、点灯していないとアーチの構造物で邪魔なものにしか見えないからです。
ビデオで見てあまり目立たない感じに見えているのは、カメラの絞りのレンジが狭いからであって、見えてないわけではないです。
それから、これは、ここに書いていいものかと思うのですが、当然一般の照明機材よりも明るいもの(ただし、これは光源が見えているのでさほどの光量は必要としないと思います。本家の方はふつうに電球使ってるので相当明るいですが…)であれば問題ないと思います。
光源を入れるボックス自体は黒の方がいいように思います。
本家も黒だし。
白でもいいけど、照明機材やバックは大概が黒なのがふつうなので。
ちなみに、これを使った仕込みの時には当然虹仕様で仕込みをしないとだめな感じです。
照明を虹前と奥で分けるとか、虹用に回路をあけておくとか。
そして、出遅れたw
基本「虹」は点灯が前提で仕込むものだと思います。
なぜなら、点灯していないとアーチの構造物で邪魔なものにしか見えないからです。
ビデオで見てあまり目立たない感じに見えているのは、カメラの絞りのレンジが狭いからであって、見えてないわけではないです。
それから、これは、ここに書いていいものかと思うのですが、当然一般の照明機材よりも明るいもの(ただし、これは光源が見えているのでさほどの光量は必要としないと思います。本家の方はふつうに電球使ってるので相当明るいですが…)であれば問題ないと思います。
光源を入れるボックス自体は黒の方がいいように思います。
本家も黒だし。
白でもいいけど、照明機材やバックは大概が黒なのがふつうなので。
ちなみに、これを使った仕込みの時には当然虹仕様で仕込みをしないとだめな感じです。
照明を虹前と奥で分けるとか、虹用に回路をあけておくとか。
>魔王さん
発光体を載せる土台(木工部分)の試作についてですが
電球かLEDを実際に装着し「その色味や明るさ、にじみを確認する為のモノ」
と割り切ってますんで、全アーチ分を丸ごと試作するのではなく
何分割かのうちの「一つか二つ」を試験的にこしらえる予定です。
ベニヤだけは切り出しました。
実物には4mmもしくは5.5mmの厚手のベニヤが必要とは思いますが、
今回はあくまで実験用なんで、ウチの仕事場に転がっていた薄手のベニヤと
残っていた廃材を利用してと考えてますから大丈夫ですよ。
それより、試作とはいえ電気部品のほうが圧倒的に出費が多そうなんで、
そこいらの方の整合を考えましょう!
一応、その試作品の寸法ですが
●アーチ外周・・・2700アール
●アーチ内周・・・2380アール
●虹幅・・・・・・320ミリ
あくまで試作ですんで、一応この寸法でベニヤは切り出してあります。
発光体をどのように配列して載せるのかが決まってはいないので
裏の補強材は出来るだけ電球等取り付けの邪魔にならぬよう、
内外周全部と両サイドだけ。
要はベニアの回りに這わせるだけにしておこうと思ってます。
あまりに強度が不足しているようなら、真ん中あたりに
縦に1本だけ通そうかと思ってます。
発光体を載せる土台(木工部分)の試作についてですが
電球かLEDを実際に装着し「その色味や明るさ、にじみを確認する為のモノ」
と割り切ってますんで、全アーチ分を丸ごと試作するのではなく
何分割かのうちの「一つか二つ」を試験的にこしらえる予定です。
ベニヤだけは切り出しました。
実物には4mmもしくは5.5mmの厚手のベニヤが必要とは思いますが、
今回はあくまで実験用なんで、ウチの仕事場に転がっていた薄手のベニヤと
残っていた廃材を利用してと考えてますから大丈夫ですよ。
それより、試作とはいえ電気部品のほうが圧倒的に出費が多そうなんで、
そこいらの方の整合を考えましょう!
一応、その試作品の寸法ですが
●アーチ外周・・・2700アール
●アーチ内周・・・2380アール
●虹幅・・・・・・320ミリ
あくまで試作ですんで、一応この寸法でベニヤは切り出してあります。
発光体をどのように配列して載せるのかが決まってはいないので
裏の補強材は出来るだけ電球等取り付けの邪魔にならぬよう、
内外周全部と両サイドだけ。
要はベニアの回りに這わせるだけにしておこうと思ってます。
あまりに強度が不足しているようなら、真ん中あたりに
縦に1本だけ通そうかと思ってます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
虹アーチ会 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-