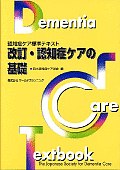認知症高齢者に対するフォーマルケア Part1?
A:医療・保健サービス
a.医療保険制度
・地域保険→市町村国民健康保険組合
・職域保険→自営業者保険→国民健康保険組合
→被用者保険→特定被用者保険→船員保険
→国家公務員共済組合
→地方公務員等共済組合
→私立学校教職員共済
一般被用者保険→健康保険→政府管掌健康保険
→組合管掌健康保険
<健康保険>
・民間企業の被用者を対象とする健康保険
大企業の従業員を対象とした⇒組合管掌健康保険
中小企業の従業員を対象に ⇒政府管掌健康保険
※政府管掌健康保険の保険者については
2008年10月から国とは切り離した全国単位の全国健康保険協会が
設立される。
・被用者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡、分娩に関して保険給付
・75歳未満の被保険者:3割負担
75歳以上の被保険者:老人保健法の適用を受けるため、1割負担
(一定以上の所得者は3割負担(2006年10月から))
・入院時の食事:標準負担額 1日あたり780円
但し、療養病床に入院する70歳以上の被保険者については
2006年10月から、原則食費・居住費が保険適用外。
・財源:保険料と国庫負担
<国民健康保険>
・自営業者や無職者など被用者の医療保険の適用を受けていない者を対象
市町村が運営する場合が大多数だが、同業種の自営業者等により
組織される国民健康保険組合もある。
・療養要する費用:3割負担
・入院時食事代自己負担は健康保険と同様。
・財源:保険料と公費(国、都道府県、市町村)
※退職者医療制度の財源は、
退職者の保険料と被用者保険制度からの拠出金で賄われる。
●医療保険における高齢者の取扱い
75歳以上になると、老人保健法に基づく医療の対象となる。
2008年度以降は、75歳以上の後期高齢者のための独立した医療制度が
創設される。
b.老人保健制度(1982年交付、翌年2月施行)
・医療等・・・75歳以上の者及び65歳から75歳未満で
市町村長に一定の障害があると認定された者
・医療等以外の保健事業・・・40歳以上の者を対象
・医療等
(医療、入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費、
移送費、高額医療費)
老人保健法に基づく医療の給付を受けた場合
原則として、かかった医療費の1割負担
一定所得者(課税対象額が145万円以上の者)は3割負担
・医療等以外の保健事業
(健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、
訪問指導)
原則として自己負担はないが、健康診査については
その費用の一部が受診者が負担することがある。
※2008年度から
糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査と保健指導は
(高齢者の医療の確保に関する法律)のもとで実施が義務付けられる。
それ以外の保健事業については、
現行の老人保健法の規定を(健康増進法)に移行し、市町村が実施する。
A:医療・保健サービス
a.医療保険制度
・地域保険→市町村国民健康保険組合
・職域保険→自営業者保険→国民健康保険組合
→被用者保険→特定被用者保険→船員保険
→国家公務員共済組合
→地方公務員等共済組合
→私立学校教職員共済
一般被用者保険→健康保険→政府管掌健康保険
→組合管掌健康保険
<健康保険>
・民間企業の被用者を対象とする健康保険
大企業の従業員を対象とした⇒組合管掌健康保険
中小企業の従業員を対象に ⇒政府管掌健康保険
※政府管掌健康保険の保険者については
2008年10月から国とは切り離した全国単位の全国健康保険協会が
設立される。
・被用者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡、分娩に関して保険給付
・75歳未満の被保険者:3割負担
75歳以上の被保険者:老人保健法の適用を受けるため、1割負担
(一定以上の所得者は3割負担(2006年10月から))
・入院時の食事:標準負担額 1日あたり780円
但し、療養病床に入院する70歳以上の被保険者については
2006年10月から、原則食費・居住費が保険適用外。
・財源:保険料と国庫負担
<国民健康保険>
・自営業者や無職者など被用者の医療保険の適用を受けていない者を対象
市町村が運営する場合が大多数だが、同業種の自営業者等により
組織される国民健康保険組合もある。
・療養要する費用:3割負担
・入院時食事代自己負担は健康保険と同様。
・財源:保険料と公費(国、都道府県、市町村)
※退職者医療制度の財源は、
退職者の保険料と被用者保険制度からの拠出金で賄われる。
●医療保険における高齢者の取扱い
75歳以上になると、老人保健法に基づく医療の対象となる。
2008年度以降は、75歳以上の後期高齢者のための独立した医療制度が
創設される。
b.老人保健制度(1982年交付、翌年2月施行)
・医療等・・・75歳以上の者及び65歳から75歳未満で
市町村長に一定の障害があると認定された者
・医療等以外の保健事業・・・40歳以上の者を対象
・医療等
(医療、入院時食事療養費、特定療養費、老人訪問看護療養費、
移送費、高額医療費)
老人保健法に基づく医療の給付を受けた場合
原則として、かかった医療費の1割負担
一定所得者(課税対象額が145万円以上の者)は3割負担
・医療等以外の保健事業
(健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、
訪問指導)
原則として自己負担はないが、健康診査については
その費用の一部が受診者が負担することがある。
※2008年度から
糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査と保健指導は
(高齢者の医療の確保に関する法律)のもとで実施が義務付けられる。
それ以外の保健事業については、
現行の老人保健法の規定を(健康増進法)に移行し、市町村が実施する。
|
|
|
|
コメント(11)
認知症高齢者に対するフォーマルケア Part1?
B:介護サービス
1989年 ゴールドプラン策定
1990年 福祉関係八法の改正…市町村への一元化、在宅サービスの重視
1994年 新ゴールドプラン策定
1997年 介護保険法成立
1999年 ゴールドプラン21策定・・・介護サービスと介護予防サービス、
介護サービスの質、利用環境の整備
2000年 介護保険法施行
2003年 2015年の高齢者介護
〜高齢者の尊厳の保持〜
・介護予防・リハビリテーションの充実
・生活の継続性を維持するための新しい介護サービス体系
・新しいケアモデルの確立・認知症高齢者ケア
・サービスの質の確保と向上
2006年 改正介護保険法施行・・・介護予防重視、
地域密着型サービスの創設
<介護保険制度>
保険者 :市町村(特別区を含む)
被保険者 :第1号(65歳以上の者)
第2号(40〜64歳のもので医療保険加入者)
費用負担 :在宅サービス(国25%、都道府県・市町村が各12.5%)
施設サービス(国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%)
要介護・要支援認定:介護認定審査会(市町村)
認定の更新:有効期限日の60日以内に申請)
認定の有効期間:標準6ヵ月、更新認定は標準12ヶ月)
保険給付 :要支援⇒介護予防サービル
要介護⇒介護サービス(施設サービスを含む)
費用の9割が保険給付、残りの1割が自己負担)
B:介護サービス
1989年 ゴールドプラン策定
1990年 福祉関係八法の改正…市町村への一元化、在宅サービスの重視
1994年 新ゴールドプラン策定
1997年 介護保険法成立
1999年 ゴールドプラン21策定・・・介護サービスと介護予防サービス、
介護サービスの質、利用環境の整備
2000年 介護保険法施行
2003年 2015年の高齢者介護
〜高齢者の尊厳の保持〜
・介護予防・リハビリテーションの充実
・生活の継続性を維持するための新しい介護サービス体系
・新しいケアモデルの確立・認知症高齢者ケア
・サービスの質の確保と向上
2006年 改正介護保険法施行・・・介護予防重視、
地域密着型サービスの創設
<介護保険制度>
保険者 :市町村(特別区を含む)
被保険者 :第1号(65歳以上の者)
第2号(40〜64歳のもので医療保険加入者)
費用負担 :在宅サービス(国25%、都道府県・市町村が各12.5%)
施設サービス(国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%)
要介護・要支援認定:介護認定審査会(市町村)
認定の更新:有効期限日の60日以内に申請)
認定の有効期間:標準6ヵ月、更新認定は標準12ヶ月)
保険給付 :要支援⇒介護予防サービル
要介護⇒介護サービス(施設サービスを含む)
費用の9割が保険給付、残りの1割が自己負担)
認知症高齢者に対するフォーマルケア Part2
A:地域密着型サービス (2006年4月より新設)
市町村は生活に密着した小地域を設定し、生活圏域ごとに必要なサービス
量を計画する。市町村が事業所の指定を行う。
a.夜間対応型訪問介護
b.認知症対応型通所介護(定員12名)
c.小規模多機能型居宅介護(定員25名)
通所サービスを中心として、訪問、泊まりを組み合わせる)
d.認知症対応型共同生活介護(2006年4月から地域密着型サービスに位置付)
5〜9名を定員とし、1ユニット。居室は個室。2ユニットまで。
e.地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29名以下の介護型有料老人ホーム等に入居して介護を受ける
f.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員29名以下の特別養護老人ホーム等に入所して介護を受ける
B:介護予防サービスと地域支援事業
要支援認定・・・介護予防サービス
自立・・・・・・地域支援事業による予防給付を市町村が一体的に運営
a.介護予防サービス
通所サービスを中心として実施される。
運動器の機能向上、口腔機能の向上、栄養改善など
b.地域包括支援センター
・介護予防マネジメント
・総合相談
・包括的・継続的マネジメント
・権利擁護事業
※認知症高齢者に関連する高齢者保健福祉施策
・認知症介護研修事業
・身体拘束ゼロ作戦
・認知症を知り地域を作る10ヵ年構想
・認知症地域医療支援事業
C:認知症高齢者のための小規模多機能型サービス
2006年4月から制度化され、日常生活圏に1ヶ所ずつ整備されることになった
通い、泊まり、居住、訪問を組み合わせたケア
小規模多機能型サービス拠点の計画に際してのポイント
・在宅を支える仕組み
概ね、25人以下の登録利用者のうち
日中 15人以下の通い(10人以上が在宅で昼を過ごす)
夜間 5〜9人が泊まり(20〜16人が在宅で夜を過ごす)
・安心で見当の付けやすい、住まいに近い空間
家庭に近いスケールを雰囲気を有した安心した空間を用意する
・顔の見えるなじみの関係性
小規模な定員の設定で、なじみの関係を築きやすくする
・在宅に近い姿勢
在宅に近い平座位の導入、靴を脱ぐ生活
・動きを作る
生活動作を通じて介護予防を図る視点も重要
・昼夜の利用者数の変化への対応
最大15人使う昼と最小3人となる夜の差を考慮する
A:地域密着型サービス (2006年4月より新設)
市町村は生活に密着した小地域を設定し、生活圏域ごとに必要なサービス
量を計画する。市町村が事業所の指定を行う。
a.夜間対応型訪問介護
b.認知症対応型通所介護(定員12名)
c.小規模多機能型居宅介護(定員25名)
通所サービスを中心として、訪問、泊まりを組み合わせる)
d.認知症対応型共同生活介護(2006年4月から地域密着型サービスに位置付)
5〜9名を定員とし、1ユニット。居室は個室。2ユニットまで。
e.地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29名以下の介護型有料老人ホーム等に入居して介護を受ける
f.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員29名以下の特別養護老人ホーム等に入所して介護を受ける
B:介護予防サービスと地域支援事業
要支援認定・・・介護予防サービス
自立・・・・・・地域支援事業による予防給付を市町村が一体的に運営
a.介護予防サービス
通所サービスを中心として実施される。
運動器の機能向上、口腔機能の向上、栄養改善など
b.地域包括支援センター
・介護予防マネジメント
・総合相談
・包括的・継続的マネジメント
・権利擁護事業
※認知症高齢者に関連する高齢者保健福祉施策
・認知症介護研修事業
・身体拘束ゼロ作戦
・認知症を知り地域を作る10ヵ年構想
・認知症地域医療支援事業
C:認知症高齢者のための小規模多機能型サービス
2006年4月から制度化され、日常生活圏に1ヶ所ずつ整備されることになった
通い、泊まり、居住、訪問を組み合わせたケア
小規模多機能型サービス拠点の計画に際してのポイント
・在宅を支える仕組み
概ね、25人以下の登録利用者のうち
日中 15人以下の通い(10人以上が在宅で昼を過ごす)
夜間 5〜9人が泊まり(20〜16人が在宅で夜を過ごす)
・安心で見当の付けやすい、住まいに近い空間
家庭に近いスケールを雰囲気を有した安心した空間を用意する
・顔の見えるなじみの関係性
小規模な定員の設定で、なじみの関係を築きやすくする
・在宅に近い姿勢
在宅に近い平座位の導入、靴を脱ぐ生活
・動きを作る
生活動作を通じて介護予防を図る視点も重要
・昼夜の利用者数の変化への対応
最大15人使う昼と最小3人となる夜の差を考慮する
所得保障
A:公的年金制度
a.国民年金…日本国内に住む20歳以上60歳未満の者、全員加入。
第一号被保険者…自営業者、学生、無職の者
第二号被保険者…サラリーマンなど
第三号被保険者…第二号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の者
・老齢基礎年金…65歳から支給
20〜60歳までの間に、最低25年の加入
満額(794500円)を受給するためには40年の加入が必要
・保険料…………第一号被保険者:月額13580円
※法定免除…障害年金や生活保護受給者
※申請免除…所得などに応じ、都道府県知事に申請する
(全額・1/4・1/2・3/4)
・老齢厚生年金…民間被用者の場合、65歳から老齢基礎年金と併せて受給
・障害年金………一定の障害を持った場合に支給される
・遺族年金………国民年金に加入中あるいは加入していた者が死亡した場合
その者に生計を維持されていた18歳未満の子または
18歳未満の子を持つ妻に対して遺族基礎年金が支給される
※被用者の場合は、遺族厚生年金がある
・子のある妻や子の場合
:遺族基礎年金と併せて支給
・子のない妻や父、父母、孫、祖父母の場合
:遺族厚生年金のみ支給
B:生活保護制度
8種類:(生活・住宅・教育・医療・介護・生業・葬祭・出産)扶助
・生活扶助…衣食など基本生活のニードを充足させるための扶助
個人の年齢別の基準と世帯人数による基準を組合せて算定する
母子加算、障害者加算などがある
地域格差を考慮して大都市から地方まで6つに分けた基準額
・介護保険料⇒生活扶助に上乗せして支給される
・介護サービスを受けた場合⇒1割の自己負担分を介護扶助から支給
C:社会手当
認知症に関連する社会手当として特別障害者手当がある
・特別障害者手当:精神または身体に著しく重度の障害を有するために
日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の
20歳以上の者に対して、月額約26000円支給される
(施設入所者が対象外)
A:公的年金制度
a.国民年金…日本国内に住む20歳以上60歳未満の者、全員加入。
第一号被保険者…自営業者、学生、無職の者
第二号被保険者…サラリーマンなど
第三号被保険者…第二号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の者
・老齢基礎年金…65歳から支給
20〜60歳までの間に、最低25年の加入
満額(794500円)を受給するためには40年の加入が必要
・保険料…………第一号被保険者:月額13580円
※法定免除…障害年金や生活保護受給者
※申請免除…所得などに応じ、都道府県知事に申請する
(全額・1/4・1/2・3/4)
・老齢厚生年金…民間被用者の場合、65歳から老齢基礎年金と併せて受給
・障害年金………一定の障害を持った場合に支給される
・遺族年金………国民年金に加入中あるいは加入していた者が死亡した場合
その者に生計を維持されていた18歳未満の子または
18歳未満の子を持つ妻に対して遺族基礎年金が支給される
※被用者の場合は、遺族厚生年金がある
・子のある妻や子の場合
:遺族基礎年金と併せて支給
・子のない妻や父、父母、孫、祖父母の場合
:遺族厚生年金のみ支給
B:生活保護制度
8種類:(生活・住宅・教育・医療・介護・生業・葬祭・出産)扶助
・生活扶助…衣食など基本生活のニードを充足させるための扶助
個人の年齢別の基準と世帯人数による基準を組合せて算定する
母子加算、障害者加算などがある
地域格差を考慮して大都市から地方まで6つに分けた基準額
・介護保険料⇒生活扶助に上乗せして支給される
・介護サービスを受けた場合⇒1割の自己負担分を介護扶助から支給
C:社会手当
認知症に関連する社会手当として特別障害者手当がある
・特別障害者手当:精神または身体に著しく重度の障害を有するために
日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の
20歳以上の者に対して、月額約26000円支給される
(施設入所者が対象外)
権利擁護?
A:成年後見制度(2000年4月)
判断力の不十分な、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者を保護し
また、支援するための制度
財産管理、身上監護についての契約を行う
a.後見・・・判断能力が欠く常況
b.補佐・・・判断能力が著しく不十分
c.補助・・・判断能力が不十分
※補助の類型はこれまで対象とならなかった経度の精神上の障害により
判断能力が不十分な人のために新たに出来た類型である
d.任意後見制度
本人が判断能力の十分あるうちに、前もって代理人である任意後見人に
財産管理や身上監護の事務などについて代理権を与える任意後見契約を
公正証書で結んでおく
任意後見人には、公正証書の契約で定めた代理権のみが与えられる
本人の判断能力が不十分になった場合に
家庭裁判所に任意後見監督人の選出を申立てる
B:福祉サービス利用援助事業
都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体
第2種社会福祉事業(社会福祉法)
福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類等の預かり等を行う
判断能力が不十分な認知症のある人、知的障害者、精神障害者など
※この事業の契約内容に関して、
判断しうる能力を有していると認められることが必要
<援助の流れ>
・相談受付
基幹的社会福祉協議会の専門員が訪問相談を実施
・初期相談
専門員による事業の説明、情況把握
・契約締結能力の調査・関係調査
契約締結判定ガイドラインに基づいて調査を行う
・契約書・支援計画
・契約締結
・援助開始
支援計画に基づいて生活支援員により開始される
・支援計画の評価
契約締結後3ヵ月を経た時点で評価を行う
・契約終了
本人が解約を申し出た時、本人が施設入所、長期入院、転居
した時は、契約を終了する
A:成年後見制度(2000年4月)
判断力の不十分な、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者を保護し
また、支援するための制度
財産管理、身上監護についての契約を行う
a.後見・・・判断能力が欠く常況
b.補佐・・・判断能力が著しく不十分
c.補助・・・判断能力が不十分
※補助の類型はこれまで対象とならなかった経度の精神上の障害により
判断能力が不十分な人のために新たに出来た類型である
d.任意後見制度
本人が判断能力の十分あるうちに、前もって代理人である任意後見人に
財産管理や身上監護の事務などについて代理権を与える任意後見契約を
公正証書で結んでおく
任意後見人には、公正証書の契約で定めた代理権のみが与えられる
本人の判断能力が不十分になった場合に
家庭裁判所に任意後見監督人の選出を申立てる
B:福祉サービス利用援助事業
都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体
第2種社会福祉事業(社会福祉法)
福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類等の預かり等を行う
判断能力が不十分な認知症のある人、知的障害者、精神障害者など
※この事業の契約内容に関して、
判断しうる能力を有していると認められることが必要
<援助の流れ>
・相談受付
基幹的社会福祉協議会の専門員が訪問相談を実施
・初期相談
専門員による事業の説明、情況把握
・契約締結能力の調査・関係調査
契約締結判定ガイドラインに基づいて調査を行う
・契約書・支援計画
・契約締結
・援助開始
支援計画に基づいて生活支援員により開始される
・支援計画の評価
契約締結後3ヵ月を経た時点で評価を行う
・契約終了
本人が解約を申し出た時、本人が施設入所、長期入院、転居
した時は、契約を終了する
権利擁護?
C:悪徳商法
・マルチ商法(クーリングオフ 20日間)
・催眠商法(クーリングオフ 8日間)
・点検商法(クーリングオフ 8日間)
※クーリングオフ:契約書面を受け取った日から8日間以内に、
書面で解約意思を通知することによって無条件で
解約することができる
※契約の取消し:クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも
不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した時は、
契約の取消しができる
(誤認に気づいた時、または迷惑行為から 6ヵ月以内)
(契約の時から 5年以内)
D:高齢者虐待防止法(2006年4月)
国際比較
・日本………高齢者虐待防止法(65歳以上の高齢者を対象)
介護保険法、老人福祉法、成年後見制度
・アメリカ…連邦法 92年改正連邦高齢者法(高齢者を対象)
74年改正社会保障法
州法 成人保護サービス法(障害のある成人と高齢者を対象)
・ドイツ……98年改正世話法
(18歳以上で自分のことが全部または一部処理できない者を対象)
・スウェーデン
…99年社会サービス法
(高齢者・障害者で介護ケアを受けている者を対象)
具体的な支援ネットワーク
・民生委員、地域住民、社会福祉協議会等からなる
⇒早期発見・見守りネットワーク
・介護保険サービス事業者からなる
⇒医療福祉サービス介入ネットワーク
・行政機関、法律関係者、医療機関等からなる
⇒医療専門機関介入支援ネットワーク
虐待の種類
・身体的虐待
・介護・世話の放棄
・心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待
立入り調査…市町村長また市町村直営の地域包括支援センターに限られる
必要があると認められる時は、警察署の署長に援助を要請できる
老人福祉法による緊急措置
緊急ショートステイ、一時入院、虐待家族との一時分離
市町村は、このような虐待を受けた高齢者について老人福祉法の
規定による措置を取るために必要の居室を確保する
E:介護サービスと品質評価
・自己評価
・第三者評価(ISO9001)
・利用者評価
C:悪徳商法
・マルチ商法(クーリングオフ 20日間)
・催眠商法(クーリングオフ 8日間)
・点検商法(クーリングオフ 8日間)
※クーリングオフ:契約書面を受け取った日から8日間以内に、
書面で解約意思を通知することによって無条件で
解約することができる
※契約の取消し:クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも
不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した時は、
契約の取消しができる
(誤認に気づいた時、または迷惑行為から 6ヵ月以内)
(契約の時から 5年以内)
D:高齢者虐待防止法(2006年4月)
国際比較
・日本………高齢者虐待防止法(65歳以上の高齢者を対象)
介護保険法、老人福祉法、成年後見制度
・アメリカ…連邦法 92年改正連邦高齢者法(高齢者を対象)
74年改正社会保障法
州法 成人保護サービス法(障害のある成人と高齢者を対象)
・ドイツ……98年改正世話法
(18歳以上で自分のことが全部または一部処理できない者を対象)
・スウェーデン
…99年社会サービス法
(高齢者・障害者で介護ケアを受けている者を対象)
具体的な支援ネットワーク
・民生委員、地域住民、社会福祉協議会等からなる
⇒早期発見・見守りネットワーク
・介護保険サービス事業者からなる
⇒医療福祉サービス介入ネットワーク
・行政機関、法律関係者、医療機関等からなる
⇒医療専門機関介入支援ネットワーク
虐待の種類
・身体的虐待
・介護・世話の放棄
・心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待
立入り調査…市町村長また市町村直営の地域包括支援センターに限られる
必要があると認められる時は、警察署の署長に援助を要請できる
老人福祉法による緊急措置
緊急ショートステイ、一時入院、虐待家族との一時分離
市町村は、このような虐待を受けた高齢者について老人福祉法の
規定による措置を取るために必要の居室を確保する
E:介護サービスと品質評価
・自己評価
・第三者評価(ISO9001)
・利用者評価
認知症高齢者に対するインフォーマルケア?
A:家族
認知症高齢者の約7割が居宅で介護されている
主介護者の8割は同居者(東京都)
配偶者 :3割
娘 :3割弱
息子の嫁:2割強
家族介護の客観的困難に関わる要因
a.介護される側の要因
身体の活動性、特に歩行可能な程度
夜間介護の必要性
意思疎通の程度
行動障害の程度
他の要介護者、要保護者の有無
b.介護者側の要因
年齢
健康状態
就労状態
他の資源の活用可能性
B:近隣
近隣が認知症高齢者のケアに果たす役割
a.直接的には、家族がいない場合、認知症であることに気づくのは
近隣が最初である
b.間接的には、できるだけ家族を支えていくことである
C:友人
これまでの所、友人による認知症高齢者の介護は多く行われていない
それよりもむしろ、友人には家族介護者を支える役割が期待できる
D:家族会 社団法人認知症の人と家族の会の場合
活動(25年余りの間、様々な取組みをしてきた)
a.集い
全国41都道府県にある支部で定期開催している(多くは毎月)
・苦労を理解しあう
・他の人の介護の方法を知ることで、自分にあった介護の方法を
見つけることができる
・介護に関わる様々な情報交換や学習の場ともなる
b.相談
電話相談なども受けている
c.会報
集いと相談とに加え、家族会の活動の三本柱の一つ
会報の編集理念(介護家族の精神的な支援と情報提供)
d.デイサービスなどの支援
のちの認知症高齢者のみを対象としたE型デイサービスのモデル
e.認知症の人と家族への援助をすすめる全国研究集会
1995年京都で開催 毎年、全国各地で開催されている
f.調査活動
家族の会は、ほぼ毎年、主に会員を対象とした調査活動を行っている
ここ20年の大きな変化は、介護の長期化
男性介護者の増加
社会的サービス利用の増加
g.要望活動
その結果として・若年期認知症の人が老人保健施設を利用できる事
・高齢期認知症が介護保険の対象者となり
若年期認知症も介護保険の特定疾患となった事
・介護保険施設での身体拘束が禁止された事
h.啓発活動
国際アルツハイマー病協会の全世界的な啓発活動
毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと提起した
A:家族
認知症高齢者の約7割が居宅で介護されている
主介護者の8割は同居者(東京都)
配偶者 :3割
娘 :3割弱
息子の嫁:2割強
家族介護の客観的困難に関わる要因
a.介護される側の要因
身体の活動性、特に歩行可能な程度
夜間介護の必要性
意思疎通の程度
行動障害の程度
他の要介護者、要保護者の有無
b.介護者側の要因
年齢
健康状態
就労状態
他の資源の活用可能性
B:近隣
近隣が認知症高齢者のケアに果たす役割
a.直接的には、家族がいない場合、認知症であることに気づくのは
近隣が最初である
b.間接的には、できるだけ家族を支えていくことである
C:友人
これまでの所、友人による認知症高齢者の介護は多く行われていない
それよりもむしろ、友人には家族介護者を支える役割が期待できる
D:家族会 社団法人認知症の人と家族の会の場合
活動(25年余りの間、様々な取組みをしてきた)
a.集い
全国41都道府県にある支部で定期開催している(多くは毎月)
・苦労を理解しあう
・他の人の介護の方法を知ることで、自分にあった介護の方法を
見つけることができる
・介護に関わる様々な情報交換や学習の場ともなる
b.相談
電話相談なども受けている
c.会報
集いと相談とに加え、家族会の活動の三本柱の一つ
会報の編集理念(介護家族の精神的な支援と情報提供)
d.デイサービスなどの支援
のちの認知症高齢者のみを対象としたE型デイサービスのモデル
e.認知症の人と家族への援助をすすめる全国研究集会
1995年京都で開催 毎年、全国各地で開催されている
f.調査活動
家族の会は、ほぼ毎年、主に会員を対象とした調査活動を行っている
ここ20年の大きな変化は、介護の長期化
男性介護者の増加
社会的サービス利用の増加
g.要望活動
その結果として・若年期認知症の人が老人保健施設を利用できる事
・高齢期認知症が介護保険の対象者となり
若年期認知症も介護保険の特定疾患となった事
・介護保険施設での身体拘束が禁止された事
h.啓発活動
国際アルツハイマー病協会の全世界的な啓発活動
毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと提起した
認知症高齢者に対するインフォーマルケア?
E:民生委員・ボランティア
a.民生委員:民生委員法により規定。任期3年。給与は支給されない。
市町村の民生委員推薦会により推薦した者について
都道府県知事は、都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて
厚生労働大臣に推薦し、
厚生労働大臣が委嘱を行う。
<職務>
・住民の生活状態の把握
・援助を必要とするものに対する生活に関する相談・援助
・福祉サービスの適切な利用に必要な情報提供など
・社会福祉を目的とする事業の経営者または活動を主なう者との連携
・福祉事務所など関係行政機関の業務への協力
b.ボランティア
<ボランティア活動の概念>
・活動する側に関わる性格:自発性、主体性
・活動の目的に関わる性格:社会性、連帯性、利他性、福祉性、公共性
・報酬に関わる性格 :無償性、無給性
※ボランティア活動が評価され定着したのは
1995年阪神淡路大震災におけるボランティア活動である
F:ソーシャルサポートの役割
a.配偶者
:非常に重要なソーシャルサポート提供者である
単に身体的介護の提供者となるだけでなく、情緒的サポートや
経済的サポートの提供者となる事が多い
b.子ども
:重要なソーシャルサポート提供者であるが、配偶者と異なり
必ずしも身体的介護の提供者となる必要性がない場合もあり
情緒的サポートや経済的サポート提供者にとどまる場合もある
配偶者に次ぐ、重要な役割を果たしている
c.近隣及び友人
:身体的、経済的サポートを提供する担い手となることは少ない
話し明いてなどの情緒的なサポートの提供者となる事が多い
d.民生委員・ボランティア
・ボランティア:家族、近隣、友人とは異なり、認知症高齢者との
接点や共有できる情報が少なく、どちらかと言えば
第三者的な存在である
・民生委員 :近隣よりも公的な立場としてとらえる
支援ネットワークづくりの担い手の一人になる事が
できる
E:民生委員・ボランティア
a.民生委員:民生委員法により規定。任期3年。給与は支給されない。
市町村の民生委員推薦会により推薦した者について
都道府県知事は、都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて
厚生労働大臣に推薦し、
厚生労働大臣が委嘱を行う。
<職務>
・住民の生活状態の把握
・援助を必要とするものに対する生活に関する相談・援助
・福祉サービスの適切な利用に必要な情報提供など
・社会福祉を目的とする事業の経営者または活動を主なう者との連携
・福祉事務所など関係行政機関の業務への協力
b.ボランティア
<ボランティア活動の概念>
・活動する側に関わる性格:自発性、主体性
・活動の目的に関わる性格:社会性、連帯性、利他性、福祉性、公共性
・報酬に関わる性格 :無償性、無給性
※ボランティア活動が評価され定着したのは
1995年阪神淡路大震災におけるボランティア活動である
F:ソーシャルサポートの役割
a.配偶者
:非常に重要なソーシャルサポート提供者である
単に身体的介護の提供者となるだけでなく、情緒的サポートや
経済的サポートの提供者となる事が多い
b.子ども
:重要なソーシャルサポート提供者であるが、配偶者と異なり
必ずしも身体的介護の提供者となる必要性がない場合もあり
情緒的サポートや経済的サポート提供者にとどまる場合もある
配偶者に次ぐ、重要な役割を果たしている
c.近隣及び友人
:身体的、経済的サポートを提供する担い手となることは少ない
話し明いてなどの情緒的なサポートの提供者となる事が多い
d.民生委員・ボランティア
・ボランティア:家族、近隣、友人とは異なり、認知症高齢者との
接点や共有できる情報が少なく、どちらかと言えば
第三者的な存在である
・民生委員 :近隣よりも公的な立場としてとらえる
支援ネットワークづくりの担い手の一人になる事が
できる
認知症の相談窓口
A:老人性認知症センター(都道府県が指定)
保健医療・福祉期間と連携を図りながら
専門医療相談、鑑別診断・治療方針の選定、夜間や休日の救急対応を行う
認知症に関する情報提供を行うこともある
精神科を有する総合病院や精神科病院などに設置される
B:医療機関
大学附属病院や総合病院など認知症高齢者の相談窓口を開設している
もの忘れ外来を開設しているところもある
C:保健所・保健センター
保健所においては老人精神保健相談指導事業が行われている
精神保健福祉相談員が対応したり、精神保健専任保健師を配置している
認知症疾患の予防・普及啓発、医療機関の紹介も行われている
D:精神保健福祉センター
全国の都道府県に設置
保健所の技術援助をはじめ、福祉事務所その他関係行政機関等と連携し
相談・指導のうち、複雑または困難なケースを扱う
E:地域包括支援センター
改正介護保険法において地域支援事業が示され、総合相談・支援事業を
行う機関として地域包括支援センターが位置づけられた
F:在宅介護支援センター
実施主体は市町村であるが、地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、
民間事業者などに委託することができる
G:市町村の保健福祉担当課、福祉事務所、社会福祉協議会
H:高齢者総合相談センター(シルバー110番)
都道府県に設置
法律・税金・年金・保険・健康・疾病などの心配事や悩み事、その他の
生活上の様々な問題についての相談を受ける中で、認知症高齢者について
相談も受ける
I:認知症の人と家族の会
認知症に関わる当事者を中心とした全国組織
国際アルツハイマー病協会(ADI)にも加盟している
J:その他の相談機関
財団法人ぼけ予防協会(無料の電話相談)
国際長寿センター
A:老人性認知症センター(都道府県が指定)
保健医療・福祉期間と連携を図りながら
専門医療相談、鑑別診断・治療方針の選定、夜間や休日の救急対応を行う
認知症に関する情報提供を行うこともある
精神科を有する総合病院や精神科病院などに設置される
B:医療機関
大学附属病院や総合病院など認知症高齢者の相談窓口を開設している
もの忘れ外来を開設しているところもある
C:保健所・保健センター
保健所においては老人精神保健相談指導事業が行われている
精神保健福祉相談員が対応したり、精神保健専任保健師を配置している
認知症疾患の予防・普及啓発、医療機関の紹介も行われている
D:精神保健福祉センター
全国の都道府県に設置
保健所の技術援助をはじめ、福祉事務所その他関係行政機関等と連携し
相談・指導のうち、複雑または困難なケースを扱う
E:地域包括支援センター
改正介護保険法において地域支援事業が示され、総合相談・支援事業を
行う機関として地域包括支援センターが位置づけられた
F:在宅介護支援センター
実施主体は市町村であるが、地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、
民間事業者などに委託することができる
G:市町村の保健福祉担当課、福祉事務所、社会福祉協議会
H:高齢者総合相談センター(シルバー110番)
都道府県に設置
法律・税金・年金・保険・健康・疾病などの心配事や悩み事、その他の
生活上の様々な問題についての相談を受ける中で、認知症高齢者について
相談も受ける
I:認知症の人と家族の会
認知症に関わる当事者を中心とした全国組織
国際アルツハイマー病協会(ADI)にも加盟している
J:その他の相談機関
財団法人ぼけ予防協会(無料の電話相談)
国際長寿センター
地域で認知症高齢者を支えるために
認知症高齢者を支えるための地域ケアシステム
A:認知症の早期発見の意義
治療可能な認知症疾患の鑑別診断
(18.5%にアルツハイマー型認知症以外の治療可能な原因が示された)
65歳以上の認知症高齢者の半数以上はATDである
ATDであれば、今は治療薬を用いることができる(アリセプト)
B:早期発見の阻害因子
a.家族の認識の問題
本人お何らかの日常生活上の変化に家族が気づき
専門的な相談機関及び医療機関を訪れた家族の割合は1割
b.かかりつけ医の認識
かかりつけ医の認知症に関する認識も必ずしも十分ではない
もの忘れが顕著であっても歳のせいと片付けられてしまう
認知症は治らない病気だからといって聞いてももらえない
※身近な人の認知症の症状を相談した相手⇒かかりつけ医が26.6%である
厚生労働省はかかりつけ医が参画した早期からの認知症高齢者支援体制を策定し
かかりつけ医に対する研修プログラムを含めた認知症対策総合支援事業を行う
ケアマネジメント
ケアマネジメントは利用者の自立を支援し生活の質を高めていくことを目指す
<ケアマネジメントの過程>
a.入口…ケースの発見、スクリーニング、インテークが行われる
b.アセスメント…利用者の社会生活上の全体的な観点から捉え、
諸々の問題点やニーズを査定する
c.ケース目標の設定とケアプランの作成
d.ケアプラン実施
e.モニター及びフォローアップ
f.再アセスメント
認知症高齢者に対する留意点
高齢者本人の感じているフェルトニーズと
専門家が考えるプロフェッショナルニーズのすり合わせが難しい
これは高齢者が意思表示を十分出来ないからである
a.できる限り本人からケアプランについての了解を取ることである
b.本人の身近な理解者と一緒にケアプランを作ることもある
c.地域福祉権利擁護事業での生活支援員とともにケアプランを作っていく
d.他職種の専門職とのケアカンファレンスの中で、相互のディスカッションに
よる複合的な視点で、的確なニーズやその解決方法を得ていく
e.職場の上司とスーパービジョンを受けてケアプランを作成し、実施する
認知症高齢者を支えるための地域ケアシステム
A:認知症の早期発見の意義
治療可能な認知症疾患の鑑別診断
(18.5%にアルツハイマー型認知症以外の治療可能な原因が示された)
65歳以上の認知症高齢者の半数以上はATDである
ATDであれば、今は治療薬を用いることができる(アリセプト)
B:早期発見の阻害因子
a.家族の認識の問題
本人お何らかの日常生活上の変化に家族が気づき
専門的な相談機関及び医療機関を訪れた家族の割合は1割
b.かかりつけ医の認識
かかりつけ医の認知症に関する認識も必ずしも十分ではない
もの忘れが顕著であっても歳のせいと片付けられてしまう
認知症は治らない病気だからといって聞いてももらえない
※身近な人の認知症の症状を相談した相手⇒かかりつけ医が26.6%である
厚生労働省はかかりつけ医が参画した早期からの認知症高齢者支援体制を策定し
かかりつけ医に対する研修プログラムを含めた認知症対策総合支援事業を行う
ケアマネジメント
ケアマネジメントは利用者の自立を支援し生活の質を高めていくことを目指す
<ケアマネジメントの過程>
a.入口…ケースの発見、スクリーニング、インテークが行われる
b.アセスメント…利用者の社会生活上の全体的な観点から捉え、
諸々の問題点やニーズを査定する
c.ケース目標の設定とケアプランの作成
d.ケアプラン実施
e.モニター及びフォローアップ
f.再アセスメント
認知症高齢者に対する留意点
高齢者本人の感じているフェルトニーズと
専門家が考えるプロフェッショナルニーズのすり合わせが難しい
これは高齢者が意思表示を十分出来ないからである
a.できる限り本人からケアプランについての了解を取ることである
b.本人の身近な理解者と一緒にケアプランを作ることもある
c.地域福祉権利擁護事業での生活支援員とともにケアプランを作っていく
d.他職種の専門職とのケアカンファレンスの中で、相互のディスカッションに
よる複合的な視点で、的確なニーズやその解決方法を得ていく
e.職場の上司とスーパービジョンを受けてケアプランを作成し、実施する
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
認知症ケア専門士になろう! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
認知症ケア専門士になろう!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90040人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6420人
- 3位
- 独り言
- 9045人