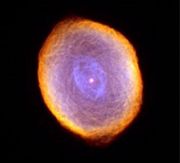|
|
|
|
コメント(26)
私は北インドにいますので、PCとモバイルのインターネット・コネクションがなかなかうまくつながりません、その間・・・下書きの文章がどんどん長くなって来ました、
(〜c〜;)ははは・・・
日本でもようやく、一般的にクラニオ・ワークが知られるようになってきましたが、まだまだ成熟したプラクティショナーの数はそんなに多くありません。 こういった医学的な理解も私達プラクティショナーは知っておく必要があるでしょう。
クライアントの多くが持ち込む症状のなかには、この脳脊髄液減少症が関係しているかも知れないからです。 この病状に、急性と慢性があると言われていますが、ひょとしたら、そんなに稀な現象ではないかもしれません。 慢性的に、そして一定時的に、脳脊髄液の生産がうまく行われずに、その日は髄液が理想的な量に達していなかったりするかもしれませんね。 例えば、私のような低血圧症の人は、こういった現象がひんぱんに起っているかもしれません。 また、脱水状態によって生じることもあるそうです。 そういった場合、水分を十分に補給する必要があるそうです。 急性なものには、アクシデントによるクモ膜の破損などが取り上げられ、それによって脳脊髄液がクモ膜下腔からもれるという症状を引き起こします。 以下にインターネットのサイトから簡潔に拾ったものを提示しましょう。
*****************************
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)=クラニオ・システムの膜システム内(クモ膜下腔)に循環している脳脊髄液が標準量より少なくなり髄圧が低くなる、その原因として考えられているのが:
1.事故や強度の打撲によるクモ膜の損傷によって脳脊髄液がクモ膜下腔から漏れ出す。むち打ち症にいたっては脳脊髄液の一定時に髄圧が急上昇し、腰椎の神経根に強い圧が加わりクモ膜が避ける、など。
2.脳脊髄液の生産の低下。
3.過剰な髄液吸収、実際にそのようなことが起っているのはさだかではなきようですが・・。
この病状にも急性と慢性があるようです。慢性の人は特に、その症状が軽かったり、一時的であったりするので、診断が難しいとも言われています。
そして、ありとあらゆる症状がそれに関係していると考えられ:
頭痛・偏頭痛・頚椎通・背部痛、腰痛、手足の痛み・耳鳴り、聴覚過敏、めまい、ふらつきなどでメニエール病や特発性難聴・目に関する症状のもろもろ・顔面痛、しびれ、歯痛、顎関節症・微熱、体温調整障害、動悸、呼吸困難、胃腸障害、頻尿などの症状・胃食道逆流症、頑固な便秘・思考力、集中力が極度に低下・うつや無気力もよく見られる症状・極度の倦怠感、易疲労感、睡眠障害、免疫異常により風邪をひきやすくなる、アトピーの悪化、内分泌機能異常として性欲低下、月経異常、子宮内膜症の悪化などの症状・などなど・・・、
なんと!病気と言う病気のほとんどの症状が関係するではありませんか!!!
そして、これらの症状にはある特徴がみられ、1つは天候に左右されること。ことに気圧の変化に応じて症状が変化します。雨の降る前や台風の接近により頭痛、めまい、吐き気、だるさなどが悪化する傾向があります。 体をおこしていると症状が悪化し横になると軽快する傾向もみられます。2つ目は脱水で症状が悪化することです。十分な水分が摂れないときや下痢、発熱時のような脱水状態で症状が悪化することが多く見られます。
詳しくは(私の友人が去年、この脳脊髄液減少症について質問された時に送ってきたサイトです):
http://npo-aswp.org/shinonaga2.html
http://atami.iuhw.ac.jp/shinryou/nogeka/gensyo1.html
(〜c〜;)ははは・・・
日本でもようやく、一般的にクラニオ・ワークが知られるようになってきましたが、まだまだ成熟したプラクティショナーの数はそんなに多くありません。 こういった医学的な理解も私達プラクティショナーは知っておく必要があるでしょう。
クライアントの多くが持ち込む症状のなかには、この脳脊髄液減少症が関係しているかも知れないからです。 この病状に、急性と慢性があると言われていますが、ひょとしたら、そんなに稀な現象ではないかもしれません。 慢性的に、そして一定時的に、脳脊髄液の生産がうまく行われずに、その日は髄液が理想的な量に達していなかったりするかもしれませんね。 例えば、私のような低血圧症の人は、こういった現象がひんぱんに起っているかもしれません。 また、脱水状態によって生じることもあるそうです。 そういった場合、水分を十分に補給する必要があるそうです。 急性なものには、アクシデントによるクモ膜の破損などが取り上げられ、それによって脳脊髄液がクモ膜下腔からもれるという症状を引き起こします。 以下にインターネットのサイトから簡潔に拾ったものを提示しましょう。
*****************************
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)=クラニオ・システムの膜システム内(クモ膜下腔)に循環している脳脊髄液が標準量より少なくなり髄圧が低くなる、その原因として考えられているのが:
1.事故や強度の打撲によるクモ膜の損傷によって脳脊髄液がクモ膜下腔から漏れ出す。むち打ち症にいたっては脳脊髄液の一定時に髄圧が急上昇し、腰椎の神経根に強い圧が加わりクモ膜が避ける、など。
2.脳脊髄液の生産の低下。
3.過剰な髄液吸収、実際にそのようなことが起っているのはさだかではなきようですが・・。
この病状にも急性と慢性があるようです。慢性の人は特に、その症状が軽かったり、一時的であったりするので、診断が難しいとも言われています。
そして、ありとあらゆる症状がそれに関係していると考えられ:
頭痛・偏頭痛・頚椎通・背部痛、腰痛、手足の痛み・耳鳴り、聴覚過敏、めまい、ふらつきなどでメニエール病や特発性難聴・目に関する症状のもろもろ・顔面痛、しびれ、歯痛、顎関節症・微熱、体温調整障害、動悸、呼吸困難、胃腸障害、頻尿などの症状・胃食道逆流症、頑固な便秘・思考力、集中力が極度に低下・うつや無気力もよく見られる症状・極度の倦怠感、易疲労感、睡眠障害、免疫異常により風邪をひきやすくなる、アトピーの悪化、内分泌機能異常として性欲低下、月経異常、子宮内膜症の悪化などの症状・などなど・・・、
なんと!病気と言う病気のほとんどの症状が関係するではありませんか!!!
そして、これらの症状にはある特徴がみられ、1つは天候に左右されること。ことに気圧の変化に応じて症状が変化します。雨の降る前や台風の接近により頭痛、めまい、吐き気、だるさなどが悪化する傾向があります。 体をおこしていると症状が悪化し横になると軽快する傾向もみられます。2つ目は脱水で症状が悪化することです。十分な水分が摂れないときや下痢、発熱時のような脱水状態で症状が悪化することが多く見られます。
詳しくは(私の友人が去年、この脳脊髄液減少症について質問された時に送ってきたサイトです):
http://npo-aswp.org/shinonaga2.html
http://atami.iuhw.ac.jp/shinryou/nogeka/gensyo1.html
続き:
もちろん、システム内の脳脊髄液が理想的な量に達しないと、そこは中枢神経系の王道の位置でもあるので、上記のようなさまざまな症状がでても驚きはしません。
さて、クラニオ・プラクティショナーとして何が出来るか? が、つるぎさんの問いですが・・・上記の事柄から思考してみると・・・、
まず、上記で述べられているような現象を、大きく2つに分けてみましょう。 ひとつは、‘クモ膜の破損による髄液のもれ’ですが、これは、組織が破損しているため、それが改善されなければならないでしょう。
もし、膜が裂けて破損しているのであれば、新しい細胞の誕生によって修復されるのを待つのが望ましいのでしょうが・・・(一般医学では手術で修復する方法を取っているようです)、それには時間がすこしかかるようなので、その間、例えば、意図的な膜の牽引などは十分に考慮しなければならないでしょう。 CRI的なワークを学んでいる方は特に注意する必要があると思われます。
また、膜外の緊張や癒着または圧縮などによって膜システムの一部が脊髄神経根の位置(中枢神経が脊柱の外に出来ていく経路部)にて、周辺の組織のつっぱりや捻じれなどにより、神経と膜の間に隙間が開き、髄液のもれるスペースをつくっているのかもしれません。 この脊髄神経根の位置では膜が小袖のようになって脊髄神経の出入り口を取り囲んでいますが、それはまったく張り付いたように接着しているわけではないようなので、破損がなくても、微量の脳脊髄液が膜システムから流れ出しているというように私は教えられました。
さて、アプローチとしては、まずは、システム全体に注目してみましょう。 そして、正中線を上昇/沈降する波動に注目してみましょう。 むやみに、組織レベルのワークでマニピュレートすると、それが本来の健康が現す治癒力と相容れない場合、システムが無意味に混乱することになるでしょう。 アクシデントの直後であれば、まず、身体の生理システムはその修復のために必要なありとあらゆることを行うと思われます。 まず、その邪魔をしないこと。身体の本来の治癒力をサポートすることが一番の策だと思います。
サザーランドいわく!「身体の治癒力(BOLの潜在力)は、私達の思考よりもインテリジェンス(知的)である」と、語っています。 バイオのアプローチを行っている人は、ロングタイドのフィールドを保ち、その作用を見守っているのが良いでしょう。 システムが落ち着き始めた頃に、ミッドタイドの様子を伺い、その修復作用をサポートします(ロングタイドの状態でもこれは行えます)。 それは、バイオキネティック・フォースと呼ばれている外傷フォースの消散を試みることです。 そのフォースが未解決の状態でそこに居つくことがないようにすることでシステムの修繕作用をサポートします。 いかにあれ、システムの固有の修復作用に従います。
もうひとつは、‘脳脊髄液の生産不足または脳脊髄液の過剰吸収・・・’と言われているもので、生産不足は水分を十分に補給すると、数週間後に改善されると言われますが、クラニオ・プラクティショナーが出来ることは、身体の生理環境を整え、システムが理想的に機能するように促すことです。
何故、生産不足なのか?の根本的な理解も必要でしょう。 症状によってアプローチが異なると思いますが、例えば、私のような慢性性低血圧症ですが、スティル・ポイントは場合によってはCV4ではなくEV4が望ましい時もあります。 髄液の生産不足と低血圧は関係するかもしれません。 この場合、EV4によって、髄液の現すインハレーションを高めることで生産能力をサポートすることが出来るかもしれません。
脳脊髄液は、脳質の脈絡叢の位置から分泌されています。 さて、もし、この生産機能がうまく働いていなければ、もちろん脳脊髄液の生産量は少なく、こういった原因に対してもプラクティショナーは十分に考慮する必要があるかもしれません。 一般的にあまり知られていませんが、生命のイグニッションに注目することも出来るでしょう。 身体メカニズムの機動力を高める意味で、です。 これは、第3脳質で様子を伺う、または頭の頭頂から数メートル離れた位置から様子を伺います。 もし波動のリズムがあわなければ、システムを混乱させることに成り得るので、熟練したプラクティショナーのアプローチ法です。 また、もし、生産不足の原因が、バーストラウマにあったとしたら・・・・? 頭蓋骨組織の骨内または骨間の圧縮が生産作用の妨げとなっていたら? 発生学的に捉えていると、誕生時の骨内そして骨間の圧縮のみならず、発生初期にめざましく成長する中枢神経系/脈絡叢は脳の中央部にあたるので、脳脊髄液‐生産の妨げとなるような何らかの力が初期の発生プロセスにすでに作用していたら? 深く考えると・・、原因はいろいろあるでしょう。
DR.サザーランドの言葉を借りると、脳脊髄液は、生命をバックアップする潜在力が現れる崇高なエレメントであると定義づけています。 身体は細胞集団の集まった組織構造体であるだけでなく、ある一定の法則に従ったエネルギーのフィールドとしても考慮すべきです。
話を戻しますが、髄液の過剰吸収はどうでしょう? もし、そのような現象が本当にあったとしたら、クライアントはどんな症状を訴えてくるでしょう? その症状によってアプローチを変えていかなければならないでしょう。 アプローチを詳細に考えるとしたら、まずクライアントの症状を知る、組織の状態を調査する、そして生命のエネルギー・フィールドの様子を見る、すると、芋づる式にその個人のヒストリーが連なって出てきます。 セッションをたくさん取っている人は、これらがある程度、整理されていますが、まったくひどい状態になるまでケアーしていない人は、がんじがらめのシステムを抱えてやってくることになります。 脳脊髄液減少症とその原因は、‘卵が先か?鶏が先か?’です。 取りあえず、大きな意味では、ひとつひとつの問題をタイムリーに消散していかなければならないでしょう。
*****************
続き:
さて、クラニオ・ワークは身体の固有の健康をサポートすることが出来るワークですので、もし、プラクティショナーが;例えば、仙骨でモーションに耳を傾けていたとしましょう。 インハレーションとエクスハレーションの縦の波動/Longitudinal fluctuationと呼ばれている正中線を上昇/沈降する生命の波動に何らかの変異が感じられることでしょう。 組織の破損や髄液の漏れなどの箇所に波動の乱れが感じられると思います。 この波動の乱れを落ち着かせ、システムの健康(治癒)の作用を最大限に引き上げてみることを試みます。
インスティチュートによっては、アプローチの違いはあるかもしれませんが、まずは、何かを意図する前に、身体に耳を傾け、それが何をしようとしているのか、視野を広げて十分なスペースと時間を与え、そして見守ってみてください。 それがヒーリングへの近道でしょう。アプローチは、身体の固有のインテリジェンスがおのずと示してくれます。 私達はそれに従います。 あなたはプラクティショナーとして、そのインテリジェンスが現す現象を見守るウイットネス/witnessとなるのです。これは熟練すればするほど、“謙虚な気持ち”にさせられます。
最初にも言いましたが、日本における成熟したクラニオ・プラクティショナーの数はそんなに多くありません。 また、クラニオ・プラクティショナーによるこれらの症状に対する臨床リサーチもあまり行われているとはいえません。 つるぎさん、どうですか? リサーチしてみますか? もしよろしければ一緒に、それらについて調査してみましょう。
もちろん、システム内の脳脊髄液が理想的な量に達しないと、そこは中枢神経系の王道の位置でもあるので、上記のようなさまざまな症状がでても驚きはしません。
さて、クラニオ・プラクティショナーとして何が出来るか? が、つるぎさんの問いですが・・・上記の事柄から思考してみると・・・、
まず、上記で述べられているような現象を、大きく2つに分けてみましょう。 ひとつは、‘クモ膜の破損による髄液のもれ’ですが、これは、組織が破損しているため、それが改善されなければならないでしょう。
もし、膜が裂けて破損しているのであれば、新しい細胞の誕生によって修復されるのを待つのが望ましいのでしょうが・・・(一般医学では手術で修復する方法を取っているようです)、それには時間がすこしかかるようなので、その間、例えば、意図的な膜の牽引などは十分に考慮しなければならないでしょう。 CRI的なワークを学んでいる方は特に注意する必要があると思われます。
また、膜外の緊張や癒着または圧縮などによって膜システムの一部が脊髄神経根の位置(中枢神経が脊柱の外に出来ていく経路部)にて、周辺の組織のつっぱりや捻じれなどにより、神経と膜の間に隙間が開き、髄液のもれるスペースをつくっているのかもしれません。 この脊髄神経根の位置では膜が小袖のようになって脊髄神経の出入り口を取り囲んでいますが、それはまったく張り付いたように接着しているわけではないようなので、破損がなくても、微量の脳脊髄液が膜システムから流れ出しているというように私は教えられました。
さて、アプローチとしては、まずは、システム全体に注目してみましょう。 そして、正中線を上昇/沈降する波動に注目してみましょう。 むやみに、組織レベルのワークでマニピュレートすると、それが本来の健康が現す治癒力と相容れない場合、システムが無意味に混乱することになるでしょう。 アクシデントの直後であれば、まず、身体の生理システムはその修復のために必要なありとあらゆることを行うと思われます。 まず、その邪魔をしないこと。身体の本来の治癒力をサポートすることが一番の策だと思います。
サザーランドいわく!「身体の治癒力(BOLの潜在力)は、私達の思考よりもインテリジェンス(知的)である」と、語っています。 バイオのアプローチを行っている人は、ロングタイドのフィールドを保ち、その作用を見守っているのが良いでしょう。 システムが落ち着き始めた頃に、ミッドタイドの様子を伺い、その修復作用をサポートします(ロングタイドの状態でもこれは行えます)。 それは、バイオキネティック・フォースと呼ばれている外傷フォースの消散を試みることです。 そのフォースが未解決の状態でそこに居つくことがないようにすることでシステムの修繕作用をサポートします。 いかにあれ、システムの固有の修復作用に従います。
もうひとつは、‘脳脊髄液の生産不足または脳脊髄液の過剰吸収・・・’と言われているもので、生産不足は水分を十分に補給すると、数週間後に改善されると言われますが、クラニオ・プラクティショナーが出来ることは、身体の生理環境を整え、システムが理想的に機能するように促すことです。
何故、生産不足なのか?の根本的な理解も必要でしょう。 症状によってアプローチが異なると思いますが、例えば、私のような慢性性低血圧症ですが、スティル・ポイントは場合によってはCV4ではなくEV4が望ましい時もあります。 髄液の生産不足と低血圧は関係するかもしれません。 この場合、EV4によって、髄液の現すインハレーションを高めることで生産能力をサポートすることが出来るかもしれません。
脳脊髄液は、脳質の脈絡叢の位置から分泌されています。 さて、もし、この生産機能がうまく働いていなければ、もちろん脳脊髄液の生産量は少なく、こういった原因に対してもプラクティショナーは十分に考慮する必要があるかもしれません。 一般的にあまり知られていませんが、生命のイグニッションに注目することも出来るでしょう。 身体メカニズムの機動力を高める意味で、です。 これは、第3脳質で様子を伺う、または頭の頭頂から数メートル離れた位置から様子を伺います。 もし波動のリズムがあわなければ、システムを混乱させることに成り得るので、熟練したプラクティショナーのアプローチ法です。 また、もし、生産不足の原因が、バーストラウマにあったとしたら・・・・? 頭蓋骨組織の骨内または骨間の圧縮が生産作用の妨げとなっていたら? 発生学的に捉えていると、誕生時の骨内そして骨間の圧縮のみならず、発生初期にめざましく成長する中枢神経系/脈絡叢は脳の中央部にあたるので、脳脊髄液‐生産の妨げとなるような何らかの力が初期の発生プロセスにすでに作用していたら? 深く考えると・・、原因はいろいろあるでしょう。
DR.サザーランドの言葉を借りると、脳脊髄液は、生命をバックアップする潜在力が現れる崇高なエレメントであると定義づけています。 身体は細胞集団の集まった組織構造体であるだけでなく、ある一定の法則に従ったエネルギーのフィールドとしても考慮すべきです。
話を戻しますが、髄液の過剰吸収はどうでしょう? もし、そのような現象が本当にあったとしたら、クライアントはどんな症状を訴えてくるでしょう? その症状によってアプローチを変えていかなければならないでしょう。 アプローチを詳細に考えるとしたら、まずクライアントの症状を知る、組織の状態を調査する、そして生命のエネルギー・フィールドの様子を見る、すると、芋づる式にその個人のヒストリーが連なって出てきます。 セッションをたくさん取っている人は、これらがある程度、整理されていますが、まったくひどい状態になるまでケアーしていない人は、がんじがらめのシステムを抱えてやってくることになります。 脳脊髄液減少症とその原因は、‘卵が先か?鶏が先か?’です。 取りあえず、大きな意味では、ひとつひとつの問題をタイムリーに消散していかなければならないでしょう。
*****************
続き:
さて、クラニオ・ワークは身体の固有の健康をサポートすることが出来るワークですので、もし、プラクティショナーが;例えば、仙骨でモーションに耳を傾けていたとしましょう。 インハレーションとエクスハレーションの縦の波動/Longitudinal fluctuationと呼ばれている正中線を上昇/沈降する生命の波動に何らかの変異が感じられることでしょう。 組織の破損や髄液の漏れなどの箇所に波動の乱れが感じられると思います。 この波動の乱れを落ち着かせ、システムの健康(治癒)の作用を最大限に引き上げてみることを試みます。
インスティチュートによっては、アプローチの違いはあるかもしれませんが、まずは、何かを意図する前に、身体に耳を傾け、それが何をしようとしているのか、視野を広げて十分なスペースと時間を与え、そして見守ってみてください。 それがヒーリングへの近道でしょう。アプローチは、身体の固有のインテリジェンスがおのずと示してくれます。 私達はそれに従います。 あなたはプラクティショナーとして、そのインテリジェンスが現す現象を見守るウイットネス/witnessとなるのです。これは熟練すればするほど、“謙虚な気持ち”にさせられます。
最初にも言いましたが、日本における成熟したクラニオ・プラクティショナーの数はそんなに多くありません。 また、クラニオ・プラクティショナーによるこれらの症状に対する臨床リサーチもあまり行われているとはいえません。 つるぎさん、どうですか? リサーチしてみますか? もしよろしければ一緒に、それらについて調査してみましょう。
脳脊髄液減少症ではありませんが、ひとつ私の体験を書いてみましょう。 と言うのも、身体の生理機能に大きく影響を与えるクラニオワークについてなので。
ある時、私は、あるインスティチュートのチューター(指導員)としてベーシック・トレーニングを受けていた生徒さんのフィードバック・セッションを行っていました。 彼は、私の仙骨の位置にて、モーションを伺っていました。
深い静寂が訪れ、ホリスティック・シフトという現象が起った後、しばらくして、
“はぁっ!”・・・っと、肺に呼吸が入りました、その時、私は産道を出た直後の新生児のように、酸素が、生まれて初めての呼吸とともに肺に送られてきたような感覚にとらわれました。
私は以前から、私の呼吸は浅いと言うことを知っていました。呼吸とともに、腹部の運動がうまく行われていず、気がついたら無呼吸の状態に陥っている時が稀ではなかったように覚えています。
ですが、このセッションの後、私の呼吸は止まることなく、継続的に呼吸による腹部の運動が行われるようになりました。 これは私にとって、大きな身体機能の変化でした。 私の呼吸に対する生理機能が改善されたのです。 何か呼吸機能を妨害していたエネルギーが改善された、または妨害作用が消散されたのでしょう。
脳脊髄液減少症も、このように、もし何かの妨害作用が生じていて、それが改善されると、うまく髄液の生産機能が改善されるかもしれません。 このようなアプローチは、一般医学とはすこし異なった手法ですが、試してみる価値は十分にあります。
もうひとつ、去年頃でしたか、あるクライアントさんを仙骨で触診していた時、いきなり心臓の鼓動のような大きなパルスが長い間感じられました。 それは本当に、心臓の力強い鼓動のようでした。このクライアントさんは、確か、生まれた頃から病弱で、あまり激しい運動など出来なかったようです。 体つきも、か細い感じで色白の男性でした。 数日後、彼と会ったとき、セッションの次の日はまったく普段感じたことがないように快適で、ダンスまで楽しんだようでした。 もう一度セッションを申し込まれ、その時、私はインドにいましたので、2回のセッションの後、彼は日本に戻りました。
この時も私が自分の肺機能で感じたように、プラクティショナーとして確かに実感したのは、彼の心臓機能が何らかの代償作用(妨害作用)から解放されたということです。
障害は、このように、何かの力によって、その機能が妨害されていることもあるようです。 そして、その妨害または代償作用はクラニオ・ワークによって消散することが出来ます。
ある時、私は、あるインスティチュートのチューター(指導員)としてベーシック・トレーニングを受けていた生徒さんのフィードバック・セッションを行っていました。 彼は、私の仙骨の位置にて、モーションを伺っていました。
深い静寂が訪れ、ホリスティック・シフトという現象が起った後、しばらくして、
“はぁっ!”・・・っと、肺に呼吸が入りました、その時、私は産道を出た直後の新生児のように、酸素が、生まれて初めての呼吸とともに肺に送られてきたような感覚にとらわれました。
私は以前から、私の呼吸は浅いと言うことを知っていました。呼吸とともに、腹部の運動がうまく行われていず、気がついたら無呼吸の状態に陥っている時が稀ではなかったように覚えています。
ですが、このセッションの後、私の呼吸は止まることなく、継続的に呼吸による腹部の運動が行われるようになりました。 これは私にとって、大きな身体機能の変化でした。 私の呼吸に対する生理機能が改善されたのです。 何か呼吸機能を妨害していたエネルギーが改善された、または妨害作用が消散されたのでしょう。
脳脊髄液減少症も、このように、もし何かの妨害作用が生じていて、それが改善されると、うまく髄液の生産機能が改善されるかもしれません。 このようなアプローチは、一般医学とはすこし異なった手法ですが、試してみる価値は十分にあります。
もうひとつ、去年頃でしたか、あるクライアントさんを仙骨で触診していた時、いきなり心臓の鼓動のような大きなパルスが長い間感じられました。 それは本当に、心臓の力強い鼓動のようでした。このクライアントさんは、確か、生まれた頃から病弱で、あまり激しい運動など出来なかったようです。 体つきも、か細い感じで色白の男性でした。 数日後、彼と会ったとき、セッションの次の日はまったく普段感じたことがないように快適で、ダンスまで楽しんだようでした。 もう一度セッションを申し込まれ、その時、私はインドにいましたので、2回のセッションの後、彼は日本に戻りました。
この時も私が自分の肺機能で感じたように、プラクティショナーとして確かに実感したのは、彼の心臓機能が何らかの代償作用(妨害作用)から解放されたということです。
障害は、このように、何かの力によって、その機能が妨害されていることもあるようです。 そして、その妨害または代償作用はクラニオ・ワークによって消散することが出来ます。
あれから、しばらく考えていたのですが、
**「髄液の過剰吸収」による脳脊髄液減少症について**
もし、このような現象があるとしたら;
髄液の生産不足(例えば、低血圧による脈絡叢への血液の押し出しが弱い場合)は、“EV4”によって改善される可能性があるかもしれないと上記で述べましたが、
逆の髄液の過剰吸収は・・・、
中枢神経による髄液の過剰吸収という減少があるとしたら、果たして中枢神経はそれほどの滋養を必要としているとしたら・・・、
まるで、大都会に住んでいるストレス症で神経がいつも張り詰めている社会人、または、精神の過剰興奮状態にある若者・・、に当てはまるかもしれませんね。
こういった場合、確かに、中枢神経の過剰状態を落ち着かせ、自律神経を一定のバランスに整えることが出来る“CV4”が役立つかもしれません。
この、どちらの例をとっても、これらの症状に至るには、ほとんどの人が、ひとつではなく、いくつもの折り重なった要因があるようで、そうすると、例えば、よくある質問なのですが;「どの症状にCV4またはEV4のどちらが好ましいのですか?」 と聞かれることがあります。
どちらが適切であるのかは、システムに聞いてみることです。 あなたが、もし、正しく耳を傾ける能力を持っていたら、システムが必要な瞬間に必要な分だけ、CV4もしくはEV4に入っていくのが分かります。 私達はそれをサポートすることが、適切で間違いがありません。 システムがどちらを必要としているかが明らかであると言うことと、まったくシステムの行っている固有の治癒力と正反対のことしないと言う、とても安全な方法だからです。
**「髄液の過剰吸収」による脳脊髄液減少症について**
もし、このような現象があるとしたら;
髄液の生産不足(例えば、低血圧による脈絡叢への血液の押し出しが弱い場合)は、“EV4”によって改善される可能性があるかもしれないと上記で述べましたが、
逆の髄液の過剰吸収は・・・、
中枢神経による髄液の過剰吸収という減少があるとしたら、果たして中枢神経はそれほどの滋養を必要としているとしたら・・・、
まるで、大都会に住んでいるストレス症で神経がいつも張り詰めている社会人、または、精神の過剰興奮状態にある若者・・、に当てはまるかもしれませんね。
こういった場合、確かに、中枢神経の過剰状態を落ち着かせ、自律神経を一定のバランスに整えることが出来る“CV4”が役立つかもしれません。
この、どちらの例をとっても、これらの症状に至るには、ほとんどの人が、ひとつではなく、いくつもの折り重なった要因があるようで、そうすると、例えば、よくある質問なのですが;「どの症状にCV4またはEV4のどちらが好ましいのですか?」 と聞かれることがあります。
どちらが適切であるのかは、システムに聞いてみることです。 あなたが、もし、正しく耳を傾ける能力を持っていたら、システムが必要な瞬間に必要な分だけ、CV4もしくはEV4に入っていくのが分かります。 私達はそれをサポートすることが、適切で間違いがありません。 システムがどちらを必要としているかが明らかであると言うことと、まったくシステムの行っている固有の治癒力と正反対のことしないと言う、とても安全な方法だからです。
遅くなりました。
いやいや、小生の住んでいるメキシコ、ひどいもんで先日行われた大統領選に敗れた側の支持者たちが大阪でいうところの御堂筋線を封鎖・占領してしまいまして、毎日往復2時間の徒歩+地下鉄+バスの通勤を余儀なくされていて、コンピュータを開ける時間もありませんでした。そして昨日、せっかく書き終わったところに落雷。画面が真っ暗、小生は真っ青。幸い故障はしていなかったので今からまた挑戦です。
(言い訳がましくてすみません・・・)
低髄液圧症候群に関していくつかのサイトを覗いてきましたが、意外な側面が見えてきました。というのもこの症例についてドクターたちの間で大きく2グループに分かれているようなのです。
1つは、鞭打ち症の後遺症などから低髄液圧症候群をあげ治療法としてブラッドパッチを推奨グループ。
もう1つは、低髄液圧症候群をマスコミに作り上げられた病気としブラッドパッチに対し懐疑的なグループです。
この病気の診断はRI脳槽シンチグラフィーで漏出している場所の確認により、根幹症状としてひどい頭痛も横になると15〜20分で急激に改善することがあげられます。
ブラッドパッチというのは簡単にいうと髄液の漏れている箇所に自分の血糊を貼り付けて穴をふさぐ、といったものです。この治療により改善した方ももちろんいらっしゃるのですが、逆に悪化された方もかなりの数に上るようです。これに対し後者のグループは、繰り返されるパッチにより脊髄くも膜下腔の癒着肥厚が起こり隋液循環吸収障害を招くことによるとし、改善例に対しても、パッチ後の安静臥床により結果的に頚部安静が保たれるためとしています。
今回の書き込みはアプローチの視点にはあまり関係はありませんが、低髄液圧症候群における医学界の現状としてあげさせていただきます。
何もわからないままいくつか文献を読んだりネットで検索してみてぼんやりとこの病気についてわかりかけてきました。しかしまだまだ医学的にも不明な点が多いようですので要チェックですね。
なにかご存知の方やご専門の方、ご意見や「それは間違ってる」というようなご指摘がございましたらどんどんお申し付けください。
いやいや、小生の住んでいるメキシコ、ひどいもんで先日行われた大統領選に敗れた側の支持者たちが大阪でいうところの御堂筋線を封鎖・占領してしまいまして、毎日往復2時間の徒歩+地下鉄+バスの通勤を余儀なくされていて、コンピュータを開ける時間もありませんでした。そして昨日、せっかく書き終わったところに落雷。画面が真っ暗、小生は真っ青。幸い故障はしていなかったので今からまた挑戦です。
(言い訳がましくてすみません・・・)
低髄液圧症候群に関していくつかのサイトを覗いてきましたが、意外な側面が見えてきました。というのもこの症例についてドクターたちの間で大きく2グループに分かれているようなのです。
1つは、鞭打ち症の後遺症などから低髄液圧症候群をあげ治療法としてブラッドパッチを推奨グループ。
もう1つは、低髄液圧症候群をマスコミに作り上げられた病気としブラッドパッチに対し懐疑的なグループです。
この病気の診断はRI脳槽シンチグラフィーで漏出している場所の確認により、根幹症状としてひどい頭痛も横になると15〜20分で急激に改善することがあげられます。
ブラッドパッチというのは簡単にいうと髄液の漏れている箇所に自分の血糊を貼り付けて穴をふさぐ、といったものです。この治療により改善した方ももちろんいらっしゃるのですが、逆に悪化された方もかなりの数に上るようです。これに対し後者のグループは、繰り返されるパッチにより脊髄くも膜下腔の癒着肥厚が起こり隋液循環吸収障害を招くことによるとし、改善例に対しても、パッチ後の安静臥床により結果的に頚部安静が保たれるためとしています。
今回の書き込みはアプローチの視点にはあまり関係はありませんが、低髄液圧症候群における医学界の現状としてあげさせていただきます。
何もわからないままいくつか文献を読んだりネットで検索してみてぼんやりとこの病気についてわかりかけてきました。しかしまだまだ医学的にも不明な点が多いようですので要チェックですね。
なにかご存知の方やご専門の方、ご意見や「それは間違ってる」というようなご指摘がございましたらどんどんお申し付けください。
はじめまして。
クラニオを勉強中です。
私の練習相手になってくれている人は、
おそらく後天的(事故による)脳脊髄液減少症です。
始めて間もないので、タイドもまだ細く弱い状態です。
確かに、気候の変わり目や水分補給を怠ると
頭痛やめまいがひどくなるようです。
別件で、
勤め先の病院では、脳脊髄液減少症の検査「は」行なっています。
去年あたりから、徐々に対象患者さんが増えてきています。
ブラッドパッチは保健診療外のため、
当院では、実施していません。
クリニカルブレインという、脳外科関係の雑誌で、
数年前に脳脊髄液を特集していましたが、
症状については、明記されており、
つるぎさんの説明と同じ感じでしたが、
対処法については、まだ手探り段階という内容でした。
クラニオを勉強中です。
私の練習相手になってくれている人は、
おそらく後天的(事故による)脳脊髄液減少症です。
始めて間もないので、タイドもまだ細く弱い状態です。
確かに、気候の変わり目や水分補給を怠ると
頭痛やめまいがひどくなるようです。
別件で、
勤め先の病院では、脳脊髄液減少症の検査「は」行なっています。
去年あたりから、徐々に対象患者さんが増えてきています。
ブラッドパッチは保健診療外のため、
当院では、実施していません。
クリニカルブレインという、脳外科関係の雑誌で、
数年前に脳脊髄液を特集していましたが、
症状については、明記されており、
つるぎさんの説明と同じ感じでしたが、
対処法については、まだ手探り段階という内容でした。
14番の方はお名前なしですか?
**脳脊髄液減少症と関係があるのでしょうか?
**コマちゃん、お答えいただければ幸いです。
私も医者ではありません、それと、クライアントさんがどのような症状をお持ちであり、医者にかかっている等の情報なしに、このような質問への回答を持ち合わせていないことをご理解ください。
クライアントさんの情報に対しても、本人の承諾なしに“多く”を書き込むことは「個人情報」として考慮してください。 よろしくお願いします。
そのうえで、CV4とは何かをご存じない方に:
一般的に知られているCV4は・・・
「Compression of 4th ventricle/第4脳室の圧縮」として知られています。CRIレベルにおけるCV4は第4脳室が近隣する後頭骨周辺にて、エクステンション方向に向う組織に微細な圧を用いることで脳脊髄液がシステム内に入り込むのを一時的に抑えることを意図します。 ですが、脳室では血液が脈絡叢を通してCSF(脳脊髄液)に作り変えられる作業が常時起っていると思われます。
脳室が充たされると、システムは自然にCV4から自立的に解放され、そしてシステム(中枢神経周辺そしてそれを取り囲む硬膜内)に脳脊髄液が勢いよく流れ込むことで老廃物を一掃し、また膜の癒着等の解放を促すことが出来る可能性が考えられます。
ただし! バーストラウマなどによる骨内圧縮または頭部への強打によるAO部の圧縮フォースがみられる時、例えそれが微細な圧であったとしても適切な処置ではないことがあります。 プラクティショナーの方、十分にご注意を!
**脳脊髄液減少症と関係があるのでしょうか?
**コマちゃん、お答えいただければ幸いです。
私も医者ではありません、それと、クライアントさんがどのような症状をお持ちであり、医者にかかっている等の情報なしに、このような質問への回答を持ち合わせていないことをご理解ください。
クライアントさんの情報に対しても、本人の承諾なしに“多く”を書き込むことは「個人情報」として考慮してください。 よろしくお願いします。
そのうえで、CV4とは何かをご存じない方に:
一般的に知られているCV4は・・・
「Compression of 4th ventricle/第4脳室の圧縮」として知られています。CRIレベルにおけるCV4は第4脳室が近隣する後頭骨周辺にて、エクステンション方向に向う組織に微細な圧を用いることで脳脊髄液がシステム内に入り込むのを一時的に抑えることを意図します。 ですが、脳室では血液が脈絡叢を通してCSF(脳脊髄液)に作り変えられる作業が常時起っていると思われます。
脳室が充たされると、システムは自然にCV4から自立的に解放され、そしてシステム(中枢神経周辺そしてそれを取り囲む硬膜内)に脳脊髄液が勢いよく流れ込むことで老廃物を一掃し、また膜の癒着等の解放を促すことが出来る可能性が考えられます。
ただし! バーストラウマなどによる骨内圧縮または頭部への強打によるAO部の圧縮フォースがみられる時、例えそれが微細な圧であったとしても適切な処置ではないことがあります。 プラクティショナーの方、十分にご注意を!
10月21日の毎日新聞 朝刊1面と3面に「脳脊髄(せきずい)液減少症」の記事が出てました。ご存知の方も多いと思いますが、一応ご報告を。↓
髄液漏れ:未解明な点も多く…病気として認知は?
医学界の大発見か、それとも大暴論か。論争が続いてきた「脳脊髄(せきずい)液減少症」(髄液漏れ)について、日本脳神経外科学会の学術委員会が、本格的な研究に取り組む。発症のメカニズムなど、依然として未解明な点も多い髄液漏れは、病気として認められるのか。今後の行方を探った。【渡辺暖、入江直樹、野田武】
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20061021k0000m040161000c.html
1面から抜粋
(前略)潜在的な患者は数万 〜 数十万人といわれているが、治療や補償に関する社会の救済システムは手つかずのままだ。(略) 暫定版ガイドラインによると、髄液漏れを「脳脊髄液が減少することで頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠などさまざまな症状があらわれる病気」と定義している。髄液漏れは02年、篠永氏が「軽微な外傷でも髄液が漏出する」と発表した。医学界では異端視されてきたが、支持する医師は増え続けた。一方、交通事故後に発症した患者達が、損害保険会社・共済から「事故で髄液は漏出しない」と治療費を打ち切られたり、学校嫌いとみなされる子供の患者の存在が明らかになっている。
髄液漏れ:未解明な点も多く…病気として認知は?
医学界の大発見か、それとも大暴論か。論争が続いてきた「脳脊髄(せきずい)液減少症」(髄液漏れ)について、日本脳神経外科学会の学術委員会が、本格的な研究に取り組む。発症のメカニズムなど、依然として未解明な点も多い髄液漏れは、病気として認められるのか。今後の行方を探った。【渡辺暖、入江直樹、野田武】
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20061021k0000m040161000c.html
1面から抜粋
(前略)潜在的な患者は数万 〜 数十万人といわれているが、治療や補償に関する社会の救済システムは手つかずのままだ。(略) 暫定版ガイドラインによると、髄液漏れを「脳脊髄液が減少することで頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠などさまざまな症状があらわれる病気」と定義している。髄液漏れは02年、篠永氏が「軽微な外傷でも髄液が漏出する」と発表した。医学界では異端視されてきたが、支持する医師は増え続けた。一方、交通事故後に発症した患者達が、損害保険会社・共済から「事故で髄液は漏出しない」と治療費を打ち切られたり、学校嫌いとみなされる子供の患者の存在が明らかになっている。
この病のおおもとの原因はなんなんでしょうね。
実は僕は昔擬似脳脊髄液減少症の様な症状にあったことがあります。
バイクレースをしていた僕は、レース用のバイクが壊れていたので憂さ晴らしに峠を攻めに行きました。調子に乗って攻めている時にソアラと正面衝突してしまい。右大腿骨骨折で残りの下りは救急車でした。幸い治りも早く約半年後には大腿部に入ったステンレスの棒をぬく手術をすることになりました。
挿入の手術は全身麻酔だったのですが、今回は下半身麻酔でした。執当医が未熟だったため、麻酔が上手く行かず、5回以上は刺したり抜いたり中で何かしているのか強烈に来る鈍い鈍痛に耐えていた覚えがあります。
手術後1日目少しでも体位を変えると回転性の眩暈と浮遊性の眩暈が遅い吐きそうになりました。2日目何とか起きあがろうとするものの眩暈と頭痛と内臓のむかつき感で座ることすら出来ません。こんな状態が1週間は続きました。幸いにして2週間ぐらいからまともになり始め、1ヶ月後には元に戻りました。今から思えば1次的にしても脳脊髄液減少症だったのかと思います。
でも、ここで不思議なのはなぜ、僕は治ったのかということでした。
穴が針という小さなモノだったからなのでしょうか?
脳脊髄液が漏れだすと言う生命の危機に近い状態をどうして身体は容認し続けているのでしょうか?
気がつかないのか?…それとも…
何かのシステムが破綻しているということなのでしょうか?
疑問は続く…。
実は僕は昔擬似脳脊髄液減少症の様な症状にあったことがあります。
バイクレースをしていた僕は、レース用のバイクが壊れていたので憂さ晴らしに峠を攻めに行きました。調子に乗って攻めている時にソアラと正面衝突してしまい。右大腿骨骨折で残りの下りは救急車でした。幸い治りも早く約半年後には大腿部に入ったステンレスの棒をぬく手術をすることになりました。
挿入の手術は全身麻酔だったのですが、今回は下半身麻酔でした。執当医が未熟だったため、麻酔が上手く行かず、5回以上は刺したり抜いたり中で何かしているのか強烈に来る鈍い鈍痛に耐えていた覚えがあります。
手術後1日目少しでも体位を変えると回転性の眩暈と浮遊性の眩暈が遅い吐きそうになりました。2日目何とか起きあがろうとするものの眩暈と頭痛と内臓のむかつき感で座ることすら出来ません。こんな状態が1週間は続きました。幸いにして2週間ぐらいからまともになり始め、1ヶ月後には元に戻りました。今から思えば1次的にしても脳脊髄液減少症だったのかと思います。
でも、ここで不思議なのはなぜ、僕は治ったのかということでした。
穴が針という小さなモノだったからなのでしょうか?
脳脊髄液が漏れだすと言う生命の危機に近い状態をどうして身体は容認し続けているのでしょうか?
気がつかないのか?…それとも…
何かのシステムが破綻しているということなのでしょうか?
疑問は続く…。
数年前に髄膜炎を煩い、それ以来、軽い頭痛があるという事で、いらしたクライアントさんが居ます。半年ほど続けて来て頂いて、症状がかなり改善したとのことで、しばらくご無沙汰でした。先日仕事が山を超えたので、という事で久々に来られ、セッションさせて頂いたところ、何度かEV4が起るのを感じました。
モーションのリズムは割と規則的なのですが、
とにかく弱々しかったのを覚えています。
EV4の際のイメージは、まるで標高の高い山中で、思いっきり少ない酸素を吸い込む深呼吸をしているような感じでした。
酸素=CSFというイメージでしたので、髄液が減ってるかもしれないので、
念のため病院でチェックしてみるようお勧めしました。
結果は、やはり髄液が減少していて、
とりあえず2週間は安静という診断だったそうです。
体力が戻ったら、またセッションを続けてみたいという事なので、
その際にドクターの診断などを聞いてみるつもりです。
自分のセッションは、本当に「何もしない」ので、
どなたかも書かれていましたが、それが一番安全で結果も良いように思いました。
正確に言えば、何もしないのではなく、
何が必要なのかを身体が表現してくれるのを待ち、
サインが出てきたらそれをひたすら聴きながら追随するだけという感じです。
諸先輩に比べると、まだまだ経験が足りないのですが、
この方の場合、EV4が立て続けに起るという身体のサインが意味していたことは、
髄液の減少だったという体験を一つ得られたので、
シェアさせて頂きました。
近い体験もしくはアドバイスがあれば、伺いたいと思っています。
このトピがあり、いろいろ参照することができて、
大変助けになりました。
モーションのリズムは割と規則的なのですが、
とにかく弱々しかったのを覚えています。
EV4の際のイメージは、まるで標高の高い山中で、思いっきり少ない酸素を吸い込む深呼吸をしているような感じでした。
酸素=CSFというイメージでしたので、髄液が減ってるかもしれないので、
念のため病院でチェックしてみるようお勧めしました。
結果は、やはり髄液が減少していて、
とりあえず2週間は安静という診断だったそうです。
体力が戻ったら、またセッションを続けてみたいという事なので、
その際にドクターの診断などを聞いてみるつもりです。
自分のセッションは、本当に「何もしない」ので、
どなたかも書かれていましたが、それが一番安全で結果も良いように思いました。
正確に言えば、何もしないのではなく、
何が必要なのかを身体が表現してくれるのを待ち、
サインが出てきたらそれをひたすら聴きながら追随するだけという感じです。
諸先輩に比べると、まだまだ経験が足りないのですが、
この方の場合、EV4が立て続けに起るという身体のサインが意味していたことは、
髄液の減少だったという体験を一つ得られたので、
シェアさせて頂きました。
近い体験もしくはアドバイスがあれば、伺いたいと思っています。
このトピがあり、いろいろ参照することができて、
大変助けになりました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラニオ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
クラニオのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90001人
- 3位
- 酒好き
- 170653人