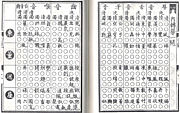主要な変化のみを挙げます。(随時補足)
1.上古音から中古音への変化
●舌頭音(t, t`, d, n)から舌上音(tj, tj`, dj, nj)が分化
*福建語はこの変化を経ていない
●侵部[-@m]の一部が [-iung]に変化
例「熊」「風」
2.前期中古音から後期中古音への変化
●唇音(p, p`, b, m)から軽唇音(pf, pf`, bv, mj)が分化
例「風」pIung > pfIung
●2種の拗介音 -I- / -i- の差がなくなる
●声母の清濁の別がなくなり始める(北方において)
3.中古音から『中原音韻』近古音への変化
●声母の清濁の別がなくなる(中古音期にすでに進行)
●舌上音(tj, tj`)が正歯音三等(tsj, tsj`)に合流
●入声韻尾(-p, -t, -k)が徐々に消失
●二等韻(狭いaなど)が拗介音を伴うようになる
例
「家」ka > kia
「佳」kai > kiai
「江」kaung > kiang
「夏」ha > hia
4.近古音から近代音への変化
●鼻音韻尾 -m が -n に合流
例「三」sam > san
●介音iの前で k, h が口蓋化する
例
「家」kia > chia
「江」kiang > chiang
「香」hiang > hsiang
●尖音と団音の区別がなくなる
例
「西」si:「希」hsi > hsi(xi)
「相」siang:「香」hsiang >hsiang(xiang)
1.上古音から中古音への変化
●舌頭音(t, t`, d, n)から舌上音(tj, tj`, dj, nj)が分化
*福建語はこの変化を経ていない
●侵部[-@m]の一部が [-iung]に変化
例「熊」「風」
2.前期中古音から後期中古音への変化
●唇音(p, p`, b, m)から軽唇音(pf, pf`, bv, mj)が分化
例「風」pIung > pfIung
●2種の拗介音 -I- / -i- の差がなくなる
●声母の清濁の別がなくなり始める(北方において)
3.中古音から『中原音韻』近古音への変化
●声母の清濁の別がなくなる(中古音期にすでに進行)
●舌上音(tj, tj`)が正歯音三等(tsj, tsj`)に合流
●入声韻尾(-p, -t, -k)が徐々に消失
●二等韻(狭いaなど)が拗介音を伴うようになる
例
「家」ka > kia
「佳」kai > kiai
「江」kaung > kiang
「夏」ha > hia
4.近古音から近代音への変化
●鼻音韻尾 -m が -n に合流
例「三」sam > san
●介音iの前で k, h が口蓋化する
例
「家」kia > chia
「江」kiang > chiang
「香」hiang > hsiang
●尖音と団音の区別がなくなる
例
「西」si:「希」hsi > hsi(xi)
「相」siang:「香」hsiang >hsiang(xiang)
|
|
|
|
コメント(5)
nhatさん、
冬部と侵部は同韻だったという説があります。詩経では、熊など中古音以降では-ung, -ongという韻をもつ一部の字が、「侵部」-əmの字と押韻されることがありました。また凡ボムと風フウという形声文字の声符も二つの韻が近かったことを裏付けていると考えられます。
章炳麟は上古の時期には冬部と侵部の韻が近かった、と考えたようです。王力は「冬部」を「侵部」に合一させています。(参照:王力『漢語音韻』中華書局)
*冬部と侵部の関係について、次のような記述を見つけましたので、
紹介いたします。↓
http://www.for.aichi-pu.ac.jp/museum/pdf/nohara49.pdf
>台湾語(ホーロー語、閩南語)でクマを< hîm >という こと を 根拠としているのでしょうか?
「熊」の字音についてですが、これは逆に、閩語が上古音の特徴をとどめていることの例として挙げられています。(三省堂『言語学大事典』閩南語の項)
とすれば、
>朝鮮語の < kom >と同系統の単語である。」と
逆に上古漢語の *hîəm が古代朝鮮語に借用されてそれが kom に成った
との解釈も成り立つのではないでしょうか。
冬部と侵部は同韻だったという説があります。詩経では、熊など中古音以降では-ung, -ongという韻をもつ一部の字が、「侵部」-əmの字と押韻されることがありました。また凡ボムと風フウという形声文字の声符も二つの韻が近かったことを裏付けていると考えられます。
章炳麟は上古の時期には冬部と侵部の韻が近かった、と考えたようです。王力は「冬部」を「侵部」に合一させています。(参照:王力『漢語音韻』中華書局)
*冬部と侵部の関係について、次のような記述を見つけましたので、
紹介いたします。↓
http://www.for.aichi-pu.ac.jp/museum/pdf/nohara49.pdf
>台湾語(ホーロー語、閩南語)でクマを< hîm >という こと を 根拠としているのでしょうか?
「熊」の字音についてですが、これは逆に、閩語が上古音の特徴をとどめていることの例として挙げられています。(三省堂『言語学大事典』閩南語の項)
とすれば、
>朝鮮語の < kom >と同系統の単語である。」と
逆に上古漢語の *hîəm が古代朝鮮語に借用されてそれが kom に成った
との解釈も成り立つのではないでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
古漢語音韻学 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
古漢語音韻学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82540人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人