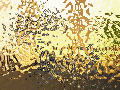パーテーションがしょぼいので、数でごまかそうとベランダのゴミ箱もUP
春に部屋を模様替えしたんだけど、ドアを開けるとベッドが丸見えになった。生活感がですぎなので(笑)、パーテーションを製作。
1連の高さ120×幅47で、枠の内側に柔らかい針金を入れて、風をある程度通す布を入れた。柔らかい針金なので、布は取り外し可能で汚れたら洗える。
動かしやすいように2連分だけキャスターをつけ、残り2連は余った板で台を作り安定させる。
ベランダ用のゴミ箱は、ビンや金属系など台所に置くほど頻繁にでないゴミ用です。
置き場所はエアコンの室外機の上にして、ベランダが狭くならないようにしました。
室外機とゴミ箱の中に入れているプラ箱(100均で買って使わなくなったもの)のサイズがちょうど合うように設定。
中の掃除を簡単にできるようゴミ箱の前板は、板が取り外せるようになっています。
春に部屋を模様替えしたんだけど、ドアを開けるとベッドが丸見えになった。生活感がですぎなので(笑)、パーテーションを製作。
1連の高さ120×幅47で、枠の内側に柔らかい針金を入れて、風をある程度通す布を入れた。柔らかい針金なので、布は取り外し可能で汚れたら洗える。
動かしやすいように2連分だけキャスターをつけ、残り2連は余った板で台を作り安定させる。
ベランダ用のゴミ箱は、ビンや金属系など台所に置くほど頻繁にでないゴミ用です。
置き場所はエアコンの室外機の上にして、ベランダが狭くならないようにしました。
室外機とゴミ箱の中に入れているプラ箱(100均で買って使わなくなったもの)のサイズがちょうど合うように設定。
中の掃除を簡単にできるようゴミ箱の前板は、板が取り外せるようになっています。
|
|
|
|
コメント(151)
プリンターをのせるためのスライドをスチールラックに取り付けました。ラックの枠にスライド部分がぶつかってしまうため、もう一枚間に木を挟んだり・・・思った以上に木材が硬くてネジが入らず、バカにしてしまったり・・・何度も試行錯誤しながら3時間程かかってやっと完了しました!
スライド自体は重量45キロまで大丈夫って書いてありましたが、自分の仕事は信用してないので、スライドは必要な時しか使わない方向でσ(^_^;)
使用した木材は、廃棄処分だった家具の一部と無垢の端材です。
一枚目は設置完了後、無垢材部分にブライワックスで色塗りしました。
二枚目は設置完了直後に、スライドの滑り具合を確認中です。
スライド自体は重量45キロまで大丈夫って書いてありましたが、自分の仕事は信用してないので、スライドは必要な時しか使わない方向でσ(^_^;)
使用した木材は、廃棄処分だった家具の一部と無垢の端材です。
一枚目は設置完了後、無垢材部分にブライワックスで色塗りしました。
二枚目は設置完了直後に、スライドの滑り具合を確認中です。
「先端農業技術体験フェア」
農作業の効率化に向けた最先端の機械や技術を紹介する
国と福島県の主催で東京電力福島第一原発事故で避難区域が設定された地域での営農再開や生産規模拡大を支援する。
1..農薬散布や農地のデータ収集に活用できる農業用のドローン(小型無人機)を実演する。
2..無人で農作業ができる「ロボットトラクタ」
3..農家の作業負担を軽減するアシストスーツ、
4..人工知能(AI)を活用した生産者支援サービスや農作業の記録システム
5..除草ロボットなども紹介する。
午後零時半からは講演を行う。舞台アグリイノベーションの針生信夫社長が日本の農業の展望を語る。
27日正午から福島県南相馬市原町区の県立テクノアカデミー浜で開かれる。
「先端農業技術体験フェア」は福島・国際研究産業都市構想。
参加無料で、21日まで申し込みを受け付けている。
申し込み、問い合わせは福島県フェア事務局へ。
農作業の効率化に向けた最先端の機械や技術を紹介する
国と福島県の主催で東京電力福島第一原発事故で避難区域が設定された地域での営農再開や生産規模拡大を支援する。
1..農薬散布や農地のデータ収集に活用できる農業用のドローン(小型無人機)を実演する。
2..無人で農作業ができる「ロボットトラクタ」
3..農家の作業負担を軽減するアシストスーツ、
4..人工知能(AI)を活用した生産者支援サービスや農作業の記録システム
5..除草ロボットなども紹介する。
午後零時半からは講演を行う。舞台アグリイノベーションの針生信夫社長が日本の農業の展望を語る。
27日正午から福島県南相馬市原町区の県立テクノアカデミー浜で開かれる。
「先端農業技術体験フェア」は福島・国際研究産業都市構想。
参加無料で、21日まで申し込みを受け付けている。
申し込み、問い合わせは福島県フェア事務局へ。
スマート農業で耕作放棄地復元へ
設立したのは白山AIファーム株式会社(本社福井市開発4丁目)。5月に法人登記し、社長は野坂氏が務める。
野坂社長は「県内をはじめ日本の農業者はどんどん高齢化し、農業を続けられなくなっている」と危機を感じた。
県内で広く農地の提供者を募り、越前、大野、勝山、福井、あわらの5市で計13・65ヘクタールを借りたり購入したりして確保。
クリ、ナシ、ブドウの果樹やコメ、ソバなど、さまざまな農産物を生産していく。
本格的な活動は、11月にクリの木の植樹から始める計画。13・65ヘクタールのうち3分の2は中山間地という。
小型無人機ドローンも使いながらイノシシやサルなどの獣害を防ぎ、山林との境界の明確化にも努める。
衛星利用測位システム(GPS)やICTなどを駆使した「スマート農業」で若者の就農への魅力を高め、耕作放棄地の増大に歯止めをかけたいという。
人工知能(AI)や情報通信技術(ICT)を駆使して福井県内の耕作放棄地復元に取り組むとともに、都市部の若者のIターンやUターンを促して5年で計700人の採用を計画。
福井の農業の再生・発展を図りながら、後継者育成や人口減の抑制につなげていく。
若者の採用は東京、京都、名古屋などの大学と連携し、福井大の県外出身者を含め既に6人が入社の見込みとなった。
農業向けAIシステムや、GPSを利用した農機、水田への給水やハウス内の温度を管理するICTを順次導入していく計画です。
野坂社長は「若者の活躍の場は広い。農業を楽しく、新しいものにしたい」と意欲を示している。
設立したのは白山AIファーム株式会社(本社福井市開発4丁目)。5月に法人登記し、社長は野坂氏が務める。
野坂社長は「県内をはじめ日本の農業者はどんどん高齢化し、農業を続けられなくなっている」と危機を感じた。
県内で広く農地の提供者を募り、越前、大野、勝山、福井、あわらの5市で計13・65ヘクタールを借りたり購入したりして確保。
クリ、ナシ、ブドウの果樹やコメ、ソバなど、さまざまな農産物を生産していく。
本格的な活動は、11月にクリの木の植樹から始める計画。13・65ヘクタールのうち3分の2は中山間地という。
小型無人機ドローンも使いながらイノシシやサルなどの獣害を防ぎ、山林との境界の明確化にも努める。
衛星利用測位システム(GPS)やICTなどを駆使した「スマート農業」で若者の就農への魅力を高め、耕作放棄地の増大に歯止めをかけたいという。
人工知能(AI)や情報通信技術(ICT)を駆使して福井県内の耕作放棄地復元に取り組むとともに、都市部の若者のIターンやUターンを促して5年で計700人の採用を計画。
福井の農業の再生・発展を図りながら、後継者育成や人口減の抑制につなげていく。
若者の採用は東京、京都、名古屋などの大学と連携し、福井大の県外出身者を含め既に6人が入社の見込みとなった。
農業向けAIシステムや、GPSを利用した農機、水田への給水やハウス内の温度を管理するICTを順次導入していく計画です。
野坂社長は「若者の活躍の場は広い。農業を楽しく、新しいものにしたい」と意欲を示している。
今秋のテレビにAI番組が5本も
今秋始まった『人間ってナンだ?超AI入門』(公式HPより)
この秋の番組改編で多くの新番組が登場したが、そのなかのひとつにAI(人工知能)を使ったものがある。なんと一気に5本も始まったのだ。私たちの暮らしを大きく変えるといわれるAIは、テレビ番組をどう変えるのか。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。
* * *
「よく5本もそろったな」という印象です。まず6日に『人間ってナンだ?超AI入門』(NHK Eテレ、金曜22時〜)がスタート。最新の人工知能を楽しく学ぶ教養エンタメ番組で、第1回は「会話」をテーマに放送されました。
2本目は、23日スタートの『AI-TV』(フジテレビ系、月曜23時〜)。「AIが考えた企画案をもとに番組を作る」というコンセプトの実験的な番組です。
3本目は、スタート日時未定の『ロボット旅 日本一周〜タカラモノクダサイ〜』(テレビ朝日系、日曜14時40分〜)。「二足歩行ロボと芸能人が旅に出て、全国の宝物を探す」という内容で、今年6月に放送された単発番組が早くもレギュラー化されました。
4本目は、2日と9日の前後編で放送するドラマ『アイ〜私と彼女と人工知能』(フジテレビ系、月曜25時25分〜)。イケメンAI(志尊淳)と2人の20代女性(香里奈、池田エライザ)との共同生活を描く恋愛コメディです。
5本目は、放送中のドラマ『トットちゃん!』(テレビ朝日系、月〜金曜12時30分〜)。黒柳徹子さんのアンドロイド「totto」が、劇中ではなく、番宣などでスポット的に出演しています。
今秋始まった『人間ってナンだ?超AI入門』(公式HPより)
この秋の番組改編で多くの新番組が登場したが、そのなかのひとつにAI(人工知能)を使ったものがある。なんと一気に5本も始まったのだ。私たちの暮らしを大きく変えるといわれるAIは、テレビ番組をどう変えるのか。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。
* * *
「よく5本もそろったな」という印象です。まず6日に『人間ってナンだ?超AI入門』(NHK Eテレ、金曜22時〜)がスタート。最新の人工知能を楽しく学ぶ教養エンタメ番組で、第1回は「会話」をテーマに放送されました。
2本目は、23日スタートの『AI-TV』(フジテレビ系、月曜23時〜)。「AIが考えた企画案をもとに番組を作る」というコンセプトの実験的な番組です。
3本目は、スタート日時未定の『ロボット旅 日本一周〜タカラモノクダサイ〜』(テレビ朝日系、日曜14時40分〜)。「二足歩行ロボと芸能人が旅に出て、全国の宝物を探す」という内容で、今年6月に放送された単発番組が早くもレギュラー化されました。
4本目は、2日と9日の前後編で放送するドラマ『アイ〜私と彼女と人工知能』(フジテレビ系、月曜25時25分〜)。イケメンAI(志尊淳)と2人の20代女性(香里奈、池田エライザ)との共同生活を描く恋愛コメディです。
5本目は、放送中のドラマ『トットちゃん!』(テレビ朝日系、月〜金曜12時30分〜)。黒柳徹子さんのアンドロイド「totto」が、劇中ではなく、番宣などでスポット的に出演しています。
有明貯水池(ため池)浮かぶ太陽光発電
有明海近くの有明貯水池(杵島郡白石町)が、陽光をキラリと反射した。風に乗って近づくと、光ったのは水面(みなも)ではなく、水上に浮かんだ太陽光パネルだった。
これは全国最大規模のメガソーラー(大規模太陽光発電所)で、約9500枚のパネルがぎょろりと太陽を凝視する。
長方形をした藍色のパネルが連なる様子は、どこか周りの佐賀平野にも似ていた。
白石町と全国で太陽光発電事業を手掛けるウエストエネルギーソリューション(広島市)が2年前に協定を結び、昨年3月から稼働を始めた。
同社によると、昨年度は、一般家庭約920世帯に相当する3036メガワット時を発電した。
パネルが見上げる先には秋晴れの空。たまには日の光を浴びながら、のんびり充電するのもいいかもしれない。
有明海近くの有明貯水池(杵島郡白石町)が、陽光をキラリと反射した。風に乗って近づくと、光ったのは水面(みなも)ではなく、水上に浮かんだ太陽光パネルだった。
これは全国最大規模のメガソーラー(大規模太陽光発電所)で、約9500枚のパネルがぎょろりと太陽を凝視する。
長方形をした藍色のパネルが連なる様子は、どこか周りの佐賀平野にも似ていた。
白石町と全国で太陽光発電事業を手掛けるウエストエネルギーソリューション(広島市)が2年前に協定を結び、昨年3月から稼働を始めた。
同社によると、昨年度は、一般家庭約920世帯に相当する3036メガワット時を発電した。
パネルが見上げる先には秋晴れの空。たまには日の光を浴びながら、のんびり充電するのもいいかもしれない。
ドローン-農業機械-建築機械の自動運転へ
日本版GPS衛星「みちびき」4号機打ち上げ
スマートフォンなどの位置情報システムの性能を飛躍的に高める日本版GPS衛星「みちびき」の4号機が、10月10日午前7時すぎ、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。
打ち上げが成功すれば、GPSの位置情報の誤差を現在の最大10メートルほどから数センチにまで小さくし、建設機械の自動運転など社会のさまざまな分野で新たなサービスが展開できると期待されています。
日本版GPS衛星、「みちびき」の4号機を載せたH2Aロケット36号機は、9日種子島宇宙センターにある建物から発射場に移され、現在、打ち上げに向けた最終的な点検作業が進められています。
「みちびき」はアメリカのGPS衛星のように位置情報が得られる衛星で、打ち上げは、ことし8月の3号機に続き、4機目です。
今回の打ち上げによってみちびきの4機体制が整い、来年春に本格運用が始まれば、GPSの位置情報の誤差を現在の最大10メートルほどから数センチにまで小さくできるということです。
これによって農業機械や建設機械の自動運転、それにドローンによる物資の輸送など社会のさまざまな分野で新たなサービスが展開できると期待されています。
「みちびき」の4号機を載せたH2Aロケット36号機は10月10日午前7時1分ごろ打ち上げられる予定で、30分ほどで打ち上げの成否が判明するということです。
日本版GPS衛星「みちびき」4号機打ち上げ
スマートフォンなどの位置情報システムの性能を飛躍的に高める日本版GPS衛星「みちびき」の4号機が、10月10日午前7時すぎ、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。
打ち上げが成功すれば、GPSの位置情報の誤差を現在の最大10メートルほどから数センチにまで小さくし、建設機械の自動運転など社会のさまざまな分野で新たなサービスが展開できると期待されています。
日本版GPS衛星、「みちびき」の4号機を載せたH2Aロケット36号機は、9日種子島宇宙センターにある建物から発射場に移され、現在、打ち上げに向けた最終的な点検作業が進められています。
「みちびき」はアメリカのGPS衛星のように位置情報が得られる衛星で、打ち上げは、ことし8月の3号機に続き、4機目です。
今回の打ち上げによってみちびきの4機体制が整い、来年春に本格運用が始まれば、GPSの位置情報の誤差を現在の最大10メートルほどから数センチにまで小さくできるということです。
これによって農業機械や建設機械の自動運転、それにドローンによる物資の輸送など社会のさまざまな分野で新たなサービスが展開できると期待されています。
「みちびき」の4号機を載せたH2Aロケット36号機は10月10日午前7時1分ごろ打ち上げられる予定で、30分ほどで打ち上げの成否が判明するということです。
番外編です。(^_^)v
映画「ドリーム私たちのアポロ計画」
「ドリーム 私たちのアポロ計画」は、東京・TOHOシネマズシャンテほかで9月29日(金)よりいよいよ公開される。
日の目を見なかった三人の黒人女性「縁の下の力持ち」を称賛
1960年代初頭、ときは東西冷戦の時代。アメリカにとって宇宙開発は、ソ連と張り合う、国の威信を賭けた一大プロジェクトだった。合衆国悲願の有人飛行計画を実現するべく、NASAは懸命な毎日を送っている。
そこには、ロケットの打ち上げに必要な「計算」を行う、黒人女性たちのグループがあった。
『ドリーム』は、そのうちの3人にスポットを当て、ともすれば歴史の中で日の目を見なかった「縁の下の力持ち」を心から称賛する感動のドラマなのだ。
アメリカ映画には、マイノリティを肯定する精神がある。
なぜなら、移民が作り上げた国だからだ。それぞれが「違う出自」の人間たち。だが、争ったり、ぶつかったりするのではない、違うやり方で、互いを高め合うことができるのではないか。そんな真っ当な可能性を求めて、アメリカ映画は形作られている。このことは、どんなに時代が変わろうと普遍のものとして存在する。
いまにつながる逆境で働くことの意義
『ドリーム』が描く1960年代初頭は、黒人というだけで、どんなに才能があっても活躍を許されない時代だった。
主人公の一人は、幼い頃から天才数学少女として評価されるが、ようやく配属された宇宙特別研究本部はオール白人男性の職場であり、どこか排他的。
また、別の主人公は、技術者養成プログラムを受けたいと思っても、学校が白人専用の姿勢を崩さないため、学ぶ自由を得られなかった。
さらに、彼女たちは女性であり、黒人であること。そして、それぞれに家庭があること。この3つが、働く上でどれだけの「制限」であるか。
女性を取り巻く環境は、いまも大本では根本的に改善されているわけではない。だからこそ、『ドリーム』の女性たちの踏ん張りが胸を熱くする。
『ドリーム』に登場する白人男性の中にも、きちんと彼女たちの才能を認める人間は存在する。本作では、そこを丹念に描いている。
必ず誰かは見ていてくれるのだと。印象的なのは、技術者養成プログラムを受けるために、裁判所に誓願した女性の言葉だ。彼女は、裁判長にこう訴える。
「偉大なる前例を作りませんか?あなたは、何十年後かに、その前例を作った人物になるのですよ」。
この映画は実話である。未来のために「前例」を作ること。それはたやすいことではないが、きわめて尊い。
この映画が、多くの人に愛されている理由は、誇り高き「前例」の物語であるからに他ならない。
映画「ドリーム私たちのアポロ計画」
「ドリーム 私たちのアポロ計画」は、東京・TOHOシネマズシャンテほかで9月29日(金)よりいよいよ公開される。
日の目を見なかった三人の黒人女性「縁の下の力持ち」を称賛
1960年代初頭、ときは東西冷戦の時代。アメリカにとって宇宙開発は、ソ連と張り合う、国の威信を賭けた一大プロジェクトだった。合衆国悲願の有人飛行計画を実現するべく、NASAは懸命な毎日を送っている。
そこには、ロケットの打ち上げに必要な「計算」を行う、黒人女性たちのグループがあった。
『ドリーム』は、そのうちの3人にスポットを当て、ともすれば歴史の中で日の目を見なかった「縁の下の力持ち」を心から称賛する感動のドラマなのだ。
アメリカ映画には、マイノリティを肯定する精神がある。
なぜなら、移民が作り上げた国だからだ。それぞれが「違う出自」の人間たち。だが、争ったり、ぶつかったりするのではない、違うやり方で、互いを高め合うことができるのではないか。そんな真っ当な可能性を求めて、アメリカ映画は形作られている。このことは、どんなに時代が変わろうと普遍のものとして存在する。
いまにつながる逆境で働くことの意義
『ドリーム』が描く1960年代初頭は、黒人というだけで、どんなに才能があっても活躍を許されない時代だった。
主人公の一人は、幼い頃から天才数学少女として評価されるが、ようやく配属された宇宙特別研究本部はオール白人男性の職場であり、どこか排他的。
また、別の主人公は、技術者養成プログラムを受けたいと思っても、学校が白人専用の姿勢を崩さないため、学ぶ自由を得られなかった。
さらに、彼女たちは女性であり、黒人であること。そして、それぞれに家庭があること。この3つが、働く上でどれだけの「制限」であるか。
女性を取り巻く環境は、いまも大本では根本的に改善されているわけではない。だからこそ、『ドリーム』の女性たちの踏ん張りが胸を熱くする。
『ドリーム』に登場する白人男性の中にも、きちんと彼女たちの才能を認める人間は存在する。本作では、そこを丹念に描いている。
必ず誰かは見ていてくれるのだと。印象的なのは、技術者養成プログラムを受けるために、裁判所に誓願した女性の言葉だ。彼女は、裁判長にこう訴える。
「偉大なる前例を作りませんか?あなたは、何十年後かに、その前例を作った人物になるのですよ」。
この映画は実話である。未来のために「前例」を作ること。それはたやすいことではないが、きわめて尊い。
この映画が、多くの人に愛されている理由は、誇り高き「前例」の物語であるからに他ならない。
1分に1枚1400枚の写真をAIが学習!
トマトの高糖度はAIにお任せ
静岡大学、葉の状態監視、技術開発
トマトの成育を3段摘芯の栽培で試験した。(1)茎頂部の草姿写真(2)温度(3)湿度(4)照度――のデータをAIに学習させた。成育を1分に1枚撮影し、しおれる動きが大きい部分だけ抽出したものを、1400枚使い、AIに記憶させた。
葉がしおれる時に茎がごくわずかに細くなることが分かっているが、学習したAIは高精度で予測し、かん水の量とタイミングを判断できることを確かめた。
静岡大学は、人工知能(AI)を使い誰でも高糖度トマト(フルーツトマト)を安定生産できる養液栽培技術を開発した。
AIが葉のしおれや環境データを基に「トマトのストレス度合い」を瞬時に推測し、かん水量を調節する。
熟練者の経験と勘が必要だった高糖度化までの水管理を自動化することで、糖度8以上の果実が安定して生産できる見込みだ。
高糖度トマトは、かん水を抑えて糖度を高める。生育と糖度を両立させる水管理が難しい。同大は熟練農家が、葉のしおれ具合や光沢を見ていることに注目。葉の様子をAIに学ばせて、熟練農家並みのかん水量判断ができるか検討した。
同大学術院情報学領域の峰野博史准教授は「(AIの予測通りにかん水すれば)糖度8以上の果実を安定生産できる」とみている。熟練農家の技術を数値化できるため、技術の継承にもつながると期待する。今後、現地試験を進める予定だ。
トマトの高糖度はAIにお任せ
静岡大学、葉の状態監視、技術開発
トマトの成育を3段摘芯の栽培で試験した。(1)茎頂部の草姿写真(2)温度(3)湿度(4)照度――のデータをAIに学習させた。成育を1分に1枚撮影し、しおれる動きが大きい部分だけ抽出したものを、1400枚使い、AIに記憶させた。
葉がしおれる時に茎がごくわずかに細くなることが分かっているが、学習したAIは高精度で予測し、かん水の量とタイミングを判断できることを確かめた。
静岡大学は、人工知能(AI)を使い誰でも高糖度トマト(フルーツトマト)を安定生産できる養液栽培技術を開発した。
AIが葉のしおれや環境データを基に「トマトのストレス度合い」を瞬時に推測し、かん水量を調節する。
熟練者の経験と勘が必要だった高糖度化までの水管理を自動化することで、糖度8以上の果実が安定して生産できる見込みだ。
高糖度トマトは、かん水を抑えて糖度を高める。生育と糖度を両立させる水管理が難しい。同大は熟練農家が、葉のしおれ具合や光沢を見ていることに注目。葉の様子をAIに学ばせて、熟練農家並みのかん水量判断ができるか検討した。
同大学術院情報学領域の峰野博史准教授は「(AIの予測通りにかん水すれば)糖度8以上の果実を安定生産できる」とみている。熟練農家の技術を数値化できるため、技術の継承にもつながると期待する。今後、現地試験を進める予定だ。
宇宙ビジネスアイデアコンテト「S-Booster 2017」、10月30日に最終選抜会開催
S-Booster 2017の概要
◆宇宙のアセット「通信、地球観測、測位、有人宇宙活動、宇宙輸送等の宇宙技術やそこで取得した衛星データや運用ノウハウ等、全てが対象」を利用した、新たなビジネスモデル等の発掘等を目的に、ビジネスアイデアコンテストを実施。
◆ベンチャー企業のみならず、学生や個人、異業種のアイデアなども幅広く集め、事業化の可能性検討などの支援を行う。
内閣府宇宙開発戦略推進事務局、JAXA、ANAホールディングス、三井物産、大林組、スカパーJSATらが開催している宇宙ビジネスアイディアコンテンスト
「SBooster 2017(エスブースタ2017)」
そして10月30日の最終選抜会では15組のファイナリストがそれぞれの事業提案のプレゼンテーションを行い、大賞(賞金300万円)、各スポンサー賞(賞金100万円)、審査員特別賞(賞金10万円)が決定されるのです。
当日のイベントの模様はニコニコ生放送で13時50分から配信される他、宇宙飛行士の若田光一さんや女優の剛力彩芽さんも登壇するとのこと。
視聴URLはこちらからどうぞ。
ニコニコ生放送によるライブ配信 (13:50より会場から生中継)
http://live.nicovideo.jp/gate/lv307551745
【公式ホームページ】
https://s-booster.jp/
【参考】
https://youtu.be/swAsGvDa8NA
「国際協力」
○中国の宇宙で一帯一路
○中国の宇宙ステーション開発
○北京大学で仮想宇宙生活の実験
○NASAがCCPを推進
○HPEとNASAがISSで使用するスパコン
○国際宇宙ステーションの参加
○JAXAとアメリカで人類月面探査
○アメリカと観測衛星
深宇宙気候観測衛星
地球観測衛星
軌道上炭素観測衛星
放射収支観測衛星
○インドと月面探査
○フランスと火星探査機
○トルコと通信衛星
○月の地面の下に、全長50kmにもおよぶ巨大な空洞が広がっている――。そんなSF的な想像をいろいろとかき立てられる研究結果を、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2017年10月18日に発表した。
○EUアリアン社は、月面で3Dプリンタを使って月の表土から宇宙基地を作る計画
「JAXAと民間の開発」
○総務省、火星の生命体を電磁波で調査
○JAXA三菱が英通信衛星打ち上げ受注
○JAXA-IHI-キャノンでミニロケット
○JAXA、欧州水星探査衛星
○JAXA、ミニロケット開発
○JAXAと信州大学、森林の観測衛星
○JAXAと千葉大学、レーダー観測衛星
○JAXAと埼玉大学、天体観測
○JAXAと気象庁で集中豪雨観測
○JAXAと京大でGPSデータ地震予知
○JAXAと大阪工業大で掌size人工衛星
○JAXAとFedxが乱気流の予測
○JAXAと国土地理院が活断層の観測
「GPSと地球資源の開発」
GPSで富士山の環境調査
GPSで地震予知
GPSでインフラの劣化調査
GPSでゲリラ豪雨の予測
GPS海流と漁獲量の予測
GPSを利用した「先物取引」
(石油タンカー-大豆の生産-駐車場の車)
GPSを使い海上保安庁は中国の領海侵入対策や海難救助に利用
S-Booster 2017の概要
◆宇宙のアセット「通信、地球観測、測位、有人宇宙活動、宇宙輸送等の宇宙技術やそこで取得した衛星データや運用ノウハウ等、全てが対象」を利用した、新たなビジネスモデル等の発掘等を目的に、ビジネスアイデアコンテストを実施。
◆ベンチャー企業のみならず、学生や個人、異業種のアイデアなども幅広く集め、事業化の可能性検討などの支援を行う。
内閣府宇宙開発戦略推進事務局、JAXA、ANAホールディングス、三井物産、大林組、スカパーJSATらが開催している宇宙ビジネスアイディアコンテンスト
「SBooster 2017(エスブースタ2017)」
そして10月30日の最終選抜会では15組のファイナリストがそれぞれの事業提案のプレゼンテーションを行い、大賞(賞金300万円)、各スポンサー賞(賞金100万円)、審査員特別賞(賞金10万円)が決定されるのです。
当日のイベントの模様はニコニコ生放送で13時50分から配信される他、宇宙飛行士の若田光一さんや女優の剛力彩芽さんも登壇するとのこと。
視聴URLはこちらからどうぞ。
ニコニコ生放送によるライブ配信 (13:50より会場から生中継)
http://live.nicovideo.jp/gate/lv307551745
【公式ホームページ】
https://s-booster.jp/
【参考】
https://youtu.be/swAsGvDa8NA
「国際協力」
○中国の宇宙で一帯一路
○中国の宇宙ステーション開発
○北京大学で仮想宇宙生活の実験
○NASAがCCPを推進
○HPEとNASAがISSで使用するスパコン
○国際宇宙ステーションの参加
○JAXAとアメリカで人類月面探査
○アメリカと観測衛星
深宇宙気候観測衛星
地球観測衛星
軌道上炭素観測衛星
放射収支観測衛星
○インドと月面探査
○フランスと火星探査機
○トルコと通信衛星
○月の地面の下に、全長50kmにもおよぶ巨大な空洞が広がっている――。そんなSF的な想像をいろいろとかき立てられる研究結果を、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2017年10月18日に発表した。
○EUアリアン社は、月面で3Dプリンタを使って月の表土から宇宙基地を作る計画
「JAXAと民間の開発」
○総務省、火星の生命体を電磁波で調査
○JAXA三菱が英通信衛星打ち上げ受注
○JAXA-IHI-キャノンでミニロケット
○JAXA、欧州水星探査衛星
○JAXA、ミニロケット開発
○JAXAと信州大学、森林の観測衛星
○JAXAと千葉大学、レーダー観測衛星
○JAXAと埼玉大学、天体観測
○JAXAと気象庁で集中豪雨観測
○JAXAと京大でGPSデータ地震予知
○JAXAと大阪工業大で掌size人工衛星
○JAXAとFedxが乱気流の予測
○JAXAと国土地理院が活断層の観測
「GPSと地球資源の開発」
GPSで富士山の環境調査
GPSで地震予知
GPSでインフラの劣化調査
GPSでゲリラ豪雨の予測
GPS海流と漁獲量の予測
GPSを利用した「先物取引」
(石油タンカー-大豆の生産-駐車場の車)
GPSを使い海上保安庁は中国の領海侵入対策や海難救助に利用
ICTを活用して“主体的な学び”を引き出す
今、学校ではICT(情報通信技術)を活用したさまざまな授業が行われています。デジタル機器やインターネットを取り入れることで、子どもたちの学びはどう変わっていくのでしょう。ICTを活用した授業の現状と、そこから見えてくる今後の学びの可能性についてお話しいたします。
●外国の中学生とテレビ会議も 〜ICTを活用した授業の最前線〜
ICTを活用した授業というと、どのような学びをイメージしますか?
文部科学省の「学びのイノベーション事業」では、平成23年度より全国20校の実証校(小・中学校、特別支援学校)を対象に、一人一台の情報端末、電子黒板、無線LANなどが整備された環境のもとで、ICTを活用して子どもたちが主体的に学習する「新しい学び」を創造するための実証研究を実施してきました。
・国語(小学校)
タブレット端末で教材本文を読みながら、重要な文や語句に傍線を引いたり、自分の考えをワークシートに入力したりしたものを電子黒板に映して、なぜそう考えたのかを説明します。自分と友だちの意見を比べることを通じて、多様な考え方に触れたり、文章の内容をより深く的確に捉えたりすることができます。
・英語(中学校)
テレビ会議システムを使って外国の中学生と自国・他国の文化について英語で伝え合います。どのような表現をすればより明確に伝わるかを考えることで、英語に関する表現力が育まれます。
・体育(小学校)
マット運動や跳び箱などでは、自分がどのような動きをしているのかを自分自身で見る機会がなかなかありません。タブレット端末の録画機能を使えば、その場で自分の動きを確認したり見本の動画と比較したりして、修正ポイントを自覚しながら、技能の向上を図ることができます。
ほかにも、中学校の社会では、インターネットなどを用いて課題についての資料を収集し、電子模造紙やプレゼンテーションソフトを使ってまとめたり、グループで議論したりします。数学では、デジタル教材のシミュレーション機能を使って立体図形のイメージをつかんだりと、より深い学びを実現する授業が行われています。
もちろん、ここで紹介した授業は先進的な事例ですが少しずつ広まっており、将来的にはこのような授業がどこの学校でも行われ、子どもたちの学びが大きく変わっていくことは間違いないでしょう。
ICTを活用した授業は、次のような学習効果があるとされています。
(1)映像や音声などを用いて、子どもたちがわかりやすい授業を実現できる
(2)学ぶ内容のレベルやスピードを、一人ひとりの理解の状況や特性に応じて合わせることができる(個別学習)
(3)子ども同士が意見を共有しながら異なる考え方に気づいたり、話し合いを通じて自分の考えを深めたりすることができる(協働学習)
このような効果が期待できるICTを活用した授業は、次期学習指導要領を通じて実現しようとしている「新しい学び」を推進するものとして期待されています。
今、学校ではICT(情報通信技術)を活用したさまざまな授業が行われています。デジタル機器やインターネットを取り入れることで、子どもたちの学びはどう変わっていくのでしょう。ICTを活用した授業の現状と、そこから見えてくる今後の学びの可能性についてお話しいたします。
●外国の中学生とテレビ会議も 〜ICTを活用した授業の最前線〜
ICTを活用した授業というと、どのような学びをイメージしますか?
文部科学省の「学びのイノベーション事業」では、平成23年度より全国20校の実証校(小・中学校、特別支援学校)を対象に、一人一台の情報端末、電子黒板、無線LANなどが整備された環境のもとで、ICTを活用して子どもたちが主体的に学習する「新しい学び」を創造するための実証研究を実施してきました。
・国語(小学校)
タブレット端末で教材本文を読みながら、重要な文や語句に傍線を引いたり、自分の考えをワークシートに入力したりしたものを電子黒板に映して、なぜそう考えたのかを説明します。自分と友だちの意見を比べることを通じて、多様な考え方に触れたり、文章の内容をより深く的確に捉えたりすることができます。
・英語(中学校)
テレビ会議システムを使って外国の中学生と自国・他国の文化について英語で伝え合います。どのような表現をすればより明確に伝わるかを考えることで、英語に関する表現力が育まれます。
・体育(小学校)
マット運動や跳び箱などでは、自分がどのような動きをしているのかを自分自身で見る機会がなかなかありません。タブレット端末の録画機能を使えば、その場で自分の動きを確認したり見本の動画と比較したりして、修正ポイントを自覚しながら、技能の向上を図ることができます。
ほかにも、中学校の社会では、インターネットなどを用いて課題についての資料を収集し、電子模造紙やプレゼンテーションソフトを使ってまとめたり、グループで議論したりします。数学では、デジタル教材のシミュレーション機能を使って立体図形のイメージをつかんだりと、より深い学びを実現する授業が行われています。
もちろん、ここで紹介した授業は先進的な事例ですが少しずつ広まっており、将来的にはこのような授業がどこの学校でも行われ、子どもたちの学びが大きく変わっていくことは間違いないでしょう。
ICTを活用した授業は、次のような学習効果があるとされています。
(1)映像や音声などを用いて、子どもたちがわかりやすい授業を実現できる
(2)学ぶ内容のレベルやスピードを、一人ひとりの理解の状況や特性に応じて合わせることができる(個別学習)
(3)子ども同士が意見を共有しながら異なる考え方に気づいたり、話し合いを通じて自分の考えを深めたりすることができる(協働学習)
このような効果が期待できるICTを活用した授業は、次期学習指導要領を通じて実現しようとしている「新しい学び」を推進するものとして期待されています。
2020年度から小学校でプログラミング教育が必修に。
ディープラーニングを含む、機械学習などを習練した“先端IT人材”は圧倒的に不足しているといわれてます。経済産業省が出した予測では、2020年には約4万8000人が不足するとしており、人工知能のビジネス活用が遅れる要因の1つとして挙げられています。
●小学生に「プログラミング教育」
小学生のうちからコーディングを学ぶようにも受け取れますが、そうではありません。同省は、プログラミング教育に対する有識者会議の結果を「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」として公表しています。その中で、プログラミング教育について、以下のように定義しています。
「プログラミング教育とは、子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」などを育むことであり、コーディングを覚えることが目的ではない」
ここで紹介している「プログラミング的思考」について、文中では「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つひとつの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」と紹介しています。
プログラミング教育の理念は素晴らしいものではあるものの、これを誰が、どのような教材を使って、何を教えるのかは不透明です。
報告書の文中にも、以下のような指導例はあります。特定の科目として設けるのではなく、総合学習、理科、算数、音楽など、あらゆる授業で、プログラミング的思考を用いた指導を行う方針のようですが、具体性を欠いていると言わざるを得ません。抽象度の高い、誰も反論できない高尚な理念だけが先行しているとも言えます。
●大学は「産業ニーズ」に応える組織であるべきか?
データサイエンティストの圧倒的な不足を背景に、文理を問わずSTEM教育(科学=Science、技術=Technology、工学=Engineering、数学=Mathematicsといった理工系教育分野の総称)の重要度が高まってきています。2017年4月には、滋賀大学に日本発のデータサイエンス学部が設置され、注目を集めました。
また、経済産業省が主催する産業構造審議会の新産業構造部会では、高等教育に「産業ニーズに応じた教育」が重要だと発表しています。人工知能が浸透する、この先の日本においては「実社会に欠かせないデータサイエンスの教育」という、教育界への要請は今後ますます強まるでしょう。
政府関係者もそう考えているようで、2014年5月6日に開催されたOECD閣僚理事会で、安倍首相は次のように講演しています。
「日本では、みんな横並び、単線型の教育ばかりを行ってきました。小学校6年、中学校3年、高校3年の後、理系学生の半分以上が、工学部の研究室に入る。こればかりを繰り返してきたのです。しかし、そうしたモノカルチャー型の高等教育では、斬新な発想は生まれません。だからこそ、私は、教育改革を進めています。学術研究を深めるのではなく、もっと社会のニーズを見据えた、もっと実践的な、職業教育を行う。そうした新たな枠組みを、高等教育に取り込みたいと考えています」
ディープラーニングを含む、機械学習などを習練した“先端IT人材”は圧倒的に不足しているといわれてます。経済産業省が出した予測では、2020年には約4万8000人が不足するとしており、人工知能のビジネス活用が遅れる要因の1つとして挙げられています。
●小学生に「プログラミング教育」
小学生のうちからコーディングを学ぶようにも受け取れますが、そうではありません。同省は、プログラミング教育に対する有識者会議の結果を「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」として公表しています。その中で、プログラミング教育について、以下のように定義しています。
「プログラミング教育とは、子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」などを育むことであり、コーディングを覚えることが目的ではない」
ここで紹介している「プログラミング的思考」について、文中では「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つひとつの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」と紹介しています。
プログラミング教育の理念は素晴らしいものではあるものの、これを誰が、どのような教材を使って、何を教えるのかは不透明です。
報告書の文中にも、以下のような指導例はあります。特定の科目として設けるのではなく、総合学習、理科、算数、音楽など、あらゆる授業で、プログラミング的思考を用いた指導を行う方針のようですが、具体性を欠いていると言わざるを得ません。抽象度の高い、誰も反論できない高尚な理念だけが先行しているとも言えます。
●大学は「産業ニーズ」に応える組織であるべきか?
データサイエンティストの圧倒的な不足を背景に、文理を問わずSTEM教育(科学=Science、技術=Technology、工学=Engineering、数学=Mathematicsといった理工系教育分野の総称)の重要度が高まってきています。2017年4月には、滋賀大学に日本発のデータサイエンス学部が設置され、注目を集めました。
また、経済産業省が主催する産業構造審議会の新産業構造部会では、高等教育に「産業ニーズに応じた教育」が重要だと発表しています。人工知能が浸透する、この先の日本においては「実社会に欠かせないデータサイエンスの教育」という、教育界への要請は今後ますます強まるでしょう。
政府関係者もそう考えているようで、2014年5月6日に開催されたOECD閣僚理事会で、安倍首相は次のように講演しています。
「日本では、みんな横並び、単線型の教育ばかりを行ってきました。小学校6年、中学校3年、高校3年の後、理系学生の半分以上が、工学部の研究室に入る。こればかりを繰り返してきたのです。しかし、そうしたモノカルチャー型の高等教育では、斬新な発想は生まれません。だからこそ、私は、教育改革を進めています。学術研究を深めるのではなく、もっと社会のニーズを見据えた、もっと実践的な、職業教育を行う。そうした新たな枠組みを、高等教育に取り込みたいと考えています」
11月9日(木)のEテレビ22時〜
『ドキュランドへ ようこそ!』
「ロボットがもたらす“仕事”の未来」と題して放送。オートメーション化!
アメリカの町で何が起こっているかを取材する。
舞台は、ニューヨーク郊外の町・ニューバード。工場や倉庫などで働く労働者たちの仕事は急速にロボットに奪われ、資格や学歴がない人たちは失業状況に追い込まれている。
新聞記事を書くソフトや自動車の無人運転など、複雑なアルゴリズムが可能となり、「ロボットにはできない」とされてきた職種は急激に減っている。
ロボットやAIが大半の仕事をこなす時代、我々人間は何をすればいいのか?
近未来、私たちの仕事がどうなっていくのかを探る。
『ドキュランドへ ようこそ!』
「ロボットがもたらす“仕事”の未来」と題して放送。オートメーション化!
アメリカの町で何が起こっているかを取材する。
舞台は、ニューヨーク郊外の町・ニューバード。工場や倉庫などで働く労働者たちの仕事は急速にロボットに奪われ、資格や学歴がない人たちは失業状況に追い込まれている。
新聞記事を書くソフトや自動車の無人運転など、複雑なアルゴリズムが可能となり、「ロボットにはできない」とされてきた職種は急激に減っている。
ロボットやAIが大半の仕事をこなす時代、我々人間は何をすればいいのか?
近未来、私たちの仕事がどうなっていくのかを探る。
大人の遠足-1/2
「宇宙開発や超伝導にふれる」
ニコニコ学会βサマーキャンプ2017
○野田司令、筑波研修センターに現れる
キャンプ2日目の9月3日、会場である茨城県つくば市の筑波研修センターに現れたのは野田司令こと野田篤司さん(以下、野田さん)。
野田さんは、世界で一番低い軌道を飛ぶ衛星(超低高度衛星)の概念設計を行ったJAXAの現役エンジニア、超低高度衛星は今年12月に打ち上げ予定だ。
あまり公になっていないが、インターステラテクノロジズにもかんでいたり、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』のSF設定に協力していたり、知る人ぞ知るのマッドサイエンティストだ。
研究所見学、JAXA筑波宇宙センターの見学に先立ち、野田さんから宇宙開発についてレクチャーがあるのだ。
▲野田さんのトークは、わかりやすく、おもしろい
野田さんは「誰でも宇宙にタッチできるような世界を作りたい」という。それには、今のような一機100億円もかかるようなロケットの作り方ではなく、もっと安いコストで、誰でも作れるようにならないと無理だ。
野田さんが、次に狙っているのは世界最軽量の人工衛星だ。いま世界的にどのくらいまで可能になっているかというと、今年7月に米国コーネル大学のザク・マンチェスター氏らにより開発され、宇宙へ打ち上げられた「Sprite」が4g。ということで、4g未満で実用に目処をつける衛星が狙うところだという。
▲JAXA筑波宇宙センター
筑波宇宙センターの位置付けについて。
これも野田さんがレクチャーしてくれたことだが、JAXAが持っている宇宙関係の施設のうち、種子島宇宙センター、内之浦宇宙空間観測所についで広いのが筑波宇宙センターだという。
種子島はロケット発射設備があるので広い。これは、ロケットが爆発しても外側に被害が広がらないように(ちなみに、ロケットの発射台がある射点は海に突き出し、山に囲まれているが、これは山を隔てることで爆発しても爆風が民家に行かないためにそうしている)。
一方、筑波宇宙センターはオフィス部分に加え、研究開発が行われている実験装置や試験装置を持つ。開発製造した人工衛星やロケットを打ち上げる前に宇宙空間で壊れないこと、動くことを試験するための機関ということになる。
また、人工衛星のコントロールを行う追跡管制設備、宇宙ステーションのコントロールを行うところ、宇宙飛行士が常駐しているところという面もある。
宇宙航空開発施設の一部を見学するツアー(有料:500円)もあるが、今回は残念ながら、スペースドームのみ。スペースドームは一般に公開されている無料の展示スペースで、人工衛星のフライトモデルなどが展示されている。
人工衛星というと一点ものというイメージだが、同じものを複数個作るのだ。1つは前述のように過酷な試験を行い、宇宙空間で動くことを徹底的に試す。こうした人工衛星や宇宙ステーションのモックアップなどが展示されている。
▲月周回衛星「かぐや」(実物大の試験機)
▲実験用中型放送衛星「ゆり」(実物大の試験機)
▲データ中継技術衛星「こだま」(実物大の試験機)
▲「きぼう」は、国際宇宙ステーション(ISS)の一部として機能する日本の宇宙実験棟。スペースドームにはそのモックアップがあり、中にも入れるようになっている
「きぼう」モックアップの中に入ったところで、野田さんからの問題が来た。
「何か、気づきませんか? 宇宙ステーションの内部はこうなっているんですが……」と。
答えは、「上下をわざと作っている」こと。
本来、宇宙空間には上下はないので、すべての面に操作スイッチをつけてもいいが、上には明るい照明を付け、下には暗くして、区別をつけている。
1970年代にアメリカが宇宙ステーションの1号機を打ち上げたとき、最も効率的な使い方をしようと全面が使える、上も下もない設計にしたら、宇宙飛行士がやめてくれという話になったそう。
▲「きぼう」内。上部は明るい
▲H-IIA/Bロケット第1段エンジン「LE-7A」
▲H-IIA/Bロケット第2段エンジン「LE-5」
▲小惑星探査機「はやぶさ」(2分の1モデル)
▲小惑星探査機「はやぶさ2」(模型)
▲宇宙飛行士のスーツ、計器類の文字が反転しているのは鏡越しで確認するからだという
敷地内の「ロケット広場」には、H-IIロケットの実機が展示されている。50mもある本物のロケット!
▲実物のロケットの下で現役宇宙機エンジニアに話を聞く!
▲ここで、みんなで記念撮影
館内・館外とも、野田さんならではの解説を聞き、ツアーは無事終了。
「宇宙開発や超伝導にふれる」
ニコニコ学会βサマーキャンプ2017
○野田司令、筑波研修センターに現れる
キャンプ2日目の9月3日、会場である茨城県つくば市の筑波研修センターに現れたのは野田司令こと野田篤司さん(以下、野田さん)。
野田さんは、世界で一番低い軌道を飛ぶ衛星(超低高度衛星)の概念設計を行ったJAXAの現役エンジニア、超低高度衛星は今年12月に打ち上げ予定だ。
あまり公になっていないが、インターステラテクノロジズにもかんでいたり、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』のSF設定に協力していたり、知る人ぞ知るのマッドサイエンティストだ。
研究所見学、JAXA筑波宇宙センターの見学に先立ち、野田さんから宇宙開発についてレクチャーがあるのだ。
▲野田さんのトークは、わかりやすく、おもしろい
野田さんは「誰でも宇宙にタッチできるような世界を作りたい」という。それには、今のような一機100億円もかかるようなロケットの作り方ではなく、もっと安いコストで、誰でも作れるようにならないと無理だ。
野田さんが、次に狙っているのは世界最軽量の人工衛星だ。いま世界的にどのくらいまで可能になっているかというと、今年7月に米国コーネル大学のザク・マンチェスター氏らにより開発され、宇宙へ打ち上げられた「Sprite」が4g。ということで、4g未満で実用に目処をつける衛星が狙うところだという。
▲JAXA筑波宇宙センター
筑波宇宙センターの位置付けについて。
これも野田さんがレクチャーしてくれたことだが、JAXAが持っている宇宙関係の施設のうち、種子島宇宙センター、内之浦宇宙空間観測所についで広いのが筑波宇宙センターだという。
種子島はロケット発射設備があるので広い。これは、ロケットが爆発しても外側に被害が広がらないように(ちなみに、ロケットの発射台がある射点は海に突き出し、山に囲まれているが、これは山を隔てることで爆発しても爆風が民家に行かないためにそうしている)。
一方、筑波宇宙センターはオフィス部分に加え、研究開発が行われている実験装置や試験装置を持つ。開発製造した人工衛星やロケットを打ち上げる前に宇宙空間で壊れないこと、動くことを試験するための機関ということになる。
また、人工衛星のコントロールを行う追跡管制設備、宇宙ステーションのコントロールを行うところ、宇宙飛行士が常駐しているところという面もある。
宇宙航空開発施設の一部を見学するツアー(有料:500円)もあるが、今回は残念ながら、スペースドームのみ。スペースドームは一般に公開されている無料の展示スペースで、人工衛星のフライトモデルなどが展示されている。
人工衛星というと一点ものというイメージだが、同じものを複数個作るのだ。1つは前述のように過酷な試験を行い、宇宙空間で動くことを徹底的に試す。こうした人工衛星や宇宙ステーションのモックアップなどが展示されている。
▲月周回衛星「かぐや」(実物大の試験機)
▲実験用中型放送衛星「ゆり」(実物大の試験機)
▲データ中継技術衛星「こだま」(実物大の試験機)
▲「きぼう」は、国際宇宙ステーション(ISS)の一部として機能する日本の宇宙実験棟。スペースドームにはそのモックアップがあり、中にも入れるようになっている
「きぼう」モックアップの中に入ったところで、野田さんからの問題が来た。
「何か、気づきませんか? 宇宙ステーションの内部はこうなっているんですが……」と。
答えは、「上下をわざと作っている」こと。
本来、宇宙空間には上下はないので、すべての面に操作スイッチをつけてもいいが、上には明るい照明を付け、下には暗くして、区別をつけている。
1970年代にアメリカが宇宙ステーションの1号機を打ち上げたとき、最も効率的な使い方をしようと全面が使える、上も下もない設計にしたら、宇宙飛行士がやめてくれという話になったそう。
▲「きぼう」内。上部は明るい
▲H-IIA/Bロケット第1段エンジン「LE-7A」
▲H-IIA/Bロケット第2段エンジン「LE-5」
▲小惑星探査機「はやぶさ」(2分の1モデル)
▲小惑星探査機「はやぶさ2」(模型)
▲宇宙飛行士のスーツ、計器類の文字が反転しているのは鏡越しで確認するからだという
敷地内の「ロケット広場」には、H-IIロケットの実機が展示されている。50mもある本物のロケット!
▲実物のロケットの下で現役宇宙機エンジニアに話を聞く!
▲ここで、みんなで記念撮影
館内・館外とも、野田さんならではの解説を聞き、ツアーは無事終了。
大人の遠足-2/2
「宇宙開発や超伝導にふれる」
ニコニコ学会βサマーキャンプ2017
○超伝導の世界
続いて、NIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)に向かう。物質・材料に関する基礎研究などを総合的に行っている研究機関だ。
ここでは、超伝導のデモンストレーション見学と物質の中の原子の立体配置が見える装置「アトムプローブ」を見学する、2つのグループに分かれた。筆者が参加したのは超伝導の解説&デモンストレーション。
超伝導について解説してくれるのは、高野義彦さん
高野義彦さん(NIMSのナノフロンティア超伝導材料グループ グループリーダー)
そもそも超伝導とは何か?
まず、作られた電気が運ばれる話から。電気は発電所から運ばれてくるが、途中、電線には電気抵抗があるため、いくらか熱になってしまう。せっかく生まれた電気が届くまでに目減りしてしまう。電線の抵抗が少なければスムーズに電気が目的地まで着くはず。
つまり、それが”完璧に無抵抗である”という状態が超伝導。完璧に無抵抗というのは「0」(ゼロ)であること。
1911年、ある金属や化合物などの物質を非常に低い温度へ冷却したときに電気抵抗が0になる現象がオランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オンネスにより発見され、以降、どういう物質が何度で超伝導体へ転移する(超伝導体に転移する温度を「転移温度」という)か、などの研究が行われてきた。
今、一番世の中に貢献している超伝導を活用した装置がMRI、続いて、東京-名古屋を結ぶリニアモーターカーの社会実装が期待されている。そのほか、風力発電機を超伝導にしようという動きがあったり、超伝導のモーターを入れた車が試作されていたり、船舶への転用、超電導電磁推進船ヤマト1号など応用の研究も進んでいる。
応用の研究は進んでいるが、まだ実用には至っていない。その大きな理由は、超伝導は物質を冷やすことで起きる現象だから。その物質により転移温度は異なるが、超伝導を起こすのにマイナス200度以下に冷やす必要があるとなれば、大掛かりな装置が必要で、一般の私たちが扱うには現実的ではない。
そこで、あまり冷やさなくても超伝導を起こす物質・化合物(それが室温超伝導と言われる夢の物質)を探そうということなのだ。高野さんは、これを天文学における彗星発見にたとえて、「マイ超伝導を発見する」と表現する。ちなみに、高野さんにもマイ超伝導があるそう。
▲超伝導物質の歴史。縦軸の単位はケルミン(K)、絶対零度(0°C)が273ケルミン
まだまだ程遠いように感じるが、2014年に硫化水素が203Kで超伝導体を示すことが発見され、もう決して夢ではないところまで現実が進んできている。可能性の範囲に入ったのではないかと、高野さんはいう。
203Kというとマイナス70°C。ドライアイスが約マイナス80°Cなので、市販で入手可能なドライアイスで超伝導が可能という、超高温超伝導の世界が来ている。
超伝導体を探すといっても、具体的にどういうことをしているかというと、発見された超伝導体の結晶構造を元に、結晶構造のどこが何のために働いているのかを見極め、組み合わせを変えたり、圧力をかけたりする。最高のパフォーマンスを出すよう、目には見えない結晶の設計をするのだ。そうして、いろいろな超伝導体が発見されてきている。
こうして、超伝導研究とはどういうことか基本的な話を聞き、実際に超伝導にさわらせてもらう。
いくつかデモの体験をさせてもらうが、基本原理は、超伝導による磁気浮上を使ったものだ。液体窒素でYBa2Cu3O7という銅化合物を超伝導にし、磁石に置く。すると、磁束を退けるマイスナー効果とピン止め効果(磁束が捕らえられ、ピンで止めたように動かなくなる現象)により超伝導磁気浮上が起きる、というもの。
▲超伝導体を磁石に置く。浮上しつつも、ピン留め効果により、逆さにしても落ちない
▲超伝導体でジェットコースター
▲超電導浮上装置。超伝導の磁気浮上で人を浮かせてしまったもの。浮いているため、手を押されるだけでクルクル回転する
デモには超伝導の状態を作る必要があったため、当日も到着時間前から仕込んでくれていたそう。デモ中、液体窒素を都度、追加するなど、研究室のスタッフのみなさんにもお世話になった。
▲自ら試してみる参加者、夢中になっている
これにて、全日程終了。
「宇宙開発や超伝導にふれる」
ニコニコ学会βサマーキャンプ2017
○超伝導の世界
続いて、NIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)に向かう。物質・材料に関する基礎研究などを総合的に行っている研究機関だ。
ここでは、超伝導のデモンストレーション見学と物質の中の原子の立体配置が見える装置「アトムプローブ」を見学する、2つのグループに分かれた。筆者が参加したのは超伝導の解説&デモンストレーション。
超伝導について解説してくれるのは、高野義彦さん
高野義彦さん(NIMSのナノフロンティア超伝導材料グループ グループリーダー)
そもそも超伝導とは何か?
まず、作られた電気が運ばれる話から。電気は発電所から運ばれてくるが、途中、電線には電気抵抗があるため、いくらか熱になってしまう。せっかく生まれた電気が届くまでに目減りしてしまう。電線の抵抗が少なければスムーズに電気が目的地まで着くはず。
つまり、それが”完璧に無抵抗である”という状態が超伝導。完璧に無抵抗というのは「0」(ゼロ)であること。
1911年、ある金属や化合物などの物質を非常に低い温度へ冷却したときに電気抵抗が0になる現象がオランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オンネスにより発見され、以降、どういう物質が何度で超伝導体へ転移する(超伝導体に転移する温度を「転移温度」という)か、などの研究が行われてきた。
今、一番世の中に貢献している超伝導を活用した装置がMRI、続いて、東京-名古屋を結ぶリニアモーターカーの社会実装が期待されている。そのほか、風力発電機を超伝導にしようという動きがあったり、超伝導のモーターを入れた車が試作されていたり、船舶への転用、超電導電磁推進船ヤマト1号など応用の研究も進んでいる。
応用の研究は進んでいるが、まだ実用には至っていない。その大きな理由は、超伝導は物質を冷やすことで起きる現象だから。その物質により転移温度は異なるが、超伝導を起こすのにマイナス200度以下に冷やす必要があるとなれば、大掛かりな装置が必要で、一般の私たちが扱うには現実的ではない。
そこで、あまり冷やさなくても超伝導を起こす物質・化合物(それが室温超伝導と言われる夢の物質)を探そうということなのだ。高野さんは、これを天文学における彗星発見にたとえて、「マイ超伝導を発見する」と表現する。ちなみに、高野さんにもマイ超伝導があるそう。
▲超伝導物質の歴史。縦軸の単位はケルミン(K)、絶対零度(0°C)が273ケルミン
まだまだ程遠いように感じるが、2014年に硫化水素が203Kで超伝導体を示すことが発見され、もう決して夢ではないところまで現実が進んできている。可能性の範囲に入ったのではないかと、高野さんはいう。
203Kというとマイナス70°C。ドライアイスが約マイナス80°Cなので、市販で入手可能なドライアイスで超伝導が可能という、超高温超伝導の世界が来ている。
超伝導体を探すといっても、具体的にどういうことをしているかというと、発見された超伝導体の結晶構造を元に、結晶構造のどこが何のために働いているのかを見極め、組み合わせを変えたり、圧力をかけたりする。最高のパフォーマンスを出すよう、目には見えない結晶の設計をするのだ。そうして、いろいろな超伝導体が発見されてきている。
こうして、超伝導研究とはどういうことか基本的な話を聞き、実際に超伝導にさわらせてもらう。
いくつかデモの体験をさせてもらうが、基本原理は、超伝導による磁気浮上を使ったものだ。液体窒素でYBa2Cu3O7という銅化合物を超伝導にし、磁石に置く。すると、磁束を退けるマイスナー効果とピン止め効果(磁束が捕らえられ、ピンで止めたように動かなくなる現象)により超伝導磁気浮上が起きる、というもの。
▲超伝導体を磁石に置く。浮上しつつも、ピン留め効果により、逆さにしても落ちない
▲超伝導体でジェットコースター
▲超電導浮上装置。超伝導の磁気浮上で人を浮かせてしまったもの。浮いているため、手を押されるだけでクルクル回転する
デモには超伝導の状態を作る必要があったため、当日も到着時間前から仕込んでくれていたそう。デモ中、液体窒素を都度、追加するなど、研究室のスタッフのみなさんにもお世話になった。
▲自ら試してみる参加者、夢中になっている
これにて、全日程終了。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
DIY(女性編) 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-