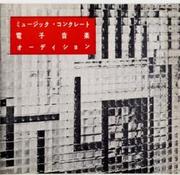|
|
|
|
コメント(48)
コンピュータを、タオ(道教)の「無為」の条件に委ねなければならない。つまり、支配する/支配されるという図式に無理に従わせるのをやめ、西田幾多郎や和辻哲郎が名付けた「主体の論理」(デカルト風に言えば、「自然の主人にして支配者」)と決別しなければならない。芸術の主権とは、テクノロジーに、つまりテクネのロゴスに、ラジカルな非力を与えることにあるのではないだろうか。(略)今日ほど芸術の機能が美学の型を示すことになく、コミュニケーションの経済とエコロジーであった時代はなかった。そして、エレクトロニクスのネットワークは、かつてないほど美学と経済の相互関係の場となっている。華厳宗の論理から派生した「妨害無き相互浸透」という概念は、西田幾多郎から西谷啓治、鈴木大拙らの哲学者、またジョン・ケージらのアーティストによって見直されている。この概念は、出発点を宗教におきながらも、上記の研究者らによって哲学の分野に取り込まれ、芸術の分野においても大きな影響を及ぼす結果となった。「総合芸術」の作家たちはメディア・テクノロジーの文化が必要としている革新の方法論を樹立することによって、「妨害無き相互浸透」という概念、すなわち散在する個々、しかも離れられないこれらの各要素の既存の調和という事実の原理をまさに生かし、証明し、明白にし、擁護していると思われる。この(メディア・テクノロジーの意味での)コンピュータアートの展開により、歴史、時空を超えた同一性が現われていると言える。
↑これは実験工房の話ではありませんが、重要な間接的関係がある話だと思うので載せさせていただきます。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from『Der Gute Ton zum Schönen Bild/美しい絵に良い音』(SAP Journal/セゾン・アート・プログラム・ジャーナル 2002年5月発行本テキスト)
↑これは実験工房の話ではありませんが、重要な間接的関係がある話だと思うので載せさせていただきます。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from『Der Gute Ton zum Schönen Bild/美しい絵に良い音』(SAP Journal/セゾン・アート・プログラム・ジャーナル 2002年5月発行本テキスト)
いま日本における継続性と非継続性について触れたように、20 世紀西洋の芸術に関しても、二つの異なった傾向が認められる。一つは、ルネッサンス以来造形芸術の分野でも音楽でも進められてきたある企てを、尊重する傾向である。芸術や科学の様々な領域を区分けし、それぞれの分野の中をさらに明確に、専門的に定義していく。もう一つの傾向は、むしろ区分を開放し、混合させ、コミュニケーションと相互作用を行うこと、つまりそれぞれの分野がネットワーク状態にあることを再認識することである。後者は透視画法、集中化、ヒエラルキー、線形性を拒否し、多様性、分散化、円環性を提案する。前者がデカルト哲学を後盾にしているとすれば、物質の構造と「世界の統一性という観念」 を研究した量子物理学を論拠とする後者は、東洋哲学と通じるものである。明治時代になって西洋世界に門戸を開いた日本は、西洋の文化的構造を受け入れると公言し、政治、経済、行政、教育の各方面で完全にシステムを変更した。同じようなことが芸術の世界でも起こった。特に大学では、西洋の絵画、彫刻、音楽を、19 世紀まで発展してきた形で学ぶために、日本の伝統芸術は脇へ追いやられた。しかし日本が方向転換を行った直後に、この方向は疑問に付されるようになる。そして、新しく生まれた〈未来派〉、〈ダダ〉、〈シュールレアリズム〉の動きに、初めから敏感だった日本の芸術家たちは、大変早くからこの「解毒剤」の恩恵を受けることになった。次いで第二次世界大戦が芸術の世界を含む全ての構造を覆し、日本ではほとんど全ての価値観が崩壊し、見なおされることとなったのである。日本がそのために大変苦しんだのは確かだが、この根本的再検討は悪いことばかりではなかった。19 世紀西洋芸術への方向転換は、幸運にも深く浸透してはいなかった。〈実験工房〉、〈具体〉、〈九州派〉、〈ネオ・ダダ・オーガナイザー〉、〈ハイ・レッド・センター〉から〈ビデオ・アース〉、〈ビデオひろば〉といった、50 年代から 70 年代にかけての多くの前衛運動がそのことを示している。「実験的な」芸術に携わる者は常に、その定義により、あまりにも秩序立った「土台」を疑問視するものなのである。戦後の再検討はこうして一つの力となり、未だ「継続性」の幻想に捉われているヨーロッパの前衛を超える前衛へと、日本の芸術家たちを導いていくのである。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」序論/0-8.日本の映像芸術作家の分類のために』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」序論/0-8.日本の映像芸術作家の分類のために』
以前からの知り合いの<実験工房>のメンバー、山口勝弘と北代省三に、日本の自転車の輸出のプロモーション映画の共同制作を提案した。松本が構成を担当し、山口と北代に美術監督として参加するという企画だった。新理研映画社にそのプロジェクトを提案したら、予算がとれることになった。《銀輪》は日本初のカラー実験映画だった。最初の段階から、幾つかの問題が現われた。<実験工房>のメンバーと松本はスペシャル・エフェクト(特別効果)は実現が困難でも、是非挑戦したいと思っていた。カラー・シネマスコープが誕生したところだったので、映画制作の関係者は皆カラーを積極的に使おうとしている時代だった。その実験は秘密裡に東宝社の実験室で行われていたが、東宝映画の円谷栄二監督に相談し、協力を得ることにした。松本は円谷監督に評価され、その後東宝映画で仕事するように依頼されたが、《ゴジラ》のシリーズを担当するよりも自分の研究に集中したかったため、辞退した。彼は《銀輪》の制作で実践したものをさらに追求し、特別効果を研究することには深く興味を持った。《銀輪》はサウンドトラックをも一新することとなった。武満徹はその時初めてサウンドトラックを作曲した折しも、ミュージック・コンクレートの先駆者、ピエール・シェフェールとピエール・アンリのレコードが日本で初めて発売されるところだった。彼等が提案した電気音響学的技術を日本でも実際に使用するきっかけとなった。材料として録音された鳥の声を使い、当時の初歩的な機器を使用し、テープの速度変化やコラージュを行った。映画の内容は未定だったため、映像の場合も、音の場合も、第一の問題は制作方法のルールを決定することだった。解決方法の一つとして、サウンドトラックと映像のある場面はチャンス・オペレーションによって実験的に構成された。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第四章 松本俊夫/4-1.美学的実験と社会的宣言/4-1-1.芸術と映画、<実験工房>とのコラボレーション』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第四章 松本俊夫/4-1.美学的実験と社会的宣言/4-1-1.芸術と映画、<実験工房>とのコラボレーション』
せんい社は1967年、松本に対して、1970年の<大阪国際万国博覧会>で建設予定のパビリオンのために、芸術的構想を建ててほしいと依頼した。会社の責任者たちは、主に映像で空間が構成されることを想定していたのだ。そこで松本は条件を出した。完全に自由な決定権が与えられること、そして、参加アーティストの選択を、松本に一任すること、である。この条件は受け入れられ、財政援助も無条件に与えられることになった。(略)20メートルの高さの建物の内部に、松本は鐘の形をしたドームを想定し、内部に映像を浴びせかけることにした。映像、彫刻、スライド、音響を混ぜ合わせ、「エロスとタナトス」というテーマに彩られた、バロック的な時空間を作りたいと考えた。神殿のようにそびえる大きなドームの中で、男女の肉体の映像が、恐るべき効果を持ったスペクタクルに観客を引き込むのだ。会社の責任者たちは驚いたが興味を示し、プロジェクトは実現へ向かう運びとなった。松本は1967年の初めに参加メンバーを集めた。多くの参加者の中に、横尾忠則がいる。横尾は芸術監督、そして、建物内部の建築構想を任された。秋山邦晴は、作曲者と音響技術者の募集を担当し、パビリオンの音響環境のために、湯浅譲二を指名した。やはり<実験工房>の活動的なメンバーだった今井尚治は、スライドを作ることになった。この企画には二つの原則があった。一つは空間内部の構想に関することだ。これは各パートで共通して行う作業であり、参加者全員の承認無しには、何一つ決定、もしくは計画されないこと。二つ目は、会社の委員会の決定に対するアーティストたちの自由と自立を再度確認したものだった。参加アーティストの承認無しには、何一つ計画されないこと。方法上のプランとして、松本のメンバーたちは、内容の前に容器を決めてしまうような、通常よく見られるやり方はとらないことにした。ドーム内部で行われるイベントの性格によって、具体的に建築を構想することが重要であった。建築的な機能にしたがって空間が創られるのではなく、空間と選んだテーマをよく考察した上で、建築が決定されるべきだ。というのも、松本は、明らかに調和を欠いていた<万博>全体の構成を、改善しようという方向で考えを進めていたからだ。メンバーたちは、絶対に、楽観的で「近代的」な未来論に裏付けられた建物を作ってはならない。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第四章 松本俊夫/4-2.映像の変容/4-2-3.1970年、国際万国博覧会:エロチックな空間』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第四章 松本俊夫/4-2.映像の変容/4-2-3.1970年、国際万国博覧会:エロチックな空間』
1948年の夏、北代省三、福島秀子と山口勝弘は〈日本アヴァンギャルド美術家倶楽部〉主催の近代美術に関するセミナーの際に出会う。その後、〈トリダン〉という名称のグループ活動を始めた。また、画家の岡本太郎や勅使河原宏、文学作家の安部公房、評論家、針生一郎らが設立した〈アヴァンギャルド芸術研究会〉のミーティングにも出席していた。1948年11月、同研究会は〈七耀会〉に改名し、東京の北草画廊で初めてのグループ展を開いた。北代省三はカルダーの作品からインスパイアされた《モビール》を発表したが、山口勝弘は「カルダーの三次元的な動きを、二次元上の絵画的イメージとして表わすことに熱中し、抽象的な絵画とレリーフを発表することになる」 。福島秀子の弟、和男は音楽家で、すでに作曲活動をしていた。友達の武満徹や鈴木博義も、山口勝弘と北代省三らもよく福島兄弟の家を訪ねていた。そのころに、造形芸術と音楽の新しい関係について思考をめぐらしていた。北代省三は〈横山はるひバレエ団〉のスペクタクルのための舞台美術を制作し始めていた。このように〈七耀会〉のアーティストたちは多数の芸術分野が混ざる領域を追求していた。北代省三は東京都美術館で1949年から1963年まで、読売新聞によって開催されていた〈読売インデパンダン〉展の際に作品を発表し続けた。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-1.〈実験工房〉の結成』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-1.〈実験工房〉の結成』
北代省三は東京都美術館で1949年から1963年まで、読売新聞によって開催されていた〈読売インデパンダン〉展の際に作品を発表し続けた。その時、瀧口修造は海藤日出男に、読売新聞に掲載するように招かれ、北代省三の作品の評判は好評であったため、瀧口修造は北代に会いに行った。その時から、北代省三、山口勝弘、武満徹、鈴木博義、秋山邦晴と福島兄弟はよく瀧口修造の家を訪ねるようになった。1951年に、山崎英夫、園田高弘と今井直次が加わり、〈アトム〉に改名し、日本橋の三越デパートでの展示会の準備に入る。
「趣旨芸術の諸種の分野を統合して在来の展覧会形式に見られなかった。異質の、芸術相互の有機的な結合を見出し、より生活に結び付いた者改正のある新しい芸術形式の発展のために努力する一つの試金石として、本展覧会を発表する。(中略)但し上記の諸項目の展示または発表に際しては、各個に独立して発表する形態をとらず、相互に有機的な関連を賦与せしめ、会場全体一つの構成物とする。またこの展覧会の他の特色として在来の展覧会において殆ど考慮されていなかった。展示物tの照明に多大の関心を払い、事情が許せば、機会的及び電気的な諸機構により、照明にも動きを与える予定である。」
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-1.〈実験工房〉の結成』
「趣旨芸術の諸種の分野を統合して在来の展覧会形式に見られなかった。異質の、芸術相互の有機的な結合を見出し、より生活に結び付いた者改正のある新しい芸術形式の発展のために努力する一つの試金石として、本展覧会を発表する。(中略)但し上記の諸項目の展示または発表に際しては、各個に独立して発表する形態をとらず、相互に有機的な関連を賦与せしめ、会場全体一つの構成物とする。またこの展覧会の他の特色として在来の展覧会において殆ど考慮されていなかった。展示物tの照明に多大の関心を払い、事情が許せば、機会的及び電気的な諸機構により、照明にも動きを与える予定である。」
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-1.〈実験工房〉の結成』
しかし、メンバーはグループ名を納得できず、「はからずも名付親になってしまった」瀧口修造は彼らのグループに〈実験工房〉を名付けた。四つの漢字で構成されたこの名称は、『詩的実験』という詩集の名称のように響き、言語的な面で、詩に於て、平凡過ぎる表現となっていた語意に対する対応を示していたように思える。瀧口修造はそれぞれの分野の専門化に対して、その平凡の境界線を越えるように、それらの分野の相互作用を追求していた。1910年代のヨーロッパの芸術運動を勉強しながら、アヴァンギャルド運動に参加し、その精神を常に生かし続けていた稀有な存在であった。
読売新聞社主催の〈ピカソ展〉は多数の芸術を組み合わせる機会となった。1951年11月、〈実験工房〉のアーティストたちは、日比谷公会堂で行われたバレー《生きる悦び》のテキスト、音楽や照明などを制作するように招待された。1952年、〈実験工房第二回発表会〉の際、日本で初めて、構成主義的なオブジェの舞台を使って、オリヴィエ・メシャンの音楽を紹介した。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-1.〈実験工房〉の結成』
読売新聞社主催の〈ピカソ展〉は多数の芸術を組み合わせる機会となった。1951年11月、〈実験工房〉のアーティストたちは、日比谷公会堂で行われたバレー《生きる悦び》のテキスト、音楽や照明などを制作するように招待された。1952年、〈実験工房第二回発表会〉の際、日本で初めて、構成主義的なオブジェの舞台を使って、オリヴィエ・メシャンの音楽を紹介した。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-1.〈実験工房〉の結成』
山口勝弘はモホリ・ナジの『ヴィジョン・イン・モーション』 (Vision in Motion、1929年) や『ザ・ニュー・ヴィジョン』 (The New Vision) を読み、キネティック・アートに興味を持ち、《ヴィトリーヌ》を制作し始めた。ガラスの板を使用し、光学の原理を実践した。マルセル・デュシャンがカルダーの作品について提案した《モビール》に対しての、瀧口修造が提案した《ヴィトリーヌ》という名称は、その作品のシリーズを示していた。山口勝弘の《ヴィトリーヌ》は1952年3月に、タケミヤ画廊で行われた〈実験工房第三回発表会〉の際や、また同年8月、銀座の松島画廊において油絵と共に《モビール》と共に展示された。1953年に、大辻清司は北代と山口の作品の撮影を行い、瀧口修造の推薦によって、その写真を『アサヒグラフ』誌の「アサヒ・フォト・ニュース」の欄に掲載された。その後、〈実験工房〉の多様的な活動はより詳しく資料化することが可能となり、その意味で写真との出会いは大切な出来事になった。その新しいメディアは創造しようとしていた舞台装置にとって相応しいと考えられていた。1956年に山口勝弘は音楽芸術誌に『主張と実現・実験工房』という記事を掲載した↓
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
↑彼にとって、「実験工房のエネルギーは、いつも球心的方向と遠心的な方向へ向かって放射されてきた。球心的な方向というのは、外形的な工房としてのチーム・ワークを離れて、個人の仕事の中へ帰ろうとするエネルギーの方向であり、遠心的というのは、美術と音楽、文学など各分野の仕事が、必然的な意思によって結び付こうとするエネルギーの方向である」。「しかし、芸術の各分野による結合の機会は、予期にしたほどたやすくは現われなかった」「だが、1953年の9月に工房の全部のメンバーが参加して、新しい結合の場を見出した。それは、オート・スライドによる発表であった」。(中略)「或る意味ではプリミティヴな表現方法による実験ではあったが、キャンバスクリストフ・シャルル・現代日本の映像芸術・第六章:山口勝弘・4やピアノによる表現手段をこえて、新しい表現手段であるオート・スライドやテープ・レコーダーなどの機会を通して、人間の視覚や音楽を発見しようという一つの課題にぶつかったのである。一方では映画という綜合芸術が、大資本による商業主義によって習慣的な表現へ陥っているとき、こういう機械を通して人間を表現する実験は、20世紀後半の芸術家が立ち向かうべき一つの避けることのできない仕事だと思う。」 〈実験工房〉のメンバーは、コンサートなどの際に舞台美術やインスタレーションなどを考えながら、アートとテクノロジーとの関係についても興味を見せていた。1953年5月と6月に、山口勝弘と北代省三は武宮画廊で続けて個展を開いた。前者は新作の《ヴィトリーヌ》の《空虚の目》と《イカルス》を展示し、後者は《写真版画》という印画紙を使った作品を発表した。同時に、日劇ミュージック・ホールのディレクター、岡田圭吉に依頼され、実験映画《モビールとヴィトリーヌ》も制作していた。その映画はスペクタクル《神の国から谷底を見れば》の映像として、スライドと共に三つのスクリーンに上映された。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
↑同年9月、東京第一生命ホールでの〈実験工房第五回発表会〉の際に、オートスライド(連続的4に投影されるスライドによる作品)が何点も上映された。福島秀子と和男による《水泡は創られる》、駒井哲郎と湯浅譲二による、ロベル・ガンゾの詩に基づいた《レスピューグ》、北代省三、鈴木博義と湯浅による《見知らぬ世界の話》などが上映された。《試験飛行家WS氏の目の冒険》では、北代省三は撮影を、鈴木博義は音楽を担当した。山口勝弘は飛行家の目に入り込んだ水晶の中に展開する構成主義的な風景を表す、ガラスや紙などを使用した77の模型を制作する。1955年、実験劇場のスペクタクル、《イリュミネーション》の際に、〈松尾明美バレエ団〉は〈実験工房〉とのコラボレーションを行う。舞台監督、山口勝弘はW.S.氏が見た風景のある要素を使用した。「『イルミナシオン』(装置・山口勝弘)は光とガラスのあいだを白い人間が出たり入ったりして、いわば主観と客観の急激な交錯による一種の虚像の世界を現出しようとしている。」 松本俊夫が勤めていた新理研映画社に、自転車の輸出のためのプロモーション映画の依頼が来た。《銀輪》というタイトルのその映画では、北代省三と山口勝弘が構成を、武満徹と5鈴木博義が音楽を制作し、東宝映画社のもっとも想像力のあるエンジニアー、円谷英二の協力を得て、松本は特種効果を実現することとなる。円谷はその後、ゴジラのシリーズの特殊効果などを担当した。PR映画にもかかわらず、《銀輪》は、そのような特種効果をカラー・フィルムで実験した日本で初めての作品となった。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
〈実験工房〉のメンバーは様々な実験を続きながら、なおかつ作曲家の武満徹、福島和男、鈴木博義、秋山邦晴、若山浅香、湯浅譲二らによって、日本でまだ知られていなかった西洋の作曲家、エリック・サティ (Erik Satie) 、アロン・コプランド (Aaron Copland) 、ダリュス・ミロー (Darius Milhaud) 、サミュエル・バーバー (Samuel Barber) 、オリヴィエ・メシャンやジョン・ケージなどを紹介をしつつあった。瀧口修造はそれについてこう記述している。「文学ではカミユやエリュアルが訳されたり、絵画ではピカソの新作やサロン・ド・メーが紹介されたりする時代に、音楽だけが同時代の世界の空気が伝わらないのは全くふしぎです。 恐らく、ミュージック・コンクレートやエレクトロニック・ミュージックの展開と共に、それぞれの芸術分野の融合の新しい可能性は次第に明らかになっていったと思われる。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-2.芸術分野の相互作用、芸術とテクノロジーとの出会い』
1956年より、〈実験工房〉の活動は減退してゆく。1956年1月、武満徹と鈴木博義はヤマハ・ホールでミュージック・コンクレートのオーディションを主催した。山口勝弘は会場構成を依頼され、客席の間に、床から天井まで白いロープの束を引き、会場の壁面構造と視覚的に相互作用が行われるような装置を創造した。《ヴィトリーヌ》の基本概念である、観客自身がインスタレーション作品の透明さを様々な観点から体験できることを実現するものであった。3月の〈読売アンデパンダン〉展に、ガラスと合成樹脂を使用した作品を出品した。北代省三は「暮れる時」という写真作品。同年8月に、新宿風月堂、〈実験工房のメンバーによる新しい視覚と空間を楽しむ夏のエキジビション〉の際に、福島秀子の油絵、北代省三と山口勝弘の新作などが展示され、又武満徹の音楽も秋山邦晴によって、テープで発表された。翌年、グループの最後の展覧会、〈実験工房メンバーによるサマーエキジビション〉が同じ場所で開かれた。
ここでなぜグループ活動が減退していったかという疑問が生じるだろう。戦後、ヨーロッパやアメリカでも、そのような活動をしているグループは比較的少ない。にもかかわらず、その中の幾つかは存在していた。1951年、ブラック・マウンテーン・カレッジで、《アンタイトルド・エベント》(Untitled Event) が行なわれた。これは、ジョン・ケージによる開催であったが、絵画、フィルムとスライド(ロバート・ラウシェンバーグ)、ダンス(マース・カニングハム)、詩(チャールズ・オルソンとメリーカロリン・リチャーズ)、ピアノ(デーヴィト・チュドアー)やラジオと講演(ジョン・ケージ)が組み合わされ、観客を取り囲むように行なわれた。関西においては、〈実験工房〉と同一の存在が〈具体美術協会〉であった。アメリカの〈フルクサス〉がその活動を行う以前に、〈具体〉のメンバーはアクション、「ハプニング」(当時はこの名では呼ばれなかった)を行っていた。1955年、東京の小原会館で行われた〈第一回具体美術展〉では、村上三郎が障子を突き抜けた行為が非常に有名となった。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-3.1956年1958年:〈実験工房〉の第三期』
ここでなぜグループ活動が減退していったかという疑問が生じるだろう。戦後、ヨーロッパやアメリカでも、そのような活動をしているグループは比較的少ない。にもかかわらず、その中の幾つかは存在していた。1951年、ブラック・マウンテーン・カレッジで、《アンタイトルド・エベント》(Untitled Event) が行なわれた。これは、ジョン・ケージによる開催であったが、絵画、フィルムとスライド(ロバート・ラウシェンバーグ)、ダンス(マース・カニングハム)、詩(チャールズ・オルソンとメリーカロリン・リチャーズ)、ピアノ(デーヴィト・チュドアー)やラジオと講演(ジョン・ケージ)が組み合わされ、観客を取り囲むように行なわれた。関西においては、〈実験工房〉と同一の存在が〈具体美術協会〉であった。アメリカの〈フルクサス〉がその活動を行う以前に、〈具体〉のメンバーはアクション、「ハプニング」(当時はこの名では呼ばれなかった)を行っていた。1955年、東京の小原会館で行われた〈第一回具体美術展〉では、村上三郎が障子を突き抜けた行為が非常に有名となった。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-3.1956年1958年:〈実験工房〉の第三期』
「ただ、この1960年代はじめのアーティストたちは、各種の工業用素材の可能性の実験という点で、戦前の構成主義的思想を引き継いでいでいると同時に、ダダイズムからシュールレアリズムを通って流れている、幻想的世界やナンセンスな遊びの領域に関わっているポル・ブリなども含まれる。」アナスタジオ・ディ・フェリチェが指摘したように、〈未来派〉のパフォーマンスはルネッサンスのマルティメディア的なスペクタクルを連想させ、そのルネッサンスのパフォーマンスもプラトンとアリストテレスの宇宙構成に於ける思想を実験していたと言える。山口勝弘によれば、「1960年代の現代美術の特徴は、第二次大戦後の都市環境の変化に対する第二の応答とみることができる。この第二応答に於ても、1920年代と殆ど同様な経過を辿って作品が現われている」。日本の戦後美術史をみると、日常生活用のテクノロジーは1960年代からアメリカの水準に到達するが、美術分野では、一種の「テクノロジー・アレルギー」が現われている。伝統的芸術の資産を守ろうとする傾向は、日本人が過去の文化に大きなこだわりを持っていることを明確にあらわしていると思われる。当時、日本を訪ねているフランスの評論家ミシェル・タピエは〈具体〉と、〈実験工房〉の紹介記事では、このように書いている。「福島、山口の二人の画家のためによいと思われるのは武満徹、鈴木博義、佐藤慶次郎、湯浅譲二、といったミュジック・コンクレート、或いは電子音楽の作曲家たち、それに若い批評家で、詩人、秋山邦晴が同じグループに肩を並べて活躍しているという事実である。こうして一つの聡明な力動体が構成され、これは活気に満ちその行動において明晰というグループの全体雰囲気のためにきわめて幸いに働いている」。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-3.1956年1958年:〈実験工房〉の第三期』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-3.1956年1958年:〈実験工房〉の第三期』
〈未来主義〉や〈構成主義〉の後継するグループとして、「すべての実験芸術を包括する初めてで、殆ど唯一の例である」〈実験工房〉は、戦後の美術史ではユーニクな位置であると思われる。〈実験工房〉を創立したそれぞれの作家が異なる分野からにもかかわらず、オープンな形態を守ることにしていた。つまり、他のアーティスト、組織や会社が企画したイベントなどに参加する自由を保っていた。そのオープンな形によって、逆に活動が困難な場合もあり、さらに記録をまとめる作業も混乱した状況だったかもしれなかった。1991年に、山口勝弘は次のような文章で説明しているように、「当時のヨーロッパにもなかった〈実験工房〉の活動は、前述したように、〈具体〉グループよりも3年も早くスタートし、1957年には殆ど終わろうとしていた。ということは、日本ではもちろんのこと、当時の欧米の美術界を見ても、あまりにも早過ぎた活動だったということができるだろう。(中略)1960年代が本当の〈実験工房〉のための時代であるはずだったという気がするのである。」確かに、様々なプロジェクトや研究内容の大胆さを考えると、当時の〈実験工房〉の活動は比較的、認められなかったと思われる。山口勝弘の制作活動を見ると、造形に於ける創造力と、当時、取り上げられた美学に於ける問題を詳しく組み合わせたということが明らかである。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-3.1956年1958年:〈実験工房〉の第三期』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-3.1956年1958年:〈実験工房〉の第三期』
1940年代の終わりに、〈ロシア構成主義〉を研究していた山口勝弘はモホリ・ナギの思想に影響を受けた。〈バウハウス〉の作家が《光の絵》について提案した概念に影響され、造形的要素に集中した。「画財屋よりも、ガラス屋に行く方がよほど面白かった」。山口勝弘がガラスやアルミの板をはじめ、セルロイドや金網などを集め、「バウハウスのアトリエのように見えた」。様々な素材の組み合わせによって、光の反射や透明感の効果を実験していた。モンドリアンの最後に描いた絵《ヴィクトリーブギーウギー》 (Victory Boogie Woogie、1944年) の上に、モール・ガラスを動かしてみると、描いた円、四角などが視覚的に変形することが分かり、光学のレンズのように扱ったモール・ガラスが重なり、色々な仕掛けを創造すると、色々な効果が発生した。山口勝弘は、筆を使うという身体行為は、「自分」を強調することになるというふうに解釈し、筆を扱うことをなるべく避けようとしていた。山口勝弘にとっての、そのような意図と同様な解釈で、デュシャンは《大ガラス》の幾何学的な機械たちを描いた。山口勝弘はそのような「自分」に反発することにより、「日本の社会的な風土、状況は非常に、まずイデオロギー的であった。政治的にも。それからもう一つは情念的なものが芸術を動かす原理として考えられていた。そういうものを意識的に避けて、(中略)筆によって描くという、肉体的な描くという行為の痕跡消し去り、ガラスの上に絵具を塗って、しかも描かれるパターンはあくまでもカラスグチによる幾何学的な線を使っていたわけです。」意識的にカンヴァスと絵を忘れると、次には視覚的な作品の構造を、「空間的に描かれた面が浮遊する」ために、ガラスの物理的な特徴を考えていた。すると、観客は、自分の身体の動きによって、鑑賞している作品の形態を自分で定義する。動きによって絵の形を変えたり、拡大したり、縮小したりすることができるので、観客にとって観る行為はパフォーマンスとなる。「作品と、見る側が相対的な関係の中に置かれるということをやっていたわけです」。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-4.山口勝弘の造形作品、《ヴィトリーヌ》』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-4.山口勝弘の造形作品、《ヴィトリーヌ》』
《ヴィトリーヌNo1》 (20.8 × 17.8) は1952年12月に制作された。薄い箱の形で、その正面に2枚のガラスの板の間に長方形が相互浸透するような形で絵が観える。ガラス板から2センチほど離れている奥はグレーの平面に幾何学的な形態が描いてある。従って、観点によってそれぞれの形態とそれの影の視覚的な関係を変えたりする。山口勝弘は幾つかのタイプの《ヴィトリーヌ》を制作し、それぞれの材料の特徴に従い、様々な重ね方や組み合わせ方を考えた。又、その上に傾く「井」のような形態や、モニュメントのような柱の形態などが、その中に光の電器装置を入れることによって、様々な可能性があった。タイトルは作品の一部として扱われ、抽象的な作品を具体化する役割があると思われる。《アフリカの華》 (1953年、56 × 94.5 cm) 、《夜の進行》 (1954年、60.6 × 51 cm) や《静かな昇天》 (1955年、94.5 × 65 cm) などがある。1958年、《風》 (120 × 360 cm) は、以前より規模の大きな作品で、展覧会場の壁全体に展示される。《風景》 (180 × 120 cm) などが支柱に支えており、会場の空間を区分する。当時山口勝弘はオブジェよりも、スペースを制作する意識を持ち、1958年12月の和光画廊に於ける個展の、インテリアー・デザインや展示会の構成を丹下健三に依頼した。その時から、箱が解体し、内面にある要素も構成主義的な部分も流出している。それらの作品は、造形物よりも、「新しい感覚を与える機械」として考えられた。その意味で、ジャン・アルプやベン・ニコルソンのレリーフとは違い、モホリ・ナギの構成主義的な空間的作品、《スペース・モデュレータ》 の系列として構想された。1958年、《ヴィトリーヌ》のシリーズの制作は〈実験工房〉の活動の終わりと共に中止される。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-4. 山口勝弘の造形作品、《ヴィトリーヌ》』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-1.初歩/6-1-4. 山口勝弘の造形作品、《ヴィトリーヌ》』
1961年10月、山口勝弘はヨーロッパやア メリカでバウハウスなどについて日本で手に入らない資料を入手するために、100日 間の旅に出掛けた。ローマに一カ月ほど滞在している間に、アメリカへのビザを待ち ながらバルセロナへ渡り、ガウディの建築や陶芸などを発見することにより、自己の中に19世紀のヨーロッパの工芸の影響を強く感じる。その際、西洋の芸術の軌跡を意 識すると、西洋美術の世界について疑問を持ち始めた。ニューヨークでは、小野洋子 に歓迎され、クリスマスの日にレオ・カステリの家に招かれた。そこで、建築家のフレデリック・キスラーと出会う事となる。キスラーのアトリエを訪ねた際に、「エン ドレス・ハウス」等の作品を見せられる。その時、彼は人間の感覚によって構成され た環境をどのように創造するのか、という点に関し、理解することに至る。キスラー はすでに作品と観客の相互関係に注目し、建築の基本的な問題は、観客の「パフォー マンス」、つまり態度の質を定義しなければならないという「ソフトウアー」の問題 を主に取り上げた。ある作品を、例えば穴の開いている壁の裏に展示する行為など は、再びデュシャンの作品、特にスペインのハシエンダの扉の裏に、妙な風景が見え るようなインスタレーションである《遺作》 (Étant Donnés: 1- La chuted’eau, 2- Le gaz d’éclairage) と関係するのではないかと思われた。キスラーは観客の視覚から他の要素が離れ、一つだけの作品に集中する状況を考えていた。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代:空虚から巨大化まで6-2-1.旅行、空虚や新しい方向』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代:空虚から巨大化まで6-2-1.旅行、空虚や新しい方向』
1942年に、デュシャンがニューヨークに着いた時に、キスラーの家で泊まったので、作品はその環境といかなる関係を持つかということによって、観客の対応、反応やパフォーマンスの問題について、話す機会があったと思われる。つまり、作品はオブジェとしてではなく、むしろある環境の中で広がるために、環境的な展示の仕方を考えることを必要とする。旅行中に資料や情報を集めたことによって、帰国した後、『不定形美術ろん』という本を書き下ろした。「ろん」を平仮名で書いてあるのは恐らく「論」の意味を弱くするためであろう。その中で観客と作品との相互作用から、作品と展示の仕方、光の非物質性、形態と無形態、工芸、化粧や入れ墨、料理までという様々な問題を取り上げることができる。ヨーロッパで失望したことやニューヨークでの出会いは確かに「刺激的な体験」であった。「装置的要素と博覧会ディスプレイ混合したインスタレーション」を発表し、60年代のミニマル彫刻の代表的存在だったロバート ・モリスを知り合ったにもかかわらず、自分に「空虚」が出来、「造形の形態に対して関心を失った」。同年の秋に、父親が亡くなり、雑誌『美術手帳』では幾つか の記事に書いたように60年代の初めは「瀕死の芸術家」として過ごした。そのような 体験は芸術活動には、確かに大きな影響を与えたと思われる。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代:空虚から巨大化まで6-2-1.旅行、空虚や新しい方向』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代:空虚から巨大化まで6-2-1.旅行、空虚や新しい方向』
1970年まで、山口勝弘は《布張り彫刻》や光とアクリル板の彫刻を制作し続ける。1967年、《作品》は〈第四回長岡現代美術館賞〉、《ユニバース》は〈東京都近代美術館賞〉を受け、1968年《キス》、《五月の橋》と《サイン・ポール》は〈ベニス・ビエンナール〉で展示される。ニューヨークにおいて、小野洋子によってフルクサスのアーティストに紹介され、〈リビング・シアター〉 (Living Theater) のイベントにも参加した。小野洋子と共に、椅子を壊すまでに踊る、という、一柳慧の作曲を演奏した。帰国後も、アメリカの現代芸術と関係しているアーティストや作曲家と共に、幾度もイベントやハプニングに参加する。1965年9月、銀座のクリスタル画廊で、秋山邦晴と〈Flux Week〉を共同企画し、資料、オブジェ、ノテーションや詩を展示し、《レインボー・オペレーション》を演奏した。透明なビニール・シーツの環境の中で、光の仕掛けを使用しながら、詩を朗読するパフォーマンスだった。1966年11月、銀座の松屋デパート主催の〈空間から環境へ〉展の関連イベントとして、草月会館で横尾忠則、秋山邦晴、塩見允枝子と共演し、又靉嘔と共に、同年12月18日、品川倉庫から、原宿の明治神宮、護国寺までバスで移動し、《水たまりのイベント》や《握手のピース》を行った。又東野芳明と共に草月会館で〈 Expose 68 〉などというイベントも企画し、映画やスライドを透明なスクリーンに上映しながら、カメラやモニターをテレビ局にレンタルし、ビデオの「クローズ・サーキット」の中のシンポジウムを実現した。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-3.フルクサスとの出会い:イベントやハプニング』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-3.フルクサスとの出会い:イベントやハプニング』
テレビに於ける初めての試みの後、《イメージ・モデュレータ》 (1969年) を制作する。それは、一般の番組を、映っているテレビモニターの前に、《ヴィトリーヌ》の制作で使ったモール・グラスをセットするというインスタレーションだった。以前行った追求だが、今度はスチールではなく、動く映像を観客の位置によって抽象化し、変化させる装置である。ナム・ジュン・パイクが何年か前に、テレビの上に大きな磁石を置き、観客自身が番組の映像を変える可能性を与えていたように、観客は身体の動きによってその実験を行うことができた。1969年に、銀座のソニー・ビルで行われた〈Electromagica 69〉の際に《水変調機・Water Modulator》を発表する。170cm の高さで、4本の透明なパイプの中に水が入っており、そのパイプの底にファンの羽が水に運動を起こさせるという作品であった。これは以前の光の彫刻を思いださせるが、運動に於ける研究も含み、今後ビデオを使用することにより、より豊かな可能性を感じさせる作品であった。本展覧会の名称である<国際サイテック・アート展(Psytech Art)エレクトロマジカ>は精神(Psycho)と技術(Technology)の結びついた芸術を意味し、エレクトロマジカはこのイベントのテーマである電気による不思議な仕掛けを指すものである。しかも同展覧会では、このテーマに相応しい作家を外国より招くなど、画期的な試みがなされた。この展覧会は今後の美術の流れに重要な意味をもつ。具体的には、翌年の<エキスポ‘70>のプロローグともいえる日本で初めての大規模な芸術とテクロジーの一大イベントであった。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-3.フルクサスとの出会い:イベントやハプニング』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-3.フルクサスとの出会い:イベントやハプニング』
大阪に大阪に於てアジアで初めての〈万国博覧会〉が行なわれた。3月14日から9月13日までの半年で、64.218.770人もの人々がそこを訪れた。この観客動員数は大変なものである。しかし、残念ながら、この万博は、その後の現代美術の発展に余り影響を与えるまでには力が及ばなかったと思われる。西嶋憲生は、「日本政府が、過多のビデオ実験に補助金を出したにもかかわらず、明日の無い実験であった」とまで発言している。〈万博〉は既に世界中で行なわれ、各国の芸術家を招き、大々的な計画への参加を依頼することも数多くあった。〈大阪万博〉の場合、日本においては前代未聞の、並外れた資金が投じられ、多数の前衛芸術家が動員された。山口勝弘の要約によると、その理由は二つある。「1つの理由は、大阪万博では、直接的な商品展示が禁じられたことである。従って、芸術的な展示によるパビリオン間の競争が起こった。2つ目の理由は、第1の理由とも関係するのだが、わが国の工業技術社会のハードウエア面は、ほぼ世界的水準に達し、そこで、それらのテクノロジーの利用技術、つまり、ソフトウエアの開発に対する産業界の期待があった」。その意味で、〈大阪万博〉は、60年代に明らかになり始めた傾向を結集したと言える。また、情報社会への道をも示した。そして、当時、科学や社会の様々な分野にコンピュータが普及し、大幅に利用されたことによって、コンピュータ・アートが生まれたと言うこともできる。そのような企画に参加したメンバーには、アーティストのみならず、建築家も多かった。ジョン・ケージ、ロバート・ラウシェンバーグとデーヴィド・チュドアによる〈EAT〉グループのインターメディア的な方法論の影響で、「モニュメント的な建築技術上の実験」が行なわれ、事務所的建築物より、表現的な建築物を作るという傾向が現われた。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-4.巨大なプロジェクト:大阪万国博覧会』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-4.巨大なプロジェクト:大阪万国博覧会』
山口勝弘が言及しているように、〈大阪万博〉は「一種の映像博」であった。〈太陽の塔〉内部の粟津潔による《マンダラマ》、東芝IHI館では泉真也による《グローバル・ヴィジョン》、またせんい館の松本俊夫による《スペース・プロジェクション・アコ》、などもあった。鉄鋼館では武満徹の音楽と、宇佐見圭司のレーザー光線のスペクタクルが発表されていた。山口勝弘は建築家、東隆光と伊原道夫と共に三井グループ館のディレクションを担当した。全体のプロジェクトは《スペース・レヴュー》と名付けられ、館内の空間、つまりそこで行われるスペクタクルによって、館の建築は構成された。「三井パビリオンでは、建築自体とその内部でおこなわれる催しや展示を分けて考えず、その両面を一体化して、一貫した演出方針に沿って展開される連続した環境の集合体としてとらえられている。その結果、ここには建築の要素がすべての環境を成立させるための道具・装置である〈装置化建築〉が出現した」。ドームの中に行われたスペクタクルは《宇宙と創造の旅》と名付けられ、その主な仕掛けは観客が昇る事ができる三つの回転する台であった。それぞれの台には80人までが乗ることが出来、上下に10メートルから20メートルの高さで移動することが出来た。360度のスクリーンや天井に設置された彫刻に、フィルム上映機やストロボによって、光や映像の投影が行われた。一柳慧、佐藤圭次郎と奥山重之介が創造した音楽が、スクリーンの裏や地面に設置された何百台のスピーカーから聞こえていた。出口は長い廊下に配置され、その壁に小さなスピーカーが取付けられており、詩などを朗読する声が聞こえ、この廊下部分の音量はドームの中それとは対照的に小さな音量であった。映像実験が多過ぎたため、観客の中にも、「テクノロジック・アート」に対しての否定的な反応は多かった。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-4.巨大なプロジェクト:大阪万国博覧会』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-4.巨大なプロジェクト:大阪万国博覧会』
又、山口勝弘によれば、「万国博の会場に現われた50.000.000近い人間群の影響が前衛的な芸術家達の上にも起こってきていた。どちらかと言えば、個人的な発表でしかなかったこれらの芸術作品が、半年間の間に、50.000.000近い人間達の眼に晒されるという経験は、彼らにとって初めてのことだった。さらに、仲間内に近い学芸欄や文化欄でなく、社会面で作品の評価を問われることも初めての経験となった。また、私を含めて、何人かの芸術家達は、この会場が大量の観客に対する一方的コミュニケーションの場とならざるを得なかったことに、深い反省を抱いた」。1970年は、 社会的、政治的な出来事が多発し、それによって「情報社会」の曙となり、同時に芸術家の役割についても考えさせられた時代であった。芸術家たちは、コミュニケーションの新しい可能性に適応した利用法、また政府及び企業に対しての対応を新たな定義付けを余儀なくされた。したがって数年前に出版されたマーシャル・マクルーハンの理論の研究を再認識する必要性があった。「この新しいメディア論の特徴は、マスメディアを前提としたものではなく、むしろメディアを利用する情報の作り手が、パーソナルになり、コミュニティーとなり、今までのマスメディアの受けて側の論理から出発している点である。」これらの記述からも分かるように、日本ビデオ・アートの歴史に関心を持つ人々にとって、〈大阪万博〉は意味を見いだすことができないイベントであった。しかしながら、1970年は、政治社会的出来事が多く、また情報社会の黎明期でもあったので、芸術家の役割について多くの基本的反省がなされたことは、特筆に値するであろう。「万国博そのものの成果はとにかくとして、その後の数年間に、これら環境演出の手法は一つのノウハウとして、社会的に定着していたのである。」
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-4.巨大なプロジェクト:大阪万国博覧会』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-2.60年代/6-2-4.巨大なプロジェクト:大阪万国博覧会』
〈大阪万博〉によって、芸術家は60年代に問題されたテーマから離れ、今後、アートとコミュニケーションは主なテーマになった。60年代に始まった造形芸術による環境の占領は第一方向であり、又その方向が起こす問題を定義する手段としてのコミュニケーションの具体的回路が必要となった。ビデオが誕生した際に、これは大衆と芸術家の間のコミュニケーションを支える造形的表現のためのメディアになるかと思われた。ビデオメディアは撮ると撮られる、観ると造るの間に存在するかのように感じられた。映像を造ることとモニター上で現われる映像との関係はリアル・タイムで行われ、ライブ感覚で行われていた。1971年に山口勝弘はもう一度アメリカやヨーロッパに旅行し、帰国後、「情報構成彫刻」のアイディアが生まれた。それは、ビデオ機器と造形作品の組併せによって、観客の参加、つまりリアル・タイムのパフォーマンスを必要とする「造形的コミュニケーション」を提案した。そのプロジェクトは殆ど即時にパフォーマンス《Eat》として具体化し、又数年後インスタレーション《ラス・メニナス》の形態として発表されている。山口勝弘はそれを《ビデオラマ》と呼んでいる。その作品シリーズは、ビデオ・アートが創造するコミュニケーションの場、または具体的空間の中にディスプレイされ、三次元の造形への認識を示している。《ビデオラマ》は鏡と数台のモニターを使ったカレイドスコープ的なビデオ彫刻である。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-3.日本のビデオ・アートの誕生(1972年1974年)/6-3-1.再発見された著名な観点』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-3.日本のビデオ・アートの誕生(1972年1974年)/6-3-1.再発見された著名な観点』
《ビデオラマ》は1950年代の《ヴィトリーヌ》、又1960年代の《光の彫刻》で追求していたことと同じように環境の問題に直接触れていた。1972年2月24日から同年3月5日まで、ソニー・ビルで行われた〈Do It Yourself Kit〉展の際に、山口勝弘は小林はくどうと共に、セザンヌの《カード遊びをする人たち》 (1890-92年) からインスパイアされた作品《Eat》を実現した。二人の男はテーブルに座り、互いにビデオ・カメラで撮影している。その映像はパフォーマの後方に見える。もう一つのカメラは、せザンヌの位置全体のシーンを撮影している。山口勝弘によると、その複数の観点はビデオというメディアの可能性によってセザンヌの絵を表現しながら、「絵の構造をよりメディア的に開いた」 。同年10月、東京を360度の角度で見たインスタレーションを実現した。この作品はパフォーマンスの方法で制作した。東京の何箇所かを訪ね、それぞれの場所で、ビデオ・カメラを360度で回転しながら撮影を行った。同じ映像を映す45台の 8 × 10cm程のモニターと鏡のセットを使用したこの《トウキョウラマ》を東京アメリカン・センターで発表する。1974年5月、〈第11回日本国際美術展〉に、ビデオ部門が設立された。山口勝弘はインスタレーション《ラス・メニナス》を発表し、「一つのモニターの上に環境を表現する、あるいはシュミレートされた環境を眺めるということは、シュミレートされた環境と人間の一対一の関係でしかない」。ピカソが同じ《メニナス》を制作した17年後、山口はベラスケスの絵を再び解釈した。山口勝弘はミシェル・フーコーがその絵について指摘したことを現実に作品化した。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-3.日本のビデオ・アートの誕生(1972年1974年)/6-3-1.再発見された著名な観点』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-3.日本のビデオ・アートの誕生(1972年1974年)/6-3-1.再発見された著名な観点』
「そこでは表象がその諸契機それぞれにおいて表象されているわけであって、その場合の諸契機とは、画家であり、パレットであり、裏返しにされた画布の大きなくすんだ表面であり、壁に掛けられたいくつもの絵であり、自ら眺めていながら自分たちを眺めている人々によって額縁にはめこまれている人物たちであり、最後に、表象関係の中央、その中心で、本質的なものの最も近くにあるーしかも、表象の最もはかない二重化にすぎなくなるほど、はるかに遠く、非実在の空間の奥深く挿しこまれ、よそに向けられているあらゆる視線とは無縁な、反映としてー表象されているものを示す鏡にほかならない。絵の内部のあらゆる線、とりわけ、中心にあるその反映からくる線は、表象されつつ不在であるものそのものを目指している。それは客体でありー表象された芸術家が画布の上に写しつつあるものであるからー同時に主体であるー画家が自身をその制作を通じて表象しながら見ていたのは、画家自身にほかならず、絵に描かれている視線は、王というあの虚構の点に向けられているが現実にはそこに画家がおり、画家と至上のものとがまたたく間にいわば際限もなく後退していくこの両義的場所の主人こそ、最終的には、その視線が絵を一つの客体に、あの本質的欠如の純粋な表象にと変形していく、鑑賞者にほかならないからだ。」《Video Exercise》(1974年) というサブタイとルの第一バージョンは、ベラスケスの絵のコピー、ビデオ・モニターとビデオ・カメラが使用された。その前に、テーブルと椅子が用意され、全体のシーンはカメラによって映され、モニター上に現われていた。山口勝弘は作品について観客の感想などを聞き、話しをしていた。第二のバージョンでは、絵のコピーを2枚用意し、一方はカラー、もう一方はモノクロで、モノクロの絵の鏡のところ(ベラスケスの位置)に穴を開け、後ろからカメラを設置する。観客が王子と王女の位置におり、右左にセットされたビデオ・モニターに映される。真中のモニターに、モノクロの絵の鏡から見たシーンが映される。観客はカラーの絵に向かうと、自分の背中も見える。すると、絵の「鏡像的」な機能ははっきり分かる。観客は絵の構造に入り、それぞれの空間的な層を発見し、体験することができる。「山口がビデオを用いて、《ラス・メニナス》にかくされた視線のドラマを、その構造と共に認識のプロセスとして対象化しようとしたことは明らかである。その意味でそれは「考」と名付けられるのにふさわしいが、同時にその構造をビデオのシステムに重ねて思考している意味で、すぐれて「ビデオ・メディア考」にもなっていることを見逃すことはできない。」
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-3.日本のビデオ・アートの誕生(1972年1974年)/6-3-1.再発見された著名な観点』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第六章 山口勝弘/6-3.日本のビデオ・アートの誕生(1972年1974年)/6-3-1.再発見された著名な観点』
芸術と技術の関係に関する楽観論機械の美しさを讃えた未来派宣言は、1909年2月20日に『フィガロ』紙に発表された数ヶ月後には日本語に訳されている。したがって、芸術と近代的技術の融合の初めの軌跡は、1910年代にまで遡ることになる。ちょうど映画、写真、そしてキネティックな彫刻が登場していた頃だ。それまで厳密に隔てられていた異なる芸術分野が、ヨーロッパのダダイストやシュールレアリスト、構成主義の芸術家、そして〈バウハウス〉の運動の影響によって、ついに歩み寄り始めていた。そして建築やデザイン、家具、服飾、絵画、照明、音楽、演劇、映画、写真、ホログラフィーの問題が、「相互補完性」という新しい光の下に見なおされることとなるのだ。また戦前は、この種のコミュニケーションを励ます社会主義のメッセージに応えるアーティストもいた。もっとも、大々的に検閲が行われていた緊張した空気の中で、その動きは妨げられはしたが。基準通りの芸術の間の「相互補完性」、つまり芸術の「ジャンル」の開放は、古典的な芸術分野の間隙で創造し、混成の芸術を作り出すもので、20世紀のアカデミズムの信奉者たちから疑いや敵意をもって見られた。一例を挙げれば、エティエンヌ・スリオの「様々な芸術間の連絡」という概念は、その論理がいかに慎重なものであっても、「良識ある」人々の目には左派のイデオロギーを構成するものと映った。彼らは、自分たちにとって神聖な各分野をごちゃ混ぜにする恐れのある概念をつかまえて、好き勝手に横滑りしていたのではないだろうか。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第十章 結論10∞1.』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第十章 結論10∞1.』
1967年にアメリカでマイケル・フリードが『アートフォーム』誌に書いた「芸術と物性」という記事は、意味のある論議だったといえるだろう。近代主義の代表的な理論家、クレメント・グリーンバーグの弟子であるフリードは、ミニマリズムを攻撃し、混成芸術は半分魚、半分肉であるようなあいまいな作品を作って、通時的感覚様式を危険に陥れたり身体的な身振りにおとしめていると主張し、それは人間の感覚様式を、演劇、つまり「唯一の真実である抽象的本質を忘れた実存的現前」の(頽廃的)混沌へと還元してしまうと書く。フリードは深刻な調子で続ける。「芸術は、演劇的条件に近付くとたちまち頽廃する」。フリードの明晰な論理は、ミニマリズムのみならずローシェンバーグもジョン・ケージもシュールレアリズムもダダも退けてしまう。しかし反近代の側では、「演劇的な」、あるいは「ポスト・モダン的な」多くの前衛芸術の中で、混合は必然的なものとなっていた。このような混合は、日本に目を向けると一層強く感じられる。恐らくはパラドックスとひきかえにではあるが。しかし西田幾多郎が言ったように、日本的論理とは、「同時に存在する相反するものの逆説的な弁証法」のことではなかったか。1940年代に、京都学派の最も勝れた哲学者たち、ジョン・ケージの未来の師である鈴木大拙や、西谷啓司が盛んに討論していた。このことはオーギュスタン・ベルクが和辻哲郎の思想を研究していることから、彼によって取り上げている。いったいどのような討論だったのだろうか。マイケル・フリードは25年後にこの時のことを取り上げて、西洋の芸術から「社会環境の現実である場の論理」を取り除かなければならないと主張することになる。それは「Aが非Aになりうる」論理であり、「矛盾も意味の相反も知らない映像的な論理」である。これに対してフリードの、そしてヨーロッパの伝統的な論理とは、「矛盾や意味の相反に従うディスクールの論理(つまり狭義の論理、ロゴスの論理)」である。ロラン・バルトがいつもの鋭い洞察力で日本の風習の根本的な「演劇性」について述べていたことを、ここにも見いだすべきなのだろうか。本論は、テーマを「映像芸術」に限っており、オーギュスタン・ベルクが紹介したような和辻の哲学的思考を研究することは、明らかに目的の範囲外である。しかし、「風土性」、すなわちベルクの翻訳によれば、「社会環境に対する人間存在の関わり」は、和辻が1935年に『風土』という著作で展開した学説を越えて、ここで取り上げた様々な芸術上の実験にも影響を与えている。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第十章 結論10∞1.』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第十章 結論10∞1.』
しかし、日本のアーティストがこのような実験を行う自由を得たのは、やっと戦後になってからである。モホイ・ナジ、アレクサンダー・カルダー、ジョージー・ケペーシュに影響を受けて出発した〈実験工房〉のメンバーたちは、まもなく日本の前衛芸術の代表者として認められる。〈実験工房〉から生み出された作品は、複数のカテゴリーを混合したもので、一つの分野に入れることが、本質的に不可能なものばかりであった。芸術は、様々な組合せを可能にするメディアと深く関わっていく。このような作業に発表の場を与えたのは、まず1949年から1963年まで続いた〈読売アンデパンダン展〉であり、ついで新しい芸術傾向の発者として、70年代初めまで指導的な役割を果たした〈草月アートセンター〉である。このような観点から見ると、山口勝弘の作品はカテゴリーやジャンルに挑む「メディア・アート」の最初の例と言える。山口は大変明晰に芸術分野におけるメディアの有効性を示し、本質的な機能を表す包括的な用語、「イマジナリウム」という言葉に統括した。それは、イマジネーションが生まれることを可能にする環境という意味である。初期の作品《ヴィトリーヌ》にすでにテクノロジーが登場している。二次元絵画を三次元の環境に変換しているのである。絵の上にモールグラスを重ねることで、見る者が位置を変えることを促し、一挙に様々な伝統に近付いた。キネティック・アートを産んだ構成主義、そしてすでに何世紀もの歴史を持つ日本の「環境芸術」、庭園である。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第十章 結論10∞1.』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第十章 結論10∞1.』
詩人の瀧口修造は、20世紀の日本の芸術界で、最も重要な役割を果たした人物である。アンドレ・ブルトンやマルセル・デュシャンの友人である瀧口は、ダダイズムとシュールレアリズムの重要性をいち早く支持した。そして、1947年からマヤ・ダレンやホイットニー兄弟の映画を紹介していた。50年代初めに、若い芸術家たちが<実験工房>という名の下に集まり、戦後日本の芸術界を先鋭的なアバンギャルドへと引っ張っていくよう、励ましたのも、やはり瀧口である。<実験工房>の独創性は、仲間が才能を集結し、共同で仕事をするときに一段と際立った。そんな中、1953年に、山口勝弘と北代省三は、踊りと歌のマルチメディア・スペクタクルを必要としていた日劇ミュージックホールの支配人、岡田恵吉に招かれ、実験映画《モビールとヴィトリーヌ》を作った。この映画は当時、実験映画ではなく、抽象映画と名付けられ、同年9月、アメリカ文化センターで、単独上映された。ついで山口と作曲家の武満徹は、映画作家、松本俊夫の協力で、日本初の実験映画、《銀輪》を35ミリのカラーで製作するという、またとないチャンスを手に入れた。自転車の販売促進のために用意されていた予算を、最大限に活用できることになったのである。1986年にポンピドウー・センターで開かれた<日本実験映画展>では、イメージ・フォラムの中島崇によって選ばれた作品が出品された。1955年に、<グラフィック集団>の大辻清司、石元泰博と辻彩子が制作した《キネカリグラフ》は、約150mの16mmフィルムに引っ掻き傷を付けたものである。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-3. 日本の実験映画の誕生』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-3. 日本の実験映画の誕生』
関東の<実験工房>に対して、関西の芦屋市に生12まれた<具体美術協会>も映画の制作を行っていた。現在名古屋在住の嶋本昭三は1958年の第2回舞台を使用する具体美術展の際に《具体映画》を発表した。天皇陛下が現われていたニュース映画を変色させ、作ったものである。松本俊夫が映画作家として活動を続け、《安保条約》(1959)と《西陣》(1961)が国際映画フェスティバルで受賞する。また評論家として、1958年に、『前衛記録映画論』を出版し、商業映画から開放する「もう一つの映画」の必要性を宣言する。日本大学に<日大映研>が設立され、1958年、彼らの初めての白黒16ミリフィルムを何本か製作した。まだ学生であったにもかかわらず、彼らの作品は、大学生が作る一般の映画とは、質の面ではっきりと一線を画していた。《釘と靴下の対話》(16ミリ、白黒、30分)は、造形と光の点で質の高い映画である。詩情豊かな寓話がとりあげられていて、ドキュメンタリーでもフィクションでもなく、既成のどんなカテゴリーにも属さないものである。シュールレアリスティックな場面が、やわらかな明暗の中で継起する。以後卒業まで、それぞれ同じグループで、半分実験映画、半分ドキュメンタリーという映画を撮り続ける。城之内元晴が監督をした《プープー》(16ミリ、白黒、20分、1959年)もその一つである。これは「若者の活力あふれる映画で、混乱した時代を生きることを余儀なくされた人々の中に入り、その日々の生活と青年の魂の世界をつづったもの」である。一方、神原寛は《Nの記録》(16ミリ、白黒、20分、1959年)を撮り、多数の人命を奪った1959年9月の伊勢湾台風の混乱の中で撮った映像を用い、「混乱して無感覚になった」被災者たちのインタビューで名高い。日本の初期の映画監督たちは、媒体の「新しさ」ゆえに本来の状態を保っている。そのことは、ビ14デオアートや、他の様々な分野でも同じであろう。映画の技術は1895年に生まれたにもかかわらず、日本の芸術家たちがそれをまったく自由に使い始めるのは、やっと戦後になってからだ。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-3. 日本の実験映画の誕生』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-3. 日本の実験映画の誕生』
ところで、初期の実験映画は、造形作家や写真家によって作られている。彼らは、映画の技術に厳密であろうという配慮なしに、この新しい分野に挑んでいった。この点で比較すれば、日大の学生たちは、戦前からの劇映画やドキュメンタリーの実験を継続させ、すすんで映画の伝統の中に身を置いていたということができるだろう。このタイプの映画表現の頂点は、西嶋によれば、金井勝の作品にあるという。洗練された複雑な作品の中で、現実と不条理を関わらせる金井の才能は、《無人島》(1969年)や《Good-Bye》の中に十分感じ取れるであろう。日本映画の数多い分析で有名なアメリカ人、ドナルド・リチーは、また作家で批評家でもあるが、1957年から、《青山怪談》(8ミリフィルム)、《犠牲》(1959年)、《戦争ごっこ》(1962年、16ミリフィルム、白黒、30分)、《猫と少年》(1966年)、《五つの哲学的寓話》(1967年、50分)など、多くの短篇を作った。リチーは様々なフェスティバルで日本の作品を紹介した。マヤ・ダレンやケネス・アンガーの影響を受けていたリチーは、アメリカで起きているアンダー・グラウンド映画の動きを日本に伝えた最初の人でもあったようだ。リチーはまた、日本映画の輸出にも尽力した。特に、俳句や生け花などの伝統芸術を復興するものと、リチーが認めたものを扱った。そこには、かわなかのぶひろや萩原朔美、安藤紘平、居田伊佐雄などの監督たちによって作られた作品があった。1966年、MoMA(ニューヨーク近代美術館)でのリチーの発言を引用して、西嶋憲生は、「日本は俳句の国である。俳句は、短く明晰で、内面を表現するものであり、意味ははっきりと言われるのではなく、暗示される。瞑想がコミュニケーションよりも重要である。日本の実験映画は、20年代後半に再び高まった伝統に属し、大衆の心を捉えるように作られてはいなかった。日本の実験映画は、生け花とも似ている。観客は、称賛するか、まるっきり無視するかのどちらかである。」
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-3. 日本の実験映画の誕生』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-3. 日本の実験映画の誕生』
今日では現代音楽の最も優れた批評家の一人に数えられている秋山邦晴は、かつては<実験工房>にも参加していた作曲家であり、草月会館のことを、「60年代には前衛芸術の震源地であった」と回想している。ここで草月会館の性格と歩みを振り返ってみよう。草月流は、1927年に勅使河原蒼風によって創始された。蒼風は、厳しい規則にがんじがらめになって、ごく少数の愛好家にしか見られなくなっていた生け花の将来に「満足できず、絶望していた」。そこで、父の和風に、「科学と同じくらいに厳密」で、しかも真の芸術として認められる生け花を始める手助けをしてほしいと説得する。父子は勅使河原家の家紋に草と月があることから、<草月>という名前を選んだ。草月流の初期の展覧会は、主婦の友社と、日本で最初のラジオ局、JOAKの援助で、銀座と神田で開かれた。JOAKは始まったばかりで、日本のお茶の間で絶大な人気を博していた。蒼風がラジオで連続講演を行うと、蒼風の「革命的な」表明に耳を傾ける聴衆は、どんどん増えていった。蒼風は1930年に「懐古趣味の拒否、(中略)既成の型の拒否、(中略)道徳的な観念の拒否、(中略)植物学による制限の拒否、(中略)」を宣言し、「生け花は成長し続けており、一つの決まった型に留まるものではない」と語った。1931年に父が亡くなってから、蒼風は生徒の熱意に励まされ、東京の真ん中の三番町に「草月講堂」を建てる。また、日本大学の芸術学部は蒼風を招いて、1939年、「自然の芸術」という講座を始めた。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
草月講堂は1945年5月に東京大空襲で破壊され、戦後は生け花の用具も大変見つ けにくくなったが、蒼風は1945年秋には早くも生け花の授業を再開し、在京のアメリカ人女性にも教えるようになった。そして様々なグループ展を行い、中には西洋人の生徒の作20品を展示する「国際的」な展覧会もあった。蒼風はまた、雑誌『草月人』を発刊し、マッカーサー夫人に記事を依頼したりもした。***蒼風は30年代の初めから、ヨーロッパの前衛芸術、特にシュールレアレズムに興味を持つようになる。そして、1930年までパリで生活していた福沢一郎の個展を1934年に訪ねる。「いままでの形式を脱却して、自由な精神の世界に迫まる反逆運動としてのシュールレアリスムに、いけばなにおいて同じことをめざしていた蒼風さんが共鳴したのは、きわめて当然だった。」1938年には、「華道とオブジェ」という特集を組んだ『アトリエ』の特別号に蒼風と福沢の対談が掲載された。蒼風は、床の間に飾る奇石や、生け花に使う鳥の羽や針金など、シュールレアリスムの作品を思わせるものを、「日本のオブジェ」だと言っている。40年代終わりの蒼風の作風には、明らかにこのような精神の刻印があり、当時の前衛芸術が提起する問題に対する深い理解と感受性を物語っている。読売新聞の記者だった海藤日出男の紹介で、蒼風は、後に20世紀日本の芸術の中心的存在になる芸術家たち、またはすでにそうなっていた芸術家たちと出会う機会に恵まれた。建築家の丹下健三、画家の岡本太郎22、写真家の土門拳、デザイナーの亀倉雄
策。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
策。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
蒼風ももはや単なる生け花の教師ではなかった。同時代の芸術の傾向を反映したオブジェや彫刻も作るようになっていた。出版活動にも積極的で、1951年に、息子の宏の協力で雑誌、『草月』を創刊している。宏はすでに、岡本太郎に紹介してもらった安部公房や関根弘とともに、<世紀の会>などの様々な芸術サークルに参加していた。川端康成や瀧口修造も、『草月』の編集委員として招かれた。蒼風は1955年にパリに赴き、当時特派員をしていた海藤日出男に迎えられる。海藤は、当時パリに住んでいた画家、今井俊満と堂本尚郎を蒼風に紹介する。蒼風は二人の手助けで、バガテル公園で個展を開き、「花のピカソ」と呼ばれた。また、ヨーロッパ滞在を利用して、訪れた各地で写真を撮り、日本に戻ると、<草月カメラクラブ第一回展>を企画した。そこには、50人前後のメンバーたちの作品に混ざって、土門拳、石元泰博、大辻清司、亀倉雄策、北代省三など、若い先生たちの作品も展示されていた。というのも、蒼風は常に見方を知る必要性を説き、生け花の構成を見るためにもカメラを使っていたのだ。1958年には、草月流の新しい本拠地の落成式が行われた。秋山邦晴が言っていたように、草月会館は第一級の芸術的なイベントを行う場となる。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
赤坂にあるこの建物は、丹下健三によって設計された。地下には草月ホールがあり、コンサートや映画の上映に使われることになっていた。実験的なアートが、ようやく発表の場を見つけたわけだった。***勅使河原宏は、1953年に映画界にデビューした。瀧口修造がシナリオを書いたドキュメンタリー・フィルム、《北斎》の監督を任されることになったのだ。50年代に入ると様々なフェスティバルが開かれるようになり、<ヌーベル・バーグ>も出現する。佐藤忠雄によれば、初めての傑作と呼ばれるべき作品は55年に羽仁進によって撮られた《教室の子供達》である。ここには「自然な自発性」といったものが横溢している。谷川俊太郎は、鉛筆のように扱い易いビデオの特性について語る際にこの「自然な自発性」という言葉を強調してるが、谷川のその主張は、正に、羽仁の「映画万年筆説」を思い起こさせるものである。かわなかのぶひろ (1941年生まれ)は大変独創的な映画・ビデオ作家であるが、イメージ・フォーラムの教師でもあり、次のように書いている。「画面の上に、作家は「光のダンス」という抽象的、無形態的なイメージを作って試みていた。戦後の日本では、実験映画は、映画の新しいメディア学に於ける可能性の手探り、いわゆる「Frame by Frame」の研究に始まった」。1953年27の『キネマ旬報』では、羽仁の作品が一位となり、《北斎》は第二位であった。勅使河原宏は、青年プロにいたとき知合った井川浩三と一緒に、ホールの技術的な構想をたてた。このホールで初めて上映されたのは、1957年に行われた東京フェスティバルだった。その中には、<シネマ57>のプログラムに入っていて、同年の<ブッリュッセル実験映画祭>でも紹介された、羽仁進や勅使河原宏の作品もあった。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-1. 実験映画の歴史と概要/1-1-4. 草月流の創始:いけばなと前衛』
1960年、草月会館に新しい法人組織が生まれた。<草月アート・センター>は、芸術的なイベントの企画を、自律した形で行うものだった。九人の作曲家、芥川也寸志、武満徹、林光、松平則暁、間宮芳生、黛敏郎、三善晃、諸井誠、そして岩城宏之は、作曲家集団という名のもとに集まり、お互いを分かつ専門分野を越え、日本の現代音楽を有効に発展させていこうという意志を表明した。打ってつけの場所があったのだから、あとは行動を起こすだけだった。初めの試みは、10年前に<実験工房>ですでに実践に移されていた、諸芸術の交流という考え方に基づいて、ミュージカルを創ることにした。林光の音楽に安部公房のシナリオ、それにスライドのアニメーション技術として、真鍋博が加わり、同年の三月に上演が実現した。この活動は<草月コンテンポラリー・シリーズ>として続けられることとなり、現代音楽だけでなく、モダン・ジャズも紹介された。また、音楽にとどまらず、美術、とりわけ舞台美術に貢献した。中でも1964年の山口勝弘の参加は記憶されるべきだろう。ジャン・タルデューのシナリオに基づいた《鍵穴》という作品で、<第一回草月実験劇場>として公開されたものだ。このような音楽や演劇の活動はまた、宣伝も重要である。杉浦康平は、革新的なアイディアでポスターを作った。宣伝美術という新しい芸術は、もちろん展覧会などの対象となっていった。草月アート・センターは外国の作曲家を呼ぶことにも力を尽くし、エドガー・ヴァレーズを招いた。しかし、残念ながらヴァレーズは心臓病のために来られなくなり、代わりにジョン・ケージの名が挙げられた。このアメリカの作曲家はすでに日本でも有名になっていたが、<実験工房>も<二十世紀音楽研究所>もケージを招くという計画を実行に移すことはできなかった。しかし、ちょうど一柳慧がニューヨークから帰国したところだった。そして、一柳はケージと知り合い、大きな恩恵を受けたらしく、ケージの来日を実現するためにできるかぎりのことをした。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
1962年にケージとデイビド・チュードアが、東京、京都、大阪、札幌で数々のコンサートを行った後で、中原佑介は書いている。「今年最大の収穫は、ケージの来日だ」。日本の音楽界は「ジョン・ケージ・ショック」を受け、秋山邦晴、吉岡康弘、中原佑介、高橋悠治らを熱狂させた。彼らは小野洋子が1962年3月に帰国した時、フルクサスの精神を受け継いだ、日本で最初のハプニングの一つを行い、観客がホールにいるかぎり、決して舞台から降りないという試みをした。ジョン・ケージは1964年、今度はマース・カニングハム・ダンス・カンパニーの音楽家として再来日した。舞台美術は画家のロバート・ロウシェンバーグが担当した。草月ホールはダンスを上演しただけでなく、東野芳明の企画で、ローシェンバーグに対する質問会を開いた。ローシェンバーグは、質問が的外れだと判断すると、立ち上がって、自分の沈黙を具体的に絵で表した。1950年にヴィレム・デ・クーニングの絵を消した時のように、今度は極東の芸術のシンボルである金色の屏風に、白い絵の具を塗ったのである。1958年4月15日、ダグラス・カレッジで、アラン・カプローは初めてハプニングを発表した。1959年10月14日、ニューヨークのロイベン・ギャラリーで行なわれた有名な《6部で分割されたハプニング》の際には、観客が、「ハプニングの一部となり、同時にハプニングを経験することができた」。パリのイブ・クライン、ティンゲリーとクリスト、ウィーンの<ヴィーナー・グルッペ>やジョン・ケージの<ニュー・スクール・フォア・ソーシャル・リサーチ>などは「ハプニング」と「ライブ・アート」という芸術の新方向の代表者になった。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
日本でも、比較に値するグループが設立されている。吉原治良を中心に、村上三郎、嶋本昭三、工藤哲巳、元永定正、<ゼロ・グループ>の白髪一雄、田中敦子と金子明が、<具体>グループとして、1950年代半ばからパフォーマンスを行なったことは銘記しなければならない。1955年10月、村上三郎は、東京小原ホールで障子のように張り巡らした一連の紙を、体を使って突き破るという非常に印象的なイベントを実行した。前衛的なグループによる示威行動も盛んに行なわれるようになり、<具体>、<ハイ・レッド・センター>、<ネオ・ダダ・オーガナイザー>、<九州派>といったグループが次々に生まれた。彼らは芸術的にも、社会的にも既成の価値観を打ち破ろうとしていた。そして、ヨーロッパやアメリカ、特にフルクサスの運動と結び付いたアーティストに主張を認められ、勇気を得る。ここに交流と交換の時代が幕を開けた。小杉武久は、東京芸術大学に、音楽における即興について書いた卒業論文を提出したところだった。フルクサスのアメリカでの活動が、一柳慧の尽力で草月ホールで紹介されたばかりだった。小杉もその機会に自分のグループ、<グループ音楽>を率いて、「音響オブジェ」という概念によって即興音楽のコンサートを行った。「音響オブジェ」とはこの場合、音を出すオブジェのことではなく、具体音楽の創始者たちが定義したように、オブジェとして捉えられた音のことである。ここでは、それぞれの音が、他の音とのハーモニーやリズムのためにあるのではなく、その音自身のためにあると見做される。この「音響オブジェ」は、エレクトロニック装置の場合もあったし、そうでない場合もあったが、演奏者が自分で作ったもので、しばしば大変壊れやすく見え、あらゆる思37いがけない音を出した。小杉は幼い頃からラジオが大好きで、ラジオを分解して作りなおし、コンサートの時に操作できるようにした。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
「ハイ・レッド・センター」という呼称は、創始者三人の名前から取っている。高松次郎の高、high、赤瀬川原平の赤、red、中西夏之の中、centerである。1962年11月に、九州派の「英雄たちの大集会」は博多湾で行なわれた.福岡市美術館1988年に黒田雷児学芸員等による<九州派展>が開かれた。当時<グループ音楽>には、塩見允枝子、卓植元一、戸島美喜夫、刀根康尚、水野修孝がいた。小杉武久著『音楽のピクニック』、東京、書肆風の薔薇社、1991年、小杉武久や久保田成子、靉嘔や小野洋子らは、国外、ことにアメリカに活動の拠点を求めていった。1965年6月27日、ニューヨークのカーネギー・ホールで<フルクサス・シンフォニー・オーケストラ>を主宰した秋山邦晴は、9月には東京のクリスタル・ギャラリーで、<フルクサス・ウイーク・イン・トーキョー>を山口勝弘と共に組織した。山口はこの時に《レインボー・オペーレーション》を発表している。***草月アート・センターで行われた様々なイベントが、それを支えた作曲家や美術家や批評家や映画作家たちの努力によって明らかにしているのは、当時の日本のアーティストたちが前衛について鋭い理解を持っていたこと、また、前衛とは、ヨーロッパやアメリカから来るものあったということである。ある場合には、日本のアーティストが西洋の前衛の先を行っていることもあった。草月アート・センターの活動は、1965年までは音楽や実験劇の公演に集中していたが、60年代の後半には、勅使河原宏にとって重要なものであった映画表現の方に力を入れることになる。宏は、1962年に初めての長編、《おとし穴》を撮るが、これは安部公房の同名の小説を元にしたものである。翌年には安部公房の《砂の女》を、「女」の役に岸田今日子を配し、浜松の砂丘で撮影している。この映画は日本の批評家たちの絶賛を浴び、カンヌ映画祭に行って《シェルブールの雨傘》と競った結果、審査員特別賞を受賞している。サンフランシスコやベルギー、メキシコ、そして日本でも、『キネマ旬報』や『毎日新聞』で、その年の「ベスト・ワン」に選ばれている。やはり安部公房の小説を映画化した二つの作品、1966年の《他人の顔》、1968年の《燃えつきた地図》も、多くの賞を受賞している。
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
by CHRISTOPHE CHARLES/クリストフ・シャルル
from 『論文「現代日本の映像芸術」第一章 芸術の実験:映画、インターメディア、ビデオ/1-2.1960年代、諸芸術の交流/1-2-1. 草月アート・センターの活動
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
実験工房. 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-