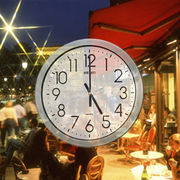|
|
|
|
コメント(14)
「業績が悪く残業代払えない」という会社の言い分は覆せるか
http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/131209/ecn13120915090011-n1.html
近年、ブラック企業の存在が顕在化し、厚生労働省が調査に乗り出すなど、国ぐるみの対応が始まっている。パワハラやセクハラ、高すぎるノルマ設定など、ブラック企業にも色々なパターンが存在するが、「残業代を払わない」というのも典型的なやり口の一つ。「残業代を支払ってくれない会社に対し、どう対処すればよいか」という質問に、弁護士の竹下正己氏はこう回答している。
【質問】
ソフト会社に勤めています。仕事は忙しく残業も多いのですが、会社は残業代を払ってくれません。払う意思はあるが、業績がともなわず払えないの一点張りです。払う意思があると説明されると、こちらは何もいえないのですが、それでも残業代を支払ってもらったほうがいいでしょうか。
【回答】
残業代は労働者の権利です。行使するかしないかはあなたの判断です。元々雇用契約は、一定の時間の労働を提供して報酬を得る関係です。その時間は、労働者の福祉と健康のため、労働基準法で一定の小規模事業を除き、一日8時間、一週間40時間が上限とされています。
雇用契約では、その範囲で労働時間を定めなくてはなりません。労働者は、非常事態を除き、時間外労働を拒否できます。これが原則ですが、使用者は労組や職場の代表との間で残業時間などを定めた36協定を結び、労働基準監督署に届けたときには、残業命令を出せることになっています。
しかし、残業した労働者に対し、残業時間に対して25%の割増賃金を支払う義務があり、午後10時から朝5時までの間はさらに25%の割増賃金が付きます。こうした残業代を使用者が支払わないと、労働者が請求したときには残業代と、同額の付加金の支払い義務を負うだけでなく、不払いには6か月以下の懲役か30万円以下の罰金の刑事罰があります。
残業時間の制約がないのは、経営の一翼を担う管理職です。そこで使用者の中には、名目だけの管理職にして(「名ばかり管理職」)残業代の支払いを免れたり、残業の申告をさせないまま働かせる、いわゆるサービス残業をさせたりする例も少なくありません。
他方、こうした違法行為に対して労働基準監督署は厳しく対処しており、会社に調査が入れば、難しいことになります。その意味では、遠慮なく残業代を請求し、会社の姿勢を正させるのも方法です。また請求しないと、残業代は時効になります。不法行為として3年という考えもありますが、確実なところは2年です。会社に残業代を請求しても無視されたら、労働基準監督署に匿名で情報提供し、調査に入ってもらうのも一案です。
※週刊ポスト2013年12月13日号
http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/131209/ecn13120915090011-n1.html
近年、ブラック企業の存在が顕在化し、厚生労働省が調査に乗り出すなど、国ぐるみの対応が始まっている。パワハラやセクハラ、高すぎるノルマ設定など、ブラック企業にも色々なパターンが存在するが、「残業代を払わない」というのも典型的なやり口の一つ。「残業代を支払ってくれない会社に対し、どう対処すればよいか」という質問に、弁護士の竹下正己氏はこう回答している。
【質問】
ソフト会社に勤めています。仕事は忙しく残業も多いのですが、会社は残業代を払ってくれません。払う意思はあるが、業績がともなわず払えないの一点張りです。払う意思があると説明されると、こちらは何もいえないのですが、それでも残業代を支払ってもらったほうがいいでしょうか。
【回答】
残業代は労働者の権利です。行使するかしないかはあなたの判断です。元々雇用契約は、一定の時間の労働を提供して報酬を得る関係です。その時間は、労働者の福祉と健康のため、労働基準法で一定の小規模事業を除き、一日8時間、一週間40時間が上限とされています。
雇用契約では、その範囲で労働時間を定めなくてはなりません。労働者は、非常事態を除き、時間外労働を拒否できます。これが原則ですが、使用者は労組や職場の代表との間で残業時間などを定めた36協定を結び、労働基準監督署に届けたときには、残業命令を出せることになっています。
しかし、残業した労働者に対し、残業時間に対して25%の割増賃金を支払う義務があり、午後10時から朝5時までの間はさらに25%の割増賃金が付きます。こうした残業代を使用者が支払わないと、労働者が請求したときには残業代と、同額の付加金の支払い義務を負うだけでなく、不払いには6か月以下の懲役か30万円以下の罰金の刑事罰があります。
残業時間の制約がないのは、経営の一翼を担う管理職です。そこで使用者の中には、名目だけの管理職にして(「名ばかり管理職」)残業代の支払いを免れたり、残業の申告をさせないまま働かせる、いわゆるサービス残業をさせたりする例も少なくありません。
他方、こうした違法行為に対して労働基準監督署は厳しく対処しており、会社に調査が入れば、難しいことになります。その意味では、遠慮なく残業代を請求し、会社の姿勢を正させるのも方法です。また請求しないと、残業代は時効になります。不法行為として3年という考えもありますが、確実なところは2年です。会社に残業代を請求しても無視されたら、労働基準監督署に匿名で情報提供し、調査に入ってもらうのも一案です。
※週刊ポスト2013年12月13日号
導入検討の残業代ゼロ法案 欧米とは似て非なるただ働き制度
http://www.news-postseven.com/archives/20130403_179843.html
安倍晋三政権が、サラリーマンを直撃するとんでもない法案を導入しようとしている。「ホワイトカラー・エグゼンプション(WE)制度」だ。
これは一定収入以上のホワイトカラーを労働基準法の労働時間規制の対象から除外(エグゼンプション)し、管理職同様、何時間働いても会社は残業代を支払わなくていいようにするものだ。ひと言でいえば、「残業代ゼロ制度」である。
首相が鳴り物入りで設置した産業競争力会議で、民間委員の三木谷浩史・楽天会長は「WEの欧米並み適用」を主張しているが、日本で検討されているのは裁量労働制と呼ばれるものだ。ホワイトカラーに勤務時間の裁量権を持たせるかわりに労働時間制限(週40時間まで)を撤廃し、何時間働いてもその社員の裁量とすることで会社は残業手当・割増賃金の支払い義務を負わないという、企業に都合のいい論理である。
それは欧米の仕組みとはまるで違う。
WE制度が生まれた米国には勤務時間の規制はなく、雇用主が労働者に週40時間以上の時間外労働をさせる場合には5割増しの賃金を支払うことを義務づけている。ただし、一定の収入と役職以上のホワイトカラーはその割り増しを除外されている。社員はそれでも困らない。米国企業に出向経験がある商社マンが語る。
「米国では原則として社員を契約で決めた以上の時間は働かせないし、社員も残業代をあてにしていない。エリートビジネスマンには土日も休まずに働くケースは少なくないが、それは成果主義が徹底されていて働くだけ収入が増える見込みがあるからです」
しかも、サービス残業は絶対タブーだという。
「経営者は契約した労働時間でどれだけ仕事を処理できるかで社員の能力を判断し、そのプロジェクトに何人のマンパワーが必要かを計算する。それなのに、社員の1人が無給で残業して仕事を進めるとどうなるか。
経営者にはその仕事が実際より少ない人数でできるという間違った認識が生まれる。それでは次に同じ仕事をするメンバーが正確な評価を得られなくなる。だからチームで仕事をする場合はサービス残業は厳禁なのです」(同前)
逆に欧州諸国は失業を減らすためにワークシェアリングを重視し、労働時間に厳しい規制をかけて残業を「悪」とみなしている。ドイツには残業の割増賃金制度がなく、管理職は労働時間の規制が適用されないというだけだ。フランスやイギリスのWEに相当する制度も、管理職や専門職を労働時間規制の対象外とし、「残業代ゼロ」でただ働きさせるわけではない。
いかにも欧米の制度を導入するかのようにいいながら、日本のWEは名前だけを利用した日本独自の「社員ただ働き制度」なのだ。
※週刊ポスト2013年4月12日号
http://www.news-postseven.com/archives/20130403_179843.html
安倍晋三政権が、サラリーマンを直撃するとんでもない法案を導入しようとしている。「ホワイトカラー・エグゼンプション(WE)制度」だ。
これは一定収入以上のホワイトカラーを労働基準法の労働時間規制の対象から除外(エグゼンプション)し、管理職同様、何時間働いても会社は残業代を支払わなくていいようにするものだ。ひと言でいえば、「残業代ゼロ制度」である。
首相が鳴り物入りで設置した産業競争力会議で、民間委員の三木谷浩史・楽天会長は「WEの欧米並み適用」を主張しているが、日本で検討されているのは裁量労働制と呼ばれるものだ。ホワイトカラーに勤務時間の裁量権を持たせるかわりに労働時間制限(週40時間まで)を撤廃し、何時間働いてもその社員の裁量とすることで会社は残業手当・割増賃金の支払い義務を負わないという、企業に都合のいい論理である。
それは欧米の仕組みとはまるで違う。
WE制度が生まれた米国には勤務時間の規制はなく、雇用主が労働者に週40時間以上の時間外労働をさせる場合には5割増しの賃金を支払うことを義務づけている。ただし、一定の収入と役職以上のホワイトカラーはその割り増しを除外されている。社員はそれでも困らない。米国企業に出向経験がある商社マンが語る。
「米国では原則として社員を契約で決めた以上の時間は働かせないし、社員も残業代をあてにしていない。エリートビジネスマンには土日も休まずに働くケースは少なくないが、それは成果主義が徹底されていて働くだけ収入が増える見込みがあるからです」
しかも、サービス残業は絶対タブーだという。
「経営者は契約した労働時間でどれだけ仕事を処理できるかで社員の能力を判断し、そのプロジェクトに何人のマンパワーが必要かを計算する。それなのに、社員の1人が無給で残業して仕事を進めるとどうなるか。
経営者にはその仕事が実際より少ない人数でできるという間違った認識が生まれる。それでは次に同じ仕事をするメンバーが正確な評価を得られなくなる。だからチームで仕事をする場合はサービス残業は厳禁なのです」(同前)
逆に欧州諸国は失業を減らすためにワークシェアリングを重視し、労働時間に厳しい規制をかけて残業を「悪」とみなしている。ドイツには残業の割増賃金制度がなく、管理職は労働時間の規制が適用されないというだけだ。フランスやイギリスのWEに相当する制度も、管理職や専門職を労働時間規制の対象外とし、「残業代ゼロ」でただ働きさせるわけではない。
いかにも欧米の制度を導入するかのようにいいながら、日本のWEは名前だけを利用した日本独自の「社員ただ働き制度」なのだ。
※週刊ポスト2013年4月12日号
残業頑張っても評価変わらず…社員と認識にずれ
読売新聞 5月13日(火)21時4分配信
社員は残業が評価につながると考えているのに、会社は人事評価で考慮していない――内閣府が13日に発表した「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」で、個人と企業の認識のギャップが浮き彫りになった。
調査は昨年9〜10月に、企業1016社と、全国の男女3154人を対象に行われた。調査結果によると、残業が上司からどう思われていると思うかを正社員に複数回答で聞いたところ、1日12時間以上働いている人のうち、最も多い53%が「がんばっている(と思っている)」と回答、12時間未満、10時間未満の正社員でも、「がんばっている」がもっとも多かった。
これに対し、「社員が残業や休日出勤をほとんどせず、時間内に仕事を終えて帰宅している」場合に、「マイナスの人事評価をしている」企業は6%で、「考慮されていない」が74%に上った。
最終更新:5月14日(水)9時10分
読売新聞 5月13日(火)21時4分配信
社員は残業が評価につながると考えているのに、会社は人事評価で考慮していない――内閣府が13日に発表した「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」で、個人と企業の認識のギャップが浮き彫りになった。
調査は昨年9〜10月に、企業1016社と、全国の男女3154人を対象に行われた。調査結果によると、残業が上司からどう思われていると思うかを正社員に複数回答で聞いたところ、1日12時間以上働いている人のうち、最も多い53%が「がんばっている(と思っている)」と回答、12時間未満、10時間未満の正社員でも、「がんばっている」がもっとも多かった。
これに対し、「社員が残業や休日出勤をほとんどせず、時間内に仕事を終えて帰宅している」場合に、「マイナスの人事評価をしている」企業は6%で、「考慮されていない」が74%に上った。
最終更新:5月14日(水)9時10分
【6月15日 AFP】就労が保障されず、雇用主から要請があった時にだけ労働力を提供する待機労働契約、いわゆる「ゼロ時間契約」が広まっている英国で先月、政府が発表した新たな案が、大きな論争を呼んでいる。デービッド・キャメロン(David Cameron)首相率いる与党は、失業給付の受給者がゼロ時間契約での就労を拒否した場合、給付を数か月にわたって一時停止することを提案している。
待機労働契約で就労している労働者は、国内に約140万人。しかし、労働組合はこうした労働者らが雇用形態を強要されていると主張。激しい反対運動を展開している。
英国で待機労働契約が導入されたのは1996年。当時のジョン・メージャー(John Major)首相と与党・保守党が柔軟な働き方を求める学生や季節労働者の雇用を容易にすることを目的に採用した。
そして現在、同国ではファストフード大手マクドナルド(McDonald's)やアイルランドの格安航空会社ライアンエア(Ryanair)の従業員、さらにはバッキンガム宮殿(Buckingham Palace)の職員の採用にまで、この労働形態が採用されている。英紙ガーディアン(Guardian)の調査によれば、英政府も待機労働契約で職員25万人を雇用している。
英統計局(Office for National Statistics)が今年1〜2月の2週間に実施した調査では、待機労働契約を導入していることを認めた雇用主は全体の約13%。観光業と飲食業、健康産業では、その割合は50%に達した。労働市場の柔軟性拡大と経済活性化を目指す欧州連合(EU)加盟各国からは、英国のこうした状況に高い注目が集まっている。
■労働者が置かれた厳しい現状
待機労働契約で3年間、重度の身体障害がある人の施設で介護福祉士として勤務したローラ・ルイス(Laura Lewis)さん(25)はAFPに対し、「常に待機していなければいけない。就労日や休暇の取得について、私たちからは何も言えない」と語った。「雇用主の意向次第で、25日間続けて勤務することもあれば、全く仕事がない時もあった」という。こうした厳しい条件のもと、待機労働契約で働く介護福祉士は約30万人に上る。
また、20年前から待機労働契約で家政婦の仕事をしているロシェル・モンテ(Rochelle Monte)さん(38)は、「仕事について、選択肢は1つもない」と話す。仕事量が安定していたことはなく、給与は月によって400〜1100ポンド(約6万9000〜19万円)と大きな隔たりがあり、仕事以外の計画を立てるのはとても難しいという。
英国の失業率は7%未満と、EU加盟国の中では低水準となっている。政府は、待機労働契約が国内経済に必要な柔軟性を増していると指摘する。
一方で批評家らは、こうした労働契約は働く側に大きな犠牲を強いていると主張している。国内最大の公務員労働、UNISONのデイブ・プレンティス(Dave Prentis)事務局長によれば、「家族がいても、住宅ローンを申し込んだり、住宅を購入したり、月々の予定を立てたりすることができない」。
労組は新たな政府案に猛反発している。国内最大規模の労働組合会議(TUC)のフランシス・オグレディ(Frances O'Grady)事務局長は、政府案は「失業者の就業支援どころか懲罰だ」と非難している。(c)AFP/Stephanie De Silguy
「英政府が狙う「ゼロ時間契約」の拡大、労組は猛反発」
http://www.afpbb.com/articles/-/3017746?pid=0
待機労働契約で就労している労働者は、国内に約140万人。しかし、労働組合はこうした労働者らが雇用形態を強要されていると主張。激しい反対運動を展開している。
英国で待機労働契約が導入されたのは1996年。当時のジョン・メージャー(John Major)首相と与党・保守党が柔軟な働き方を求める学生や季節労働者の雇用を容易にすることを目的に採用した。
そして現在、同国ではファストフード大手マクドナルド(McDonald's)やアイルランドの格安航空会社ライアンエア(Ryanair)の従業員、さらにはバッキンガム宮殿(Buckingham Palace)の職員の採用にまで、この労働形態が採用されている。英紙ガーディアン(Guardian)の調査によれば、英政府も待機労働契約で職員25万人を雇用している。
英統計局(Office for National Statistics)が今年1〜2月の2週間に実施した調査では、待機労働契約を導入していることを認めた雇用主は全体の約13%。観光業と飲食業、健康産業では、その割合は50%に達した。労働市場の柔軟性拡大と経済活性化を目指す欧州連合(EU)加盟各国からは、英国のこうした状況に高い注目が集まっている。
■労働者が置かれた厳しい現状
待機労働契約で3年間、重度の身体障害がある人の施設で介護福祉士として勤務したローラ・ルイス(Laura Lewis)さん(25)はAFPに対し、「常に待機していなければいけない。就労日や休暇の取得について、私たちからは何も言えない」と語った。「雇用主の意向次第で、25日間続けて勤務することもあれば、全く仕事がない時もあった」という。こうした厳しい条件のもと、待機労働契約で働く介護福祉士は約30万人に上る。
また、20年前から待機労働契約で家政婦の仕事をしているロシェル・モンテ(Rochelle Monte)さん(38)は、「仕事について、選択肢は1つもない」と話す。仕事量が安定していたことはなく、給与は月によって400〜1100ポンド(約6万9000〜19万円)と大きな隔たりがあり、仕事以外の計画を立てるのはとても難しいという。
英国の失業率は7%未満と、EU加盟国の中では低水準となっている。政府は、待機労働契約が国内経済に必要な柔軟性を増していると指摘する。
一方で批評家らは、こうした労働契約は働く側に大きな犠牲を強いていると主張している。国内最大の公務員労働、UNISONのデイブ・プレンティス(Dave Prentis)事務局長によれば、「家族がいても、住宅ローンを申し込んだり、住宅を購入したり、月々の予定を立てたりすることができない」。
労組は新たな政府案に猛反発している。国内最大規模の労働組合会議(TUC)のフランシス・オグレディ(Frances O'Grady)事務局長は、政府案は「失業者の就業支援どころか懲罰だ」と非難している。(c)AFP/Stephanie De Silguy
「英政府が狙う「ゼロ時間契約」の拡大、労組は猛反発」
http://www.afpbb.com/articles/-/3017746?pid=0
ABCマートの書類送検で活躍ーーブラック企業を摘発する「かとく」ってどんな組織?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150703-00003333-bengocom-soci
靴販売大手「ABCマート」(東京都・渋谷区)の従業員4人が、不適切な形で月100時間前後の時間外労働をさせられていたとして、東京労働局は同社と役員・店長2人を労働基準法違反の疑いで、書類送検した。
ABCマートは2014年4月〜5月の1カ月に、「Grand Stage池袋店」で、残業にかんする協定書を労基署に出さないまま、従業員2人にそれぞれ97時間・112時間の残業をさせた疑いがある。また、「原宿店」では、協定で定めた残業限度時間(月79時間)を超えて、2人にそれぞれ98時間・109時間の残業をさせた疑いがもたれている。
このケースは、今年4月に東京労働局に新設された「過重労働撲滅特別対策班」(通称・かとく)が、初めて書類送検した事例だという。
●どんな組織なのか?
2014年11月に厚労省が「過重労働撲滅キャンペーン」で4561の事業所を調査したところ、過半数の2304事業所で違法な時間外労働が発覚した。この結果を受け、いわゆるブラック企業への監督指導・捜査体制の強化策の一環として「かとく」が東京労働局と大阪労働局に新設された。
東京労働局は、厚労省(国)の出先機関で、都内に18ある労働基準監督署をまとめる役割を担っている。東京労働局の「かとく」には、事業所に立ち入って調査・指導や摘発を行う「労働基準監督官」が7人配属された。監督官は「特別司法警察員」として、事業所への捜査を行い、検察庁に送検する役割も担っている。
そのうちのひとりによると、所属している7人は監督官歴10年以上のベテラン揃いで、長時間労働の問題に特に強い。パソコンのデータから不正を隠すための改ざんを見抜いたり、削除されたデータを復元したりする証拠収集技術「デジタル・フォレンジック」に詳しいメンバーもいるという。
もともと、違法な長時間労働への対応は、それぞれの労働基準監督署にいる監督官が行っている。東京労働局「かとく」が担当するのは、その中でも特に、犯罪の立証に高度な捜査技術が必要なケースだ。かとくの担当者は「それぞれの労基署の管轄エリアを越えて広域で活動している大きな企業などを中心に扱っていきたい」と話している。
弁護士ドットコムニュース編集部
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150703-00003333-bengocom-soci
靴販売大手「ABCマート」(東京都・渋谷区)の従業員4人が、不適切な形で月100時間前後の時間外労働をさせられていたとして、東京労働局は同社と役員・店長2人を労働基準法違反の疑いで、書類送検した。
ABCマートは2014年4月〜5月の1カ月に、「Grand Stage池袋店」で、残業にかんする協定書を労基署に出さないまま、従業員2人にそれぞれ97時間・112時間の残業をさせた疑いがある。また、「原宿店」では、協定で定めた残業限度時間(月79時間)を超えて、2人にそれぞれ98時間・109時間の残業をさせた疑いがもたれている。
このケースは、今年4月に東京労働局に新設された「過重労働撲滅特別対策班」(通称・かとく)が、初めて書類送検した事例だという。
●どんな組織なのか?
2014年11月に厚労省が「過重労働撲滅キャンペーン」で4561の事業所を調査したところ、過半数の2304事業所で違法な時間外労働が発覚した。この結果を受け、いわゆるブラック企業への監督指導・捜査体制の強化策の一環として「かとく」が東京労働局と大阪労働局に新設された。
東京労働局は、厚労省(国)の出先機関で、都内に18ある労働基準監督署をまとめる役割を担っている。東京労働局の「かとく」には、事業所に立ち入って調査・指導や摘発を行う「労働基準監督官」が7人配属された。監督官は「特別司法警察員」として、事業所への捜査を行い、検察庁に送検する役割も担っている。
そのうちのひとりによると、所属している7人は監督官歴10年以上のベテラン揃いで、長時間労働の問題に特に強い。パソコンのデータから不正を隠すための改ざんを見抜いたり、削除されたデータを復元したりする証拠収集技術「デジタル・フォレンジック」に詳しいメンバーもいるという。
もともと、違法な長時間労働への対応は、それぞれの労働基準監督署にいる監督官が行っている。東京労働局「かとく」が担当するのは、その中でも特に、犯罪の立証に高度な捜査技術が必要なケースだ。かとくの担当者は「それぞれの労基署の管轄エリアを越えて広域で活動している大きな企業などを中心に扱っていきたい」と話している。
弁護士ドットコムニュース編集部
世界のどこででも生きていける
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161011-00002225-cakes-soci
電通の新入社員の方の自殺が労災認定された件が話題になっていますが、海外経験豊富な @May_Roma (めいろま)さんは、日本社会に殺されたようなものだと語ります。
ネットではここ数日、 電通の新入社員の方の自殺が労災認定された件が話題になっています。
東大を卒業して電通に入社した高橋まつりさんは、入社後にインターネット広告を担当するデジタル・アカウント部に配属されましたが、月の残業時間が105時間を超え、昨年12月のクリスマスの日に会社の寮から投身自殺してしまいます。
ネットを見ていると大半の人の反応は、過酷な労働環境を批判するものですが、武蔵野大学の長谷川秀夫教授は、残業100時間で自殺とは情けないという死者にムチ打つ発言で大炎上しています。(その後謝罪)
高橋さんの死は「電通や広告業界特有の働き方が問題じゃないのか」と批判する人もいますが、長谷川教授や同世代の人々が「大した残業じゃないな。俺の頃はもっと酷い」と、腐ったクリープの様な発言をFacebookとかニュース何とかに投稿しているのを見ると、過労死とか長時間労働というのは、はっきりいって、広告業界とか官庁とか商社など、高学歴ハイスペック人材が集う職場だけの問題じゃなく、日本の文化的な話なんじゃないかと思うわけです。
広告業界の働き方の闇に関しては、中川淳一郎さんの博報堂時代の体験が参考になるわけですが、必要のない業務(例:無駄なあいさつ回り)、プレゼンティズム(自分の仕事は終わってるのに、先輩や上司のおつきあいで物理的に存在しなくてはならない)、長時間労働すると評価される、必要ない行事、社内営業など、とにかく無駄のオンパレードです。
しかしこういうのって広告業界だけじゃなく、日本の多くの職場では似たようなものですね。
大概の職場にはKPIなんてなくて、長時間いれば評価されます。飲み会で甲斐甲斐しく世話役をやれば「いい人」。専門知識がないバカでも料理の取り分けやってれば首になりません。
女性が職場の嫌な男に「女子力が足りない」なんて言われて、イジメを受けるのは当たり前みたいなもんですし、定時上がりなんて出来てる人のほうが少ない。
通信環境は多分世界最高の部類の国なんですけど、相変わらず在宅勤務も広まってない。効率、効率というわりには、文書管理システムとか、プロジェクト管理システムもなかなかいれない。ケチだから生産性を高めるような道具を入れたがらない会社や上司が多い。
日本は効率的で凄いとか吠えてるサラリーマンは真性のバカというか、田舎の田吾作なんじゃないですか。日本の会社の非効率ぶり、道具を入れないケチっぷりを見ると、欧州とか北米から来た人が凍りますからね。今だにFAXなんて使ってるの日本だけですし。会議にも無駄な人が大量に来るし。
ご挨拶とか情報交換という名目で、特に用もないのに会社に来たりする。「何で日本人用もないのに来るの?俺忙しいから迷惑なんだよね。人件費1時間いくらだと思ってんの?ただで話を聞こうってアホなんじゃないの?」と言ってる人が大量にいます。顔見せただけで業務発注したり、コラボしてくれるなんて甘い考えは通用しないですよ。日本じゃないですからね。
日本の会社だと、エクセルには誰かが作った凝ったテンプレを仕込んで、経理業務や文書作成にまで使うんですけど、テンプレの変更方法が異様に難しいので、フォーマットの変更に何時間もかかるなんてバカげたことがあって、さらに大馬鹿が多い会社だと、エクセルが方眼紙になっていて、そこに要件定義をかけとかいわれるんですが、それをインドに送ってしまって、インド人技術者が激怒して会社を辞めてしまったりします。タンザニア人とかボリビア人も驚いて凍ってましたよ。ナイジェリアでさえそんなもん使いませんから。(全部実話)
こういう無駄、非効率、変な慣行に、誰も文句を言わず、提案もせず、そのままにしている。理不尽な命令をされても何もいわずに従う。 日本のサラリーマンはバカの集まりなんじゃないかと思いますよ。
バブル世代が悪い、奴らさえ消えれば変わるといってる若い人もいますけど、私から見ると、日本の若い人は、年寄りたちの非効率性や、プレゼンティズム万歳の習慣をしっかり受け継いでいますよ。
だって欧州的なやり方を提案すると、ぎょっとする人が少なくないのですもの。KPIの勉強すらしようとしない。やりましょう、文書に落としましょう といっても「そんなに厳しくしなくても」という反応が返ってくる。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161011-00002225-cakes-soci
電通の新入社員の方の自殺が労災認定された件が話題になっていますが、海外経験豊富な @May_Roma (めいろま)さんは、日本社会に殺されたようなものだと語ります。
ネットではここ数日、 電通の新入社員の方の自殺が労災認定された件が話題になっています。
東大を卒業して電通に入社した高橋まつりさんは、入社後にインターネット広告を担当するデジタル・アカウント部に配属されましたが、月の残業時間が105時間を超え、昨年12月のクリスマスの日に会社の寮から投身自殺してしまいます。
ネットを見ていると大半の人の反応は、過酷な労働環境を批判するものですが、武蔵野大学の長谷川秀夫教授は、残業100時間で自殺とは情けないという死者にムチ打つ発言で大炎上しています。(その後謝罪)
高橋さんの死は「電通や広告業界特有の働き方が問題じゃないのか」と批判する人もいますが、長谷川教授や同世代の人々が「大した残業じゃないな。俺の頃はもっと酷い」と、腐ったクリープの様な発言をFacebookとかニュース何とかに投稿しているのを見ると、過労死とか長時間労働というのは、はっきりいって、広告業界とか官庁とか商社など、高学歴ハイスペック人材が集う職場だけの問題じゃなく、日本の文化的な話なんじゃないかと思うわけです。
広告業界の働き方の闇に関しては、中川淳一郎さんの博報堂時代の体験が参考になるわけですが、必要のない業務(例:無駄なあいさつ回り)、プレゼンティズム(自分の仕事は終わってるのに、先輩や上司のおつきあいで物理的に存在しなくてはならない)、長時間労働すると評価される、必要ない行事、社内営業など、とにかく無駄のオンパレードです。
しかしこういうのって広告業界だけじゃなく、日本の多くの職場では似たようなものですね。
大概の職場にはKPIなんてなくて、長時間いれば評価されます。飲み会で甲斐甲斐しく世話役をやれば「いい人」。専門知識がないバカでも料理の取り分けやってれば首になりません。
女性が職場の嫌な男に「女子力が足りない」なんて言われて、イジメを受けるのは当たり前みたいなもんですし、定時上がりなんて出来てる人のほうが少ない。
通信環境は多分世界最高の部類の国なんですけど、相変わらず在宅勤務も広まってない。効率、効率というわりには、文書管理システムとか、プロジェクト管理システムもなかなかいれない。ケチだから生産性を高めるような道具を入れたがらない会社や上司が多い。
日本は効率的で凄いとか吠えてるサラリーマンは真性のバカというか、田舎の田吾作なんじゃないですか。日本の会社の非効率ぶり、道具を入れないケチっぷりを見ると、欧州とか北米から来た人が凍りますからね。今だにFAXなんて使ってるの日本だけですし。会議にも無駄な人が大量に来るし。
ご挨拶とか情報交換という名目で、特に用もないのに会社に来たりする。「何で日本人用もないのに来るの?俺忙しいから迷惑なんだよね。人件費1時間いくらだと思ってんの?ただで話を聞こうってアホなんじゃないの?」と言ってる人が大量にいます。顔見せただけで業務発注したり、コラボしてくれるなんて甘い考えは通用しないですよ。日本じゃないですからね。
日本の会社だと、エクセルには誰かが作った凝ったテンプレを仕込んで、経理業務や文書作成にまで使うんですけど、テンプレの変更方法が異様に難しいので、フォーマットの変更に何時間もかかるなんてバカげたことがあって、さらに大馬鹿が多い会社だと、エクセルが方眼紙になっていて、そこに要件定義をかけとかいわれるんですが、それをインドに送ってしまって、インド人技術者が激怒して会社を辞めてしまったりします。タンザニア人とかボリビア人も驚いて凍ってましたよ。ナイジェリアでさえそんなもん使いませんから。(全部実話)
こういう無駄、非効率、変な慣行に、誰も文句を言わず、提案もせず、そのままにしている。理不尽な命令をされても何もいわずに従う。 日本のサラリーマンはバカの集まりなんじゃないかと思いますよ。
バブル世代が悪い、奴らさえ消えれば変わるといってる若い人もいますけど、私から見ると、日本の若い人は、年寄りたちの非効率性や、プレゼンティズム万歳の習慣をしっかり受け継いでいますよ。
だって欧州的なやり方を提案すると、ぎょっとする人が少なくないのですもの。KPIの勉強すらしようとしない。やりましょう、文書に落としましょう といっても「そんなに厳しくしなくても」という反応が返ってくる。
結局は、文句だけ言っていて何も変えたくないのです。長時間労働や職場のヘンな慣行に従ってれば、首にはなりませんから、多くの人にとっては、多分その方がいいんです。
この件だって、多分延々と電通だけを批判して、自分の働き方のことを考える人はいないでしょう。苦しそうな同僚のことは遠くから見るだけです。
死のうがどうしようが自分には関係ないし、ライバルが一人減ったぐらいにしか感じないのでしょう。
非効率の容認、無反抗、自分だけ目立たない、苦しそうな同僚に声をかけない、自殺しそうな同僚を無理やり病院に連れて行くようなお節介をしない。
そういう冷たさ、創造性のなさ、批判精神のなさ、無関心の積み重ねが高橋さんを殺してしまったのです。これは電通だけの問題じゃなく、日本の職場全体の問題です。
著書にも書きましたが、こういう人だらけの日本は、トイレはピカピカだけど、世界一貧しい国なのです。
この件だって、多分延々と電通だけを批判して、自分の働き方のことを考える人はいないでしょう。苦しそうな同僚のことは遠くから見るだけです。
死のうがどうしようが自分には関係ないし、ライバルが一人減ったぐらいにしか感じないのでしょう。
非効率の容認、無反抗、自分だけ目立たない、苦しそうな同僚に声をかけない、自殺しそうな同僚を無理やり病院に連れて行くようなお節介をしない。
そういう冷たさ、創造性のなさ、批判精神のなさ、無関心の積み重ねが高橋さんを殺してしまったのです。これは電通だけの問題じゃなく、日本の職場全体の問題です。
著書にも書きましたが、こういう人だらけの日本は、トイレはピカピカだけど、世界一貧しい国なのです。
日本人、それってオカシイよ 「過労死」を生む日本企業の“常識”
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161018-00000019-zdn_mkt-bus_all
最近、日本では過労死の問題が大きな話題になっている。
電通に勤めていた女性社員が過労死で自殺したニュースや、長時間勤務で死亡したフィリピン人男性のケースが過労死と認定された話などが大きく報じられてさまざまな議論を生んでいる。ちなみに2015年、過労死で労災認定されたのは96人にもなり、未遂も含む過労自殺は93人が労災認定されている。
【海外メディアが指摘! 日本企業の弱点】
10月7日、日本政府は「過労死等防止対策白書」を閣議決定した。2014年に施行された過労死等防止対策推進法を受けて、厚生労働省は日本の企業や労働者に対する大規模な調査を行なって白書にまとめている。「過労死」の労災認定の目安となる月80時間を超えた残業をする正社員がいる企業は22.7%に達していることや、正社員の36.9%が高いストレスを抱えていることが判明した。
今さらだが、この状況は世界的に見ると普通ではない。
過労死などが声高に叫ばれるようになった80年代から、日本の過酷な労働状況は世界でたびたび報じられ、外国人の目に奇妙に映っている。また経済大国である日本は実のところ「生産性が悪いのではないか」との指摘まで出ている。外国のメディアで報じられている報道から、日本の労働環境について見てみたい。
●日本人が過労死してしまう理由
10月16日付のニュージーランド・ヘラルド紙は、日本人が過労死してしまう理由のひとつには、日本では転職が世界と比べてあまり行われないことが挙げられると指摘する。「労働者の大半が一度企業に入社を果たせば、会社やキャリアそのものをめったに変えることがない」日本のような国は、「従業員たちの労働時間が不健康であるとして悪名高い」と。
確かに、転職をすることでベターな労働環境を求めることはできる。追い詰められて過労死した人に「会社を辞めるべきだった」「転職するべきだった」などと言いたのではないが、確かに日本が転職に対してもっと柔軟な認識をもつ社会であれば、もしかしたら過労死した人たちのストレスは多少でも軽減された可能性はある。もう少し労働環境のいい職場に移るという選択肢にすっと頭がいくかもしれない。
米国などではさらによい労働条件を求めて転職するのは当たり前であり、給料アップや昇進のために転職をしていくことは普通である。海外のように転職によるキャリア構築は、日本では広がっていない。
ニュージーランド・ヘラルド紙はこんな問題も指摘している。日本は、「世界で見ても与えられる年間の有給休暇がかなり低い」。確かに、米経済政策研究センターのデータによれば、日本は世界と比べて有給休暇が少ない国である。同紙によれば、日本では平均10日間の有給休暇が得られる(その後、勤務年数が増えるごとに1日ずつ増え、最大で20日)のだが、他の国と比べて少ない。世界的に見て有給休暇が多いオーストリアやポルトガルは35日、スペインは34日、フランスは31日、英国では28日などと続く。
さらに問題なのは、日本人は与えられた有給休暇を消化していないことだ。旅行サイト・エクスペディアの調査によると、日本の有給消化率は60%である。ちなみに有給の多いフランス、スペイン、オーストリアなどでは消化率は100%である。この「有給休暇を使わない」感覚も、過労死の根底にはあるかもしれない。
●日本人の仕事に対する意識
日本人の仕事に対する意識も、少し心配になるような調査結果が出ている。2016年5月、世界15カ国で行われた「仕事」に対する意識調査の結果が報じられ、当時、広く世界で報じられていた。この調査からは日本人が仕事をどう見ているのが明らかになっている。
仏企業「Edenred」と調査会社「IPSOS」が世界15カ国で行なったこの調査によると、日本人は世界と比べて、ダントツで仕事にいい印象をもっていないことが分かった。日本人は仕事に対する意識が異様に低い。ちなみにこの調査によると、世界で最も仕事に前向きなイメージを持っているのはインド人だった。
ニュージーランド・ヘラルド紙はこんな問題も指摘している。日本は、「世界で見ても与えられる年間の有給休暇がかなり低い」。確かに、米経済政策研究センターのデータによれば、日本は世界と比べて有給休暇が少ない国である。同紙によれば、日本では平均10日間の有給休暇が得られる(その後、勤務年数が増えるごとに1日ずつ増え、最大で20日)のだが、他の国と比べて少ない。世界的に見て有給休暇が多いオーストリアやポルトガルは35日、スペインは34日、フランスは31日、英国では28日などと続く。
さらに問題なのは、日本人は与えられた有給休暇を消化していないことだ。旅行サイト・エクスペディアの調査によると、日本の有給消化率は60%である。ちなみに有給の多いフランス、スペイン、オーストリアなどでは消化率は100%である。この「有給休暇を使わない」感覚も、過労死の根底にはあるかもしれない。
●日本人の仕事に対する意識
日本人の仕事に対する意識も、少し心配になるような調査結果が出ている。2016年5月、世界15カ国で行われた「仕事」に対する意識調査の結果が報じられ、当時、広く世界で報じられていた。この調査からは日本人が仕事をどう見ているのが明らかになっている。
仏企業「Edenred」と調査会社「IPSOS」が世界15カ国で行なったこの調査によると、日本人は世界と比べて、ダントツで仕事にいい印象をもっていないことが分かった。日本人は仕事に対する意識が異様に低い。ちなみにこの調査によると、世界で最も仕事に前向きなイメージを持っているのはインド人だった。
この調査結果のリポートをもう少し詳しく見ると、日本人は仕事に次のようなイメージをもっていることが指摘されている。「朝、出社するのが苦痛」で、「職場環境は刺激的ではなく」、多くの社員が「上司から尊重されていない」と感じているが、「会社から何を求められているのかは明確に分かっている」。つまり、日本人は会社が自分に求めることははっきりと認識しているが、会社が嫌いなのである。この結果を見ると、日本人は会社から仕事を押し付けられて、いやいや働いている人が多いという印象を受ける。
そんな意識が原因となっているのかどうかは分からないが、海外メディアから「日本の会社は労働生産性が悪い」といった指摘も出ている。例えば、英エコノミスト紙(10月15日付)は、一連の過労死問題についてこのように書いている。「仕事の成果よりも会社で過ごす時間や仕事への献身さに価値を見出している(日本のような)文化では、仕事のビジネス慣行を根本的に変えるのは容易ではない。あるIT企業の会社員(42、匿名を条件に取材に応じた)は、『会社は大きなチームのようなもの。私が早く帰ったら私の仕事を誰かが引き継いでやる必要が出てきて、かなり罪悪感を感じる』と話す」
外国や外資系企業で働いたことがある人なら分かるはずだが、多くの外国人にはこういう「責任感」はないと言っていい。筆者は英企業に勤めた経験があるし、米国でもいくつもの企業や大学、研究所を訪問したり、友人などから話を聞いたりするが、勤務終了時間になれば、見事なまでにオフィスから皆いなくなるし、他人の仕事を気遣って残業するなんてことはまずない。特に米国では、上司が帰るのを待ってから、とか、ダラダラとオフィスに残って仕事をするなんてことがない。
ただそんな米国は、今も世界最大の経済大国である。これについては、なぜなのかと疑問に感じていたが、英エコノミスト紙はその理由を皮肉たっぷりに書いている。「(日本の)超過労働は経済にあまり恩恵をもたらしていない。なぜなら、要領の悪い労働文化と、進まないテクノロジー利用のおかげもあって、日本は富裕国からなるOECD(経済協力開発機構)諸国の中でも、最も生産性の悪い経済のひとつであり、日本が1時間で生み出すGDPはたったの39ドルで、米国は62ドルである。つまり、労働者が燃え尽きたり、時に過労死するのは、悲劇であるのと同時に無意味なのだ」
●日本人の労働生産性
日本人の労働生産性は世界的に見て、非常に低く、ほかのOECD諸国より劣る。ちなみに、世界各国は1時間でどれほどのGDPを生み出しているのか。ランキングにするとこうなる(2014年)。
1. ルクセンブルグ 79.3ドル
2. ノルウェー 79ドル
3. アイルランド 64ドル
4. 米国 62.5ドル
5. ベルギー 62.2ドル
6. オランダ 60.9ドル
7. フランス 60.3ドル
8. ドイツ 59.1ドル
(G7の平均は54.5ドル)
いかに日本の生産性が悪いかが分かるだろう。エコノミストの指摘を見れば、過労死をなくすには、日本の非効率な労働を見直す必要があるということなのだ。どうすれば米国などのように、時間内に帰れるのかを真剣に議論しなければならないのである。
最近、国際的に活躍する日本人と、外国の企業などで世界中の人たちと働く際の苦労について話をした。筆者も米国やシンガポールで働いた経験がある。日本人は、仕事が細かく丁寧で、まじめで時間に厳しく、人の良さから同僚などの仕事も助けてしまう。
一方の外国人はどうか。誤解を恐れずに言うと、日本人以外は基本的に「いい加減」である。自分の仕事しかしないし、気が利かない。そして日本人が集まると、外国人は「使えない」「ダメダメだ」などと愚痴るのだが、実はそれが普通なのかもしれない。事実、労働生産性のランキングを見ると大きな差はないどころか、日本人は劣っているのである。
これから分かることは、過労死対策として日本は強制的に労働時間を減らすしかないのではないか。そして生産性を上げるようにする。東京都の小池百合子知事は9月14日に都庁での「20時以降の残業禁止」を発表したが、これは素晴らしい提案である。例えばドイツ労働省は2013年から勤務時間後に上司が職員に連絡するのを禁止しており、同様の対策はすでに世界では始まっている。
そんな意識が原因となっているのかどうかは分からないが、海外メディアから「日本の会社は労働生産性が悪い」といった指摘も出ている。例えば、英エコノミスト紙(10月15日付)は、一連の過労死問題についてこのように書いている。「仕事の成果よりも会社で過ごす時間や仕事への献身さに価値を見出している(日本のような)文化では、仕事のビジネス慣行を根本的に変えるのは容易ではない。あるIT企業の会社員(42、匿名を条件に取材に応じた)は、『会社は大きなチームのようなもの。私が早く帰ったら私の仕事を誰かが引き継いでやる必要が出てきて、かなり罪悪感を感じる』と話す」
外国や外資系企業で働いたことがある人なら分かるはずだが、多くの外国人にはこういう「責任感」はないと言っていい。筆者は英企業に勤めた経験があるし、米国でもいくつもの企業や大学、研究所を訪問したり、友人などから話を聞いたりするが、勤務終了時間になれば、見事なまでにオフィスから皆いなくなるし、他人の仕事を気遣って残業するなんてことはまずない。特に米国では、上司が帰るのを待ってから、とか、ダラダラとオフィスに残って仕事をするなんてことがない。
ただそんな米国は、今も世界最大の経済大国である。これについては、なぜなのかと疑問に感じていたが、英エコノミスト紙はその理由を皮肉たっぷりに書いている。「(日本の)超過労働は経済にあまり恩恵をもたらしていない。なぜなら、要領の悪い労働文化と、進まないテクノロジー利用のおかげもあって、日本は富裕国からなるOECD(経済協力開発機構)諸国の中でも、最も生産性の悪い経済のひとつであり、日本が1時間で生み出すGDPはたったの39ドルで、米国は62ドルである。つまり、労働者が燃え尽きたり、時に過労死するのは、悲劇であるのと同時に無意味なのだ」
●日本人の労働生産性
日本人の労働生産性は世界的に見て、非常に低く、ほかのOECD諸国より劣る。ちなみに、世界各国は1時間でどれほどのGDPを生み出しているのか。ランキングにするとこうなる(2014年)。
1. ルクセンブルグ 79.3ドル
2. ノルウェー 79ドル
3. アイルランド 64ドル
4. 米国 62.5ドル
5. ベルギー 62.2ドル
6. オランダ 60.9ドル
7. フランス 60.3ドル
8. ドイツ 59.1ドル
(G7の平均は54.5ドル)
いかに日本の生産性が悪いかが分かるだろう。エコノミストの指摘を見れば、過労死をなくすには、日本の非効率な労働を見直す必要があるということなのだ。どうすれば米国などのように、時間内に帰れるのかを真剣に議論しなければならないのである。
最近、国際的に活躍する日本人と、外国の企業などで世界中の人たちと働く際の苦労について話をした。筆者も米国やシンガポールで働いた経験がある。日本人は、仕事が細かく丁寧で、まじめで時間に厳しく、人の良さから同僚などの仕事も助けてしまう。
一方の外国人はどうか。誤解を恐れずに言うと、日本人以外は基本的に「いい加減」である。自分の仕事しかしないし、気が利かない。そして日本人が集まると、外国人は「使えない」「ダメダメだ」などと愚痴るのだが、実はそれが普通なのかもしれない。事実、労働生産性のランキングを見ると大きな差はないどころか、日本人は劣っているのである。
これから分かることは、過労死対策として日本は強制的に労働時間を減らすしかないのではないか。そして生産性を上げるようにする。東京都の小池百合子知事は9月14日に都庁での「20時以降の残業禁止」を発表したが、これは素晴らしい提案である。例えばドイツ労働省は2013年から勤務時間後に上司が職員に連絡するのを禁止しており、同様の対策はすでに世界では始まっている。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
アフター5のススメ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-