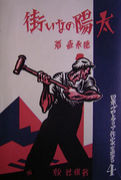5月5日、愛媛県へ、中西伊之助研究会の調査に行くことになった。中西の代表作のひとつ『戯曲武左衛門一揆』についての調査だ。
ブログに書いた。
http://
武左衛門一揆とは
山奥筋の上大野村(現北宇和郡鬼北村上大野)の百姓だった武左衛門は、藩政を改めさせようと決心。浄瑠璃語り(チョンガリともいう)になりすまし、信頼できる人物を探し歩き、三年間の内に24人の同志を得たと伝えられている。
1793(寛政5)年2月10日、武左衛門率いる山奥筋(広見川上流域)が立ち上がると、ただちに吉田藩全村が呼応。大綱を用意した人々は、恨み重なる法華津屋を打ちこわそうとした。
こうして宇和島城下の八幡河原に、吉田藩全領83か村の7646人の百姓が集結した。
八幡河原に出向いた吉田藩家老安藤儀太夫は、藩政の非をわび、速やかに願書を提出するようにと申し渡して切腹した。宇和島藩は、提出された願書をすべて認め、しかも一揆の指導者を処罰しないと裁決した。
百姓側の「まる勝ち」だった。
吉田藩は懸命に指導者を探したが、農民は誰もその名を明かさなかった。役人が、百姓たちに酒を振る舞い、一揆の指導者をほめたたえ、酔った百姓の口から、武左衛門の名を聞き出した。武左衛門は、その夜の内に捕らえ、取り調べの後、処刑された。藩は供養を禁じたが、人々はいのこ唄や盆踊りを通じて、武左衛門の功績を後世に伝えた。語ることをはばかられた武左衛門を、世に出したのは日吉村(現鬼北町)初代村長井谷正命で、明治の末のことだった。
戯曲にした中西伊之助
1925年愛媛県農民組合の井谷正吉(正命の子)の招きで、講演にきた中西伊之助は、その話を聞いた。
武左衛門に農民運動の指導者像をみた伊之助は、深く興味を持った。以後2年にわたり、伝記や文献を調べ、『戯曲武左衛門一揆』を書き上げた。
1927年5月に解放社から発刊された。芝居としては国内では上演禁止になったが、ロシヤで訳され上演されたとのことだ。
中西伊之助は、武左衛門一揆の他にも、同時期の筑紫野ー久留米藩での宝暦一揆を題材に戯曲と小説を書いている。小説『筑紫野写生帳』は伊之助最後の刊行本となった。
伊之助は、農民一揆を深く研究していた。日本の封建時代の終焉は、経済・政治の破綻とともに、庶民の運動・エネルギーが大きな役割をはたしたのであろうと、私は思う。同時に、江戸時代末期の百姓一揆には、郡上一揆や、宝暦一揆、武左衛門一揆など、大きな成功をおさめた一揆があった。そこには指導者と、青、老、壮という年代、百姓、庄屋、知識人という階層の共闘関係が存在したのではないだろうか。
伊之助の社会変革の道の探求、そして、文学活動の最後の仕事のひとつだったのが一揆研究だったのではないだろうか。単身、小豆島に移り、老体を推し、最後の力を振り絞って1967年12月25日『筑紫野写生帳』を発刊した。そして、家族の元に帰り、58年9月1日中西は永眠した。
武左衛門に革命家像を見た伊之助の代表作『戯曲武左衛門一揆』。その一揆の地、愛媛県鬼北町、宇和島市を09年5月5日、中西伊之助研究会が調査に行くことになっている。
ブログに書いた。
http://
武左衛門一揆とは
山奥筋の上大野村(現北宇和郡鬼北村上大野)の百姓だった武左衛門は、藩政を改めさせようと決心。浄瑠璃語り(チョンガリともいう)になりすまし、信頼できる人物を探し歩き、三年間の内に24人の同志を得たと伝えられている。
1793(寛政5)年2月10日、武左衛門率いる山奥筋(広見川上流域)が立ち上がると、ただちに吉田藩全村が呼応。大綱を用意した人々は、恨み重なる法華津屋を打ちこわそうとした。
こうして宇和島城下の八幡河原に、吉田藩全領83か村の7646人の百姓が集結した。
八幡河原に出向いた吉田藩家老安藤儀太夫は、藩政の非をわび、速やかに願書を提出するようにと申し渡して切腹した。宇和島藩は、提出された願書をすべて認め、しかも一揆の指導者を処罰しないと裁決した。
百姓側の「まる勝ち」だった。
吉田藩は懸命に指導者を探したが、農民は誰もその名を明かさなかった。役人が、百姓たちに酒を振る舞い、一揆の指導者をほめたたえ、酔った百姓の口から、武左衛門の名を聞き出した。武左衛門は、その夜の内に捕らえ、取り調べの後、処刑された。藩は供養を禁じたが、人々はいのこ唄や盆踊りを通じて、武左衛門の功績を後世に伝えた。語ることをはばかられた武左衛門を、世に出したのは日吉村(現鬼北町)初代村長井谷正命で、明治の末のことだった。
戯曲にした中西伊之助
1925年愛媛県農民組合の井谷正吉(正命の子)の招きで、講演にきた中西伊之助は、その話を聞いた。
武左衛門に農民運動の指導者像をみた伊之助は、深く興味を持った。以後2年にわたり、伝記や文献を調べ、『戯曲武左衛門一揆』を書き上げた。
1927年5月に解放社から発刊された。芝居としては国内では上演禁止になったが、ロシヤで訳され上演されたとのことだ。
中西伊之助は、武左衛門一揆の他にも、同時期の筑紫野ー久留米藩での宝暦一揆を題材に戯曲と小説を書いている。小説『筑紫野写生帳』は伊之助最後の刊行本となった。
伊之助は、農民一揆を深く研究していた。日本の封建時代の終焉は、経済・政治の破綻とともに、庶民の運動・エネルギーが大きな役割をはたしたのであろうと、私は思う。同時に、江戸時代末期の百姓一揆には、郡上一揆や、宝暦一揆、武左衛門一揆など、大きな成功をおさめた一揆があった。そこには指導者と、青、老、壮という年代、百姓、庄屋、知識人という階層の共闘関係が存在したのではないだろうか。
伊之助の社会変革の道の探求、そして、文学活動の最後の仕事のひとつだったのが一揆研究だったのではないだろうか。単身、小豆島に移り、老体を推し、最後の力を振り絞って1967年12月25日『筑紫野写生帳』を発刊した。そして、家族の元に帰り、58年9月1日中西は永眠した。
武左衛門に革命家像を見た伊之助の代表作『戯曲武左衛門一揆』。その一揆の地、愛媛県鬼北町、宇和島市を09年5月5日、中西伊之助研究会が調査に行くことになっている。
|
|
|
|
|
|
|
|
プロレタリア文学 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
プロレタリア文学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75489人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6451人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人