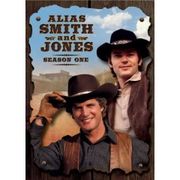放送日 1973/01/27
監督 Nicholas Colasanto
原案 Arnold Somkin and John Thomas James
脚色 John Thomas James
ゲスト Carmen Matthews :ミセス・キャロライン・レングレー[ Caroline Rangely ],
John Ragin :エドワード・フィールディング[ Edward Fielding ],
Sian Barbara Allen :シスター・グレース[ Sister Grace ],
Patricia Harty :ルーシー・フィールディング[ Lucy Fielding ],
Logan Ramsey :スマザーズ[ Smithers ]
http://
http://
ここはとある西部の町。昔は金が出てにぎわっていたが、今ではゴーストタウン1歩手前のようなうら悲しさが漂っている。乾燥がひどく、あちらもこちらも砂埃だらけ。こういう場所にはつきもののタンブリング・ウィードが大きな塊となって、風が吹くたびにコロコロと転がっていく。
ヘイズとカーリーはそんな町にたどり着いた。二人はゆっくりと、町の空気を感じながら馬に乗っている。
「なんつったけ、この町?」カーリーが尋ねる。
「アパッチスプリング」ヘイズはいつもカーリーの問いにすぐさま答える。
「いいねぇ。我が家みたいなムード。ひなびた感じでしっとりと」
「ほぉんと。おまけに保安官なしときたもんだ」
いつながらの二人の会話である。
少し行くと、小さなホテルの前に着いた。二人は馬を降り、中に入っていく。
そこには小太りの、少し髪が寂しくなりかけている中年のホテル・オーナーがいた。
「はいはい、いらっしゃいませ」オーナーは少し媚びたような笑顔を見せる。
「お部屋とお風呂、たのんますよ」カーリーが言うと、
「ついでに馬の面倒みてもらいたいな」ヘイズが続く。
「はいはい、ただいますぐやらせますので、まずは宿帳の方おば・・・」
宿帳を差し出すオーナーを横目に、ヘイズはあたりを見回す。
「ポーカー、やってないの?」ヘイズは暇つぶしを探しているようである。
「たいがい土曜の晩にご開帳でございまして、カーボーイが集いまして、酒にポーカーという段取りで・・・」オーナーが言うと、すかさずカーリーが
「待つよ」
「どうせヒマなんだから」ヘイズも間髪を入れない。
オーナーは二人の言葉に驚き、
「しかしあなた、6日もお待ちになりましても、お素人集の勝負でございますよ」
「お素人結構、ボク大好き」またもヘイズは間髪入れずに答えた。
そんな会話に中年おばさんが割り込んできた。
「ちょいごめんなさい。でしゃばりおばさんと思われるかもしれないけど、若い男前が二人もそろってくりゃ、好奇心が沸くのが人情ってもんでね。あんたたち仕事は何やってんのよ?」
「ええ、まぁあちこちであれこれと・・・」カーリーが答えると、
「あっそういうの。言いたくないってのね」おばさんはむっとする。
ヘイズはあわててカーリーの言葉に付け加えて、
「そうじゃなくて、何でも屋だってんですよ。手間賃しだいでなんでも」
「ああ、了解。じゃ、落ち着いてからでいいからさ、後で話に来てくんない?」
「あ、いいですよ」
「喜んで」
二人はそういい残して2回の部屋へ向かった。
おばさんは少しほくそえみ、オーナーにこう言った。
「ねぇ、スマザーズ。おあつらえ向きの兄さんが転がり込んできたようよ。若くって、丈夫で、身軽でさ。りこうそうでないの」
四頭立ての馬車が砂埃を上げてやってくる。スマザーズと呼ばれるオーナーは馬車を出迎えにドアから出てきて、馬車を覗き込んだ。
「これはこれは、フィールディング様。おそろいでようこそ。お手紙頂きまして、用意万端整えてお待ち申し上げておりました」
馬車にはとても楽しそうな笑顔の男性と、とても不愉快そうな顔の女性が乗っていた。
「いやぁ、ありがとうありがとう。楽しいねぇ、本物の西部は」
男性の妻とおぼしきその女性はあからさまにいやそうな顔をして、大きなため息を一つついた。スマザーズが荷物を運び、3人はホテルの中へと入ってくる。相変わらず不満いっぱいの女性ははき捨てるように、
「この砂埃、どこからやって参りますの? どこかで製造してるんですか?」
スマザーズは少し困ったような顔をして、
「いや、ははは・・・え、お部屋は当方で最高の続き部屋にしておきましたから、はい・・・」
「それにこの暑さ! 暖房でしたらとめていただけませんかしら!」
そう捨てセリフを残して女性は2階の部屋へと去っていった。
2階の部屋からヘイズとカーリーが降りてきた。
「お二人さん、こっちこっち」おばさんが二人を見つけて、バーのカウンターからそう言った。
「お兄さんがた、今なんか予定あるの?」
「いや、土曜日のポーカーまで空きなんですよ。御用があるなら承りますよ」カーリーが答える。
「いい仕事があんのよ。儲けさせるよ」
「ははは、どういうの?」ヘイズが聞くと、
「いやなに、あるものを回収して、持って帰りゃいいのよ。」と答えるおばさん。
「あるものってのは?」怪訝そうにカーリーが言う。
「カネよ。それも札なんてけちなもんじゃない、砂金よ」
「あ、そりゃいいお話」カーリーは嬉しそうな顔で話に食いついてきた。
「いいぞ、乗ってきたね。飲んどくれ。ビールでいいね。はいよ」おばさんは二人にビールを注ぎながら話を続ける。
「あたしゃキャロラインっての。ミセス・レングレー。どっちでもいいよ。でもママさんとかおばさんなんてのだけはお断りだよ」
「わかりました。で、その砂金の話だけど・・・」ビールを飲みながらヘイズが聞く。
「あせらないの。仕事の内容詳しく言ったら、やる気なくすかもよ」
「なくすかもね」あっさりと答えるヘイズ。
「なによ、その態度は! せっかく儲けさせるってのに」
怒ったキャロラインの言葉に、
「ああ、何もそんなつもりじゃぁ・・・」ヘイズはあわてて訂正する。
「もういい、もういい。今日日はまともすぎるヤツばっかりでさ。肝っ玉の据わった男らしい男なんていやしないや。自分の影におびえてさ、腰抜かしてんだから、世話無いよ」「腰抜かすようなことなの?」カーリーが尋ねる。
「あぁん、あんた、インディアンよ。あたしらね、夫婦でここへきたのが20年前だったよ。この辺ももっと田舎でさ。亭主はバーニーって名で。もう天に召されちゃったがね。とにかくあの頃はさ、みんな助け合ったもんだよ。信じあってさ。ところがどう?今じゃもう」
「ほんと、わかるな」妙に納得するカーリー。
「わかるんならもうちょい打ち解けてちょうだいよ」
「いいだろう。でぇ、金ってどこにあるんだ、キャロライン?」話の先を聞こうとヘイズが促す。
「その20年前はね、この裏の山で金が出てゴールドラッシュだよ。でもそれも一時。やがて掘り尽くしちゃった。さて、あたしと主人はね、2年前に行ってみたんだよ。もう掘ってるものはいやしない。そこをかっさらって砂金で6千ドルがとこ集めたわけよ。もっとも場所は12箇所になったけど。集めては埋める、埋めては次へ移ったわけよ。」
「それで?」興味津々のヘイズ。
「インディアンよ!しゃくだねぇ。チリカワ族が5・60人、居留地から脱走してさ、山に立てこもっちゃったんだわさ。生意気にもう、あたしらを撃ちゃがんの。バンバン撃ってくるの」
「そのときだんなが・・・」察したカーリーが言う。
「やられちまったよ、バーニーは。チリカワのやつにさ」がらにもなく少ししょげるキャロライン。
「で、砂金のほうは?」神妙な顔をしながらも、一番の目的が気になるヘイズである。
「冷たいねえ。亭主が死んだ話をしてほろっとなってるのに、横から金は、金はって」
天を見上げるおばさん。
「金はどうなった?」バツ悪そうに、しかししつこく尋ねるヘイズ。
「いまだに埋めたまんまなのよ。どう?」
「どうって〜、何が?」よく飲み込めずにヘイズが言った。
「やるかやらないかよ。山へ行ってもらいたいのよ。あそこ行って、あたし達が埋めた砂金を掘り出して、持って帰ってもらいたいの。そしたら・・・そうね。20%、あげちゃうわ」
「20%!?」呆れ顔のヘイズ。
「インディアン、何人いるって言った?」納得いかない顔のカーリーが言う。
「そうね、噂じゃ5・60人かな。なぁに、腹を空かせたひょろひょろインディアンよ」
「フッフッ」お話にならない、という感じでカーリーが笑う。
「でもだんなを殺したんだろ?それがいる山へ20%で行けっての?」ヘイズは明らかに不服そうである。
「だってあたしらは2年がかりよ。あんた達なら2日ですんじまうじゃないのよ」
「それはそっちだけの言い分だよ」
「3人で3等分だね」当然、といった顔でカーリーが言った。
「3等分!?」キャロラインの言葉に顔を見合わせる二人。ヘイズはキャロラインを説き伏せようと、
「そう、それが当然だと思うよ」
(この時、2台目の馬車が若い女性を運んでやってきた)
「誰がそんなこと! 死んでもやだよ。なんだよこの恥知らずやろうが!
か弱い女の足元を見てつけこみやがってからに! けっ、っもう!」
おばさんはものすごい剣幕でまくし立て、去って行く。
「ヘイズよ」
「うん?」
「か弱いんだってさ」
「あのタンカで?」
「ふふふ・・・」
二人は仲良く、乾杯。
馬車から女性が降りてくる。馬車の御者は乱暴に女性の荷物を馬車から放り投げて、馬車を走らせて行ってしまった。それを見ていたカーリーが女性に声をかけた。
「荷物、持ちましょうか?」
「すいません」
「人手が無くてね。愛想が無い町なんです」荷物を運びながら女性に言った。
ホテルの中に入ると、女性はカーリーにチップを渡そうとした。
「あはは、いいんですよ。ボーイじゃないから」そう言ってカーボーイハットを脱ぎ、軽く会釈をした。
「すいません」
女性はスマザーズの姿を見つけ、近づいていった。それに気付いたスマザーズは、
「おお、これはこれは、いらっしゃいませ」
「部屋が欲しいんですけど・・・」
「どうぞどうぞ、よりどりみどりです。へへへ」宿帳を差し出すスマザーズ。
「ただ、困ったことに・・・あたしあの・・・お金を持ってないんです」
「それはゆゆしき大問題ですな」
「ここまで来るのに駅馬車の切符代に有り金はたいてしまったんです」
「顔に似合わぬ無鉄砲なお方ですな」
「今度の日曜まで待っていただけません? そしたら払えますから。あたし、巡回説教師なんです。伝道師です。お説教しますから、寄付も集まると思うんです」
シスターと思しきその女性は一生懸命話している。しかしスマザーズはあまり聞いていなさそうである。
「あのね、お嬢さん。このアパッチスプリングも昔は金がでて、そりゃあ人もわんさか集まってきましたよ。だけど今じゃあなた、人口はわずかの60人。しかもそのうち30人は近くにちらばってる牧場のカーボーイという状態だ。日曜日は全員二日酔い。あんたがどんなありがたいお説教をするか知らないが、耳を貸すやつなんていやしないよ。寄付なんか当てにするだけ損ってもんだ」スマザーズはシスターにそう言うが、シスターの方はかたくなである。
「あたしは神を信じてます」
「あっそう・・・あ〜、名前を伺っておきましょうか?」
「シスター・グレースと申します」シスターはにっこり笑って答える。
「どうだろうね、予定外の客があって人手不足なんだが・・・コックをやってくれたら部屋を提供するがね。もちろん食事も」
この申し出にきょとんとして、シスターが尋ねた。
「給料はいただけないんですか? 部屋と食事だけですか?」
スマザーズは少し後ろめたそうに顔をそむけて答えた。
「いやいや、そんなひどいことは言わないよ。一週間に8ドルで」
「部屋代は普通おいくら?」
「週4ドルだね」
「食費は?」
「週に4ドル」
「引き受けます」
商談成立である。少し納得がいってなさそうではあるが・・・
部屋で泡風呂に入り、リラックスしているヘイズ。そこへドアのノックが聞こえ、ヘイズは驚いてガンを取り、ドアに向けた。そこへ入ってきたのはあのおばさん、キャロラインだった。ヘイズは慌ててガンを別の方向に向け、自分は泡の中に沈んだ。
「負けたよ、ぼうや。フィフティ・フィフティの山分けでどうだい?」
おばさんの提案にヘイズはのった。
「よっしゃ。この格好なんで、握手はかんべんな」
「ああ、いいっていいって。女が見て平気は裸はとイエス・キリストだけだ。うまいだろバーニー? ははは」
「ははは、はははは・・・」
笑いながら、ぶくぶくと泡の中に沈んでいきそうなヘイズであった・・・
食堂でヘイズ、カーリー、そしてキャロラインの三人がテーブルを囲んでいる。
「うぶっぽい顔してるくせに、どうして食えない兄さんだよ」「へへへ」肉を切りながら笑うヘイズ。「でも引き受けた限りはバッチリやるよ。ま、まかしといてもらいましょう。さ、食って食って食って」カーリーは育ちが良くないらしく、フォークをキャロラインに向けて話している。そこへ先ほどの夫妻がやってきた。それを見つけたキャロラインが二人を誘う。
「あ、いらっしゃいよこっちへ。食事はみんなでわいわいやった方がうまいよ」
「いやぁ、こりゃどうも」
ヘイズとカーリーは立ち上がって、ヘイズは握手を求めた。
「初めまして。ジョシュア・スミスと言います」
「わたくし、フィールディング。これ、家内のルーシー」
「よろしく。こちらはキャロライン・ラングレーさん。」
「よろしく」
「サディアス・ジョーンズです」カーリーも握手を求める。
「スミスとジョーンズ? ますます食えないわね」怪訝そうな顔をするキャロライン。
「またなんだってこんな辺鄙なとこにいらしたんです?」話題を変えるカーリー。
「わたし、インディアン管理局から派遣されましてね」
「インディアンをどうするっていうんです? チリカワ族ってのは、結構血に飢えてますよ」おばさんは興味津々に尋ねた。
「さぁて、どうしたもんですかね。まずは会って話してみますか」
その言葉にヘイズの肉を切る手が止まった。
「軍隊を連れて行くんですか?」キャロラインも驚いてそう聞いた。
「主人にそんなものいりませんわ。たとえ相手がインディアンでも話せば分かるという主義ですから、軍隊なんて」
バカにしたような感じで答えるのは妻のルーシー。その雰囲気を察してヘイズが続けて言った。
「なるほど、そうですか。で、やつら何で居留地を飛び出したんです?」
「実は管理官の一人が彼らに渡す肉を横流ししまして・・・そいつは転勤させたんですがまだあるんですよ。土地の状態が約束とはだいぶ違うんですね。それで怒ったんです。
で、私が全権大使として、チリカワ族の気持ちを和らげようと、そういう訳なんです」
「荒れてんですか、やつら?」インディアンの動向が気になるカーリーが尋ねた。
「報告によると相当後悔しているようですが・・・何か気にかかる理由でも?」
「うん、山へ行くんでね。インディアンのいる方へは行かないけど」ヘイズが答えた。
「しかしそううまくは・・・」
「うまくやりたいってことです」カーリーがヘイズの顔を見ながら言った。
「ははは」こんな会話を楽しんでいるかのようにフィールディングは笑った。
「どうなの、キャロライン? インディアン部落のど真ん中へ行けっての?」
カーリーは非難するような目でおばさんを見ている。
「大丈夫よ、あいつらがとぐろ巻いてんのは、東だもん。あたしたち西の方でもやっといたからさ、そっちからかかってよ」
「残ったものは何すればいいんでしょう?」相変わらず不機嫌そうにルーシーが尋ねる。「何がやりたいんです」少し機嫌を取るようにヘイズが言うと、
「それがとんとわからなくて・・・西部旅行は初めてだし。実は早くも帰りたくなってますの」投げやりに答えるルーシー。
「土曜日の晩になれば少しは景気良くなりますよ」カーリーはルーシーをなだめるようにそう言った。
「おや、何かありますの?」
「あ?ああ、その辺のカーボーイが集まってきましてね。飲む、打つ、喧嘩で絢爛たるお遊び絵巻を繰り広げるんですよ」楽しそうに説明するヘイズ。
「それは景気もでるだろうよ」
フィールディングは嬉しそうに笑っている。しかし、ルーシーは相変わらず無愛想な顔をしていた。
地図を入れた鍵つきの頑丈な黒い箱が金庫の中にある。スマザーズはその金庫を開け、その箱を取り出し、キャロラインに渡した。
「んん〜」咳払いをするスマザーズ。キャロラインは嬉しそうな顔をして受け取り、鍵を開ける。
「はさみ取って」
「あぁん」
おばさんは新聞紙大の比較的大きな地図を取り出し、1/6ほどを切り取った。そしてまた大事そうにしまい込んで、鍵をかけた。
(続きと感想は、コメントへ)
監督 Nicholas Colasanto
原案 Arnold Somkin and John Thomas James
脚色 John Thomas James
ゲスト Carmen Matthews :ミセス・キャロライン・レングレー[ Caroline Rangely ],
John Ragin :エドワード・フィールディング[ Edward Fielding ],
Sian Barbara Allen :シスター・グレース[ Sister Grace ],
Patricia Harty :ルーシー・フィールディング[ Lucy Fielding ],
Logan Ramsey :スマザーズ[ Smithers ]
http://
http://
ここはとある西部の町。昔は金が出てにぎわっていたが、今ではゴーストタウン1歩手前のようなうら悲しさが漂っている。乾燥がひどく、あちらもこちらも砂埃だらけ。こういう場所にはつきもののタンブリング・ウィードが大きな塊となって、風が吹くたびにコロコロと転がっていく。
ヘイズとカーリーはそんな町にたどり着いた。二人はゆっくりと、町の空気を感じながら馬に乗っている。
「なんつったけ、この町?」カーリーが尋ねる。
「アパッチスプリング」ヘイズはいつもカーリーの問いにすぐさま答える。
「いいねぇ。我が家みたいなムード。ひなびた感じでしっとりと」
「ほぉんと。おまけに保安官なしときたもんだ」
いつながらの二人の会話である。
少し行くと、小さなホテルの前に着いた。二人は馬を降り、中に入っていく。
そこには小太りの、少し髪が寂しくなりかけている中年のホテル・オーナーがいた。
「はいはい、いらっしゃいませ」オーナーは少し媚びたような笑顔を見せる。
「お部屋とお風呂、たのんますよ」カーリーが言うと、
「ついでに馬の面倒みてもらいたいな」ヘイズが続く。
「はいはい、ただいますぐやらせますので、まずは宿帳の方おば・・・」
宿帳を差し出すオーナーを横目に、ヘイズはあたりを見回す。
「ポーカー、やってないの?」ヘイズは暇つぶしを探しているようである。
「たいがい土曜の晩にご開帳でございまして、カーボーイが集いまして、酒にポーカーという段取りで・・・」オーナーが言うと、すかさずカーリーが
「待つよ」
「どうせヒマなんだから」ヘイズも間髪を入れない。
オーナーは二人の言葉に驚き、
「しかしあなた、6日もお待ちになりましても、お素人集の勝負でございますよ」
「お素人結構、ボク大好き」またもヘイズは間髪入れずに答えた。
そんな会話に中年おばさんが割り込んできた。
「ちょいごめんなさい。でしゃばりおばさんと思われるかもしれないけど、若い男前が二人もそろってくりゃ、好奇心が沸くのが人情ってもんでね。あんたたち仕事は何やってんのよ?」
「ええ、まぁあちこちであれこれと・・・」カーリーが答えると、
「あっそういうの。言いたくないってのね」おばさんはむっとする。
ヘイズはあわててカーリーの言葉に付け加えて、
「そうじゃなくて、何でも屋だってんですよ。手間賃しだいでなんでも」
「ああ、了解。じゃ、落ち着いてからでいいからさ、後で話に来てくんない?」
「あ、いいですよ」
「喜んで」
二人はそういい残して2回の部屋へ向かった。
おばさんは少しほくそえみ、オーナーにこう言った。
「ねぇ、スマザーズ。おあつらえ向きの兄さんが転がり込んできたようよ。若くって、丈夫で、身軽でさ。りこうそうでないの」
四頭立ての馬車が砂埃を上げてやってくる。スマザーズと呼ばれるオーナーは馬車を出迎えにドアから出てきて、馬車を覗き込んだ。
「これはこれは、フィールディング様。おそろいでようこそ。お手紙頂きまして、用意万端整えてお待ち申し上げておりました」
馬車にはとても楽しそうな笑顔の男性と、とても不愉快そうな顔の女性が乗っていた。
「いやぁ、ありがとうありがとう。楽しいねぇ、本物の西部は」
男性の妻とおぼしきその女性はあからさまにいやそうな顔をして、大きなため息を一つついた。スマザーズが荷物を運び、3人はホテルの中へと入ってくる。相変わらず不満いっぱいの女性ははき捨てるように、
「この砂埃、どこからやって参りますの? どこかで製造してるんですか?」
スマザーズは少し困ったような顔をして、
「いや、ははは・・・え、お部屋は当方で最高の続き部屋にしておきましたから、はい・・・」
「それにこの暑さ! 暖房でしたらとめていただけませんかしら!」
そう捨てセリフを残して女性は2階の部屋へと去っていった。
2階の部屋からヘイズとカーリーが降りてきた。
「お二人さん、こっちこっち」おばさんが二人を見つけて、バーのカウンターからそう言った。
「お兄さんがた、今なんか予定あるの?」
「いや、土曜日のポーカーまで空きなんですよ。御用があるなら承りますよ」カーリーが答える。
「いい仕事があんのよ。儲けさせるよ」
「ははは、どういうの?」ヘイズが聞くと、
「いやなに、あるものを回収して、持って帰りゃいいのよ。」と答えるおばさん。
「あるものってのは?」怪訝そうにカーリーが言う。
「カネよ。それも札なんてけちなもんじゃない、砂金よ」
「あ、そりゃいいお話」カーリーは嬉しそうな顔で話に食いついてきた。
「いいぞ、乗ってきたね。飲んどくれ。ビールでいいね。はいよ」おばさんは二人にビールを注ぎながら話を続ける。
「あたしゃキャロラインっての。ミセス・レングレー。どっちでもいいよ。でもママさんとかおばさんなんてのだけはお断りだよ」
「わかりました。で、その砂金の話だけど・・・」ビールを飲みながらヘイズが聞く。
「あせらないの。仕事の内容詳しく言ったら、やる気なくすかもよ」
「なくすかもね」あっさりと答えるヘイズ。
「なによ、その態度は! せっかく儲けさせるってのに」
怒ったキャロラインの言葉に、
「ああ、何もそんなつもりじゃぁ・・・」ヘイズはあわてて訂正する。
「もういい、もういい。今日日はまともすぎるヤツばっかりでさ。肝っ玉の据わった男らしい男なんていやしないや。自分の影におびえてさ、腰抜かしてんだから、世話無いよ」「腰抜かすようなことなの?」カーリーが尋ねる。
「あぁん、あんた、インディアンよ。あたしらね、夫婦でここへきたのが20年前だったよ。この辺ももっと田舎でさ。亭主はバーニーって名で。もう天に召されちゃったがね。とにかくあの頃はさ、みんな助け合ったもんだよ。信じあってさ。ところがどう?今じゃもう」
「ほんと、わかるな」妙に納得するカーリー。
「わかるんならもうちょい打ち解けてちょうだいよ」
「いいだろう。でぇ、金ってどこにあるんだ、キャロライン?」話の先を聞こうとヘイズが促す。
「その20年前はね、この裏の山で金が出てゴールドラッシュだよ。でもそれも一時。やがて掘り尽くしちゃった。さて、あたしと主人はね、2年前に行ってみたんだよ。もう掘ってるものはいやしない。そこをかっさらって砂金で6千ドルがとこ集めたわけよ。もっとも場所は12箇所になったけど。集めては埋める、埋めては次へ移ったわけよ。」
「それで?」興味津々のヘイズ。
「インディアンよ!しゃくだねぇ。チリカワ族が5・60人、居留地から脱走してさ、山に立てこもっちゃったんだわさ。生意気にもう、あたしらを撃ちゃがんの。バンバン撃ってくるの」
「そのときだんなが・・・」察したカーリーが言う。
「やられちまったよ、バーニーは。チリカワのやつにさ」がらにもなく少ししょげるキャロライン。
「で、砂金のほうは?」神妙な顔をしながらも、一番の目的が気になるヘイズである。
「冷たいねえ。亭主が死んだ話をしてほろっとなってるのに、横から金は、金はって」
天を見上げるおばさん。
「金はどうなった?」バツ悪そうに、しかししつこく尋ねるヘイズ。
「いまだに埋めたまんまなのよ。どう?」
「どうって〜、何が?」よく飲み込めずにヘイズが言った。
「やるかやらないかよ。山へ行ってもらいたいのよ。あそこ行って、あたし達が埋めた砂金を掘り出して、持って帰ってもらいたいの。そしたら・・・そうね。20%、あげちゃうわ」
「20%!?」呆れ顔のヘイズ。
「インディアン、何人いるって言った?」納得いかない顔のカーリーが言う。
「そうね、噂じゃ5・60人かな。なぁに、腹を空かせたひょろひょろインディアンよ」
「フッフッ」お話にならない、という感じでカーリーが笑う。
「でもだんなを殺したんだろ?それがいる山へ20%で行けっての?」ヘイズは明らかに不服そうである。
「だってあたしらは2年がかりよ。あんた達なら2日ですんじまうじゃないのよ」
「それはそっちだけの言い分だよ」
「3人で3等分だね」当然、といった顔でカーリーが言った。
「3等分!?」キャロラインの言葉に顔を見合わせる二人。ヘイズはキャロラインを説き伏せようと、
「そう、それが当然だと思うよ」
(この時、2台目の馬車が若い女性を運んでやってきた)
「誰がそんなこと! 死んでもやだよ。なんだよこの恥知らずやろうが!
か弱い女の足元を見てつけこみやがってからに! けっ、っもう!」
おばさんはものすごい剣幕でまくし立て、去って行く。
「ヘイズよ」
「うん?」
「か弱いんだってさ」
「あのタンカで?」
「ふふふ・・・」
二人は仲良く、乾杯。
馬車から女性が降りてくる。馬車の御者は乱暴に女性の荷物を馬車から放り投げて、馬車を走らせて行ってしまった。それを見ていたカーリーが女性に声をかけた。
「荷物、持ちましょうか?」
「すいません」
「人手が無くてね。愛想が無い町なんです」荷物を運びながら女性に言った。
ホテルの中に入ると、女性はカーリーにチップを渡そうとした。
「あはは、いいんですよ。ボーイじゃないから」そう言ってカーボーイハットを脱ぎ、軽く会釈をした。
「すいません」
女性はスマザーズの姿を見つけ、近づいていった。それに気付いたスマザーズは、
「おお、これはこれは、いらっしゃいませ」
「部屋が欲しいんですけど・・・」
「どうぞどうぞ、よりどりみどりです。へへへ」宿帳を差し出すスマザーズ。
「ただ、困ったことに・・・あたしあの・・・お金を持ってないんです」
「それはゆゆしき大問題ですな」
「ここまで来るのに駅馬車の切符代に有り金はたいてしまったんです」
「顔に似合わぬ無鉄砲なお方ですな」
「今度の日曜まで待っていただけません? そしたら払えますから。あたし、巡回説教師なんです。伝道師です。お説教しますから、寄付も集まると思うんです」
シスターと思しきその女性は一生懸命話している。しかしスマザーズはあまり聞いていなさそうである。
「あのね、お嬢さん。このアパッチスプリングも昔は金がでて、そりゃあ人もわんさか集まってきましたよ。だけど今じゃあなた、人口はわずかの60人。しかもそのうち30人は近くにちらばってる牧場のカーボーイという状態だ。日曜日は全員二日酔い。あんたがどんなありがたいお説教をするか知らないが、耳を貸すやつなんていやしないよ。寄付なんか当てにするだけ損ってもんだ」スマザーズはシスターにそう言うが、シスターの方はかたくなである。
「あたしは神を信じてます」
「あっそう・・・あ〜、名前を伺っておきましょうか?」
「シスター・グレースと申します」シスターはにっこり笑って答える。
「どうだろうね、予定外の客があって人手不足なんだが・・・コックをやってくれたら部屋を提供するがね。もちろん食事も」
この申し出にきょとんとして、シスターが尋ねた。
「給料はいただけないんですか? 部屋と食事だけですか?」
スマザーズは少し後ろめたそうに顔をそむけて答えた。
「いやいや、そんなひどいことは言わないよ。一週間に8ドルで」
「部屋代は普通おいくら?」
「週4ドルだね」
「食費は?」
「週に4ドル」
「引き受けます」
商談成立である。少し納得がいってなさそうではあるが・・・
部屋で泡風呂に入り、リラックスしているヘイズ。そこへドアのノックが聞こえ、ヘイズは驚いてガンを取り、ドアに向けた。そこへ入ってきたのはあのおばさん、キャロラインだった。ヘイズは慌ててガンを別の方向に向け、自分は泡の中に沈んだ。
「負けたよ、ぼうや。フィフティ・フィフティの山分けでどうだい?」
おばさんの提案にヘイズはのった。
「よっしゃ。この格好なんで、握手はかんべんな」
「ああ、いいっていいって。女が見て平気は裸はとイエス・キリストだけだ。うまいだろバーニー? ははは」
「ははは、はははは・・・」
笑いながら、ぶくぶくと泡の中に沈んでいきそうなヘイズであった・・・
食堂でヘイズ、カーリー、そしてキャロラインの三人がテーブルを囲んでいる。
「うぶっぽい顔してるくせに、どうして食えない兄さんだよ」「へへへ」肉を切りながら笑うヘイズ。「でも引き受けた限りはバッチリやるよ。ま、まかしといてもらいましょう。さ、食って食って食って」カーリーは育ちが良くないらしく、フォークをキャロラインに向けて話している。そこへ先ほどの夫妻がやってきた。それを見つけたキャロラインが二人を誘う。
「あ、いらっしゃいよこっちへ。食事はみんなでわいわいやった方がうまいよ」
「いやぁ、こりゃどうも」
ヘイズとカーリーは立ち上がって、ヘイズは握手を求めた。
「初めまして。ジョシュア・スミスと言います」
「わたくし、フィールディング。これ、家内のルーシー」
「よろしく。こちらはキャロライン・ラングレーさん。」
「よろしく」
「サディアス・ジョーンズです」カーリーも握手を求める。
「スミスとジョーンズ? ますます食えないわね」怪訝そうな顔をするキャロライン。
「またなんだってこんな辺鄙なとこにいらしたんです?」話題を変えるカーリー。
「わたし、インディアン管理局から派遣されましてね」
「インディアンをどうするっていうんです? チリカワ族ってのは、結構血に飢えてますよ」おばさんは興味津々に尋ねた。
「さぁて、どうしたもんですかね。まずは会って話してみますか」
その言葉にヘイズの肉を切る手が止まった。
「軍隊を連れて行くんですか?」キャロラインも驚いてそう聞いた。
「主人にそんなものいりませんわ。たとえ相手がインディアンでも話せば分かるという主義ですから、軍隊なんて」
バカにしたような感じで答えるのは妻のルーシー。その雰囲気を察してヘイズが続けて言った。
「なるほど、そうですか。で、やつら何で居留地を飛び出したんです?」
「実は管理官の一人が彼らに渡す肉を横流ししまして・・・そいつは転勤させたんですがまだあるんですよ。土地の状態が約束とはだいぶ違うんですね。それで怒ったんです。
で、私が全権大使として、チリカワ族の気持ちを和らげようと、そういう訳なんです」
「荒れてんですか、やつら?」インディアンの動向が気になるカーリーが尋ねた。
「報告によると相当後悔しているようですが・・・何か気にかかる理由でも?」
「うん、山へ行くんでね。インディアンのいる方へは行かないけど」ヘイズが答えた。
「しかしそううまくは・・・」
「うまくやりたいってことです」カーリーがヘイズの顔を見ながら言った。
「ははは」こんな会話を楽しんでいるかのようにフィールディングは笑った。
「どうなの、キャロライン? インディアン部落のど真ん中へ行けっての?」
カーリーは非難するような目でおばさんを見ている。
「大丈夫よ、あいつらがとぐろ巻いてんのは、東だもん。あたしたち西の方でもやっといたからさ、そっちからかかってよ」
「残ったものは何すればいいんでしょう?」相変わらず不機嫌そうにルーシーが尋ねる。「何がやりたいんです」少し機嫌を取るようにヘイズが言うと、
「それがとんとわからなくて・・・西部旅行は初めてだし。実は早くも帰りたくなってますの」投げやりに答えるルーシー。
「土曜日の晩になれば少しは景気良くなりますよ」カーリーはルーシーをなだめるようにそう言った。
「おや、何かありますの?」
「あ?ああ、その辺のカーボーイが集まってきましてね。飲む、打つ、喧嘩で絢爛たるお遊び絵巻を繰り広げるんですよ」楽しそうに説明するヘイズ。
「それは景気もでるだろうよ」
フィールディングは嬉しそうに笑っている。しかし、ルーシーは相変わらず無愛想な顔をしていた。
地図を入れた鍵つきの頑丈な黒い箱が金庫の中にある。スマザーズはその金庫を開け、その箱を取り出し、キャロラインに渡した。
「んん〜」咳払いをするスマザーズ。キャロラインは嬉しそうな顔をして受け取り、鍵を開ける。
「はさみ取って」
「あぁん」
おばさんは新聞紙大の比較的大きな地図を取り出し、1/6ほどを切り取った。そしてまた大事そうにしまい込んで、鍵をかけた。
(続きと感想は、コメントへ)
|
|
|
|
|
|
|
|
西部二人組普及促進委員会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-