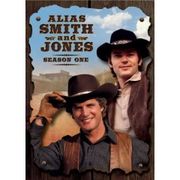http://
http://
放送日 1972/10/28
監督 Jeffrey Hayden
原案 Dick Nelson
脚色 Robert Guy Barrows
ゲスト Joan Hackett:アリス・バニオン [ Alice Banion ] 山東昭子
J.D. Cannon :ハリー・ブリスコー[ Harry Briscoe ] 南原宏治
Guy Raymond :保安官 [ Sheriff Carver ] 加藤精三
Billy "Green" Bush:チャーリー [ Charlie O'Rourke ] 中野誠也
Erik Holland :シュミット[ Kurt Schmitt ] 森川公也
Hank Underwood:ヴィク [ Vic ] 溝井哲夫
Gary Van Orman:クライド[ Clyde ] 仲木隆司
牧師 松岡文雄
馬に乗って町中を進むヘイズとカーリー。監獄の建物前に差しかかったときである。
「おい!キッド!」
突然どこからともなくふってわいた声に驚いて馬を止める二人。素早く辺りを見回す。
「よお!こっちこっち!」
声の主は鉄格子のはまった窓の中。金網に手を掛けて嬉しそうに二人を見ていた。
「なん・・・」相手に気づいたヘイズ。
「まーたでけえ声で」押し殺した声のカーリー。
「お懐かしいお二人さん!」
「よーお、チャーリー!」
相手に手を上げ、威勢よくこたえたヘイズ。笑い声を上げながら慌てて馬から降りる。
カーリーも急いで馬をつなぐ。牢の中の男ははしゃぐように言った。
「しばらくだったな!どうしてた、変わりなかったかよ!」
陽気な笑い声を立てながら小走りに窓に近づいてきた二人に、チャーリーは懐かしそうに言った。
「こんなところで昔なじみに会えるとはなあ」
「まままま、チャーリー、チャーリー」
辺りに気を配りながらカーリーが言った。
「お静かに」
「あ?」
「声が高いよ」
「あ、いけねいけね。まだ追われ追われの身だったな」
大きくうなずくカーリー。ヘイズが小声で言った。
「なんとか逃げ切りてえんだ」
「わりいわりい。あんまり懐かしいもんでよ。思わずわあわあ言っちゃった。ごめんなさいよ」
「まあ、いいっていいって」
カーリーが言った。
「なんで入ってんだ、このたびは」
「あれ?ご存じねえの」
「何をよ」
「おれのことさ」
「知らね」
ヘイズがこたえると、
「今、町中の評判男なんだぜ、おれあ。おれのせいでホテルも満員だ。おめえさんがたもそれで来たんじゃなかったのか?」
「じゃなんだ、おまえが人寄せしてるってのか?」
おもしろそうに訪ねるカーリー。
「そ。おれのせいなんだよ。これが受けたね。見てもらいたかったよ、おめえさんらにも。だけど一番いい出し物は見られるよな」
「なんのことだ」
「おれの死刑だ。明日吊されるんだよ」
ヘイズとカーリーは無言のまま顔を見合わせた。
「面会だぞ、チャーリー」
看守が牢屋の鍵を開けてヘイズとカーリーを連れてきながら言った。
「しかしこいつの友達だなんて名乗るやつがいるとは思わなかったな」
「どうしてよ。別れの挨拶がおかしいかい?」
ヘイズが言うと、
「いや。しかしどっちにしても“良きサマリヤ人”とは思えんからなあ。やっぱりあんたらもうまくいきゃあ一攫千金狙ってるんだろ。え?図星だろうが」
憮然とした顔で男を見送ったヘイズとカーリーは、次いでにこやかに牢の前に立った。
鉄格子の中から伸びた腕がヘイズとカーリーの肩に回される。カーリーもつかみ返して笑顔で言った。
「チャーリー」
「なんだいありゃ」
ヘイズが訊ねる。カーリーも真顔になって、
「一攫千金とかさあ。なんのこと?」
「よせやい。おれのほんとヤマのこと知らねえのかよ」
「ヤマ?」
「10万ドルの金の延べ棒。やっつけたんだよ」
ヘイズがうつむき加減に笑ってカーリーを見た。鉄格子に腕を掛けたカーリーは首を振って、
「そら知らないよ。今来たばかりだもの。聞いてないねえ。10万だって?金の延べ棒でかい!」
「おれは聞きたくねえな」
明るい顔でヘイズが言うと、
「また心にもないこと言って」
カーリーがまぜ返す。一瞬あいだを置いてからヘイズは言った。
「ああ、いいよ、聞くよ。金がなんだって?」
「砂漠に埋めてあるんだよ」
楊子代わりにマッチをくわえていたチャーリーが言った。
「捕まる前に埋めたんだ。その秘密を抱いたまま死ぬかと思うとおれあもう心残りでよ。だけどおめえたちが来たから──」
「だめ」
すばやくヘイズがこたえた。
「やっぱり聞くのやめ」
ヘイズの横顔を見ていたカーリーが言った。
「なんで」
「だって盗品だろ?」
カーリーのほうを向いてヘイズは言った。
「たとえおれたちがやったんじゃなくったって、そいつを掘り出しゃ共犯てことにもなる」
するとチャーリーが意外そうに、
「共犯がなんだよ。大金持ちになれるってのに何が気に入らねえんだよ」
「知事が堅気を通せば恩赦をやるって約束してくれてんだ。だからまずいんだよ」
「じゃなにかおれあ」
口から取ったマッチを格子でバチッと擦ったチャーリーは火をじっと見つめながら、
「みすみす10万ドルの金塊を砂漠の肥やしにしたままこの世におさらばするのか」
すぐにはこたえられなかったヘイズは考え込むように言った。
「役人に打ち明けたら?刑の執行延期ってことも」
火を吹き消してチャーリーは首を横に振った。
「今度の仕事じゃほかに二人いたんだけど、こいつらがまたやけに荒え野郎でな。追っ手と撃ち合って、結局死んだけど・・・やあもう派手なドンパチを繰り広げたんだ」
「てことはなんだい」
カーリーが言った。
「追っ手を何人か殺したのか」
「そういうこと」
二人を見つめてうなずいたチャーリーは三本指を立てて見せながらこたえた。
「だから無理なんだよ。たとえ半分の5万ドル出したって延期なんてとてもじゃねえや」
マッチの燃えかすで手のひらを汚していたチャーリーは、
「まあいいや。寝かせの黄金てのもおつなもんだ。贅沢な死に方と思って諦めら」
じっとチャーリーを見つめていたヘイズは申し訳なさそうに頭を振って言った。
「ああ・・・悪いな。どうしても恩赦は逃がしたくねえんでな」
「ほかの頼みなら、聞いてくれるか?いまわの願いってやつをよ」
「そらもう。なんだい」
カーリーが応じた。消し炭で手のひらを汚し続けていたチャーリーは顔を上げて二人を見た。静かな口調で言った。
「おれが吊されるのを見届けてくれ」
保安官事務所を出るなりヘイズが言った。
「今あり金いくらだ」
「二人で15ドル。金の延べ棒が欲しかったかい?」
「いやあ、一杯やりてえんだよ。気が滅入った。あいつが呼び止めなきゃよかったんだ」 「チャーリーでよかったよ。あれが保安官だってみろ」
二人はまっすぐ早足でサルーンへ向かって歩いていた。すると目前のスィングドアがパッと開いた。黒い帽子に紺の三揃えといった中年男が現れた。
「よおっ!」
出てきた男を見るなりヘイズとカーリーはくるっと回れ右して二、三歩引き返し、立ち止まった。低い声でカーリーが言った。
「あの旦那」
「そ!はりきりガードマンのブリスコーさんだ」
作り笑いを浮かべてから振り向いた二人は笑い声をあげながらブリスコーに近づいた。
「やあやあやあ!」
「やあ、ブリスコーさん」
「やあ、奇遇だなあ!」
威勢のいい声をあげながらブリスコーは二人と交互に握手を交わした。
「吊し首を見に来たのか」
「いやいや、そうじゃないんです」
カーリーがこたえた。
「通りすがりなんですよ」
「おお、そうかい。しかしあのときは世話になったなあ、ブリムストンの列車強盗事件では!ハハハ、おかげでわしはえらく男をあげたぞ、ほんっと。ちょうどいい!あのときの礼といってもたいしたことはできんが、あとで酒でもおごらせてくれよ」
「じゃあ、ごちそうになりましょう」
ヘイズが言った。
「今夜泊まりますから」
「そおか、よろしい。どこで会う」
「じゃ、サルーンで」
「わかった、ジョーンズ」
「おれスミス。ジョーンズこれ」
「わかってる。確認したまでだ」
二人をじっと見つめたブリスコーは、
「ではあとで」
そう言い置いて立ち去った。バイバイと手を振って見せるカーリー。二人はしばらくブリスコーの背中を見送っていたが、ブリスコーは保安官事務所へ向かって歩いていった。 「ヘイズさんよ」
カーリーが言った。
「ちょっとヤバいんじゃないの?その筋の関係者と飲むなんてのはさ」
「ほんと。おそらく酒もまずくなりますよ」
そのままサルーンへ向かって歩き出した二人はドアの前でふと立ち止まり、後ろを振り返った。見るとブリスコーが保安官とこっちを見ながら立ち話をしている。
「あれおれたちのこと言ってるんじゃない?」
カーリーの言葉にヘイズも表情を曇らせて、
「どーもよろしくない雰囲気だ。下手すりゃ二十年食らうかもよ」
顔を見合わせ、二人はそのまま店の中へ入った。
店は活気に満ちていた。陽気な音楽と話し声が響く中、客のあいだを縫ってカウンターへ近づくヘイズとカーリー。
その二人をじっと見ていた女がいた。豊かな黒髪を結い上げ、ラベンダー色のドレスを着ている。若くはないがなかなか艶っぽい。ワイングラスをかかげたまま、ヘイズとカーリーの動きを目で追っていた。
「ウィスキーを頼みます。二杯」
バーテンダーに向かって金を出しながらヘイズが言った。すると相手は酒をグラスに注ぎながら、
「銭はポッポに入れときな。何でもじゃんじゃんやってくれ。店のおごりだ」
「・・・ていうと、タダ?」
「あんたがたチャーリーの友達だろ?」
バーテンダーの言葉にカーリーがやりきれないといった声でグラスを口に運びながら、
「噂は早いなあ」
「ほんと」
「チャーリーの友達ってことはわしの友達だ。重ねていく?」
「ああ、そりゃもう」
ヘイズが応じてグラスを差し出した。
「いただきます」
「おおっと、待った」
背後から現れたのはブリスコー。ヘイズとカーリーのあいだに入って鷹揚に言った。
「この二人にはわしのを注いでやれ。ここではなんだ、あっちのテーブルへ行こう」 二人を交互に見てブリスコーは続けた。
「思ったより話がありそうなんでな。きみたちのことで保安官からひじょーに興味あることを聞いた」
言い置いてブリスコーはテーブルへ向かった。顔を見合わせ、ブリスコーがいなくなってからサッとカーリーの横に並び立ち、カーリーとともにテーブルのほうを見つめるヘイズ。二人はしばし言葉もなかったが、やがてヘイズが先に歩き出し、カーリーもあとに続こうとした。
そのとき、カーリーの後ろに女がぶつかってきた。黒髪、ラベンダー色のドレスの女だ。
「ああ、すみません。あたしうっかりしてて」
振り向いたカーリーは軽く帽子をあげて見せ、
「いや、うっかりしたのはこっち。失礼」
二人はしばし視線を交わし、カーリーはそのままヘイズとブリスコーの待つテーブルに着いた。
「ああ、掛けて掛けて」
自分のショットグラスを眺めながらブリスコーが言った。
「これはケンタッキーコーン。そこらのウィスキーとはちょっと違うぞ」
ヘイズとカーリーは黙ってグラスをかかげ、口をつけた。
酒を味わい、葉巻を手に椅子の背にもたれたブリスコーが言った。
「さて何の話だっけ」
「話はそっちがあるんじゃないすか?」
カーリーがこたえるとブリスコーは煙をひと吹き、
「おお、そうだったな。おもしろいことを聞いたよ。保安官の話じゃあ、きみたちはなんでも、チャーリーに面会したそうだな。話し込んでた」
黙って顔を見合わせたヘイズとカーリーはあらためてブリスコーの顔を見た。先にカーリーが口を開いた。
「いやなに」
「挨拶に寄っただけ」
「そしてさよなら」
葉巻を見つめていたブリスコーの目が光った。
「強盗殺人犯に挨拶か。てことは、あいつと知り合いだって・・・ことだな?」
カーリーはちらっとヘイズを見た。ヘイズも無言で視線に応じる。
「隠すな隠すな」
ブリスコーが言った。
「ほんとは通りすがりじゃないんだろ?チャーリーに呼ばれて来たんだろう」
ばかばかしいといった口調でヘイズが言った。
「名うての無法者がなんだっておれたちを呼ぶんです?」
「さ、それだよ。それが不思議だ。とは言うものの、アタリはついてる。前にきみたち言ってたな。例のお尋ね者、ハンニバル・ヘイズとキッド・カーリーとは面識もあればつきあいもある。恩人だみたいなことを言ってた」
「そう」
ヘイズがこたえた。
「それは事実です」
カーリーもうなずいて、
「あの二人には世話になった。おかげで今もこうやって、身を持ち崩さずにやってるわけだ」
「じゃあ悪党とのつきあいはそのときだけだったと言うのか」
手に取ったグラスをためつすがめつしながら、おもしろそうにブリスコーが言った。
「なんかだんだん酒の味が変わってきたな」
投げやるようにヘイズが言った。
「なんです?何が言いたいんです?」
「よし、訊こう。なんでチャーリーを知ってるんだ。やつは〈地獄の穴一味〉だ」
「知り合いは多いよ。いいのもいりゃ悪いのもいる。でも友達は友達さ」
「我々も友達だ。だが仕事に友情は挟まんぞ。いざとなればこれで私も結構冷酷になれるんだ」
ヘイズは思わず目で宙を仰ぎ、じっとブリスコーを見つめていたカーリーが言った。
「いざって?」
ブリスコーはやおらテーブルに身を乗り出した。
「私はチャーリーがどこに金(きん)を隠したか知りたい。町を出る前に教えていってくれ。それだけだ。無事に町を出たかったら教えることだ」
「なんか脅迫じみて聞こえるけど」
「いやいや。警告だ。町の者も鵜の目鷹の目だ。金を捜しに出かけたら後ろに行列が着くと思え。町を出る前に殺されるかもしれん。隠し場所を言えってんで袋叩きだ」
ブリスコーを見つめていたヘイズは冷めた顔で持っていたグラスを放し、頬杖をついた。ブリスコーはうまそうに酒を飲んだ。
「考えとけ。金は逃げん。じっくりやるさ」
しっかと栓をしたボトルを手に、ブリスコーは席を立ったいった。
「けっ」
グラスに口をつけてカーリーが言った。
「町に腰落ち着けるゼニもないのに出て行くことも叶わずか」
「出て行きたきゃ10万ドル寄越せときた。まあなんにしてもここにいりゃ酒は飲みほうだいだ。悪くない待遇だぜ」
そのとき、テーブルの上に赤いリボンで結ばれた巻紙が落ちてきた。思わず上を見上げたヘイズとカーリー。音楽と口笛に合わせ、鳥籠のような入れ物に入った女がけばけばしい赤いドレスの下から黒い編みタイツの足をぶらぶらさせながらゆっくりと降りてきた。カーリーがリボンをはずしにかかった。
「なんだ」
上を見上げたままヘイズが言った。カーリーはすまして、
「何が」
「おまえが拾ったものよ!」
「手紙」
「それはわかってるよ。なんと書いてある」
手紙に目を通していたカーリーは弾んだ声で、
「“会いに来てちょうだい。部屋へ。アリス”」
目を丸くしてヘイズが言った。
「誰が」
「あの子」
カーリーはにっこりして籠を指さした。籠とカーリーとを見比べていたヘイズは早口に、
「じゃねえかと思ったけど、どっちだ。どっちに来いって?」
手紙を見ていたカーリーはおやという顔でヘイズを見ると、
「おれの近くに落ちてきたんだぜ?」
ヘイズはまじまじとカーリーの顔を見返し、
「いやあ、おれのほうに寄ってたよ」
二人は籠のほうに気を取られながらも期待に満ちた視線と笑顔を交わしていた。
「いやあ、しかし」
女の部屋でやや緊張しながら紅茶をごちそうになっているヘイズとカーリー。衝立の向こうでアリスは着替えの最中だった。
「どちらさまへのご招待かはっきりしないんだけど」
そう言ってヘイズは紅茶をすすった。すると衝立の陰からアリスが顔を出して、
「そりゃご両人ともよ。一人じゃ一人がひがむでしょ?」
「ああ、なるほど。そこまで考えてくれたワケ」
ヘイズがこたえ、カーリーはやれやれといった顔でカップを受け皿に置いた。
「お茶好きだったかしら。この草深い町じゃ文明の香りのするものといったらお茶ぐらいですもんね」
アリスの声にカーリーは衝立のほうを振り返った。
「嫌いなの、このブラウンタウンが?」
「だーい嫌い。あたしはサンフランシスコを目指してきたのよ。ところが不運にもここで沈没しちゃってさ」
苦笑した顔をヘイズと見合わせたカーリーは、
「もうどのくらい?」
「そう。一年半ね。いずれは行くつもりよ、サンフランシスコ。資金をこしらえてね。自分のお店を開くのよ」
胸のボタンをかけながらアリスが衝立の中から現れ、ヘイズとカーリーはカップを受け皿に乗せたままの姿ですばやく立ち上がった。フリルのついた薄桃色の部屋着はアリスをいっそうあだっぽく見せていた。
「自分のサルーン?」
ヘイズが言うと、
「まあ、そんなところでしょうね。あたしとしては、あんな格好でほんとは歌いたくないんだけど・・・掛けて」
ヘイズとカーリーは並んで腰掛け、アリスは二人の前に腰を下ろした。
「きみならどんな格好だって」
にこやかにカーリーが言った。
「そのオーバーを着てポーカーテーブルの上に突っ立ってもうけちゃうよ。なんたってあの歌いっぷりだもんねえ」
「泣かせること言ってくれるのねえ。優しいんだわ、ほんと。だから呼んだのよ。そういう人だから来てもらったの」
カップを置いてヘイズが言った。
「・・・というと」
「実はね。お二人に、かんでほしいの。あたしのビジネスに」
ヘイズのほうに顔を向けてからカーリーが言った。
「というと?」
「提携よ」
「はー・・・提携ね」
妙な雲行きになってきたといった顔で、ヘイズがこたえた。勢い込んでアリスが言った。
「三人で組んでサンフランシスコに店を出すのよ。あたしの歌ならいけるでしょ?」
「おれたちはカネ?」
すかさずヘイズが返す。アリスはノンシャランと、
「ええ、まあそういうことね。キャッシュがあれば助かるわ」
ヘイズと顔を見合わせたカーリーが疲れたような声で言った。
「これもチャーリーの金(きん)の隠し場所を言えってナゾらしいよ。いやんなっちゃうなあ」
「胸くそ悪くなってきたよ」
カップを置いてヘイズは言った。
「行こう」
二人はすばやく立ち上がって部屋を出た。二人を引き留めるでもなく、アリスは黙って自分の紅茶を飲んだ。
牢の鍵が開けられた。
「さあ、どうぞ」
食事をしようとしていたチャーリーが振り返るとギターを持ったアリスが入ってきた。彼女が牢番に訊いた。
「面会時間は?」
「そうさなあ。まあ四時間までだろうな」
牢が開かれ、アリスは中に入った。チャーリーは嬉しそうな、はにかむような表情で入ってきた女を見上げた。牢番が言った。
「だけどそんなにいるつもりかね」
「いるつもりよ。チャーリーさんさえよかったら」
「いいも悪いもねえよ」
チャーリーがこたえ、アリスは微笑んでギターを抱えるとチャーリーの横に座った。チャーリーが彼女に言った。
「でもなんだって」
「いえね。歌の二つ三つも歌ってお話相手をしたら少しはあなたの・・・気も晴れるかと」
「じゃ『カウボーイの嘆き』。あれを頼む」
アリスはうなずいてギターをつま弾き、甘く優しい声で歌い出した。
歌を聞いていたチャーリーの瞳がみるみる潤み、胸の思いをかき乱されてか熱いため息をもらした。目を赤くさせ、彼は最後の食事を始めた。歌を聞きながら静かにハムを口に運ぶ彼の様子は従順な少年のようだった。
(続きと感想は、コメントへ)
http://
放送日 1972/10/28
監督 Jeffrey Hayden
原案 Dick Nelson
脚色 Robert Guy Barrows
ゲスト Joan Hackett:アリス・バニオン [ Alice Banion ] 山東昭子
J.D. Cannon :ハリー・ブリスコー[ Harry Briscoe ] 南原宏治
Guy Raymond :保安官 [ Sheriff Carver ] 加藤精三
Billy "Green" Bush:チャーリー [ Charlie O'Rourke ] 中野誠也
Erik Holland :シュミット[ Kurt Schmitt ] 森川公也
Hank Underwood:ヴィク [ Vic ] 溝井哲夫
Gary Van Orman:クライド[ Clyde ] 仲木隆司
牧師 松岡文雄
馬に乗って町中を進むヘイズとカーリー。監獄の建物前に差しかかったときである。
「おい!キッド!」
突然どこからともなくふってわいた声に驚いて馬を止める二人。素早く辺りを見回す。
「よお!こっちこっち!」
声の主は鉄格子のはまった窓の中。金網に手を掛けて嬉しそうに二人を見ていた。
「なん・・・」相手に気づいたヘイズ。
「まーたでけえ声で」押し殺した声のカーリー。
「お懐かしいお二人さん!」
「よーお、チャーリー!」
相手に手を上げ、威勢よくこたえたヘイズ。笑い声を上げながら慌てて馬から降りる。
カーリーも急いで馬をつなぐ。牢の中の男ははしゃぐように言った。
「しばらくだったな!どうしてた、変わりなかったかよ!」
陽気な笑い声を立てながら小走りに窓に近づいてきた二人に、チャーリーは懐かしそうに言った。
「こんなところで昔なじみに会えるとはなあ」
「まままま、チャーリー、チャーリー」
辺りに気を配りながらカーリーが言った。
「お静かに」
「あ?」
「声が高いよ」
「あ、いけねいけね。まだ追われ追われの身だったな」
大きくうなずくカーリー。ヘイズが小声で言った。
「なんとか逃げ切りてえんだ」
「わりいわりい。あんまり懐かしいもんでよ。思わずわあわあ言っちゃった。ごめんなさいよ」
「まあ、いいっていいって」
カーリーが言った。
「なんで入ってんだ、このたびは」
「あれ?ご存じねえの」
「何をよ」
「おれのことさ」
「知らね」
ヘイズがこたえると、
「今、町中の評判男なんだぜ、おれあ。おれのせいでホテルも満員だ。おめえさんがたもそれで来たんじゃなかったのか?」
「じゃなんだ、おまえが人寄せしてるってのか?」
おもしろそうに訪ねるカーリー。
「そ。おれのせいなんだよ。これが受けたね。見てもらいたかったよ、おめえさんらにも。だけど一番いい出し物は見られるよな」
「なんのことだ」
「おれの死刑だ。明日吊されるんだよ」
ヘイズとカーリーは無言のまま顔を見合わせた。
「面会だぞ、チャーリー」
看守が牢屋の鍵を開けてヘイズとカーリーを連れてきながら言った。
「しかしこいつの友達だなんて名乗るやつがいるとは思わなかったな」
「どうしてよ。別れの挨拶がおかしいかい?」
ヘイズが言うと、
「いや。しかしどっちにしても“良きサマリヤ人”とは思えんからなあ。やっぱりあんたらもうまくいきゃあ一攫千金狙ってるんだろ。え?図星だろうが」
憮然とした顔で男を見送ったヘイズとカーリーは、次いでにこやかに牢の前に立った。
鉄格子の中から伸びた腕がヘイズとカーリーの肩に回される。カーリーもつかみ返して笑顔で言った。
「チャーリー」
「なんだいありゃ」
ヘイズが訊ねる。カーリーも真顔になって、
「一攫千金とかさあ。なんのこと?」
「よせやい。おれのほんとヤマのこと知らねえのかよ」
「ヤマ?」
「10万ドルの金の延べ棒。やっつけたんだよ」
ヘイズがうつむき加減に笑ってカーリーを見た。鉄格子に腕を掛けたカーリーは首を振って、
「そら知らないよ。今来たばかりだもの。聞いてないねえ。10万だって?金の延べ棒でかい!」
「おれは聞きたくねえな」
明るい顔でヘイズが言うと、
「また心にもないこと言って」
カーリーがまぜ返す。一瞬あいだを置いてからヘイズは言った。
「ああ、いいよ、聞くよ。金がなんだって?」
「砂漠に埋めてあるんだよ」
楊子代わりにマッチをくわえていたチャーリーが言った。
「捕まる前に埋めたんだ。その秘密を抱いたまま死ぬかと思うとおれあもう心残りでよ。だけどおめえたちが来たから──」
「だめ」
すばやくヘイズがこたえた。
「やっぱり聞くのやめ」
ヘイズの横顔を見ていたカーリーが言った。
「なんで」
「だって盗品だろ?」
カーリーのほうを向いてヘイズは言った。
「たとえおれたちがやったんじゃなくったって、そいつを掘り出しゃ共犯てことにもなる」
するとチャーリーが意外そうに、
「共犯がなんだよ。大金持ちになれるってのに何が気に入らねえんだよ」
「知事が堅気を通せば恩赦をやるって約束してくれてんだ。だからまずいんだよ」
「じゃなにかおれあ」
口から取ったマッチを格子でバチッと擦ったチャーリーは火をじっと見つめながら、
「みすみす10万ドルの金塊を砂漠の肥やしにしたままこの世におさらばするのか」
すぐにはこたえられなかったヘイズは考え込むように言った。
「役人に打ち明けたら?刑の執行延期ってことも」
火を吹き消してチャーリーは首を横に振った。
「今度の仕事じゃほかに二人いたんだけど、こいつらがまたやけに荒え野郎でな。追っ手と撃ち合って、結局死んだけど・・・やあもう派手なドンパチを繰り広げたんだ」
「てことはなんだい」
カーリーが言った。
「追っ手を何人か殺したのか」
「そういうこと」
二人を見つめてうなずいたチャーリーは三本指を立てて見せながらこたえた。
「だから無理なんだよ。たとえ半分の5万ドル出したって延期なんてとてもじゃねえや」
マッチの燃えかすで手のひらを汚していたチャーリーは、
「まあいいや。寝かせの黄金てのもおつなもんだ。贅沢な死に方と思って諦めら」
じっとチャーリーを見つめていたヘイズは申し訳なさそうに頭を振って言った。
「ああ・・・悪いな。どうしても恩赦は逃がしたくねえんでな」
「ほかの頼みなら、聞いてくれるか?いまわの願いってやつをよ」
「そらもう。なんだい」
カーリーが応じた。消し炭で手のひらを汚し続けていたチャーリーは顔を上げて二人を見た。静かな口調で言った。
「おれが吊されるのを見届けてくれ」
保安官事務所を出るなりヘイズが言った。
「今あり金いくらだ」
「二人で15ドル。金の延べ棒が欲しかったかい?」
「いやあ、一杯やりてえんだよ。気が滅入った。あいつが呼び止めなきゃよかったんだ」 「チャーリーでよかったよ。あれが保安官だってみろ」
二人はまっすぐ早足でサルーンへ向かって歩いていた。すると目前のスィングドアがパッと開いた。黒い帽子に紺の三揃えといった中年男が現れた。
「よおっ!」
出てきた男を見るなりヘイズとカーリーはくるっと回れ右して二、三歩引き返し、立ち止まった。低い声でカーリーが言った。
「あの旦那」
「そ!はりきりガードマンのブリスコーさんだ」
作り笑いを浮かべてから振り向いた二人は笑い声をあげながらブリスコーに近づいた。
「やあやあやあ!」
「やあ、ブリスコーさん」
「やあ、奇遇だなあ!」
威勢のいい声をあげながらブリスコーは二人と交互に握手を交わした。
「吊し首を見に来たのか」
「いやいや、そうじゃないんです」
カーリーがこたえた。
「通りすがりなんですよ」
「おお、そうかい。しかしあのときは世話になったなあ、ブリムストンの列車強盗事件では!ハハハ、おかげでわしはえらく男をあげたぞ、ほんっと。ちょうどいい!あのときの礼といってもたいしたことはできんが、あとで酒でもおごらせてくれよ」
「じゃあ、ごちそうになりましょう」
ヘイズが言った。
「今夜泊まりますから」
「そおか、よろしい。どこで会う」
「じゃ、サルーンで」
「わかった、ジョーンズ」
「おれスミス。ジョーンズこれ」
「わかってる。確認したまでだ」
二人をじっと見つめたブリスコーは、
「ではあとで」
そう言い置いて立ち去った。バイバイと手を振って見せるカーリー。二人はしばらくブリスコーの背中を見送っていたが、ブリスコーは保安官事務所へ向かって歩いていった。 「ヘイズさんよ」
カーリーが言った。
「ちょっとヤバいんじゃないの?その筋の関係者と飲むなんてのはさ」
「ほんと。おそらく酒もまずくなりますよ」
そのままサルーンへ向かって歩き出した二人はドアの前でふと立ち止まり、後ろを振り返った。見るとブリスコーが保安官とこっちを見ながら立ち話をしている。
「あれおれたちのこと言ってるんじゃない?」
カーリーの言葉にヘイズも表情を曇らせて、
「どーもよろしくない雰囲気だ。下手すりゃ二十年食らうかもよ」
顔を見合わせ、二人はそのまま店の中へ入った。
店は活気に満ちていた。陽気な音楽と話し声が響く中、客のあいだを縫ってカウンターへ近づくヘイズとカーリー。
その二人をじっと見ていた女がいた。豊かな黒髪を結い上げ、ラベンダー色のドレスを着ている。若くはないがなかなか艶っぽい。ワイングラスをかかげたまま、ヘイズとカーリーの動きを目で追っていた。
「ウィスキーを頼みます。二杯」
バーテンダーに向かって金を出しながらヘイズが言った。すると相手は酒をグラスに注ぎながら、
「銭はポッポに入れときな。何でもじゃんじゃんやってくれ。店のおごりだ」
「・・・ていうと、タダ?」
「あんたがたチャーリーの友達だろ?」
バーテンダーの言葉にカーリーがやりきれないといった声でグラスを口に運びながら、
「噂は早いなあ」
「ほんと」
「チャーリーの友達ってことはわしの友達だ。重ねていく?」
「ああ、そりゃもう」
ヘイズが応じてグラスを差し出した。
「いただきます」
「おおっと、待った」
背後から現れたのはブリスコー。ヘイズとカーリーのあいだに入って鷹揚に言った。
「この二人にはわしのを注いでやれ。ここではなんだ、あっちのテーブルへ行こう」 二人を交互に見てブリスコーは続けた。
「思ったより話がありそうなんでな。きみたちのことで保安官からひじょーに興味あることを聞いた」
言い置いてブリスコーはテーブルへ向かった。顔を見合わせ、ブリスコーがいなくなってからサッとカーリーの横に並び立ち、カーリーとともにテーブルのほうを見つめるヘイズ。二人はしばし言葉もなかったが、やがてヘイズが先に歩き出し、カーリーもあとに続こうとした。
そのとき、カーリーの後ろに女がぶつかってきた。黒髪、ラベンダー色のドレスの女だ。
「ああ、すみません。あたしうっかりしてて」
振り向いたカーリーは軽く帽子をあげて見せ、
「いや、うっかりしたのはこっち。失礼」
二人はしばし視線を交わし、カーリーはそのままヘイズとブリスコーの待つテーブルに着いた。
「ああ、掛けて掛けて」
自分のショットグラスを眺めながらブリスコーが言った。
「これはケンタッキーコーン。そこらのウィスキーとはちょっと違うぞ」
ヘイズとカーリーは黙ってグラスをかかげ、口をつけた。
酒を味わい、葉巻を手に椅子の背にもたれたブリスコーが言った。
「さて何の話だっけ」
「話はそっちがあるんじゃないすか?」
カーリーがこたえるとブリスコーは煙をひと吹き、
「おお、そうだったな。おもしろいことを聞いたよ。保安官の話じゃあ、きみたちはなんでも、チャーリーに面会したそうだな。話し込んでた」
黙って顔を見合わせたヘイズとカーリーはあらためてブリスコーの顔を見た。先にカーリーが口を開いた。
「いやなに」
「挨拶に寄っただけ」
「そしてさよなら」
葉巻を見つめていたブリスコーの目が光った。
「強盗殺人犯に挨拶か。てことは、あいつと知り合いだって・・・ことだな?」
カーリーはちらっとヘイズを見た。ヘイズも無言で視線に応じる。
「隠すな隠すな」
ブリスコーが言った。
「ほんとは通りすがりじゃないんだろ?チャーリーに呼ばれて来たんだろう」
ばかばかしいといった口調でヘイズが言った。
「名うての無法者がなんだっておれたちを呼ぶんです?」
「さ、それだよ。それが不思議だ。とは言うものの、アタリはついてる。前にきみたち言ってたな。例のお尋ね者、ハンニバル・ヘイズとキッド・カーリーとは面識もあればつきあいもある。恩人だみたいなことを言ってた」
「そう」
ヘイズがこたえた。
「それは事実です」
カーリーもうなずいて、
「あの二人には世話になった。おかげで今もこうやって、身を持ち崩さずにやってるわけだ」
「じゃあ悪党とのつきあいはそのときだけだったと言うのか」
手に取ったグラスをためつすがめつしながら、おもしろそうにブリスコーが言った。
「なんかだんだん酒の味が変わってきたな」
投げやるようにヘイズが言った。
「なんです?何が言いたいんです?」
「よし、訊こう。なんでチャーリーを知ってるんだ。やつは〈地獄の穴一味〉だ」
「知り合いは多いよ。いいのもいりゃ悪いのもいる。でも友達は友達さ」
「我々も友達だ。だが仕事に友情は挟まんぞ。いざとなればこれで私も結構冷酷になれるんだ」
ヘイズは思わず目で宙を仰ぎ、じっとブリスコーを見つめていたカーリーが言った。
「いざって?」
ブリスコーはやおらテーブルに身を乗り出した。
「私はチャーリーがどこに金(きん)を隠したか知りたい。町を出る前に教えていってくれ。それだけだ。無事に町を出たかったら教えることだ」
「なんか脅迫じみて聞こえるけど」
「いやいや。警告だ。町の者も鵜の目鷹の目だ。金を捜しに出かけたら後ろに行列が着くと思え。町を出る前に殺されるかもしれん。隠し場所を言えってんで袋叩きだ」
ブリスコーを見つめていたヘイズは冷めた顔で持っていたグラスを放し、頬杖をついた。ブリスコーはうまそうに酒を飲んだ。
「考えとけ。金は逃げん。じっくりやるさ」
しっかと栓をしたボトルを手に、ブリスコーは席を立ったいった。
「けっ」
グラスに口をつけてカーリーが言った。
「町に腰落ち着けるゼニもないのに出て行くことも叶わずか」
「出て行きたきゃ10万ドル寄越せときた。まあなんにしてもここにいりゃ酒は飲みほうだいだ。悪くない待遇だぜ」
そのとき、テーブルの上に赤いリボンで結ばれた巻紙が落ちてきた。思わず上を見上げたヘイズとカーリー。音楽と口笛に合わせ、鳥籠のような入れ物に入った女がけばけばしい赤いドレスの下から黒い編みタイツの足をぶらぶらさせながらゆっくりと降りてきた。カーリーがリボンをはずしにかかった。
「なんだ」
上を見上げたままヘイズが言った。カーリーはすまして、
「何が」
「おまえが拾ったものよ!」
「手紙」
「それはわかってるよ。なんと書いてある」
手紙に目を通していたカーリーは弾んだ声で、
「“会いに来てちょうだい。部屋へ。アリス”」
目を丸くしてヘイズが言った。
「誰が」
「あの子」
カーリーはにっこりして籠を指さした。籠とカーリーとを見比べていたヘイズは早口に、
「じゃねえかと思ったけど、どっちだ。どっちに来いって?」
手紙を見ていたカーリーはおやという顔でヘイズを見ると、
「おれの近くに落ちてきたんだぜ?」
ヘイズはまじまじとカーリーの顔を見返し、
「いやあ、おれのほうに寄ってたよ」
二人は籠のほうに気を取られながらも期待に満ちた視線と笑顔を交わしていた。
「いやあ、しかし」
女の部屋でやや緊張しながら紅茶をごちそうになっているヘイズとカーリー。衝立の向こうでアリスは着替えの最中だった。
「どちらさまへのご招待かはっきりしないんだけど」
そう言ってヘイズは紅茶をすすった。すると衝立の陰からアリスが顔を出して、
「そりゃご両人ともよ。一人じゃ一人がひがむでしょ?」
「ああ、なるほど。そこまで考えてくれたワケ」
ヘイズがこたえ、カーリーはやれやれといった顔でカップを受け皿に置いた。
「お茶好きだったかしら。この草深い町じゃ文明の香りのするものといったらお茶ぐらいですもんね」
アリスの声にカーリーは衝立のほうを振り返った。
「嫌いなの、このブラウンタウンが?」
「だーい嫌い。あたしはサンフランシスコを目指してきたのよ。ところが不運にもここで沈没しちゃってさ」
苦笑した顔をヘイズと見合わせたカーリーは、
「もうどのくらい?」
「そう。一年半ね。いずれは行くつもりよ、サンフランシスコ。資金をこしらえてね。自分のお店を開くのよ」
胸のボタンをかけながらアリスが衝立の中から現れ、ヘイズとカーリーはカップを受け皿に乗せたままの姿ですばやく立ち上がった。フリルのついた薄桃色の部屋着はアリスをいっそうあだっぽく見せていた。
「自分のサルーン?」
ヘイズが言うと、
「まあ、そんなところでしょうね。あたしとしては、あんな格好でほんとは歌いたくないんだけど・・・掛けて」
ヘイズとカーリーは並んで腰掛け、アリスは二人の前に腰を下ろした。
「きみならどんな格好だって」
にこやかにカーリーが言った。
「そのオーバーを着てポーカーテーブルの上に突っ立ってもうけちゃうよ。なんたってあの歌いっぷりだもんねえ」
「泣かせること言ってくれるのねえ。優しいんだわ、ほんと。だから呼んだのよ。そういう人だから来てもらったの」
カップを置いてヘイズが言った。
「・・・というと」
「実はね。お二人に、かんでほしいの。あたしのビジネスに」
ヘイズのほうに顔を向けてからカーリーが言った。
「というと?」
「提携よ」
「はー・・・提携ね」
妙な雲行きになってきたといった顔で、ヘイズがこたえた。勢い込んでアリスが言った。
「三人で組んでサンフランシスコに店を出すのよ。あたしの歌ならいけるでしょ?」
「おれたちはカネ?」
すかさずヘイズが返す。アリスはノンシャランと、
「ええ、まあそういうことね。キャッシュがあれば助かるわ」
ヘイズと顔を見合わせたカーリーが疲れたような声で言った。
「これもチャーリーの金(きん)の隠し場所を言えってナゾらしいよ。いやんなっちゃうなあ」
「胸くそ悪くなってきたよ」
カップを置いてヘイズは言った。
「行こう」
二人はすばやく立ち上がって部屋を出た。二人を引き留めるでもなく、アリスは黙って自分の紅茶を飲んだ。
牢の鍵が開けられた。
「さあ、どうぞ」
食事をしようとしていたチャーリーが振り返るとギターを持ったアリスが入ってきた。彼女が牢番に訊いた。
「面会時間は?」
「そうさなあ。まあ四時間までだろうな」
牢が開かれ、アリスは中に入った。チャーリーは嬉しそうな、はにかむような表情で入ってきた女を見上げた。牢番が言った。
「だけどそんなにいるつもりかね」
「いるつもりよ。チャーリーさんさえよかったら」
「いいも悪いもねえよ」
チャーリーがこたえ、アリスは微笑んでギターを抱えるとチャーリーの横に座った。チャーリーが彼女に言った。
「でもなんだって」
「いえね。歌の二つ三つも歌ってお話相手をしたら少しはあなたの・・・気も晴れるかと」
「じゃ『カウボーイの嘆き』。あれを頼む」
アリスはうなずいてギターをつま弾き、甘く優しい声で歌い出した。
歌を聞いていたチャーリーの瞳がみるみる潤み、胸の思いをかき乱されてか熱いため息をもらした。目を赤くさせ、彼は最後の食事を始めた。歌を聞きながら静かにハムを口に運ぶ彼の様子は従順な少年のようだった。
(続きと感想は、コメントへ)
|
|
|
|
|
|
|
|
西部二人組普及促進委員会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
西部二人組普及促進委員会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90074人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37147人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75521人