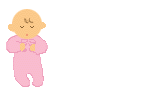どこの国語に限らず、ただ惰性で解いていては、読解力はなかなかつきません。
塾や公文に通わせてさえいれば国語が得意になるか? NOです。
国語教材に限らず、ポイントとなるべき箇所をしっかり押さえて、
単語や熟語の意味(言葉の意味)を確認ながらやっていくのは大切なポイントです。
くもんならBまでは重要な基礎部分ですね。
ここまでをしっかり押さえていけば、読解力はついていくでしょう。
読書をすれば読解力がつくか、そうでもありません。
流し読みをしていて、内容まで頭に入っていない場合があります。
ただ絵をみているだけのお子さんもいます。
本を見ていると(読んでいると、ではなく)親が喜ぶから そうなったのでしょう。
★選択肢をチェックする(英語のG1以降もね♪)
★わからない言葉や読めない漢字を把握する
などが必要です。
これらはただ教材をやるだけではつきません。
ちょっとしたワンポイントアドバイスが必要です。
その上で進めていけば、必ず読解力も作文力もつきますよ。
公文以外の・・・・例えば進学塾のテストなどでも、
常に高い点数を取ることができるはずです。
たまに
「パターンで解いているから、他のテストや問題では点が取れない」
とおっしゃる方がいますが、
パターンで解いているのを初期の段階で見抜かなければなりません。
また、パターンで解いている子は Fからはとっても難しく感じるでしょうし、
手も足も出ない状態になる場合もあるかもしれませんね。
★問題を読んでいるか
★すみからすみまで文字を読んでいるか
★語彙があるか、意味がわかっているか
★音読のスピードとなめらかさ
これらを観察すれば、惰性で解いているか、
パターンで解いているか(大抵の場合、問題を読んでいない)わかりますね。
6A5A5Aあたりだったでしょうか、
読めたら丸をかきましょう、のところでちゃんと丸と書いているか、
4Aの選択して丸をする部分を抜かしていないか
(抜かす子は問題を読んでいない)
先生は把握していても、教室は7日のうちの2日、あとの5日は家庭学習ですからね。
お直しを少なくするためにも、親も把握してあげると良いでしょう。
そうすれば、必ず国語が得意な子に育ちますよ♪
何よりも大事なのは、親子の会話と幼児期の読み聞かせだと思います。
惰性や義務で読むのではなく
読んであげる方ご自身が楽しく読んであげると、素敵なお子さんに育ちますよ。
公文は計算だけだから・・・・このような話も聞きますが、
その前にお母さん、お父さん、おうちで算数遊び していますか?
してきましたか?
乳幼児であれば、お散歩しているときに
あ、犬が3匹いるね。大きい犬が1匹、小さい犬が2匹。
あれは子供かなあ。
あ! チューリップが咲いてるね!
赤い花は何本あるかな・・・1.2.3.4 4本だ♪
と親が数えてみせる、楽しむのです。
質問するのではなくてね。
日頃から生活の中で数を取り入れていれば、文章題は怖くないです。
むしろ、楽しいですね。
トランプ遊びや人生ゲームなどを親子でやったか、も重要です。
そういうのも大事ですし、全部つながっていきますよ。
だって、人生ゲーム、お金の計算がありますもの♪
電車に乗るときは、何個目の駅で降りる?
キップの4ケタの数字を四則を使って10にする遊び
車に乗れば、ナンバー足し算、引き算、黒い車が何台あるか数えよう!
など、色々遊べますね。
お買い物に行けば、あ! 牛肉2割引き? って、いくらよ?
と答えを出すのもいいし、
みかん・・・1袋4個入りで200円と
1袋5個入りで230円、どっちがおとく?
なんてやってもいいですね。
お手伝いも大事。
お料理をお手伝いする子はグラムやccに強いですよ♪
中学受験で重要な比も、お料理をやっている子は得意です。
文章問題に強くなるかどうか、は、どれだけ算数体験が多いか、
生活の中で数に慣れ親しんでいるか、がポイントとなります。
机上でいっぱい問題をやるのはそのあと。 経験なくして解けません。
それよりも遊びや生活の中で楽しくやって、自然と身につけて欲しいと思います。
文章や図形をパターンで覚える方法には限界があると思うから。
文章問題は読解力!
なんて言いますが、もちろんそうです。
でもそれだけでもないです。
問題や算数用語に慣れることも大事。
つまり練習量。
算数Bの文章問題、むずかしくないですか?
特に幼児さんがやる場合、??? となることも。
5枚、10枚単位で復習するのではなく
文章問題部分だけをノートに書いて、絵や図にして何度もやればOKです。
次に数字や物をちょっと変えて同じような問題をやるとよいですね。
文章問題は、自分の言葉でその問題の意味を説明できるようにする習慣をつけると良いですよ。
図形はピタゴラスで遊んでいればいいんじゃないかな?
ブロックとかね。
我が家では レゴが大活躍していますよ。いまだに。
http://
あとは、日頃から何についても考える子に育てていくと良いですね。
すぐに手伝ってあげたりするのではなく、
最後まで自分でやるのを見届けてあげることも大事です。
赤ちゃんがハイハイする、おきあがる、靴を履く、ズボンをはく・・・・
そういう頃から・・・・ね♪
指示するのではなく、「どうする?」と5W1Hで問いかけていくといいですね。
塾や公文に通わせてさえいれば国語が得意になるか? NOです。
国語教材に限らず、ポイントとなるべき箇所をしっかり押さえて、
単語や熟語の意味(言葉の意味)を確認ながらやっていくのは大切なポイントです。
くもんならBまでは重要な基礎部分ですね。
ここまでをしっかり押さえていけば、読解力はついていくでしょう。
読書をすれば読解力がつくか、そうでもありません。
流し読みをしていて、内容まで頭に入っていない場合があります。
ただ絵をみているだけのお子さんもいます。
本を見ていると(読んでいると、ではなく)親が喜ぶから そうなったのでしょう。
★選択肢をチェックする(英語のG1以降もね♪)
★わからない言葉や読めない漢字を把握する
などが必要です。
これらはただ教材をやるだけではつきません。
ちょっとしたワンポイントアドバイスが必要です。
その上で進めていけば、必ず読解力も作文力もつきますよ。
公文以外の・・・・例えば進学塾のテストなどでも、
常に高い点数を取ることができるはずです。
たまに
「パターンで解いているから、他のテストや問題では点が取れない」
とおっしゃる方がいますが、
パターンで解いているのを初期の段階で見抜かなければなりません。
また、パターンで解いている子は Fからはとっても難しく感じるでしょうし、
手も足も出ない状態になる場合もあるかもしれませんね。
★問題を読んでいるか
★すみからすみまで文字を読んでいるか
★語彙があるか、意味がわかっているか
★音読のスピードとなめらかさ
これらを観察すれば、惰性で解いているか、
パターンで解いているか(大抵の場合、問題を読んでいない)わかりますね。
6A5A5Aあたりだったでしょうか、
読めたら丸をかきましょう、のところでちゃんと丸と書いているか、
4Aの選択して丸をする部分を抜かしていないか
(抜かす子は問題を読んでいない)
先生は把握していても、教室は7日のうちの2日、あとの5日は家庭学習ですからね。
お直しを少なくするためにも、親も把握してあげると良いでしょう。
そうすれば、必ず国語が得意な子に育ちますよ♪
何よりも大事なのは、親子の会話と幼児期の読み聞かせだと思います。
惰性や義務で読むのではなく
読んであげる方ご自身が楽しく読んであげると、素敵なお子さんに育ちますよ。
公文は計算だけだから・・・・このような話も聞きますが、
その前にお母さん、お父さん、おうちで算数遊び していますか?
してきましたか?
乳幼児であれば、お散歩しているときに
あ、犬が3匹いるね。大きい犬が1匹、小さい犬が2匹。
あれは子供かなあ。
あ! チューリップが咲いてるね!
赤い花は何本あるかな・・・1.2.3.4 4本だ♪
と親が数えてみせる、楽しむのです。
質問するのではなくてね。
日頃から生活の中で数を取り入れていれば、文章題は怖くないです。
むしろ、楽しいですね。
トランプ遊びや人生ゲームなどを親子でやったか、も重要です。
そういうのも大事ですし、全部つながっていきますよ。
だって、人生ゲーム、お金の計算がありますもの♪
電車に乗るときは、何個目の駅で降りる?
キップの4ケタの数字を四則を使って10にする遊び
車に乗れば、ナンバー足し算、引き算、黒い車が何台あるか数えよう!
など、色々遊べますね。
お買い物に行けば、あ! 牛肉2割引き? って、いくらよ?
と答えを出すのもいいし、
みかん・・・1袋4個入りで200円と
1袋5個入りで230円、どっちがおとく?
なんてやってもいいですね。
お手伝いも大事。
お料理をお手伝いする子はグラムやccに強いですよ♪
中学受験で重要な比も、お料理をやっている子は得意です。
文章問題に強くなるかどうか、は、どれだけ算数体験が多いか、
生活の中で数に慣れ親しんでいるか、がポイントとなります。
机上でいっぱい問題をやるのはそのあと。 経験なくして解けません。
それよりも遊びや生活の中で楽しくやって、自然と身につけて欲しいと思います。
文章や図形をパターンで覚える方法には限界があると思うから。
文章問題は読解力!
なんて言いますが、もちろんそうです。
でもそれだけでもないです。
問題や算数用語に慣れることも大事。
つまり練習量。
算数Bの文章問題、むずかしくないですか?
特に幼児さんがやる場合、??? となることも。
5枚、10枚単位で復習するのではなく
文章問題部分だけをノートに書いて、絵や図にして何度もやればOKです。
次に数字や物をちょっと変えて同じような問題をやるとよいですね。
文章問題は、自分の言葉でその問題の意味を説明できるようにする習慣をつけると良いですよ。
図形はピタゴラスで遊んでいればいいんじゃないかな?
ブロックとかね。
我が家では レゴが大活躍していますよ。いまだに。
http://
あとは、日頃から何についても考える子に育てていくと良いですね。
すぐに手伝ってあげたりするのではなく、
最後まで自分でやるのを見届けてあげることも大事です。
赤ちゃんがハイハイする、おきあがる、靴を履く、ズボンをはく・・・・
そういう頃から・・・・ね♪
指示するのではなく、「どうする?」と5W1Hで問いかけていくといいですね。
|
|
|
|
コメント(15)
学習って、どこで何をやるか
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
学習って、どこで何をやるか
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
学習って、どこで何をやるか
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
学習って、どこで何をやるか
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
ではなく、どのようにやるか
が重要ですね。
先生や親の希望やビジョンを子どもに無理やり当てはめたり、おしつけたり
するのではなく
子どもの現状を把握して、そこから少しずつ育てていけばいいのね♪
常に子どもの気持ちと現状を主語にして細かいステップで笑顔のまま
すすめていけば
どんな子も、どんな状態の子も、どこで何をやっていた子でも
ちゃんと伸びていきますよ♪
まわりの大人の笑顔と喜びが一番大きいな、って思います。
生徒の中には図形に強い子もいます。
もともとの性質もありますが、後からの育て方によることが多いです。
空間認知が弱い子も、空間認知の遊びをすれば徐々に出来るようになります。
大抵はね♪
プリントやドリルをやるのではなく、実際に手を使って遊ぶことだよね♪
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ガウディア・育児・英語・公文 更新情報
-
最新のアンケート
ガウディア・育児・英語・公文のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77424人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209457人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19956人