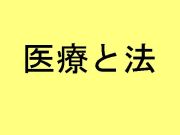|
|
|
|
コメント(27)
読売新聞(2006年5月24日社会面)
「検察官」第5部あすへの模索3
「医療過誤」積極摘発
刑事司法脱却の過渡期
(一部引用)
「捜査機関とは別に専門医が調査し,その結果に基づき行政処分するシステムが出きれば,検察が扱うべき事案は,患者取り違えのような悪質なものに限られる.今はその過渡期だ」と分析する.
「重大事件が相次ぎ,医療不信が高まる中,検察は遺族感情に突き動かされて刑事罰を積極的に適用してきた.しかし,すべてを刑事事件にするのがいいのかどうか」.ある検察幹部は,揺れる胸の内をそう語る.刑事司法がどこまで医療事故に踏み込むべきか−.最高検の研究会は明確な結論を出せないでいる.
「検察官」第5部あすへの模索3
「医療過誤」積極摘発
刑事司法脱却の過渡期
(一部引用)
「捜査機関とは別に専門医が調査し,その結果に基づき行政処分するシステムが出きれば,検察が扱うべき事案は,患者取り違えのような悪質なものに限られる.今はその過渡期だ」と分析する.
「重大事件が相次ぎ,医療不信が高まる中,検察は遺族感情に突き動かされて刑事罰を積極的に適用してきた.しかし,すべてを刑事事件にするのがいいのかどうか」.ある検察幹部は,揺れる胸の内をそう語る.刑事司法がどこまで医療事故に踏み込むべきか−.最高検の研究会は明確な結論を出せないでいる.
読売新聞(2006年5月26日社会面)
医療安全米国報告(4)
日本の制度不備を痛感
大野病院事件 医師逮捕に驚きの声
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/feature/20060526ik04.htm
「えっ,それで医師が逮捕されるの?」
ワシントンの政府系医療機能評価機関の主任研究員,デボラ・クイーンが驚きの声を挙げた.
(中略)
日本では,「医療事故だかけど業務上過失致傷罪から除外する理由はない」とする法曹界と,反発する医療界の”溝”が埋まらない.
昨年,法医学,病理学,臨床の3者が解剖と検証,評価を行うモデル事業が始まったが,過失の評価や好評の方法について明確な基準を出せずにいる.
「なぜ,県ごとにボードを作らないのですか.警察に頼らない事故検証と懲罰の仕組みをつくらなければ,医療はダメになりますよ」.自由主義を掲げ,規制の強化には基本的に反対の立場であるはずの民間研究機関「ケイトー研究所」の担当者でさえそう懸念するのを聞き,日本の制度設計の遅れを強く感じた.
医療安全米国報告(4)
日本の制度不備を痛感
大野病院事件 医師逮捕に驚きの声
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/feature/20060526ik04.htm
「えっ,それで医師が逮捕されるの?」
ワシントンの政府系医療機能評価機関の主任研究員,デボラ・クイーンが驚きの声を挙げた.
(中略)
日本では,「医療事故だかけど業務上過失致傷罪から除外する理由はない」とする法曹界と,反発する医療界の”溝”が埋まらない.
昨年,法医学,病理学,臨床の3者が解剖と検証,評価を行うモデル事業が始まったが,過失の評価や好評の方法について明確な基準を出せずにいる.
「なぜ,県ごとにボードを作らないのですか.警察に頼らない事故検証と懲罰の仕組みをつくらなければ,医療はダメになりますよ」.自由主義を掲げ,規制の強化には基本的に反対の立場であるはずの民間研究機関「ケイトー研究所」の担当者でさえそう懸念するのを聞き,日本の制度設計の遅れを強く感じた.
刑事医療過誤?(飯田英男)判例 タイムズ社
「医療行為の特質と刑事処罰の必要性について」(p11)から引用
ところで,現在,民事,刑事を問わず,医療過誤訴訟に対しては医療者側から様々な批判が加えられている.その内容には,医療者側の法に対する無知や誤解によると思われるものも少なくないが,根本的な問題として,医療行為が本来有している危険性に対して,法側の理解が必ずしも十分ではないとする医療者側の不信・不満が根底にあることを見落としてはならないと思う.すなわち,医療者側からしばしば言われる「医療過誤訴訟が増加すれば萎縮医療に陥る」という批判に対しては,「医療者の本来の使命を忘れた妄言」とすることも可能ではあろう.しかしながら,医療者は,医療行為には危険性が伴っていることを承知の上で治療を行うことをその使命としているのに対して,これを法的に見れば予見可能性があるとして,悪結果が発生すれば直ちに過失責任を問われるというのであれば,危険な行為は回避せざるを得ないという医療者側の言い分にも,それなりの理屈があることは認めざるを得ない.
「医療行為の特質と刑事処罰の必要性について」(p11)から引用
ところで,現在,民事,刑事を問わず,医療過誤訴訟に対しては医療者側から様々な批判が加えられている.その内容には,医療者側の法に対する無知や誤解によると思われるものも少なくないが,根本的な問題として,医療行為が本来有している危険性に対して,法側の理解が必ずしも十分ではないとする医療者側の不信・不満が根底にあることを見落としてはならないと思う.すなわち,医療者側からしばしば言われる「医療過誤訴訟が増加すれば萎縮医療に陥る」という批判に対しては,「医療者の本来の使命を忘れた妄言」とすることも可能ではあろう.しかしながら,医療者は,医療行為には危険性が伴っていることを承知の上で治療を行うことをその使命としているのに対して,これを法的に見れば予見可能性があるとして,悪結果が発生すれば直ちに過失責任を問われるというのであれば,危険な行為は回避せざるを得ないという医療者側の言い分にも,それなりの理屈があることは認めざるを得ない.
「医行為」について
(平成17年7月26日付け厚生労働省の通知)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=851&PAGE=1&FILE=&POS=0
○医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
(平成17年7月26日)
(医政発第0726005号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。
なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。
(別紙)
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
? 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
? 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
? 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
? 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
? 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
? 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
? ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
? 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
? 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。
また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。
注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。
注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。
(平成17年7月26日付け厚生労働省の通知)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=851&PAGE=1&FILE=&POS=0
○医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
(平成17年7月26日)
(医政発第0726005号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。
なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。
(別紙)
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
? 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
? 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
? 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
? 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
? 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
? 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
? ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
? 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
? 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。
また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。
注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。
注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。
ジュリスト2006.11.15号(No.1323)
【特集1】医療安全と法
I 総 論
医療安全と法の日米比較●ロバート・B・レフラー/三瀬朋子(訳)
診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業について●田原克志
II 医療安全に関する法の対応
医療安全に関する刑事司法の現状●佐伯仁志
医療安全に関する民事訴訟の現状●近藤昌昭
医療安全に関する行政処分の現状●宇賀克也
III コメント
〔医師の立場から〕
病理解剖を基にした「医療関連死の医療評価システム」の構築と法整備●深山正久/加治一毅
過失の追及と医療安全の推進●山口 徹
〔弁護士の立場から〕
医師法21条をめぐる現実的な課題●児玉安司
医療事故に関連して発生する刑事処分と行政処分●畔柳達雄
医療被害者の「5つの願い」を踏まえたシステム構築を●加藤良夫
【特集1】医療安全と法
I 総 論
医療安全と法の日米比較●ロバート・B・レフラー/三瀬朋子(訳)
診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業について●田原克志
II 医療安全に関する法の対応
医療安全に関する刑事司法の現状●佐伯仁志
医療安全に関する民事訴訟の現状●近藤昌昭
医療安全に関する行政処分の現状●宇賀克也
III コメント
〔医師の立場から〕
病理解剖を基にした「医療関連死の医療評価システム」の構築と法整備●深山正久/加治一毅
過失の追及と医療安全の推進●山口 徹
〔弁護士の立場から〕
医師法21条をめぐる現実的な課題●児玉安司
医療事故に関連して発生する刑事処分と行政処分●畔柳達雄
医療被害者の「5つの願い」を踏まえたシステム構築を●加藤良夫
厚生労働省のページより
医療安全対策について
---------------------
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/index.html
○法令・通知等
1 安全管理体制全般に関するもの
【平成20年9月1日】医療事故情報収集等事業における報告すべき事案等の周知について(通知)(PDF:313KB)
【平成19年5月8日】院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きについて(PDF:50KB)(PDF:406KB)(PDF:346KB)(PDF:339KB)(1〜12ページ(PDF:549KB)、 13〜26ページ(PDF:548KB)、 27〜41ページ(PDF:549KB)、 42〜55ページ(PDF:546KB)、 56〜59ページ(PDF:452KB)、全体版(PDF:938KB))
【平成19年3月30日】良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について
(1〜10ページ(PDF:487KB)、11〜20ページ(PDF:477KB)、21〜28ページ(PDF:288KB)、全体版(PDF:1,249KB))
【平成19年3月30日】医療安全支援センター運営要領について(PDF:205KB)
【平成19年3月30日】「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルについて(通知(PDF:61KB))
手順書作成マニュアル(PDF:513KB)
手順書作成マニュアル巻末参考(PDF:126KB)
【平成19年3月30日】医療器機に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(PDF:208KB)
【平成19年3月30日】集中治療室(ICU)における安全管理について(報告書)について(PDF:124KB)(PDF:369KB)
【平成19年3月30日】医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針について(PDF:93KB)(PDF:250KB)
【平成17年3月15日】ヒヤリ・ハット事例収集事業の実施について(PDF:25KB) ヒヤリ・ハット事例収集事業要綱(PDF)
【平成16年9月21日】医療法施行規則の一部を改正する省令の一部施行について(特定機能病院などにおける事故事例の報告に関する事項)(PDF:213KB) (官報)(PDF:226KB)
【平成15年12月】厚生労働大臣医療事故対策緊急アピール(PDF:46KB)
【平成15年11月5日】「医療法施行規則の一部を改正する省令」の施行
(特定機能病院に専任の院内感染対策を行う者を配置すること等に係る改正関係について)(PDF:97KB)
【平成15年6月12日】医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について
【平成14年10月7日】医療法施行規則の一部を改正する省令の一部施行について(特定機能病院における安全管理のための体制の確保)(PDF:105KB)
【平成14年8月30日】医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について(病院、有床診療所における安全管理体制の確保について)(PDF:96KB) (官報)(PDF:43KB)
【平成14年4月17日】「医療安全総合対策」について(PDF:35KB) 医療安全総合対策報告書
【平成13年11月7日】「医療安全推進週間」の制定について(PDF:60KB)
【平成12年9月24日】厚生労働大臣メッセージ
【平成12年3月31日】医療施設における医療事故防止対策の強化について
(1〜6ページ(PDF:460KB)、7〜9ページ(PDF:90KB))
【平成11年5月28日】医療施設における医療事故防止の推進について(PDF:81KB)
医療安全対策について
---------------------
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/index.html
○法令・通知等
1 安全管理体制全般に関するもの
【平成20年9月1日】医療事故情報収集等事業における報告すべき事案等の周知について(通知)(PDF:313KB)
【平成19年5月8日】院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引きについて(PDF:50KB)(PDF:406KB)(PDF:346KB)(PDF:339KB)(1〜12ページ(PDF:549KB)、 13〜26ページ(PDF:548KB)、 27〜41ページ(PDF:549KB)、 42〜55ページ(PDF:546KB)、 56〜59ページ(PDF:452KB)、全体版(PDF:938KB))
【平成19年3月30日】良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について
(1〜10ページ(PDF:487KB)、11〜20ページ(PDF:477KB)、21〜28ページ(PDF:288KB)、全体版(PDF:1,249KB))
【平成19年3月30日】医療安全支援センター運営要領について(PDF:205KB)
【平成19年3月30日】「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルについて(通知(PDF:61KB))
手順書作成マニュアル(PDF:513KB)
手順書作成マニュアル巻末参考(PDF:126KB)
【平成19年3月30日】医療器機に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について(PDF:208KB)
【平成19年3月30日】集中治療室(ICU)における安全管理について(報告書)について(PDF:124KB)(PDF:369KB)
【平成19年3月30日】医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針について(PDF:93KB)(PDF:250KB)
【平成17年3月15日】ヒヤリ・ハット事例収集事業の実施について(PDF:25KB) ヒヤリ・ハット事例収集事業要綱(PDF)
【平成16年9月21日】医療法施行規則の一部を改正する省令の一部施行について(特定機能病院などにおける事故事例の報告に関する事項)(PDF:213KB) (官報)(PDF:226KB)
【平成15年12月】厚生労働大臣医療事故対策緊急アピール(PDF:46KB)
【平成15年11月5日】「医療法施行規則の一部を改正する省令」の施行
(特定機能病院に専任の院内感染対策を行う者を配置すること等に係る改正関係について)(PDF:97KB)
【平成15年6月12日】医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について
【平成14年10月7日】医療法施行規則の一部を改正する省令の一部施行について(特定機能病院における安全管理のための体制の確保)(PDF:105KB)
【平成14年8月30日】医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について(病院、有床診療所における安全管理体制の確保について)(PDF:96KB) (官報)(PDF:43KB)
【平成14年4月17日】「医療安全総合対策」について(PDF:35KB) 医療安全総合対策報告書
【平成13年11月7日】「医療安全推進週間」の制定について(PDF:60KB)
【平成12年9月24日】厚生労働大臣メッセージ
【平成12年3月31日】医療施設における医療事故防止対策の強化について
(1〜6ページ(PDF:460KB)、7〜9ページ(PDF:90KB))
【平成11年5月28日】医療施設における医療事故防止の推進について(PDF:81KB)
2 個別の事業に関するもの
【平成20年10月1日】宮城県における診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施について(通知(PDF:443KB) )
【平成20年7月23日】岡山県における診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施について(通知(PDF:151KB) )(添付資料(PDF:248KB) )
【平成19年7月3日】「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」福岡県における事業実施について(PDF:371KB)
【平成18年9月6日】「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」札幌市における事業実施について(PDF:90KB)
【平成18年1月6日】「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」茨城県における事業実施について(PDF:95KB)
【平成17年8月5日】診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施について
【平成16年3月30日】医療安全対策ネットワーク整備事業(ヒヤリ・ハット事例収集事業)の実施について
【平成20年10月1日】宮城県における診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施について(通知(PDF:443KB) )
【平成20年7月23日】岡山県における診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施について(通知(PDF:151KB) )(添付資料(PDF:248KB) )
【平成19年7月3日】「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」福岡県における事業実施について(PDF:371KB)
【平成18年9月6日】「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」札幌市における事業実施について(PDF:90KB)
【平成18年1月6日】「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」茨城県における事業実施について(PDF:95KB)
【平成17年8月5日】診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の実施について
【平成16年3月30日】医療安全対策ネットワーク整備事業(ヒヤリ・ハット事例収集事業)の実施について
3 その他個別の安全対策に関するもの
【平成20年12月9日】医療事故情報収集等事業第15回報告書の公表について 通知(1〜2ページ(PDF:207KB)、 3ページ(PDF:778KB)、 4ページ(PDF:734KB)、
5ページ(PDF:737KB)、 6ページ(PDF:734KB)、全体版(PDF:1,102KB)) 報告書12月9日
【平成20年12月4日】医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について(注意喚起)(通知)(PDF:260KB)12月5日
【平成20年10月20日】抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与(過剰投与)防止のための取扱いについて(注意喚起)(通知)(1〜7ページ(PDF:472KB)、 8〜12ページ(PDF:495KB)、 13ページ(PDF:258KB)、全体版(PDF:927KB))
【平成20年10月3日】ペン型インスリン注入器の取扱いについて(医療機関への注意喚起及び周知徹底依頼)(通知)(PDF:313KB)
【平成20年9月30日】医療事故情報収集等事業第14回報告書の公表について 通知(1ページ(PDF:99KB)、 2ページ(PDF:731KB)、 3ページ(PDF:684KB)、
4ページ(PDF:687KB)、 5ページ(PDF:644KB)、 6ページ(PDF:643KB)、
全体版(PDF:945KB)) 報告書
【平成20年8月13日】医療事故情報収集等事業 平成19年年報の公表について 通知(PDF:39KB) 報告書
【平成20年6月18日】医療事故情報収集等事業第13回報告書の公表について 通知 (1ページ(PDF:314KB)、 2ページ(PDF:717KB)、 3ページ(PDF:675KB)、
4ページ(PDF:677KB)、 5ページ(PDF:630KB)、 6〜7ページ(PDF:197KB)、全体版(PDF:1,119KB)) 報告書
【平成20年5月22日】採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて(注意喚起)(通知(PDF:489KB) )
【平成20年3月19日】医療事故情報収集等事業第12回報告書の公表について 通知(1ページ(PDF:81KB)、 2ページ(PDF:719KB)、 3ページ(PDF:693KB)、 4ページ(PDF:697KB)、 5ページ(PDF:632KB)、全体版(PDF:876KB)) 報告書)
【平成20年3月11日】医療機関用・介護用ベッドのサイドレール・手すりによる事故について(通知(1〜5ページ(PDF:482KB)、 6〜9ページ(PDF:343KB)、全体版(PDF:850KB)) )
【平成20年1月18日】気管切開チューブに装着する器具に関する取扱いについて(通知(PDF:66KB))
【平成19年12月28日】診療行為に伴う院内感染事例の発生及び安全管理体制の徹底について (通知(PDF:32KB) 参考資料(1〜11ページ(PDF:470KB)、12〜15ページ(PDF:125KB)、全体版(PDF:600KB)))
【平成19年12月19日】医療事故情報収集等事業第11回報告書の公表について 通知(PDF:296KB) 報告書
【平成19年10月30日】薬剤耐性菌による院内感染対策の徹底及び発生後の対応について (通知(PDF:65KB) 参考資料(1〜18ページ(PDF:457KB)、 19〜20ページ(PDF:95KB)、全体版(PDF:658KB)))
【平成19年9月18日】医療事故情報収集等事業第10回報告書の公表について(PDF)(PDF:171KB)
【平成19年9月14日】手動式肺人工蘇生器の自主回収等について(依頼)(PDF:105KB)
【平成19年7月18日】医療事故情報収集等事業 平成18年 年報の公表について(PDF)(PDF:13KB)
【平成19年6月27日】医療事故情報収集等事業第9回報告書の公表について(PDF)
(1ページ(PDF:37KB)、 2ページ(PDF:721KB)、 3ページ(PDF:752KB)、全体版(PDF:850KB))
【平成19年2月28日】医療事故情報収集等事業第8回報告書の公表について(PDF)(PDF:106KB)
【平成18年12月26日】医療事故情報収集等事業第7回報告書(PDF)の公表および「医療安全情報」(PDF)提供の開始について(PDF:44KB)
【平成18年11月27日】無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
【平成18年9月25日】医療機関における安全管理体制について(院内で発生する乳児連れ去りや盗難等の被害及び職員への暴力被害への取り組みに関して(PDF)(PDF:46KB)
【平成18年9月13日】医療事故情報収集事業第6回報告書の公表について(PDF)(PDF:69KB)
【平成18年6月15日】医療事故情報収集事業第5回報告書の公表について(PDF)(PDF:62KB)
【平成18年3月8日】医療事故情報収集事業第4回報告書の公表について(PDF)(PDF:41KB)
【平成17年11月25日】X線CT装置等と植え込み型心臓ペースメーカ等装置の相互作用に係る「使用上の注意」の改訂指示等について(PDF:361KB)
【平成20年12月9日】医療事故情報収集等事業第15回報告書の公表について 通知(1〜2ページ(PDF:207KB)、 3ページ(PDF:778KB)、 4ページ(PDF:734KB)、
5ページ(PDF:737KB)、 6ページ(PDF:734KB)、全体版(PDF:1,102KB)) 報告書12月9日
【平成20年12月4日】医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化・徹底について(注意喚起)(通知)(PDF:260KB)12月5日
【平成20年10月20日】抗リウマチ剤メトトレキサート製剤の誤投与(過剰投与)防止のための取扱いについて(注意喚起)(通知)(1〜7ページ(PDF:472KB)、 8〜12ページ(PDF:495KB)、 13ページ(PDF:258KB)、全体版(PDF:927KB))
【平成20年10月3日】ペン型インスリン注入器の取扱いについて(医療機関への注意喚起及び周知徹底依頼)(通知)(PDF:313KB)
【平成20年9月30日】医療事故情報収集等事業第14回報告書の公表について 通知(1ページ(PDF:99KB)、 2ページ(PDF:731KB)、 3ページ(PDF:684KB)、
4ページ(PDF:687KB)、 5ページ(PDF:644KB)、 6ページ(PDF:643KB)、
全体版(PDF:945KB)) 報告書
【平成20年8月13日】医療事故情報収集等事業 平成19年年報の公表について 通知(PDF:39KB) 報告書
【平成20年6月18日】医療事故情報収集等事業第13回報告書の公表について 通知 (1ページ(PDF:314KB)、 2ページ(PDF:717KB)、 3ページ(PDF:675KB)、
4ページ(PDF:677KB)、 5ページ(PDF:630KB)、 6〜7ページ(PDF:197KB)、全体版(PDF:1,119KB)) 報告書
【平成20年5月22日】採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて(注意喚起)(通知(PDF:489KB) )
【平成20年3月19日】医療事故情報収集等事業第12回報告書の公表について 通知(1ページ(PDF:81KB)、 2ページ(PDF:719KB)、 3ページ(PDF:693KB)、 4ページ(PDF:697KB)、 5ページ(PDF:632KB)、全体版(PDF:876KB)) 報告書)
【平成20年3月11日】医療機関用・介護用ベッドのサイドレール・手すりによる事故について(通知(1〜5ページ(PDF:482KB)、 6〜9ページ(PDF:343KB)、全体版(PDF:850KB)) )
【平成20年1月18日】気管切開チューブに装着する器具に関する取扱いについて(通知(PDF:66KB))
【平成19年12月28日】診療行為に伴う院内感染事例の発生及び安全管理体制の徹底について (通知(PDF:32KB) 参考資料(1〜11ページ(PDF:470KB)、12〜15ページ(PDF:125KB)、全体版(PDF:600KB)))
【平成19年12月19日】医療事故情報収集等事業第11回報告書の公表について 通知(PDF:296KB) 報告書
【平成19年10月30日】薬剤耐性菌による院内感染対策の徹底及び発生後の対応について (通知(PDF:65KB) 参考資料(1〜18ページ(PDF:457KB)、 19〜20ページ(PDF:95KB)、全体版(PDF:658KB)))
【平成19年9月18日】医療事故情報収集等事業第10回報告書の公表について(PDF)(PDF:171KB)
【平成19年9月14日】手動式肺人工蘇生器の自主回収等について(依頼)(PDF:105KB)
【平成19年7月18日】医療事故情報収集等事業 平成18年 年報の公表について(PDF)(PDF:13KB)
【平成19年6月27日】医療事故情報収集等事業第9回報告書の公表について(PDF)
(1ページ(PDF:37KB)、 2ページ(PDF:721KB)、 3ページ(PDF:752KB)、全体版(PDF:850KB))
【平成19年2月28日】医療事故情報収集等事業第8回報告書の公表について(PDF)(PDF:106KB)
【平成18年12月26日】医療事故情報収集等事業第7回報告書(PDF)の公表および「医療安全情報」(PDF)提供の開始について(PDF:44KB)
【平成18年11月27日】無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
【平成18年9月25日】医療機関における安全管理体制について(院内で発生する乳児連れ去りや盗難等の被害及び職員への暴力被害への取り組みに関して(PDF)(PDF:46KB)
【平成18年9月13日】医療事故情報収集事業第6回報告書の公表について(PDF)(PDF:69KB)
【平成18年6月15日】医療事故情報収集事業第5回報告書の公表について(PDF)(PDF:62KB)
【平成18年3月8日】医療事故情報収集事業第4回報告書の公表について(PDF)(PDF:41KB)
【平成17年11月25日】X線CT装置等と植え込み型心臓ペースメーカ等装置の相互作用に係る「使用上の注意」の改訂指示等について(PDF:361KB)
【平成17年11月24日】輸液ポンプの承認基準等の制定に伴う医療機関などの対応について(PDF:271KB)
【平成17年10月31日】医療事故情報収集等事業第3回報告書の公表について(PDF)(PDF:52KB)
【平成17年9月30日】点滴用キシロカイン10%の供給停止について(PDF:337KB)
【平成17年9月30日】カートリッジ式のインスリン製剤(ランタス注オプチクリック300)及び専用の手動式医薬品注入器(オプチクリック)の安全対策について(依頼)(PDF:220KB)
【平成17年9月12日】総務省取りまとめにより「各種電波利用機器の電波が植込み型医用機器へ及ぼす影響を防止するための指針」の送付について
(1〜4ページ(PDF:498KB)、5ページ(PDF:271KB)、6ページ(PDF:321KB)、
7〜8ページ(PDF:422KB)、9〜10ページ(PDF:304KB))
【平成17年7月29日】医療事故情報収集事業第2回報告書の公表について(PDF)(PDF:38KB)
【平成17年3月29日】点滴用キシロカインの取り扱いについて(PDF:39KB)
【平成17年2月7日】簡易自己血糖測定器及び自己血糖検査用グルコースキット(グルコース脱水素酵素法のうち補酵素にピロロキノリンキノンを使用するもの)の安全対策について(PDF:48KB)
【平成16年6月2日】医療機関における医療事故防止対策の強化・徹底について(医薬品の取り違え防止対策の徹底について)(PDF:318KB)
【平成16年2月9日】単回使用医療用具に関する取り扱いについて(PDF:23KB)
【平成15年11月27日】医療機関における医療事故防止の強化について(間違いやすい医薬品の採用状況の確認)(PDF:61KB)
【平成17年10月31日】医療事故情報収集等事業第3回報告書の公表について(PDF)(PDF:52KB)
【平成17年9月30日】点滴用キシロカイン10%の供給停止について(PDF:337KB)
【平成17年9月30日】カートリッジ式のインスリン製剤(ランタス注オプチクリック300)及び専用の手動式医薬品注入器(オプチクリック)の安全対策について(依頼)(PDF:220KB)
【平成17年9月12日】総務省取りまとめにより「各種電波利用機器の電波が植込み型医用機器へ及ぼす影響を防止するための指針」の送付について
(1〜4ページ(PDF:498KB)、5ページ(PDF:271KB)、6ページ(PDF:321KB)、
7〜8ページ(PDF:422KB)、9〜10ページ(PDF:304KB))
【平成17年7月29日】医療事故情報収集事業第2回報告書の公表について(PDF)(PDF:38KB)
【平成17年3月29日】点滴用キシロカインの取り扱いについて(PDF:39KB)
【平成17年2月7日】簡易自己血糖測定器及び自己血糖検査用グルコースキット(グルコース脱水素酵素法のうち補酵素にピロロキノリンキノンを使用するもの)の安全対策について(PDF:48KB)
【平成16年6月2日】医療機関における医療事故防止対策の強化・徹底について(医薬品の取り違え防止対策の徹底について)(PDF:318KB)
【平成16年2月9日】単回使用医療用具に関する取り扱いについて(PDF:23KB)
【平成15年11月27日】医療機関における医療事故防止の強化について(間違いやすい医薬品の採用状況の確認)(PDF:61KB)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
医療と法 更新情報
-
最新のアンケート