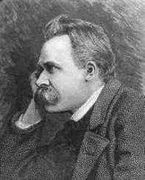|
|
|
|
コメント(28)
>留吉onlineさん
「既に誰かが思いついている」って、どういうイメージの言葉だと思います?
哲学者のやっている哲学も、昔の哲学者の言っていることに+αしたりとか、別の見方をしているとか、そういう形で進んでいるのは変わらないと思うんですよね。ときどきニュートン力学に対する相対性理論みたいのがあらわれて、過去の哲学が「間違っていた」と解釈されることもあるのでしょうが。
だから、私は哲学に何らかの評価を与えるとするなら、それは深いか浅いかといったイメージなのかなって思ってます。深いってのはそれまでよくわからなかったこともよく説明できるってことでしょうか。
より深い哲学をわかっている人は、より浅い哲学をわかっている人のいうことをすぐ理解できて、それが「ああ、もうそれは誰それが言っているよ」という感覚につながるんだと思います。
「既に誰かが思いついている」って、どういうイメージの言葉だと思います?
哲学者のやっている哲学も、昔の哲学者の言っていることに+αしたりとか、別の見方をしているとか、そういう形で進んでいるのは変わらないと思うんですよね。ときどきニュートン力学に対する相対性理論みたいのがあらわれて、過去の哲学が「間違っていた」と解釈されることもあるのでしょうが。
だから、私は哲学に何らかの評価を与えるとするなら、それは深いか浅いかといったイメージなのかなって思ってます。深いってのはそれまでよくわからなかったこともよく説明できるってことでしょうか。
より深い哲学をわかっている人は、より浅い哲学をわかっている人のいうことをすぐ理解できて、それが「ああ、もうそれは誰それが言っているよ」という感覚につながるんだと思います。
>サーペントさん
もうだれかが思いついているのにその人が外に伝えなかったから残らなかった考えというのは、いっぱいあると思います。
死以外にも人に考えが伝わらなくなることとして、発狂があります。
ニーチェは発狂する前に友人に以下の手紙を送ってます。
「私が人間であるというのは偏見です。…私はインドに居たころは仏陀でしたし、ギリシアではディオニュソスでした。…アレクサンドロス大王とカエサルは私の化身ですし、ヴォルテールとナポレオンだったこともあります。…リヒャルト・ヴァーグナーだったことがあるような気もしないではありません。…十字架にかけられたこともあります。…愛しのアリアドネへ、ディオニュソスより」
狂気の兆候とみなされているようですが、もしニーチェが西洋の思考の枠にとどまらないものの見方にたどり着いたと考えるなら、これは狂った手紙を書いたというよりは他人が理解できない手紙を書いたということであって、ニーチェ自身はその意味を「理解している」といってもいいかと思います(「理解している」とは「人に説明できること」という話もありますが、おいておきましょう)。
実際東洋哲学のノリでこの手紙を眺めてみると、ごく普通の平凡で浅い見解にしか見えないんじゃないでしょうか(量子力学者とかで東洋哲学にひかれた人っているみたいですが、二元論を超えるとこういう手紙のような感覚で世の中を見始めるんだと思います)。
話が長くなりましたが、例えばかつてニーチェより高速にニーチェと同じような思考をたどった人がいた場合でも、その人は世の中に考えを出す前に発狂してしまってて、その考えが世の中にでることはなかったでしょう。
あるいは相当早い段階(小児とか)に発狂寸前のニーチェと同じように世界をみるようになった人は、社会からは狂人か、せめて相当変わった人という見方をされて、彼らの考えも世にでることはないでしょう(それも東洋でうまれるか西洋でうまれるかによってかわるかもしれませんね)。
もうだれかが思いついているのにその人が外に伝えなかったから残らなかった考えというのは、いっぱいあると思います。
死以外にも人に考えが伝わらなくなることとして、発狂があります。
ニーチェは発狂する前に友人に以下の手紙を送ってます。
「私が人間であるというのは偏見です。…私はインドに居たころは仏陀でしたし、ギリシアではディオニュソスでした。…アレクサンドロス大王とカエサルは私の化身ですし、ヴォルテールとナポレオンだったこともあります。…リヒャルト・ヴァーグナーだったことがあるような気もしないではありません。…十字架にかけられたこともあります。…愛しのアリアドネへ、ディオニュソスより」
狂気の兆候とみなされているようですが、もしニーチェが西洋の思考の枠にとどまらないものの見方にたどり着いたと考えるなら、これは狂った手紙を書いたというよりは他人が理解できない手紙を書いたということであって、ニーチェ自身はその意味を「理解している」といってもいいかと思います(「理解している」とは「人に説明できること」という話もありますが、おいておきましょう)。
実際東洋哲学のノリでこの手紙を眺めてみると、ごく普通の平凡で浅い見解にしか見えないんじゃないでしょうか(量子力学者とかで東洋哲学にひかれた人っているみたいですが、二元論を超えるとこういう手紙のような感覚で世の中を見始めるんだと思います)。
話が長くなりましたが、例えばかつてニーチェより高速にニーチェと同じような思考をたどった人がいた場合でも、その人は世の中に考えを出す前に発狂してしまってて、その考えが世の中にでることはなかったでしょう。
あるいは相当早い段階(小児とか)に発狂寸前のニーチェと同じように世界をみるようになった人は、社会からは狂人か、せめて相当変わった人という見方をされて、彼らの考えも世にでることはないでしょう(それも東洋でうまれるか西洋でうまれるかによってかわるかもしれませんね)。
> 〇永遠氏
その辞書に記載されている意味は妥当なものではないね、
形而上の問題はその限りではないからね、
根本原理は過去未来に関わらず万物すべてに共通する原則によって導出されなければ現実的に考えて意味を為さない。
故に“絶対的な真理など存在しない”となれば哲学は現実対応するための都合解釈。一定のルールに基づく言葉遊びにしかならない。
しかし、人間が道徳的によく生きていくための有用価値のあるツールにはなる。
また、過去は現在的に立脚された点から見れば確定事項であるが未来には不確定要素が含まれるがゆえ、確実な未来予測は困難を窮める。
未来・過去の存在の是非は事実解釈として、これとは別に問われるところ、
未来そのものの観念が語られない訳ではない。
その辞書に記載されている意味は妥当なものではないね、
形而上の問題はその限りではないからね、
根本原理は過去未来に関わらず万物すべてに共通する原則によって導出されなければ現実的に考えて意味を為さない。
故に“絶対的な真理など存在しない”となれば哲学は現実対応するための都合解釈。一定のルールに基づく言葉遊びにしかならない。
しかし、人間が道徳的によく生きていくための有用価値のあるツールにはなる。
また、過去は現在的に立脚された点から見れば確定事項であるが未来には不確定要素が含まれるがゆえ、確実な未来予測は困難を窮める。
未来・過去の存在の是非は事実解釈として、これとは別に問われるところ、
未来そのものの観念が語られない訳ではない。
>未来そのものの観念が語られない訳ではない。
「未来」という概念については確かにそうだけど....。
例えば、ソクラテスやプラトンの時代に「携帯電話」や「インターネット」や「テレビゲーム」について語られたかというと、その頃にはそんなものは存在しなかったので、もちろん話題にのぼる事はなかった。
これらに関する話題が哲学的でないかというと、決してそんな事はない。
ネット社会がもたらすものや、TVゲームにしか興味がない人間についてなど、けっこうトピの話題としてもあげられている。
同様に、これから先、人間が新しく創造するものや、未来のその時点まで観測されることのないもの(現代人の想像力の限界を超えているもの)については、「現時点では」語りようがないのでは?
「未来」という概念については確かにそうだけど....。
例えば、ソクラテスやプラトンの時代に「携帯電話」や「インターネット」や「テレビゲーム」について語られたかというと、その頃にはそんなものは存在しなかったので、もちろん話題にのぼる事はなかった。
これらに関する話題が哲学的でないかというと、決してそんな事はない。
ネット社会がもたらすものや、TVゲームにしか興味がない人間についてなど、けっこうトピの話題としてもあげられている。
同様に、これから先、人間が新しく創造するものや、未来のその時点まで観測されることのないもの(現代人の想像力の限界を超えているもの)については、「現時点では」語りようがないのでは?
> 春助さん
>008での、
哲学の意味に
『根本原理』という、
表現が、適切でないということですね?
形而上の問題を、
扱う哲学だから。
辞典のはじめに書いてあった、
「仮説に基づかず」のところに、
ちょっと引っかかりを感じて、
未来は、仮説に基づかないと、語れないので、
その最初の部分のみ、
引用しました。
あと「……自然や、社会を貫く 一般的な法則性を 探究する学問…ギリシャに始まる…(哲学の簡単な流れ)…Philosophia………
西周が…希哲学と訳したことに、始まる」
結構、長いです
〔金田一春彦監修〕
「一般的な法則性」というのは、
春助さんのご見解に近いでしょうか。
未来という観念について、語るとして、
哲学は、時間を、
超える、普遍的な真理を、持ち得るんでしょうね。
「仮説に基づいて 」というのは、
」というのは、
哲学的態度では、
ないのでしょうか。
そうならば、未来については、哲学からのアプローチは、
しにくいですが。
>008での、
哲学の意味に
『根本原理』という、
表現が、適切でないということですね?
形而上の問題を、
扱う哲学だから。
辞典のはじめに書いてあった、
「仮説に基づかず」のところに、
ちょっと引っかかりを感じて、
未来は、仮説に基づかないと、語れないので、
その最初の部分のみ、
引用しました。
あと「……自然や、社会を貫く 一般的な法則性を 探究する学問…ギリシャに始まる…(哲学の簡単な流れ)…Philosophia………
西周が…希哲学と訳したことに、始まる」
結構、長いです
〔金田一春彦監修〕
「一般的な法則性」というのは、
春助さんのご見解に近いでしょうか。
未来という観念について、語るとして、
哲学は、時間を、
超える、普遍的な真理を、持ち得るんでしょうね。
「仮説に基づいて
哲学的態度では、
ないのでしょうか。
そうならば、未来については、哲学からのアプローチは、
しにくいですが。
> yopisound氏
現在的な立脚点から見れば確実な未来予測は困難を窮める。
現時点での想像力の範疇を逸脱していれば、想像することが出来ないので語ることは出来ないだろうね、
ただ、包括的に捉えれば言葉で表現される以上、個人の想像を越えているものであれど人間の想像力の範疇におさまる。
特に物理的現象は超越的で認識されない限りに於いては知りようがない。
人間の想像力で創造されたものが人間の想像力を超えた未来予測を打ち立てることも考えられる。
あくまでも未来予測は事実確認から因果関係を明白にし、そこからその法則性を見出だし推測するしかない。
時空間世界そのものが自由意志による決定によりバタフライエフェクトを起こしていると仮定すればその未来が遠ければ遠いほど可能性として未来が細分化されて存在することが想定されるため、決定論としての予測はより困難となる。
いずれにせよ未来が客観的実在として存在しているとしても現在的にしか生きられない私達人間には原理的に未来そのものを知ることが出来ないだろう。
現在的な立脚点から見れば確実な未来予測は困難を窮める。
現時点での想像力の範疇を逸脱していれば、想像することが出来ないので語ることは出来ないだろうね、
ただ、包括的に捉えれば言葉で表現される以上、個人の想像を越えているものであれど人間の想像力の範疇におさまる。
特に物理的現象は超越的で認識されない限りに於いては知りようがない。
人間の想像力で創造されたものが人間の想像力を超えた未来予測を打ち立てることも考えられる。
あくまでも未来予測は事実確認から因果関係を明白にし、そこからその法則性を見出だし推測するしかない。
時空間世界そのものが自由意志による決定によりバタフライエフェクトを起こしていると仮定すればその未来が遠ければ遠いほど可能性として未来が細分化されて存在することが想定されるため、決定論としての予測はより困難となる。
いずれにせよ未来が客観的実在として存在しているとしても現在的にしか生きられない私達人間には原理的に未来そのものを知ることが出来ないだろう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|