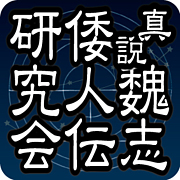守山 敬之
岩元学説で導き出される驚きの真説の一つに、伊都國を宮崎県日之影町に比定する説がある。末盧國を博多に比定する岩元説では、そこから「東南陸行五百里」の記述をもって(ただし1里を魏朝の標準里437・4mとし、それに変尺率3/5を乗じる)、伊都國を日之影に比定する。この比定は、奴國が日向、不彌國が延岡に比定されることとセットである。
ひとつの文献学的到達点と考えられる説だが、邪馬台國九州説にせよ畿内説にせよ、伊都國が北部九州(糸島付近)であることを動かぬ定理とする「通説」信奉者には、どうしても受け入れがたい。これには北部九州の考古学的発掘成果や「怡土」「糸島」などの地名、「一大率」が置かれるなど重要な役割を持っていたと推察される倭人伝の記述も裏付けとなっているが、それ以上に日之影や隣りの高千穂という土地に「千餘戸」「郡使往来常所駐」の伊都國が存在しえたのかという「イメージ」も大きくかかわっている。ましてや岩元説では伊都國を公孫氏の拠点としている。
しかし三世紀にそこに本当に國邑があったかどうかは、本来は我々の抱く印象の問題ではないし、「伊都國」なるものに対する「通説」的なイメージも突き詰めれば主観的なものに過ぎない。
試みに日之影の現在の人口と世帯数を調べてみた。今の人口を調べても何の役にも立たないと言う人も間違いなくいるだろう。同感である。しかしここでの目的はあくまでも主観的なイメージの払しょくであり、通説的な思い込みが必ずしも絶対的なものではなく、どんな仮説も想像の要素なくしては語られ得ないという指摘なので、お付き合い程度のつもりで見ていただきたい。
日之影町の統計だが、町のホームページ(http://
いずれも山に囲まれた山間の町であり、平野部のように近世から近現代にかけて大幅に規模や人口が拡張するとは考えにくい土地である。現代と古代とで、キャパシティーには大きな変化はない。建築技術や生産技術の発展を差し引いても三世紀に「千餘戸」を擁したことが否定できるものではない。耕す土地がなければそれなりの人口を養うことができないというのは決めつけで、『魏志』倭人伝の対馬(對海國)や壱岐(一大國)の記述を読めばわかるが、良田がなくとも交易などの方法はある。
この地は北から南に日之影川が流れ、西から東に下る五ヶ瀬川に合流する。山間の川沿いの地は守るによし暮らすによしで、縄文時代から営々と築き上げられてきた國邑が弥生時代にも引き継がれ、公孫氏が天下ってからも、あるいは信仰の対象として、あるいは防衛や交易の拠点として特別視されてきたのではないか、などと「想像」することもできる。
伊都國が古代倭人にとって何かしら特別な信仰の地であったと考えると、メリットもある。公孫氏がそこをおさえた理由も、卑彌呼が奴國(日向)に遷都した理由もその事象と繋げることができるからだ。天孫降臨神話が醸成されるのは無論そのあとのことだが、それ以前からも土着の信仰や、あるいは公孫氏よりずっと前に大陸からもたらされていた道教信仰などが幾重にも折り重なり習合して、土台となっていたのである。これを公孫氏も調査済みだったし、卑彌呼も(彼女が何者であれ)もちろん熟知していたに違いない。伊都國・奴國の官名に見られる「觚(こ)」字の原義は祭祀に用いる青銅のカップであり、青銅のポットである「爵(しゃく)」とセットで使われるという。それは殷代の話だが、時代が下って「爵」が身分を表したように、「觚」もまた祭祀に携わる官を意味する文字として使用されたのかもしれない。
言うまでもなく、「想像」は裏付けにはならない。ただし条件がそろっていれば蓋然性は否定できない。日之影説の問題は考古学的な裏付けがない点である。仮に発掘しても、「通説」派が期待するような「伊都國」の面影は見つからないかもしれない。ではそこが「伊都國」ではないのかというと、そうも結論付けられない。それならそれで、そういう「伊都國」像があってもよいと柔軟に考える余地が残っている。魏志倭人伝は私たちの想像までは制限しない。だからこそ伊都國を北部九州に持っていこうとする「想像」も許されるのである。逆に「通説」の問題は末盧國からの距離や方位など魏志倭人伝の記述と合致しないという意味で文献学的な裏付けがない点であり、裏付けがないところを「想像」によって補填しているという意味ではイーブンであろう。そのような土地を倭人伝に載る地名に因んで「伊都國」と名付けるのは便宜であり、ロマンであって、結論ではない。
伊都國=日之影説の蓋然性を指摘したうえで、日之影説に期待を寄せる方々のためにもう一歩踏み込ませていただこう。日之影にも遺跡がないわけではない。大字七折(ななおれ)の最大標高差12mという丘陵斜面で町営グラウンド造成に伴い見つかった「平底遺跡(ひらそこいせき)」の報告書を、平成15年に日之影町教育委員会がまとめた(『日之影町教育委員会 発掘調査報告書 第1集 平底遺跡 町営「水と緑の夢空間事業」に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』2003、奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」よりダウンロード可能http://
報告書によると、五ヶ瀬川にそそぐ長谷川の西岸斜面に位置するこの遺跡は、縄文時代晩期から弥生時代を経て古墳時代中頃までの息の長い遺跡で、住居跡や石器・土器とわずかな鉄器が発掘されている。日之影町・高千穂町・五ヶ瀬町からなる西臼杵郡では最大規模の遺跡であるという。それまでに日之影町で発掘された遺跡は決して少なくないが、古墳時代まで続く遺跡はここが初めて。
発掘された「工字突帯文土器」などの土器については弥生時代後期から終末期にかけてのものと考えられ、宮崎県北部平野部や大分県とのつながりが指摘される。五世紀中頃の古墳時代の遺構からは松山産の須恵器が出土している。また、平底遺跡にはなかったが、日之影町内の別の遺跡からは「安国寺式土器」という、国東地方の土器がわずかに出ている。日之影が延岡や大分を経て瀬戸内海地域と交流していた様子がうかがわれる。おそらく、これらの地方は北部九州の勢力とは一線を画していたに違いない。
しかしそうなると、今度は中国の公孫氏を匂わせる遺物が出ていないことの意味を考えなければならなくなる。平底遺跡は古代日本人の暮らしがそこにあったことを示しているが、祭祀だとか権力者だとか聖職者などの存在をそこから想像することは難しい。そうした要素は存在しなかったのか、まだ発掘されていないだけなのか、ある時期に根こそぎ消え去ったのか、まったく謎である。ただ後世、高千穂に神話と伝説だけが語られるようになった。名こそ流れてなのである。
※写真はグーグルマップのストリートビューより、平底遺跡が発掘された現「癒しの森運動公園」付近。日之影町の雄大な景色に、静かな神々しさも感じられませんか。
岩元学説で導き出される驚きの真説の一つに、伊都國を宮崎県日之影町に比定する説がある。末盧國を博多に比定する岩元説では、そこから「東南陸行五百里」の記述をもって(ただし1里を魏朝の標準里437・4mとし、それに変尺率3/5を乗じる)、伊都國を日之影に比定する。この比定は、奴國が日向、不彌國が延岡に比定されることとセットである。
ひとつの文献学的到達点と考えられる説だが、邪馬台國九州説にせよ畿内説にせよ、伊都國が北部九州(糸島付近)であることを動かぬ定理とする「通説」信奉者には、どうしても受け入れがたい。これには北部九州の考古学的発掘成果や「怡土」「糸島」などの地名、「一大率」が置かれるなど重要な役割を持っていたと推察される倭人伝の記述も裏付けとなっているが、それ以上に日之影や隣りの高千穂という土地に「千餘戸」「郡使往来常所駐」の伊都國が存在しえたのかという「イメージ」も大きくかかわっている。ましてや岩元説では伊都國を公孫氏の拠点としている。
しかし三世紀にそこに本当に國邑があったかどうかは、本来は我々の抱く印象の問題ではないし、「伊都國」なるものに対する「通説」的なイメージも突き詰めれば主観的なものに過ぎない。
試みに日之影の現在の人口と世帯数を調べてみた。今の人口を調べても何の役にも立たないと言う人も間違いなくいるだろう。同感である。しかしここでの目的はあくまでも主観的なイメージの払しょくであり、通説的な思い込みが必ずしも絶対的なものではなく、どんな仮説も想像の要素なくしては語られ得ないという指摘なので、お付き合い程度のつもりで見ていただきたい。
日之影町の統計だが、町のホームページ(http://
いずれも山に囲まれた山間の町であり、平野部のように近世から近現代にかけて大幅に規模や人口が拡張するとは考えにくい土地である。現代と古代とで、キャパシティーには大きな変化はない。建築技術や生産技術の発展を差し引いても三世紀に「千餘戸」を擁したことが否定できるものではない。耕す土地がなければそれなりの人口を養うことができないというのは決めつけで、『魏志』倭人伝の対馬(對海國)や壱岐(一大國)の記述を読めばわかるが、良田がなくとも交易などの方法はある。
この地は北から南に日之影川が流れ、西から東に下る五ヶ瀬川に合流する。山間の川沿いの地は守るによし暮らすによしで、縄文時代から営々と築き上げられてきた國邑が弥生時代にも引き継がれ、公孫氏が天下ってからも、あるいは信仰の対象として、あるいは防衛や交易の拠点として特別視されてきたのではないか、などと「想像」することもできる。
伊都國が古代倭人にとって何かしら特別な信仰の地であったと考えると、メリットもある。公孫氏がそこをおさえた理由も、卑彌呼が奴國(日向)に遷都した理由もその事象と繋げることができるからだ。天孫降臨神話が醸成されるのは無論そのあとのことだが、それ以前からも土着の信仰や、あるいは公孫氏よりずっと前に大陸からもたらされていた道教信仰などが幾重にも折り重なり習合して、土台となっていたのである。これを公孫氏も調査済みだったし、卑彌呼も(彼女が何者であれ)もちろん熟知していたに違いない。伊都國・奴國の官名に見られる「觚(こ)」字の原義は祭祀に用いる青銅のカップであり、青銅のポットである「爵(しゃく)」とセットで使われるという。それは殷代の話だが、時代が下って「爵」が身分を表したように、「觚」もまた祭祀に携わる官を意味する文字として使用されたのかもしれない。
言うまでもなく、「想像」は裏付けにはならない。ただし条件がそろっていれば蓋然性は否定できない。日之影説の問題は考古学的な裏付けがない点である。仮に発掘しても、「通説」派が期待するような「伊都國」の面影は見つからないかもしれない。ではそこが「伊都國」ではないのかというと、そうも結論付けられない。それならそれで、そういう「伊都國」像があってもよいと柔軟に考える余地が残っている。魏志倭人伝は私たちの想像までは制限しない。だからこそ伊都國を北部九州に持っていこうとする「想像」も許されるのである。逆に「通説」の問題は末盧國からの距離や方位など魏志倭人伝の記述と合致しないという意味で文献学的な裏付けがない点であり、裏付けがないところを「想像」によって補填しているという意味ではイーブンであろう。そのような土地を倭人伝に載る地名に因んで「伊都國」と名付けるのは便宜であり、ロマンであって、結論ではない。
伊都國=日之影説の蓋然性を指摘したうえで、日之影説に期待を寄せる方々のためにもう一歩踏み込ませていただこう。日之影にも遺跡がないわけではない。大字七折(ななおれ)の最大標高差12mという丘陵斜面で町営グラウンド造成に伴い見つかった「平底遺跡(ひらそこいせき)」の報告書を、平成15年に日之影町教育委員会がまとめた(『日之影町教育委員会 発掘調査報告書 第1集 平底遺跡 町営「水と緑の夢空間事業」に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』2003、奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」よりダウンロード可能http://
報告書によると、五ヶ瀬川にそそぐ長谷川の西岸斜面に位置するこの遺跡は、縄文時代晩期から弥生時代を経て古墳時代中頃までの息の長い遺跡で、住居跡や石器・土器とわずかな鉄器が発掘されている。日之影町・高千穂町・五ヶ瀬町からなる西臼杵郡では最大規模の遺跡であるという。それまでに日之影町で発掘された遺跡は決して少なくないが、古墳時代まで続く遺跡はここが初めて。
発掘された「工字突帯文土器」などの土器については弥生時代後期から終末期にかけてのものと考えられ、宮崎県北部平野部や大分県とのつながりが指摘される。五世紀中頃の古墳時代の遺構からは松山産の須恵器が出土している。また、平底遺跡にはなかったが、日之影町内の別の遺跡からは「安国寺式土器」という、国東地方の土器がわずかに出ている。日之影が延岡や大分を経て瀬戸内海地域と交流していた様子がうかがわれる。おそらく、これらの地方は北部九州の勢力とは一線を画していたに違いない。
しかしそうなると、今度は中国の公孫氏を匂わせる遺物が出ていないことの意味を考えなければならなくなる。平底遺跡は古代日本人の暮らしがそこにあったことを示しているが、祭祀だとか権力者だとか聖職者などの存在をそこから想像することは難しい。そうした要素は存在しなかったのか、まだ発掘されていないだけなのか、ある時期に根こそぎ消え去ったのか、まったく謎である。ただ後世、高千穂に神話と伝説だけが語られるようになった。名こそ流れてなのである。
※写真はグーグルマップのストリートビューより、平底遺跡が発掘された現「癒しの森運動公園」付近。日之影町の雄大な景色に、静かな神々しさも感じられませんか。
|
|
|
|
コメント(2)
「考察からの私感」
「東南陸行五百里」は、末盧国が呼子だとしたら、伊都国は吉野ヶ里ということも考えられます。地図を確認すると新たな発見がありました。唐津街道の存在です。江戸時代に整備されたとはいえ、山間の貴重な道だったと想像出来るからです。五百里が問題になりますが、方向や遺跡の情況から見れば、吉野ヶ里が伊都国であるとしてもおかしくはありません。ちなみに、呼子から吉野ヶ里遺跡までは直線距離で、51.1kmです。短里とすれば、納得のいく距離なのです。岩元学説の疑問点である、なぜ「至」を魏の史官が「到」に書換えたか。伊都国王は、帥升の末裔だと言う事を認識していたからです。魏としては、卑弥呼は始めて朝貢してきた倭人でした。だからそれだけ書けばよいのですが、公孫氏と倭人との関係は、卑弥呼ではなく、伊都国王だからです。この後に書かれる後漢書の記述のなかに登場する倭国王帥升の存在をどうするかで、わざと脇道ルートを使い、それとなく登場させているのです。つまり、公孫氏は伊都国までを正規なルートと考えていたのです。だから「至」字を使用したのです。107年に帥升が朝貢し、その後3代ほど続いた王は、倭国大乱で衰退し、173年に女王に即位した卑弥呼により、息を吹き返すのです。伊都国は卑弥呼の生誕地でもあると思います。伊都国は173年に女王国になりました。だから倭人伝には突如として女王国が出てくるのです。公孫氏は帯方郡経営(204年帯方郡設置それ以降から派遣していたか)と平行して、魏と呉に対してのデマゴギーの一環として、伊都国(女王国)に帯方郡の役人を派遣するようになります。それが常駐化(228年公孫淵が燕を建国した頃)していきました。一時的に卑弥呼は伊都国(女王国)を放棄し、公孫氏が支配下に置いたと考えます。卑弥呼は、邪馬台国(親戚)を頼り、一時期、畿内か九州の別の地にいたのだと思います。そして238年公孫氏が司馬懿に滅ぼされたのを知ると、九州の奴国に遷都し、女王国国邑郡の再編をします。すぐに帯方郡に使者を出し、魏に朝貢するのです。魏の史官は「到」字を使用したのです。
「東南陸行五百里」は、末盧国が呼子だとしたら、伊都国は吉野ヶ里ということも考えられます。地図を確認すると新たな発見がありました。唐津街道の存在です。江戸時代に整備されたとはいえ、山間の貴重な道だったと想像出来るからです。五百里が問題になりますが、方向や遺跡の情況から見れば、吉野ヶ里が伊都国であるとしてもおかしくはありません。ちなみに、呼子から吉野ヶ里遺跡までは直線距離で、51.1kmです。短里とすれば、納得のいく距離なのです。岩元学説の疑問点である、なぜ「至」を魏の史官が「到」に書換えたか。伊都国王は、帥升の末裔だと言う事を認識していたからです。魏としては、卑弥呼は始めて朝貢してきた倭人でした。だからそれだけ書けばよいのですが、公孫氏と倭人との関係は、卑弥呼ではなく、伊都国王だからです。この後に書かれる後漢書の記述のなかに登場する倭国王帥升の存在をどうするかで、わざと脇道ルートを使い、それとなく登場させているのです。つまり、公孫氏は伊都国までを正規なルートと考えていたのです。だから「至」字を使用したのです。107年に帥升が朝貢し、その後3代ほど続いた王は、倭国大乱で衰退し、173年に女王に即位した卑弥呼により、息を吹き返すのです。伊都国は卑弥呼の生誕地でもあると思います。伊都国は173年に女王国になりました。だから倭人伝には突如として女王国が出てくるのです。公孫氏は帯方郡経営(204年帯方郡設置それ以降から派遣していたか)と平行して、魏と呉に対してのデマゴギーの一環として、伊都国(女王国)に帯方郡の役人を派遣するようになります。それが常駐化(228年公孫淵が燕を建国した頃)していきました。一時的に卑弥呼は伊都国(女王国)を放棄し、公孫氏が支配下に置いたと考えます。卑弥呼は、邪馬台国(親戚)を頼り、一時期、畿内か九州の別の地にいたのだと思います。そして238年公孫氏が司馬懿に滅ぼされたのを知ると、九州の奴国に遷都し、女王国国邑郡の再編をします。すぐに帯方郡に使者を出し、魏に朝貢するのです。魏の史官は「到」字を使用したのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
真説魏志倭人伝研究会メンバーズ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-