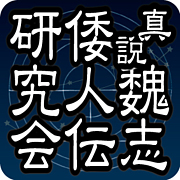|
|
|
|
コメント(1)
後漢の許慎がまとめた部首別漢字字典、『説文解字(せつもんかいじ)』。現在の漢字解釈は18世紀の清代に成る『康熙字典』をもとにしていますが、より漢字の出現期に近い時代(といっても漢字出現期を3300年前とすると、それより1400年も後の時代)に書かれた『説文解字』には、現代人の知らない、あるいは忘れてしまった深い含蓄があります。また、『説文解字』解釈の最高峰と言われる清の段玉裁による『説文解字注』は、難解な『説文解字』を現代の私たちにもなんとか分かりやすく伝える中継所として、なくてはならない手引きです。
『説文解字』 は呼んで字の如く「文を説き、字を解く」という意味です。私たちは「文字」という言葉でひとくくりに考えていますが、そもそも「文」と「字」との端的な違いは何かというと、「文」は絵画的な、すなわち象徴としての文字、「字」は記号や符号としての文字という考え方ができます。語弊を恐れずに言うならば、「文」はアナログ、「字」はデジタルと言い換えてもよいでしょう。
私たちは漢字が一種の象形文字であり、それが「読み」と「意味」を持っているということを知っています。そのことを「文」と「字」という二字が語っているのです。が、『説文解字』を眺めていると、それよりももっと深い意味がこめられていると感じます。
それは特に「文」のほうに感じることができます。漢字の絵画的な要素とは、具象的なイメージだけでなく抽象的なイメージでもあり、その「文」が成立する過程で洗練されていった思想であり世界観にほかなりません。私たち、とくに日本人は一般に、漢字というものを「字」として考えています。それはつまり、「義(意味)」と「音(読みかた)」を併せ持つ記号としての、つまり表音表意文字としての漢字です。しかし古代中国の人々が考えた深遠な成立背景を持つ「文」としての要素を併せて考えたときには、はっとさせられます。この点、他の言語の文字にはない深さが漢字にはあります。アルファベットや仮名は何年たっても変わりませんが、表意文字である漢字は変化することを宿命づけられているかのようです。
日本人が訓読みを発明したことは、多くの人が「離れ業」と評しています。それを世界に類を見ない日本の漫画文化の隆盛と結びつけて考える人もいます。つまり、日本人は絵に言葉をつけて読むという技術に長けているというのです。この考えは多くの人が認めるところかもしれません。
しかしそれと同時に、この技術には盲点があるのではないかと、『説文解字』 を眺めながら思うときがあります。漢字を「絵」として捉えることができて、そこの「意味」と「読み」を読み取ることができるとしても、それだけが漢字の全てではないと感じるからです。私たちの多くは漢字の要素として「意味」と「読み」を挙げることができます。しかし私はこの二つの要素に、もう一つ、「物語」という要素を付け加えたい。言い換えると「思想」とか「思い」とか「哲学」とか、あるいは「苦心」とか「工夫」とか「ドラマ」と言ってもいい。つまり「説文」の「文」の持つ背景思想の要素のことです。
これが何故重要なのかというと、単に現代人に忘れ去られているという理由だけではありません。 中国だけでなく日本でも書かれた著名な古代漢籍を解読していく上で、この忘れ去られた背景思想が、実はとても重要な、そして古代人にとっては常識的な主要素として、一つ一つの文字に込められていたのではないか、そしてそれが一種のコードとして前後の文脈と有機的に関連を持ちながら働いていたのではないか、という気がしてならないからです。
漢字は一種の化学物質のようなものです。それも非常に単純な構造の無機物から、複雑な構造を持つ有機化合物のようなものまであります。前後の物質とつながりをもつとき、まったく影響しないこともあれば、例えばDNAのような物質がタンパク質を合成するかのような複雑かつ神秘的なメカニズムで影響しあうこともあるのではないでしょうか。
『説文解字』 は呼んで字の如く「文を説き、字を解く」という意味です。私たちは「文字」という言葉でひとくくりに考えていますが、そもそも「文」と「字」との端的な違いは何かというと、「文」は絵画的な、すなわち象徴としての文字、「字」は記号や符号としての文字という考え方ができます。語弊を恐れずに言うならば、「文」はアナログ、「字」はデジタルと言い換えてもよいでしょう。
私たちは漢字が一種の象形文字であり、それが「読み」と「意味」を持っているということを知っています。そのことを「文」と「字」という二字が語っているのです。が、『説文解字』を眺めていると、それよりももっと深い意味がこめられていると感じます。
それは特に「文」のほうに感じることができます。漢字の絵画的な要素とは、具象的なイメージだけでなく抽象的なイメージでもあり、その「文」が成立する過程で洗練されていった思想であり世界観にほかなりません。私たち、とくに日本人は一般に、漢字というものを「字」として考えています。それはつまり、「義(意味)」と「音(読みかた)」を併せ持つ記号としての、つまり表音表意文字としての漢字です。しかし古代中国の人々が考えた深遠な成立背景を持つ「文」としての要素を併せて考えたときには、はっとさせられます。この点、他の言語の文字にはない深さが漢字にはあります。アルファベットや仮名は何年たっても変わりませんが、表意文字である漢字は変化することを宿命づけられているかのようです。
日本人が訓読みを発明したことは、多くの人が「離れ業」と評しています。それを世界に類を見ない日本の漫画文化の隆盛と結びつけて考える人もいます。つまり、日本人は絵に言葉をつけて読むという技術に長けているというのです。この考えは多くの人が認めるところかもしれません。
しかしそれと同時に、この技術には盲点があるのではないかと、『説文解字』 を眺めながら思うときがあります。漢字を「絵」として捉えることができて、そこの「意味」と「読み」を読み取ることができるとしても、それだけが漢字の全てではないと感じるからです。私たちの多くは漢字の要素として「意味」と「読み」を挙げることができます。しかし私はこの二つの要素に、もう一つ、「物語」という要素を付け加えたい。言い換えると「思想」とか「思い」とか「哲学」とか、あるいは「苦心」とか「工夫」とか「ドラマ」と言ってもいい。つまり「説文」の「文」の持つ背景思想の要素のことです。
これが何故重要なのかというと、単に現代人に忘れ去られているという理由だけではありません。 中国だけでなく日本でも書かれた著名な古代漢籍を解読していく上で、この忘れ去られた背景思想が、実はとても重要な、そして古代人にとっては常識的な主要素として、一つ一つの文字に込められていたのではないか、そしてそれが一種のコードとして前後の文脈と有機的に関連を持ちながら働いていたのではないか、という気がしてならないからです。
漢字は一種の化学物質のようなものです。それも非常に単純な構造の無機物から、複雑な構造を持つ有機化合物のようなものまであります。前後の物質とつながりをもつとき、まったく影響しないこともあれば、例えばDNAのような物質がタンパク質を合成するかのような複雑かつ神秘的なメカニズムで影響しあうこともあるのではないでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
真説魏志倭人伝研究会メンバーズ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
真説魏志倭人伝研究会メンバーズのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人