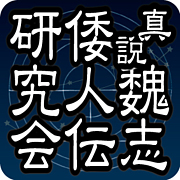|
|
|
|
コメント(37)
マイナーなこと 2
大陸と倭国との通行に関し、次のような記述があります。
其行來渡海詣中國恒使一人不梳頭不去蟣蝨衣服垢汚不食肉不近婦人如喪人名之爲持衰
汚ねーな、不近婦人は当たり前だろう、とは思いますが、なんとこの渡海は”詣中國”なんですね。
”中國”ってどう読むのでしょう。 チュウゴクではないでしょうね。 ナカツクニと読むのでしょうか。
中華人民共和国、あるいは中華民国ではないことは明白です。
陳 寿は太原の国々を”中國”と呼んでいたんでしょうかね。 そのこころはなんだったのでしょう。
世界の真ん中に位置する中華の国、ということで中國と呼んだのでしょうか。
魏志倭人伝には問題となるところではないですが、とにかく面白いところです。
大陸と倭国との通行に関し、次のような記述があります。
其行來渡海詣中國恒使一人不梳頭不去蟣蝨衣服垢汚不食肉不近婦人如喪人名之爲持衰
汚ねーな、不近婦人は当たり前だろう、とは思いますが、なんとこの渡海は”詣中國”なんですね。
”中國”ってどう読むのでしょう。 チュウゴクではないでしょうね。 ナカツクニと読むのでしょうか。
中華人民共和国、あるいは中華民国ではないことは明白です。
陳 寿は太原の国々を”中國”と呼んでいたんでしょうかね。 そのこころはなんだったのでしょう。
世界の真ん中に位置する中華の国、ということで中國と呼んだのでしょうか。
魏志倭人伝には問題となるところではないですが、とにかく面白いところです。
先日、新聞に天皇制の「謎」について書かれていたので、紹介します。
「万世一系」?血縁どこまで
祭祀司り、特別な存在に
歴史の中の天皇
「万世一系」という言葉がある。天皇家の血筋が連綿と続いてきたことを示す文脈で使われる事が多い。実際、「日本書紀」」などを読む限り、神武天皇や続く「欠史八代」などを除けば、古代からの天皇家が、血縁に基づき王位や皇位を世襲で継承してきたことは疑いがないように見える。
実力主義だった?
だが国立歴史民俗博物館の仁藤敦史教授(日本古代史)は「6世紀以前の王位はむしろ、実力・能力主義で決められていたのでは」と考えている。それを示唆するのが「倭の五王」だ。中国の歴史書に出てくる、5世紀の日本列島を治めたとされる讃、珍、済、興、武の5人の王のことで、自ら甲冑を身につけ、山河を駆け巡って東西を平らげた・・・などと中国の皇帝あての文書に記したことで知られる。それぞれをどの天皇にあてるか意見が分れるが、済は19代の允恭天皇、興は20代の安康天皇、武は21代の雄略天皇とする説が有力だ。「天皇は元々、自然神などを祭る祭祀を司ることで、特別な存在となっていくが、5世紀になると、軍事や外交などの実務に秀でていなければ務まらなくなる。そんな状況下では、親から子への世襲より、広い意味での血縁・婚姻関係の中で優れた能力を持った人物が王位に就いていた可能性が高い」と仁藤さん。仁藤さんによると、聖徳太子の伝記「上宮聖徳法王帝説」には、29代の「欽明以降の5代は、他人を雑えず天下を治めた」との記述があり、「そのまま読めば、それ以前の天皇は血縁関係になかったということになる。6世紀以前は世襲第一ではなかったと思う」にもかかわらず、日本書紀などで天皇がすべて世襲であるように記されたのは、それらが編纂された8世紀に、中国から、男系での皇位世襲を重視する思想が入ってきていたからで、「それに従う形で歴史が改変された結果」とみる。一方、このような考え方には反論もある。たとえば、堺女子短期大学の水谷千秋教授(日本古代史)は「少なくとも5世紀頃からは、基本的に古事記や日本書紀の記述は信用できる」との立場だ。ただし、ここで問題になるのが、26代の継体天皇である。書紀などによると、25代の武烈天皇が506年に跡継ぎを決めずに死去したため、15代の応神天皇から5代離れた男大迹王が越前(今の福井)から迎えられ、王位に就いたという。
王朝交代の危機は
これに対して、古代史学者の水野祐氏が戦後に唱えたのが、「三王朝交代説」だ。継体天皇は王位を奪い取った人物で、10代の崇神天皇や15代の応神天皇に始まる前代の王朝とは血が繋がっていないと説いた。この水野説については、根拠とした「古事記」の真福寺本の書き入れの資料性に問題が指摘されたこともあり、現在、学界では有力視されていない。水谷さんも「5代離れた傍系の有力王族という解釈でいいのではないか」と話す。では、日本では、血筋以外の人物が王位に就く危機はなかったのだろうか。水谷さんが「古代で可能性が極めて高かった」と考えるのが、35代皇極天皇に仕えた蘇我入鹿(?〜645)と46代孝謙天皇(48代称徳天皇)に重用された僧・道鏡(?〜772)だ。「入鹿は皇位継承さえ左右した権力者であり、自らも政治の表に出ようとする傾向があった。乙巳の変で暗殺されなかったら、将来的には天皇の位に就いていたのではないか」また道鏡については、「孝謙天皇は疫病や相次ぐ天災を自らに徳がないのが原因と憂え、その救いを仏教に求めた父の聖武天皇(45代)の影響を強く受けていた。僧である道鏡に国を委ねることで、『天命』を更新し、仏教によって国を立て直していこうとした可能性が高い」と推測する。一方、仁藤さんは「日本では藤原氏なども基本的に王位を奪うのではなく『第一の臣下』のポジションを志向してきた」と話す。「天皇がすべてのセンターで他の貴族の貴種性もすべて天皇家に依拠している。このため、取って代わるという事が起きにくかった」歴史をひもとくと、天皇家の権威の源は元々、祭祀にあり、それを司ってきたからこそ、人々の尊敬を集め、血筋が続いてきたことがわかる。天皇陛下が私事として行っている「宮中祭祀」もその伝統を引き継いでいるといえるだろう。
「謎」。真実は如何に。想像する。イメージするしかない。「天皇」に関わること研究が進むことに期待です。
「万世一系」?血縁どこまで
祭祀司り、特別な存在に
歴史の中の天皇
「万世一系」という言葉がある。天皇家の血筋が連綿と続いてきたことを示す文脈で使われる事が多い。実際、「日本書紀」」などを読む限り、神武天皇や続く「欠史八代」などを除けば、古代からの天皇家が、血縁に基づき王位や皇位を世襲で継承してきたことは疑いがないように見える。
実力主義だった?
だが国立歴史民俗博物館の仁藤敦史教授(日本古代史)は「6世紀以前の王位はむしろ、実力・能力主義で決められていたのでは」と考えている。それを示唆するのが「倭の五王」だ。中国の歴史書に出てくる、5世紀の日本列島を治めたとされる讃、珍、済、興、武の5人の王のことで、自ら甲冑を身につけ、山河を駆け巡って東西を平らげた・・・などと中国の皇帝あての文書に記したことで知られる。それぞれをどの天皇にあてるか意見が分れるが、済は19代の允恭天皇、興は20代の安康天皇、武は21代の雄略天皇とする説が有力だ。「天皇は元々、自然神などを祭る祭祀を司ることで、特別な存在となっていくが、5世紀になると、軍事や外交などの実務に秀でていなければ務まらなくなる。そんな状況下では、親から子への世襲より、広い意味での血縁・婚姻関係の中で優れた能力を持った人物が王位に就いていた可能性が高い」と仁藤さん。仁藤さんによると、聖徳太子の伝記「上宮聖徳法王帝説」には、29代の「欽明以降の5代は、他人を雑えず天下を治めた」との記述があり、「そのまま読めば、それ以前の天皇は血縁関係になかったということになる。6世紀以前は世襲第一ではなかったと思う」にもかかわらず、日本書紀などで天皇がすべて世襲であるように記されたのは、それらが編纂された8世紀に、中国から、男系での皇位世襲を重視する思想が入ってきていたからで、「それに従う形で歴史が改変された結果」とみる。一方、このような考え方には反論もある。たとえば、堺女子短期大学の水谷千秋教授(日本古代史)は「少なくとも5世紀頃からは、基本的に古事記や日本書紀の記述は信用できる」との立場だ。ただし、ここで問題になるのが、26代の継体天皇である。書紀などによると、25代の武烈天皇が506年に跡継ぎを決めずに死去したため、15代の応神天皇から5代離れた男大迹王が越前(今の福井)から迎えられ、王位に就いたという。
王朝交代の危機は
これに対して、古代史学者の水野祐氏が戦後に唱えたのが、「三王朝交代説」だ。継体天皇は王位を奪い取った人物で、10代の崇神天皇や15代の応神天皇に始まる前代の王朝とは血が繋がっていないと説いた。この水野説については、根拠とした「古事記」の真福寺本の書き入れの資料性に問題が指摘されたこともあり、現在、学界では有力視されていない。水谷さんも「5代離れた傍系の有力王族という解釈でいいのではないか」と話す。では、日本では、血筋以外の人物が王位に就く危機はなかったのだろうか。水谷さんが「古代で可能性が極めて高かった」と考えるのが、35代皇極天皇に仕えた蘇我入鹿(?〜645)と46代孝謙天皇(48代称徳天皇)に重用された僧・道鏡(?〜772)だ。「入鹿は皇位継承さえ左右した権力者であり、自らも政治の表に出ようとする傾向があった。乙巳の変で暗殺されなかったら、将来的には天皇の位に就いていたのではないか」また道鏡については、「孝謙天皇は疫病や相次ぐ天災を自らに徳がないのが原因と憂え、その救いを仏教に求めた父の聖武天皇(45代)の影響を強く受けていた。僧である道鏡に国を委ねることで、『天命』を更新し、仏教によって国を立て直していこうとした可能性が高い」と推測する。一方、仁藤さんは「日本では藤原氏なども基本的に王位を奪うのではなく『第一の臣下』のポジションを志向してきた」と話す。「天皇がすべてのセンターで他の貴族の貴種性もすべて天皇家に依拠している。このため、取って代わるという事が起きにくかった」歴史をひもとくと、天皇家の権威の源は元々、祭祀にあり、それを司ってきたからこそ、人々の尊敬を集め、血筋が続いてきたことがわかる。天皇陛下が私事として行っている「宮中祭祀」もその伝統を引き継いでいるといえるだろう。
「謎」。真実は如何に。想像する。イメージするしかない。「天皇」に関わること研究が進むことに期待です。
>>[7]さん
祭り上げている状態が好きなんでしょうね。たぶん。おみこしをかついでいる自分が好き!という人は日本には多いと思います。終戦前まで、天皇を神格化してまで担いだ人たちは、戦後はおみこしを一生懸命担いでいると思います。一部の人は天皇を担ぐかわりに保守的な政治リーダーを勝手に担いでいますが。
もともとおみこしの話ではないのですが、神輿や山車をぶつけあうお祭りというのもあります。神輿の中の神様をたたき起こすためとも言われていますが、どう見ても喧嘩です。どこのおみこしが次のリーダーになるか勝負!ということでしょうか。
信長は始皇帝のようになる一歩手前まで行きましたが、秀吉も家康もある意味ではその理念を日本人らしく変容させて継承したのではないかと思います。天皇制と幕藩体制という聖俗の二重構造は古代(卑彌呼と男弟)からの伝統なのでしょうか。しかし徳川家という世俗の神輿が気に入らなかった薩長は思わず討幕してしまいました。どっちが日本人らしいのか、非常に難しいです。
祭り上げている状態が好きなんでしょうね。たぶん。おみこしをかついでいる自分が好き!という人は日本には多いと思います。終戦前まで、天皇を神格化してまで担いだ人たちは、戦後はおみこしを一生懸命担いでいると思います。一部の人は天皇を担ぐかわりに保守的な政治リーダーを勝手に担いでいますが。
もともとおみこしの話ではないのですが、神輿や山車をぶつけあうお祭りというのもあります。神輿の中の神様をたたき起こすためとも言われていますが、どう見ても喧嘩です。どこのおみこしが次のリーダーになるか勝負!ということでしょうか。
信長は始皇帝のようになる一歩手前まで行きましたが、秀吉も家康もある意味ではその理念を日本人らしく変容させて継承したのではないかと思います。天皇制と幕藩体制という聖俗の二重構造は古代(卑彌呼と男弟)からの伝統なのでしょうか。しかし徳川家という世俗の神輿が気に入らなかった薩長は思わず討幕してしまいました。どっちが日本人らしいのか、非常に難しいです。
天皇皇后両陛下が日高市の高麗神社と巾着田へご旅行! その後、ありがたいことに私の郷里熊谷市にて一泊中。明日は深谷へ行幸。
北朝鮮をとりまく国際情勢が緊迫し、トランプ大統領が金正恩をロケットマンと呼び、国連でならず者呼ばわりしている、このタイミングでの高麗神社参詣。
今でも北朝鮮の最大の仮想敵国は中国ですが、かつて高句麗が大唐帝国に滅ぼされ、日本に逃れてきた一部の王族と難民を住まわせたのが始まりとされる高麗郡。陛下の「私的」旅行を政治的に解釈するのは野暮ってもんですが、高句麗の文化である拉致や恫喝は問題ありとはいえ、歴史的には北朝鮮と日本が複雑で深い関わりをもった民族同士であるというゆかりがあるのは事実で、トランプのような表面的な軽率な言動とはまるで次元の違う行動に感じます。いろいろな問題がありますが、落ち着いて歴史を見つめ、互いの歴史や、共に歩んだ歴史を振り返り、先人達の労苦に思いをいたしましょう、というお考えなのかどうかは察するべくもありませんが、陛下の人柄とウィットを感じます。
どうせ野暮なら、せめてそうした北朝鮮がらみの解釈をするべきだと思いますが、朝日や毎日、東京新聞などの報道を見ると、何故か陛下が01年に桓武天皇の生母が百済の血筋であることに「韓国」とのゆかりを感じると発言したことなどを挙げ、あくまでも日韓関係に結びつけて今回の旅行を論じているのです。これが本当の野暮というものでしょう。歴史に対する無知というより、独善や扇動に近いと思います。陛下が高麗神社に行かれたから日韓で仲良くしましょう、とでも言いたいのでしょうか。あるいは北朝鮮に対する国民の認識が改善する芽を摘んでおこうとでもいうのでしょうか。どうも不思議です。
北朝鮮をとりまく国際情勢が緊迫し、トランプ大統領が金正恩をロケットマンと呼び、国連でならず者呼ばわりしている、このタイミングでの高麗神社参詣。
今でも北朝鮮の最大の仮想敵国は中国ですが、かつて高句麗が大唐帝国に滅ぼされ、日本に逃れてきた一部の王族と難民を住まわせたのが始まりとされる高麗郡。陛下の「私的」旅行を政治的に解釈するのは野暮ってもんですが、高句麗の文化である拉致や恫喝は問題ありとはいえ、歴史的には北朝鮮と日本が複雑で深い関わりをもった民族同士であるというゆかりがあるのは事実で、トランプのような表面的な軽率な言動とはまるで次元の違う行動に感じます。いろいろな問題がありますが、落ち着いて歴史を見つめ、互いの歴史や、共に歩んだ歴史を振り返り、先人達の労苦に思いをいたしましょう、というお考えなのかどうかは察するべくもありませんが、陛下の人柄とウィットを感じます。
どうせ野暮なら、せめてそうした北朝鮮がらみの解釈をするべきだと思いますが、朝日や毎日、東京新聞などの報道を見ると、何故か陛下が01年に桓武天皇の生母が百済の血筋であることに「韓国」とのゆかりを感じると発言したことなどを挙げ、あくまでも日韓関係に結びつけて今回の旅行を論じているのです。これが本当の野暮というものでしょう。歴史に対する無知というより、独善や扇動に近いと思います。陛下が高麗神社に行かれたから日韓で仲良くしましょう、とでも言いたいのでしょうか。あるいは北朝鮮に対する国民の認識が改善する芽を摘んでおこうとでもいうのでしょうか。どうも不思議です。
全邪馬連・東京地区の講演会に行ってきました(平成29年9月24日)。
用事があったため、1つめの小林敏男先生(大東文化大学名誉教授)のほうだけ聴講。
陳寿は「女王国」(普通名詞)を「邪馬台國」(固有名詞)に想定したものの、それは複数の元史料を参照したことによる混乱であるとし、「女王国」と「邪馬台國」は本来別の概念であったとのご指摘でした。投馬國や邪馬台國の叙述ぶりが他の伊都國系(女王国系)のそれと違うのは、別の伝承(伝聞)によったためということです。この違いは、筑後と畿内にそれぞれ「ヤマト」国があったことに由来しているようです。
また、小林先生の行程叙述解釈では、陳寿は「直線式」に書いているとのことでした。その直線の及ぶ範囲には伊都國や奴國・不彌國だけでなく、投馬國や邪馬台國まで含まれるとの考えです。漢字学的な根拠はわかりませんが、『梁書』倭伝の「又……。又……。」という書き方を「直線式」の書き方だと捉えているようです。では古代漢籍において「放射線式」に記述をしたい場合、そのような書き方はあるのか、どのような書き方になるのか、それを質問したかったのですが時間がなく断念しました。
それから、「水行」語の意味するところは陸伝いでの(船による)移動であって、「渡海」語と対照的な言葉であるとの認識でした。
投馬國や邪馬台國の叙述が伊都國系とは別系統の伝承であるとして、もしそうであるならば投馬國と邪馬台國への行程(所要日数)の起点が、それぞれ不彌國だの投馬國だのというふうに直線式につなげる必要がないのではないかと思い、これも質問したかったのですが、断念。個人的にはすべてを直線式におさめるのは無理だと思っています。
用事があったため、1つめの小林敏男先生(大東文化大学名誉教授)のほうだけ聴講。
陳寿は「女王国」(普通名詞)を「邪馬台國」(固有名詞)に想定したものの、それは複数の元史料を参照したことによる混乱であるとし、「女王国」と「邪馬台國」は本来別の概念であったとのご指摘でした。投馬國や邪馬台國の叙述ぶりが他の伊都國系(女王国系)のそれと違うのは、別の伝承(伝聞)によったためということです。この違いは、筑後と畿内にそれぞれ「ヤマト」国があったことに由来しているようです。
また、小林先生の行程叙述解釈では、陳寿は「直線式」に書いているとのことでした。その直線の及ぶ範囲には伊都國や奴國・不彌國だけでなく、投馬國や邪馬台國まで含まれるとの考えです。漢字学的な根拠はわかりませんが、『梁書』倭伝の「又……。又……。」という書き方を「直線式」の書き方だと捉えているようです。では古代漢籍において「放射線式」に記述をしたい場合、そのような書き方はあるのか、どのような書き方になるのか、それを質問したかったのですが時間がなく断念しました。
それから、「水行」語の意味するところは陸伝いでの(船による)移動であって、「渡海」語と対照的な言葉であるとの認識でした。
投馬國や邪馬台國の叙述が伊都國系とは別系統の伝承であるとして、もしそうであるならば投馬國と邪馬台國への行程(所要日数)の起点が、それぞれ不彌國だの投馬國だのというふうに直線式につなげる必要がないのではないかと思い、これも質問したかったのですが、断念。個人的にはすべてを直線式におさめるのは無理だと思っています。
認証ありがとうございました。よくわかりませんが、ためしにコメント致します。。。
おっしゃる通りです。高麗神社と韓国を結びつけるメディアには辟易しますね。“フェイク・ニュース!”で決まりです。
もうひとつ。北の敵は中国とは、守山さん、流石です。そうすると、敵の敵は味方ということで、日本と北は手が組めます。これが独自外交というもので、オリジナリティなくして日本の外交力は出てきません。ひとりぼっちのトランプおじさんとのお友達外交に頼っていては、どちらかいなくなったら、今はやりの“リセット”になってしまいます。
さて独自外交で “黒電話”氏に何を言うかというと、「核を使うなら満州に向けなさい。福島原発事故でまっ先に逃げ出したのが中国人労働者たちだから、水爆とまではいかなくても、ちょこっと脅せば、みんないなくなりますよ。南を相手に“高麗連邦”を夢見なくとも、高句麗の故郷を回復できます」と。さぁ、どうでしょう。
おっしゃる通りです。高麗神社と韓国を結びつけるメディアには辟易しますね。“フェイク・ニュース!”で決まりです。
もうひとつ。北の敵は中国とは、守山さん、流石です。そうすると、敵の敵は味方ということで、日本と北は手が組めます。これが独自外交というもので、オリジナリティなくして日本の外交力は出てきません。ひとりぼっちのトランプおじさんとのお友達外交に頼っていては、どちらかいなくなったら、今はやりの“リセット”になってしまいます。
さて独自外交で “黒電話”氏に何を言うかというと、「核を使うなら満州に向けなさい。福島原発事故でまっ先に逃げ出したのが中国人労働者たちだから、水爆とまではいかなくても、ちょこっと脅せば、みんないなくなりますよ。南を相手に“高麗連邦”を夢見なくとも、高句麗の故郷を回復できます」と。さぁ、どうでしょう。
まさしく、彼らの故郷のひとつは満州ですから、いつでも方向転換しうると思います。中国にしてみればそれが一番コマります。最悪のシナリオは日本が独自外交で北朝鮮と組んでしまうこと。そうならないように中国は適度に北朝鮮を支援し続けなければいけませんし、安易に国連の制裁決議に賛同できないのです。韓国も日本と北朝鮮が結びつかないよう必死です。ときどき人道支援をしておかないといけません。また、アメリカも日本と北朝鮮が独自のパイプを持つことを恐れています。アメリカが公の場で拉致問題に関心を示さずにきたのは、そのせいだと思います。でもトランプはヒートアップしすぎて拉致問題を持ち出しちゃった。うっかり歓迎してしまったのは日本のメディアだけで、海外のフェイクニュースはそのことにほとんど触れていないようです。
それはさておき、埼玉の高麗郡や東京の狛江、神奈川県大磯町高麗など、高句麗や高麗のゆかりの地は日本にいくつもあり、古墳にも高句麗式のものがあったり、特に7世紀の終わり頃からは帰化する人たちが増えたりしたので、8世紀初めの律令国家樹立時代の文化や政治にも影響を与えたことと思います。
高麗を「こま」と読む由来は分かっておらず、これだけでも論文が書けそうです。
それはさておき、埼玉の高麗郡や東京の狛江、神奈川県大磯町高麗など、高句麗や高麗のゆかりの地は日本にいくつもあり、古墳にも高句麗式のものがあったり、特に7世紀の終わり頃からは帰化する人たちが増えたりしたので、8世紀初めの律令国家樹立時代の文化や政治にも影響を与えたことと思います。
高麗を「こま」と読む由来は分かっておらず、これだけでも論文が書けそうです。
米国が戦後ずっと日露交渉を妨害してきたことは明らかです。昨年末の安倍・プーチン会談に際しても「北方領土は日米安保の例外なき範囲内」との報道を最近目にして驚きました。これが本当なら、はなから還ってくる道理はありません。プーチンがあきれて突き放す訳です。
時限を切っても四島には米軍基地は置かない、米軍人は中に入れない程度の日米合意がなければ、まとまらないですね。いまだに交渉が進展してないので、日米お友達関係でも許してもらえないのでしょうか。「ロシアと組んで中国を倒す」のがトランプ=バノンの政策目標だった筈が、よく分からなくなりました。その意味で、対北独自外交も怪しいですね。
それはさておき「高句麗」と「こま」の由来は面白いです。長くなるので、項を改めます。
時限を切っても四島には米軍基地は置かない、米軍人は中に入れない程度の日米合意がなければ、まとまらないですね。いまだに交渉が進展してないので、日米お友達関係でも許してもらえないのでしょうか。「ロシアと組んで中国を倒す」のがトランプ=バノンの政策目標だった筈が、よく分からなくなりました。その意味で、対北独自外交も怪しいですね。
それはさておき「高句麗」と「こま」の由来は面白いです。長くなるので、項を改めます。
なんとなく平成29年の出来事を振り返ってみた中で、今年もたくさんの著名人が世を去ったものだと、寂しい思いがしています。
(敬称略)
藤村俊二
松方弘樹
時天空
鈴木清順
ディック・ブルーナ
ムッシュかまやつ
渡瀬恒彦
大岡信
京唄子
ペギー葉山
渡部昇一
ズビグニュー・ブレジンスキー
ロジャー・ムーア
与謝野馨
大田昌秀
野際陽子
劉暁波
日野原重明
平尾昌晃
羽田孜
(以上11月まで)
さらに今月
海老一染之助
野村沙知代
チャールズ・ジェンキンス
個人的には、おヒョイさんとムッシュですかね。
平成もいよいよ30年を数えるようになり、子供の頃当たり前のように活躍していた昭和のスターが毎年のように亡くなられます。
ご冥福をお祈りします。
(敬称略)
藤村俊二
松方弘樹
時天空
鈴木清順
ディック・ブルーナ
ムッシュかまやつ
渡瀬恒彦
大岡信
京唄子
ペギー葉山
渡部昇一
ズビグニュー・ブレジンスキー
ロジャー・ムーア
与謝野馨
大田昌秀
野際陽子
劉暁波
日野原重明
平尾昌晃
羽田孜
(以上11月まで)
さらに今月
海老一染之助
野村沙知代
チャールズ・ジェンキンス
個人的には、おヒョイさんとムッシュですかね。
平成もいよいよ30年を数えるようになり、子供の頃当たり前のように活躍していた昭和のスターが毎年のように亡くなられます。
ご冥福をお祈りします。
4月14日の国会議事堂前のデモは、主催者発表なるもっとも信用できない数値で3万人とも、「のべ」5万人とも言われていますが、この数値を朝日と毎日がそのまま実数であるかのように見出しにして報道しています。文献批判という考えは全くないようです。
ちなみに警察発表は4000人程度との情報があり、これはこれで把握できた規模のみを言っているものと思われますが、それでも報道値よりは信憑性があります。実際に映像や画像を見ても、何万人もいるようには見えません。
これを踏まえて魏志倭人伝を読んでみましょう!
数値にしても、方位にしても、どれが主催者発表か、「のべ」か、第三者発表か、見極める必要があります。
ちなみに警察発表は4000人程度との情報があり、これはこれで把握できた規模のみを言っているものと思われますが、それでも報道値よりは信憑性があります。実際に映像や画像を見ても、何万人もいるようには見えません。
これを踏まえて魏志倭人伝を読んでみましょう!
数値にしても、方位にしても、どれが主催者発表か、「のべ」か、第三者発表か、見極める必要があります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
真説魏志倭人伝研究会メンバーズ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
真説魏志倭人伝研究会メンバーズのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6478人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19254人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人