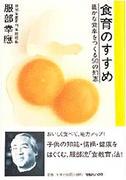思い切ってトピを作成させていただきました。
このたびの地震で、栄養士、コミュの仲間、大切な方、知り合いの方、
患者様が地震に合われ、現在も辛い生活をされていると思います。
そして、皆さまも食品の納入や材料費の高騰、停電や災害時の対応に
苦慮されていることと思います。
今回、日本栄養士会では東北地方太平洋沖地震緊急対策本部をたちあげ、
義援金、寄付金を募っています。
私は中村丁次先生の文章に感銘を受け、わずかではありますが栄養士として
義援金を贈ろうと思います。
何か行動を起こそうと思っているみなさん、ぜひ栄養士として国民へエールを
送りませんか。
詳細は日本栄養士会のホームページをごらんください。
http://
このたびの地震で、栄養士、コミュの仲間、大切な方、知り合いの方、
患者様が地震に合われ、現在も辛い生活をされていると思います。
そして、皆さまも食品の納入や材料費の高騰、停電や災害時の対応に
苦慮されていることと思います。
今回、日本栄養士会では東北地方太平洋沖地震緊急対策本部をたちあげ、
義援金、寄付金を募っています。
私は中村丁次先生の文章に感銘を受け、わずかではありますが栄養士として
義援金を贈ろうと思います。
何か行動を起こそうと思っているみなさん、ぜひ栄養士として国民へエールを
送りませんか。
詳細は日本栄養士会のホームページをごらんください。
http://
|
|
|
|
コメント(46)
茨城県取手市ホームページより
福島県南相馬市避難市民支援ボランティアを募集します。
市と災害協定を結んでいる福島県南相馬市民が市内福祉施設に避難されています。そこで避難されて来られた方たちへの食事を提供できるボランティアグループを募集します。
応募内容
朝・昼・晩の食事を2〜3日連続して作れるボランティアグループ
※1回約40食を予定しています。
活動場所
取手市立「かたらいの郷」(取手市長兵衛新田193−2)
その他
食材及び調理機器は市で用意いたします。
ボランティア保険に加入します。(市が負担)
申し込み先
取手市役所市民活動支援課(0297−74−2141) 内線1172
栄養士としてできること。探せば他にも色々あると思います。
福島県南相馬市避難市民支援ボランティアを募集します。
市と災害協定を結んでいる福島県南相馬市民が市内福祉施設に避難されています。そこで避難されて来られた方たちへの食事を提供できるボランティアグループを募集します。
応募内容
朝・昼・晩の食事を2〜3日連続して作れるボランティアグループ
※1回約40食を予定しています。
活動場所
取手市立「かたらいの郷」(取手市長兵衛新田193−2)
その他
食材及び調理機器は市で用意いたします。
ボランティア保険に加入します。(市が負担)
申し込み先
取手市役所市民活動支援課(0297−74−2141) 内線1172
栄養士としてできること。探せば他にも色々あると思います。
素敵なトピックありがとうございます。
放射能について掲載します。専門職として適切に情報処理し対応しましょうね♪
関係者一同
おつかれさまです。
今日 大阪大学大学院医学部大橋教授に福島原子力事故における放射線被爆時の
妊娠被爆時の妊娠婦人・授乳婦人へのヨウ化カリウム投与(甲状腺がん発症予防)に
ついてを学びました。
日本産婦人科学会
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/disasterguideline_20110321.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/association_20110322mhlw.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324mhlw.pdf
放射線の専門家のblog
http://takedanet.com/
福島原発の放射能を理解する
2011年3月19日公開の翻訳バージョン1へのリンク
翻訳された講演スライドのダウンロード
http://ribf.riken.jp/~koji/jishin/zhen_zai.html
野尻美保子(高エネルギー加速器研究機構/東京大学IPMU)
久世正弘(東京工業大学理工学研究科)
前野昌弘(琉球大学理学部)
衛藤稔・石井貴昭・橋本幸士(理化学研究所仁科加速器研究センター)
翻訳の許可をオリジナル作成者よりいただいています。
資料の部分抜き出しによる流布はご遠慮ください.
翻訳者:
メッセージ: 素粒子原子核分野の研究者/院生の皆さん
今回の震災に起因した福島原発の事故について国民の不安が高まっています。チェルノブイリのようになってしまうと思っている人も多いです。
放射線を学び、利用し、国民の税金で物理を研究させてもらっている我々が、持っている知識を周りの人々に伝えるべき時です。
アメリカのBen Monreal教授が非常に良い解説を作ってくれました。もちろん個人的な見解ですが、我々ツイッター物理クラスタの有志はこれに賛同し、このスライドの日本語訳を作りました。能力不足から至らない点もありますが、皆さん、これを参考にして自分の周り(家族、近所、学校など)で国民の不安を少しでも取り除くための「街角紙芝居」に出て頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。
注記(2011年3月20日23:00)
本ホームページのアドレス(http://ribf.riken.jp/~koji/jishin/)を転送してください。
随時更新されておりますのでごらんくださいませ。
今 学びましたのでUPします。 ご参考に♪
放射能について掲載します。専門職として適切に情報処理し対応しましょうね♪
関係者一同
おつかれさまです。
今日 大阪大学大学院医学部大橋教授に福島原子力事故における放射線被爆時の
妊娠被爆時の妊娠婦人・授乳婦人へのヨウ化カリウム投与(甲状腺がん発症予防)に
ついてを学びました。
日本産婦人科学会
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/disasterguideline_20110321.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/association_20110322mhlw.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324mhlw.pdf
放射線の専門家のblog
http://takedanet.com/
福島原発の放射能を理解する
2011年3月19日公開の翻訳バージョン1へのリンク
翻訳された講演スライドのダウンロード
http://ribf.riken.jp/~koji/jishin/zhen_zai.html
野尻美保子(高エネルギー加速器研究機構/東京大学IPMU)
久世正弘(東京工業大学理工学研究科)
前野昌弘(琉球大学理学部)
衛藤稔・石井貴昭・橋本幸士(理化学研究所仁科加速器研究センター)
翻訳の許可をオリジナル作成者よりいただいています。
資料の部分抜き出しによる流布はご遠慮ください.
翻訳者:
メッセージ: 素粒子原子核分野の研究者/院生の皆さん
今回の震災に起因した福島原発の事故について国民の不安が高まっています。チェルノブイリのようになってしまうと思っている人も多いです。
放射線を学び、利用し、国民の税金で物理を研究させてもらっている我々が、持っている知識を周りの人々に伝えるべき時です。
アメリカのBen Monreal教授が非常に良い解説を作ってくれました。もちろん個人的な見解ですが、我々ツイッター物理クラスタの有志はこれに賛同し、このスライドの日本語訳を作りました。能力不足から至らない点もありますが、皆さん、これを参考にして自分の周り(家族、近所、学校など)で国民の不安を少しでも取り除くための「街角紙芝居」に出て頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。
注記(2011年3月20日23:00)
本ホームページのアドレス(http://ribf.riken.jp/~koji/jishin/)を転送してください。
随時更新されておりますのでごらんくださいませ。
今 学びましたのでUPします。 ご参考に♪
栄養士・管理栄養士のみなさまへ
お疲れ様です。
日本栄養士会は 阪神淡路大震災もとても活躍しております。
各所属栄養士会にて情報を処理し対応しております。
わたしは阪神淡路大震災時 大阪の急性期病院主任管理栄養士でした。
休みの日は 日本栄養士会から兵庫県に支援いかせていただきました。
日本栄養士会からの指示を待ち ボランティアいける方職場・家庭など
調整し ご参加いただけると幸いです。
http://www.dietitian.or.jp/eq/index.html
災害支援栄養士・管理栄養士募集
http://www.dietitian.or.jp/eq/110325.html
全国社会福祉協議会
過去の功績
http://www.shakyo.or.jp/saigai/index.htm
大阪市社会福祉協議会
http://www.osaka-sishakyo.jp/
災害時の栄養・食生活に関して
http://hfnet.nih.go.jp/usr/news/110316/saigaiji%20eiyou-110316.pdf
栄養士みんなで 学問を活かせれば幸いです。
白 鳳
お疲れ様です。
日本栄養士会は 阪神淡路大震災もとても活躍しております。
各所属栄養士会にて情報を処理し対応しております。
わたしは阪神淡路大震災時 大阪の急性期病院主任管理栄養士でした。
休みの日は 日本栄養士会から兵庫県に支援いかせていただきました。
日本栄養士会からの指示を待ち ボランティアいける方職場・家庭など
調整し ご参加いただけると幸いです。
http://www.dietitian.or.jp/eq/index.html
災害支援栄養士・管理栄養士募集
http://www.dietitian.or.jp/eq/110325.html
全国社会福祉協議会
過去の功績
http://www.shakyo.or.jp/saigai/index.htm
大阪市社会福祉協議会
http://www.osaka-sishakyo.jp/
災害時の栄養・食生活に関して
http://hfnet.nih.go.jp/usr/news/110316/saigaiji%20eiyou-110316.pdf
栄養士みんなで 学問を活かせれば幸いです。
白 鳳
おはようございます。
● 日本栄養士会からのお知らせ ●
http://www.dietitian.or.jp/eq/index.html
被災地からの管理栄養士・栄養士の声」をお寄せください。
東北地方太平洋沖地震で被災された地域での管理栄養士・栄養士の体験、情報をお寄せください。
?被災地での体験―あの時、私は―
?避難所の食事・栄養問題の解析、解決するための要望、困っていること
?避難所のメニュー記録 等
被災地での活動の参考とさせていただくとともに、一部は、本会ホームページ、「日本栄養士会雑誌」等でご紹介させていただく予定です。
以下にご記入のうえ、E-mail(jda-jimu@dietitian.or.jp)にて、件名を「被災地からの管理栄養士・栄養士の声」とし、添付ファイルでお送りください。
ご協力お願い申し上げます。
被災地への支援・的確にできるように♪
白 鳳
栄養士・管理栄養士がんばろなぁ〜!!!
東日本大震災 医療ボランティア報告会
〜医療現場を中心に〜
阪神淡路大震災の地から私たちに何ができるか。
なかなか行動に移すことができず悩んでいる人も多いと思います。
今回は、AMDAの医療支援で被災地に入った医療従事者の方々の報告を聞いて、特に医療支援から考えるためのヒントを見つけます。
これからボランティアに参加される方、自分で何ができるか考えている方、興味のある方はどなたでもどうぞご参加ください。
日時:2011年4月9日(土) 午前10時半〜12時半(開場午前10時)
場所:ひょうごボランタリープラザ セミナー室
神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー6F
(JR神戸駅徒歩3分) TEL 078-360-8845
定員:70名(先着順)
事前申し込み:不要
参加費:無料
報告者1:桂木聡子さん(AMDA第6次派遣隊釜石市・大槌町)
薬剤師、兵庫医療大学講師、AMDAの活動以外にもJICA研修生や外国人留学生の日本語支援や生活支援もされています。
報告者2:鈴記好博さん(AMDA第4次派遣隊仙台市・第14次派遣隊大槌町 )
医師、北淡診療所、AMDAネパール子ども病院を支援されています。
報告者3:早瀬麻子さん(AMDA第6次派遣隊釜石市・大槌町)
助産師、大阪大学大学院生、AMDAネパール子ども病院での医療ボランティア経験をお持ちです。
主催:医療通訳研究会(MEDINT) お問い合わせはhttp://medint.jp
共催:AMDA兵庫県支部
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
医療通訳士協議会(JAMI)事務局
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘1-2
大阪大学大学院人間科学研究科
グローバル人間科学専攻 国際協力論講座
mailto:jami@hus.osaka-u.ac.jp
http://jami.hus.osaka-u.ac.jp/
FAX: +81-6-6879-8064
お時間のある方報告会いかがでしょうか? 白 鳳
日本栄養士会
避難生活向けリーフレット、災害時の栄養・食生活支援マニュアル
避難生活を送られている方々の食生活の参考としていただくためのリーフレットを、国立健康・栄養研究所と日本栄養士会が作成しました。管理栄養士・栄養士等専門職向けの解説資料と「災害時の栄
栄養・食生活支援マニュアル」も作成しましたので、合わせてご利用ください。
避難生活向けリーフレット・解説資料
栄養・食生活リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」(PDF:198KB)
栄養・食生活リーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:231KB)
衛生管理リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」(PDF:184KB)
衛生管理リーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:198KB)
赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」(PDF:
504KB)
赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:283KB)
ご高齢の方向けリーフレット「あなたの元気がみんなの元気 !!」(PDF:206KB)
ご高齢の方向けリーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:235KB)
災害時の栄養・食生活支援マニュアル
災害時の栄養・食生活支援マニュアル(専門職向け)(PDF:356KB)
マニュアル内の記入シート(word:52KB)
案内チラシ(word:80KB)
http://www.dietitian.or.jp/eq/110408.html
厚生労働省
事務連絡平成23年4月1日地方厚生(支)局医療課 御中
厚生労働省医政局経済課保険局医療課
経腸栄養剤の適正使用に関するお願いについて
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の影響により、経腸栄養剤「エ
ンシュア・リキッド」(250mL 缶入)及び「エンシュア・H」(250mL 缶入)(製
造販売:明治乳業株式会社(4月1日から株式会社明治)、販売:アボット ジ
ャパン株式会社)については同製剤の缶容器を製造・供給する企業の仙台工場
が被災したため、同製剤の製造が一時中断しております。
同社は、現在、製造再開に向けた準備(出荷開始は5月下旬予定)、被災の
影響のなかった「エンシュア・リキッド」(500mL バッグ入)の増産、海外か
らの「エンシュア・H」の輸入・販売を進めております。
また、国内で代替医薬品となる「ラコール配合経腸用液」を製造販売してい
るイーエヌ大塚製薬株式会社においても増産を行っています。
上記のような対応により、遅くとも6月以降は震災前と同じ量が供給されま
すが、4月及び5月は、現時点における在庫(約1ヶ月分)を含めても経腸栄
養剤(医薬品)全体として、最大2割程度分の不足となる状況が想定されてい
ます。このような状況の下、一時的な供給量減少による患者への影響を最小限とす
るため、下記につきご協力をお願いしたく、貴管下の保険医療機関及び保険薬
局への周知をお願いいたします。
記
1.医療機関及び薬局におかれましては、経腸栄養剤(医薬品)の通常時を
上回る在庫の保持を控えていただきたいこと
2.経腸栄養剤については薬事法上の医薬品として承認を得ているものの
ほか、いわゆる医療食としての扱いを受けている類似の製品があります。
在宅療養患者等の場合には、いわゆる医療食への切り換えにより自己
負担が増大することから、当面、経腸栄養剤(医薬品)については、外
科手術後の患者など真に必要な患者への使用を最優先していただきつ
つも、入院患者でいわゆる医療食等を用いた食事療養が可能な患者につ
いては、出来る限り院内での食事療養費で対応していただくこととし、
在宅患者等へ医薬品を優先的に使用することとしていただきたいこと。
3.医療機関及び薬局においては、患者への最適な医療を確保しつつも、当
面、医薬品の長期処方の自粛あるいは分割調剤の考慮など、必要最小限
の最適な処方・調剤を行っていただきたいこと
がんばっぺし 白鳳
避難生活向けリーフレット、災害時の栄養・食生活支援マニュアル
避難生活を送られている方々の食生活の参考としていただくためのリーフレットを、国立健康・栄養研究所と日本栄養士会が作成しました。管理栄養士・栄養士等専門職向けの解説資料と「災害時の栄
栄養・食生活支援マニュアル」も作成しましたので、合わせてご利用ください。
避難生活向けリーフレット・解説資料
栄養・食生活リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」(PDF:198KB)
栄養・食生活リーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:231KB)
衛生管理リーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」(PDF:184KB)
衛生管理リーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:198KB)
赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレット「避難生活を少しでも元気に過ごすために」(PDF:
504KB)
赤ちゃん、妊婦・授乳婦の方向けリーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:283KB)
ご高齢の方向けリーフレット「あなたの元気がみんなの元気 !!」(PDF:206KB)
ご高齢の方向けリーフレットの解説資料(専門職向け)(PDF:235KB)
災害時の栄養・食生活支援マニュアル
災害時の栄養・食生活支援マニュアル(専門職向け)(PDF:356KB)
マニュアル内の記入シート(word:52KB)
案内チラシ(word:80KB)
http://www.dietitian.or.jp/eq/110408.html
厚生労働省
事務連絡平成23年4月1日地方厚生(支)局医療課 御中
厚生労働省医政局経済課保険局医療課
経腸栄養剤の適正使用に関するお願いについて
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の影響により、経腸栄養剤「エ
ンシュア・リキッド」(250mL 缶入)及び「エンシュア・H」(250mL 缶入)(製
造販売:明治乳業株式会社(4月1日から株式会社明治)、販売:アボット ジ
ャパン株式会社)については同製剤の缶容器を製造・供給する企業の仙台工場
が被災したため、同製剤の製造が一時中断しております。
同社は、現在、製造再開に向けた準備(出荷開始は5月下旬予定)、被災の
影響のなかった「エンシュア・リキッド」(500mL バッグ入)の増産、海外か
らの「エンシュア・H」の輸入・販売を進めております。
また、国内で代替医薬品となる「ラコール配合経腸用液」を製造販売してい
るイーエヌ大塚製薬株式会社においても増産を行っています。
上記のような対応により、遅くとも6月以降は震災前と同じ量が供給されま
すが、4月及び5月は、現時点における在庫(約1ヶ月分)を含めても経腸栄
養剤(医薬品)全体として、最大2割程度分の不足となる状況が想定されてい
ます。このような状況の下、一時的な供給量減少による患者への影響を最小限とす
るため、下記につきご協力をお願いしたく、貴管下の保険医療機関及び保険薬
局への周知をお願いいたします。
記
1.医療機関及び薬局におかれましては、経腸栄養剤(医薬品)の通常時を
上回る在庫の保持を控えていただきたいこと
2.経腸栄養剤については薬事法上の医薬品として承認を得ているものの
ほか、いわゆる医療食としての扱いを受けている類似の製品があります。
在宅療養患者等の場合には、いわゆる医療食への切り換えにより自己
負担が増大することから、当面、経腸栄養剤(医薬品)については、外
科手術後の患者など真に必要な患者への使用を最優先していただきつ
つも、入院患者でいわゆる医療食等を用いた食事療養が可能な患者につ
いては、出来る限り院内での食事療養費で対応していただくこととし、
在宅患者等へ医薬品を優先的に使用することとしていただきたいこと。
3.医療機関及び薬局においては、患者への最適な医療を確保しつつも、当
面、医薬品の長期処方の自粛あるいは分割調剤の考慮など、必要最小限
の最適な処方・調剤を行っていただきたいこと
がんばっぺし 白鳳
お疲れ様です。 まだ電波復旧してない地域もある様でやっと mixiご覧
いただけた病院栄養士さん ほんとうに お疲れ様です。
日本栄養士会会長からです。
被災者の栄養状態が心配…「ご飯・パンだけ」続く
2011年4月10日 提供:読売新聞
東日本大震災からまもなく1か月。長引く避難生活で被災者がビタミンなどの必要な栄養を取れない恐れが出てきた。支援に携わる栄養士らは「一刻も早い対策が必要」と訴えている。
日本栄養士会(東京)は、先月13日に緊急対策本部を発足させ、被災地支援ができる栄養士を全国から募った。第1陣として、宮城県気仙沼市に派遣されていた専務理事の迫(さこ)和子さんは「まだおむすびとパンといった炭水化物しか届かない避難所もある」と現状を話す。
阪神大震災時には、1週間程度で、周辺から弁当などが届いたという。しかし、今回は「被災地が広く、避難所が点在して、物流も途絶えている。救援物資のご飯とパンだけの災害初期の食事がこんなに続くのは想定外」と話す。
同会会長で、対策本部長も務める中村丁次(ていじ)さんは、「炭水化物をエネルギーに変えるには、ビタミンB群が欠かせないが、体には数週間しか蓄積できない。肉や野菜などが届かない所では、すでに欠乏に陥っている可能性がある」と心配する。
ビタミンだけでなく、たんぱく質不足が続けば、筋力が落ちる。管理栄養士で同志社女子大教授の小松龍史さんは「体重の減少や体がだるいなど不調が表れている人は、ビタミンやたんぱく質、ミネラルなどの栄養が欠乏している可能性がある」と注意を促す。
特に糖尿病や腎臓病など食事療法が必要な持病がある場合は管理栄養士のアドバイスを受けたい。中村さんによると、減塩しょうゆなどの「病者用食品」が手に入らないか、医療機関などに聞いてみるのも手だという。「糖尿病の人は、少しずつ食べたり、おかずとご飯を一緒に食べたりすれば、血糖値の急上昇を防げるでしょう。塩分制限がある腎臓病の人はみそ汁の量を少なめに」
*********************************
0−157 平成米騒動 阪神淡路と20代に経験したので情報の大切さ
切実に思います。素敵な横の繋がり同じ免許のもん同士仲良くしましょうね!
栄養士がんばっぺし
地域活動食生活改善委員活用すべし。
白 鳳
食いもん屋の底力だしませふ♪
いただけた病院栄養士さん ほんとうに お疲れ様です。
日本栄養士会会長からです。
被災者の栄養状態が心配…「ご飯・パンだけ」続く
2011年4月10日 提供:読売新聞
東日本大震災からまもなく1か月。長引く避難生活で被災者がビタミンなどの必要な栄養を取れない恐れが出てきた。支援に携わる栄養士らは「一刻も早い対策が必要」と訴えている。
日本栄養士会(東京)は、先月13日に緊急対策本部を発足させ、被災地支援ができる栄養士を全国から募った。第1陣として、宮城県気仙沼市に派遣されていた専務理事の迫(さこ)和子さんは「まだおむすびとパンといった炭水化物しか届かない避難所もある」と現状を話す。
阪神大震災時には、1週間程度で、周辺から弁当などが届いたという。しかし、今回は「被災地が広く、避難所が点在して、物流も途絶えている。救援物資のご飯とパンだけの災害初期の食事がこんなに続くのは想定外」と話す。
同会会長で、対策本部長も務める中村丁次(ていじ)さんは、「炭水化物をエネルギーに変えるには、ビタミンB群が欠かせないが、体には数週間しか蓄積できない。肉や野菜などが届かない所では、すでに欠乏に陥っている可能性がある」と心配する。
ビタミンだけでなく、たんぱく質不足が続けば、筋力が落ちる。管理栄養士で同志社女子大教授の小松龍史さんは「体重の減少や体がだるいなど不調が表れている人は、ビタミンやたんぱく質、ミネラルなどの栄養が欠乏している可能性がある」と注意を促す。
特に糖尿病や腎臓病など食事療法が必要な持病がある場合は管理栄養士のアドバイスを受けたい。中村さんによると、減塩しょうゆなどの「病者用食品」が手に入らないか、医療機関などに聞いてみるのも手だという。「糖尿病の人は、少しずつ食べたり、おかずとご飯を一緒に食べたりすれば、血糖値の急上昇を防げるでしょう。塩分制限がある腎臓病の人はみそ汁の量を少なめに」
*********************************
0−157 平成米騒動 阪神淡路と20代に経験したので情報の大切さ
切実に思います。素敵な横の繋がり同じ免許のもん同士仲良くしましょうね!
栄養士がんばっぺし
地域活動食生活改善委員活用すべし。
白 鳳
食いもん屋の底力だしませふ♪
栄養偏る避難所の食事 「慢性病悪化も」と懸念 「日本の試練 現場から」避難所の栄養問題
2011年4月11日 提供:共同通信社
大震災から1カ月となっても東北地方の約10万人が身を寄せる避難所で、入所者の栄養管理が課題となっている。ビタミンやタンパク質が不足し、偏った食事で命をつながなければならない期間が阪神大震災の際よりも長引いており、専門家は「長期化すれば栄養障害や慢性病の悪化にもつながる」と懸念している。
▽「野菜を」
宮城県気仙沼市で約500人が暮らす気仙沼中学校。市が支援物資を振り分け配給した9日の昼食は、カップラーメンとおにぎりだけ。近くの避難所で炊き出されるラーメンをもらいに雨の中、傘を差し列に並ぶ人も。
市職員の三浦直子(みうら・なおこ)さん(44)は「市が配る食事だけでは栄養が偏る。もう少し野菜を取れたらいいんだけど」と表情を曇らせた。
多くの避難所では1日3食が配給されるようになったが、量は少なく、自衛隊やボランティアの炊き出しで補っているのが実情だ。炊き出しも人数の多い避難所に偏りがちで、高齢や病気で列に並べない人もいる。
メニューはどうしても炭水化物が中心に。岩手県宮古市の津軽石小学校で配られたある日の夕食は、ご飯とインスタントラーメン、昼食で残ったパスタ。付け合わせの野菜炒めはほんの少しだった。
▽ビタミン不足
日本栄養士会の迫和子(さこ・かずこ)専務理事は「自治体の配給食はタンパク質が少し取れるくらいで、基本的には炭水化物ばかり。1日で1食分のカロリーしか摂取できていない所もある」と栄養状態の悪さを指摘する。
炭水化物を燃焼させるために必要なビタミンB1。1日の必要量は1ミリグラム程度だが、0・12〜0・4ミリグラムほどしか摂取できない避難所もあった。タンパク質や鉄分も必要量の半分程度だという。
同志社女子大の小松龍史(こまつ・たつし)教授(臨床栄養学)も「1カ月もこういう食事が続くと食欲不振や倦怠(けんたい)感が出て、栄養をとりにくい悪循環に陥る」とさらなる悪化を懸念する。
最も影響を受けやすいのが慢性疾患の患者だ。被災地の救護班に加わった東京都の田口健(たぐち・たけし)被災地調整担当課長によると、避難所を回る医師からは連日「糖尿病や腎臓病患者の食事コントロールが全くできていない」という報告があった。気仙沼市立病院ではすでに、人工透析が必要なレベルまで症状が悪化した腎臓病患者もいるという。
▽改善策
阪神大震災では発生の約3週間後から避難所の食事が順次、より栄養バランスの取れた弁当形式に切り替えられた。しかし、今回は東北地方の広範囲に千カ所以上の避難所が散在。地元の会社も被災し、1日数十万食の弁当提供は困難だ。
宮城県の物資調達担当者は「食中毒だけは起こせないので、時間がかかる県外からの調達も厳しい」と話す。炊き出しの栄養不足を補うため、野菜ジュースや魚肉ソーセージ、乳製品などの提供を国に要請している。
日本栄養士会はスタッフを被災地に派遣し避難住民の食事調査に乗り出した。ビタミン強化米などを導入、栄養状況の改善を進める考えだ。迫専務理事は「まずは高齢者や病人などの弱者が最優先」と対応を急ぐ。
http://www.dietitian.or.jp/eq/index.html
がんばっぺし♪
2011年4月11日 提供:共同通信社
大震災から1カ月となっても東北地方の約10万人が身を寄せる避難所で、入所者の栄養管理が課題となっている。ビタミンやタンパク質が不足し、偏った食事で命をつながなければならない期間が阪神大震災の際よりも長引いており、専門家は「長期化すれば栄養障害や慢性病の悪化にもつながる」と懸念している。
▽「野菜を」
宮城県気仙沼市で約500人が暮らす気仙沼中学校。市が支援物資を振り分け配給した9日の昼食は、カップラーメンとおにぎりだけ。近くの避難所で炊き出されるラーメンをもらいに雨の中、傘を差し列に並ぶ人も。
市職員の三浦直子(みうら・なおこ)さん(44)は「市が配る食事だけでは栄養が偏る。もう少し野菜を取れたらいいんだけど」と表情を曇らせた。
多くの避難所では1日3食が配給されるようになったが、量は少なく、自衛隊やボランティアの炊き出しで補っているのが実情だ。炊き出しも人数の多い避難所に偏りがちで、高齢や病気で列に並べない人もいる。
メニューはどうしても炭水化物が中心に。岩手県宮古市の津軽石小学校で配られたある日の夕食は、ご飯とインスタントラーメン、昼食で残ったパスタ。付け合わせの野菜炒めはほんの少しだった。
▽ビタミン不足
日本栄養士会の迫和子(さこ・かずこ)専務理事は「自治体の配給食はタンパク質が少し取れるくらいで、基本的には炭水化物ばかり。1日で1食分のカロリーしか摂取できていない所もある」と栄養状態の悪さを指摘する。
炭水化物を燃焼させるために必要なビタミンB1。1日の必要量は1ミリグラム程度だが、0・12〜0・4ミリグラムほどしか摂取できない避難所もあった。タンパク質や鉄分も必要量の半分程度だという。
同志社女子大の小松龍史(こまつ・たつし)教授(臨床栄養学)も「1カ月もこういう食事が続くと食欲不振や倦怠(けんたい)感が出て、栄養をとりにくい悪循環に陥る」とさらなる悪化を懸念する。
最も影響を受けやすいのが慢性疾患の患者だ。被災地の救護班に加わった東京都の田口健(たぐち・たけし)被災地調整担当課長によると、避難所を回る医師からは連日「糖尿病や腎臓病患者の食事コントロールが全くできていない」という報告があった。気仙沼市立病院ではすでに、人工透析が必要なレベルまで症状が悪化した腎臓病患者もいるという。
▽改善策
阪神大震災では発生の約3週間後から避難所の食事が順次、より栄養バランスの取れた弁当形式に切り替えられた。しかし、今回は東北地方の広範囲に千カ所以上の避難所が散在。地元の会社も被災し、1日数十万食の弁当提供は困難だ。
宮城県の物資調達担当者は「食中毒だけは起こせないので、時間がかかる県外からの調達も厳しい」と話す。炊き出しの栄養不足を補うため、野菜ジュースや魚肉ソーセージ、乳製品などの提供を国に要請している。
日本栄養士会はスタッフを被災地に派遣し避難住民の食事調査に乗り出した。ビタミン強化米などを導入、栄養状況の改善を進める考えだ。迫専務理事は「まずは高齢者や病人などの弱者が最優先」と対応を急ぐ。
http://www.dietitian.or.jp/eq/index.html
がんばっぺし♪
お疲れ様です。
厚生労働省からです。各現場・立場でご活用くださいませ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015f26.html
○ 共通事項
【被災地の社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣について】
介護職員等が不足している社会福祉施設等に対して、厚生労働省と都道府県等が協力して、介護職員等を派遣する仕組みをつくりました。
・都道府県や関係団体等を通じて、被災地の社会福祉施設等への一時的な派遣に応じていただける介護職員等の皆様を募集しています。(HTML/PDF:197KB)
※ 別添事務連絡で示している〆切後の御応募も可能です。
・介護職員等の派遣を希望する被災地の社会福祉施設等におかれましては、まずは県に御相談下さい。(HTML/PDF:106KB)
【被災地の要援護者の受入れについて】
被災地の社会福祉施設等において避難生活が必要となった要援護者が生じた場合、厚生労働省と都道府県等が協力して、他自治体の社会福祉施設等で要援護者を受け入れる仕組みをつくりました。
・都道府県や関係団体等を通じて、避難生活が必要となった要援護者を受け入れていただける社会福祉施設等を募集しています。
(HTML/PDF:651KB)
※ 別添事務連絡で示している〆切後の御応募も可能です。
・また、他自治体での受入れを希望する要援護者がいらっしゃる被災地の社会福祉施設等におかれましては、まずは県に御相談下さい。(HTML/PDF:145KB)
【社会福祉施設等での受入について】
要援護者(介護が必要な高齢の方、心身に障害がある方等)の方々を、社会福祉施設において定員を超えて受入れを行うことを可能とするとともに、施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう、全国社会福祉協議会を通じて関係各団体に依頼をしています。(HTML/PDF:46KB)
【福祉医療機構の融資について】
社会福祉施設等の早期復旧の支援策として、独立行政法人福祉医療機構において貸付利率等の優遇措置を実施することとなりました。詳細は福祉医療機構ホームページへリンクをご覧ください。
いろんなこと知らないとなぁ〜
厚生労働省からです。各現場・立場でご活用くださいませ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015f26.html
○ 共通事項
【被災地の社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣について】
介護職員等が不足している社会福祉施設等に対して、厚生労働省と都道府県等が協力して、介護職員等を派遣する仕組みをつくりました。
・都道府県や関係団体等を通じて、被災地の社会福祉施設等への一時的な派遣に応じていただける介護職員等の皆様を募集しています。(HTML/PDF:197KB)
※ 別添事務連絡で示している〆切後の御応募も可能です。
・介護職員等の派遣を希望する被災地の社会福祉施設等におかれましては、まずは県に御相談下さい。(HTML/PDF:106KB)
【被災地の要援護者の受入れについて】
被災地の社会福祉施設等において避難生活が必要となった要援護者が生じた場合、厚生労働省と都道府県等が協力して、他自治体の社会福祉施設等で要援護者を受け入れる仕組みをつくりました。
・都道府県や関係団体等を通じて、避難生活が必要となった要援護者を受け入れていただける社会福祉施設等を募集しています。
(HTML/PDF:651KB)
※ 別添事務連絡で示している〆切後の御応募も可能です。
・また、他自治体での受入れを希望する要援護者がいらっしゃる被災地の社会福祉施設等におかれましては、まずは県に御相談下さい。(HTML/PDF:145KB)
【社会福祉施設等での受入について】
要援護者(介護が必要な高齢の方、心身に障害がある方等)の方々を、社会福祉施設において定員を超えて受入れを行うことを可能とするとともに、施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう、全国社会福祉協議会を通じて関係各団体に依頼をしています。(HTML/PDF:46KB)
【福祉医療機構の融資について】
社会福祉施設等の早期復旧の支援策として、独立行政法人福祉医療機構において貸付利率等の優遇措置を実施することとなりました。詳細は福祉医療機構ホームページへリンクをご覧ください。
いろんなこと知らないとなぁ〜
はじめまして。
聞きたいことが沢山あるので、この場所でよいか分かりませんが、よろしくお願いします。
専門の方の意見が聞きたいです。
私は一応、看護師ですが軟食や介護食は詳しくありません。
実は今回の震災で動いている神奈川のNPOの方からの相談です。
支援物資は各地から届いてきているようですが、カップラーメンなどか多く、高齢の方の軟食を作るのに材料が足りず、困っているようです。
エンシュアリキッドも全国的に不足しているようです。
昨日、その方の日記にコメントがあり私なりにはいろいろ考えたのですが、エンシュアの代わりに豆乳はどうでしょうか?
少し糖分は加える必要があるかもとは思いますが…。
また、加える糖分は精製された白砂糖よりも、ミネラルを含み血糖が急激に上がらない黒砂糖やきび砂糖、花見糖などが適しているかと思いますがどうでしょうか?
ちなみに三温糖は精製後カラメル着色のものがほとんどです。
それから、軟食と言っても具体的には刻みとかペースト状とかいろいろあるかと思います。
ちょっと、そのへんがあまり詳しくないので…。
トロミ調整剤は必須だと思いますから、最初は避難所から要らないと言われても、まずは導入するほうがよいと思います。
また、できるだけ低価格で日持ちするもので、全国的に不足していないものが材料でしたら、全国から物資が集まりやすいかと思います。
ゼラチンがあっても、冷やせず固まらなかったら使えないですし。
介護食を作るのに人手や手間が沢山いるようだったら負担だと思います。
寒天は使えないし。
私が思いついたのは、豆乳とクリームコーンの缶詰めやパック、ゼラチン、カットトマト缶、魚の缶詰めくらいでした。
どのようなことでもよいので、教えていただけると有り難いです。
よろしくお願いします。
東日本大震災◇マトリクス情報網
http://m.mixi.jp/view_community.pl?id=5530794&guid=ON&guid=ON>
コミュ仕分けが間に合っていなくて申し訳ないです。
ツイッターアカウント
yuikarinn
坂口結香
yuikarinn@gmail.com
聞きたいことが沢山あるので、この場所でよいか分かりませんが、よろしくお願いします。
専門の方の意見が聞きたいです。
私は一応、看護師ですが軟食や介護食は詳しくありません。
実は今回の震災で動いている神奈川のNPOの方からの相談です。
支援物資は各地から届いてきているようですが、カップラーメンなどか多く、高齢の方の軟食を作るのに材料が足りず、困っているようです。
エンシュアリキッドも全国的に不足しているようです。
昨日、その方の日記にコメントがあり私なりにはいろいろ考えたのですが、エンシュアの代わりに豆乳はどうでしょうか?
少し糖分は加える必要があるかもとは思いますが…。
また、加える糖分は精製された白砂糖よりも、ミネラルを含み血糖が急激に上がらない黒砂糖やきび砂糖、花見糖などが適しているかと思いますがどうでしょうか?
ちなみに三温糖は精製後カラメル着色のものがほとんどです。
それから、軟食と言っても具体的には刻みとかペースト状とかいろいろあるかと思います。
ちょっと、そのへんがあまり詳しくないので…。
トロミ調整剤は必須だと思いますから、最初は避難所から要らないと言われても、まずは導入するほうがよいと思います。
また、できるだけ低価格で日持ちするもので、全国的に不足していないものが材料でしたら、全国から物資が集まりやすいかと思います。
ゼラチンがあっても、冷やせず固まらなかったら使えないですし。
介護食を作るのに人手や手間が沢山いるようだったら負担だと思います。
寒天は使えないし。
私が思いついたのは、豆乳とクリームコーンの缶詰めやパック、ゼラチン、カットトマト缶、魚の缶詰めくらいでした。
どのようなことでもよいので、教えていただけると有り難いです。
よろしくお願いします。
東日本大震災◇マトリクス情報網
http://m.mixi.jp/view_community.pl?id=5530794&guid=ON&guid=ON>
コミュ仕分けが間に合っていなくて申し訳ないです。
ツイッターアカウント
yuikarinn
坂口結香
yuikarinn@gmail.com
家族支える「託老所」 施設流失の陸前高田 在宅介護支援の声も
2011年4月15日 提供:共同通信社
大震災で介護施設を失った高齢者を抱える家族を支援しようと、岩手県陸前高田市は「託老所」を開設した。しかし、20人しか受け入れられない上、要介護度が高い人は対象外。制約の多さに、在宅介護を支援すべきだとの声も出ている。
被災を免れた山間部の市の交流施設を利用して5日にオープンした。福井県勝山市の保健師ら十数人がボランティアで働き、夜勤は4人態勢。休憩室に女性10人、別の一室に男性4人が、1人2畳くらいの広さで雑魚寝している。健康チェックや入浴、屋外での散歩や体操もし、グループホームのようだ。
勝山市の保健師桜井陽子(さくらい・ようこ)さん(48)は「面倒をみられないから、と預けていく家族がほとんど」という。
一方、要介護度の高い高齢者は、在宅に頼るしかなく、家族のストレスが高まる懸念がある。
介護福祉士佐々木祐也(ささき・ゆうや)さん(33)が所長を務める小規模多機能ホームは浸水。高齢者を預かることができなくなり、現在は利用者20人を1日3〜4人順次訪問し、支援物資を届けたり、おむつを交換したりしながら様子をうかがう。
意思表示ができず、とろみがない食事は取れない87歳の母親を夫婦で介護する農業菊池秀樹(きくち・ひでき)さん(64)は、寝たきりの母親のデイサービスを佐々木さんに頼んでいたが、24時間介護に。「年寄り中心の生活に一変した。5月から農作業が始まれば介護ができなくなる」と不安を訴える。夫婦そろっての外出はできなくなり、ささいなことでイライラしてけんかも増えたという。
阪神大震災の避難所や仮設住宅で高齢者を見守ったNPO法人「阪神高齢者・障害者支援ネットワーク」理事長黒田裕子(くろだ・ひろこ)さん(68)は「託老所には限界がある。避難所に加えて在宅介護の支援を充実すべきだ」と強調。「高齢者が体調を悪化させ家族の負担が増えれば、虐待につながる恐れもある」と指摘している。
※託老所
民家などを利用し家庭的な雰囲気の中で柔軟なケアをする小規模事業所。1980年代から草の根的に始まったとされる。デイサービスだけだったり、ショートステイを受け入れたり、グループホームのようだったり、形態はさまざま。介護保険の指定事業所になっているところもあれば、利用料だけで運営しているところもある。「宅老所」としている事業所が多い。
**********************************
さて多角的な栄養支援考えなきゃぁ〜!
2011年4月15日 提供:共同通信社
大震災で介護施設を失った高齢者を抱える家族を支援しようと、岩手県陸前高田市は「託老所」を開設した。しかし、20人しか受け入れられない上、要介護度が高い人は対象外。制約の多さに、在宅介護を支援すべきだとの声も出ている。
被災を免れた山間部の市の交流施設を利用して5日にオープンした。福井県勝山市の保健師ら十数人がボランティアで働き、夜勤は4人態勢。休憩室に女性10人、別の一室に男性4人が、1人2畳くらいの広さで雑魚寝している。健康チェックや入浴、屋外での散歩や体操もし、グループホームのようだ。
勝山市の保健師桜井陽子(さくらい・ようこ)さん(48)は「面倒をみられないから、と預けていく家族がほとんど」という。
一方、要介護度の高い高齢者は、在宅に頼るしかなく、家族のストレスが高まる懸念がある。
介護福祉士佐々木祐也(ささき・ゆうや)さん(33)が所長を務める小規模多機能ホームは浸水。高齢者を預かることができなくなり、現在は利用者20人を1日3〜4人順次訪問し、支援物資を届けたり、おむつを交換したりしながら様子をうかがう。
意思表示ができず、とろみがない食事は取れない87歳の母親を夫婦で介護する農業菊池秀樹(きくち・ひでき)さん(64)は、寝たきりの母親のデイサービスを佐々木さんに頼んでいたが、24時間介護に。「年寄り中心の生活に一変した。5月から農作業が始まれば介護ができなくなる」と不安を訴える。夫婦そろっての外出はできなくなり、ささいなことでイライラしてけんかも増えたという。
阪神大震災の避難所や仮設住宅で高齢者を見守ったNPO法人「阪神高齢者・障害者支援ネットワーク」理事長黒田裕子(くろだ・ひろこ)さん(68)は「託老所には限界がある。避難所に加えて在宅介護の支援を充実すべきだ」と強調。「高齢者が体調を悪化させ家族の負担が増えれば、虐待につながる恐れもある」と指摘している。
※託老所
民家などを利用し家庭的な雰囲気の中で柔軟なケアをする小規模事業所。1980年代から草の根的に始まったとされる。デイサービスだけだったり、ショートステイを受け入れたり、グループホームのようだったり、形態はさまざま。介護保険の指定事業所になっているところもあれば、利用料だけで運営しているところもある。「宅老所」としている事業所が多い。
**********************************
さて多角的な栄養支援考えなきゃぁ〜!
昨年修行させていただいたジャパンプラットフォームと連携とれそうです。
http://www.japanplatform.org/top.html
「炊き出し」に関する調整・情報交換Mtgのご案内です。
JPFでは毎週土曜日に支援の調整会合(@東京)を主催しておりますが、
来たる16日の会合では「炊き出し」にテーマに、
NGO団体、企業・団体の皆さまと連携の余地があるのか可能性を探りたいと考えております。
「炊き出し」に関係する、例えば以下のような企業・団体さまがいらっしゃいましたら、
お気兼ねなく、是非ご参加下さい。
当日は、「炊き出し」現場の様子や、関係各所と調整すべき事項などの情報も共有させていただきます。
<ご参加いただきたい企業・団体さまの例>
・炊き出しの社員ボランティアを、実施 and/or 検討している
・調理ノウハウをお持ちの外食産業の企業で、実施 and/or 検討している
・食材の提供を、実施 and/or 検討している
・調理器具の提供を、実施 and/or 検討している
・食器(使い捨て等)の提供を、実施 and/or 検討している
・現地への輸送(食材や調理器具など)を、実施 and/or 検討している
<「炊き出し」にまつわる調整・情報交換Mtg>
日時:4月16日(土) 13:00-16:00
場所:東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル6F 670号室
http://www.japanplatform.org/jpf_map/office-map.html
※JPF事務局と同じビルの6階です
使用言語:日本語
出席:支援活動を実施する団体(JPF参加NGO、NGO、海外からの支援団体)
「炊き出し」に関係する支援を、実施 and/or 検討している企業・団体の皆さま
お申込み: 「御社名」、「お名前」、「実施 and/or 検討している内容」をご記入のうえ、
emergency@japanplatform.org (C.C. soumu@japanplatform.org )まで。
JPF担当: 野副(のぞえ)
まだ組織としての方針が確立されておらず、可能性を探っている段階の企業・団体の方も
多いことと思います。
ご出席された方の個人的な意見として、ご発言いただいてもなんら差し支えありません。
日本栄養士会と連携とり支援していきます。
白 鳳
お疲れ様です。
日本栄養士会 災害対策本部UPされてますので掲載します。
http://www.dietitian.or.jp/eq/pdf/web017.pdf
2011.4.17
災害支援管理栄養士・栄養士の登録 全国で445 名
4 月13 日現在で、災害支援管理栄養士・栄養士の登録は、全国で445 名となりました。
被災地の方々の支援をしたいという皆様の思いを重く受け止め、感謝申し上げます。
登録いただいた方々に早く現地で活動していただきたいと思いますが、
前号でお知らせしたとおり、必要に応じて活動していただくために、現在、当
該栄養士会・県等と調整中ですので、今しばらくお待ちくださるようお願いいたします。
登録いただいた方々には、ホームページでご案内することとしています。
災害支援管理栄養士・栄養士(ボランティア)は、自己完結型で活動していただくことと
なります。
現在「災害支援管理栄養士活動ハンドブック(ver.l)」を作成中ですが、
事前準備として次の事項を記載しています。
【個人で用意する物品】基本的な個人の必要物品の具体例
■防災用具(リュック、ヘルメット(帽子等)、防災服(防寒着)、
防災靴(底のしっかりした動きやすい靴)、軍手、ホイッスル等
■生活必需品(雨具(レインコート)、寝袋、懐中電灯(予備乾電池)、
洗面具、下着、着替え、ウエットティッシュ、はさみ等
■食料、水、水筒
■情報通信手段(携帯電話(充電器を含む)、ラジオ、パソコン等)
■現金
■事務用品(電卓、個人的に必要な書籍等)
■その他(派遣先によっては白衣が必要と思われ場合もあるため、持参が望ましい)
※ 個人の荷物が多すぎて活動に支障を来さないよう、荷物はコンパクトにまとめ、
必要最小限に留める必要があります。
その他、各自のご判断で十分な準備をしておくことが必要ですが、
原則は自己完結にてお願いします。
被災地では、被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動で災害
支援ボランティア活動に参加していただけるようお願いします。
被災地は衣・食・住、衛生環境を含め、非常に厳しい状況です。ボランティア活動はボラン
ティア本人の自発的な意志と責任により活動に参加し行動していただくことが基本です、
ご理解の上ご活躍いただけますようお願いします。
○ 現地での災害支援管理栄養士・栄養士活動人員(4 月13 日現在)
日本栄養士会 気仙沼地区:在宅療養・施設・避難所支援活動
(実)30 名、3 月26 日〜岩手県栄養士会 大船渡大槌・宮古・釜石地区の避難所の
状況把握 3チーム9 名
宮城県栄養士会 石巻市・山元町の栄養支援活動 延べ47 名
以上 白鳳転載
お疲れ様です♪
医師ら1万5千人被災地入り…震災後1か月で
2011年4月16日 提供:読売新聞
東日本大震災の発生から1か月間に、全国から被災地に医療支援に入った医師や看護師らの数は、1万5000人以上にのぼることが、読売新聞の調べで分かった。
阪神大震災を機に整備が進んだ災害医療支援は、過去最大の規模になることは間違いなさそうだ。
調査は今月14日までに、医療関連の各団体と都道府県を対象に、震災後1か月間に派遣した医療者の人数を電話などで確認した。
国は阪神大震災で救急医療が遅れた反省から、災害初期の救命医療を担う災害派遣医療チーム「D(ディー)MAT(マット)」を全国に整備、今回の震災では発生の翌日までに全国から1000人以上が被災地入りした。2007年の新潟県中越沖地震では、42チーム、約200人が出動したが、今回はその7倍以上の約320チーム、約1500人が活動。3月22日までに支援を終了した。
いっぱい いっぱい栄養士地域活動・行政・病院・企業など動いてるからね♪
白 鳳
医師ら1万5千人被災地入り…震災後1か月で
2011年4月16日 提供:読売新聞
東日本大震災の発生から1か月間に、全国から被災地に医療支援に入った医師や看護師らの数は、1万5000人以上にのぼることが、読売新聞の調べで分かった。
阪神大震災を機に整備が進んだ災害医療支援は、過去最大の規模になることは間違いなさそうだ。
調査は今月14日までに、医療関連の各団体と都道府県を対象に、震災後1か月間に派遣した医療者の人数を電話などで確認した。
国は阪神大震災で救急医療が遅れた反省から、災害初期の救命医療を担う災害派遣医療チーム「D(ディー)MAT(マット)」を全国に整備、今回の震災では発生の翌日までに全国から1000人以上が被災地入りした。2007年の新潟県中越沖地震では、42チーム、約200人が出動したが、今回はその7倍以上の約320チーム、約1500人が活動。3月22日までに支援を終了した。
いっぱい いっぱい栄養士地域活動・行政・病院・企業など動いてるからね♪
白 鳳
平成23 年4 月18 日
社団法人 日本栄養士会 災害対策本部
○ マスコミ報道、管理栄養士・栄養士に注目
東日本大震災から1 月を越えるなか、避難所生活、自宅で居住する被災者にも、支援物資の提供
は進んでいるものの、栄養のアンバランスな状況からくる健康問題に悩む方が多くなっています。
ここで求められるのは、管理栄養士・栄養士の技術です。マスコミの報道でも管理栄養士・栄養士
に期待するものが多いと推測されます。
・読売新聞4 月16 日:「被災地から ビタミン不足対策急ぐ 遠野から周辺市町支援」
・朝日新聞4 月17 日:「被災地 偏る栄養 栄養士、現地入り支援」
・東奥日報4 月10 日:「栄養偏る避難所生活 慢性病悪化の懸念も」(共同通信の配信によるもの思
われますので、他の地方紙にも掲載されると思います。)
○ 石巻市でも日本プライマリ・ケア連合学会と連携活動
前号でお知らせしましたが、気仙沼市に続き、石巻市でも日本プライマリ・ケア連合学会と連携し
た活動を4 月12 日から始めました。この活動は、全国在宅訪問栄養食事指導研究会の協力を得て行
っています。
日本栄養士会より
社団法人 日本栄養士会 災害対策本部
○ マスコミ報道、管理栄養士・栄養士に注目
東日本大震災から1 月を越えるなか、避難所生活、自宅で居住する被災者にも、支援物資の提供
は進んでいるものの、栄養のアンバランスな状況からくる健康問題に悩む方が多くなっています。
ここで求められるのは、管理栄養士・栄養士の技術です。マスコミの報道でも管理栄養士・栄養士
に期待するものが多いと推測されます。
・読売新聞4 月16 日:「被災地から ビタミン不足対策急ぐ 遠野から周辺市町支援」
・朝日新聞4 月17 日:「被災地 偏る栄養 栄養士、現地入り支援」
・東奥日報4 月10 日:「栄養偏る避難所生活 慢性病悪化の懸念も」(共同通信の配信によるもの思
われますので、他の地方紙にも掲載されると思います。)
○ 石巻市でも日本プライマリ・ケア連合学会と連携活動
前号でお知らせしましたが、気仙沼市に続き、石巻市でも日本プライマリ・ケア連合学会と連携し
た活動を4 月12 日から始めました。この活動は、全国在宅訪問栄養食事指導研究会の協力を得て行
っています。
日本栄養士会より
東日本大震災の発生に伴う第25回管理栄養士国家試験の追加試験の実施について
1.試験期日 平成23年7月31日(日)
2.試験地
宮城県(平成23年3月20日に宮城県で受験する予定であった者)、
東京都(平成23年3月20日に宮城県以外の試験地で受験する予定であった者)
3.試験科目 第25回管理栄養士国家試験と同様
4.受験資格 第25回管理栄養士国家試験の受験票の送付を受けたにも関わらず、東日本大震災の発生に伴い同試験を受験できなかった者(同試験の受験申し込みに際し、卒業・履修見込証明書又は実務終了見込証明書を提出した者にあっては、当該卒業・履修又は実務経験に係る資格を満たしている者に限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
(1)平成23年3月20日に宮城県で受験する予定であった者
(2)平成23年3月20日において東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内に居住地を有していた者
(3)平成23年3月20日において特定被災区域内に勤務地を有していた者
(4)第25回管理栄養士国家試験を受験できなかったことにつき、東日本大震災が発生したことに起因する正当な理由を有すると認められる者
5.受験手続き
(1)受験に関する書類の受付期間(追加試験申込みに必要な書類は後日公表)
平成23年5月30日(月)〜平成23年6月6日(月)
*平成23年3月20日に宮城県にて受験する予定であった者は、受験に関する書類の提出は必要ない。
(ただし、試験地の変更を希望する場合は、申出書の提出が必要である。)
(2)受験手数料は徴収しない
(3)受験者には追加試験の受験票を交付する
6.合格発表 平成23年8月22日(月)
<試験地別照会先>
宮城県 〒980-8426 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号
花京院スクエア21階 東北厚生局 国家試験担当
電話番号:022(716)7331
東京都 〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局 国家試験担当
電話番号:048(740)0810
厚生労働省
1.試験期日 平成23年7月31日(日)
2.試験地
宮城県(平成23年3月20日に宮城県で受験する予定であった者)、
東京都(平成23年3月20日に宮城県以外の試験地で受験する予定であった者)
3.試験科目 第25回管理栄養士国家試験と同様
4.受験資格 第25回管理栄養士国家試験の受験票の送付を受けたにも関わらず、東日本大震災の発生に伴い同試験を受験できなかった者(同試験の受験申し込みに際し、卒業・履修見込証明書又は実務終了見込証明書を提出した者にあっては、当該卒業・履修又は実務経験に係る資格を満たしている者に限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
(1)平成23年3月20日に宮城県で受験する予定であった者
(2)平成23年3月20日において東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内に居住地を有していた者
(3)平成23年3月20日において特定被災区域内に勤務地を有していた者
(4)第25回管理栄養士国家試験を受験できなかったことにつき、東日本大震災が発生したことに起因する正当な理由を有すると認められる者
5.受験手続き
(1)受験に関する書類の受付期間(追加試験申込みに必要な書類は後日公表)
平成23年5月30日(月)〜平成23年6月6日(月)
*平成23年3月20日に宮城県にて受験する予定であった者は、受験に関する書類の提出は必要ない。
(ただし、試験地の変更を希望する場合は、申出書の提出が必要である。)
(2)受験手数料は徴収しない
(3)受験者には追加試験の受験票を交付する
6.合格発表 平成23年8月22日(月)
<試験地別照会先>
宮城県 〒980-8426 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号
花京院スクエア21階 東北厚生局 国家試験担当
電話番号:022(716)7331
東京都 〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局 国家試験担当
電話番号:048(740)0810
厚生労働省
お疲れ様です。
ビタミンなどの目標量明示 避難所の食事で厚労省
2011年4月22日 提供:共同通信社
厚生労働省は21日、東日本大震災の避難所で出される食事の栄養バランスに偏りがみられるため、必要なビタミンやエネルギーなどの摂取目標量を設け、避難所のある岩手、宮城、福島の3県など関係自治体に通知した。
1歳以上の1人1日当たりの目標量はエネルギーが2千キロカロリー、タンパク質が55グラム、ビタミンB1が1・1ミリグラム、ビタミンB2が1・2ミリグラム、ビタミンCが100ミリグラム。
避難所では、ご飯などの主食が中心で、肉や魚、野菜などの副食が不十分と指摘されている。厚労省は、避難所での生活が長引き、被災者の間に栄養不足や体力低下が広がる恐れがあるため、6月までの目標として示した。
宮城県などで避難所の食事内容の確認が進んでおり、目標に満たない場合は、県などに改善を働き掛ける。
健康への影響、7月に報告 食安委作業部会が初会合
2011年4月22日 提供:共同通信社
内閣府の食品安全委員会は21日、放射性物質の健康への影響を評価する作業部会の初会合を開き、食品に含まれる放射性物質の発がん性や胎児への影響などについて、検討結果の報告を7月にまとめることを決めた。
会合に出席した松原純子(まつばら・じゅんこ)元原子力安全委員会委員長代理は、チェルノブイリ原発事故の現地調査などを踏まえ「食物連鎖に伴う生物への放射性物質の濃縮は起こる」と強調し、海への放射性物質の放出はとくに注意深く監視する必要があると指摘した。
福島第1原発事故を受け、野菜などから放射性のヨウ素やセシウムの検出が相次いでおり、作業部会はデータが少ないストロンチウムやプルトニウムなどについても影響評価を行う。
作業部会は衛生学や食品安全の専門家13人で構成。この日は、座長に山添康(やまぞえ・やすし)東北大大学院教授を選出した。
ご活用くださいませ。
白 鳳
2011年4月22日 提供:共同通信社
内閣府の食品安全委員会は21日、放射性物質の健康への影響を評価する作業部会の初会合を開き、食品に含まれる放射性物質の発がん性や胎児への影響などについて、検討結果の報告を7月にまとめることを決めた。
会合に出席した松原純子(まつばら・じゅんこ)元原子力安全委員会委員長代理は、チェルノブイリ原発事故の現地調査などを踏まえ「食物連鎖に伴う生物への放射性物質の濃縮は起こる」と強調し、海への放射性物質の放出はとくに注意深く監視する必要があると指摘した。
福島第1原発事故を受け、野菜などから放射性のヨウ素やセシウムの検出が相次いでおり、作業部会はデータが少ないストロンチウムやプルトニウムなどについても影響評価を行う。
作業部会は衛生学や食品安全の専門家13人で構成。この日は、座長に山添康(やまぞえ・やすし)東北大大学院教授を選出した。
ご活用くださいませ。
白 鳳
お疲れ様です。
放射線関係 産婦人科医@大阪大学保健学科教授と打ち合わせしております。
災害時に、市長が市民の皆様に「避難勧告」と「避難指示」を発令する場合があります。
これらの違いをあらかじめ理解しておくことが「自らの身を守る」ことにつながりますし、自らの判断で早めに避難することも重要です。
よく「避難命令」という言葉が用いられますが、法律的には「避難のための立ち退きの勧告」(避難勧告)と「避難のための立ち退きの指示」(避難指示)という規定しかありません。
今回の避難勧告 20Sy(シーベルト) 年
例えば 成長率
0→20歳
99.7% 0.3%
10mSy 体内被曝 9ヶ月 99.6% 0.4&
<これを1.4倍と記載>
100mSy 99.1% 0.9%
ご参考に! 白 鳳
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110418.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110418.pdf
放射線関係 産婦人科医@大阪大学保健学科教授と打ち合わせしております。
災害時に、市長が市民の皆様に「避難勧告」と「避難指示」を発令する場合があります。
これらの違いをあらかじめ理解しておくことが「自らの身を守る」ことにつながりますし、自らの判断で早めに避難することも重要です。
よく「避難命令」という言葉が用いられますが、法律的には「避難のための立ち退きの勧告」(避難勧告)と「避難のための立ち退きの指示」(避難指示)という規定しかありません。
今回の避難勧告 20Sy(シーベルト) 年
例えば 成長率
0→20歳
99.7% 0.3%
10mSy 体内被曝 9ヶ月 99.6% 0.4&
<これを1.4倍と記載>
100mSy 99.1% 0.9%
ご参考に! 白 鳳
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110418.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110418.pdf
水道水について心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内
平成23 年3 月24 日
日本産科婦人科学会
胎児が100,000〜500,000 マイクロシーベルト(100〜500 ミリシーベルト)の被曝を受けても胎児の形態異常は増加しないとの研究報告もあり、ICRP84 は「100 ミリシーベルト未満の胎児被曝量は妊娠継続をあきらめる理由とはならない」と勧告しています。
妊娠中女性は脱水(体の中の水分が不足すること)には特に注意する必要
があります。したがって、のどがかわいた場合は決してがまんせず、水分
を取る必要があります。のどがかわいた場合には、スポーツドリンク、ミ
ネラルウォーター(軟水のもの)、ジュース、牛乳などがお勧めです。
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf
平成23 年3 月24 日
日本産科婦人科学会
胎児が100,000〜500,000 マイクロシーベルト(100〜500 ミリシーベルト)の被曝を受けても胎児の形態異常は増加しないとの研究報告もあり、ICRP84 は「100 ミリシーベルト未満の胎児被曝量は妊娠継続をあきらめる理由とはならない」と勧告しています。
妊娠中女性は脱水(体の中の水分が不足すること)には特に注意する必要
があります。したがって、のどがかわいた場合は決してがまんせず、水分
を取る必要があります。のどがかわいた場合には、スポーツドリンク、ミ
ネラルウォーター(軟水のもの)、ジュース、牛乳などがお勧めです。
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf
大気や飲食物の軽度放射性物質汚染について心配しておられる妊娠・授乳
中女性のためのQ&A
平成23 年4 月18 日
日本産科婦人科学会
Q1. 「放射性ヨウ素」って何ですか?
A1.原子力発電所などの事故の場合に大気中などに放出される放射能活性を持
った極めて小さなチリのようなものです。
Q2. 「内部被曝」って何ですか?
A2. 大気中にばらまかれた放射性ヨウ素は、時間をかけて地上に降りて来ます。
その間に体の表面から受ける放射能被曝を外部被曝と言います。この外部被曝
が大量だと、やけどや体内の臓器障害が起こります。一方、この細かな放射性
ヨウ素は吸気ともに肺から体の中に、また地上に降りた放射性ヨウ素は食べ物
表面に付着したり水道水に混入し、飲食物として体の中に入ってきます。体の
中に入った放射性ヨウ素は少量でも近くにある臓器を攻撃しますので健康被害
を引き起こす可能性があります。これを内部被曝と言います。
Q3.内部被曝を受けるとどんなことが起こりますか?
A3. いったん、体の中に入ったヨウ素(I-131)は甲状腺に集まりやすいという
性質があります。そのため、甲状腺が最も被害を受けやすくなります。甲状腺
が50mSv (ミリシーベルト) 以上の被曝を受けると甲状腺がんになりやすくな
ります。ただし、40 歳以上では影響を受けず、若い人ほど甲状腺がんになりや
すいとされています。また、被曝により起こった甲状腺がんは比較的穏やかな
がん(進行がゆっくり)と言われています。
Q4.内部被曝を避けるためにはどんな注意が必要ですか?
A4.最も影響を受けやすい甲状腺を守ることは体全体を守ることになります。そ
のため多くの国で、水や食べ物について、甲状腺を守るための(安全に食べる
ことができる)基準値(1kg に含まれるベクレル基準値)を示しています。日
本では外国よりもむしろ厳しい(より安全な)基準値を示しています。そのた
め、実際には、水道水や流通している食品を摂取しているかぎり健康被害の心
配はないと考えられています。しかし、妊娠・授乳婦人は用心に越したことは
ありません。繰り返しになりますが、甲状腺が50mSv の被曝を受けると健康被
害の心配がでてきます。
中女性のためのQ&A
平成23 年4 月18 日
日本産科婦人科学会
Q1. 「放射性ヨウ素」って何ですか?
A1.原子力発電所などの事故の場合に大気中などに放出される放射能活性を持
った極めて小さなチリのようなものです。
Q2. 「内部被曝」って何ですか?
A2. 大気中にばらまかれた放射性ヨウ素は、時間をかけて地上に降りて来ます。
その間に体の表面から受ける放射能被曝を外部被曝と言います。この外部被曝
が大量だと、やけどや体内の臓器障害が起こります。一方、この細かな放射性
ヨウ素は吸気ともに肺から体の中に、また地上に降りた放射性ヨウ素は食べ物
表面に付着したり水道水に混入し、飲食物として体の中に入ってきます。体の
中に入った放射性ヨウ素は少量でも近くにある臓器を攻撃しますので健康被害
を引き起こす可能性があります。これを内部被曝と言います。
Q3.内部被曝を受けるとどんなことが起こりますか?
A3. いったん、体の中に入ったヨウ素(I-131)は甲状腺に集まりやすいという
性質があります。そのため、甲状腺が最も被害を受けやすくなります。甲状腺
が50mSv (ミリシーベルト) 以上の被曝を受けると甲状腺がんになりやすくな
ります。ただし、40 歳以上では影響を受けず、若い人ほど甲状腺がんになりや
すいとされています。また、被曝により起こった甲状腺がんは比較的穏やかな
がん(進行がゆっくり)と言われています。
Q4.内部被曝を避けるためにはどんな注意が必要ですか?
A4.最も影響を受けやすい甲状腺を守ることは体全体を守ることになります。そ
のため多くの国で、水や食べ物について、甲状腺を守るための(安全に食べる
ことができる)基準値(1kg に含まれるベクレル基準値)を示しています。日
本では外国よりもむしろ厳しい(より安全な)基準値を示しています。そのた
め、実際には、水道水や流通している食品を摂取しているかぎり健康被害の心
配はないと考えられています。しかし、妊娠・授乳婦人は用心に越したことは
ありません。繰り返しになりますが、甲状腺が50mSv の被曝を受けると健康被
害の心配がでてきます。
Q5. 胎児(お腹の中の赤ちゃん)を守るための食事の注意は?
A5. 胎児の甲状腺はお母さんの甲状腺より影響を受けやすいので、妊娠してな
い成人より、お母さんはより安全でバランスのいい食事が必要です。
水が汚染されている場合には、野菜なども汚染されていることが多く、また
今回の場合は魚介類の汚染も心配です。しかし、本人の健康維持、胎児(お腹
の中の赤ちゃんのこと)、ならびに授乳のためにはバランスのいい食事が必要で
す。下表の組み合わせの飲食は最大危険時を想定したものですが、毎日続けた
場合、約82 日間で胎児甲状腺の被曝は50mSv になります。現在のところ入手で
きる食品にはほとんど汚染がなく、水道水汚染もありません。しかし、爆発な
ど起きるとまた汚染が心配されますので、報道等にはご注意下さい。
摂取したベクレルの総量に0.00047 をかけると胎児甲状腺被曝量(mSv)になります。
摂取したベクレルの総量に0.00032 をかけると母体甲状腺被曝量(mSv)になります。
1 日に1170 ベクレル摂取すると、胎児甲状腺被曝は1 日あたり0.55mSv となり、82 日で45mSv
になる(残り5mSv の被曝は母親の大気から暴露を想定している)。計50mSv の被曝を受ける場
合、水から11.1mSv、野菜から11.1mSv、乳製品から11.1mSv、その他の食品(穀類、肉、魚介、
卵など)と大気から16.7mSv の被曝を受けることを想定している。
Q6. 粉ミルクを飲んでる赤ちゃんは安心ですか?
A6. 粉ミルクを汚染した水道水で溶かして飲ませた場合の話です。仮にその水
道水が1 リットルあたり100 ベクレル含み、毎日0.8 リットル(800 ミリリッ
トル)その赤ちゃんが飲み続けた場合、200 日で赤ちゃんの甲状腺被曝量は
50mSv に達します。(乳児の場合には摂取ベクレルに0.0028 をかけると乳児甲状腺被曝量
になる。例えばこの場合、1 日あたり80 ベクレル飲むので、200 日では 80×200×0.0028=
45mSv, 残り5mSv は乳児が呼吸により被曝することを想定している)。
Q7. その他、被曝量を少なくするための注意はありますか?
Q7. 野菜や魚介類表面には放射性ヨウ素が付着している場合がありますので、よ
く洗ってから調理するようにします。もし、水道水汚染の発表があった場合に
は、1 日〜2 日間、冷蔵庫保存してから飲むと、放射能を9%〜18%程度減少さ
せることができます。ただし、2 日以上保存した場合は細菌が増えている場合が
ありますので、一旦沸かしてから飲むようにすると安心です。
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110418.pdf
現場・地域で是非みなさまの専門活用してくださいませ。
白 鳳
A5. 胎児の甲状腺はお母さんの甲状腺より影響を受けやすいので、妊娠してな
い成人より、お母さんはより安全でバランスのいい食事が必要です。
水が汚染されている場合には、野菜なども汚染されていることが多く、また
今回の場合は魚介類の汚染も心配です。しかし、本人の健康維持、胎児(お腹
の中の赤ちゃんのこと)、ならびに授乳のためにはバランスのいい食事が必要で
す。下表の組み合わせの飲食は最大危険時を想定したものですが、毎日続けた
場合、約82 日間で胎児甲状腺の被曝は50mSv になります。現在のところ入手で
きる食品にはほとんど汚染がなく、水道水汚染もありません。しかし、爆発な
ど起きるとまた汚染が心配されますので、報道等にはご注意下さい。
摂取したベクレルの総量に0.00047 をかけると胎児甲状腺被曝量(mSv)になります。
摂取したベクレルの総量に0.00032 をかけると母体甲状腺被曝量(mSv)になります。
1 日に1170 ベクレル摂取すると、胎児甲状腺被曝は1 日あたり0.55mSv となり、82 日で45mSv
になる(残り5mSv の被曝は母親の大気から暴露を想定している)。計50mSv の被曝を受ける場
合、水から11.1mSv、野菜から11.1mSv、乳製品から11.1mSv、その他の食品(穀類、肉、魚介、
卵など)と大気から16.7mSv の被曝を受けることを想定している。
Q6. 粉ミルクを飲んでる赤ちゃんは安心ですか?
A6. 粉ミルクを汚染した水道水で溶かして飲ませた場合の話です。仮にその水
道水が1 リットルあたり100 ベクレル含み、毎日0.8 リットル(800 ミリリッ
トル)その赤ちゃんが飲み続けた場合、200 日で赤ちゃんの甲状腺被曝量は
50mSv に達します。(乳児の場合には摂取ベクレルに0.0028 をかけると乳児甲状腺被曝量
になる。例えばこの場合、1 日あたり80 ベクレル飲むので、200 日では 80×200×0.0028=
45mSv, 残り5mSv は乳児が呼吸により被曝することを想定している)。
Q7. その他、被曝量を少なくするための注意はありますか?
Q7. 野菜や魚介類表面には放射性ヨウ素が付着している場合がありますので、よ
く洗ってから調理するようにします。もし、水道水汚染の発表があった場合に
は、1 日〜2 日間、冷蔵庫保存してから飲むと、放射能を9%〜18%程度減少さ
せることができます。ただし、2 日以上保存した場合は細菌が増えている場合が
ありますので、一旦沸かしてから飲むようにすると安心です。
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110418.pdf
現場・地域で是非みなさまの専門活用してくださいませ。
白 鳳
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110418.pdf
大気や飲食物の軽度放射性物質汚染について心配しておられる妊娠・授乳
中女性のためのQ&A
平成23 年4 月18 日
日本産科婦人科学会
Q1. 「放射性ヨウ素」って何ですか?
A1.原子力発電所などの事故の場合に大気中などに放出される放射能活性を持
った極めて小さなチリのようなものです。
Q2. 「内部被曝」って何ですか?
A2. 大気中にばらまかれた放射性ヨウ素は、時間をかけて地上に降りて来ます。
その間に体の表面から受ける放射能被曝を外部被曝と言います。この外部被曝
が大量だと、やけどや体内の臓器障害が起こります。一方、この細かな放射性
ヨウ素は吸気ともに肺から体の中に、また地上に降りた放射性ヨウ素は食べ物
表面に付着したり水道水に混入し、飲食物として体の中に入ってきます。体の
中に入った放射性ヨウ素は少量でも近くにある臓器を攻撃しますので健康被害
を引き起こす可能性があります。これを内部被曝と言います。
Q3.内部被曝を受けるとどんなことが起こりますか?
A3. いったん、体の中に入ったヨウ素(I-131)は甲状腺に集まりやすいという
性質があります。そのため、甲状腺が最も被害を受けやすくなります。甲状腺
が50mSv (ミリシーベルト) 以上の被曝を受けると甲状腺がんになりやすくな
ります。ただし、40 歳以上では影響を受けず、若い人ほど甲状腺がんになりや
すいとされています。また、被曝により起こった甲状腺がんは比較的穏やかな
がん(進行がゆっくり)と言われています。
Q4.内部被曝を避けるためにはどんな注意が必要ですか?
A4.最も影響を受けやすい甲状腺を守ることは体全体を守ることになります。そ
のため多くの国で、水や食べ物について、甲状腺を守るための(安全に食べる
ことができる)基準値(1kg に含まれるベクレル基準値)を示しています。日
本では外国よりもむしろ厳しい(より安全な)基準値を示しています。そのた
め、実際には、水道水や流通している食品を摂取しているかぎり健康被害の心
配はないと考えられています。しかし、妊娠・授乳婦人は用心に越したことは
ありません。繰り返しになりますが、甲状腺が50mSv の被曝を受けると健康被
害の心配がでてきます。
大気や飲食物の軽度放射性物質汚染について心配しておられる妊娠・授乳
中女性のためのQ&A
平成23 年4 月18 日
日本産科婦人科学会
Q1. 「放射性ヨウ素」って何ですか?
A1.原子力発電所などの事故の場合に大気中などに放出される放射能活性を持
った極めて小さなチリのようなものです。
Q2. 「内部被曝」って何ですか?
A2. 大気中にばらまかれた放射性ヨウ素は、時間をかけて地上に降りて来ます。
その間に体の表面から受ける放射能被曝を外部被曝と言います。この外部被曝
が大量だと、やけどや体内の臓器障害が起こります。一方、この細かな放射性
ヨウ素は吸気ともに肺から体の中に、また地上に降りた放射性ヨウ素は食べ物
表面に付着したり水道水に混入し、飲食物として体の中に入ってきます。体の
中に入った放射性ヨウ素は少量でも近くにある臓器を攻撃しますので健康被害
を引き起こす可能性があります。これを内部被曝と言います。
Q3.内部被曝を受けるとどんなことが起こりますか?
A3. いったん、体の中に入ったヨウ素(I-131)は甲状腺に集まりやすいという
性質があります。そのため、甲状腺が最も被害を受けやすくなります。甲状腺
が50mSv (ミリシーベルト) 以上の被曝を受けると甲状腺がんになりやすくな
ります。ただし、40 歳以上では影響を受けず、若い人ほど甲状腺がんになりや
すいとされています。また、被曝により起こった甲状腺がんは比較的穏やかな
がん(進行がゆっくり)と言われています。
Q4.内部被曝を避けるためにはどんな注意が必要ですか?
A4.最も影響を受けやすい甲状腺を守ることは体全体を守ることになります。そ
のため多くの国で、水や食べ物について、甲状腺を守るための(安全に食べる
ことができる)基準値(1kg に含まれるベクレル基準値)を示しています。日
本では外国よりもむしろ厳しい(より安全な)基準値を示しています。そのた
め、実際には、水道水や流通している食品を摂取しているかぎり健康被害の心
配はないと考えられています。しかし、妊娠・授乳婦人は用心に越したことは
ありません。繰り返しになりますが、甲状腺が50mSv の被曝を受けると健康被
害の心配がでてきます。
Q5. 胎児(お腹の中の赤ちゃん)を守るための食事の注意は?
A5. 胎児の甲状腺はお母さんの甲状腺より影響を受けやすいので、妊娠してな
い成人より、お母さんはより安全でバランスのいい食事が必要です。
水が汚染されている場合には、野菜なども汚染されていることが多く、また
今回の場合は魚介類の汚染も心配です。しかし、本人の健康維持、胎児(お腹
の中の赤ちゃんのこと)、ならびに授乳のためにはバランスのいい食事が必要で
す。下表の組み合わせの飲食は最大危険時を想定したものですが、毎日続けた
場合、約82 日間で胎児甲状腺の被曝は50mSv になります。現在のところ入手で
きる食品にはほとんど汚染がなく、水道水汚染もありません。しかし、爆発な
ど起きるとまた汚染が心配されますので、報道等にはご注意下さい。
摂取したベクレルの総量に0.00047 をかけると胎児甲状腺被曝量(mSv)になります。
摂取したベクレルの総量に0.00032 をかけると母体甲状腺被曝量(mSv)になります。
1 日に1170 ベクレル摂取すると、胎児甲状腺被曝は1 日あたり0.55mSv となり、82 日で45mSv
になる(残り5mSv の被曝は母親の大気から暴露を想定している)。計50mSv の被曝を受ける場
合、水から11.1mSv、野菜から11.1mSv、乳製品から11.1mSv、その他の食品(穀類、肉、魚介、
卵など)と大気から16.7mSv の被曝を受けることを想定している。
Q6. 粉ミルクを飲んでる赤ちゃんは安心ですか?
A6. 粉ミルクを汚染した水道水で溶かして飲ませた場合の話です。仮にその水
道水が1 リットルあたり100 ベクレル含み、毎日0.8 リットル(800 ミリリッ
トル)その赤ちゃんが飲み続けた場合、200 日で赤ちゃんの甲状腺被曝量は
50mSv に達します。(乳児の場合には摂取ベクレルに0.0028 をかけると乳児甲状腺被曝量
になる。例えばこの場合、1 日あたり80 ベクレル飲むので、200 日では 80×200×0.0028=
45mSv, 残り5mSv は乳児が呼吸により被曝することを想定している)。
Q7. その他、被曝量を少なくするための注意はありますか?
Q7. 野菜や魚介類表面には放射性ヨウ素が付着している場合がありますので、よ
く洗ってから調理するようにします。もし、水道水汚染の発表があった場合に
は、1 日〜2 日間、冷蔵庫保存してから飲むと、放射能を9%〜18%程度減少さ
せることができます。ただし、2 日以上保存した場合は細菌が増えている場合が
ありますので、一旦沸かしてから飲むようにすると安心です。
職場・地域で 専門性活用くださいませ。 白 鳳
A5. 胎児の甲状腺はお母さんの甲状腺より影響を受けやすいので、妊娠してな
い成人より、お母さんはより安全でバランスのいい食事が必要です。
水が汚染されている場合には、野菜なども汚染されていることが多く、また
今回の場合は魚介類の汚染も心配です。しかし、本人の健康維持、胎児(お腹
の中の赤ちゃんのこと)、ならびに授乳のためにはバランスのいい食事が必要で
す。下表の組み合わせの飲食は最大危険時を想定したものですが、毎日続けた
場合、約82 日間で胎児甲状腺の被曝は50mSv になります。現在のところ入手で
きる食品にはほとんど汚染がなく、水道水汚染もありません。しかし、爆発な
ど起きるとまた汚染が心配されますので、報道等にはご注意下さい。
摂取したベクレルの総量に0.00047 をかけると胎児甲状腺被曝量(mSv)になります。
摂取したベクレルの総量に0.00032 をかけると母体甲状腺被曝量(mSv)になります。
1 日に1170 ベクレル摂取すると、胎児甲状腺被曝は1 日あたり0.55mSv となり、82 日で45mSv
になる(残り5mSv の被曝は母親の大気から暴露を想定している)。計50mSv の被曝を受ける場
合、水から11.1mSv、野菜から11.1mSv、乳製品から11.1mSv、その他の食品(穀類、肉、魚介、
卵など)と大気から16.7mSv の被曝を受けることを想定している。
Q6. 粉ミルクを飲んでる赤ちゃんは安心ですか?
A6. 粉ミルクを汚染した水道水で溶かして飲ませた場合の話です。仮にその水
道水が1 リットルあたり100 ベクレル含み、毎日0.8 リットル(800 ミリリッ
トル)その赤ちゃんが飲み続けた場合、200 日で赤ちゃんの甲状腺被曝量は
50mSv に達します。(乳児の場合には摂取ベクレルに0.0028 をかけると乳児甲状腺被曝量
になる。例えばこの場合、1 日あたり80 ベクレル飲むので、200 日では 80×200×0.0028=
45mSv, 残り5mSv は乳児が呼吸により被曝することを想定している)。
Q7. その他、被曝量を少なくするための注意はありますか?
Q7. 野菜や魚介類表面には放射性ヨウ素が付着している場合がありますので、よ
く洗ってから調理するようにします。もし、水道水汚染の発表があった場合に
は、1 日〜2 日間、冷蔵庫保存してから飲むと、放射能を9%〜18%程度減少さ
せることができます。ただし、2 日以上保存した場合は細菌が増えている場合が
ありますので、一旦沸かしてから飲むようにすると安心です。
職場・地域で 専門性活用くださいませ。 白 鳳
9割で目標カロリー下回る 宮城県が避難所調査
2011年4月25日 提供:共同通信社
宮城県が行った東日本大震災の県内避難所住民の栄養状況調査で、エネルギーを調査できた避難所266カ所のうち、約9割で摂取カロリーが目標の2千キロカロリーを下回っていたことが25日、分かった。266カ所の平均は1546キロカロリー。県の担当者が災害対策本部会議で明らかにした。
県は「栄養不足は病気や健康悪化の原因になる。牛乳や野菜などをバランスよく提供していかなければならない」(健康推進課)としており、調査結果を踏まえ、避難所の食事環境の改善につなげる考え。
調査は被害が大きかった沿岸13市町で1〜12日に実施した。避難所の規模別では、500人以上が暮らす、規模の大きい14カ所の栄養状態が最も悪く、これらの平均摂取カロリーは1340キロカロリーだった。食事回数も、500人以上の避難所のうち、この項目について回答のあった11カ所中5カ所が1日2回しか提供されていなかった。
主な栄養素別状況を見ると、タンパク質は、分析可能だった施設の約8割(207カ所)で目標を下回ったほか、ビタミンCはすべての分析可能施設(134カ所)で目標栄養量を下回り、平均摂取量が目標の3分の1程度にとどまった。
また、アレルギーや離乳食など食事内容への配慮では、回答があった施設のうち約9割が「なし」と回答した。
**********************************
みなさん どう感じますか? 教えてください。 白 鳳
2011年4月25日 提供:共同通信社
宮城県が行った東日本大震災の県内避難所住民の栄養状況調査で、エネルギーを調査できた避難所266カ所のうち、約9割で摂取カロリーが目標の2千キロカロリーを下回っていたことが25日、分かった。266カ所の平均は1546キロカロリー。県の担当者が災害対策本部会議で明らかにした。
県は「栄養不足は病気や健康悪化の原因になる。牛乳や野菜などをバランスよく提供していかなければならない」(健康推進課)としており、調査結果を踏まえ、避難所の食事環境の改善につなげる考え。
調査は被害が大きかった沿岸13市町で1〜12日に実施した。避難所の規模別では、500人以上が暮らす、規模の大きい14カ所の栄養状態が最も悪く、これらの平均摂取カロリーは1340キロカロリーだった。食事回数も、500人以上の避難所のうち、この項目について回答のあった11カ所中5カ所が1日2回しか提供されていなかった。
主な栄養素別状況を見ると、タンパク質は、分析可能だった施設の約8割(207カ所)で目標を下回ったほか、ビタミンCはすべての分析可能施設(134カ所)で目標栄養量を下回り、平均摂取量が目標の3分の1程度にとどまった。
また、アレルギーや離乳食など食事内容への配慮では、回答があった施設のうち約9割が「なし」と回答した。
**********************************
みなさん どう感じますか? 教えてください。 白 鳳
平成23 年4 月27 日
社団法人 日本栄養士会 災害対策本部
○ 宮城県が避難所における食事状況を調査
4 月25 日に宮城県(保健福祉部健康増進課)は、被害の大きかった沿岸部の13 市町村に設置されて
いる全避難所での食事状況等について、調査を行いその結果を発表しました。この調査には宮城県栄
養士会も協力しました。
振り返れば、国民健康・栄養調査は、戦後の食糧不足の時代に、エネルギー、栄養素の不足状況を
把握するために行われ、食料の国際支援につながりました。これにより、当時の児童の栄養摂取状況
が改善されました。そして、これらの児童たちが戦後の高度成長期を担うこととなりました。今回の
食事状況を踏まえて、管理栄養士・栄養士は、支援活動を展開する必要があると考えます。
宮城県の避難所における食事状況調査に関して、以下に掲載されましたのでお知らせします。
・毎日新聞4 月25 日夕刊 ・朝日新聞4 月26 日 ・読売新聞4 月26 日
・日本経済新聞4 月26 日 ・産経新聞4 月26 日 ・しんぶん赤旗4 月26 日
・河北新報4 月26 日
○ 現地で管理栄養士・栄養士は住民のために活動
被災地では、市町村、都道府県、さらに被災県栄養士会の会員である管理栄養士・栄養士は、自ら
が被災している方もいらっしゃいますが、地域の被災者の方々の生命の維持、また、災害弱者の方々
のために尽力されています。
日本栄養士会では、気仙沼市、石巻市など宮城県を中心に災害支援管理栄養士・栄養士を派遣し、
活動を行っています。さらに、福島県栄養士会、宮城県栄養士会、岩手県栄養士会でも避難所等での
活動を展開しております。
日本栄養士会では、公益社団法人の設立を目指し、『すべての人びとの「自己実現をめざし健やか
によりよく生きる」とのニーズに応え、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、専門職業人と
しての倫理と科学的かつ高度な技術に裏づけられた食と栄養の指導をとおして公衆衛生の向上に寄
与することを目的とする』としました。
管理栄養士・栄養士は、国民の皆さんの健康を守るための専門職であり、47 都道府県栄養士会に
は、公益社団法人を目指していただきたいと考えています。
4 月22 日現在、629 名が支援管理栄養士・栄養士として登録されています。しかし、派遣地との調
整、移動手段、現地での宿泊場所等の確保の関係から、すべての方々に活動をお願いできていません
が、ご容赦とご理解をお願いいたします。このような意志を持つ方が多いことに対して、心から感謝
申し上げます。
http://www.dietitian.or.jp/eq/pdf/web021.pdf 白鳳転載
社団法人 日本栄養士会 災害対策本部
○ 宮城県が避難所における食事状況を調査
4 月25 日に宮城県(保健福祉部健康増進課)は、被害の大きかった沿岸部の13 市町村に設置されて
いる全避難所での食事状況等について、調査を行いその結果を発表しました。この調査には宮城県栄
養士会も協力しました。
振り返れば、国民健康・栄養調査は、戦後の食糧不足の時代に、エネルギー、栄養素の不足状況を
把握するために行われ、食料の国際支援につながりました。これにより、当時の児童の栄養摂取状況
が改善されました。そして、これらの児童たちが戦後の高度成長期を担うこととなりました。今回の
食事状況を踏まえて、管理栄養士・栄養士は、支援活動を展開する必要があると考えます。
宮城県の避難所における食事状況調査に関して、以下に掲載されましたのでお知らせします。
・毎日新聞4 月25 日夕刊 ・朝日新聞4 月26 日 ・読売新聞4 月26 日
・日本経済新聞4 月26 日 ・産経新聞4 月26 日 ・しんぶん赤旗4 月26 日
・河北新報4 月26 日
○ 現地で管理栄養士・栄養士は住民のために活動
被災地では、市町村、都道府県、さらに被災県栄養士会の会員である管理栄養士・栄養士は、自ら
が被災している方もいらっしゃいますが、地域の被災者の方々の生命の維持、また、災害弱者の方々
のために尽力されています。
日本栄養士会では、気仙沼市、石巻市など宮城県を中心に災害支援管理栄養士・栄養士を派遣し、
活動を行っています。さらに、福島県栄養士会、宮城県栄養士会、岩手県栄養士会でも避難所等での
活動を展開しております。
日本栄養士会では、公益社団法人の設立を目指し、『すべての人びとの「自己実現をめざし健やか
によりよく生きる」とのニーズに応え、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、専門職業人と
しての倫理と科学的かつ高度な技術に裏づけられた食と栄養の指導をとおして公衆衛生の向上に寄
与することを目的とする』としました。
管理栄養士・栄養士は、国民の皆さんの健康を守るための専門職であり、47 都道府県栄養士会に
は、公益社団法人を目指していただきたいと考えています。
4 月22 日現在、629 名が支援管理栄養士・栄養士として登録されています。しかし、派遣地との調
整、移動手段、現地での宿泊場所等の確保の関係から、すべての方々に活動をお願いできていません
が、ご容赦とご理解をお願いいたします。このような意志を持つ方が多いことに対して、心から感謝
申し上げます。
http://www.dietitian.or.jp/eq/pdf/web021.pdf 白鳳転載
災害時のボランティア活動について近年の台風による風水害や地震災害時には、災害救援ボランティア活動が大きな力を発揮し、ボランティア活動が果たす大きな役割の一つとなっています。
災害救援ボランティア活動には大きな期待が寄せられますが、一方で、ボランティア活動が被災地の人々や他のボランティアの負担や迷惑にならないよう、ボランティア一人ひとりが自分自身の行動と安全に責任を持つ必要があります。
ここでは、災害救援ボランティア活動に参加する際の基本的な注意事項についてご案内します。災害救援ボランティア活動への参加の参考としてください。
災害救援ボランティア活動は、ボランティア本人の自発的な意思と責任により被災地での活動に参加・行動することが基本です。
まずは、自分自身で被災地の情報を収集し、現地に行くか、行かないかを判断することです。家族の理解も大切です。その際には、必ず現地に設置されている災害救援ボランティアセンターに事前に連絡し、ボランティア活動への参加方法や注意点について確認してください。災害救援ボランティアセンターの連絡先は、本会のホームページでもお知らせしています。
被災地での活動は、危険がともなうことや重労働となる場合があります。安全や健康についてボランティアが自分自身で管理することであることを理解したうえで参加してください。体調が悪ければ、参加を中止することが肝心です。
被災地で活動する際の宿所は、ボランティア自身が事前に被災地の状況を確認し、手配してください。水、食料、その他身の回りのものについてもボランティア自身が事前に用意し、携行のうえ被災地でのボランティア活動を開始してください。
被災地に到着した後は、必ず災害救援ボランティアセンターを訪れ、ボランティア活動の登録を行ってください。
被災地における緊急連絡先・連絡網を必ず確認するとともに、地理や気候等周辺環境を把握したうえで活動してください。
被災地では、被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動と言葉づかいでボランティア活動に参加してください。
被災地では、必ず災害救援ボランティアセンターやボランティアコーディネーター等、現地受け入れ機関の指示、指導に従って活動してください。単独行動はできるだけ避けてください。組織的に活動することで、より大きな力となることができます。
自分にできる範囲の活動を行ってください。休憩を心がけましょう。無理な活動は、思わぬ事故につながり、かえって被災地の人々の負担となってしまいます。
備えとして、ボランティア活動保険に加入しましょう。
http://www.shakyo.or.jp/saigai/katudou.html 転載白鳳
災害救援ボランティア活動には大きな期待が寄せられますが、一方で、ボランティア活動が被災地の人々や他のボランティアの負担や迷惑にならないよう、ボランティア一人ひとりが自分自身の行動と安全に責任を持つ必要があります。
ここでは、災害救援ボランティア活動に参加する際の基本的な注意事項についてご案内します。災害救援ボランティア活動への参加の参考としてください。
災害救援ボランティア活動は、ボランティア本人の自発的な意思と責任により被災地での活動に参加・行動することが基本です。
まずは、自分自身で被災地の情報を収集し、現地に行くか、行かないかを判断することです。家族の理解も大切です。その際には、必ず現地に設置されている災害救援ボランティアセンターに事前に連絡し、ボランティア活動への参加方法や注意点について確認してください。災害救援ボランティアセンターの連絡先は、本会のホームページでもお知らせしています。
被災地での活動は、危険がともなうことや重労働となる場合があります。安全や健康についてボランティアが自分自身で管理することであることを理解したうえで参加してください。体調が悪ければ、参加を中止することが肝心です。
被災地で活動する際の宿所は、ボランティア自身が事前に被災地の状況を確認し、手配してください。水、食料、その他身の回りのものについてもボランティア自身が事前に用意し、携行のうえ被災地でのボランティア活動を開始してください。
被災地に到着した後は、必ず災害救援ボランティアセンターを訪れ、ボランティア活動の登録を行ってください。
被災地における緊急連絡先・連絡網を必ず確認するとともに、地理や気候等周辺環境を把握したうえで活動してください。
被災地では、被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動と言葉づかいでボランティア活動に参加してください。
被災地では、必ず災害救援ボランティアセンターやボランティアコーディネーター等、現地受け入れ機関の指示、指導に従って活動してください。単独行動はできるだけ避けてください。組織的に活動することで、より大きな力となることができます。
自分にできる範囲の活動を行ってください。休憩を心がけましょう。無理な活動は、思わぬ事故につながり、かえって被災地の人々の負担となってしまいます。
備えとして、ボランティア活動保険に加入しましょう。
http://www.shakyo.or.jp/saigai/katudou.html 転載白鳳
平成23年4月28日
被災地での災害ボランティアセンター設置とボランティア募集状況
1.災害ボランティアセンターの設置状況
4月27日現在、被災地における市町村段階の災害ボランティアセンター設置数は、被害の大きかった7県で83センターとなっています(本会把握数)。
青森県1、岩手県20、宮城県16(うち仙台市5)、福島県29、茨城県14、
栃木県2、長野県1
※市町村別センターの設置状況一覧を掲載していますのでご参照ください。
→ 市町村災害ボランティアセンター一覧へ
http://www.shakyo.or.jp/saigai/pdf/20110330_02_v9.pdf
2.ボランティアの募集状況
これらのセンターのうち、ボランティアニーズが多く出されているのは、津波被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県の沿岸部地域のセンターです。
内陸部を中心とした多くのセンターにおいては、県外からの募集までは行っていない状況です。
※沿岸部災害ボランティアセンターの詳細情報はこちらから
http://www.saigaivc.com/vc設置状況-pdfファイル/#engan
3.ボランティア活動希望の皆様へのお願い
被災地でのボランティア活動を希望される場合は、まずホームページにより募集の有無、募集の範囲をご確認ください。
ホームページ上で、事前の電話連絡が明記されている場合を除いては、できる限り電話での照会はご遠慮ください。多くの電話が集中すると、センター業務の円滑な運営に支障を与えることがありますのでご理解ください。
http://www.shakyo.or.jp/saigai/touhokuzisin.html 転載白鳳
被災地での災害ボランティアセンター設置とボランティア募集状況
1.災害ボランティアセンターの設置状況
4月27日現在、被災地における市町村段階の災害ボランティアセンター設置数は、被害の大きかった7県で83センターとなっています(本会把握数)。
青森県1、岩手県20、宮城県16(うち仙台市5)、福島県29、茨城県14、
栃木県2、長野県1
※市町村別センターの設置状況一覧を掲載していますのでご参照ください。
→ 市町村災害ボランティアセンター一覧へ
http://www.shakyo.or.jp/saigai/pdf/20110330_02_v9.pdf
2.ボランティアの募集状況
これらのセンターのうち、ボランティアニーズが多く出されているのは、津波被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県の沿岸部地域のセンターです。
内陸部を中心とした多くのセンターにおいては、県外からの募集までは行っていない状況です。
※沿岸部災害ボランティアセンターの詳細情報はこちらから
http://www.saigaivc.com/vc設置状況-pdfファイル/#engan
3.ボランティア活動希望の皆様へのお願い
被災地でのボランティア活動を希望される場合は、まずホームページにより募集の有無、募集の範囲をご確認ください。
ホームページ上で、事前の電話連絡が明記されている場合を除いては、できる限り電話での照会はご遠慮ください。多くの電話が集中すると、センター業務の円滑な運営に支障を与えることがありますのでご理解ください。
http://www.shakyo.or.jp/saigai/touhokuzisin.html 転載白鳳
厚生労働省からの依頼により、被災地の避難所で生活する被災者の食生活の栄養管理等の支援のため、大阪府の管理栄養士を岩手県に派遣しますので、下記のとおり、その概要をお知らせいたします。
記
【活動内容】
岩手県の栄養士チームとともに、避難所での食事内容について栄養面でのサポートを行う。
食物アレルギーをお持ちの方や、嚥下障害のある方など、個別の食事管理が必要な方に対する、食事支援を
行う。
【派遣場所(活動場所)】
岩手県山田町
【派遣職種】
管理栄養士 1名
【派遣期間】
5月1日(日曜日)から5月6日(金曜日)まで (その後おおよそ1か月を目途に派遣予定)
【出発日時】
5月1日(日曜日)空路にて出発
白鳳転記
記
【活動内容】
岩手県の栄養士チームとともに、避難所での食事内容について栄養面でのサポートを行う。
食物アレルギーをお持ちの方や、嚥下障害のある方など、個別の食事管理が必要な方に対する、食事支援を
行う。
【派遣場所(活動場所)】
岩手県山田町
【派遣職種】
管理栄養士 1名
【派遣期間】
5月1日(日曜日)から5月6日(金曜日)まで (その後おおよそ1か月を目途に派遣予定)
【出発日時】
5月1日(日曜日)空路にて出発
白鳳転記
集団給食の知識が避難所で必要とされています。
もしお気持ちのある方有資格である旨申し出てボランティア協力いただけると幸いです。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年度 被災地支援・災害ボランティア情報(16号)
東日本大震災(第31報)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年5月2日(月)18時00分発行
全国社会福祉協議会 地域福祉部
全国ボランティア・市民活動振興センター
http://www.saigaivc.com/
(HPをリニューアルしました)
===========================================================
本会で把握した、東日本大震災の被災者のための支援活動の状況
等をお知らせいたします。
■ 1 災害ボランティアセンターの設置状況
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会が把握しているセンターの設置状況、ボランティア受け入れ
状況については、「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」
にて最新情報をご覧いただけます。
「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」はこちら
http://www.saigaivc.com/
ゴールデンウィーク最初の3連休のボランティアの参加数(概
数)の仮集計は次のとおりです。未集計の市町村もありますので、
参考値としてとらえてください。
この数値は、災害ボランティアセンターを経由して活動された方
の数ですのでこの他にも、NPO等の活動に多くの方が参加されてい
るものと考えられます。
岩手県 宮城県 福島県 合計
4月28日 800 2,600 500 3,900
4月29日 1,600 3,800 1,200 6,600
4月30日 2,200 5,600 1,600 9,300
3月、4月の累計 45,000 110,600 34,300 189,900
※ご使用のメーラーのフォント表示が「MSゴシック」などの等幅フ
ォントでない場合、表示が崩れる場合ははこちらをご覧ください
http://bit.ly/mNl5pX
ボランティアを多数受け入れられない理由は、地域によってさま
ざまであり、たとえば次のような理由があげられています。
・ニーズが活動希望のボランティアの方の数を下回っている。
(ただし、ニーズは今後も出てくるので、ゴールデンウィーク以
もぜひボランティア活動にご参加いただきたい。)
・多数のボランティアが移動することにより、交通渋滞を引き起
こしている。(できるだけ、団体で移動して欲しい。)
・緊急ニーズが収束し、継続的に活動ができる方に来て欲しい。
(ニーズの変化)
・重機によるがれき撤去などが中心で、現段階では一般ボランテ
ィアで対応できるニーズが限られている。
地域の被災の状況によって、さまざまですので、まず、ホームペ
ージでその地域の状況を把握してください。さらに、多くのセンタ
ーは、受付の可否や条件について電話での事前確認をお願いしてい
ます。その上で、現地への参加をお願いします。
なお、繰り返しお伝えしているところですが、現地のほとんどの
ところは、行き帰りの交通、宿泊、食料はご自分でご手配いただく
ことになります。
■ 2 ボランティアや支援活動を考えている方へのメッセージ
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ボランティアや支援活動を考えているみなさんへのメッセージを
まとめています。
http://www.saigaivc.com/ボランティアのみなさんへ/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター
電話 03−3581−4655/4656
E-mail vc00000@shakyo.or.jp
災害情報専用HP:http://www.saigaivc.com/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
転載白鳳
もしお気持ちのある方有資格である旨申し出てボランティア協力いただけると幸いです。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年度 被災地支援・災害ボランティア情報(16号)
東日本大震災(第31報)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年5月2日(月)18時00分発行
全国社会福祉協議会 地域福祉部
全国ボランティア・市民活動振興センター
http://www.saigaivc.com/
(HPをリニューアルしました)
===========================================================
本会で把握した、東日本大震災の被災者のための支援活動の状況
等をお知らせいたします。
■ 1 災害ボランティアセンターの設置状況
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会が把握しているセンターの設置状況、ボランティア受け入れ
状況については、「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」
にて最新情報をご覧いただけます。
「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」はこちら
http://www.saigaivc.com/
ゴールデンウィーク最初の3連休のボランティアの参加数(概
数)の仮集計は次のとおりです。未集計の市町村もありますので、
参考値としてとらえてください。
この数値は、災害ボランティアセンターを経由して活動された方
の数ですのでこの他にも、NPO等の活動に多くの方が参加されてい
るものと考えられます。
岩手県 宮城県 福島県 合計
4月28日 800 2,600 500 3,900
4月29日 1,600 3,800 1,200 6,600
4月30日 2,200 5,600 1,600 9,300
3月、4月の累計 45,000 110,600 34,300 189,900
※ご使用のメーラーのフォント表示が「MSゴシック」などの等幅フ
ォントでない場合、表示が崩れる場合ははこちらをご覧ください
http://bit.ly/mNl5pX
ボランティアを多数受け入れられない理由は、地域によってさま
ざまであり、たとえば次のような理由があげられています。
・ニーズが活動希望のボランティアの方の数を下回っている。
(ただし、ニーズは今後も出てくるので、ゴールデンウィーク以
もぜひボランティア活動にご参加いただきたい。)
・多数のボランティアが移動することにより、交通渋滞を引き起
こしている。(できるだけ、団体で移動して欲しい。)
・緊急ニーズが収束し、継続的に活動ができる方に来て欲しい。
(ニーズの変化)
・重機によるがれき撤去などが中心で、現段階では一般ボランテ
ィアで対応できるニーズが限られている。
地域の被災の状況によって、さまざまですので、まず、ホームペ
ージでその地域の状況を把握してください。さらに、多くのセンタ
ーは、受付の可否や条件について電話での事前確認をお願いしてい
ます。その上で、現地への参加をお願いします。
なお、繰り返しお伝えしているところですが、現地のほとんどの
ところは、行き帰りの交通、宿泊、食料はご自分でご手配いただく
ことになります。
■ 2 ボランティアや支援活動を考えている方へのメッセージ
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ボランティアや支援活動を考えているみなさんへのメッセージを
まとめています。
http://www.saigaivc.com/ボランティアのみなさんへ/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター
電話 03−3581−4655/4656
E-mail vc00000@shakyo.or.jp
災害情報専用HP:http://www.saigaivc.com/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
転載白鳳
☆緊急☆
菅首相は6日夜、首相官邸で記者会見し、中部電力浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)のすべての原子炉の運転停止を、海江田経済産業相を通じて中部電力に要請したと発表した。 理由として、静岡県を中心とする東海地震の発生確率が今後30年間で87%に上ることを挙げ、「国民の安全と安心を考えた。重大な事故が発生した場合の日本社会全体の甚大な影響もあわせて考慮した」と説明した。浜岡原発は、4、5号機が稼働中。点検のため運転を停止中の3号機は、東日本大震災の影響で運転再開を延期していた。1、2号機は運転を終了している。首相は、浜岡原発が東海地震の震源域にあることを指摘した上で、「文部科学省の地震調査研究推進本部の評価によれば、これから30年以内にマグニチュード8程度の想定東海地震が発生する可能性は87%と極めて切迫している。防潮堤の設置など、中長期の対策を確実に実施する事が必要だ」と説明した。
浜岡原発の運転停止で電力の供給に支障が生じる可能性も指摘されているが、首相は「政府としても最大限の対策を講じる。省電力、省エネルギーの工夫で必ず乗り越えていけると確信している」と強調し、「全国民の理解と協力があれば、夏場の電力需要に十分対応できる」と呼びかけた。
******** 理解と協力よろしくお願いします *********
菅首相は6日夜、首相官邸で記者会見し、中部電力浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)のすべての原子炉の運転停止を、海江田経済産業相を通じて中部電力に要請したと発表した。 理由として、静岡県を中心とする東海地震の発生確率が今後30年間で87%に上ることを挙げ、「国民の安全と安心を考えた。重大な事故が発生した場合の日本社会全体の甚大な影響もあわせて考慮した」と説明した。浜岡原発は、4、5号機が稼働中。点検のため運転を停止中の3号機は、東日本大震災の影響で運転再開を延期していた。1、2号機は運転を終了している。首相は、浜岡原発が東海地震の震源域にあることを指摘した上で、「文部科学省の地震調査研究推進本部の評価によれば、これから30年以内にマグニチュード8程度の想定東海地震が発生する可能性は87%と極めて切迫している。防潮堤の設置など、中長期の対策を確実に実施する事が必要だ」と説明した。
浜岡原発の運転停止で電力の供給に支障が生じる可能性も指摘されているが、首相は「政府としても最大限の対策を講じる。省電力、省エネルギーの工夫で必ず乗り越えていけると確信している」と強調し、「全国民の理解と協力があれば、夏場の電力需要に十分対応できる」と呼びかけた。
******** 理解と協力よろしくお願いします *********
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年度 被災地支援・災害ボランティア情報(17号)
東日本大震災(第32報)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年5月5日(木)12時00分発行
全国社会福祉協議会 地域福祉部
全国ボランティア・市民活動振興センター
http://www.saigaivc.com/
(HPをリニューアルしました)
===========================================================
本会で把握した、東日本大震災の被災者のための支援活動の状況
等をお知らせいたします。
■ 1 災害ボランティアセンターの設置状況
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会が把握しているセンターにおける、ボランティア受け入れ状
況について、3月から5月3日までの活動者数をお知らせします(5月
5日12時公表)。
なお、各センターの設置状況は「全社協 被災地支援・災害ボラ
ンティア情報」にて最新情報をご覧いただけます。
「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」はこちら
http://www.saigaivc.com/
※ゴールデンウィーク中のボランティア活動への参加数(概数)は
仮集計です。
岩手県 宮城県 福島県 合計
4月28日 800 2,600 500 3,900
4月29日 1,600 3,800 1,200 6,600
4月30日 2,200 5,600 1,600 9,400
3月、4月の累計 45,300 110,600 34,900 190,800
岩手県 宮城県 福島県 合計
5月1日 2,300 4,700 1,700 8,700
5月2日 1,800 4,400 1,600 7,800
5月3日 2,700 6,100 2,300 11,200
開始から
5月3日迄累計 51,100 125,800 40,600 218,500
■ 2 ボランティアや支援活動を考えている方へのメッセージ
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ボランティアや支援活動を考えているみなさんへのメッセージを
まとめています。
http://www.saigaivc.com/ボランティアのみなさんへ/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター
電話 03−3581−4655/4656
E-mail vc00000@shakyo.or.jp
災害情報専用HP:http://www.saigaivc.com/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
転載 白鳳
平成23年度 被災地支援・災害ボランティア情報(17号)
東日本大震災(第32報)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成23年5月5日(木)12時00分発行
全国社会福祉協議会 地域福祉部
全国ボランティア・市民活動振興センター
http://www.saigaivc.com/
(HPをリニューアルしました)
===========================================================
本会で把握した、東日本大震災の被災者のための支援活動の状況
等をお知らせいたします。
■ 1 災害ボランティアセンターの設置状況
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会が把握しているセンターにおける、ボランティア受け入れ状
況について、3月から5月3日までの活動者数をお知らせします(5月
5日12時公表)。
なお、各センターの設置状況は「全社協 被災地支援・災害ボラ
ンティア情報」にて最新情報をご覧いただけます。
「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」はこちら
http://www.saigaivc.com/
※ゴールデンウィーク中のボランティア活動への参加数(概数)は
仮集計です。
岩手県 宮城県 福島県 合計
4月28日 800 2,600 500 3,900
4月29日 1,600 3,800 1,200 6,600
4月30日 2,200 5,600 1,600 9,400
3月、4月の累計 45,300 110,600 34,900 190,800
岩手県 宮城県 福島県 合計
5月1日 2,300 4,700 1,700 8,700
5月2日 1,800 4,400 1,600 7,800
5月3日 2,700 6,100 2,300 11,200
開始から
5月3日迄累計 51,100 125,800 40,600 218,500
■ 2 ボランティアや支援活動を考えている方へのメッセージ
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ボランティアや支援活動を考えているみなさんへのメッセージを
まとめています。
http://www.saigaivc.com/ボランティアのみなさんへ/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター
電話 03−3581−4655/4656
E-mail vc00000@shakyo.or.jp
災害情報専用HP:http://www.saigaivc.com/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
転載 白鳳
******************************
社団法人 日本栄養士会
災害対策本部
mail:jda.center@dietitian.or.jp
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-39
tel:03-3295-5151
fax:03-3295-5165
******************************
「被災地からの管理栄養士・栄養士の声」をお寄せください。
東北地方太平洋沖地震で被災された地域での管理栄養士・栄養士の体験、情報をお寄せください。
?被災地での体験―あの時、私は―
?避難所の食事・栄養問題の解析、解決するための要望、困っていること
?避難所のメニュー記録 等
被災地での活動の参考とさせていただくとともに、一部は、本会ホームページ、「日本栄養士会雑誌」等でご紹介させていただく予定です。
以下にご記入のうえ、E-mail(jda.center@dietitian.or.jp)にて、件名を「被災地からの管理栄養士・栄養士の声」とし、添付ファイルでお送りください。
http://www.dietitian.or.jp/eq/index.html
http://www.dietitian.or.jp/eq/pdf/5.pdf
災害時の栄養・食生活支援マニュアル
部分抜粋
【炊き出し計画】
炊き出し計画(材料の調達、献立の作成等)は被災地の状況により様々であるため、現地で策定
されたものに従ってください。
【炊き出しの際の衛生管理について】
・食事の準備前には水で手を洗う。水がない場合は手指消毒剤を(持参するなどして)使用する。
・調理場所は直射日光やほこりを避ける(屋外では仮設テント等の使用、必要に応じてビニール
シート、台、すのこ等も使用)。容器や使用器具は、土やほこりがかからないようにビニール等
で覆う。
・保冷庫内では、生の肉・魚・卵とその他の食材を分けて保存する。これらの食品を取り扱う従
事者を限定し、取り扱う際には使い捨て手袋を使用する。また、これらの食品を取り扱う場所
は野菜を取り扱う場所から離れた場所とする。
・炊き出しの容器は、衛生面の配慮から使い捨ての容器が望ましい。
・大量調理の場合は、切るサイズをそろえる、食材の調理の順序を工夫することが必要。
・提供する食品は、提供直前に十分加熱する。また、食中毒防止のため、なるべく速やかに喫食
するよう勧める。
※ただし、手袋、ラップ、ポリ袋、使い捨て容器等は不足も予想されるため、状況に応じて適宜
対応すること。また、調理場所や保管場所も状況に応じて適宜対応する。
参考)
・兵庫県こころのケアセンター(日本語版作成):サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き第2 版(2009)
・東京都福祉保健局:災害時の「こころのケア」の手引き(2008)
・日本薬剤師会:薬局・薬剤師の災害対策マニュアル−災害時の救援活動と平時の防災対策に関する指針−(2007)
・兵庫県立大学大学院看護学研究科21世紀COEプログラム「ユビキタス社会における災害看護拠点の形成」看護専
門家支援ネットワークプロジェクト:災害時の看護ボランティア活動の知恵袋(直後〜中期:避難の時期の支
援活動)〜発災後1ヶ月程度まで〜(2007)
・新潟県災害時栄養・食生活支援活動ガイドライン
http://www.kenko-niigata.com/21/shishin/sonotakeikaku/saigaijieiyoupdf/4_takidasijireiP80_82.pdf
・兵庫県災害時食生活改善活動ガイドライン http://web.pref.hyogo.jp/contents/000111278.pdf
・津波・地震において自分、家族、同僚、地域の健康を守るヒント集
http://kojiwada.blogspot.com/2011/03/blog-post_51.html
社団法人 日本栄養士会
災害対策本部
mail:jda.center@dietitian.or.jp
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-39
tel:03-3295-5151
fax:03-3295-5165
******************************
「被災地からの管理栄養士・栄養士の声」をお寄せください。
東北地方太平洋沖地震で被災された地域での管理栄養士・栄養士の体験、情報をお寄せください。
?被災地での体験―あの時、私は―
?避難所の食事・栄養問題の解析、解決するための要望、困っていること
?避難所のメニュー記録 等
被災地での活動の参考とさせていただくとともに、一部は、本会ホームページ、「日本栄養士会雑誌」等でご紹介させていただく予定です。
以下にご記入のうえ、E-mail(jda.center@dietitian.or.jp)にて、件名を「被災地からの管理栄養士・栄養士の声」とし、添付ファイルでお送りください。
http://www.dietitian.or.jp/eq/index.html
http://www.dietitian.or.jp/eq/pdf/5.pdf
災害時の栄養・食生活支援マニュアル
部分抜粋
【炊き出し計画】
炊き出し計画(材料の調達、献立の作成等)は被災地の状況により様々であるため、現地で策定
されたものに従ってください。
【炊き出しの際の衛生管理について】
・食事の準備前には水で手を洗う。水がない場合は手指消毒剤を(持参するなどして)使用する。
・調理場所は直射日光やほこりを避ける(屋外では仮設テント等の使用、必要に応じてビニール
シート、台、すのこ等も使用)。容器や使用器具は、土やほこりがかからないようにビニール等
で覆う。
・保冷庫内では、生の肉・魚・卵とその他の食材を分けて保存する。これらの食品を取り扱う従
事者を限定し、取り扱う際には使い捨て手袋を使用する。また、これらの食品を取り扱う場所
は野菜を取り扱う場所から離れた場所とする。
・炊き出しの容器は、衛生面の配慮から使い捨ての容器が望ましい。
・大量調理の場合は、切るサイズをそろえる、食材の調理の順序を工夫することが必要。
・提供する食品は、提供直前に十分加熱する。また、食中毒防止のため、なるべく速やかに喫食
するよう勧める。
※ただし、手袋、ラップ、ポリ袋、使い捨て容器等は不足も予想されるため、状況に応じて適宜
対応すること。また、調理場所や保管場所も状況に応じて適宜対応する。
参考)
・兵庫県こころのケアセンター(日本語版作成):サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き第2 版(2009)
・東京都福祉保健局:災害時の「こころのケア」の手引き(2008)
・日本薬剤師会:薬局・薬剤師の災害対策マニュアル−災害時の救援活動と平時の防災対策に関する指針−(2007)
・兵庫県立大学大学院看護学研究科21世紀COEプログラム「ユビキタス社会における災害看護拠点の形成」看護専
門家支援ネットワークプロジェクト:災害時の看護ボランティア活動の知恵袋(直後〜中期:避難の時期の支
援活動)〜発災後1ヶ月程度まで〜(2007)
・新潟県災害時栄養・食生活支援活動ガイドライン
http://www.kenko-niigata.com/21/shishin/sonotakeikaku/saigaijieiyoupdf/4_takidasijireiP80_82.pdf
・兵庫県災害時食生活改善活動ガイドライン http://web.pref.hyogo.jp/contents/000111278.pdf
・津波・地震において自分、家族、同僚、地域の健康を守るヒント集
http://kojiwada.blogspot.com/2011/03/blog-post_51.html
大阪⇔東北 社会福祉協議会ボランティアバス&支援の案内
【第3回】
(1)実施日 平成23年5月10日(火)午後7時30分出発 〜 14日(土)午前10時帰着 [現地活動日:5月11日(水)・12日(木)・13日(金)]
(2)出発日集合日時 5月10日(火)午後6時30分
堺市役所前広場(堺市堺区南瓦町3番1号) (最寄駅:南海高野線「堺東」)
(3)事前説明会 4月28日(木)午後7時〜8時 堺市総合福祉会館(堺市堺区南瓦町2番1号) (最寄駅:南海高野線「堺東」)
(4)受付日 4月26日(火)午前9時〜午後5時 ※受付開始時間は午前9時です。先着順。定員に達した時点で締切り
※1本のお電話でお申込みできるのは1人のみです。
(5)申込先・方法 堺市社会福祉協議会(電話072-232-5420) まで電話にてお申し込みください。
2.行 き 先 :宮城県内被災地(宮城県災害ボランティアセンターとの調整により後日決定)
第一回は 石巻市でした。
3.活動内容 :被災した家屋の片付け、津波被害にあった家屋の泥だし等 ※その他さまざまな活動も想定されます。選り好みをされる方の参加はお断りします。
4.募集人数 :各回 40人(大型バス1台) ※大阪府内の市民(大阪市民・堺市民含む)に限る
5.参加費 10,000円(出発日に徴収します) ※現地2日間の宿泊料(素泊まり@4,650)、天災担保付ボランティア活動保険料(700円) ※宿泊場所:仙台市内の旅館、男女別の相部屋(3〜4人)、布団・お風呂が提供されます。 ※既に天災担保付ボランティア活動保険に加入されている場合は9,300円となります。
6.持ち物 期間中の食料(最低活動日3食×3日分、簡単にすぐ食べられるもの、宿泊場所ではお湯は使えます。火気厳禁)と飲料(活動中・バス移動中は禁酒・禁煙)・着替え、防寒着、作業着(汚れてもよい服装)、帽子またはヘルメット、ゴーグル、防塵マスク、長靴、ゴム手袋、タオル、洗面用具、携帯トイレ、保険証、常備薬他、各自必要なもの ※活動は5人1組で行い、1組に1台の1輪車(または台車)、数本のシャベルは貸し出します。
7.注意事項
(1)12〜13時間のバス往復になります。座席は男女混合、往復は車中泊。バスにトイレはあり ません。荷物はできるだけ小さくなるようにご協力願います。
(2)活動は過酷になることが予測されますのでご留意ください。また、被災地では単独行動は禁物 です。協調性をもって行動してください。
(3)被災地は余震もあり、危険を伴います。状況に応じて活動途中でも切り上げて帰阪する場合が あります。参加者は万一の事故に備えて天災担保付ボランティア保険に加入しますが、安全管 理や健康管理をご自身でできない方のお申込みはご遠慮します。
(4)参加希望者は事前説明会に必ず参加してください。説明会に欠席された場合は申込みを受け付 けていても活動にはご参加いただけません。また説明会でふさわしくないと思われた方には参 加をご遠慮いただく場合があります。
(5)当面バス運行は3回とし、その後の予定は未定です。(運行する場合は改めて発信します)
【問合せ】※問合せは各回の主軸社協・担当部署までお願いします。
5/10〜14 堺市社会福祉協議会
電話072―232−5420
人手・スキル必要あれば情報まとめてくださいませ。 白鳳
【第3回】
(1)実施日 平成23年5月10日(火)午後7時30分出発 〜 14日(土)午前10時帰着 [現地活動日:5月11日(水)・12日(木)・13日(金)]
(2)出発日集合日時 5月10日(火)午後6時30分
堺市役所前広場(堺市堺区南瓦町3番1号) (最寄駅:南海高野線「堺東」)
(3)事前説明会 4月28日(木)午後7時〜8時 堺市総合福祉会館(堺市堺区南瓦町2番1号) (最寄駅:南海高野線「堺東」)
(4)受付日 4月26日(火)午前9時〜午後5時 ※受付開始時間は午前9時です。先着順。定員に達した時点で締切り
※1本のお電話でお申込みできるのは1人のみです。
(5)申込先・方法 堺市社会福祉協議会(電話072-232-5420) まで電話にてお申し込みください。
2.行 き 先 :宮城県内被災地(宮城県災害ボランティアセンターとの調整により後日決定)
第一回は 石巻市でした。
3.活動内容 :被災した家屋の片付け、津波被害にあった家屋の泥だし等 ※その他さまざまな活動も想定されます。選り好みをされる方の参加はお断りします。
4.募集人数 :各回 40人(大型バス1台) ※大阪府内の市民(大阪市民・堺市民含む)に限る
5.参加費 10,000円(出発日に徴収します) ※現地2日間の宿泊料(素泊まり@4,650)、天災担保付ボランティア活動保険料(700円) ※宿泊場所:仙台市内の旅館、男女別の相部屋(3〜4人)、布団・お風呂が提供されます。 ※既に天災担保付ボランティア活動保険に加入されている場合は9,300円となります。
6.持ち物 期間中の食料(最低活動日3食×3日分、簡単にすぐ食べられるもの、宿泊場所ではお湯は使えます。火気厳禁)と飲料(活動中・バス移動中は禁酒・禁煙)・着替え、防寒着、作業着(汚れてもよい服装)、帽子またはヘルメット、ゴーグル、防塵マスク、長靴、ゴム手袋、タオル、洗面用具、携帯トイレ、保険証、常備薬他、各自必要なもの ※活動は5人1組で行い、1組に1台の1輪車(または台車)、数本のシャベルは貸し出します。
7.注意事項
(1)12〜13時間のバス往復になります。座席は男女混合、往復は車中泊。バスにトイレはあり ません。荷物はできるだけ小さくなるようにご協力願います。
(2)活動は過酷になることが予測されますのでご留意ください。また、被災地では単独行動は禁物 です。協調性をもって行動してください。
(3)被災地は余震もあり、危険を伴います。状況に応じて活動途中でも切り上げて帰阪する場合が あります。参加者は万一の事故に備えて天災担保付ボランティア保険に加入しますが、安全管 理や健康管理をご自身でできない方のお申込みはご遠慮します。
(4)参加希望者は事前説明会に必ず参加してください。説明会に欠席された場合は申込みを受け付 けていても活動にはご参加いただけません。また説明会でふさわしくないと思われた方には参 加をご遠慮いただく場合があります。
(5)当面バス運行は3回とし、その後の予定は未定です。(運行する場合は改めて発信します)
【問合せ】※問合せは各回の主軸社協・担当部署までお願いします。
5/10〜14 堺市社会福祉協議会
電話072―232−5420
人手・スキル必要あれば情報まとめてくださいませ。 白鳳
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
栄養士・管理栄養士・栄養学 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-