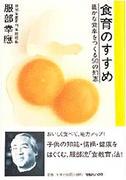開催終了「ケニア農村部での5年間の母子保健活動を通して」
詳細
2011年05月08日 01:16 更新
特定非営利活動法人HANDS主催
◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<第8回HANDSセミナー>
プロマネに聴く、国際協力現場のはなし
「ケニア農村部での5年間の母子保健活動を通して」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆
HANDSは、2005年からケニア・ケリチョー県で、
お母さんと赤ちゃんのために、地域に根ざした活動をしています。
楽あれば苦もあった、様々なエピソードとともに、
国際協力の現場では実際どんなことが行われているのか、
どんな思いを持って活動しているのかなど、本音で語ってもらいます。
当日は「インタビュータイム」をもうけていますので、
長年国際保健医療の分野で活躍してきたスピーカーに聞いてみたいことを、
是非ぶつけてみてください!
たくさんの方々のご参加をお待ちしています!!
【日 程】: 2011年5月14日(土) 14:00〜16:00
【場 所】: 東京学院ビル 4F 教室
〒101-0061 東京都千代田区三崎町3丁目6-15
(JR 総武線 水道橋駅より徒歩1分)
【参加費】: 500円(会場代)※HANDS会員は無料
【定 員】: 50名
【スピーカー】:
原口珠代さん(HANDSサポーティング・アドバイザー/
前ケニア事業 プロジェクト・マネジャー)
<スピーカープロフィール>
看護師、救急救命士。医療アドバイザーや医療調整員として、
パキスタン、スーダン、ザンビア、カンボジア、北朝鮮など、
多数の国で支援活動に携わる。HANDSに所属し、2007年4月〜
ケニア事業に関わり、2009年8月〜プロジェクト・マネジャー
として、活動(2011年3月まで)。
【プログラム】:
14:00 挨拶・HANDS紹介
14:10 第1部 原口珠代さんのおはなし
14:50 休憩
15:00 第2部 インタビュータイム
※事前にいただいた質問や会場からの質問も取り上げます
16:00 終了
▼詳細情報、お申込みはこちら
⇒ http://
─────────────────────────────
■お問い合わせ先
─────────────────────────────
特定非営利活動法人HANDS
(担当: 奥田・篠原)
東京都文京区本郷3-20-7 山の手ビル2F
TEL: 03-5805-8565 FAX: 03-5805-8667
E-mail:handssem8★hands.or.jp(★を@にしてください)
URL: http://
******************************
昨年白鳳が お世話になった大阪大学大学院人間科学グローバル国際協力学講座教授
前 東京大学国際医療准教授の小児科医が理事の会です。
栄養士も がんばろうなぁ〜!!!! 白 鳳
◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<第8回HANDSセミナー>
プロマネに聴く、国際協力現場のはなし
「ケニア農村部での5年間の母子保健活動を通して」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆
HANDSは、2005年からケニア・ケリチョー県で、
お母さんと赤ちゃんのために、地域に根ざした活動をしています。
楽あれば苦もあった、様々なエピソードとともに、
国際協力の現場では実際どんなことが行われているのか、
どんな思いを持って活動しているのかなど、本音で語ってもらいます。
当日は「インタビュータイム」をもうけていますので、
長年国際保健医療の分野で活躍してきたスピーカーに聞いてみたいことを、
是非ぶつけてみてください!
たくさんの方々のご参加をお待ちしています!!
【日 程】: 2011年5月14日(土) 14:00〜16:00
【場 所】: 東京学院ビル 4F 教室
〒101-0061 東京都千代田区三崎町3丁目6-15
(JR 総武線 水道橋駅より徒歩1分)
【参加費】: 500円(会場代)※HANDS会員は無料
【定 員】: 50名
【スピーカー】:
原口珠代さん(HANDSサポーティング・アドバイザー/
前ケニア事業 プロジェクト・マネジャー)
<スピーカープロフィール>
看護師、救急救命士。医療アドバイザーや医療調整員として、
パキスタン、スーダン、ザンビア、カンボジア、北朝鮮など、
多数の国で支援活動に携わる。HANDSに所属し、2007年4月〜
ケニア事業に関わり、2009年8月〜プロジェクト・マネジャー
として、活動(2011年3月まで)。
【プログラム】:
14:00 挨拶・HANDS紹介
14:10 第1部 原口珠代さんのおはなし
14:50 休憩
15:00 第2部 インタビュータイム
※事前にいただいた質問や会場からの質問も取り上げます
16:00 終了
▼詳細情報、お申込みはこちら
⇒ http://
─────────────────────────────
■お問い合わせ先
─────────────────────────────
特定非営利活動法人HANDS
(担当: 奥田・篠原)
東京都文京区本郷3-20-7 山の手ビル2F
TEL: 03-5805-8565 FAX: 03-5805-8667
E-mail:handssem8★hands.or.jp(★を@にしてください)
URL: http://
******************************
昨年白鳳が お世話になった大阪大学大学院人間科学グローバル国際協力学講座教授
前 東京大学国際医療准教授の小児科医が理事の会です。
栄養士も がんばろうなぁ〜!!!! 白 鳳
コメント(5)
2011年05月18日 02:16
ご参加いただいた方お疲れ様でした。
HANDSの代表理事 中村安秀医師とは別件でその時間ご一緒させていただきました。
特定非営利活動法人Health and Development Service (HANDS) は、保健医療の仕組みづくりと人づくりを通じて、世界の人びとが自らの健康を守ることができる社会を実現したいと考え、世界各地で活動しています。
2000年1月に、国際保健医療協力を行うNPOとしてHANDSを立ち上げました。私たちは、日本人の医師や看護師が医薬品をもって途上国の農村で治療するのではなく、どんな国にも医師や看護師がいるので、彼らが自国の人びとの健康を守る主役になれるような活動をしたいと考えました。そのために、途上国の保健医療システムのマネジメントや保健医療人材の養成に重点をおいた活動を行ってきました。
2001年に開始した、ブラジル・アマゾン河支流にあるマニコレ市のプロジェクト活動。「市」といっても、九州ほどの面積にわずか4万人の人口で、遠隔地コミュニティから市街地への交通手段は船だけ。果てしなく広がるアマゾンの森と河に囲まれて、人びとは小さな集落を作って暮らしていました。
病気になったからといって、すぐに病院や診療所で診察が受けられる状況ではありません。治療ではなくて、「予防」が重要です。私たちが注目したのは、すでにブラジルに存在していた「コミュニティ保健ワーカー」。彼らは医師や看護師などの専門職ではなく、川沿いの村に暮らすふつうの住民です。保健医療に関するトレーニングを受けることによって、マラリアやデング熱といった病気への理解が深まり、妊産婦や小児への保健指導ができるようになり、血圧計や体温計を使って高血圧の患者に指導できるようになりました。
2011年05月18日 02:17
住民が保健ワーカーの仕事ぶりに信頼を寄せるようになると、住民の保健衛生に関する意識も高まりました。自分の家にトイレを設置したり、飲料水を消毒や煮沸したりする家庭が激増しました。村で孤軍奮闘している保健ワーカーをサポートするために、HANDSのブラジル人スタッフは遠隔地のコミュニティを数日かけて船で訪問します。そして、保健ワーカーの相談にのり、適切な技術的アドバイスをするブラジル人スタッフをとりまとめているのが、マニコレ市に在住する唯一の日本人、HANDSの定森徹プロジェクト・マネジャーです。
このような地道な活動を通して培われた住民、保健ワーカー、市の行政機関、ブラジル人スタッフとの信頼関係に基づいて、いま、プロジェクトは地域保健の枠を超えて、学校保健、栄養改善、アグロフォレストリーと広がっています。地域で暮らす人びとの生計や教育といった生活全体を健康の視点から支援しています。
途上国の人びとが主役となり自国の人びとの健康を守ることのできる仕組みづくりと人づくりをめざした活動は、インドネシアでも根付きつつあります。ホンジュラス、スーダン、エジプト、ケニアでもHANDSの活動が始まり、新しい仲間とともに、気長に仕組みづくりと人づくりに取り組んでいきたいと思っています。
これまで、HANDSの活動は、外務省、国際協力機構(JICA)、国連人口基金、(財)国際開発センター、(株)システム科学コンサルタンツ、トヨタ財団、(株)味の素など多くの企業や行政機関に支えられてきました。私たちはいま、単に国際保健医療協力の成果を発表するだけでなく、市民の方々、企業や医療機関の皆さん方とのパートナーシップのなかで、私たちが抱えているグローバルな課題も共有したいと考えるようになりました。
例えば、HANDSが主催した「第6回母子手帳国際会議」(2008年11月)では、母子手帳を途上国のお母さん方に配布するだけでは効果が乏しく、助産師や看護師が適切な指導を行ったときに母子手帳の効果が大きくなるという議論がありました。途上国で母子手帳プロジェクトを成功させるためには、農村や漁村にも母子手帳の使い方を説明できる人材が必要になります。「人づくり」と言葉にするのは簡単ですが、全国規模でそのような人材を育てるのは大変なこと。一つのNPOだけで完遂できる仕事ではありません。
企業が蓄積してきた人づくりや組織づくりのノウハウ、大学が構築してきた留学生や研究仲間のネットワーク、国連機関やODA機関が保有するグローバル課題に関する膨大な情報などを、お互いに共有できたとき、NPOとしてのHANDSの活動もより広い世界に羽ばたいていけると思います。
少しでもHANDSの活動に関心を持っていただけたら、どうぞ気軽に事務局までご連絡ください。皆様方の忌憚ないご意見やご助言を待っています。
特定非営利活動法人HANDS 代表理事 中村安秀
http://www.hands.or.jp/
この我が国の3.11災害も 国際医療の手腕を必要とされてます。
海外に目を向けながら国内の災害・グローバリゼーション・貧困など取り組んで
いただければ 幸いです。 白 鳳 記
2011年05月20日 21:55
医療ツーリズム 阪大が通訳養成
2011年5月20日 提供:読売新聞
先端医療で外国人旅行者を呼び込む医療ツーリズムが注目される中、大阪大は、外国人患者が診断や治療の正確な情報を得る手助けをする医療通訳養成コースを今春、始めた。大学が医療通訳の教育に本格的に取り組むのは全国初だ。
外国人に安心を
対象は英語と中国語で、大学院の各研究科が協力して設置。外国人が日本で医療を受ける場合の問題点などの総論をはじめ、医学や意思の伝達法など専門知識を幅広く学ぶ。各研究科の単位として認定され、コースの修了書が発行される。
必修選択科目には医学系研究科の「がんの病態生理学」や「臨床医学概論」、言語文化研究科の「通訳翻訳学」などが並ぶ。秋には、全米医療通訳協議会から専門講師を招いた5日間の集中講座を実施。外国人患者の民族的背景や倫理規定を学び、発言を区切りながら通訳する能力を磨く。実際の場面を想定して行う訓練など実践的な教育を行う。
初年度は25人程度が受講する。修士1年の鹿島実夢(みむ)さん(24)は「ペルーへの留学から帰国し、日本語ができない国内の日系ペルー人に何か支援ができないかと考え、医療通訳に興味を持った。精神的な不安や経済的な問題にも対応することが必要だと思う」と話す。
現在、医療通訳には公的な資格はなく、民間の語学学校やNGOで養成講座などを受けた人らがボランティアや低額の報酬で行っている。大学では、経済産業省が昨秋、東京外国語大に委託して4か月間、一般向けの養成講座を開催。愛知県立大は在日ブラジル人労働者らを助ける目的で社会人向け講座を開いている。
取り組みについて、経産省は「命にかかわる場面もあるだけに、外国人患者と医師の仲介は重要な仕事。実践訓練もあり総括的なコースで画期的だ」としている。
NGOなどでつくる医療通訳士協議会会長も務める中村安秀・阪大教授(国際協力学)は「各分野のプロが講義を提供できるのは、総合大学だからこその利点。質の高い医療通訳を育てたい」と抱負を語る。
2011年05月25日 00:28
概要
自慢の浜で思いっきり遊び、地域密着の濃厚な地域医療を体験できる大人気のツアー、年々人気が増しています!
今年も熱い砂浜と講師陣が、皆さんをお待ちしています。
楽しくてためになる体験をお約束します!!
パンフレットはこちら
ツアーの内容
水曜日〜金曜日
○和田診療所での診療実習(外来・在宅医療など)と家庭医療レクチャー
○保健・福祉との連携など地域包括ケアの体験実習
○寺澤教授の地域医療ミニレクチャー(※日程??は除く)
土・日曜日
○海水浴場の救護ボランティア
※宿泊は民宿、海やイベントを楽しむ自由時間もたっぷり確保します!
※経験や興味に合わせて個別にスケジュールをたてます。
参加資格
地域医療、家庭医療に興味がある、海好きな医学生、研修医、看護学生など
日程
?7月20日〜24日
?7月27日〜7月31日
?8月3日〜7日
?8月10日〜14日
?8月17日〜21日
それぞれ初日13時集合→最終日18時解散予定
参加費
4泊5日コース 7000円 (全日程の宿泊費朝夕食事付き)
※高浜町和田までの交通費および昼食費は各自負担してください。
申し込み方法
下記申し込みフォームよりお申し込みください。定員になり次第締め切りとさせていただきます。
夏だ!海と地域医療体験ツアーin高浜'11申し込みフォーム
※応募者が多い場合はお断りすることがあります。ご了承ください。
※必ず連絡のとれるメールアドレスを入力してください。
お問い合わせ
wcc@town.takahama.fukui.jp まで、お気軽にお問い合わせください。
主催
高浜町国民健康保険 和田診療所
福井大学医学部地域プライマリケア講座
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには