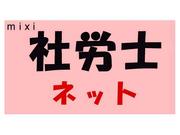|
|
|
|
コメント(3)
雇用保険率だって建設はありますよ。
たしか有期事業は二元適用だから別々に処理しなければならないんですよね……?
例えば
元請⇒山田工事(10人)
下請⇒桜土木(20人)
孫請⇒みなみ塗装(5人)
という現場が仮にありその元請の山田工事が、その現場の労災保険関連を35人分一括に処理する。
でも雇用保険分は山田工事では10人分、桜土木では20人分、みなみ塗装では5人分それぞれ雇う人数分払う。というイメージだったと思います。
継続事業は一元適用事業ですよね。
例えばダイエーで社員さんが100人いたとすると、その人たちにはダイエーが社員に労災保険と雇用保険をかけてやり一緒に書類整理をするから
継続事業の一般保険料の額= 賃金の総額×一般保険料率(労災+雇用)
という公式にあてはまるんですね。
私も受験生なので間違っていたら指摘お願いします。出先きなのでテキストがなくてうろ覚えっぽいかも……orz
たしか有期事業は二元適用だから別々に処理しなければならないんですよね……?
例えば
元請⇒山田工事(10人)
下請⇒桜土木(20人)
孫請⇒みなみ塗装(5人)
という現場が仮にありその元請の山田工事が、その現場の労災保険関連を35人分一括に処理する。
でも雇用保険分は山田工事では10人分、桜土木では20人分、みなみ塗装では5人分それぞれ雇う人数分払う。というイメージだったと思います。
継続事業は一元適用事業ですよね。
例えばダイエーで社員さんが100人いたとすると、その人たちにはダイエーが社員に労災保険と雇用保険をかけてやり一緒に書類整理をするから
継続事業の一般保険料の額= 賃金の総額×一般保険料率(労災+雇用)
という公式にあてはまるんですね。
私も受験生なので間違っていたら指摘お願いします。出先きなのでテキストがなくてうろ覚えっぽいかも……orz
徴収法は、一元適用事業と二元適用事業に分けて適用をしています。
殆どの事業は一元継続事業です。
そこで、林業や建設業は二元適用事業であるため、年度更新等の際に別々に処理を行っています。
なお、有期事業であることと二元適用事業であることは、別のことです。
以下、厚労省のHPより・・
労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある以下の事業については、両保険ごとにそれぞれ別に適用したほうが効率的なため、別個の事業とみなして二元的に処理することとなっております。これらを二元適用事業と呼びます
(1) 都道府県及び市町村の行う事業
(2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
(3) 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
(4) 農林水産の事業
(5) 建設の事業
※上記の一元適用事業以外の事業が二元適用事業です。継続事業でも二元適用事業が存在します。
一方で、有期事業とは一定期間が経過すれば事業が完了するもので、上記以外でも(博覧会その他)有期事業は存在します。
殆どの事業は一元継続事業です。
そこで、林業や建設業は二元適用事業であるため、年度更新等の際に別々に処理を行っています。
なお、有期事業であることと二元適用事業であることは、別のことです。
以下、厚労省のHPより・・
労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある以下の事業については、両保険ごとにそれぞれ別に適用したほうが効率的なため、別個の事業とみなして二元的に処理することとなっております。これらを二元適用事業と呼びます
(1) 都道府県及び市町村の行う事業
(2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
(3) 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
(4) 農林水産の事業
(5) 建設の事業
※上記の一元適用事業以外の事業が二元適用事業です。継続事業でも二元適用事業が存在します。
一方で、有期事業とは一定期間が経過すれば事業が完了するもので、上記以外でも(博覧会その他)有期事業は存在します。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
社労士 更新情報
-
最新のアンケート